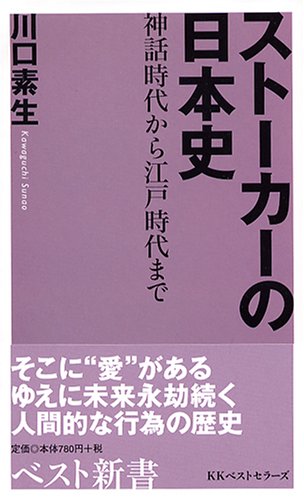- 著者
- 檜谷 美恵子 住田 昌二
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文報告集 (ISSN:09108017)
- 巻号頁・発行日
- vol.392, pp.136-146, 1988-10-30 (Released:2017-12-25)
This paper aims at making clear from both historical and spatial aspects how and by what reasons the owner-ccupation has spreaded in urban areas of Japan by means of taking the cases of 24 main cities into consideration. The conclusion concerning to historical change is summarized as follows: 1) Before the war, the private renting was the dominant tenure of urban housing excepte for housing located in the suburbs of the big cities and several new industrial cities rapidly urbanized, where the sign of the growth of the owner-occupied sector was emerging. 2) The remarkable increase of the owner-occupied ratio from 22.3% in 1941 to 41.3% in 1948 causes to an enormus degree by the war damage and the housing constructin immediately after the end of the war, which determined the changing direction of housing tenure after the war. 3) For the postwar period, the change of a distrubution ratio of housing tenure has been caused mainly by rapid urban growth, especially the intensive concentration in metropolitain areas throughout the period of the high economic growing and the amount of new rental housing has sharply reflected on it. While the number of owner-occupied housing has constantly increased throughout the same period and as compared with the renting, the owner-occupation is more stable and accumulative as tenure type. On the other hand, through the spatial ananlysis, it became clear that there were several differet patterns in the increasing process of the owner-occupation, the main two patterns are as foolows : 1) Metropolitan type・・・ After having accumulated the private renting, owner-occupied housing has increased in parallel with the real urbanization. 2) Local type ・・・In the cities where urbanization has been inseparably related to the incorporation of rural areas, the owner-occupied ratio has risen through the increasing number of a farmhouse and being based on it, the real urban housing has been formed on the side of the owner-occupied sector. Most of cities of Japan are subject to the latter model and it means that the tenure of a farmhouse has significantly contributed to the expantion of the owner-occupation. The ratio of the owner-occupied has been determined not only by the factors which caused the change in the national level as mentioned above, but also by the special factors of each city such as historical and cultural characteristics concerning to the choise of housing tenure.
2 0 0 0 OA 高松市における讃岐うどん店の立地分析
- 著者
- 金 徳謙
- 出版者
- 日本観光研究学会
- 雑誌
- 観光研究 (ISSN:13420208)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.39-48, 2015 (Released:2016-12-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
The way of enjoying Sanuki Udon has been changed from eating to tasting and comparing some different Udon shops in all over Kagawa prefecture. This trend has led to Sanuki Udon boom. The purpose of this study is to clarify the locational characteristic of Sanuki Udon shops from spatial perspective in Takamatsu city, Kagawa prefecture. The analysis used GIS from 4 viewpoints that are Type of Service, Spatiality, Population, and Accessibility. As a result, it was revealed that the Sanuki Udon shop was located not to be conscious of tourists' behavior.
2 0 0 0 OA 母子関係と間主観性の問題
- 著者
- 鯨岡 峻
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.506-529, 1986 (Released:2019-07-24)
2 0 0 0 OA 酒石酸モランテルの毒性試験の概要
- 著者
- ファイザー製薬株式会社農産事業部農産開発部
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.S323-S325, 1992-11-20 (Released:2010-08-05)
酒石酸モランテルの安全性評価のため各種毒性試験を行なった.その結果, 本剤の急性毒性は比較的弱く, 普通物に該当する. 眼に対する刺激性はわずかに認められたが, 薬剤の希釈により刺激性は軽減した. また, 皮膚に対する刺激性はなかったが, 皮膚感作性は陽性であり, 皮膚にアレルギー反応を生じる可能性があると判断された. 一方, 6か月毒性試験では高用量群 (27,500ppm) において, 死亡例の発生, 体重の減少, 摂餌量の減少, 剖検時の全身性の消耗, 諸器官の萎縮性変化などがみられたが, 本剤投与による特異的な変化は認められなかった. 変異原性は陰性であった. また, 催奇形性に関しても問題はなかった.酒石酸モランテル液剤であるグリンガードは昭和57年11月に登録を取得した. また, 8%液剤であるグリンガード・エイトは昭和61年7月に登録を取得し, マツノザイセンチュウの侵入・増殖を阻止して松枯れを防止する樹幹注入剤として使用されている.酒石酸モランテルは, 定められた使用基準を遵守すれば, 安全性が確保されるものであり, 松枯れを防止する有用な農薬として上市以来好評を得ている.
- 著者
- 木村 はるみ タカノ ミサキ ヴィオレッタ 太田 結
- 出版者
- 山梨大学教育人間科学部
- 雑誌
- 山梨大学教育人間科学部紀要 = 山梨大学教育人間科学部紀要 (ISSN:18825923)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.259-274, 2015-03-06
2 0 0 0 OA 小学校生活科教科書における“アメリカザリガニ”の記述の変遷
- 著者
- 土井 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 42 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- pp.235-236, 2018 (Released:2019-06-15)
- 参考文献数
- 2
日本の小学校生活科の教科書にある学習後のアメリカザリガニの扱いに関する記述について調査した。その結果,約 30 年の間に,記述なしあるいは野外への放逐を推奨する記述から,野外放逐と飼育継続を選択させる記述を経て,飼育継続を推奨する記述へと変遷していることが明らかとなった。
- 著者
- 中谷 江利子 中川 彰子 磯村 香代子 大隈 紘子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.29-41, 2004-03-31 (Released:2019-04-06)
Prader-Willi症候群(PWS)は、筋緊張低下、肥満、性腺発育不全、精神遅滞を主徴候とする先天性疾患である。肥満とその合併症が生命予後にかかわることから、肥満対策が不可欠とされている。今回筆者らは、身体合併症(心不全、糖尿病、睡眠時無呼吸)があり、生命維持のために減量が必要であったが、食行動異常のほか、こだわり、かんしゃく、放火、俳徊などの多くの問題行動のため、小児科での治療が困難であった13歳男子のPWSの入院治療を行った。入院後も激しい問題行動と、体重測定さえできないほど肥満治療に対しての抵抗が強く、入院生活の継続も懸念された状態であったが、刺激を統制し、オペラント強化法を用いるための治療上の工夫を行ったことにより、患者が積極的に楽しく肥満治療に取り組みながら16kgの減量に成功し、身体合併症の著明な改善がみられた。この治療成果は本症例の生涯にわたる肥満治療において重要な役割を果たすと考えられた。
2 0 0 0 太陽 = The sun
- 出版者
- 平凡社
- 巻号頁・発行日
- 1963
2 0 0 0 OA 遮光製品(サンスクリーン)とその作用
- 著者
- 福井 崇
- 出版者
- 日本香粧品学会
- 雑誌
- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.32-38, 2019-03-31 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 20
In recent years, it is reported that UV light affect DNA damage, skin cancer and photo-aging such as age-spots and wrinkle. Along with the increasing awareness to protect the skin from UV light in these days, multi-functionalization is required to sunscreen not only for pool, sea and sports use, but also for daily use. Functions of sunscreen are needed to have high UV protection efficacy and less burden use feeling on the skin such as transparency after applying, moisturizing effect and comfortable feeling. In addition to that, it is reported that friction resistant function is important from the view point of actual consumer dairy life. This article reviews sunscreen formulations with high UVA protection efficacy and moisturizing of W/O technology by using plate like zinc oxide, and even protection film O/W technology by using α-gel capsule of UV absorbers. Furthermore, it also reviews UV protect evaluation method of sunscreen and sunscreen effects for photodermatosis, skin cancer and photo-aging such as age-spot, wrinkle and skin color evenness.
2 0 0 0 OA 造礁サンゴ類の石灰化機構と地球環境変動に対する応答
- 著者
- 鈴木 淳 井上 麻夕里
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 海の研究 (ISSN:09168362)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.177-188, 2012-09-15 (Released:2019-09-01)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
造礁サンゴの石灰化について,特に溶存無機炭素の役割に着目し,これまでに提唱されている石灰化メカニズムをレビューした。サンゴの石灰化は造骨細胞と骨格に挟まれた間隙の,いわゆる石灰化母液で進行する。石灰化の進行には,この石灰化母液にカルシウムイオンと溶存無機炭素(特に炭酸水素イオン)が適切に供給される必要があり,石灰化の阻害因子となる水素イオンが適切に除去されなければならない。造骨細胞に存在する炭酸脱水酵素は溶存無機炭素の供給に寄与していると考えられる。サンゴの石灰化機構の解明は,いまだ道半ばであり,今後の一層の研究の進展が待たれる。サンゴの石灰化メカニズムの解明は,その海洋酸性化影響を評価する上でも重要である。
2 0 0 0 OA 多発性硬化症への新規治療戦略
- 著者
- 村松 里衣子 山下 俊英
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.10, pp.936-939, 2012-10-01 (Released:2016-12-16)
- 著者
- 日本バーチャルリアリティ学会 [編] = Virtual Reality Society of Japan
- 出版者
- 日本バーチャルリアリティ学会事務局
- 巻号頁・発行日
- 1996
2 0 0 0 OA 『伊曽保物語』版本書誌解題稿 : 近世日本におけるイソップ寓話集出版の正像を求めて
- 著者
- 李 澤珍
- 出版者
- 明星大学日野校
- 雑誌
- 明星大学研究紀要. 人文学部・日本文化学科 = Bulletin of Meisei University. Department of Japanese and Comparative Culture, School of Humanities (ISSN:21862818)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.51-64, 2023-03-10
2 0 0 0 OA 介護保険領域でのマネジメント ―在宅サービスのマネジメント (経営的側面から)―
- 著者
- 森本 榮
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.8, pp.486-488, 2009-12-20 (Released:2018-08-25)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA スペイン語の教科書に現れるアラビア語起源語 : 文法用・会話用教科書における分析
- 著者
- 土井 裕文 Hirofumi Doi
- 出版者
- 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部
- 雑誌
- 研究論集 = Journal of Inquiry and Research (ISSN:03881067)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, pp.63-78, 2023-03
スペイン語はアラビア語起源の単語が豊富に含まれるといわれる。本研究は関西外国語大学スペイン語学科1年次のスペイン語の文法用・会話用教科書に現れるアラビア語起源の語を調査し、出現するアラビア語のアラビア文字による情報やアラビア語における頻度を紹介し、1年次で学ぶスペイン語の単語の知識がアラビア語学習にどのぐらい助けになるかを考察する。初級の教科書では、だいたい8ページに1単語程度がアラビア語起源であった。そのアラビア語起源の単語を精査していくと、アラビア語の世界で上位2000語に現れてくるのは、1/3程度であり、上位4200語に広げても2/3程度であった。よく使われるアラビア語とスペイン語におけるアラビア語起源の単語は、あまり連動しないという結果になった。
2 0 0 0 OA 変貌する家事紛争に対応した解決モデルの構築
- 著者
- 二宮 周平 田中 通裕 村本 邦子 渡辺 惺之 櫻田 嘉章 中野 俊一郎 佐上 善和 渡辺 千原 山口 亮子 松本 克美 立石 直子 松村 歌子 廣井 亮一 酒井 一 織田 有基子 長田 真理 高杉 直 北坂 尚洋 黄 ジンティ 加波 眞一 樋爪 誠 中村 正 団 士郎 佐々木 健 松久 和彦
- 出版者
- 立命館大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2010-04-01
家事紛争の中でも未成年の子のいる夫婦の紛争は、当事者の葛藤の程度に応じて3段階に分けることができる。葛藤が低い場合には、情報の提供や相談対応で、合意解決の可能性があり、中程度の場合には、家裁の家事調停において、調停委員や家裁調査官の働きかけによって合意解決の可能性がある。DVや児童虐待など高葛藤の場合には、家裁の裁判官が当事者を説得し、再度の和解や付調停により合意解決を図るとともに、監視付き面会交流など公的な場所、機関によるサポートや養育費の強制的な取り立てなど裁判所がコントロールする。当事者の合意による解決を促進する仕組みを葛藤の段階に対応して設けることが必要である。
2 0 0 0 OA 長野県のカブ・ツケナ品種
長野県に現存するカブ・ツケナ類の在来13品種(諏訪紅蕪,羽広菜,源助蕪菜,赤根大根,王滝蕪,開田蕪,細島蕪,吉野蕪,木曽菜,保平蕪,稲核菜,野沢菜,雪菜)の来歴,栽培地域,生態的特性および栽培と採取法について1997年と1998年に現地調査を行った。なお,品種の生態的特性については信州大学農学部実験圃場でも調査した。過去に長野県内で栽培されていたことがいくつかの文献に記載されている10品種(黒瀬蕪,木祖村蕪,三岳蕪,源助蕪,駒ヶ根蕪,小谷在来蕪,マナ蕪,相木在来蕪,苅野蕪,神代蕪)については所在が不明で,消滅したものと思われた。
2 0 0 0 ストーカーの日本史 : 神話時代から江戸時代まで
2 0 0 0 OA 医療機関職員における頭痛の実態調査
- 著者
- 加藤 宏一
- 出版者
- 一般社団法人 日本頭痛学会
- 雑誌
- 日本頭痛学会誌 (ISSN:13456547)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.584-589, 2023 (Released:2023-04-20)
- 参考文献数
- 7
医療機関での頭痛の実態調査を行い,就労者の健康や職場環境のあり方につき検討した.労働者健康安全機構東京労災病院に勤務する職員に対し,アンケート方式にてデータ収集を行った (回収率97%) .頭痛は女性に有意に多く,職種別では看護師に有意に多かった.頭痛時の自覚的な就業能力も低下しており,頭痛は気圧の変化,夜勤明け,忙しいときに生じやすかった.職場での配慮に関しては「自分からは言わない」と回答した職員が53.6%いた.頭痛で早退・欠勤したことがある職員は5%以下であった.頭痛時は就業能力が低下していても休める状況ではなく,プレゼンティーズムが問題であった.職場での頭痛に対する理解や休息できる環境整備などが重要である.