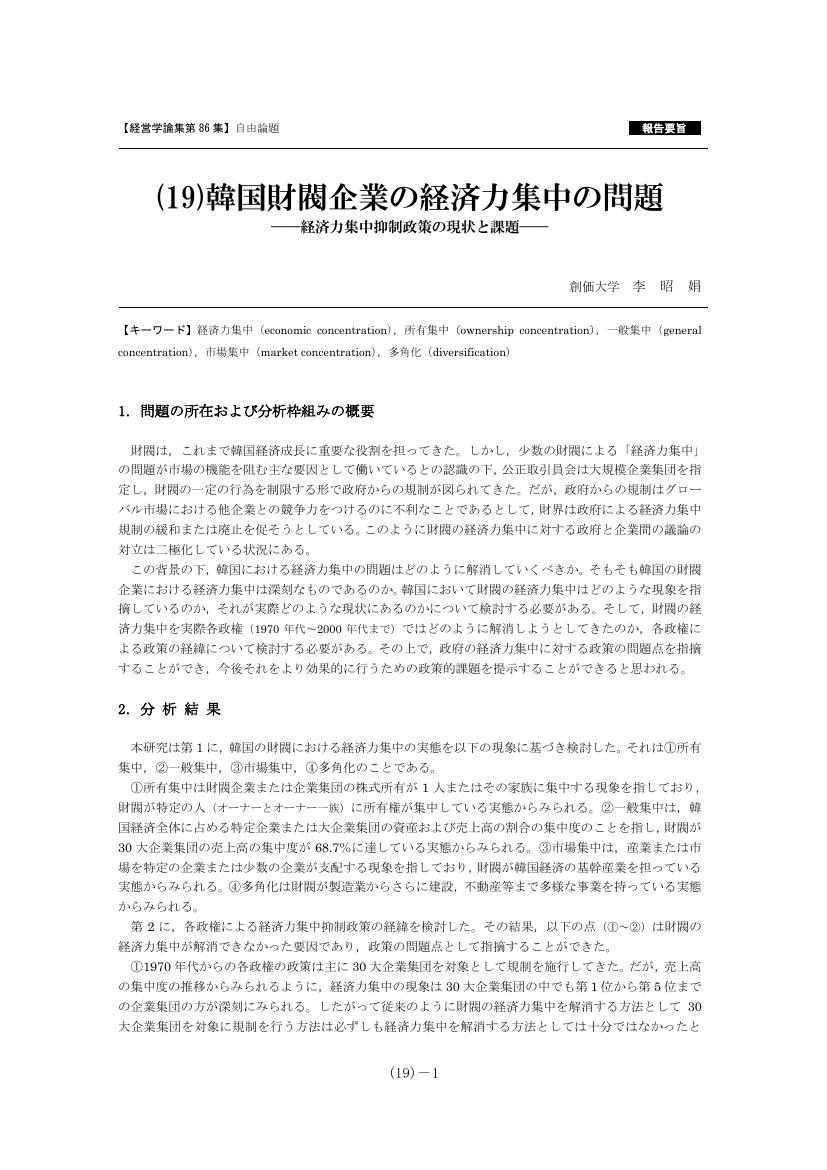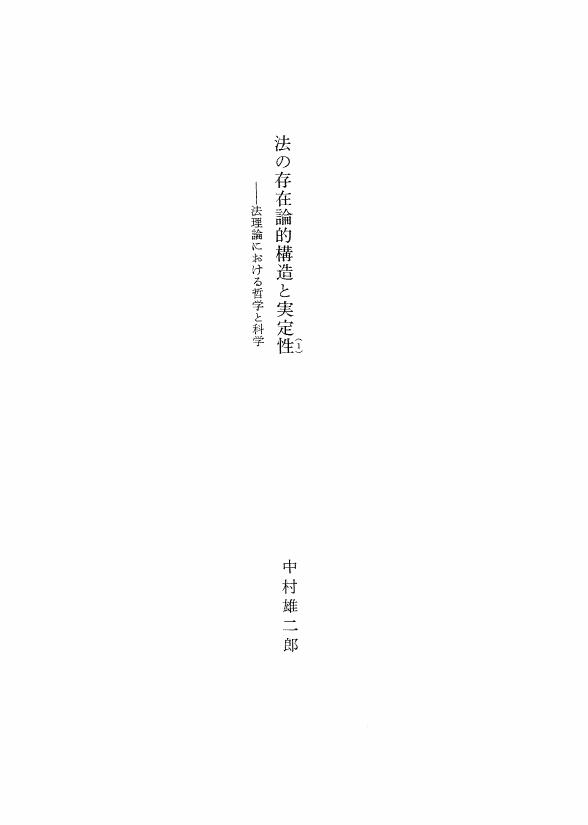2 0 0 0 OA 代替医療の利用と健康習慣の関連およびその背景
- 著者
- 中山 和弘 朝倉 隆司 宗像 恒次 園田 恭一
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.50-61, 1990 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2
The analyses presented here examine relationships between the use of alternative medicine and health practices as an attitude to health. The sample is individuals aged 20 and older living in Tokyo. Multivariate analyses show that there are two attitudes to the use of alternative medicine and health practices. One is the choice of both alternative medicine and health practice except time of sleep and living a regular life, the other is the choice of either traditional medicine or health practices. Though they don’t almost related with age, education and health status, they associate with sex, the saliency of health, and the consciousness of relationship between body and mind which is a major concept of holistic health.
2 0 0 0 OA 日中戦争下における三菱財閥の再編課程(1)
- 著者
- 浜淵 久志
- 出版者
- 北海道大学經濟學部
- 雑誌
- 北海道大學 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.263-292, 1980-03
2 0 0 0 OA (19)韓国財閥企業の経済力集中の問題 ──経済力集中抑制政策の現状と課題──
- 著者
- 李 昭娟
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F19-1-F19-2, 2016 (Released:2019-10-01)
2 0 0 0 OA 「斑人り」葉緑素突然変異体を用いた原因遺伝子の研究と最近の知見
- 著者
- 武智 克彰 坂本 亘
- 出版者
- 日本育種学会
- 雑誌
- 育種学研究 (ISSN:13447629)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.5-11, 2002 (Released:2021-08-24)
2 0 0 0 OA 腹腔側チューブが直腸に穿通し, 肛門より脱出したV-P (脳室・腹腔) シャントの1例
- 著者
- 新川 弘樹 井上 孝志 藤田 尚久 野尻 亨 古谷 嘉隆 黒田 敏彦 仲 秀司 安原 洋 和田 信昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.59-63, 2001 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3 3
V-P (脳室・腹腔) しゃんとの腹腔側ちゅーぶが直腸に穿通し, 肛門より脱出した稀有な1例を経験したので報告する. 症例は74歳の男性. 他院で脳内出血後の正常圧水頭症に対し, V-Pしゃんとを施行された. 10か月後, 髄膜炎で当院脳外科に入院, 抗生物質投与により軽快していた. 入院3か月後, 肛門よりしゃんとちゅーぶが脱出しているのを発見され, 当科紹介となった. 腹部には圧痛, 腹膜刺激症状を認めず, 白血球数6,400/mm3, CRP1.9mg/dlと炎症反応は軽度で, がすとろぐらふぃん ®による注腸造影X線検査で造影剤の漏出は認めなかった. 大腸内視鏡検査ではちゅーぶは肛門縁から10cmの直腸右側壁を穿通していた. 腹膜炎所見がないことから, 経肛門的にちゅーぶを抜去した. 1週間後の注腸検査で造影剤の漏出がないことを確認し, 経口摂取を再開した. V-Pしゃんとちゅーぶの消化管穿通はまれであるが, 注意すべき合併症の1つと考えられた.
- 著者
- 松本 洋輔
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- Nursing business = ナーシングビジネス (ISSN:18815766)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.7, pp.638-640, 2013-07
2 0 0 0 OA ナノドメインエンジニアリングによる高性能圧電材料の創成
- 著者
- 和田 智志
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.81-87, 2012-04-30 (Released:2012-05-15)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
To develop high performance piezoelectric materials, a new method called at “nanodomain engineering” was proposed and investigated in this study. The nanodomain engineering means a method, which can produce high density nanodomain configurations by control of chemical composition, i.e., to develop an intermediate state between relaxor ferroelectrics and normal ferroelectrics. To confirm the concept, ternary system ceramics of BaTiO3-Bi(Mg1/2Ti1/2)O3-BiFeO3(BT-BMT-BF) was prepared and characterized. As the results, a formation of nanodomain configurations was confirmed by a transmission electron microscopy. Moreover, for the ceramics with the nanodomain configurations, high apparent piezoelectric constants over 500 pC/N was clearly obtained, which suggested that the concept of “nanodomain engineering” might work good.
2 0 0 0 OA 不法領得の意思について
- 著者
- 穴沢 大輔
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.284-298, 2016-02-29 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 OA 戦国期本願寺教団の構造
- 著者
- 神田 千里
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.4, pp.461-495,626, 1995-04-20 (Released:2017-11-30)
The aim of this article is to shed some light upon the background of the ikkoikki (一向一揆) uprisings which took place in the Sengoku period. The author takes notice of one feature of the structure of the sect, in contrast to the previous research that has only observed the characteristics of the social class of its members. In the first place, the Hohganji-Shusu (本願寺宗主, chief priest of Honganji temple) could not be shusu Without the recognition of the Honganji family, its vassals, and the Monto (門徒, disciples). The author points out that this recognition prevailed among the bushi (武士, warrior) classes at that time. Secondly, the author analyzes gosho (御書) and goinsho (御印書) to show that the orders issued by shusu were accepted by the monto only after consultation among all the members. Therefore the sect was managed according to an agreement between the shusu and monto. Finally, the author points out the fact that this union of shusu and monto was closely concerned with both the doctrine preached by Honganji and the hope of monto to be born again in the pure land: thus, the mechanism of the uprising.
2 0 0 0 OA 三重サンベルトゾーン構想の推進と地域振興
- 著者
- 東 達二
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.603-608,a1, 1990-06-01 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 2
総合保養地域整備法が, 昭和62年6月9日公布施行された. 三重県では昭和58年3月の第2次長期総合計画において, すでに県南部のサンベルト計画があり, 国のリゾート法に素速く対応でき, これの承認第1号となった.旧来からの観光地から脱皮した長期滞在型, 開かれた国際型の薪しいリゾート構想と, その推進計画について述べた.
2 0 0 0 性同一性障害の脳科学
- 著者
- 山田 幸樹 金野 倫子 内山 真
- 出版者
- NIHON UNIVERSITY MEDICAL ASSOCIATION
- 雑誌
- 日大醫學雜誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.137-141, 2013-06-01
- 参考文献数
- 13
Gender identity disorder (GID) is defined as a sexual disorder characterized by strong self-identification with the opposite gender, followed by unpleasant feelings due to the birth-given gender. This paper examines the current diagnostic criteria and treatment for GID. While the etiology of GID remains unknown, several hypotheses have been proposed. We describe the evolution of the hypotheses on the etiology of GID. The possible biological pathogenesis of GID is also discussed mainly from the viewpoint of brain science. Similar to animal studies, it has been reported that fetal or neonatal gonadal steroids are responsible for sexual differentiation of the human brain, which might be related to gender identity and sexual orientation. Based upon the findings of investigations into the biological basis of GID, valuable insights into GID are suggested.
2 0 0 0 OA 地方再生 : 分権と自律による個性豊かな社会の創造 : 総合調査報告書
- 著者
- 国立国会図書館調査及び立法考査局
- 出版者
- 国立国会図書館
- 巻号頁・発行日
- 2006-02
- 著者
- 橋本 明
- 出版者
- 愛知県立大学『社会福祉研究』編集委員会
- 雑誌
- 社会福祉研究 = Social welfare studies (ISSN:13457179)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.21-38, 2020-11
- 著者
- HORI Madoka Nagai
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- アジア新時代の南アジアにおける日本像 : インド・SAARC諸国における日本研究の現状と必要性
- 巻号頁・発行日
- pp.119-128, 2011-03-25
アジア新時代の南アジアにおける日本像 : インド・SAARC 諸国における日本研究の現状と必要性, ジャワハルラル・ネルー大学, 2009年11月3日-4日
2 0 0 0 OA 法の存在論的構造と実定性 法理論における哲学と科学
- 著者
- 中村 雄二郎
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1973, pp.71-95, 1974-10-30 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 26
2 0 0 0 OA 非平衡効果によるプリュームを伴う恒星対流のモデリング
- 著者
- 横井 喜充 政田 洋平 滝脇 知也
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.17-23, 2022-02-01 (Released:2022-02-25)
- 参考文献数
- 8
プルームをコヒーレントな構造ゆらぎと考え,プルーム運動に沿った非平衡効果を用いて対流乱流の輸送モデルを構成し,恒星内部の対流に適用する.恒星表面での冷却で駆動される対流の顕著な特徴のひとつは,表面層の直下で観測される大きくて局在化した乱流質量輸送である.そのような輸送の特徴は,混合距離理論を用いた通常の渦粘性型モデルでは全く再現できないが,非平衡効果を組み入れた今回のモデルでよく表現することができる.本研究の結果は,非平衡効果を通してプルーム運動を乱流モデルに組み入れることは,通常の混合距離理論を用いた経験的なモデリングを超えて,平均場理論の重要で価値ある拡張となりうることを示している.
2 0 0 0 保安司(ポアンサ) : 韓国国軍保安司令部での体験
2 0 0 0 OA 災害現場で実施するfield amputationのプロトコル策定
- 著者
- 岩﨑 恵 庄古 知久 吉川 和秀 安達 朋宏 齋田 文貴 赤星 昂己 出口 善純
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.55-63, 2019-02-28 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 20
field amputationは非常にまれであるが,時間的猶予のない傷病者には救命の切り札となり得る。海外の災害では四肢切断による救助例も報告されているが,現状の東京DMATに切断資機材はない。目的:当センターにおけるfield amputationプロトコルの策定。方法:わが国のfield amputationに関する文献を医学中央雑誌で検索しその実態について調査する。 同時に海外のプロトコルや報告例も調査する。結果:わが国では過去8件の現場四肢切断実施報告があり,受傷機転は機械への巻き込まれ事案が多い。約半数で切断資機材は後から現場に持ち込まれている一方,米国では出動に関するプロトコルや資機材リストが存在した。結論:field amputationは救命のため必要な場合があり,出動段階から考慮することで救出時間短縮につながる可能性がある。出動段階から適切な対応が取れるようにプロトコルを策定すべきである。
2 0 0 0 OA 局所麻酔薬とコカイン(クスリの化学(18))
- 著者
- 梶本 哲也
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.468-469, 2007-09-20 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA 日本語の語彙的複合動詞における動詞の組み合わせ
- 著者
- 松本 曜
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.114, pp.37-83, 1998-12-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 71
ilit