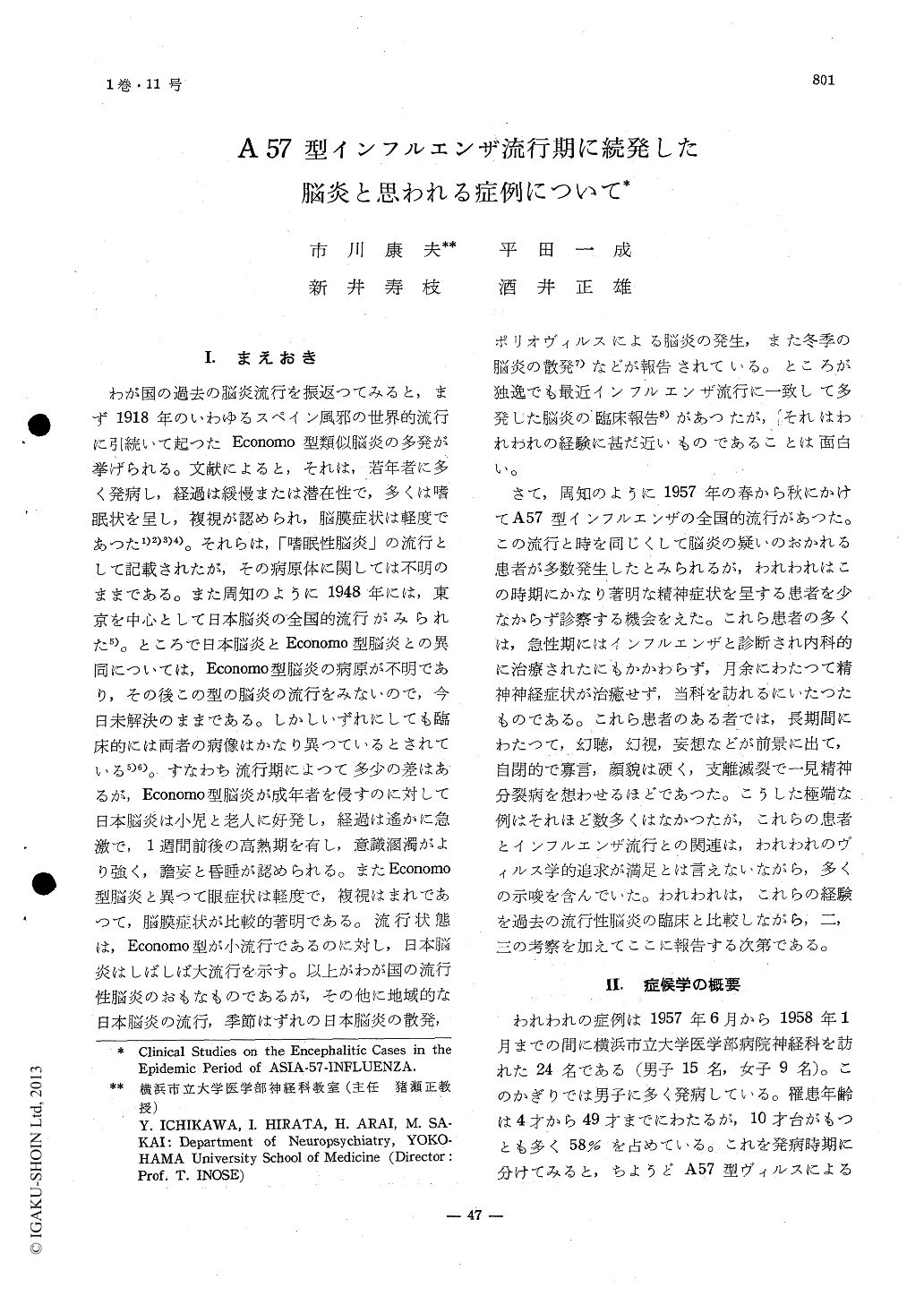2 0 0 0 OA 牛若の強盜退治附りその遺跡 : 熊坂長範と藤澤入道とは同一人か
- 著者
- 沼波 守
- 出版者
- 相愛女子短期大学
- 雑誌
- 相愛女子短期大学研究論集 (ISSN:09103546)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.1-12, 1955-03
2 0 0 0 OA 東アジアにおける労働者に対する健康診断の現状
- 著者
- 大神 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合健診医学会
- 雑誌
- 総合健診 (ISSN:13470086)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.323-328, 2020-03-10 (Released:2020-09-05)
- 参考文献数
- 18
日本型の労働者に対する健康診断のシステムは、企業によっては人間ドックや、がん検診なども含めて「健康診断」という範疇にて実施されている現状がある。労働衛生(産業保健)の分野で行われる健康診断では、医学的サーベイランスと医学的スクリーニングは個別の概念と手法で行われるべきで、労働衛生上明確かつ補完的な二次予防要素と見なされるべきである。本稿では、東アジア諸国(韓国、中華民国(台湾)、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、インド)の労働者に対する健康診断について、その法的な背景を概説しつつ、東アジア諸国の労働者の健康管理について健康診断の現況について文献的検索を試みた。
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1887年09月12日, 1887-09-12
Ⅰ.まえおき わが国の過去の脳炎流行を振返つてみると,まず1918年のいわゆるスペイン風邪の世界的流行に引続いて起つたEconomo型類似脳炎の多発が挙げられる。文献によると,それは,若年者に多く発病し,経過は緩慢または潜在性で,多くは嗜眠状を呈し,複視が認められ,脳膜症状は軽度であつた1)2)3)4)。それらは,「嗜眠性脳炎」の流行として記載されたが,その病原体に関しては不明のままである。また周知のように1948年には,東京を中心として日本脳炎の全国的流行がみられた5)。ところで日本脳炎とEconomo型脳炎との異同については,Economo型脳炎の病原が不明であり,その後この型の脳炎の流行をみないので,今日未解決のままである。しかしいずれにしても臨床的には両者の病像はかなり異つているとされている5)6)。すなわち流行期によつて多少の差はあるが,Economo型脳炎が成年者を侵すのに対して日本脳炎は小児と老人に好発し,経過は遙かに急激で,1週間前後の高熱期を有し,意識溷濁がより強く,譫妄と昏睡が認められる。またEconomo型脳炎と異つて眼症状は軽度で,複視はまれであつて,脳膜症状が比較的著明である。流行状態は,Economo型が小流行であるのに対し,日本脳炎はしばしば大流行を示す。以上がわが国の流行性脳炎のおもなものであるが,その他に地域的な日本脳炎の流行,季節はずれの日本脳炎の散発,ポリオヴィルスによる脳炎の発生,また冬季の脳炎の散発7)などが報告されている。ところが独逸でも最近インフルエンザ流行に一致して多発した脳炎の臨床報告8)があつたが,それはわれわれの経験に甚だ近いものであることは面白い。 さて,周知のように1957年の春から秋にかけてA57型インフルエンザの全国的流行があつた。この流行と時を同じくして脳炎の疑いのおかれる患者が多数発生したとみられるが,われわれはこの時期にかなり著明な精神症状を呈する患者を少なからず診察する機会をえた。これら患者の多くは,急性期にはインフルエンザと診断され内科的に治療されたにもかかわらず,月余にわたつて精神神経症状が治癒せず,当科を訪れるにいたつたものである。これら患者のある者では,長期間にわたつて,幻聴,幻視,妄想などが前景に出て,自閉的で寡言,顔貌は硬く,支離滅裂で一見精神分裂病を想わせるほどであつた。こうした極端な例はそれほど数多くはなかつたが,これらの患者とインフルエンザ流行との関連は,われわれのヴィルス学的追求が満足とは言えないながら,多くの示唆を含んでいた。われわれは,これらの経験を過去の流行性脳炎の臨床と比較しながら,二,三の考察を加えてここに報告する次第である。
2 0 0 0 OA 定松淳『科学と社会はどのようにすれ違うのか―所沢ダイオキシン問題の科学社会学的分析』
- 著者
- 立石 裕二
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.251-255, 2020-04-30 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 バーバラ・ピムの世界 : その日常性と孤独
- 著者
- 太田 洋子
- 出版者
- プール学院大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:09110690)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.29-49, 1990-12-21
2 0 0 0 IR 社会福祉における身元保証問題 : 高齢者の施設入所・病院入院に焦点を当てて
- 著者
- 飯村 史恵 イイムラ フミエ Fumie Iimura
- 雑誌
- 立教大学コミュニティ福祉研究所紀要
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.1-17, 2020-11
2 0 0 0 OA 水力発電施設に関わる災害事例の収集と溢水被害に伴う社会的影響評価法の検討
- 著者
- 梶谷 義雄 山本 広祐 豊田 康嗣 中島 正人
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F4(建設マネジメント) (ISSN:21856605)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.1-13, 2011 (Released:2011-01-20)
- 参考文献数
- 55
本研究では,水力発電施設の災害や事故による社会的影響を対象に,その分析手法や分析結果の効果的な活用方法について検討する.まず,過去の水力発電施設の被害事例の調査や分析を通じて,将来的に懸念される社会的影響発生のシナリオを構築する.次いで,過去事例にも散見される水力発電施設からの溢水が発生するシナリオを対象に,その定量的な分析手法について検討を行う.最後に,事例分析として,仮想的な水力発電施設や地域の人口・経済データを対象に,導水路損壊による社会的影響評価を実施し,被害額や発電による便益の観点から,災害対策優先度などの水力発電施設の維持管理戦略への反映可能性について考察した結果を報告する.
2 0 0 0 シリコン系極薄膜(∼1 nm)の結晶シリコン太陽電池への応用
- 著者
- 大平 圭介 中島 寛記 文 昱力 Huynh Thi Cam Tu
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面真空学会
- 雑誌
- 表面と真空 (ISSN:24335835)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.91-96, 2023-02-10 (Released:2023-02-10)
- 参考文献数
- 16
Ultrathin (∼1 nm) films have been widely used for high-efficiency crystalline silicon (c-Si) solar cells such as tunnel oxide passivated contact (TOPCon) solar cells. In this article, we present our recent results for the applications of ultrathin silicon oxide (SiOx) and silicon nitride (SiNx) films to c-Si solar cells. The following topics are reviewed. 1) Ultrathin SiNx can be utilized for passivating contacts instead of SiOx in the TOPCon structure. 2) The addition of SiOx between c-Si and thick catalytic-chemical-vapor-deposited (Cat-CVD) SiNx significantly improves the quality of surface passivation. 3) Ultrathin Al-doped SiOx films formed just by dipping in Al(NO3)3 solution on c-Si provide strong upward band bending due to negative fixed charges, which can be used for hole-selective contacts.
2 0 0 0 OA 慰安婦報道の出発点 ――1991 年 8 月に金学順が名乗り出るまで
- 著者
- 水野 孝昭
- 出版者
- 神田外語大学
- 雑誌
- 神田外語大学紀要 = The Journal of Kanda University of International Studies (ISSN:09175989)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.241-269, 2019-03
論文
2 0 0 0 IR 社会福祉におけるスピリチュアリティ : 宗教と社会福祉の対話
- 著者
- 木原 活信 Katsunobu Kihara
- 出版者
- 基督教研究会
- 雑誌
- 基督教研究 (ISSN:03873080)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.17-41, 2016-06
社会福祉とキリスト教の関係について、福祉国家以前の慈善時代と、福祉国家下の措置制度時代、そしてポスト福祉国家としての現代の市民的契約の時代の3つに分類しつつ、そこでの宗教の役割の変遷についてキリスト教を例にスピリチュアリティの概念をもとに分析した。そのなかで市民契約の時代の宗教と社会福祉の在り方に着目し、市民的公共圏における社会福祉とスピリチュアリティについてEdward Candaの理論を踏まえつつ、議論した。論文(Article)
2 0 0 0 OA 栃木県における自殺の実態 2007年,2008年の警察データの解析
- 著者
- 中村 好一 伊東 剛 千原 泉 定金 敦子 小谷 和彦 青山 泰子 上原 里程
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.807-815, 2010 (Released:2014-06-12)
- 参考文献数
- 25
目的 警察のデータを用いて栃木県の自殺の実態を明らかにし,自殺対策を進める上での要点を示すと共に,警察データの利点と問題点を検討する。方法 栃木県警察本部から提供を受けた2007年,2008年 2 年間の自殺データ(小票)を集計解析した。結果 栃木県における観察した 2 年間の自殺は1,166件(男865件,女301件)であった。人口あたりの自殺件数は全国と比較して高い傾向にあった。男では50歳代が最も多かったのに対して,女では30歳代から70歳代までほぼ同じ人数であった。20歳代,30歳代で人口あたりの件数が全国よりも高い傾向が観察された。平日の早朝や午前10時台に多い傾向が観察された。自殺場所は自宅が最も多く,手段は縊死が最も多かった(いずれも全体の約 6 割)。自殺の原因・動機(1 件の自殺について 3 つまで選択)では健康問題が最も多く(61.3%),次いで経済・生活問題(22.7%),家庭問題(17.3%)であった。健康問題では身体疾患と精神疾患がほぼ半数ずつを占めていた。経済・生活問題は20~60歳代の男で圧倒的に多く,中でも多重債務が多かった。約 3 分の 1 の者が遺書などを残していた。15.9%は自殺未遂の経験があった。以上のような結果をもとに検討した結果,栃木県の自殺対策を推進する上で,(1)学校保健や職域保健のさらなる充実,とくに20歳代および30歳代男への対応,(2)自殺のリスクが高い者に対して,家族への指導などにより常に他者の目が届くようにしておくことの重要性,(3)自殺未遂経験者へのハイリスク者としての対応,(4)相談窓口(とくに多重債務)の充実と住民への周知,(5)身体疾患をもつ患者の心のケアの充実,(6)精神疾患をもつ患者の治療を含めた管理の充実,の 6 点が重要であることを示した。さらに,警察データにおける原因・動機は,現場を捜査した警察官が判断しているために,心理学的剖検と比較すると情報の偏りが大きく妥当性は落ちるが,全数を把握しているために選択の偏りはなく,この点は心理学的剖検に勝るものであることを議論した。結論 警察のデータを用いて栃木県の自殺の実態を明らかにし,栃木県での自殺対策を進める上での要点を提示した。利点と問題点を理解した上で利用すれば,警察のデータも自殺予防対策に有用な情報を提供することを示した。
2 0 0 0 フーリエ解析を用いた死後CT画像における骨の性別判定
法医学実務における骨の鑑定は、現在もなお重要であり続けている。身元特定の第一歩としての性別判定は、その確定にDNA検査が必要であるが、骨の保存状態によってはDNA検査ができない場合があり、形態学的な判定の精度を高める必要がある。一般にDNAを用いない性別判定には、形態観察法と数値計測による方法とがある。前者は、熟練者の的中率は高いものの、客観性・再現性に問題が生じる。後者は全体や特定の部位の大きさを計測する方法がほとんどで、骨の複雑な形状を十分に反映しておらず、熟練者の形態観察に精度で劣るものが多い。男性の骨が大きく、女性の骨が相対的に小さいといった傾向がそのまま判断基準となり、中間的な大きさの骨を男女それぞれに正確に分類することはうまくいっていないものが多い。本研究の目的は人骨に対してフーリエ解析を実施することにより、客観的かつ骨形態を十分に反映した高精度の性別判定法を確立することである。フーリエ解析は画像解析の分野で広く用いられているが、その特性は複雑な骨形態の解析にもよく適している。また、本研究では死後CT画像を対象としてフーリエ解析を実施しているが、実際の骨を写真撮影などして二次元情報に落とし込むよりも、再現性・証拠保全性・易作業性といった点で優れている。頭蓋骨に関して鼻根部から冠状縫合までの正中線の形状(スブナジオン-ブレグマ間)をち抽出し、解析したところ、肉眼的な形態観察法と同等程度の的中率(83%~90%)が得られ、国際学会で報告した。最終年度には、実務に即した運用を検討し、誤判定率(10~17%)をより減らすため、男女2群に分けるのではなく、判断保留群を加えた3群に分けることにした。その結果、誤判定率を1%まで下げることができたが、同時に74%の判断保留が生じた。判断基準の設定にはなお検討を要する。
2 0 0 0 OA 明末の中国に伝えられた「科学革命」の成果
- 著者
- 橋本 敬造
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.73-86, 1981-11-30
神先秀雄・薄田桂・友松芳郎三教授古稀記念特輯
2 0 0 0 OA コルセットと女性像 : コルセットからの解放を中心に
- 著者
- 福島 利奈子
- 雑誌
- 人間文化研究 (ISSN:13480308)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.161-175, 2011-02-01
現代ではあまり馴染みのないコルセットだが、昔の女性たちには欠かすことのできないものだった。コルセットの歴史は長く、中世以降、衣服における男女差が確立し、女性の身体の曲線美をコルセットの使用によって表現するようになった。一時は鳴りを潜めていたコルセットだが、その後復活し、女性には「女らしさ」が求められ、長く着用されていくことになる。女性は社会的に抑圧された存在であり、女性たちが求められた女らしさは、男性の視線によって理想化されたものであった。そして、人々が装うのは、身体を保護するというためだけではなく、社会的な属性や地位等の表現手段ともなっていた。その後、次第に女性の衣服改革が起こるようになる。女性のライフスタイルの変化が理想の女性像まで変え、自然で直線的な身体の表現へと移行した。第一次世界大戦を境に、より女性の社会進出は進み、仕事に適さないコルセットや丈の長い衣服は消えていく。その過程を、コルセットの追放に貢献したとされるアメリア・ブルーマー、ポール・ポワレ、ガブリエル・シャネルの三人に焦点を当てて検討する。以上の問題を踏まえて、近代から現代にいたるまで長きに亘って女性が身につけてきたコルセットとはどのようなものであったのか、そしてそのコルセット着用の要因と、それほどまでに広く普及していたコルセットを女性たちがどのように脱ぎ捨ててきたのかを考察する。
- 著者
- 脇 遼太朗 楠本 泰士 高橋 克弥 加藤 愛理
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.12292, (Released:2023-02-13)
- 参考文献数
- 27
【目的】股関節筋解離術前後の歩行パターンの変化をEdinburgh Visual Gait Score(以下,EVGS)を用いて明らかにすることとした。【方法】対象は股関節筋解離術を施行したGross Motor Function Classification System(以下,GMFCS)レベルI・IIの脳性麻痺患者16名とし,手術前と退院時にEVGSの評価を行い,合計・各関節・各項目のスコアを対応のあるt検定,χ2検定にて検討した。【結果】手術前の総EVGSスコアは28.9±7.4点だったのに対し,退院時は18.5±8.0点と有意に改善が見られた。各関節の変化では全ての関節で有意な変化が見られた。【結論】GMFCSレベルI・IIの脳性麻痺患者では,股関節筋解離術と術後早期の理学療法介入によって,歩行パターンが術後9週において有意に改善した。また,股関節筋解離術後に理学療法介入を行う際は,股関節のみに注目するのではなく,全体的な歩行パターンの変化を考慮する必要があると考えられる。
2 0 0 0 OA 大久野島における観光対象の変遷と観光行動
- 著者
- 富川 久美子
- 出版者
- 日本島嶼学会
- 雑誌
- 島嶼研究 (ISSN:18847013)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.1-13, 2022-03-31 (Released:2022-04-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
Studies on island tourism, especially on areal development have been accumulated. As many of these studies in Japan are based on case studies aiming to introduce ideal tourism development to tourism developing islands, their main research objects are areas but not tourists. This study intended to clarify transition of tourist attractions and to analyze recent tourist behaviors on Okunoshima. The beginning of tourism on the island was in 1963, when a national hotel Kyukamura Okunoshima was opened. Until the early 1980’s, the main tourist attractions had been leisure facilities of Kyukamura and island’s nature. In 1988, when the poison gas museum was opened, archaeological tourism added to one of the main tourist attractions on the island. Along with the increase of rabbits on the island, tourists increased to meet and feed hundreds of rabbits. Then media and SNS ignited rabbit island boom. It is notorious that transition of tourist attractions caused by social trends of the moment, but the recent cause highly depends on information like SNS. The author analyzed 413 reviews, in which written in Japanese 214 and in English 189, on a travel website, Tripadvisor. The main tourist behavior on this island is interacting rabbits. Whereas rabbits attract lots of tourists, some environmental issues are clarified, such as overcrowded rabbits and tourists, increased injured and diseased rabbits. Other than rabbits, the poison gas museum and beautiful landscape on the island are also highly estimated especially by foreign tourists. To sustain the island tourism, diversification of tourist behaviors and limiting the number of tourists will be inevitable on Okunoshima.
- 著者
- 落合 甲太
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.644-646, 2013 (Released:2014-03-13)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA 書道界の制度と力学 : 現代日本の書道会と展覧会活動についての考察
- 著者
- 大野 加奈子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.165-187, 2007-09-30 (Released:2017-08-22)
本稿では、日本の伝統文化とされる「書」について、現在見られる日本の書道界のシステムをそこで活動する一般修練者の立場から記述して提示し、茶道やいけ花の家元制度と比較してその特徴を考察する。日本の書は、本来情報伝達手段であり実用的なものであったが、日本の近代化の中で実用的価値が薄れ消滅の危機を迎えた。「芸術」「伝統文化」へその存在価値を求めた書は、義務教育への参入を通して日本人の誰もが書を経験するものとなり、日展をはじめ出品数2万点を越す全国規模の大型展覧会の開催といった活動を通し、現在の日本の書とそれを支える書道界を作り上げた。日本の書道界では、日展を権威のヒエラルヒーの頂点とした、全国規模の大型展覧会での受賞歴により階梯を登るシステムが形成されている。そのシステムを家元制度と称し、西山松之助が『家元制度の展開』で書道界(会)について述べている。書道界(会)のシステムを家元制度との比較から考察し、そこに働く力学を探る。書道界(会)は家元制度的な組織運営形態をとっているが、代々続く家元や継承すべき型は存在せず、書道界で地歩を築き上昇するための方策として家元的制度を採用していること、またそうすることで書道界全体が日本の「伝統文化」の中に位置づけられるのを目指す意図があったことを示す。
2 0 0 0 OA 明治期和訳聖書における聖書用語--「悪魔」と「鬼」
- 著者
- 加藤 早苗
- 出版者
- 岐阜聖徳学園大学国語国文学会
- 雑誌
- 岐阜聖徳学園大学国語国文学 (ISSN:13457160)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.122-105, 2009-03