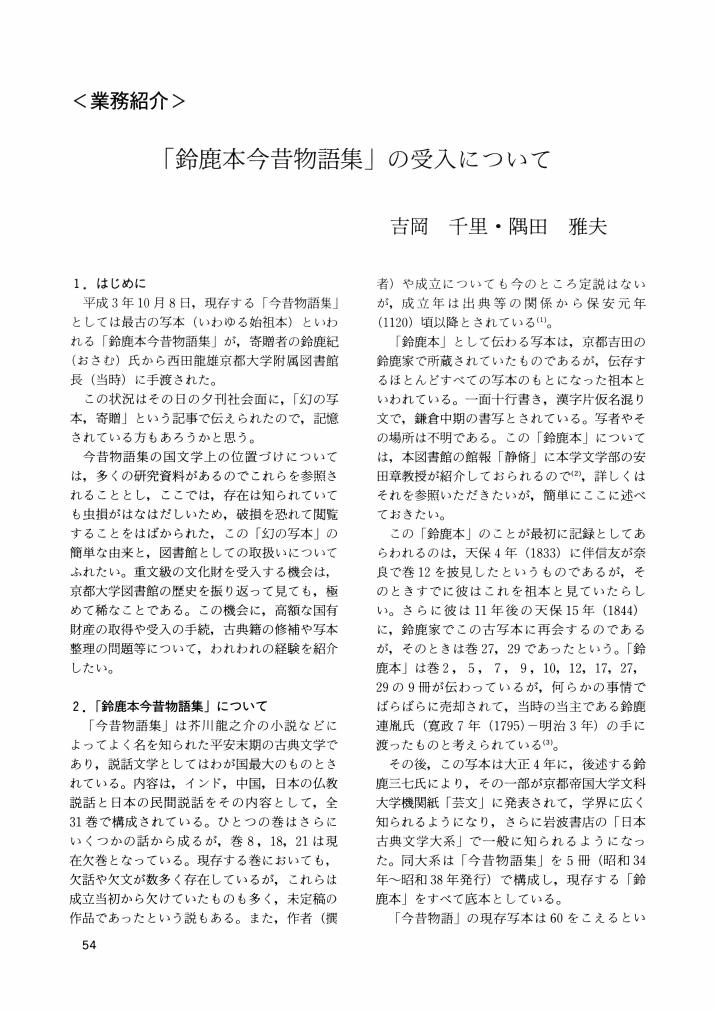2 0 0 0 OA 実験動物としてのミニブタ
- 著者
- 谷岡 功邦
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.11, pp.1026-1028, 1979-11-01 (Released:2018-08-26)
2 0 0 0 OA 競争課題において人工知能に負けたとき,人々はその敗北をどの要因に帰属するのか?
- 著者
- 横井 良典 中谷内 一也
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第85回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.PC-022, 2021 (Released:2022-03-30)
近年,「人工知能(AI)が人間の仕事を奪う」,「AIが人間を打ち負かす」といったことが議論されている。人間がAIに競争で負けとき,その敗因をどう推察するのかという原因帰属が検討されなければならない。なぜなら,原因帰属は将来の取り組み,感情,自尊心といった多くの変数に影響するからである。AIに負けたときの原因帰属を検討するために,大学生74名を対象に実験室実験を行った。AIと戦うAI条件,人間と戦う人間条件を設けたが,条件に関わらず,参加者はAIと対戦した。人間条件の参加者は事前に「別の参加者と戦います」と教示された。競争課題として,棒取りゲームというオリジナルの課題を使った。このゲームでは,参加者は必ず負けるように仕組まれていた。ゲーム終了後,参加者が敗因をどこに帰属しているのかを測定した。また,同じ相手に再挑戦したいかどうかを行動反応として選択させた。分析の結果,AI条件,人間条件に関わらず,参加者は自身の能力が最も大きな敗因であると帰属していた。再挑戦の選択に関しては,AI条件,人間条件ともに,再挑戦したい参加者の割合は少なかった。
2 0 0 0 OA 患者と家族をつなぐケアコミュニケーションサービスの実装と有効性の検証
- 著者
- 安孫子 忠彦 飯島 英則 小山 明夫 上林 憲行 成田 徳雄
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.87(2003-EIP-020), pp.55-60, 2003-08-28
参与観察手法による入院患者の生活の一日観察を通して入院患者は時間を持て余している事,その家族は忙しい中毎日面会に来ている事などの調査結果を得ることができた.そこで入院患者の生活の質(QOL: Quality Of Life)の向上を目的としたサービスとして,ネットワークとマルチメディアを用いた遠隔コミュニケーションサービスを提案する.PCをベースとし,カメラ,マイク,スピーカ,音声チャットソフトなどを用いてシステムを構築し,利用者誰もが使えるような操作簡略化の工夫を凝らした上で,この遠隔コミュニケーションサービスが実社会の入院患者に対してどれだけ有効であるかを実際のフィールドで実験を行い検証した.
2 0 0 0 OA 見えないものを撮る : 往還の行為によって生起するフォルム
2 0 0 0 OA 「鈴鹿本今昔物語集」の受入について
- 著者
- 吉岡 千里 隅田 雅夫
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.54-60, 1994-03-31 (Released:2018-02-10)
2 0 0 0 OA 日本の洋装化にみる和服地の使用について
- 著者
- 尾形 恵
- 出版者
- 文化学園大学
- 雑誌
- 文化学園大学紀要. 服装学・造形学研究 (ISSN:21873372)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.125-130, 2013-01
本論文は、日本人の洋装化がどのような経緯で普及したか、また日本人女性が着用した洋装に和服地が使われていたのかについて調査することを目的とする。日本の洋装化は江戸時代に始まっていたが市民に普及することはなく、明治時代に外交問題解決や社交場などとして造られた鹿鳴館で、上層階級の人々が欧米のバスルスタイルを取り入れた洋装化をきっかけとして、一部の市民への洋装化の浸透を促したといえる。このバスルスタイルのドレスは海外からの輸入に頼るだけではなく、洋裁技術を日本人が習得、着用する姿が浮世絵に残されていた。浮世絵に描かれる日本女性の着装しているドレスの柄と、きものの文様について関係性を調べた結果、鹿鳴館スタイルのドレスの柄には植物の柄が多く、梅や牡丹といった日本人に親しみ深い花や、蔦を図案化した唐草文様が描かれていた。唐草文様は中国より伝来し日本独自に発展した文様である。また、幾何学文様では菱文が多く見られ、発生は縄文時代と古いものである。いずれも日本のきものの柄の中にも取り入れられてきた文様である。このことからもバスルドレスを日本人が作るにあたり、和服地を利用してきたことが分かった。
2 0 0 0 OA 土木分野における女性技術者の現状と支援の動向
- 著者
- 山田 菊子 岡村 美好 日下部 治
- 出版者
- Japanese Society for Engineering Education
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.3_107-3_112, 2011 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 26
Women accounts for only some 2% of civil engineers in Japan and that is significantly small compared to the engineers of other fields, or the target “30% by 2020” set by the government. However, supports for women civil engineers in Japan first began in the 1980s and is now expanding to the private firms. In this study, the statistics of women civil engineers are grasped at first. Then the activities by firms, academic societies and organization of women civil engineers are reviewed to further discuss the possibility and challenges. Conclusion includes the importance of 30-year dedication by the self-help groups of women civil engineers, and the need of awareness and leadership by the top management for effectively supporting women civil engineers.
2 0 0 0 仙台叢書
- 著者
- 仙台叢書刊行会 [編]
- 出版者
- 仙台叢書刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.第9巻, 1926
2 0 0 0 OA 同盟はなぜ失われたのか ─日英同盟の終焉過程の再検討一九一九―一九二一─
- 著者
- 中谷 直司
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.180, pp.180_111-180_125, 2015-03-30 (Released:2016-05-12)
- 参考文献数
- 50
What was it that eventually put a period to the Anglo-Japanese alliance at the beginning of the interwar years, a treaty that had been the most successful treaty in East Asia to that moment, through two victories in the Russo-Japanese War of 1904-1905 and the First World War of 1914–1918? As many previous works have claimed, was the strong pressure from the United States decisive in terminating the alliance? Or else,as some British works in relatively recent years have argued, was the opposition of the United States no more than the last push to bring down the curtain on the arrangement, if discarding the alliance had already become all but a foregone course in London by the time Washington made clear its opposition? This study will challenge both accounts. First, it will show that the American opposition alone was not and could have not been enough to put an end to the alliance, even though this opposition did indeed create the international dispute itself over whether or not the alliance should be continued. At the same time, the study will deny that London was almost independently decided on the matter. The British government did need something external to help it with its decision; however, that was not the increase of American pressure but the restoration of the credibility of America’s commitment to a new international order-building program, at least in the Asia-Pacific region. To this point, American diplomacy had had trouble displaying this commitment, due to the country’s failure to join the League of Nations that the US itself had conceived. Therefore, secondly, this work will emphasize the serious dilemma that the British alone confronted in the international politics that led to the lapse of the alliance. That dilemma can be well understood as a variety of the “security dilemma in alliance politics” very well known to IR students. Major previous works,especially in British research, believe that Japan consistently held the alliance to be more significant than Britain did until the last day of the treaty, because the former gained greater advantages through an alliance with the leading power in world politics. However, this study will largely revise this view by describing both Britain’s international political dilemma and Japan’s diplomatic changeover in the aftermath of the Great War.
- 著者
- 中尾 知代
- 出版者
- 岡山大学文学部
- 雑誌
- 岡山大学文学部紀要 (ISSN:02854864)
- 巻号頁・発行日
- no.71, pp.17-34, 2019-06-28
- 著者
- 岡野 英之
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.019-038, 2019 (Released:2019-09-04)
- 参考文献数
- 37
アフリカ諸国の紛争を扱った政治人類学および政治学の研究において、社会の統治過程に見られるパトロン=クライアント関係の分析は重要な課題の1つとなってきた。これらの議論では、パトロンとクライアントとの間に取り結ばれるインフォーマルな人間関係が統治のツールとなっているという理解が前提となっている。政治学ではパトロン=クライアント関係に対して議会制民主主義と官僚制が対置され、両者を導入することにより、統治の場からパトロン=クライアント関係を払拭できると考えられる。では、官僚制や民主主義が組織運営に導入されると、パトロン=クライアント関係を支えるモラリティは失われるのだろうか。本稿では、内戦後のシエラレオネでバイクタクシー業を統括する全国規模の職業団体「全国商業モーターバイクライダー協会」(以降、「全国バイク協会」と略称する)を取り上げ、その日常業務について考察する。内戦末期に隆盛したバイクタクシー業では、その管理・運営においてある種のパトロン=クライアント関係が重要な役割を果たした。しかし、民主主義と官僚制に基づく組織運営を求める国際社会の潮流ともあいまって、全国バイク協会が設立される際には、官僚制的な仕組みや役員選挙制度が導入された。ただし、これによって従来のパトロン=クライアント関係が払拭されたというわけではない。ライダーたちは、官僚的で非人格的な業務を行うべきである執行役員に対してクライアントシップをもって接する。それに対して執行役員もパトロンシップをもって応えようとする。全国バイク協会の日常的な活動から見えてくるのは、執行役員がパトロン=クライアント関係のモラリティと官僚制のロジックの両者を翻訳しながらライダーとの関係性を築いていることである。
2 0 0 0 OA エントロピーを利用した推薦システムの提案 ~協調フィルタリングの新たな展開~
- 著者
- 新井 範子
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.4-13, 2006-01-16 (Released:2022-02-15)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 貧困と子どものメンタルヘルス
- 著者
- 稲葉 昭英
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.144-156, 2021-10-31 (Released:2021-11-17)
- 参考文献数
- 24
貧困・低所得の定位家族で育つことが子どもの内面に与える影響を検討するために,等価世帯所得によって定義される「世帯の貧困」と子ども(中学3年生)のメンタルヘルス(心理的ディストレス)との関連を計量的に検討する.内閣府「親と子の生活意識に関する調査」(2011年)を用いて,対象を有配偶世帯に限定して分析を行った結果,(1)男子では貧困層にディストレスが高い傾向は示されなかったが,女子では貧困層で最も高いディストレスが示された.(2)女子に見られるそうした貧困とディストレスの関連は親子関係の悪さや,親や金のことでの悩み,といった家族問題の存在によって大きく媒介されていた.この結果は貧困世帯において女子に差別的な取り扱いがあること,および女子は男子よりも家族の問題を敏感に問題化する,という二つの側面から解釈がなされた.
2 0 0 0 OA 一酸化窒素(NO)の産生・代謝機構からみた鼻副鼻腔炎症
- 著者
- 竹本 浩太 竹野 幸夫 大谷 厚子 高原 大輔 西田 学 石野 岳志
- 出版者
- JAPAN SOCIETY OF IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY IN OTOLARYNGOLOGY
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科免疫アレルギー (ISSN:09130691)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.233-239, 2019 (Released:2019-12-27)
- 参考文献数
- 39
一酸化窒素(NO)は気道防御における恒常性の維持と同時に,炎症性メディエーターとしても機能している。ヒト鼻副鼻腔は生理的に重要なNO産生の場であると同時に,呼気中NO(FeNO)濃度の変化が副鼻腔炎における病態診断や治療効果判定に役立つ可能性を有している。また好酸球性気道炎症のバイオマーカーとしても近年注目を集めている。生体におけるNO産生は3種類のNO合成酵素(NOS)isoform活性やNOS基質であるL-arginineの利用環境に影響を受けている。近年,本邦では好酸球性副鼻腔炎(ECRS)の疫学的増加が報告されている。慢性副鼻腔炎においては含気腔におけるnasal NO濃度は低下するとの報告が大多数を占めている。また好酸球性副鼻腔炎においては非好酸球性と比較して下気道FeNOが高値であり,かつNOS2の発現が亢進している。一連の研究により,鼻副鼻腔におけるNO産生の主体を占めているNOS isoformは誘導型(NOS2)と内皮型(NOS3)であるとされており,両酵素ともジェノタイプとして遺伝子多型と炎症性疾患の病態との関連性が指摘されている。NOS2ではマイクロサテライトのひとつであるCCTTT反復数が多いほうがより高い転写活性を有することが知られている。気管支喘息患者においてCCTTT反復数がFeNOレベルと有意に正の相関を示していたという報告もある。今後鼻腔NOの機能的役割についてもこれら喘息患者と同様の解析が待ち望まれる。またNOS3遺伝子多型と鼻副鼻腔疾患との関連性についても,今後のさらなる展開が望まれる。
2 0 0 0 OA 難治性吃逆患者8例の治療経験
- 著者
- 榎本 澄江 寺田 哲 木村 理恵 林 映至 新井 丈郎 奥田 泰久
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.35-37, 2016 (Released:2017-03-10)
- 参考文献数
- 8
吃逆とは,間代性で不随意な横隔膜の痙攣様収縮で,吃逆が48時間または1~2カ月以上持続もしくは発作が再発するものは難治性吃逆と定義されている.今回,当科に紹介された難治性吃逆患者8例の治療を経験したので報告する.横隔神経ブロックと薬物療法で対応して,8例中,吃逆が消失5例,軽減1例,不変2例であった.横隔神経ブロックとバクロフェンは難治性吃逆の治療に有効であることが示唆された.
2 0 0 0 今日のソ連邦
- 著者
- ソビエト社会主義共和国連邦大使館 [編]
- 出版者
- ソビエト社会主義共和国連邦大使館
- 巻号頁・発行日
- 1958
2 0 0 0 OA 沈み込み帯深部で発生するスロースリップイベントのモデル化
- 著者
- 芝崎 文一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.Supplement, pp.415-423, 2009-07-31 (Released:2013-11-21)
- 参考文献数
- 51
Recent high-resolution observations of crustal movements have revealed the occurrence of slow slip events (SSEs) along the deep parts of subduction interfaces. This report reviews the possible models for SSEs using rate- and state-dependent friction laws. SSEs can be modeled under the condition close to the stability transition. The triggered SSEs can be modeled considering a conditionally unstable cell. The self-triggered SSEs can be reproduced in a region that is unstable but close to being stable. In this case, the ranges of the constitutive law parameters for reproducing SSEs are limited. Further, SSEs can also be modeled by considering the frictional property of an unstable-stable transition zone that exhibits velocity weakening at low slip velocity and velocity strengthening at high slip velocity; this model is proposed on the basis of the results obtained in an experiment using halite around an unstable-stable transition zone. By considering this frictional property, Shibazaki and Shimamoto have reproduced short-term SSEs that are similar to the observed SSEs. This friction law needs to be verified experimentally under conditions that are relevant to the fault zones of SSEs. It is theoretically expected that for slip failure processes the propagation velocity is proportional to the slip velocity. This relationship appears to hold for observed SSEs. Therefore, SSEs can be regarded as slip failure processes occurring at deep subduction plate interfaces.
- 著者
- Ying Zhou Mengwen Yan Jiansong Yuan Yong Wang Shubin Qiao
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- International Heart Journal (ISSN:13492365)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-129, (Released:2022-07-14)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 8
This study aimed to determine the effect of continuous positive airway pressure (CPAP) therapy on patients with atrial fibrillation (AF) and obstructive sleep apnea (OSA) after radiofrequency ablation (RFCA).OSA predicts recurrence of AF in patients with AF and OSA after RFCA. However, the effect of CPAP therapy on recurrence of AF in these patients after RFCA is poorly known.All 122 patients who underwent RFCA from 2017 to 2020 were diagnosed OSA by polysomnography. A total of 62 patients were treated by CPAP, while the remaining 60 were not treated by CPAP. The recurrence of atrial tachyarrhythmia and use of antiarrhythmic drugs were compared between the two groups during a follow-up of 12 months. The outcome of these patients with OSA was compared to a group of 60 AF patients undergoing RFCA without OSA.Patients undergoing CPAP therapy had a higher AF-free survival rate compared to non-CPAP-treated patients (70.3% versus 31.5%; P = 0.02). LAD was associated with the risk of AF recurrence in patients with OSA (HR per mm increase: 1.0; 95% CI: 1.06-1.21; P = 0.01). The CPAP nonusers had more than two-fold increased risk of AF recurrence following pulmonary vein isolation (HR: 2.37; 95% CI: 1.21-4.96; P = 0.02).CPAP treatment highly increased arrhythmia-free survival in AF patients accompanied by OSA after RFCA and reduced recurrence of AF in these patients.
2 0 0 0 OA 故倉沢剛先生を偲んで(VI 倉沢剛前理事のご逝去を悼む)
- 著者
- 中川 隆
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.294, 1986-10-10 (Released:2017-06-01)