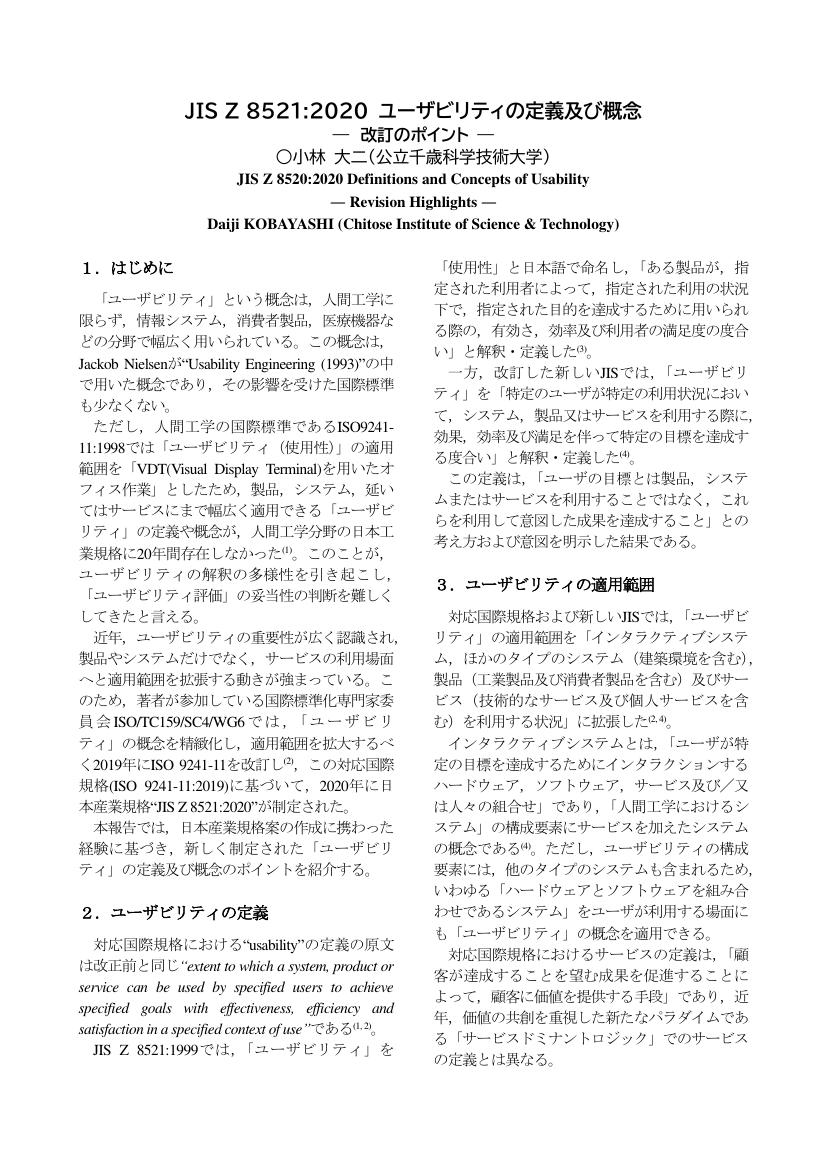- 著者
- Tomoka Hisaki Maki Aiba née Kaneko Morihiko Hirota Masato Matsuoka Hirokazu Kouzuki
- 出版者
- The Japanese Society of Toxicology
- 雑誌
- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.95-108, 2020 (Released:2020-02-15)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 8
We present a systematic, comprehensive and reproducible weight-of-evidence approach for predicting the no-observed-adverse-effect level (NOAEL) for systemic toxicity by using read-across and quantitative structure-activity relationship (QSAR) models to fill gaps in rat repeated-dose and developmental toxicity data. As a case study, we chose valproic acid, a developmental toxicant in humans and animals. High-quality in vivo oral rat repeated-dose and developmental toxicity data were available for five and nine analogues, respectively, and showed qualitative consistency, especially for developmental toxicity. Similarity between the target and analogues is readily defined computationally, and data uncertainties associated with the similarities in structural, physico-chemical and toxicological properties, including toxicophores, were low. Uncertainty associated with metabolic similarity is low-to-moderate, largely because the approach was limited to in silico prediction to enable systematic and objective data collection. Uncertainty associated with completeness of read-across was reduced by including in vitro and in silico metabolic data and expanding the experimental animal database. Taking the “worst-case” approach, the smallest NOAEL values among the analogs (i.e., 200 and 100 mg/kg/day for repeated-dose and developmental toxicity, respectively) were read-across to valproic acid. Our previous QSAR models predict repeated-dose NOAEL of 148 (males) and 228 (females) mg/kg/day, and developmental toxicity NOAEL of 390 mg/kg/day for valproic acid. Based on read-across and QSAR, the conservatively predicted NOAEL is 148 mg/kg/day for repeated-dose toxicity, and 100 mg/kg/day for developmental toxicity. Experimental values are 341 mg/kg/day and 100 mg/kg/day, respectively. The present approach appears promising for quantitative and qualitative in silico systemic toxicity prediction of untested chemicals.
2 0 0 0 OA ユリ「カサブランカ」の強い香りの抑制
- 著者
- 大久保 直美
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.102-106, 2011-03-25 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 6
強い芳香を持つユリは,狭い空間に置くとにおいが充満するため,不快に感じられることがある.強い香りを持つ花の利用を広げるため,ユリ「カサブランカ」を用いて花の香りの抑制方法を検討した.「カサブランカ」の香気成分を分析した結果,不快臭を有する成分は芳香族化合物と考えられたことから,香気成分生成抑制剤としてフェニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAL : phenylalanine ammonia-lyase)阻害剤を選択した. PAL阻害剤処理区において,香気成分量はコントロールの10〜20%程度となった.官能的にも,PAL阻害剤処理を行ったユリの香りは,無処理区に比べ弱まった.以上のことからPAL阻害剤は,「カサブランカ」の香りの抑制に利用できると考えられる.
2 0 0 0 牛白血病ウイルス:新たなる人獣共通感染症?
牛白血病ウイルス(BLV)はヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV)の近縁のウイルスであり、多くのウシが感染していることから、ヒトへの感染の有無が心配される。(1)BLVのプロウイルスDNA(pDNA)の検出末梢血単核細胞(PBMC)からのBLV pDNAの検出を、PCR+Southern blotting(SB)またはreal-time PCRを用いて行った。一部の検体からごく僅かのBLV pDNAが検出されたが、確認実験の成績は不安定であった。閾値ギリギリの微量であることが予想し、検出感度を高めるためにウイルス感染細胞と推測されるB細胞をEBウイルス感染によって不死化させ増殖させた上でDNAを抽出し検索したところ、一名の健常人検体ではSB法でtax・env遺伝子で陽性、pol遺伝子もPCR法で陽性となった。この健常人検体より増幅されたBLV env遺伝子の配列を解析し、既知のBLV遺伝子配列と共に系統樹解析を行ったところ検体中のenv遺伝子は米国や豪州のBLVと近縁で、本邦の牛のBLVと同一グループに属した。しかし、pDNAの全域の増幅と塩基配列の決定を試みたが、増幅困難な箇所が多々みられ未だ確認に至っていない。(2)抗BLV抗体の検出BLV持続感染細胞の細胞抽出液や培養上澄液に存在するBLV蛋白や、GSTとの融合蛋白としてBLVのEnvやTaxなどのウイルス蛋白を実験室内で精製した。これらを抗原として研究対象者の血清中の抗BLV抗体の有無をWB法で調べたところ、健常人で陽性1/11(9%)・保留1/11(9%)、乳癌患者で陽性1/32(3%)・保留3/32(9%)であったが、BLV pDNA検出結果との一致は明らかではなかった。【考察】過去の報告に比し人におけるBLV抗体保有率は低く、また現段階ではこれが真の感染を示唆するものかどうかの確証は得られなかった。一検体において複数のウイルス遺伝子配列が検出されたが、検出範囲は短くpDNAが全域存在する確証は得られていない。以上の結果からBLVの人への感染はあっても比較的稀であることが推察された。
2 0 0 0 OA 札幌からアフリカへ
- 著者
- 日野 舜也
- 出版者
- 日本アフリカ学会
- 雑誌
- アフリカ研究 (ISSN:00654140)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.86, pp.45-47, 2015-01-31 (Released:2015-05-21)
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA JIS Z 8521:2020 ユーザビリティの定義及び概念 ― 改訂のポイント ―
- 著者
- 小林 大二
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.Supplement, pp.S10-1, 2021-05-22 (Released:2021-05-22)
- 著者
- 酒井 大輔
- 出版者
- 明治学院大学法律科学研究所
- 雑誌
- 明治学院大学法律科学研究所年報 (ISSN:21852278)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.139-160, 2018
【共同研究:新しい国家類型論の試み】
2 0 0 0 OA 何故Madhyamikaは「中観」と翻訳されたのか?
- 著者
- 赤羽 律
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.1229-1236, 2012-03-25 (Released:2017-09-01)
中観派という呼称は仏教を少しでも齧ったことのある人ならば誰でも知っているといってよいほど広く知られた名称である.しかし,元々サンスクリット語でMadhyamikaと呼ばれ,直訳としては「中」という意味にしかならない名称が,何故「観」の字を加えられた「中観」という呼称として翻訳されたのかについては定かではない.本稿で明らかにしようと試みたのは,まさにこの点である.中観という呼称を学派名称として初めて用いたのは義浄であるとこれまで考えられてきた.しかしこの呼称そのものは決して義浄が独自に生み出したものではない.義浄以前に,中国における中観派系統の学派である三論宗の実質的な開祖である吉蔵が,Nagarjunaの『中論』を註釈した際に,そのタイトルを『中観論疏』とし,『中論』を『中観論』と呼んだことに由来すると考えられる.この『中観論』という呼称が7世紀半以降,中国を中心に広く知られていたことは明らかであり,インドに渡る以前の義浄が知っていたと十分に考えられる.それ故に,インドにおいてNagarjunaの思想に基づく学派としてMadhyamikaという呼称を耳にした義浄の脳裏に,Nagarjunaの最も重要な論書である『中論』即ち『中観論』という名称が浮かび,それを学派名称に転用したとしても何ら不思議はないであろう.また「観」の字を加えた理由は定かではないが,吉蔵の『中観論』という名称に関する注釈に従うならば,『中論』の各章に「観」の字が付けられていることに基づいたためではないかと推察される.何れにせよ,義浄以前の7世紀に活躍し,インドの仏教事情に詳しい玄奘や,630年代初頭に『般若灯論』の翻訳を行ったインド人Prabhakaramitraといった著名な仏教僧たちが何れも,中観派という呼称を用いていないことから,恐らくこの用語を学派名称として初めて用いた人物が義浄であると想定するのが現段階では妥当であろう.
2 0 0 0 OA 長野県の郷土料理における地域的特性の比較
- 著者
- 春日 千鶴葉 柏木 良明
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2016年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100058, 2016 (Released:2016-11-09)
郷土料理は以下のように定義されている(木村,1974)。(1)ある地域に古くから行われている食形態で他地方にはみられない特色をもち、その発生が明治以前であるものである。ただし、北海道に限り明治末期までに備わった食形態を取り上げる。(2) 現在は比較的広範囲の各地の人々に食されているが、江戸時代までは限られた範囲の地域の民衆生活のみ定着していた食形態であるものである。 また、郷土料理は地方の特産品をその地方に適した方法で調理したものである(岡本,1987)。その中で、食の暮らしの知恵が育まれ、おいしく健康に良い食べ方などが工夫されている(成瀬,2009)。種類や調理方法における地域性は、地形、気候、地域ごとの生産物といった自然的要因だけでなく、地域の人々の気質、宗教、産業技術の発達状況、時代・地域社会の思潮などの人為的要因によっても形成される(石川,2000)。そして、郷土料理のタイプは(1)その土地で大量に生産される食べ物をおいしく食べようと工夫したことにより生まれたもの(2)地方の特産物を利用してできたもの(3)その地方で生産されない材料を他地域からもってきて、独自の料理技術を開発して名物料理に仕上げたものに分類される(安藤,1986)。さらに、郷土料理は伝統行事に欠かせないものにもなっている。しかし、生活様式の変容などにより、その地域性が失われつつある(成瀬,2009)。 長野県の郷土料理の一つであるおやきはもともと長野県北部の農村の発祥である。かつて、囲炉裏の灰で焼いたことから「お焼き」と名付けられた。作り方は味噌で味付けしたナスなどの野菜を餡として小麦粉の皮で包み、蒸すあるいは焼く。その後、1982年におやきが手打ちソバ、御幣餅、スンキ漬、野沢菜漬とともに「食の文化財」に指定された。現在では、長野市、小川村をはじめおやきの専門工房や販売店が県内全域の広範囲に多数存在している。その上、おやきは地域差が県全域を通じて見られ、地域性がよく見られるのも特徴である。 おやきに関する研究では、ある特定の地域における特性は明確になっているが県内全域でのおやきの実態、特性を示す研究は少ない(水谷ら,2005)。故に、長野県内の中でどのような差異や共通点があるのかも不十分であり、おやきに関する明確なデータも少ない。 そこで、本研究では長野県全域を調査地域として、各地域におけるおやきの特性について比較調査するとともに、なぜ地域差が見られるのかを明らかにする。また、考察の際に五平餅との比較も取り上げる。 結果として長野県内は北信、中信、東信、南信の4つの行政区分である。調査方法は主に文献調査、聞き取り調査(25店舗)、おやきの購入・試食、写真撮影による。 北信地方で119店舗、東信地方で27店舗、中信地方で49店舗、南信地方で20店舗、計215店舗あることがわかった。特に、北信地方だけでも全体の約5割をも占めている。東信・南信では店舗自体は非常に少ない。 おやきの製法には、蒸かし、焼き蒸かし、焼き、揚げ焼きなどの種類がある。北信では小麦粉の味を生かしたおやきで蒸かしたものが多い。しかし、長野市から離れた山村地域に行くと、ほうろくの上にのせて焼く製法が見られる。東信地方では、蒸かす製法が多い傾向にあり、主に上田市に多く店舗が集中している。中信は南北に差異があり、北側は昔ながらの焼き製法、南側は蒸かし製法で作られている。南信では生地に砂糖を入れ甘く仕上げて、ふくらし粉を使用し蒸かす。 全域を通してノザワナ、ナス、小豆あんである。また、山菜やクリなど地域でとれた素材を生かして作っている場合が多い。 考察に関して、穀物において、米は盆地の河川流域に集中している一方で長野盆地には水田地帯が少なく畑作を行う傾向にある。小麦は、松本、安曇野で最も多く、全体的に収穫量は北側に集中していることから北側を中心に小麦の文化が定着しているといえる。また、県内では穀物を粉状にして食べる工夫が自然にできる環境にあった。 北部ではおやきをお盆に食べ、南部では11月20日のえびす講で、あんこを多く入れたおやきを作って供える。このようにおやきを食べる習慣が各地域により異なる。 五平餅とは南信地域で食べられる郷土料理のことである。名前の由来は、五平が始めた、神前に供える御幣の形に似ていることなどがあげられる。作り方はうるち米のみを使用して焼く。 五平餅は、「塩の道」である伊那街道沿いの地域に分布しており、終点は塩尻で南北の分岐点となっている。それを境に、南信地方では五平餅文化が存在している。そのため、南信地域にはおやき店舗よりも五平餅店舗の方が多い。その一方で北信地方では五平餅店舗は見られない。
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1951年07月21日, 1951-07-21
2 0 0 0 OA 将棋における実現可能局面数について
- 著者
- 篠田 正人
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2008論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.11, pp.116-119, 2008-10-31
将棋のゲームとしての複雑さを測る指標として,「指し始めの局面から実現可能である局面数」を提案する.本校ではこの局面数が10^60以上10^70未満であることを証明しその数え上げの方法の概略を述べることで,局面数がおおよそ10^68〜10^69程度と推測できることを説明する.
2 0 0 0 光線過敏症の基礎的ならびに臨床的研究
- 著者
- 荒木 寿枝
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, 1967
光線過敏症の研究は,1900年Raabの,acridin溶液中でぞうり虫が数分間の日光照射により死亡するという研究,および1931年Hausmannの,hematoporphyrinで前処置された白鼡が,暗所では何らの異常反応も示さないのに,日光照射を受けると数分ないし数日以内に死亡し,その時間は色素量および光量に比例するという報告,すなわちphotodynamic action(光力学的作用)に関する研究にはじまつた.その後1939年Stephan Epsteinがsulfonamideによる光線過敏症の研究において,その作用機序としてphotoallergic(光アレルギー性)とphototoxic(光毒性)の2つのmechanismの存在の可能性を示唆した.さらに,BurckhardtおよびBlumらのsulfonamideについての実験により光アレルギー現象の基礎が確立された.すなわち生理的食塩水で1%に稀釈したsulfonamide溶液を人体皮内に注射し,その部にquartz lampを用いて最小紅斑量(MED)以下の長波長紫外線を照射すると,全例において照射後直ちに紅斑が発生,色素沈着を残して数日以
- 著者
- 一二三 朋子
- 出版者
- 筑波大学大学院地域研究研究科
- 雑誌
- 筑波大学地域研究 (ISSN:09121412)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.101-111, 2008
- 著者
- 横山 尊
- 出版者
- 日本科学史学会 ; 2014-
- 雑誌
- 科学史研究. [第Ⅲ期] = Journal of history of science, Japan. [Series Ⅲ] (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- no.297, pp.66-77, 2021-04
- 著者
- 松尾 理沙 野村 和代 井上 雅彦
- 出版者
- 日本小児精神神経学会
- 雑誌
- 小児の精神と神経 (ISSN:05599040)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.53-59, 2012-03-30
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 自民党政権の意思決定システムの形成過程に関する共同研究
本研究は自民党政権の意思決定システムの形成過程に関する共同研究である。研究成果の特に重要なものとしては、事前審査制の歴史的考察がある。従来、自民党政権の事前審査制は1962年の赤城書簡を嚆矢とし、それ以後次第に慣習化されたと考えられてきた。しかしながら、我々の共同研究の結果、以下の点が明らかになった。第一にその淵源は桂園時代に遡ることができ、戦時体制下ですら与党審査が重要な意味を持っていたこと、第二に、事前審査制は自民党結党直後から今日に近い形で始まり、赤城書簡によって事前審査制が完成したことである。
2 0 0 0 OA デンマーク最近の教育事情
- 著者
- 寺田 治史
- 出版者
- 学校法人 天満学園 太成学院大学
- 雑誌
- 太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.273-283, 2011 (Released:2017-05-10)
幸福度世界一のデンマ-クと同90位の日本(2006年.英レスタ-大学ホワイト教授調べ)。この違いはどこから来るのか。5度に亘るデンマ-ク訪問の結果、その底流に両国における教育の歴史に違いを見出す事が出来る。知と情と意を統合した"対話中心の教育"(筆者はこれを人間教育と称する)を貫くデンマ-クに対して日本の教育は、知育に偏しているように思われる。デンマ-クにおける調査、聞き取り、視察を通して考察した内容を提示し、わが国における今後の議論の糧となれば幸いである。
2 0 0 0 OA 組織内デジタル文化資本がICT投資効果に与える影響
- 著者
- 清水 たくみ 平野 雅章
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2020年全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.269-272, 2021-01-28 (Released:2021-01-18)
ICT投資は経済・企業成長の主要な要因としての役割を果たし続けている。マクロレベルでのICT投資の正の影響については合意が形成されつつある一方、ミクロレベルでどのような組織がICT投資を成果に結びつけているかについては統一的な見解が得られていない。そこで本研究では「デジタル文化資本」概念に着目し、ICT投資成否を左右する組織要因について明らかにする。日本企業に対する大規模サーベイ調査のパネルデータ分析を行った結果、ICT投資は組織内デジタル文化資本の高低に応じて企業業績に与える影響が変化することが示された。本研究により、ICT投資と企業業績の関係性に関する新たな理論的・実証的貢献がもたらされた。
2 0 0 0 OA モチビック・コホモロジー,その応用と重要な予想
- 著者
- ガイサ トーマス
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.225-245, 2015-07-24 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 88
2 0 0 0 未利用樹種ネズの高付加価値化を含めた里山林バイオマス利用の再構築
- 著者
- 山場 淳史 児玉 憲昭
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース
- 巻号頁・発行日
- vol.129, 2018
<p>広島県南部では元来,アカマツが優占する里山二次林が主要な植生景観であったが,現在ではそのほとんどが松枯れ被害を受け利用されないまま放置されている。部分的に市民・住民による維持管理作業が行われている箇所もあるものの,林業施策的にはほぼ取り残されている状態である。本報は,こうした地域における里山林利用を再構築する事例として,東広島市(旧黒瀬町・安芸津町を除く)と三原市大和町を所管する賀茂地方森林組合が主体となった取り組みを解説する。木の駅方式を一部取り入れ収集した木質バイオマスをチップ・ペレット化する拠点を整備するとともに,地域に立地する企業・団体の取り組み(小規模バイオマス発電や農畜産業など)と連携し地域内で循環することを目指している。併せて,その仕組みを補強し収益性をより高めるモデルとして,松枯れ跡林分に特徴的な未利用樹種ネズ(別名ネズミサシ:<i>Juniperus rigida</i>)の球果(香料)および幹材(木工用材)の新たな需要開拓を行い商品開発に繋げた過程を紹介する。そのうえで他地域との連携も含めた里山林利用の再構築のための将来的なフレームワークを提示する。</p>
- 著者
- 北川 裕子 佐々木 司
- 出版者
- 一般社団法人 日本学校保健学会
- 雑誌
- 学校保健研究 (ISSN:03869598)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.83-90, 2021-07-20 (Released:2021-08-11)
- 参考文献数
- 21