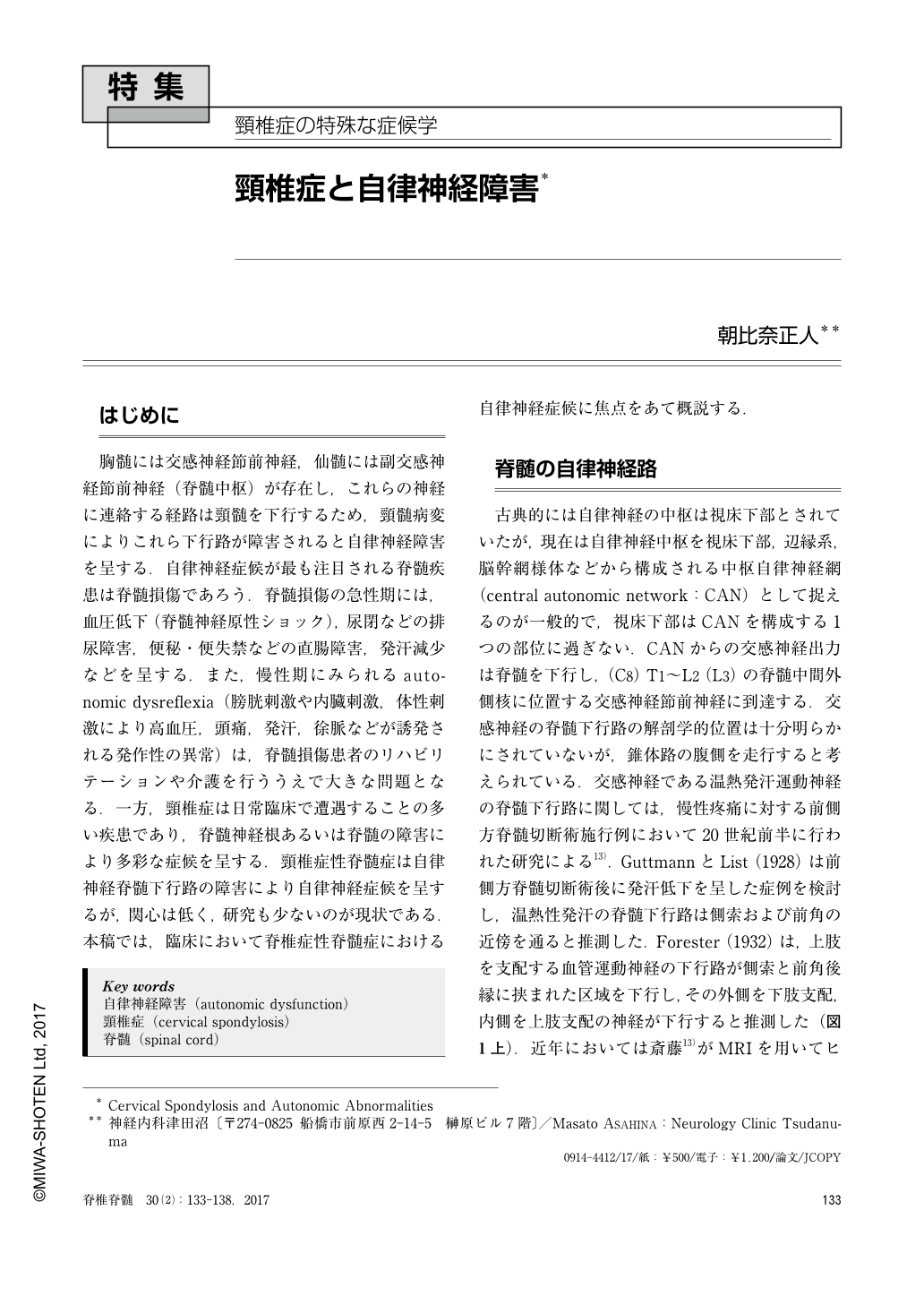2 0 0 0 OA 老子 : 中国思想の智慧への門
- 著者
- 王岳川
- 出版者
- 金沢大学
- 雑誌
- 金沢大学中国語学中国文学教室紀要
- 巻号頁・発行日
- no.3, 1999-03
- 著者
- 今村 知子 川原田 史治 杉森 文夫
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.1-16, 2015-09-30 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 53
齢既知のハシボソミズナギドリPuffinus tenuirostris 14個体の下顎骨を用い,雛から成鳥まで,成長とともに変化する骨の組織形態を調べ,年齢との関係について考察を行った。「脱灰標本法」により組織標本を作製し,デラフィールドのヘマトキシリンで染色したのち,鏡検した。その結果,成長に伴う組織形態の形成過程が明らかになり,1ヶ月齢から6ヶ月齢までの雛と幼鳥の月齢の識別ならびに亜成鳥と成鳥の判別が可能であることが見出された。齢とともに発達する年輪的な層状構造は1歳以上の3個体すべてにおいて観察されたが,年齢とは一致しなかった。ハシボソミズナギドリの下顎骨における層状構造の形成は,初め外基礎層板において広い範囲に見られるが,年齢を経るとともに,形成と同時に骨内部からハバース系の発達による侵食を受け,実際の年齢よりも本数が少なくなると考えられた。
2 0 0 0 OA 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘の成り立ち
- 著者
- 新川 登亀男
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.194, pp.277-327, 2015-03-31
本稿は,法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘が日本列島史上における初期の仏教受容のあり方を物語る長文の稀有な情報源であるとの問題意識に立つ。そして,この光背銘をいかに読み,解釈するかということに終始するのではなく,この光背銘がどのように成り立ったのか,そこにいかなる歴史文化が投映されているのかを重要視する。そのためには,銘文中の不可解な用語を単語として切り出し論じることの閉塞性を反省し,人々の行為や心情ないし思考を言い表わしていると思われる表現用法や文に注目する。そこで注目したのが,「深懷愁毒」と「當造釋像尺寸王身」の2か所である。この2か所の表現とその文脈に沿う先例は,けっして多くはない。しかし,そのなかにあって極めて注目すべき先例が,『賢愚經』巻1第1品と『大方便佛報恩經』巻1・2・3に見出せる。それは,釈尊本生の捨身(施身)供養譚や,その他の死病譚,そして優塡王像譚(仏像起源譚)などの譬喩物語に含まれている。この二経は,ともに中国南北朝期に定着し,易しい仏教入門書として流布した。光背銘文の作者は,この二経の譬喩譚を承知しており,そこで語られている王や釈尊の激烈な死(擬死)や不在(喪失)の様と,それに遭遇した人々のこれまた壮絶な哀しみや恐れの様を,現実の「上宮法皇」らの病や死とそれへの反応とに当てはめて事態を認識し,受け止めようとしたものと考えられる。加えて,そこには,自傷行為や馬祭祀などをともなう汎アジア的な葬儀習俗も作用していた。そして,このような作文を可能にするのは「司馬鞍首止利佛師」であるとみる。なぜなら,「尺寸」単位や仏像起源譚に関心をもつ「秀工」,また「司馬」でもある「止利」だからである。
2 0 0 0 OA リップ付きハードルアーのボディ形状と潜行運動
- 著者
- 三木 智宏 臺田 望 稲田 博史 酒井 拓宏 兼廣 春之
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.49-57, 2001-01-15 (Released:2008-02-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2 3
リップ付きハードルアーのボディ形状と潜行運動との関係を解明するために, 楕円形に設定したボディ側面の高さを変化させ, 他の形状要素を一定とした供試ルアーを製作して, 回流水槽とフィールドで実験を行った。その結果, ボディ側面の長短軸比κ=Lh/Lb(ボディの全長 : Lb=65mm, 高さ : Lh)をルアーボディの体高のパラメータとすると, κの増大に伴ってルアーの左右への振れ角が大きくなり潜行深度は浅くなるなどの一定の傾向が認められ, ボディの側面形状によってルアーの潜行中の振動, 深度を制御できることが示唆された。
2 0 0 0 OA 聖なる樹々(上) : ラフカディオ・ハーン「青柳物語」と「十六桜」について
2 0 0 0 二酸化塩素によるマラリア感染防止効果と蚊に対する忌避作用
- 著者
- 松岡 裕之 緒方 規男
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.203-207, 2013
マウスを麻酔して2群に分け,一群には二酸化塩素のスプレーを他の一群には水のスプレーを噴霧したのち,マラリア感染蚊自由に吸血させた.二酸化塩素をスプレーしたマウスに対しては101匹の蚊のうち6匹が吸血した (5.9%) だけで、マウスの感染は13頭中1頭のみ (7.7%) であった.水をスプレーしたマウスに対しては蚊88匹のうち42匹が吸血し (47.7%), マラリア感染は11頭中6頭 (54.5%) であった.二酸化塩素スプレー群は有意差をもって吸血率 (<i>p</i><0.01)・マラリア感染率 (<i>p</i><0.05) の低下が見られた.次に両端をメッシュで覆ったチューブの中に蚊を入れ,チューブの片方は空気のみを含むケージに,反対側は二酸化塩素を含むケージに差し込んで,蚊がどちらの側に偏在するか調べた.<i>Anopheles stephensi</i>, <i>Aedes albopictus</i>および<i>Culex pipiens pallens</i>の3種蚊とも0.03 ppm以上の二酸化塩素濃度において反対側(空気側)に偏在した.二酸化塩素は蚊に対する忌避作用があるといえた.
2 0 0 0 OA 個人の活動空間の増加がサイコロジカル・キャピタルに与える影響
- 著者
- 辺見 佳奈子
- 出版者
- 大阪商業大学商経学会
- 雑誌
- 大阪商業大学論集 = THE REVIEW OF OSAKA UNIVERSITY OF COMMERCE (ISSN:02870959)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.59-71, 2021-01-30
2 0 0 0 OA Accelerated blood clearance(ABC)現象における動物種差
- 著者
- 清水 太郎 異島 優 石田 竜弘
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.396-401, 2017-11-25 (Released:2018-02-25)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
ポリエチレングリコール(PEG)修飾リポソームなどのPEG修飾体に対するaccelerated blood clearance (ABC)現象は、これまでbio-inertと考えられてきたPEGに対する免疫反応であり、PEGに対する抗体の誘導と、この誘導された抗体がその後に投与されるPEG修飾体に結合することに端を発する血中からの速やかな排除と定義することができる。PEG修飾は、いまだ医薬品開発におけるゴールデンスタンダードであり、既存医薬品のライフサイクルマネージメントのみならず、PEG修飾によって化合物の性質を変え新薬として開発しようとする動きも出てきている。ABC現象はPEGに対する免疫反応であることから、投与する動物種によって誘導されるABC現象の程度は異なる。また、ABC現象は補体系の活性化を伴うため、アナフィラキシー様の有害事象を惹起する可能性も高いが、表現型として現れる有害事象は動物種によって大きく異なる。さらに、ヒトでの第1相試験ではdose escalation試験が行われるが、ABC現象は低投与量の場合に生じやすく、試験の進捗に悪影響を与える可能性が高い。ABC現象における動物種差の影響はこれまでほとんど報告されておらず情報が少ないのが現状である。
2 0 0 0 OA 健常者甲状腺機能への大豆の効果
- 著者
- 石突 吉持 広岡 良文 村田 善晴 富樫 和美
- 出版者
- 一般社団法人 日本内分泌学会
- 雑誌
- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.622-629, 1991-05-20 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 2
To elucidate whether soybeans would suppress the thyroid function in healthy adults, we selected 37 subjects who had never had goiters or serum antithyroid antibodies. They were given 30g of soybeans everyday and were divided into 3 groups subject to age and duration of soybean administration.In group 1, 20 subjects were given soybeans for 1 month. Groups 2 and 3 were composed of 7 younger subjects (mean 29 y. o.) and 10 elder subjects (mean 61 y. o.) respectively, and the subjects belonging to these groups received soybeans for 3 months. The Wilcoxon-test and t-test were used in the statistical analyses. In all groups, the various parameters of serum thyroid hormones remained unchanged by taking soybeans, however TSH levels rose significantly although they stayed within normal ranges. The TSH response after TRH stimulation in group 3 revealed a more significant increase than that ingroup 2, although inorganic iodide levels were lowered during the administration of the soybeans. We have not obtained any significant correlation between serum inorganic iodide and TSH.Hypometabolic symptoms (malaise, constipation, sleepiness) and goiters appeared in half the subjects in groups 2 and 3 after taking soybeans for 3 months, but they disappeared 1 month after the cessation of soybean ingestion.These findings suggested that excessive soybean ingestion for a certain duration might suppress thyroid function and cause goiters in healthy people, especially elderly subjects.
2 0 0 0 OA 伊豆・小笠原島弧の速度構造
- 著者
- 高橋 成実 小平 秀一 佐藤 壮 山下 幹也 海宝 由佳 三浦 誠一 野 徹雄 瀧澤 薫 野口 直人 下村 典夫 金田 義行
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.5, pp.813-827, 2015-10-25 (Released:2015-11-04)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 6 8
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology carried out seismic surveys using ocean bottom seismographs (OBSs) and a multi-channel reflection survey system from 2004 to understand the structural characteristics and the continuity of the Izu–Ogasawara Arc crust. The Izu–Ogasawara Arc developed from the oceanic crust and produced andesitic middle crusts. The velocity is similar to that identified in the continental crust, and the initial continental crust might have been produced during development of the arc crust. To investigate the process of the Izu–Ogasawara Arc crust, many 2-D velocity structures are compared using unified specifications of data acquisition and analysis, and structural commonalities and differences are evaluated. The specification was confirmed previously through simulation studies using the structure obtained. These arc crustal structures have common characteristics, which are an upper crust with a Vp of 4.5–6.0 km/s, a middle crust with a Vp of 6.0–6.5 km/s, and a lower crust with a Vp of 6.5–7.5 km/s. The lower crust is composed of two layers; the upper part has a Vp of 6.5–6.8 km/s and the lower part has a Vp of 6.8–7.5 km/s. The uppermost mantle has a Vp of less than 8.0 km/s. Development of the arc crust results in crustal thickening accompanied by rifting. Back arc opening after rifting plays the role of crustal thinning. The Shikoku Basin, which is the older backarc basin, has a relatively thin crust with a thickness of approximately 10 km, and the eastern part has a high velocity lower crust with a Vp of over 7 km/s. In addition, the upper crust of the eastern part of the Shikoku Basin has some intrusive materials and strike slip faults with few vertical displacements. Such a high-velocity lower crust is not distributed in the Parece Vela basin. The Ogasawara Ridge has different characteristics from the above arc crust, which are a crustal thickness of approximately 20 km but a complicated structure including a narrow and thin crust in the N–S direction. Here, we introduce the structural characteristics of the entire Izu–Ogasawara Arc crusts based on unified seismic surveys and data analysis methods.
2 0 0 0 頸椎症と自律神経障害
- 著者
- 朝比奈 正人
- 出版者
- 三輪書店
- 雑誌
- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.133-138, 2017-02-25
はじめに 胸髄には交感神経節前神経,仙髄には副交感神経節前神経(脊髄中枢)が存在し,これらの神経に連絡する経路は頸髄を下行するため,頸髄病変によりこれら下行路が障害されると自律神経障害を呈する.自律神経症候が最も注目される脊髄疾患は脊髄損傷であろう.脊髄損傷の急性期には,血圧低下(脊髄神経原性ショック),尿閉などの排尿障害,便秘・便失禁などの直腸障害,発汗減少などを呈する.また,慢性期にみられるautonomic dysreflexia(膀胱刺激や内臓刺激,体性刺激により高血圧,頭痛,発汗,徐脈などが誘発される発作性の異常)は,脊髄損傷患者のリハビリテーションや介護を行ううえで大きな問題となる.一方,頸椎症は日常臨床で遭遇することの多い疾患であり,脊髄神経根あるいは脊髄の障害により多彩な症候を呈する.頸椎症性脊髄症は自律神経脊髄下行路の障害により自律神経症候を呈するが,関心は低く,研究も少ないのが現状である.本稿では,臨床において脊椎症性脊髄症における自律神経症候に焦点をあて概説する.
- 著者
- 西山 茂
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.25-29, 1997
<p></p>
2 0 0 0 OA 臨床失行症学
- 著者
- 中川 賀嗣
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.10-18, 2010-03-31 (Released:2011-05-11)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3 1
失行の (広義の) 定義では,非失行性要因による行為・動作障害を除外する必要性が示されている。そのため,まずどのような非失行性要因が,どのような形で行為・動作に影響するかを紹介した。さらに道具使用動作も含めて,対象操作に関連する行為・動作を 2 つの系に大別した。第 1 の系は,到達・把持動作を含み,どんな道具かによらず,非特異的に対象物を扱う動作の系である。また到達・把持後においても,「各道具に特異的な使用動作」以外の,非特異的な扱い動作もこの系に含めた。この系は使用手の対側半球が担っていると考えられる。第 2 の系は,道具を把持した後の,「各道具に特異的な使用動作」からなる系である。たとえばハサミの場合には,ハサミで「紙を切る動作」がこれにあたる。この系は左優位半球が両手に対して担うと考えられる。本稿では第 1 の系が選択的に障害され,第 2 の系は保たれていると見なし得た 1 例を示し,これを新たな失行型と位置づけ,暫定的に「到達・把持失行」と呼んだ。一方第 2 の系が選択的に障害され,第 1 の系が保たれた病態は,使用失行がこれにあたると見なしうる。
2 0 0 0 IR 司法修習における刑事政策(犯罪学)教育の可能性 (柴田平三郎先生退職記念号)
- 著者
- 齋藤 実
- 出版者
- 獨協大学法学会
- 雑誌
- 独協法学 = Dokkyo law review (ISSN:03899942)
- 巻号頁・発行日
- no.102, pp.57-73, 2017-04
- 著者
- 橋本 剛
- 雑誌
- 2021年第82回応用物理学会秋季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2021-07-06
2 0 0 0 OA <論説> 漢長安城未央宮の禁中 : その領域的考察
- 著者
- 青木 俊介
- 雑誌
- 学習院史学 (ISSN:02861658)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.35-62, 2007-03-20
2 0 0 0 IR 『水滸伝』に見える「義」の解釈
- 著者
- 荒木 達雄
- 出版者
- 東京大学文学部中国語中国文学研究室
- 雑誌
- 東京大学中国語中国文学研究室紀要 (ISSN:13440187)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.22-48, 2010-11
2 0 0 0 OA グイド・グイニツェッリ論
- 著者
- 山口 秀樹
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.65-79, 1971-01-20
Riguardo al carattere della poesia di Guinizelli, si dice general, mente che egli fosse un poeta fantastico e visivo. Ci sono ragioni sufficienti perche egli sia cosi definito. Ma dal punto poetico di vista questa definizione del suo genio poetico a troppo fragmentale per significar qualcosa essenziale di lui. Perche nella corrente del Dolce Stil Nuovo egli e chiamato "padre" dall' autore della Divina Commedia che non e certamente un peta fantastico. Allora in questo saggio l'A- cerca d' indagare che cosa e veramente il suo genio poetico. Ricevendo l'immagine tradizionale, cioe quella provenzale e siciliana, Guinizelli l'ha fatta levar rancora nello spazio piu poetico e pin misurato nella canzone "Donna, l'amor mi sforza". E in questo processo della rinnovazione poetica traspare la luce dello suo spirito come poeta, cioe l'attitudine analitica. L'A. pensa che questa tendenza stessa e il suo genio poetico e che questa fiorisce pienamente nella famosa canzone "Al core qentile... ". (ma soltanto nel senso ideale, e questa canzone non ha lo stesso valore Poetico come "Donna, l'amor mi sforza"). E sebbne nella stessa canzone ci sia il grido della sua anima cruda(almeno mi pare cosi)questo grido non si puo definire come "sentimentale e fantastico". Perche l'A. pensa che questo grido non e ormai emesso dalla sua anima cruda, ma dalla convinzione d'aver potuto sistemare l'amor terreno nel piu alto livello, cioe nello schema metafisico-cristiano. Dante non puo non accorgersi del genio di Guinizelli. Percio se Dante lo chiama il padre delle rime dolci e leggiadre, non si puo pensare che Guinizelli fosse chiamato in questo modo solamente nel senso sentimentale. Per Dante e anche per noi l'A. pensa che ci siano ragioni sufficienti perche Guinirelli sia definito come "il padre del Dolce Stil Nuovo", nel senso che nel poema di Guinizelli c'e sempre una nuova tendenza a cantare il suo amore mossa dallo spirito analitico
2 0 0 0 IR ヴィエラ・ヒチロヴァーの映画『ひなぎく』(1966)について
- 著者
- 赤塚 若樹
- 出版者
- 首都大学東京人文科学研究科
- 雑誌
- 人文学報 = The Journal of social sciences and humanities (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.476, pp.1-35, 2013-03