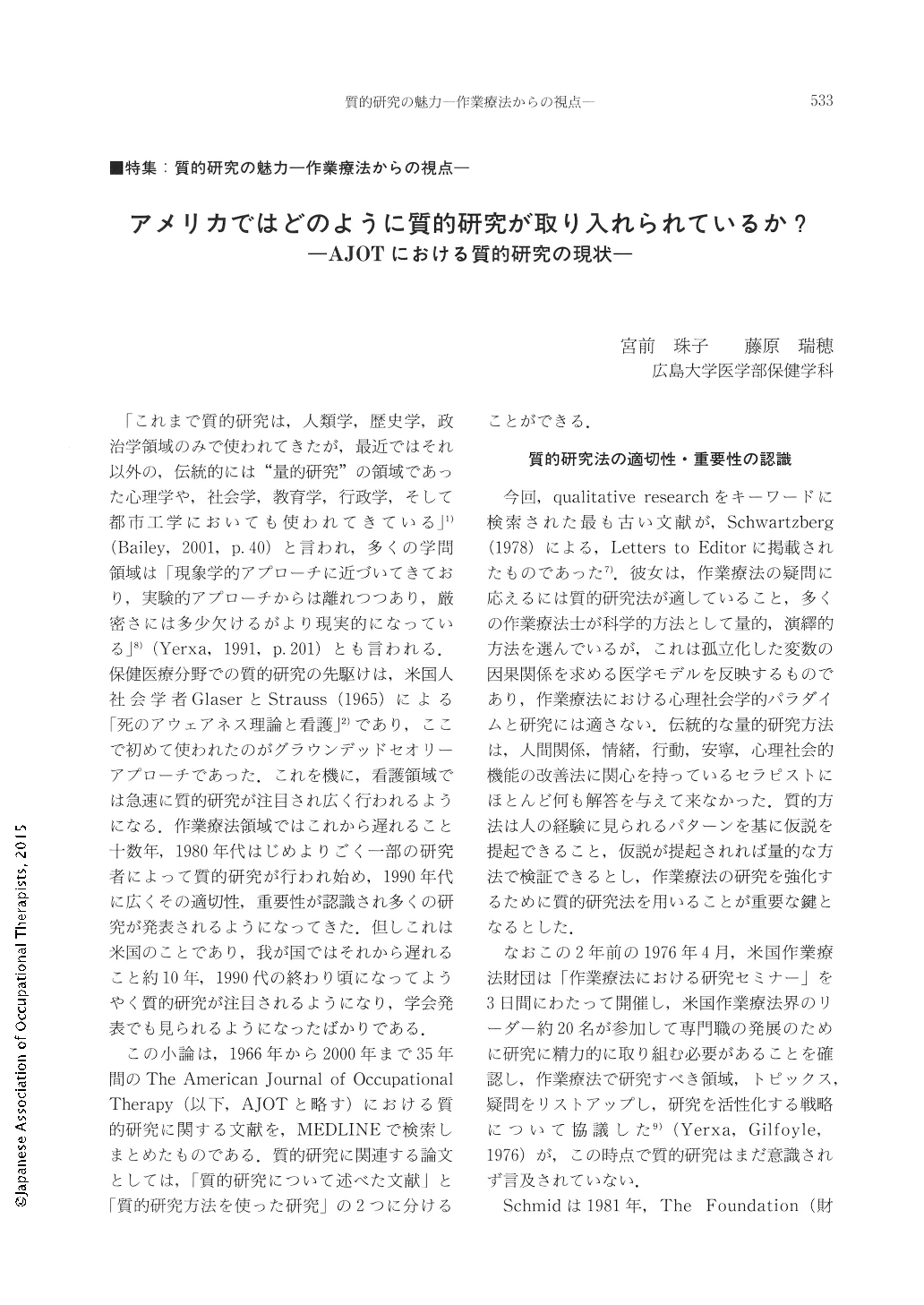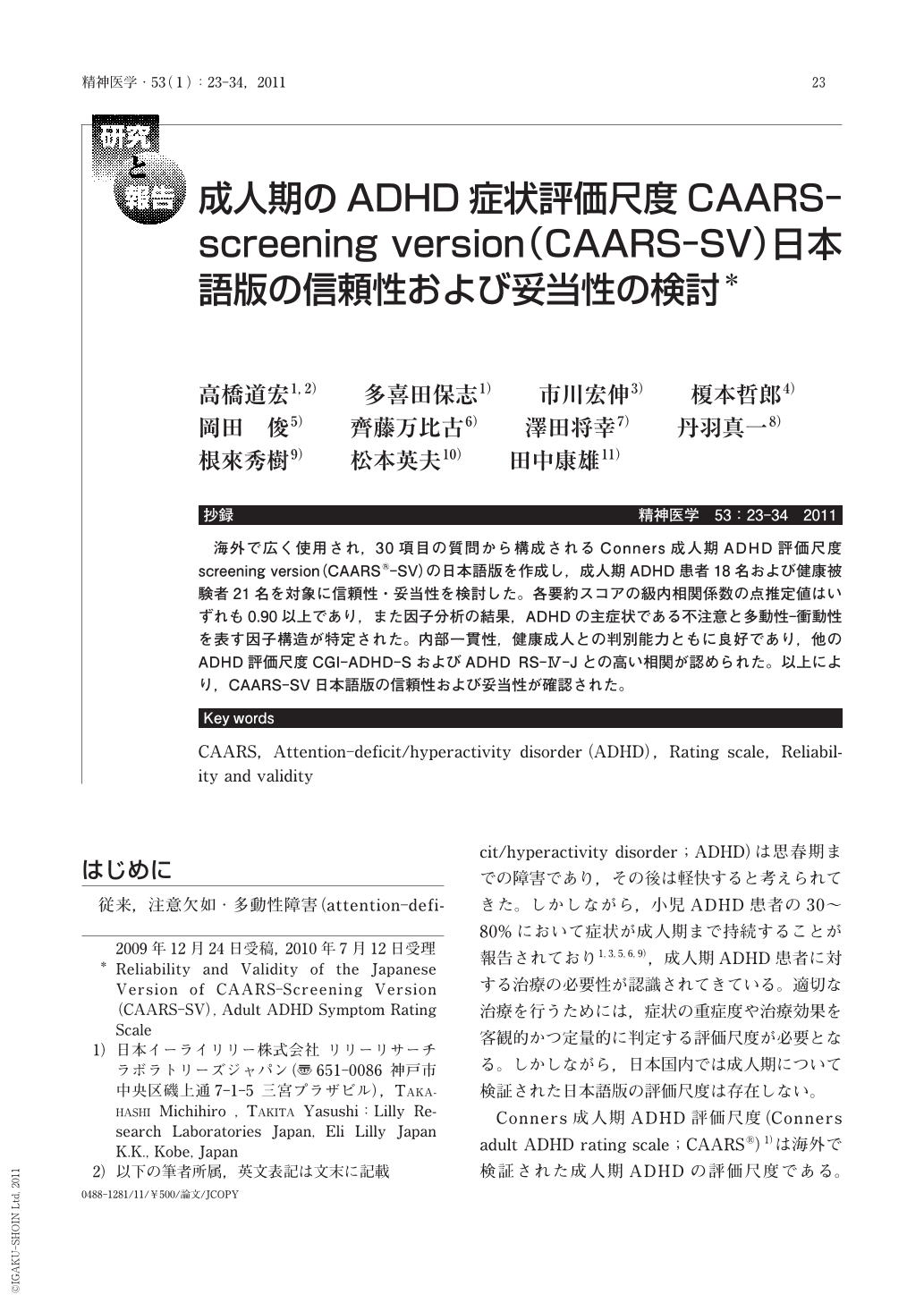- 出版者
- 全国商工会連合会
- 雑誌
- Shokokai = 商工会 : 地域を結ぶ総合情報誌
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.34-36, 2016-05
2 0 0 0 IR 植民地期シエラレオネにおける狂気の歴史
- 著者
- 落合 雄彦 金田 知子
- 出版者
- 龍谷大学
- 雑誌
- 龍谷法学 (ISSN:02864258)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.531-550, 2008-12-26
2 0 0 0 OA 安酸敏眞著『人文学概論―新しい人文学の地平を求めて』
- 著者
- 森本 あんり
- 出版者
- The Japan Society of Christian Studies
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.200-206, 2016 (Released:2018-02-22)
2 0 0 0 OA 「国主即是当今如来」論について
- 著者
- 張 雪松
- 出版者
- 東洋大学東洋学研究所
- 雑誌
- 東アジア仏教学術論集 (ISSN:21876983)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.95-113, 2014-02
第2回 中・日・韓 国際仏教学術大会論文集―南北朝時代の仏教思想― 中国人民大学仏教与宗教学理論研究所・日本東洋大学東洋学研究所・韓国金剛大学校仏教文化研究所共編
2 0 0 0 IR 日野台地の地形と自由地下水
- 著者
- 角田 清美 Sumida Kiyomi
- 出版者
- 駒澤大学文学部地理学教室・駒澤大学総合教育研究部自然科学部門
- 雑誌
- 駒澤地理 (ISSN:0454241X)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.47-62, 2012-03
2 0 0 0 OA ヴィオレ・ル・デュクの修復理論について
- 著者
- 羽生 修二
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文報告集 (ISSN:09108017)
- 巻号頁・発行日
- vol.366, pp.124-131, 1986-08-30 (Released:2017-12-25)
- 著者
- 宮前 珠子 藤原 瑞穂
- 出版者
- 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.6, pp.533-539, 2001-12-15
「これまで質的研究は,人類学,歴史学,政治学領域のみで使われてきたが,最近ではそれ以外の,伝統的には“量的研究”の領域であった心理学や,社会学,教育学,行政学,そして都市工学においても使われてきている」1)(Bailey,2001,p.40)と言われ,多くの学問領域は「現象学的アプローチに近づいてきており,実験的アプローチからは離れつつあり,厳密さには多少欠けるがより現実的になっている」8)(Yerxa,1991,p.201)とも言われる.保健医療分野での質的研究の先駆けは,米国人社会学者GlaserとStrauss(1965)による「死のアウェアネス理論と看護」2)であり,ここで初めて使われたのがグラウンデッドセオリーアプローチであった.これを機に,看護領域では急速に質的研究が注目され広く行われるようになる.作業療法領域ではこれから遅れること十数年,1980年代はじめよりごく一部の研究者によって質的研究が行われ始め,1990年代に広くその適切性,重要性が認識され多くの研究が発表されるようになってきた.但しこれは米国のことであり,我が国ではそれから遅れること約10年,1990代の終わり頃になってようやく質的研究が注目されるようになり,学会発表でも見られるようになったばかりである. この小論は,1966年から2000年まで35年間のThe American Journal of Occupational Therapy(以下,AJOTと略す)における質的研究に関する文献を,MEDLINEで検索しまとめたものである.質的研究に関連する論文としては,「質的研究について述べた文献」と「質的研究方法を使った研究」の2つに分けることができる.
2 0 0 0 OA 数理ファイナンスと金融工学:小史
- 著者
- 三浦 良造
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.288-314, 2006-07-26 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 32
- 著者
- 高橋 道宏 多喜田 保志 市川 宏伸 榎本 哲郎 岡田 俊 齊藤 万比古 澤田 将幸 丹羽 真一 根來 秀樹 松本 英夫 田中 康雄
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.23-34, 2011-01-15
抄録 海外で広く使用され,30項目の質問から構成されるConners成人期ADHD評価尺度screening version(CAARS®-SV)の日本語版を作成し,成人期ADHD患者18名および健康被験者21名を対象に信頼性・妥当性を検討した。各要約スコアの級内相関係数の点推定値はいずれも0.90以上であり,また因子分析の結果,ADHDの主症状である不注意と多動性-衝動性を表す因子構造が特定された。内部一貫性,健康成人との判別能力ともに良好であり,他のADHD評価尺度CGI-ADHD-SおよびADHD RS-Ⅳ-Jとの高い相関が認められた。以上により,CAARS-SV日本語版の信頼性および妥当性が確認された。
2 0 0 0 IR 語り手としての空白
- 著者
- 浅野 則子
- 出版者
- 別府大学会
- 雑誌
- 別府大学紀要 (ISSN:02864983)
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.1-7, 2019-02
大伴家持と妻大嬢は大伴家として望まれた婚姻であり、幸せな関係を維持したとされている。しかしながらそれを証明するのは歌のみである。二人の関係が安定したものとなる時期以前の「二人の空白期」とされる時期に家持は「亡妾」への挽歌を作っているが、この挽歌により万葉集において大嬢との幸せな関係が強調されている。
2 0 0 0 OA ホルトノキ萎黄病による街路樹の衰退枯死
- 著者
- Takamasa Komiyama Takashi Ohi Yasutake Tomata Fumiya Tanji Ichiro Tsuji Makoto Watanabe Yoshinori Hattori
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20180203, (Released:2019-01-26)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 15
Background: A growing number of epidemiology studies have shown that poor oral health is associated with an increased incidence of functional disability. However, there are few studies in which the confounding bias is adjusted appropriately. In this study, it was examined whether dental status is associated with functional disability in elderly Japanese using a 13-year prospective cohort study after elimination of confounding factors with propensity score matching.Methods: Participants were community-dwelling Japanese aged 70 years or older who lived in the Tsurugaya district of Sendai (n = 838). The number of remaining teeth (over 20 teeth/0-19 teeth) was defined as the exposure variable. The outcome was the incidence of functional disability, defined as the first certification of long-term care insurance (LTCI) in Japan. The variables that were used to determine propensity score matching were age, sex, body mass index (BMI), medical history (stroke, hypertension, myocardial infarction, cancer, and diabetes), smoking, alcohol consumption, educational attainment, depression symptoms, cognitive impairment, physical function, social support, and marital status.Results: As a result of the propensity score matching, 574 participants were selected. Participants with 0-19 teeth were more likely to develop functional disability than those with 20 or more teeth (hazard ratio, 1.33; 95% confidence interval, 1.01-1.75).Conclusions: In this prospective cohort study targeting community-dwelling older adults in Japan, less than 20 teeth was confirmed to be an independent risk factor for functional disability even after conducting propensity score matching. This study supports previous publications showing that oral health is associated with functional disability.
2 0 0 0 OA ローベルト・コッホ : 偉大なる生涯の物語
- 著者
- ヘルムート・ウンガー 著
- 出版者
- 富山房
- 巻号頁・発行日
- 1943
2 0 0 0 OA 兵庫県史蹟名勝天然記念物調査報告
2 0 0 0 OA Toxicological Property of Acetaminophen: The Dark Side of a Safe Antipyretic/Analgesic Drug?
- 著者
- Yoichi Ishitsuka Yuki Kondo Daisuke Kadowaki
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.195-206, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
- 参考文献数
- 154
- 被引用文献数
- 29
Acetaminophen (paracetamol, N-acetyl-p-aminophenol; APAP) is the most popular analgesic/antipyretic agent in the world. APAP has been regarded as a safer drug compared with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) particularly in terms of lower risks of renal dysfunction, gastrointestinal injury, and asthma/bronchospasm induction, even in high-risk patients such as the elderly, children, and pregnant women. On the other hand, the recent increasing use of APAP has raised concerns about its toxicity. In this article, we review recent pharmacological and toxicological findings about APAP from basic, clinical, and epidemiological studies, including spontaneous drug adverse events reporting system, especially focusing on drug-induced asthma and pre-and post-natal closure of ductus arteriosus. Hepatotoxicity is the greatest fault of APAP and the most frequent cause of drug-induced acute liver failure in Western countries. However, its precise mechanism remains unclear and no effective cure beyond N-acetylcysteine has been developed. Recent animal and cellular studies have demonstrated that some cellular events, such as c-jun N-terminal kinase (JNK) pathway activation, endoplasmic reticulum (ER) stress, and mitochondrial oxidative stress may play important roles in the development of hepatitis. Herein, the molecular mechanisms of APAP hepatotoxicity are summarized. We also discuss the not-so-familiar “dark side” of APAP as an otherwise safe analgesic/antipyretic drug.
2 0 0 0 OA 外国為替平衡操作と不胎化政策の効果に関する資金循環分析
- 著者
- 辻村 和佑 溝下 雅子
- 出版者
- 環太平洋産業連関分析学会
- 雑誌
- 産業連関 (ISSN:13419803)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.49-62, 2003-06-25 (Released:2015-03-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 2
本稿では資金循環分析の枠組みをもとに,外貨準備の保有形態,さらには政府短期証券の発行と国庫余裕金繰替使用との相違にまで遡って,外国為替平衡操作の効果を分析した.その結果,邦銀国内店や外銀国内拠点への預託のように,外貨準備を国内で運用する場合には為替相場への影響が限定的であるのに対して,海外で発行された外貨建債券の買入や海外の中央銀行への預託のように,これを国外で運用する場合には比較的大きな介入効果が得られることを確認した.また外国為替平衡操作に対する日本銀行の対応を一般化すると,非不胎化,不胎化,逆非不胎化,逆不胎化と4分類することができる.本稿ではそれぞれの場合に対して,利用する金融市場調節手段ごとに海外への資金流出と海外からの資金流入の値を計測することで外国為替相場に与える影響を峻別した.この結果,不胎化もしくは非不胎化が外国為替平衡操作の効果を減殺するかどうかはひとえに金融調節手段の選択に依拠しており,これを一概に定性的に論ずることはできないことを確認した.
2 0 0 0 OA 社会的行動障害への介入法─精神医学的観点からの整理─
- 著者
- 三村 將
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.26-33, 2009-03-31 (Released:2010-06-02)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 5 1
脳損傷,特に前頭葉損傷患者が示す社会的能力の障害には,自分の言動を相手がどう思うかを理解できない「心の理論」(心的推測)の問題と,衝動コントロールの問題とが複合的に関与している。本稿では,衝動コントロールの問題への介入技法について,精神科的観点から整理を試みた。衝動コントロールが悪いと,脱抑制行動や対人関係トラブルが目立ったり,一方で思うようにいかないと激しい怒りの爆発( anger burst )が生じたりする。脱抑制に対しては,種々の向精神薬が奏効することがあるが,薬物療法の効果はまだ十分なエビデンスが得られていない。心理的介入については,精神科領域で広く用いられている認知行動療法は,前頭葉損傷患者が示す anger burst に対してもしばしば有用なアプローチとなる。原則として,患者の機能や気づきのレベルが低いほど行動的アプローチが中心となり,反対に機能や気づきのレベルが高いほど認知的アプローチの導入が可能となる。これらの具体的アプローチについて概説した。衝動の背景には動機を形成する快(報酬)─不快(罰)体験がある。本稿では,前頭葉損傷例に試みた予備的な長期報酬学習訓練について紹介した。衝動コントロール不良な前頭葉損傷患者がいかにして即時的報酬を抑えて,将来的・長期的な報酬を学習・強化できるかが今後の重要な研究ターゲットであろう。
2 0 0 0 OA リアルタイム組込みウィンドウシステムの実装
- 著者
- 林 寛 並木 美太郎
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.42(2003-OS-093), pp.119-126, 2003-05-08
今日,組込み機器の高性能化や小型化により,携帯電話や家電製品などにオペレーティングシステム(OS)が搭載されるようになった.それに伴い,リアルタイム性を持つグラフィカルユーザインタフェース(GUI)の必要性も増している.そこで,本研究ではリアルタイム性を持った組込みウィンドウシステムの開発を行っている.本稿では,本システムの中心となる描画処理に関して設計と実装について述べる.描画処理に優先度と時間制約を設定することでリアルタイムな描画処理を実現し,また,資源の少ない組込み機器へ実装するため,システム本体サイズおよび実行時の使用メモリを抑えることも考慮した.その結果,描画のリアルタイム処理を実現することができた.
2 0 0 0 わが国の立法府における情報公開の新展開
- 著者
- 大蔵 綾子
- 出版者
- 記録管理学会
- 雑誌
- レコード・マネジメント : 記録管理学会誌 (ISSN:09154787)
- 巻号頁・発行日
- no.57, pp.25-44, 2009-05-30
本稿は、2008年に衆議院において情報公開制度が設けられたのを契機として、立法府における情報公開の新たな展開につき現状と課題を提示するものである。