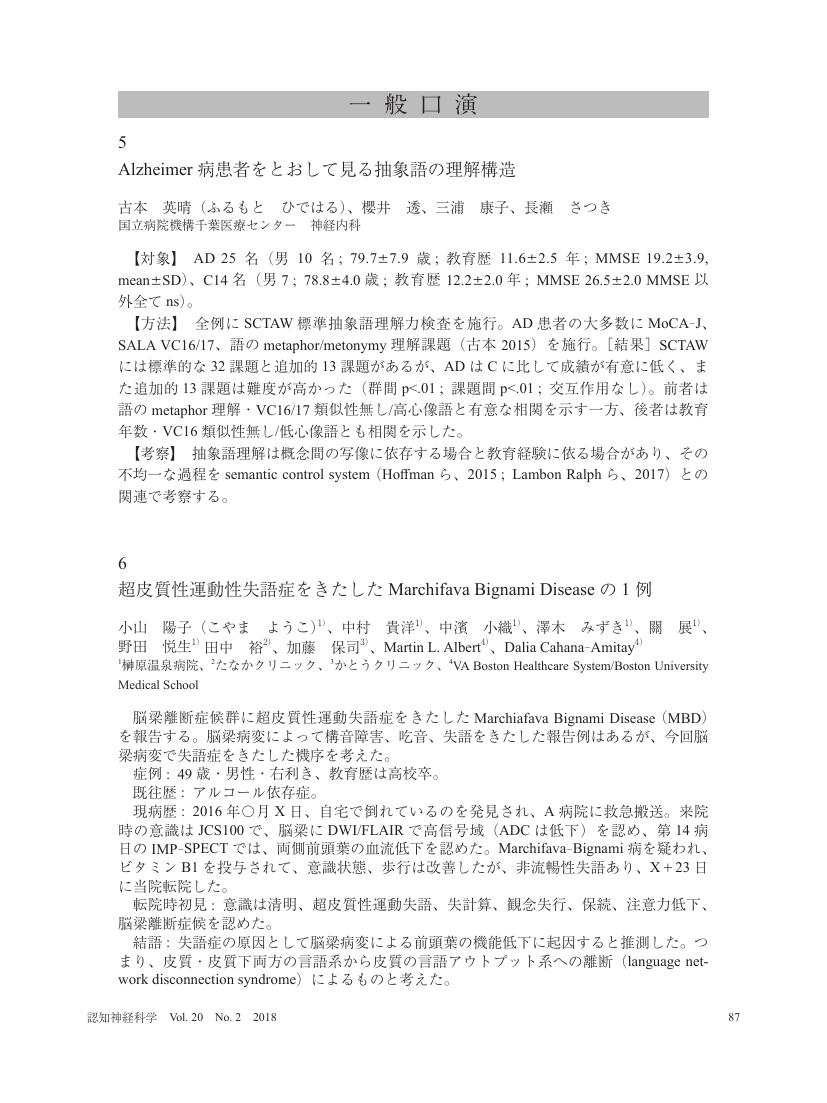- 著者
- 鯨岡 さつき
- 出版者
- 学習院大学ドイツ文学会
- 雑誌
- 学習院大学ドイツ文学会研究論集 (ISSN:18817351)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.65-96, 2017
Die deutsche Sprache ist eine plurizentrische Sprache, deren hochdeutsche Variante nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen deutschsprachigen Regionen gebildet wurde, weshalb es auch in Österreich ein „österreichisches Hochdeutsch" gibt, das e igene österreichische Ausdrücke enthält, wenn man Österreich als ein Zentrum des Hochdeutschen ansieht. Nach Wiesinger (2003) tauchte der Begriff „österreichisches Hochdeutsch" in den 1870er Jahren auf, als es insbesondere unter dem Begriff „kleindeutsch" einen Dualismus zwischen Preußen und Österreich gab. In der Untersuchung „Das Österreichische Hochdeutsch. Versuch einer Darstellung seiner hervorstechendsten Fehler und fehlerhaften Eigenthümlichkeit" (1875) zeigt der Verfasser Hermann Lewi die „hervorstechendsten Fehler und fehlerhaften Eigenthümlichkeiten" des von ihm so genannt „österreichischen Hochdeutsch" an. Auf jedem Fall enthält das „österreichische Hochdeutsch" österreichische Ausdrücke, sonst würde es keinen Unterschied zwischen dem österreichischen und dem preußischen Hochdeutsch geben. Nach Reiffenstein (2009b) folgte die beiden Söhne von Wolfgang Amadeus Mozart, die 1784 und 1791 im Wien geboren waren, „den jetzt allgemein gültigen hochdeutschen Normen", wenn sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Briefe geschrieben haben. Deshalb kann man sich vorstellen, dass zwei Musiker, Johann Strauss (1825-1899) und Gustav Mahler (1860-1911), die in Österreich geboren waren, sich besonders in Wien betätigten und dort auch starben, den preußischen Regeln auch folgten. Ich untersuchte in dieser Abhandlung die Briefen dieser beiden Musiker und ziele darauf ab, die Sprachwirklichkeit der deutschen Sprache im Österreich des 19. Jahrhunderts zu erklären. Bei der Untersuchung sammelte ich verschiedene Briefe von Strauss (1983, 1986, 1990, 1992, 1996a, 1996b, 1998, 1999, 2002, 2007) und machte daraus ein Korpus, das aus ca. 150.000 Wörtern (aus 695 Briefen) besteht. Außerdem sammelte ich verschiedene Briefe von Mahler (1995, 1996) und machte daraus ein anderes Korpus, das aus ca. 170.000 Wörtern (aus 772 Briefen) besteht. Diese Briefe der zwei Korpora habe ich in drei Gruppen eingeteilt (in vertraute Briefe, förmliche Briefe und andere Briefe). Kriterien für diese Einteilung waren u.a. der Gebrauch der Du-Anrede oder von Spitznamen usw. Soweit ich diese Korpora analysierte, lässt sich ermitteln, dass sowohl Strauss als auch Mahler den Regeln des preußischen Hochdeutsch gut folgen; aber man kann einerseits feststellen, dass sowohl Strauss als auch Mahler eine gemeinsame Tendenz in ihrem Sprachgebrauch haben; andererseits haben sie je eigene Tendenzen, die in jedem der Korpora gefunden werden kann. In Briefen von Strauss kann man bestimmte österreichische Merkmale finden, die sich auf das grammatische Feld beziehen: Beispielsweise benutzt Strauss die österreichischen Formen der singularischen Imperative, u. zw. „gebe" (statt „gieb") usw. Außerdem kann man den Wegfall der Laute „e" oder „en" bei „heut" („heute") und „mein" (statt „meinen") usw. finden. Dieser Wegfall kommt nicht nur in den vertrauten Briefen, sondern auch den förmlichen vor. Diese förmlichen Briefe schrieb Strauss an Adressaten, die in Österreich wohnten, d. h. er benutzte diese österreichischen Merkmale gegenüber Menschen, die ihm sprachlich nahestanden, obwohl die Briefe selbst doch eher steif sind. Wie Strauss befolgt Mahler einerseits die Regeln des preußischen Hochdeutsch gut; es gibt bei ihm sogar keine Sätze im österreichischen Dialekt, soweit ich untersucht habe; andererseits kann man aber in den Briefen bestimmte österreichischen Merkmale finden, die sich nicht auf das grammatische Feld beziehen, sondern auf den Wortschatz: Beispielsweise benutzt Mahler den österreichischen Wortschatz häufiger als Strauss (ich habe mich dabei an den bei Ammon (1995: 157-162) als österreichisch angegebenen Wörter orientiert). Als Ergebnis dieser Untersuchung kann man feststellen, dass Strauss und Mahler beinahe in allen Fällen sowohl in vertraulichen Briefe als auch in förmlichen Briefe nichtösterreichische Ausdrücke, u.zw. Ausdrücke nach preußischer Sprachnorm schreiben, d. h. sie sind in der preußischen Sprachnorm sehr bewandert. Österreichische Merkmale haben sich dennoch in die Briefe dieser beiden Männer eingeschlichen, auch wenn sie beabsichtigen, mit preußischen Hochdeutsch korrekt zu schreiben; auf dem grammatischen Feld in den Briefen von Strauss und im Bereich des Wortschatzes bei den Briefen von Mahler werden diese Einbrüche identifiziert. Daraus lässt es sich vermuten, dass diese verschiedenen Merkmale des Sprachgebrauchs von Österreichern „österreichisches Hochdeutsch" genannt wurden.
1 0 0 0 IR 恒川鐐之助と明治期日本の音楽
- 著者
- 井上 さつき
- 出版者
- 愛知県立芸術大学
- 雑誌
- 愛知県立芸術大学紀要 (ISSN:03898369)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.19-31, 2011
機能性精神疾患における神経細胞の機能や代謝の異常を解明するために、3Teslaの高磁場MR装置を用いて気分、不安障害患者の帯状回、左右基底核におけるプロトンMRS (proton magnetic resonance spectroscopy:^1H-MRS)の撮像を行った。中でもこれまで検出困難であったグルタミン酸やGABAなどの脳内アミノ酸神経伝達物質の変化に注目した。強迫性障害患者は帯状回でN-acetyl aspertate: NAAの有意な低下がみられグルタミン酸も健常者と比較して有意に低値であった。GABAは低値となる傾向があるものの、有意な差は見られなかった。基底核における強迫性障害患者のNAAは健常者と比較して高い傾向があり、右が左に比べて有意に高かったが、脳内アミノ酸神経伝達物質は健常者との間に有意な差はなく左右差も見られなかった。パニック障害患者では右基底核におけるグルタミン酸+グルタミンが健常者よりも有意に高かった。大うつ病障害患者では帯状回でグルタミン酸が健常者よりも有意に低かった。今回の研究では高磁場装置による強迫性障害、パニック障害、大うつ病における脳内アミノ酸神経伝遠物質の定量が行われ、それぞれの疾患に特有な脳部位における脳内代謝物変化が生じているという知見を得た。今後は症例数を増やし臨床症状の特徴との関連、薬物の影響を検討し、治療前後での比較を行うことを計画している。
1 0 0 0 OA 嚥下と姿勢および呼吸の関係
- 著者
- 南谷 さつき
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.34-39, 2014-02-20 (Released:2017-06-28)
- 著者
- ゴェッチュ=エルテン ジルケ 櫻木 さつき 川松 あかり
- 出版者
- 日本民俗学会
- 雑誌
- 日本民俗学 = Bulletin of the Folklore Society of Japan (ISSN:04288653)
- 巻号頁・発行日
- no.294, pp.30-53, 2018-05
1 0 0 0 OA 「伊豆半島大瀬崎におけるダイビング観光地の発展」
- 著者
- 池 俊介 有賀 さつき
- 出版者
- 日本地理教育学会
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.1-22, 1999-09-25 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
In recent years, coastal regions in Japan have been used as not only sea bathing resorts, but also as spaces for marine sports. This study clarifies processes and factors that lead to the formation of the tourist resort in the settlement of Osezaki in Numazu-shi, Shizuoka prefecture, as a typical case of the tourist resort for divers that located around the metropolitan area. The results are as follows.1. Scuba diving was introduced into Japan in 1947, and has become widespread rapidly after 1980's. With the increase of divers, 178 diving spots have been opened until now. They can be classified into two types; the first type locates near the metropolitan area and the second type locates on islands in low latitudes. Osezaki as a diving spot is the typical case of the first type.2. The inhabitants on Enashi-ku have depended upon coastal fishery, farming and production of firewood until 1950's. But with the rapid development of orange farming in 1960's, most of inhabitants became more dependant upon farming which utilized on terraced fields and made a comfortable income. For that reason, most of inhabitants were not interested in the operation of recreational industry on Osezaki in 1960's.3. With the improvement of traffic means and the decline of orange farming that was caused by the sudden fall of the price of oranges, some inhabitants of Enashi-ku started to operate the minsyuku (cheap lodging house in tourist resorts) as a principal occupation after 1970's. Enashi-ku as the community also started to operate the car park for tourists, using their common land.4. After the opening of diving spot of Osezaki in 1985, the number of divers has rapidly increased. And now, divers who visit to Osezaki amount to 85000 a year. As a results most of minshuku come to put diving service shops in their buildings and the settlement of Osezaki as the minshuku region changed to the tourist resort for divers.5. The superiority as a diving area (shortness of the time distance from Tokyo, beautiful landscape under the sea etc.) is important as fundamental conditions of the formation of the tourist resort for divers. On the other hand, managers of minshuku have positively offered special services for divers, because of maintaining their stability of operation. Divers who visit to Osezaki throughout the year were attractive for managers of minshuku as customers.6. The fishermen's cooperative of Uchiura has levied the charge (330yen per day) on each of divers since 1985, and about 50 percent of their income have distributed to Enashi-ku. Enashi-ku also has gained some income by the operation of the car park. These profits have been distributed to inhabitants of Enashi-ku directly or indirectly. But one of divers entered a lawsuit against the fishermen's cooperative of Uchiura on the grounds that levying of the charge by the fishermen's cooperative was unfair (it is pending in court now.) Local inhabitants are apprehensive that it may be a menace to the base of the enormous income. The desirable relationship between local inhabitants and divers is groped now.
1 0 0 0 OA てんかんと意識:非けいれん性てんかん重積状態からの考察
- 著者
- 渡邊 さつき
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.6, pp.591-594, 2018-12-01 (Released:2018-12-06)
- 参考文献数
- 9
てんかん学において「意識」は重要である。2017年に発表された国際抗てんかん連盟による新しいてんかん発作分類では, 意識を表す用語が“consciousness”から“awareness”に変更された。非けいれん性てんかん重積状態は, 患者によって様々な意識障害や認知機能障害がみられ, 幅広い臨床症状を呈する。このことから, 「意識」は様々な脳機能の集合として捉えるべきであると考える。近年EEG-fMRI研究により, Default Mode Network (DMN) と呼ばれる安静時に活動する脳領域が, てんかん性異常波が出現する際には活動が低下していることが明らかになった。DMNの各サブユニットは異なる機能的役割があることから, てんかん発作時の意識にはDMNが関与していることが示唆される。てんかん学は学際的領域であり, 神経生理学的視点を通して脳機能に迫るひとつのきっかけになるかもしれない。
- 著者
- 緒方 さつき 森松 嘉孝 幸崎 弥之助 工藤 昌尚 田尻 守拡 井 賢治 渡邉 健次郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.99-103, 2006
症例は42歳の男性。400ccの自動二輪車運転中に左側の駐車場から無灯火で出てきた普通車の右側面に衝突し,当院へ搬送された。来院時,呼吸は腹式呼吸で,両上下肢の知覚が消失し,両上下肢で徒手筋力テスト0であった。病的反射の出現は認めなかったが,肛門反射が完全に消失していた。重症の下位頸髄損傷を疑うも,頸椎単純X線,頭部CT,頸髄・胸髄・腰髄MRI検査にて異常所見は認めなかった。その後,6年前の急性一過性精神病性障害の既往が判明し,転換性障害の診断にて入院となった。徐々に症状の改善がみられ,リハビリテーション目的にて第13病日に他院へ転院となった。救急の現場において,症状と検査所見が一致しない事例をみた場合,精神病性障害である可能性に留意すべきである。
1 0 0 0 心地覚心の禅思想
- 著者
- 高柳 さつき
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.223-228, 2014
- 著者
- 小川 さつき
- 出版者
- 医学の世界社
- 雑誌
- ホルモンと臨床 (ISSN:00457167)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.p47-49, 1980-01
1 0 0 0 近畿の家庭における年末年始の行事食の現状(奈良県)
- 著者
- 三浦 さつき 太田 暁子 喜多野 宣子 志垣 瞳 島村 知歩 冨岡 典子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.199, 2010
【目的】近年、伝統的な行事食の伝承が少なくなっているといわれる。本報では、平成21、22年度の日本調理科学会特別研究として実施した「行事食調査」から、年末年始の行事食を中心に、奈良県の現状を把握し、世代間による認知度や喫食経験などの違いについて明らかにすることを目的とする。<BR>【方法】平成21年12月~平成22年3月、日本調理科学会「行事食調査」の全国統一様式による調査票により、大学生およびその家族にアンケート調査を実施した。そのうち、奈良県在住者251名(学生157名、家族94名)を対象にして、正月、人日・七草、大晦日の行事の認知度、行事食の喫食経験や調理状況について検討を行った。<BR>【結果】行事の認知・経験については、正月と大晦日は学生・家族ともほぼ100%であったが、人日・七草の認知は学生83%、家族90%であり、経験は学生57%、家族83%であった。年末年始の行事食においては、学生・家族とも喫食経験が90%以上と高かった料理は、雑煮、黒豆、かまぼこ、年越しそばであり、毎年食べている人がほとんどであった。正月の赤飯、大晦日の祝い料理やいわし料理は、喫食経験が低かった。雑煮、七草粥、年越しそばは、家庭で作って食べる割合が高かったが、昆布巻き、きんとん、だて巻き卵、かまぼこは、作って食べる割合よりも買って食べる割合のほうが高かった。学生と家族で比較すると、屠蘇、煮しめ、なます、七草粥の喫食経験に違いがみられ、家族よりも学生のほうが、年末年始の行事食の喫食経験や家庭で作って食べる人の割合が低い傾向がみられた。
- 著者
- 横山 さつき 中川 雅人 菊池 啓子 井村 保 新井 康友 浅野 俊和 水野 友有 馬場 美穂
- 出版者
- 中部学院大学総合研究センター
- 雑誌
- 中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要 (ISSN:1347328X)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.159-164, 2016-03
- 著者
- 中川 さつき
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.389-406, 2015-03
『ウティカのカトーネ』(1728)はメタスタジオにとって3 作目の音楽劇である。主人公カトーネは共和政ローマの理念を守るために,和平を拒んで名誉ある死を選ぶ。カトーネの高潔なモラルと,ライバルであるチェーザレの寛容の徳との対比がこの劇の核である。簡潔で力強い台詞と劇的な緊張感に満ちた傑作であるが,同時代の観客は愛国的なテーマにそれほど心惹かれず,また主人公が呪詛の言葉を吐きながら死んでゆく場面は激しい反発を巻き起こした。メタスタジオ自身はこの作品を偏愛していたが,『アッティリオ・レーゴロ』(1740)で一度だけ英雄悲劇に立ち戻ったことを例外として,その後は宮廷の人々の好みに従って,君主と臣下の理想的な関係を描いたハッピー・エンドの劇を書き続けたのであった。
1 0 0 0 OA Alzheimer病患者をとおして見る抽象語の理解構造
- 著者
- 北畠 さつき
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維機械学会
- 雑誌
- 繊維機械学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.8, pp.P268-P273, 1995
1 0 0 0 OA 身体環境共生学入門 : 包括的共生概念の構築に向けて
1 0 0 0 妊婦における地震の揺れに備えるための安全な姿勢の運動学的検討
- 著者
- 金井 章 渡辺 さつき 小林 小綾香 大瀬 恵子 植田 和也 後藤 寛司 森田 せつ子
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ab0453-Ab0453, 2012
【目的】 妊婦は、その経過とともに外力の影響を受けやすくなり、子宮破裂、常位胎盤早期剥離、後腹膜血腫などが生じやすい。そのため、災害時における外傷の予防には非常に注意を要する。特に、大規模地震の頻発する本邦では、地震時における妊婦の安全確保のための対策は非常に重要であるにもかかわらず、震災時の妊婦被災状況は明らかになっていないのが実情である。また、2007年より緊急地震速報の運用が始まったことで、数秒から数十秒前に揺れへの対応を取ることが可能となったものの、妊婦のサポートについて十分な検討は行われていない。そこで、妊婦における地震の揺れに備えるための安全な姿勢を検討することを目的として、揺れによる身体への外力の程度について検証した。【方法】 対象は、妊娠経験のある健常女性19名(平均年齢33.4±3.2歳、平均体重54.2±8.1kg、平均身長160.0±4.7cm)とした。被験者は、妊婦を模擬するための妊婦体験ジャケットLM-054(高研社製、重量7.2kg、妊娠8ヶ月から9ヶ月に相当)を装着・非装着の状態とし、起震車(カバヤシステムマシナリー社製)を用いて震度5弱の揺れにより身体へ加わる力を加速度計(WWA-006:ワイヤレステクノロジー社製)を用いて計測した。加速度計のサンプリング周波数は200Hzとし、左右の上後腸骨棘中央に装着した。振動時間は15秒で、中間10秒間について、3軸方向の合成加速度を解析した。計測姿勢は、揺れに備える姿勢として姿勢1:かがむ、姿勢2:膝をついてかがむ、姿勢3:お尻をついてかがむ、姿勢4:四つん這い、姿勢5:四つん這いで頭と胸を床に近づける、姿勢6:机を支えにした立位、姿勢7:壁を支えにした立位の7姿勢とした。得られた結果から、ジャケット装着の有無による差を対応のあるt検定で、姿勢による差を分散分析にて検討した。【倫理的配慮、説明と同意】 被験者へは本研究について説明し、研究への参加承諾を得た。また、本研究は豊橋創造大学生命倫理委員会にて承認を受け実施した。【結果】 平均加速度・最大加速度(単位;mG)は、ジャケット無しで姿勢1:211.6±90.5・497.1±86.3、姿勢2:234.5±99.8 ・566.4±144.7 、姿勢3:295.4±132.2 ・712.4±198.5 、姿勢4:209.5±88.7 ・503.4±149.7 、姿勢5:235.7±98.6 ・584.7±152.0 、姿勢6:248.0±121.6 ・657.6±127.9 、姿勢7:301.2±145.9・789.9±125.3 であった。ジャケット有りでは、姿勢1:200.4±79.0 ・447.1±75.0 、姿勢2:220.4±88.6 ・544.4±131.5 、姿勢3:252.8±109.4 ・607.4±110.5 、姿勢4:169.5±72.6 ・403.4±70.2 、姿勢5:219.0±89.8 ・526.1±61.7 、姿勢6:193.0±98.9 ・544.6±73.5 、姿勢7:225.0±111.8 ・586.6±102.3 であった。両群ともに、姿勢4が最も低い値を示し、ジャケット無しに比べジャケット有りで低い値を示していた。【考察】 妊婦では、平均11kgの体重増加が起こり、腹部と乳房が前方にせり出してくるため、身体重心位置が変化する。また、ホルモン環境の変化により関節が柔らかくなり、可動域が増大するため、立位姿勢が不安定となり、日常生活における種々の動作も制限される。このような状況の中で、地震時に揺れに対応するための、身体へ負担の少ない待機姿勢をとることは非常に重要である。今回の結果では、四つん這いが最も腰部への加速度は低く、負担の少ない姿勢であることが確認された。これは、四つん這いは支持基底面が広く安定した姿勢であり、腰部は揺れを生じている床の部分から一定の距離をとり、上下肢により体幹重量による慣性を利用して揺れを軽減させることができるためであると考えられた。一方で、床におしりをついてかがむ姿勢は最も大きな加速度を示していた。これは、揺れを生じている床の部分から臀部へ直接外力が伝わるため、その影響を受け易い姿勢であると考えられる。また、ジャケット無しに比べ有りで加速度が低くなっていたのは、ジャッケットによる身体重量の増加に伴う慣性力の増加効果によるものと考えられる。ただし、身体状況の変化や、その後の動作への影響などでは不利となることから、さらに検討が必要と考えられる。【理学療法学研究としての意義】 妊婦の揺れに備えるための適切な待機姿勢を明確にすることで、震災時の妊婦外傷を予防することができ、震災に対する不安感を軽減することができる。
- 著者
- 毛利 伊吹 笠井 さつき 大塚 秀実 中野 彩 木村 久美 元永 拓郎
- 出版者
- 帝京大学文学部心理学科
- 雑誌
- 帝京大学心理学紀要 (ISSN:13484788)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.31-48, 2015-03