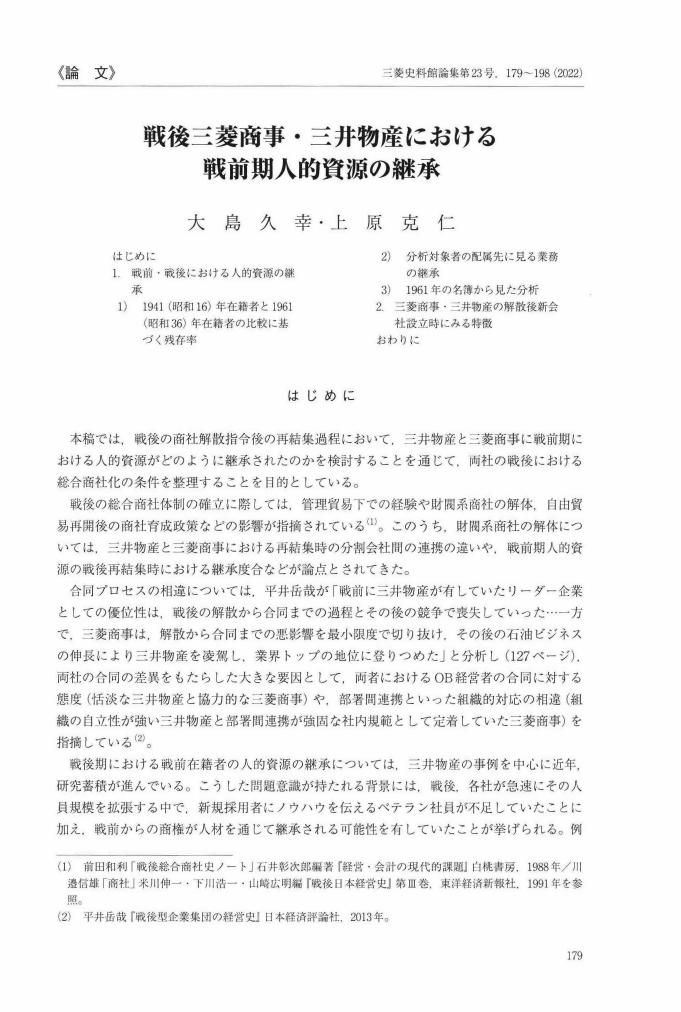61 0 0 0 新しい進化学理論の実験による探索-脊椎動物の力学対応進化学の実験系の確立
Rouxの言うように、重力など力学が進化の原因とすれば、進化のエポックを代表する動物に、進化で生じたphysicochemical stimuliを異種性に異所性に人為的に与えれば、進化で生じた物質が異種性に、異所性に生ずるはずである。局所の細胞の遺伝子の発現で、間葉系の高次機能細胞が誘導され、この細胞レベルの分化誘導の積み重ねで形態が決まるからである。この手法を研究代表者の西原が開発し、実験進化学手法(Experimental Evolutionary Research Method)と呼ぶ。これにより哺乳類において希望する間葉系高次機能細胞をハイブリッドタイプで、当該動物の細胞遺伝子を使って人為的に誘導することができる。脊椎動物の進化は、形態と機能と分子レベルでそれぞれ異なる。形態の進化は、内臓頭蓋の形態研究を行う以外には究明することが困難である。進化を遡ると、頸部・胸部・腹部・手と足との尾のすべては原索動物に至って、内臓頭蓋の原器、鰓孔のある口の嚢に収斂して、顔の原器のみとなってしまうからである。この動物がムカシホヤであり、脊椎動物の源となる本体であり、同時に顔の源とも言える生き物である。生命の営み(機能)の中心となる細胞レベルの消化・吸収・呼吸・代謝の要は造血巣であるが、この機能の進化は重力対応により腸管から脊髄腔へ移動する。このように形態と機能レベルの進化は、まぎれもなく生命体の生体力学的対応で生じており、Neo-darwinismのいうような進化の様式はどこにも観察されない。実験進化学手法を開発し次の3点につき研究した。(1)顔の源の生物マボヤの幼形進化の人為的誘発(2)人工骨脊髄バイオチャンバーによる軟骨魚類、円口類の筋肉内における造血巣の誘導(3)原始脊椎動物の組織免疫と胎児蛋白の関係の究明実験結果から、世界に先駆けてNeo-darwinismが完全否定され、脊椎動物の進化がLamarckの用不要の法則によることが検証された。本研究で、150年間脊椎動物の生物学を支配したNeo-darwinismの進化論が系統発生学の観察事実によって完全に否定され、力学対応進化学が実験的に検証された。脊椎動物の進化様式はハードのホメオボックスの情報系とソフトの環境因子と呼ばれる情報系の二重支配であったことが検証された。
47 0 0 0 OA 眠気予防薬の多量服用によるカフェイン中毒の2例
- 著者
- 北村 淳 宮部 浩道 植西 憲達 加納 秀記 平川 昭彦 原 克子 小宮山 豊 山中 克郎 武山 直志
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.5, pp.711-715, 2014-10-31 (Released:2015-01-24)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
致死量の眠気予防薬を服用した急性カフェイン中毒の2 例を経験した。症例1:20代の男性。市販の眠気予防薬を大量内服(無水カフェイン計8g)した。入院後,鎮静薬投与下においてもカフェインの作用による興奮が強く,入院2日目まで痙攣を認めた。第20病日に退院となった。症例2:30代の男性。市販の眠気予防薬を大量内服(無水カフェイン計14g)した。入院後ただちに,血液吸着および血液透析を施行した。人工呼吸管理中に興奮や痙攣などを認めず,第11病日に退院となった。両症例のカフェインおよびカフェイン代謝産物の血中濃度を経時的に測定したところ,血液吸着および血液透析後に明らかな減少を認めた。臨床所見も考慮すると,血液浄化法の早期導入がカフェイン中毒に奏功したと考えられた。致死量を内服した急性カフェイン中毒には,血液吸着に血液透析を併用した迅速な血液浄化法も有効な治療手段の一つであると考えられた。
35 0 0 0 OA FreeBSDにおけるLinux互換コンテナを対象としたマイグレーション機構の実現
- 著者
- 高川 雄平 松原 克弥
- 雑誌
- 研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS) (ISSN:21888795)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019-OS-145, no.13, pp.1-8, 2019-02-21
Linux において確立されたコンテナ型仮想化技術は,Docker の登場と普及にともなって,標準化団体 Open Container Intiative (OCI) 主導でコンテナ仕様が定義され,現在では,Windows や macOS などの他の OS 環境でもコンテナを利用できるようになった.FreeBSD 環境で動作する Docker では,FreeBSD が持つ Linux バイナリ互換機能などを活用してコンテナを実現している.しかし,FreeBSD 上の既存コンテナ実装は,プロセスのアイソレーション機能やマイグレーション機能など,OCI コンテナ仕様と比較して,その実現が十分とはいえない箇所が存在する.本研究では,FreeBSD 上で OCI 仕様に準拠するコンテナを実装し,さらに,そのコンテナのマイグレーションを実現する手法について提案する.
- 著者
- 三木 文雄 小林 宏行 杉原 徳彦 武田 博明 中里 義則 杉浦 宏詩 酒寄 享 坂川 英一郎 大崎 能伸 長内 忍 井手 宏 西垣 豊 辻 忠克 松本 博之 山崎 泰宏 藤田 結花 中尾 祥子 高橋 政明 豊嶋 恵理 山口 修二 志田 晃 小田島 奈央 吉川 隆志 青木 健志 小笹 真理子 遅野井 健 朴 明俊 井上 洋西 櫻井 滋 伊藤 晴方 毛利 孝 高橋 進 井上 千恵子 樋口 清一 渡辺 彰 菊地 暢 池田 英樹 中井 祐之 本田 芳宏 庄司 総 新妻 一直 鈴木 康稔 青木 信樹 和田 光一 桑原 克弘 狩野 哲次 柴田 和彦 中田 紘一郎 成井 浩司 佐野 靖之 大友 守 鈴木 直仁 小山 優 柴 孝也 岡田 和久 佐治 正勝 阿久津 寿江 中森 祥隆 蝶名林 直彦 松岡 緑郎 永井 英明 鈴木 幸男 竹下 啓 嶋田 甚五郎 石田 一雄 中川 武正 柴本 昌昭 中村 俊夫 駒瀬 裕子 新井 基央 島田 敏樹 中澤 靖 小田切 繁樹 綿貫 祐司 西平 隆一 平居 義裕 工藤 誠 鈴木 周雄 吉池 保博 池田 大忠 鈴木 基好 西川 正憲 高橋 健一 池原 邦彦 中村 雅夫 冬木 俊春 高木 重人 柳瀬 賢次 土手 邦夫 山本 和英 山腰 雅宏 山本 雅史 伊藤 源士 鳥 浩一郎 渡邊 篤 高橋 孝輔 澤 祥幸 吉田 勉 浅本 仁 上田 良弘 伊達 佳子 東田 有智 原口 龍太 長坂 行雄 家田 泰浩 保田 昇平 加藤 元一 小牟田 清 谷尾 吉郎 岡野 一弘 竹中 雅彦 桝野 富弥 西井 一雅 成田 亘啓 三笠 桂一 古西 満 前田 光一 竹澤 祐一 森 啓 甲斐 吉郎 杉村 裕子 種田 和清 井上 哲郎 加藤 晃史 松島 敏春 二木 芳人 吉井 耕一郎 沖本 二郎 中村 淳一 米山 浩英 小橋 吉博 城戸 優光 吉井 千春 澤江 義郎 二宮 清 田尾 義昭 宮崎 正之 高木 宏治 吉田 稔 渡辺 憲太朗 大泉 耕太郎 渡邊 尚 光武 良幸 竹田 圭介 川口 信三 光井 敬 西本 光伸 川原 正士 古賀 英之 中原 伸 高本 正祇 原田 泰子 北原 義也 加治木 章 永田 忍彦 河野 茂 朝野 和典 前崎 繁文 柳原 克紀 宮崎 義継 泉川 欣一 道津 安正 順山 尚史 石野 徹 川村 純生 田中 光 飯田 桂子 荒木 潤 渡辺 正実 永武 毅 秋山 盛登司 高橋 淳 隆杉 正和 真崎 宏則 田中 宏史 川上 健司 宇都宮 嘉明 土橋 佳子 星野 和彦 麻生 憲史 池田 秀樹 鬼塚 正三郎 小林 忍 渡辺 浩 那須 勝 時松 一成 山崎 透 河野 宏 安藤 俊二 玄同 淑子 三重野 龍彦 甲原 芳範 斎藤 厚 健山 正男 大山 泰一 副島 林造 中島 光好
- 出版者
- Japanese Society of Chemotherapy
- 雑誌
- 日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy (ISSN:13407007)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.9, pp.526-556, 2005-09-25
注射用セフェム系抗菌薬cefozopran (CZOP) の下気道感染症に対する早期治療効果を評価するため, ceftazidime (CAZ) を対照薬とした比較試験を市販後臨床試験として実施した。CZOPとCAZはともに1回1g (力価), 1日2回点滴静注により7日間投与し, 以下の結果を得た。<BR>1. 総登録症例412例中最大の解析対象集団376例の臨床効果は, 判定不能3例を除くとCZOP群92.0%(173/188), CAZ群91.4%(169/185) の有効率で, 両側90%, 95%信頼区間ともに非劣性であることが検証された。細菌性肺炎と慢性気道感染症に層別した有効率は, それぞれCZOP群90.9%(120/132), 94.6%(53/56), CAZ群93.3%(126/135), 86.0%(43/50) で, 両側90%, 95%信頼区間ともに非劣性であることが検証された。<BR>2. 原因菌が判明し, その消長を追跡し得た210例での細菌学的効果は, CZOP群89.5%(94/105), CAZ群90.5%(95/105) の菌消失率 (菌消失+菌交代) で, 両群間に有意な差はみられなかった。個々の菌別の菌消失率は, CZOP群91.1%(113/124), CAZ群90.8%(108/119) で両群問に有意な差はみられなかったが, 最も高頻度に分離された<I>Streptococcus pneumoniae</I>の消失率はCZOP群100%(42/42), CAZ群89.5%(34/38) で, CZOP群がCAZ群に比し有意に優れ (P=0.047), 投与5日後においてもCZOP群がCAZ群に比し有意に高い菌消失寧を示した (P=0.049)。<BR>3. 投薬終了時に, CZOP群では52,4%(99/189), CAZ群では50.3% (94/187) の症例において治療日的が達成され, 抗菌薬の追加投与は不必要であった。治療Il的遠成度に関して両薬剤間に有意な差は認められなかった。<BR>4. 随伴症状の発現率はCZOP群3.9%(8/206), CAZ群5.0%(10/202) で両棊剤間に有意な差はなかった。臨床検査値異常変動として, CAZ群に好酸球増多がCZOP絆より多数認められたが, 臨床検査値異常出現率としては, CZOP群31.6% (65/206), CAZ群32.2% (65/202) で, 両群間に有意な差は認められなかった。<BR>以上の成績から, CZOPは臨床効果においてCAZと比較して非劣性であることが検祉された。また<I>S. pneumoniae</I>による下気道感染症に対するCZOPの早期治療効果が確認された。
13 0 0 0 IR 宗教多元主義モデルに対する批判的考察--「排他主義」と「包括主義」の再考
- 著者
- 小原 克博
- 出版者
- 基督教研究会
- 雑誌
- 基督教研究 (ISSN:03873080)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.23-44, 2007-12
宗教の神学あるいは宗教間対話において広く用いられてきた類型に、排他主義、包括主義、多元主義がある。宗教多元主義の立場からは、しばしば、排他主義や包括主義は克服されるべき前時代的なモデルとして批判されてきた。本稿では、このような宗教多元主義モデルが前提としている進歩史的な価値観を「優越的置換主義」として批判すると共に、その問題は現実の宗教界や政治の世界などにおいても反映されていることを、西洋および日本における事例を通じて考察する。その上で、排他主義や包括主義に分類される宗教や運動の中にも、評価すべき要素があることを指摘する。また、これまでもっぱら西洋の神学サークルの中で議論されてきた多元主義モデルが、非西洋世界において、どのような有効性を持つのかを、イスラームや日本宗教の視点を適宜織り交ぜながら、批判的に検討する。最後に、西洋的価値を中心とする宗教多元主義を積極的に相対化していくためには、宗教の神学と文脈化神学を総合する必要があることを示唆する。論文(Article)
11 0 0 0 OA 精神医療技術を通じた自己形成に関する社会学的研究
- 著者
- 櫛原 克哉
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.574-591, 2015 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 20
本稿は, 社会生活への適応に困難を感じたために, 精神医療機関を利用した経験のある人々の語りを考察した. 近年の精神薬理学や臨床心理学的治療の拡充を受け, 精神医学においては従来の心理的・内面的な要因を対象とした治療に代わり, 患者の脳を中心とする生物学的要因や可視的な行動の矯正といった「フラット」な領域の治療が推進されている. N. Roseは, このような管理技術の浸透を, 精神医学の統治の「フラット化」の現象として指摘する.統治のフラット化を被治療者の観点から考察すべく, 筆者は医療機関への通院経験がある6名を対象にインタビュー調査を実施した. その結果, 「全人格型の語り」と「場面型の語り」の2類型が導出された. 「全人格型の語り」は心理学的な因果関係の文脈から過去との連続性を有する自己を導出するのに対し, 「場面型の語り」は現在属する社会環境内で問題となる思考や行動を限局的に調整しようと試みる断片的な自己という性質を有した.2つの語りは, 精神医学の治療構造の分裂を反映し, 医学のフラット化が不均質に浸透したことにより, 治療対象となる自己も分裂して生起することが確認された. このことから, 精神医療における統治により, 社会環境に適合的な自己が「フラットに」産出される一方で, 心理学的な主題に回帰して「精神の深部」を参照するような自己が, フラットな統治を下支えし治療の求心力として作用していることが示唆された.
10 0 0 0 OA 検査室の介入と患者指導によりカリウムの偽高値が改善した一例
- 著者
- 伊東 亜由美 森永 芳智 石原 香織 臼井 哲也 森 智嵩 原口 雅史 中尾 一彦 栁原 克紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.310-316, 2016-05-25 (Released:2016-07-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
検査前過程の影響で起こる検査データの偽高値や偽低値について,検査室による適切な評価と指導は適切な治療に貢献できる。偽性高カリウム(K)血症は検査前過程で発生することが多く,偽高値は不適切な治療につながり得る。今回,検査室主体の原因検討,他職種との情報共有および患者指導がK偽高値を解決した症例を経験した。症例は72歳女性,自己免疫性肝炎疑いで入院中であった。主治医よりK値の大きな日差変動(3.9–6.2 mmol/L)と患者病態および使用薬剤状況との乖離について問合せがあった。検査技師が病棟に出向き採血状況を確認すると,患者は過度のハンドグリップを行っており,解除直後のK値は4.9 mmol/Lであった。K高値がハンドグリップの影響か判断するため,完全に掌を開いた状態で採血を行うと,採血管順序に関わらずK値は4.0 mmol/Lで一定であった。以上より,ハンドグリップがK高値の原因と考えられた。この旨を診療録に記載するとともに,主治医,看護師と情報を共有した。さらに,患者本人に採血時の注意点を説明し,自己申告する内容について指導した。指導後はK偽高値を疑う値は示さなかった。正確な検査結果を得るための検査前過程の質の確保には,医療者側の対策だけでなく,患者が自身の体質を認識することも重要である。検査技師による積極的な連携と情報共有体制は,より質の高い医療につながるものと考えられる。
8 0 0 0 OA 一神教と多神教をめぐるディスコースとリアルポリティーク(<特集>宗教-相克と平和)
- 著者
- 小原 克博
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.451-474, 2005-09-30
本論文では、最初に日本および西洋における、一神教と多神教をめぐるディスコースの事例を取り上げ、その特徴を描写する。さらに、そのディスコースをオリエンタリズムやオクシデンタリズムの中に位置づけることによって、その文化的な構造を析出させ、さらに「偶像崇拝」を補助線として用いることによって、その宗教的な構造を明らかにする。偶像崇拝の禁止は三つの一神教、すなわち、ユダヤ教・キリスト教・イスラームに共通する信仰の基盤であるが、偶像崇拝は決して物質的な意味に限定されず、むしろ人間の作り出す観念やイメージをも含む「見えざる偶像崇拝」として機能する。また偶像崇拝が、近現代においては代替・拡張・反転というモデルの中で再解釈されていることを指摘する。最後に「見えざる偶像崇拝」は構造的暴力の温床になり得ることを終末論・進化論を交えて考察する。また同時に、一神教と多神教をめぐるディスコースが暴力的なディスコースへと転移しないための要諦を示唆する。
7 0 0 0 OA 大規模言語モデルを主体として扱うことの何がいけないのか?
- 著者
- 宮原 克典
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.1K5OS11b04, 2023 (Released:2023-07-10)
2022年6月、Googleのエンジニアが、大規模言語モデルLaMDAには意識があり、一人の主体として扱われるべきだと主張した。Google社は主張を退け、多くの論客がそれに賛同した。大規模言語モデル(LLM)への主体性の帰属を否定する理由は、いくつかある。(1)LLMの内在的特性に関わる理由:LLMは意識も意図ももちえない。(2)LLMへの主体性の帰属の帰結に関わる理由:LLMを主体として扱うことは、より重要な問題から社会の注意や関心を逸らせる。(3)個人のウェルビーイングに関わる理由:LLMを主体として扱うことは、本人の社会的孤立につながりうる。本発表では、これらの理由を検討し、LLMを主体として扱うべきではないと断言するのが意外に難しいことを示す。また、ロボットの道徳的地位やフィクトフィリア(架空の存在への性愛)をめぐる議論を引きながら、LLMへの主体性帰属の正当性を判断するためのポイントを整理する。
7 0 0 0 OA 症例 右心室内迷入鍼灸針の体外循環下摘出の経験
7 0 0 0 OA 異神の系譜─越境する神々と日本仏教の位相─
- 著者
- 原 克昭
- 出版者
- 東洋大学東洋学研究所
- 雑誌
- 東アジア仏教学術論集 = Proceedings of the International Conference on East Asian Buddhism (ISSN:21876983)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.261-289, 2017-01
「原克昭氏の発表論文に対するコメント」「張総氏のコメントに対する回答」含
7 0 0 0 OA 精神医療領域における認知行動療法の社会学的考察
- 著者
- 櫛原 克哉
- 出版者
- 東京通信大学
- 雑誌
- 東京通信大学紀要 = Journal of Tokyo Online University (ISSN:24346934)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.89-104, 2019-03-31
6 0 0 0 OA 戦後三菱商事・三井物産における戦前期人的資源の継承
- 著者
- 大島 久幸 上原 克仁
- 出版者
- 公益財団法人 三菱経済研究所
- 雑誌
- 三菱史料館論集 (ISSN:13453076)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.23, pp.179-198, 2022-03-20 (Released:2023-07-27)
6 0 0 0 OA 官房-原局関係からみた文部省の政策立案過程の分析(III 研究報告)
- 著者
- 青木 栄一 荻原 克男
- 出版者
- 日本教育行政学会
- 雑誌
- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.80-92, 2004-10-08 (Released:2018-01-09)
Although several attempts were made to change educational policy in the 1970s and 1980s in Japan, substantial changes were not realized until the second half of the 1990s. Why did the change occur only in the late 1990s? One explanation has been that the Ministry of Education was forced to change its former policy because of external pressures brought by ad hoc committees and councils set up in the cabinet during the 1990s. This argument appears to exaggerate the strong tendency of the Ministry as a whole to preserve the status quo and often ignores internal processes that enable changes in attitudes within the Ministry. This paper attempts to explore such internal factors in terms of the power relationship between various bureaus in the Ministry. The paper focuses on the relation between the Minister's Secretariat ('kanbou') and other bureaus ('genkyoku') such as the Elementary and Secondary Education Bureau. These two types of bureaus entail a difference in responding to the demands for change. In contrast to the other bureaus that are responsible for the implementation of specific policy, the main role of the Minister's Secretariat (MS) is to exercise a comprehensive coordinating function over all bureaus ('kanboukinou') ; and thus, the MS is more flexible when it comes to policy change than are other bureaus. We hypothesized that the MS's coordinating function was strengthened during the 1990s and that this allowed the Ministry to change its overall behavior. To examine this hypothesis, we analyzed the status of the MS within the Ministry concerning three points: (1) changes in the organizational structure of the MS; (2) the career pattern of the Director-General, or the chief, of the MS; and (3) the frequency of contacts between the Director-General of the MS and the Prime Minister. Results of our research found that, first, the sections responsible for investigation, statistics, and policy planning within the Ministry were integrated into the MS by the 1970s; in the 1980s, a Senior Deputy Director-General was newly established in the MS; and the Deputy Director-Generals of the other bureaus were transferred to the MS. These reorganizations reinforced the structure of the MS. Second, through analyzing the career pattern of the people who were appointed as Director-Generals of the MS, the paper demonstrates that, though being equal in rank to other bureau chiefs, the position grew important during the late 1990s in terms of the status which it has related to its influence on the ministry's behavior. Third, whereas there was hardly any contact between the Director-General of the MS and the Prime Minister in the 1980s, such contact sharply increased in the late 1990s. These analyses revealed that whereas the structure of the MS was empowered during the 1980s, the position of the MS's Director-General remained unimportant within the Ministry. It was in the late 1990s that the MS properly performed its coordinating function attaining its high status among the bureaus as well as relying on its reinforced structure. This empowerment of the MS's function then enabled the Ministry to change its policy during the same period.
本研究は、脊椎動物の謎と言われた骨髄腔における造血の仕組みを解明し、これを臨床応用する事を目的とした。これは進化の第二革命期の上陸に際して、造血の場が原始脊椎動物の本来の腸管を離れ、骨髄腔に移動したとする三木成夫の「脾臓の発生」研究に基づいている。人工骨髄造血器の開発は、今日、臨床上緊急の課題である。研究代表者の西原は、合成ヒドロキシアパタイトを用いて実験的に骨髄造血巣を哺乳類の筋肉内に異所性に、間葉細胞から誘導することにすでに成功し、1994年の第32回日本人工臓器学会にてオリジナル賞1位を受賞した。本研究はこの研究成果を実用化する目的のもので、次の5種類の研究を実施した。(1)間葉細胞の遺伝子発現がstreaming potentialによること (2)造血巣を誘導する電極型の人工骨髄バイオチャンバーの作製と成犬への移植による造血誘導能の観察 (3)系統発生における腸管造血から骨髄造血への変換の原因究明 (4)進化のエポックとなる哺乳類、鳥類、両生類、軟骨魚類と無顎類の筋肉内への合成アパタイト人工骨チャンバーの移植と、造血巣誘導の有無の観察 (4)牛由来のコラーゲン複合低温焼結アパタイト人工骨の開発と成犬およびドチザメへの移植による組織免疫と造血の関係の観察 (5)人類特有の免疫疾患の原因が口呼吸であることを究明し、成犬と成猫による人類型免疫病のモデル作製研究 以上の実験で異所性ならびに骨髄腔を持たない軟骨魚類における異種性の造骨と造血現象がすべてのアパタイトとチタン電極バイオチャンバーの移植により、すべての宗族に観察された。また、牛由来のコラーゲンは犬では明らかな細胞レベルの消化が観察されたが、サメでは円滑な類骨と造血巣の誘導が観察された。これらから骨髄造血の成立が、浮力に相殺された見かけ上の6分の1Gの水中から陸棲への変化に伴う1Gの作用によることが明らかとなった。また原始脊椎動物の組織は哺乳類の胎児蛋白に相当し、主要組織適合抗原を保ちないことが明らかとなり、胎児蛋白の成体型への変換が骨髄造血に伴う重力の作用によるとする結果が得られた。これらのことから組織免疫と感染免疫とアレルギーで混迷している現在の免疫学を統一的に理解できる新しい免疫学の考え方として「細胞レベルの消化・代謝・吸収」(三木)という新しい免疫学の概念を樹立することができ、同時に脊椎動物の進化の主要機序が解明され、画期的な成果が得られた。
5 0 0 0 OA 事物知覚とエナクティヴィズム どうして物を見ることが身体的行為なのか
- 著者
- 宮原 克典
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.68, pp.200-214, 2017-04-01 (Released:2017-06-14)
- 参考文献数
- 21
This paper proposes an enactive account of thing-perception by integrating a descriptive, phenomenological analysis of thing-perception with the American philosopher John Haugeland’s account of “objective perception.” Enactive views of perception hold that perception is a form of embodied action. They apply well to the kind of perception that directly guides embodied action, but so far there is no convincing account as to how they might accommodate “thing-perception,” or the kind of perception that merely presents physical objects as things as such. Phenomenologically speaking, thing-perception is a temporally extended process of transforming an inarticulate appearance of a physical object into an articulate one. Furthermore, such transformation is shaped by embodied action guided by a normative sensitivity to the environment. Accordingly, phenomenological description suggests that ordinary thing-perception depends on the operation of bodily skills or bodily habits of certain kinds. On the other hand, Haugeland submits that our perceptual experience has the structure of objectivity by virtue of our antecedent commitment to certain constitutive standards. In particular, thing-perception is essentially dependent on our commitment to the constitutive standard for thinghood: We experience things as perceptual objects because of our preparedness to maintain in our experience a pattern of phenomena in accord with this constitutive standard. I claim that it is one and the same thing to have a commitment to the constitutive standard for thinghood and to have a bodily habit of seeing physical objects as things as such. Furthermore, I argue by thus integrating the two accounts described so far that thing-perception is essentially dependent on a form of embodied action. To have a bodily habit of seeing something as such is to have a commitment to the constitutive standard for thinghood, and the latter commitment is necessary for thing-perception to take place. Therefore, thing-perception is essentially a form of embodied action.
5 0 0 0 OA フルーツグラノーラ摂取が排便状況とQOLに与える影響
- 著者
- 許 鳳浩 長谷部 久乃 石原 克之 伊藤 政喜 上馬塲 和夫 鈴木 信孝
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.23-26, 2017-03-31 (Released:2017-04-05)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
フルーツグラノーラの摂取が排便状況およびQOLに与える影響について検討するため,排便回数が週に5回以下の女性20名(平均年齢20.0 ± 1.1歳)を対象としたオープン臨床試験を行った.フルーツグラノーラ1日当たり50 gを,1食の主食に置き換えて2週間連続摂取させ,摂取前後の排便状況やQOLを比較した.試験の結果,フルーツグラノーラ摂取後は,摂取前と比べて摂取2週間目で排便回数の増加( p =0.014),排便量の増加(p =0.024)が見られ,全体的なQOLの向上(p =0.011)も認められた.このことから,フルーツグラノーラの摂取は排便状況の改善やQOL向上に有効である可能性が示唆された.
- 著者
- 西原 克成 手嶋 通雄
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
- 雑誌
- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1-2, pp.152-168, 2012-04-26 (Released:2014-01-14)
- 参考文献数
- 42
人間の生命を扱う医学で最も重要な事項は,ミトコンドリアのエネルギー代謝と環境エネルギーと動物自身の動きの生体力学エネルギーであるが,このエネルギーの概念が今日完璧に見過ごされている.筆者は医学と生命科学にこれらの考えを導入してエネルギーに立脚した革新的な「顔と口腔の医学」をまとめて出版した.この新しい医学の考えに立って筆者は,骨癒着型のインプラントに代わって新型の歯根膜を持つ釘植型人工歯根を開発した.人工歯根の基礎的研究についてはPart 1前編に報告した.本稿では釘植型人工歯根と歯科インプラントとのコンセプトの違いについて述べる.人工歯根療法を完成させるのには20 年を要した.本療法は,一般の疾病の外科手術方法とは異なり,より良い咬合状態を求めるための咀嚼器官の手術療法である.顔と口腔とはヒトの生命維持および社会生活上最も重要な器官である.この観点から実地臨床応用のための人工歯根療法を樹立することが肝要である.実際の人工歯根手術療法では,安全で容易かつ確実な手法の開発が最も肝要である.この目的にかなった人工歯根の形態を,哺乳動物のヒトの歯の器官特性つまり咀嚼時の質量のある物質の切断・摩砕機能の負担に耐えるよう太くて短いチタン製の波状円筒形の人工歯根と,歯根に相応する切削器具を開発した.手術中にほとんど出血のみられないきわめて安全で容易かつ確実な人工歯根手術法が開発された.術後15 分して人工歯根表面と歯肉および歯槽手術創の歯周間葉組織とは癒合する.したがって手術後30 分経過すれば食事は可能となる.歯科と整形外科のインプラントデバイスは,今や盛んであるが,剛対剛つまり骨とチタンインプラントの直接癒着システムである.この結合様式は反復加重下で必ず破断するために,今日では剛体力学的見地から科学的に否定されている.したがって現代社会では,医学を除いて剛体結合(骨性癒着)様式は工学的にも,機械学からも,産業科学からも建築学的にも顧みられなくなっている.現代医学では,エネルギーのみならず生体力学の概念の完全欠落によりインプラントの骨性癒着システムの誤ったコンセプトに対し,誰一人として異を唱える者がいない.整形外科と歯科のインプラントデバイスにエネルギーの概念のみならず線維組織による関節結合システムのコンセプトをただちに導入しなければならない.これにより旧態然たる医学界がようやくにして現代科学の技術水準に到達することができるのである.
4 0 0 0 OA 宗教多元主義モデルに対する批判的考察 : 「排他主義」と「包括主義」の再考
- 著者
- 小原 克博 Katsuhiro Kohara
- 出版者
- 基督教研究会
- 雑誌
- 基督教研究 = Kirisutokyo Kenkyu (Studies in Christianity) (ISSN:03873080)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.23-44, 2007-12-12
宗教の神学あるいは宗教間対話において広く用いられてきた類型に、排他主義、包括主義、多元主義がある。宗教多元主義の立場からは、しばしば、排他主義や包括主義は克服されるべき前時代的なモデルとして批判されてきた。本稿では、このような宗教多元主義モデルが前提としている進歩史的な価値観を「優越的置換主義」として批判すると共に、その問題は現実の宗教界や政治の世界などにおいても反映されていることを、西洋および日本における事例を通じて考察する。その上で、排他主義や包括主義に分類される宗教や運動の中にも、評価すべき要素があることを指摘する。また、これまでもっぱら西洋の神学サークルの中で議論されてきた多元主義モデルが、非西洋世界において、どのような有効性を持つのかを、イスラームや日本宗教の視点を適宜織り交ぜながら、批判的に検討する。最後に、西洋的価値を中心とする宗教多元主義を積極的に相対化していくためには、宗教の神学と文脈化神学を総合する必要があることを示唆する。
4 0 0 0 OA 戦後文部行政の機構と機能(下)
- 著者
- 荻原 克男
- 出版者
- 北海道大學教育學部
- 雑誌
- 北海道大學教育學部紀要 (ISSN:04410637)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.45-112, 1986-10