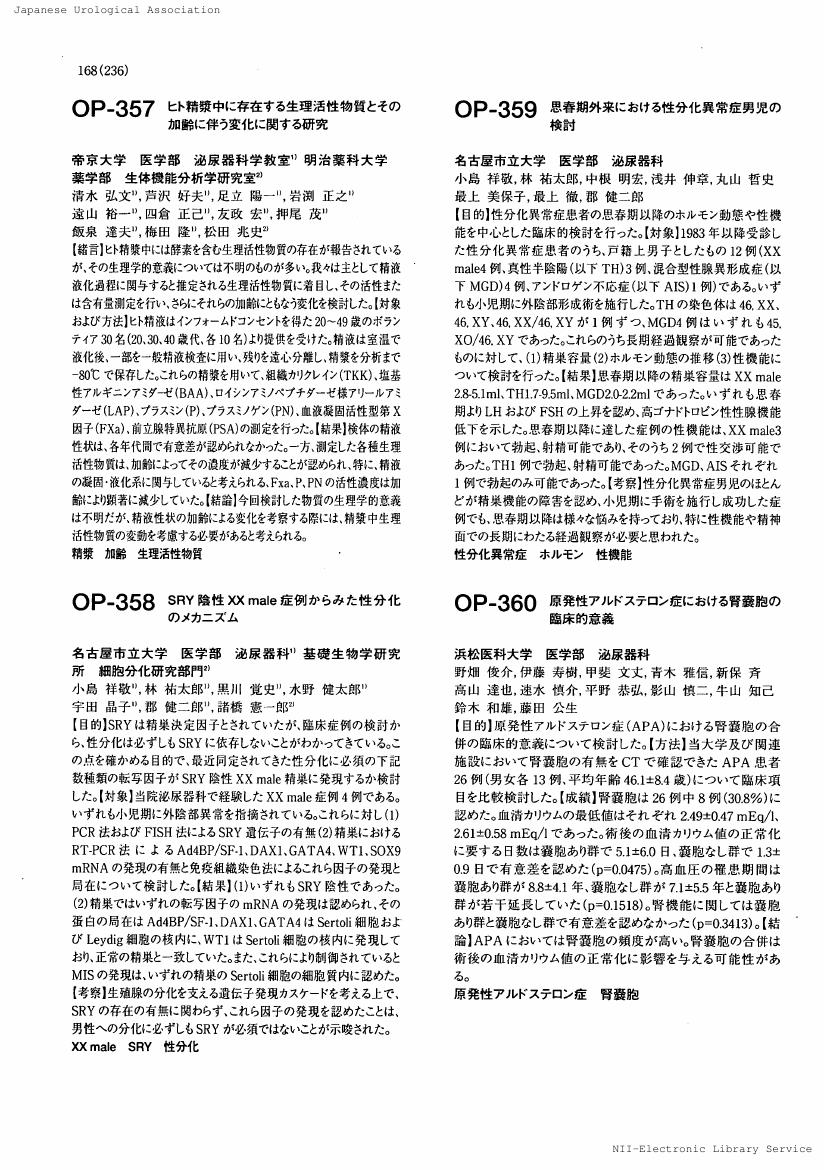1 0 0 0 IR 陸上競技選手における見た目の魅力及び顔の縦横比と競技成績との関連性
- 著者
- 上妻 歩夢 齋藤 未花 本間 洋樹 水野 増彦 横山 順一 小林 史明 畑山 茂雄 菊池 直樹
- 出版者
- 日本体育大学
- 雑誌
- 日本体育大学紀要 (ISSN:02850613)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.3015-3020, 2021
自転車競技,アメリカンフットボールなどの競技を対象に見た目の魅力と競技パフォーマンスとの関連性が報告されている。本研究では,大学陸上競技選手を対象に,見た目の魅力及びfacial width-to-height ratio(FWHR)と競技成績との関連性について検討した。本研究の対象者は,93名の大学陸上競技選手(男性42名,女性51名,年齢19.8±1.2歳)であった。競技成績から全国入賞以上を上位群,全国出場以下を下位群に分類した。魅力度は,対象者のことを知らない241名(男性124名,女性117名,年齢20.81±1.5歳)の評価者によって評価された。評価方法は,10 cmの直線を用いたVAS法で異性の評価を行った。対象者1人あたりの評価者の人数は32–37名であった。本研究の対象者の内,86名(男性40名,女性46名,年齢19.74±1.2歳)を対象にFWHRの計測を行った。FWHRは,横幅は左右の頬骨の位置,高さは上唇の上部から眉毛の下部の位置を,ImageJを用いて測定し,横幅と高さの比を求めた。短距離選手において,上位群が下位群に比べて魅力度が高い傾向にあった(p=0.053)。一方,長距離選手においては,下位群に比べて上位群で魅力度,FWHRともに有意に低かった(p=0.039, 0.047)。本研究の結果,短距離選手では競技成績が高い群で,見た目の魅力が高く,長距離選手では競技成績が低い群で,見た目の魅力とFWHRが高かった。
- 著者
- 瀬尾 和哉 佐藤 充 鎌田 圭介 小林 拓人
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- シンポジウム: スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文集 2020 (ISSN:24329509)
- 巻号頁・発行日
- pp.A-3-1, 2020 (Released:2021-06-01)
We developed a new suit for Tokyo 2020Olympic and Paralympic cycling road races. Several clothes were tested by using a truncated cone wrapped with cloth in the wind tunnel. On the basis of the drag measurements, several pilot suits were made. They were tested by using a full-scale mannequin which can pedal the bike in the wind tunnel. Finally, we succeeded in developing the new suit for Tokyo 2020Olympic and Paralympic cycling road races, which is superior to Beijing model.
1 0 0 0 IR 『正規の世界・非正規の世界』のその後
- 著者
- 神林 龍
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 経済研究 (ISSN:00229733)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.1-29, 2019-01
1980年代以降ゆらいでいるといわれる日本的雇用慣行について,中長期的な観点から議論したのが,『正規の世界・非正規の世界』(2017年,慶應義塾大学出版会)である.出版以来,いくつかの重要な指摘を受けてきたが,とくに主要な主張に関わるデータがリーマン・ショック以前の2007年に留まっていることが問題視された.本稿では,データを2012年まで延長し,リーマン・ショック以降についても本書の主要な主張,とくに長期雇用慣行の代理変数とした大卒勤続5年以上の被用者の十年残存率と,非正社員と自営業の人口に対するシェアの負の相関は変化がないことを示す.ただし,2012年の総務省『就業構造基本調査』の調査票改訂により,自分の労働契約期間がわからないとする被用者が相当数いることがわかっており,後者の主張は,これらの被用者をどう解釈するかに依存するかもしれない点も確認された.
1 0 0 0 IR 死を越えて追いかける借金取り--日本の説話に使われた中国のモチーフ
- 著者
- 小林 信彦 Nobuhiko Kobayashi
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学人間科学 (ISSN:09170227)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.35-75, 2002-07
- 著者
- 神林 飛志
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュータ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.814, pp.96-98, 2012-08-02
原価計算といった基幹バッチシステムをオープンソースの分散処理ソフト「Hadoop」で構築する─。神林飛志氏は、ログ解析や検索を念頭に開発されたHadoopを基幹系に適用した先駆者である。Hadoop以前にも、Javaなどの新技術にいち早く注目。不足する機能は自ら作り実用化を進めてきた。─Hadoopで基幹バッチシステムを構築しようと考えたきっかけは何ですか。
1 0 0 0 OA 政令指定都市のICT戦略骨子比較によるMECE指針の妥当性検証
- 著者
- 林 浩一
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-CE-146, no.10, pp.1-8, 2018-10-13
戦略コンサルティング会社に由来するロジカルシンキングの手法は,説得力のある提案や報告の作成に効果的なことから,広く普及しているが,学術的な基礎が不十分なために,経営企画の領域に適用範囲が限定されている.本研究はロジカルシンキングの手法において,推奨される手法の妥当性について,客観的な比較調査により検証することをねらいとしている.本論文ではロジカルシンキングで導入される基本的な概念である,MECE という分類指針が適切なものかどうかについて疑問を提起するとともに,その妥当性検証の検証を試みる.政令指定都市で立案された ICT 戦略の骨子について MECE の観点から比較検討を行い,その結果を踏まえ MECE に代わる分類指針として分類再現性を提案する.
1 0 0 0 OA アカヒゲホソミドリカスミカメの飛翔に影響を及ぼす各種要因 第2報温度の影響
- 著者
- 石岡 将樹 菊地 淳志 小林 徹也
- 出版者
- 北日本病害虫研究会
- 雑誌
- 北日本病害虫研究会報 (ISSN:0368623X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.55, pp.143-145, 2004-12-15 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 10
アカヒゲホソミドリカスミカメの飛翔に及ぼす温度の影響を宙吊り飛翔法により解析した. 雌では, 25, 19, 16℃ と飛翔時の温度が低下するにつれて, 飛翔回数と最長飛翔時間, 積算飛翔時間が減少し, 25℃と16℃ との間では有意な差が認められた. 最長飛翔時間か ら, 16℃では長距離の飛翔は行われないと考えられる. 雄では, 有意差は認められないものの, 最長飛翔時間と積算飛翔時間は低い温度で低下する傾向があった.
1 0 0 0 OA 赤血球の形態と染色性の死後変化
- 著者
- 平林 朗
- 出版者
- International Society of Histology and Cytology
- 雑誌
- Archivum histologicum japonicum (ISSN:00040681)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.63-69, 1953-04-20 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 9
Nach einer Reihe von Vorversuchen an Meerschweinchen wurden an der formalinfixierten Leber aus Leichen des Menschen, deren Todesursache und Todeszeit bekannt waren, die postmortalen Veränderungen der Erythrocyten untersucht, und zwar in der Zeit vom Sommer bis zum Winter. Dabei wurde das Leberstück in Celloidin eingebettet und in Schnitte zerlegt, welche mit Phosphormolybdän-Kernechtrot und Trypanblau gefärbt wurden. Die Erythrocyten vermindern im Laufe der Zeit die Färbbarkeit mit Kernechtrot, vermehren aber die Färbbarkeit mit Trypanblau und quellen auf, um schließlich nach 96 Stunden gänzlich zu zerfallen. Die Ultrastrukturdichte der Zellen erniedrigt sich also nach dem Tode. Auf Grund dieser Veränderungen ist umgekehrt die Todeszeitbestimmung möglich. Die Tafelabbildungen zum Artikel, Skizzen von je 50 Erythrocyten in der Zeit 10, 20, 30, 48 und 72 Stunden nach dem Tode, leisten Dienste in der gerichtlich-medizinischen Praxis.
1 0 0 0 OA 微量元素の高精度分析法の開発と海洋化学への応用
- 著者
- 宗林 由樹
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 海の研究 (ISSN:09168362)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.145-155, 2016-11-15 (Released:2018-10-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
海洋の微量元素は,海洋生物の微量栄養塩,現代海洋のトレーサー,古海洋研究のプロキシ(代替指標)としてきわめて重要である。しかし,海洋の微量元素は,濃度が低い,共存物質が測定を妨害する,採水から測定までの間に目的元素が汚染混入するなどの理由により分析が難しかった。著者は,簡便かつ精確な新しい分析法を開発し,それらを海洋研究に応用してきた。本稿では,以下の二つの内容について詳しく述べる。(1) 海水中アルミニウム,マンガン,鉄,コバルト,ニッケル,銅,亜鉛,カドミウム,鉛の多元素分析法の開発とその応用。(2) 海水中銅安定同位体比分析法の開発とその応用。これらの方法は,新しいキレート樹脂NOBIAS Chelate-PA1と誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)に基づいている。その分析結果の精確さは,国際共同観測計画GEOTRACESの相互較正などを通して確証された。さまざまな元素の濃度比,および濃度と安定同位体比の情報が利用できるようになり,海洋の生物地球化学サイクルに関する理解がますます深まりつつある。
1 0 0 0 IR 都市の色彩表徴と民俗文化
- 著者
- 小林 忠雄
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.p343-370, 1993-02
日本人の色彩感覚に基づく文化および制度や技術の歴史に関して,これまで多くの研究が行われてきたが,本稿では主として日本の民俗文化において表徴される色彩に焦点をあて,その民俗社会の心意的機能,あるいは庶民の色彩認識についてのアプローチを試みたものである。特に都市社会において顕著な人為的色彩は,日本の各都市において様々な諸相をみせ,ここでは伝統都市として金沢,松江,熊本の各城下町を対象に,近世からの民俗的な色彩表徴の事例を現地調査および文献を参照しながら考察し,その特徴を引き出してみた。その結果,白色をベースにした表徴機能,赤色,赤と青色,藍色,紫色,黒色,五彩色といった色調の民俗文化に都市的要素を加味した展開のあることが見出された。金沢と熊本の場合は民俗事例と藩政期からの伝承により,松江はラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の『日本瞥見記』の著作を通して,明治初年の事例とハーンの見た印象をてがかりに探ってみたものである。また,都市がなぜ民俗的な色彩表徴の機能を前提としているかについての疑問から,建築物,あるいは染色,郷土玩具といった対象によって,多少,問題アプローチへの入口を見出し得たと思われる。都市は日本の社会構造の変革をもっとも端的に表出する場であるため,モニュメント,ランドマーク,メディアの変化など外側の表徴だけでも,その変容の速度は著しく,従って色彩の記号化も激しく変化するが,しかしそうであっても日本人の基本的な色彩の認識は変わっていないという前提にて,都市のシンボルカラーを捉えねばならないと考える。それはまったく日本の民俗文化の枠を越えてはいないからであろう。
1 0 0 0 OA SRY陰性XXmale症例からみた性分化のメカニズム
- 著者
- 小島 祥敬 林 祐太郎 黒川 覚史 水野 健太郎 宇田 晶子 郡健 二郎 諸橋 憲一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.2, pp.236, 2002-02-20 (Released:2017-04-06)
1 0 0 0 夜空にブランコ:- TVMLを用いたビデオクリップ試作 -
- 著者
- 鯉渕 幹生 田中 宗一郎 高尾 契太 晝間 崇史 植田 寛 林 正樹
- 出版者
- 一般社団法人 画像電子学会
- 雑誌
- 画像電子学会研究会講演予稿
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.63-64, 2005
NHK技術研究所が開発したテレビ番組記述言語TVML用いて楽曲のイメージを表現した映像作品の試作に挑戦した。誰もが共感できる「愛」をテーマに主人公BOBが愛するMARYのために奮闘する姿を描いた。MARYに会いたいという、たった一つの目的に向かってひたすら進むBOB。あえて難解なストーリーを廃し、デフォルメされたCGを使う事によってストレートに作品のテーマを感じてもらおうと試みた。BOBはMARYに会いたいという一心でどんな試練でも乗り越えていく。その姿を見て自分の愛する人、家族や友人、恋人と共に励ましあい頑張っていく大切さ、また一人ではないという事の心強さに気づいて欲しいと思った。
1 0 0 0 日本沿岸における褐藻ヒジキの系統地理学的解析
- 著者
- 堀内 はるな 小林 穂ノ佳 岩崎 貴也 嶌田 智
- 出版者
- 日本藻類学会
- 雑誌
- 藻類 = The Japanese journal of phycology (ISSN:00381578)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.139-148, 2017-11-10
1 0 0 0 一連の住宅 (学会賞・第2部作品部門)
- 著者
- 林 雅子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- no.1183, pp.73-74, 1981-08
1 0 0 0 ガラス製エキサイトロンの格子制御特性
- 著者
- 小林 春洋
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.858, pp.288-292, 1960
- 著者
- 下林 典正
- 出版者
- 一般社団法人日本鉱物科学会
- 雑誌
- 日本鉱物科学会年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, 2012
天然に産する水晶の形状は、主に錐面(<i>r</i>:{10.1},<i>z</i>:{01.1})と柱面(<i>m</i>:{10.0})で囲まれており、底面(<i>c</i>:{00.1})の出現は極めて稀である。例外的に、米国アリゾナ州Four Peaks産のアメジストなど、限られた産地から底面をもつ水晶の産出が知られており、当地のアメジストについてはカソードルミネッセンス(CL)観察により、溶解によって底面が生じたことが示されているが(Kawasaki et al, 2006)、このような観察例は極めて乏しいのが現状である。本研究では、大阪府長谷産の高温石英のCL観察の結果、溶解ではなく成長の過程で底面が出現している組織が確認されたので報告する。