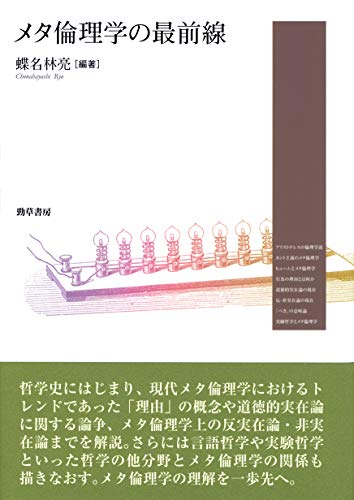- 著者
- 篠山 浩文 林 薫 藤井 貴明
- 出版者
- 千葉大学園芸学部
- 雑誌
- 千葉大学園芸学部学術報告 (ISSN:00693227)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.p267-270, 1995-03
β-D-xylosyl glycerol, lactoseを含む溶液中でEscherichia coli β-galactosidaseを作用させ, その反応液を活性炭およびセルロースカラムクロマトグラフ法に供したところ, ο-β-D-galactosyl-(1→4)-ο-β-D-xylosyl-(1→1)-glycerol, ο-β-D-galactosyl-(1→4)-ο-β-D-xylosyl-(1→2)-glycerol, ο-β-D-galactosyl-(1→4)-ο-β-D-xylosyl(1→3)-glycerolの3種の異性体からなる新規配糖体標品が得られた.
- 著者
- 星野 顕宏 阿部 祥英 冨家 俊弥 校條 愛子 中村 俊紀 齋藤 多賀子 酒井 菜穂 伊藤 良子 神谷 太郎 北林 耐 板橋 家頭夫
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.217-224, 2010 (Released:2010-10-07)
- 参考文献数
- 24
気管支喘息呼吸不全の児に対して硫酸マグネシウム(MgSO4)を点滴静注し,気管挿管を回避しえた女児例を経験した.本症例は2歳11ヵ月時に喘鳴と呼吸困難を認め,気管支喘息呼吸不全の診断で入院した.ステロイド薬静注,アミノフィリン持続点滴,イソプロテレノール持続吸入による治療を行ったが,呼吸状態は改善せず,不穏と高二酸化炭素血症認めた.気管挿管を考慮したが侵襲性が高いため,50mg/kgのMgSO4を20分かけて点滴静注した.速やかに不穏の軽快と呼吸状態の改善が得られ,投与開始1時間後に二酸化炭素分圧,心拍数,呼吸数はそれぞれ54.9mmHgから46.5 mmHg,157回/分から126回/分,48回/分から40回/分に低下した.MgSO4の有害事象は認めなかった.MgSO4は気管支平滑筋細胞からのカルシウムの駆出を増加させ,平滑筋の収縮を抑制させると考えられている.MgSO4は即効性のある薬剤として有効である可能性があり,特に治療抵抗性で気管挿管を考慮する症例にそれを回避する目的で投与する価値があると考える.
- 著者
- 大林 正史 Masafumi OBAYASHI
- 出版者
- 鳴門教育大学
- 雑誌
- 鳴門教育大学研究紀要 鳴門教育大学 編 (ISSN:18807194)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.120-134, 2020
The purpose of this study is to clarify the current status of learning support as a measure to prevent children's poverty in A prefecture in Chugoku and Shikoku region, and to consider the tasks. In this study, interviews and observations were conducted. As a result, the following four points were raised regarding the tasks of learning support as measures for poverty of children in A prefecture. The first task is that the A Prefecture Board of Education works together with the welfare department to think the community future cram school and "children's learning support project" as a child poverty countermeasure. The second task is to establish a universal system in mountainous areas, and a selective system based on academic ability in plain and urban areas. The third task is to clarify the division of roles to make the cooperation of actions related to learning support as a countermeasure for children's poverty work. The fourth issue is to reexamine the purpose of "Children's Learning Support Project" and "Regional Future School".
1 0 0 0 IR 幼児が楽しめるハンドベル奏法の一考察
- 著者
- 小林 由美子
- 出版者
- 東北女子短期大学 研究活動推進委員会(紀要・年報部会)
- 雑誌
- 東北女子短期大学紀要 (ISSN:24351385)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.18-24, 2020-03-19
ハンドベルは、カスタネット、鈴、タンバリンなどと同様に、幼児にとって持ちやすく奏でやすい楽器である。しかし、幼児用の楽譜を見ると、ハンドベルはメロディーを奏でるようになっているものがほとんどで、メロディーの音を何音か担当し、間違えないように緊張して待つのでは、折角のハンドベルを楽しむことができないように思う。私は、幼児が無理なくハンドベルを楽しむためのやり方を試行錯誤し、全体を2 つか3 つのグループに分け、各グループにⅠ、Ⅳ、Ⅴ 7 の和音のどれかを担当させ、奏でるときに、ぬいぐるみなどを使って合図をすることにより、大勢で奏でる連帯感も生まれ、余裕をもってハンドベルの持つ華やかな響きを楽しむことができるように思った。又、音域を広げたり、同じ和音を分散して奏でるなど、身近な曲を使って楽しんで行えたやり方を書かせていただいた。
1 0 0 0 OA 小笠原硫黄島の異状隆起と最近の火山現象について
- 著者
- 森本 良平 小坂 丈予 羽鳥 徳太郎 井筒屋 貞勝 浦部 和順 高橋 春男 岡田 義光 平林 順一 伊佐 喬三 磯部 宏
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.255-283, 1968-10-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3 3
Unusual uplift of the land was found about an insular active volcano Iwo-jima, Ogasawara archipelago, 1, 200 km south of Tokyo. Remarkable retreat of shore line was revealed by reviewing topographic maps and aerophotographs of the island. Some upward movements of the island are to be one of the most principal reasons of the retreat. As the clear evidences of the upheaval of the land, following phenomena were observed by the writers who investigated the island five times from 4th July to 23rd August 1968 : a) Sunken vessels and a landing craft have emerged on the western coastal beach of the island : b) Faults and cracks appeared on the abandoned run-way of the former Japanese Navy in the central part of the island ; c) Coastal reef emerged on the sea to connect off shore islet with the island ; d) New coastal terraces were formed on the sand beaches ; e) Fresh living corals were exposed on the sea.Results of the investigations are enumerated as follows : 1) About 8 m upheaval of the land since 1953-4 was revealed by levelling survey at the western coast of the island. 2) Amount of uplift observed on the above-mentioned run-way is smaller in its central part than in both terminals, maximum vertical displacement of the fault being 3 m. 3) Tide gauge installed at the western rocky coastrecorded slight relative down of sea level but further observation should be continued without disturbance by typhoon to obtain more reliable data. 4) No expected microseisms were recorded on the high sensitive electro-magnetic seismographs except 2 or 3 per day. 5) Temperature of the fumarolic gases were 95-123°C, 10-25°C higher than that observed in 1935. In spite of the rise in temperature, gases of so called high temperature type, such as sulphur dioxide and halogens, were not contained. 6) Composition of the sublimates also accords with these results of chemical analyses of the gases. 7) Content of each main component element and its ratio to other ones is quite variable in several hot springs whose pH values range from 2.1 to 6.8. 8) Analcite was identified by X-ray and DTA analyses in the tuff forming Moto-yama, an eastern main flat cone of the island. Genetic condition of the mineral inferred from its chemical composition may indicate submarine eruption of the volcano. 9) Three weak zones were recognized by the present investigations in addition to the two ones previously reported by Tsuya. Thus three are arranged radially through the center of the eastern main cone and the two are arranged concentrically around the foot of the same cone. From these weak zones phreatic explosions are expected in future, if they occur. 10) Nothing more than mere weak phreatic explosion was recorded through the historic activity of the volcano. Artificial filling up of the vent, such as the pavement of the surface often causes the small explosion at fumarole. 11) Submarine eruption recently found at the sea bottom, about 5.4 km NNE of the South Sulphur Island, about 50 km south of the island did not occur recently but must have repeated rather stationarily.According to the present investigations, no remarkable magmatic explosion could be expected except those small phreatic ones, same one of which has often occurred on the island. Chemical composition of the gases does not indicate any approach of hot magma to the surface.
1 0 0 0 OA 閉塞性動脈硬化症 (ASO) に対する高濃度人工炭酸温水浴の効果
- 著者
- 前田 真治 林 久恵 横家 正樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.156-164, 2003 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 8
ASOによる潰瘍は予後不良で切断などに至る場合が多い。そこで、血管拡張作用を強力に持つ高濃度人工炭酸温水の効果について、温水浴時の足背部の末梢組織血流 (pBF) および経皮酸素分圧 (TCPO2) を足浴10分前より足浴終了後30分まで、1分間隔で連続測定した。対象は、潰瘍が進行期あるいは安定期にあり血行再建術が不能であった Fontaine II~IV度の49例 (平均66歳、男:女=20:29) である。この虚血肢に週3回以上人工炭酸温水足浴 (38℃、濃度1000ppm) を行った経過を写真評価した。1回の足浴時間は10分間とした。その結果、治癒傾向の乏しかった潰瘍の多くは短期間に縮小ないしは治癒した。pBFは前1.1±0.5ml/min/100gで、1分後より上昇し始め10分後には4.4±1.8まで上昇したが (p<.01)、終了直後に前値に戻った。一方、TCPO2は前40.7±18.3mmHgより10分後50.7±18.2と上昇し (p<.05)、終了20分後も50.3±20.8と前値を上同っていた (p<.01)。また、Fontaine 各群別でもpBF、TCPO2とも有意に上昇していた。以上より、潰瘍を合併した虚血肢には血行改善が必要であるが、血行再建術や運動療法が行えないような症例に対しても、38℃・1000ppmの高濃度人工炭酸温水は効果があり、良好な治療成績を期待することができることが示唆される。その機序は、血管拡張作用に伴う局所組織循環血液量増加と組織酸素分圧亢進など有意な末梢循環代謝改善作用によると思われる。この効果の Fontaine 分類別の比較からも、重症のIV群でも改善は少なくなるものの改善傾向が認められ、Fontaine 分類上の重症度に関らず有用と考えられる。人工炭酸温水足浴は、下腿動脈狭窄を有するASO症例に対する治療手段の一つとして期待されるものであり、今後の発展が望まれる。
1 0 0 0 OA 打鍵時の音量変化が体幹および上肢運動制御に及ぼす影響
- 著者
- 小林 章 国分 貴徳 村木 貴洋 金村 尚彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0560, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】ピアニストは長時間の反復練習により,腕や手に特殊な障害を抱えやすい。近年overuseに加え,身体のmisuseも障害発生の要因と指摘されている。しかし,overuseが前提となっているため,運動療法が処方されることは少ない。強い打鍵や遠位の鍵盤を打鍵するために体幹も大いに用いる。これまで体幹運動は着目されてきたが,手指と全身を同時に計測する難しさから,ピアノ演奏を全身運動として解析されてこなかった。本研究の目的は,ピアノ演奏を全身運動と捉え,強い打鍵時の体幹および上肢の演奏メカニズムを調査し,新たな理学療法領域拡大の基礎データを示すことである。【方法】[対象者]ピアノ未経験者5名[仕様機器]3次元動作解析VICON,YAMAHA Clavinova(CVP-30),DTM制作ソフトGarageband(Apple社)[課題]全て同じ音量(mf)で打鍵した(課題1)。次に3回に1回,fまたはffの強さで打鍵した(課題2,3)。テンポは全て120bpmとした。計測前に十分な練習時間を設けた。[解析方法]体幹傾斜角,上肢関節角度,手指関節角度を計測した。解析区間は中指MCPマーカーが最も高くなった時点から鍵盤マーカーが最も沈み込んだ点。各角度が指先への変位量への寄与度を表すdegree of contribution(以下,DOC)と打鍵の運動力学的効率性を表すkeystroke efficiency(以下,η)を算出した。[統計処理]各関節のDOC,ηに対しFriedman検定を実施し,多重比較にはWilcoxonの符合順位検定を実施した。【結果】[DOC]体幹のDOCにはいずれの課題においても有意な差は認められなかった。同音量での打鍵動作の繰り返し(課題1)と比較して,強い打鍵が求められると(課題2・3),肩および肘関節のDOCは有意に低下したが(p<.01),その前後の打鍵では有意に増加した(p<.01)。一方で,手関節より遠位関節のDOCは有意に増加したが(p<.01),その前後の打鍵では有意に低下した(p<.01)。[η]課題1と比較して,課題2・3のηは有意に増加したが(p<.01),その前後の打鍵では有意に低下した(p<.01)。【結論】ピアノ未経験者は上肢を主体とした打鍵であり,体幹運動の寄与は少なかった。しかし,ピアノ未経験者は肩・肘関節による手の上下運動を手・手指関節伸展運動によって代償する戦略と手指と鍵盤接触角度を大きくつけた打鍵戦略の2つを使い分けて打鍵することが明らかになった。また,強い打鍵の前後では前者の戦略がより顕著になり,打鍵効率性が低下した。このことからピアノ未経験者は2つの打鍵戦略間の移行がスムーズでなかったことが示唆された。特に打鍵中のDIP関節の過剰な伸展はbreaking-in of the nail joinと呼ばれる。これは音量やテンポの制御に有害であるとされ,手指への機械的ストレスが増大した可能性がある。今後,ピアニストの演奏を全身動作として捉えた研究により演奏メカニズムが解明されていけば,音楽家の治療に応用でき,新たな理学療法分野を広げる可能性がある。
1 0 0 0 OA 横浜,イノベーション都市のこれから
- 著者
- 小林 巌生
- 出版者
- サービス学会
- 雑誌
- サービソロジー (ISSN:21885362)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.3-10, 2021-03-24 (Released:2021-04-21)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 両側外側滑膜ヒダ障害疑いの症例に対し理学療法が有効であった症例
- 著者
- 布施 彩音 今田 康大 大野 智貴 若林 敏行
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.H2-105_2-H2-105_2, 2019
<p>【症例紹介】</p><p> 症例は年齢17歳、性別男性、部活動はバレーボールであった。病歴は3年程前より明らかな誘因なく、両膝関節外側に疼痛が出現、他院にて成長痛疑いで経過観察していた。運動中の痛みは顕著ではなかったことから運動を継続していたが、1年程前から疼痛頻度が増加し、運動後には歩けない程の痛みを呈すようになった為、当院を受診した。主訴は「膝を曲げ伸ばしすると外側に痛みが出る」、Hopeは「日常生活での痛みをなくしたい。6ヵ月後の引退試合に痛みなく出場したい」であった。</p><p>【評価とリーズニング】</p><p>医師診察としてMRIにて半月板損傷、靭帯損傷、軟骨損傷は除外され、腸脛靭帯炎の診断で理学療法開始となった。初回介入時、両側の膝蓋骨下極から傍外側にかけて腫脹、熱感が認められたが、膝蓋跳動は陰性であった。非荷重位での膝関節完全伸展位から約30°屈曲時に膝蓋骨の傍外側でクリックと同時に疼痛を認め、同部位の圧痛も確認できた。Active、Passive両者ともクリック、疼痛程度に変化はないが、上記以外の角度では症状は見られず、安静時痛、夜間痛も認めなかった。部活後、長距離歩行後(1km程度)など運動後のNRS(右/左)は10/10と著明な疼痛を訴えていた。右側に関しては歩行時にひっかかり感も訴えており、日常生活にも支障があった。また疼痛の出現頻度も右側に多く認められた。静的アライメントは大腿、下腿外旋位でわずかに膝内反位、膝蓋骨外上方偏位、外側傾斜を呈しており、膝蓋骨の内下方への動きが制限されていた。膝関節の可動域は屈曲130°/135°、伸展−5°/-5°でエンドフィールは軟部組織性であった。Grinding test、Ober test、Ely test、SLRは全テスト両側で陽性となったが左右差は無かった。</p><p>クリニカルリーズニング:外側滑膜ヒダ障害と診断された先行報告と今回の症状、疼痛部位が類似していたことから、クリックは外側滑膜ヒダが膝蓋大腿関節に挟み込まれることで生じており、これが疼痛を惹起している原因だと考えた。さらに膝蓋骨が外上方偏位、外方傾斜を呈していることで膝蓋骨傍外側に、より圧縮ストレスが生じていると考え、徒手的に膝蓋骨を内下方へ誘導したところ、わずかにクリックが減少した。これらのことから膝蓋骨のマルアライメント修正することにより症状を軽減できるのではないかと考えた。</p><p>【介入内容および結果】</p><p>介入は週1回の外来理学療法を実施した。治療介入はまず疼痛誘発の原因と思われた膝蓋骨のマルアライメントを中心に理学療法を実施した。具体的には膝蓋骨傍外側を中心に超音波を実施し、炎症が強い時期には非温熱にて炎症緩和を、炎症緩和後は温熱にて膝蓋骨周辺組織の伸張性の改善を図った。その上で外側膝蓋支帯、膝蓋下脂肪体周囲のリリース、膝蓋骨のモビライゼーション、腸脛靭帯-外側広筋間のリリースを実施し膝蓋骨の外側傾斜、外方偏位の修正、内下方への可動域制限の改善を図った。また膝蓋骨の内下方への誘導を目的にテーピングを貼付したところ、歩行時の疼痛がわずかに減少したことから、日常生活、部活の際に貼付するよう指示した。その結果、介入から2ヵ月程で膝蓋骨外側の腫脹が軽減し、クリック、疼痛の程度も軽減した。介入開始から4か月ではNRS(右/左)は6/1となり、運動後の疼痛出現頻度も減少した。過度な運動後は疼痛が出現するものの、直後のアイシング、セルフケアにより疼痛自制内でコントロール可能となった。本人の希望であった引退試合に出場することもでき、日常生活にもほぼ支障がなくなったため、外来理学療法終了とした。</p><p>【結論】</p><p>先行報告において外側滑膜ヒダ障害は、膝関節30〜75°で膝蓋骨傍外側にクリックを伴う疼痛が出現するとされており、本症例の症状と類似していた。外側滑膜ヒダ障害は非常に稀であり、過去に保存療法で症状が軽減した報告は見当たらない。診断には関節鏡検査でのみ確定診断が得られるが、本人が希望しなかったため今回確定診断には至らなかった。しかし膝蓋骨のマルアライメントを修正したことで症状が軽減したことから、外側滑膜ヒダ障害と疑われる症例に対し理学療法の有効性が示された。</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>ヘルシンキ宣言に従い対象者には口頭及び文書で同意を得た。</p>
1 0 0 0 OA EMアルゴリズムを用いた土地所有形態選択問題のモデル化
- 著者
- 小林 里瑳 羽藤 英二
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.1245-1252, 2019-10-25 (Released:2019-11-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
本研究では,近代地方都市における界隈形成のメカニズム解明に向けて,土地所有形態選択問題として統計的モデルを用いた全く新たな都市形成史分析手法の提案を試みた.モデル構築において,所有筆=土地とその所有形態の同時選択確率を記述可能なCNL型の離散選択モデルを提案し,所有形態の選択に関して地主の態度の異質性を仮定した潜在クラスモデルを導入した.パラメータ推定には,隠れ変数を含む選択確率の対数尤度関数最大化問題の求解に適していることから、機械学習の代表的な手法の一つであるEMアルゴリズムを用いた.道後温泉本館周辺を対象に,旧土地台帳と付属図という近代史料をモデル推定可能な形式に変換する方法提案を行い,集積や継承,撤退といった近代地方都市の土地所有の変容の実態解析が可能なデータベース構築に成功した.さらに,非集計分析と提案したモデルを用いてパラメータ推定を行うことで,近代地方都市の地主の土地所有形態の選択に異質性があり,時間の経過とともに地租や立地条件といった要因が土地所有形態の選択に及ぼす影響が大きく変容していることを統計的に示すことができた.
1 0 0 0 IR 健常児男女のADHD RSを用いた行動比較
- 著者
- 中村 仁志 林 隆 木戸 久美子 澄川 桂子
- 出版者
- 山口県立大学看護学部
- 雑誌
- 山口県立大学看護学部紀要 (ISSN:13430904)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.13-18, 2004
AD/HDの発症比率には性差があり男子に多いとされている。今回、健常幼稚園児を対象として、その行動をADHD-RS-IV-Jの項目を用いて性差について検討した。さらに保護者の捉える子どもの特徴とADHD RS-IV-Jのどの項目の行動と関係しているのか比較検討した。 平成14年11月、Y県H幼稚園の保護者にアンケートを行い、ポジティブな特徴評価として"活発である"、"リーダータイプ"を、ネガティブな特徴評価として"拗ねやすい"、"育てにくい"を聞いた上でADHD-RS-IV-Jの回答を求めた。
1 0 0 0 IR 育児参加は父親にどのような影響を与えるか : 多胎児の父親と単胎児の父親との比較
- 著者
- 林 知里 岡本 愛花 神林 優花 花田 佳奈 渡邊 えみ 中島 美繪子 Chisato Hayashi Okamoto Aika Kanbayashi Yuka Hanada Kana Watanabe Emi Nakashima Mieko 元千里金蘭大学 看護学部 現大阪大学大学院 医学系研究科附属ツインリサーチセンター 市立豊中病院 淀川キリスト病院 市立池田病院 三木市民病院 元千里金蘭大学 看護学部
- 出版者
- 千里金蘭大学
- 雑誌
- 千里金蘭大学紀要 (ISSN:13496859)
- 巻号頁・発行日
- pp.67-75, 2012
近年、男女共同参画社会の実現、少子化問題、子どもの社会性の発達や父親自身の人格的成長、QOLやワーク・ライフ・バランスなどとの関連において、父親の育児参加が注目されている。多胎児の父親は単胎児の父親より積極的に育児参加するものが多いとの報告があるが、育児参加が父親に与える影響について多胎児と単胎児の父親を比較した調査はない。そこで、本研究では、多胎児と単胎児の父親の「子育て観・次世代育成観」「母性神話」「仕事観」「子ども観」を調査した。ツインマザースクラブの会員1016名に自己記入式アンケートを郵送、211名の父親から回答を得た(回収率20.8%)。また、比較群として、小中一貫校の児童・生徒および大学生の単胎児の父親300名にアンケート調査を実施し、101名から回答を得た(回収率33.7%)。結果、「子どもが3歳になるまで、母親は育児に専念するほうがよい」「子どもを出産した後は、母親は仕事をやめたほうがよい」といった、いわゆる「三歳児神話」や「母性神話」については、多胎児の父親は単胎児の父親と比較して反対側が有意に多かった。「子育ては自分の自由な時間を奪う」「仕事は自分の自由な時間を奪う」「子育て中は、勤務時間を自分で調整できる方がよい」は多胎児の父親で賛成側が有意に多く、「育児休暇をとると昇進にひびく」は、多胎児の父親で反対側が有意に多かった。ふたごの父親は、単胎児の父親と比較して積極的に育児参加している者が多く、育児の担い手として実質的に育児に関わる経験が母性神話に対する価値観や子育て観、仕事観に影響している可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 第8章 : 天津のなかの日本社会
1 0 0 0 IR フォース湾とその沿岸域の社会経済史--フォース・ポーツ・オーソリティの機能と役割
- 著者
- 小林 照夫
- 出版者
- 関東学院大学[文学部]人文学会
- 雑誌
- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)
- 巻号頁・発行日
- no.111, pp.3-23, 2007
本稿の考察は、複数の港を組織して成立したフォース・ポーツ・オーソリティ(the Forth Ports Authority)の事例が、東京湾諸港の問題としてのポート・オーソリティ論だけではなく、日本の多くの港の経営を考えるうえでの参考事例になるのではないかと言うことで言及した。そのための考察の手順としては、スコットランド産業革命期までの交易の中心であったフォース湾沿岸域の産業社会を、社会経済史の手法で回顧・展望する中で、かつての重要港湾リース(Leith)やグランジマウス(Grangemouth)をはじめとした現在のフォース・ポート・オーソリティを構成する諸港、グラントン(Granton)、バァントアイランド(Burntisland)、カーコーディ(Kirkcaldy)、メスィル(Methil)の史的意義を論じることにした。そうした考察を通して、フォース湾に所在するそれぞれの港とフォース・ポーツ・オーソリティの機能と役割について位置づける。
1 0 0 0 OA 回復期リハビリテーション病棟の脳卒中患者における「家事再開予測モデル」の外的妥当性
- 著者
- 小林 竜 小林 法一
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.608-615, 2021-10-15 (Released:2021-10-15)
- 参考文献数
- 16
回復期リハビリテーション病棟の脳卒中患者46名を対象に「家事再開予測モデル」の外的妥当性を検証した.回復期病棟退院時に,家事再開予測モデルを用いて退院後の家事6項目(食事の用意,食事の後片付け,洗濯,掃除や整頓,力仕事,買い物)の再開状況を予測した.退院3ヵ月後にフォローアップを行い,実際の家事再開状況を調査した.家事再開予測モデルは項目ごとに判別的中率を算出し,ROC曲線のAUCにてモデルの予測能を評価した.結果,各家事項目における判別的中率は75.0~82.2%,AUCは0.71~0.86であった.本研究により,家事再開予測モデルは中等度の予測能を有していることが示された.
1 0 0 0 コミュニケーション円滑化のためのアバター選択支援手法の検討
1 0 0 0 OA Muramyl Dipeptide (MDP) 誘導体の合成と免疫アジュバント活性
- 著者
- 小林 榮 藤野 政彦
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.395-407, 1981-05-01 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 56
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine (MDP), a minimal immunologically active constituent of cell-wall peptidoglycan, has attracted much attention since its discovery in 1974. This review deals with recent progress in the MDP field.
1 0 0 0 8131 シェア居住におけるストック活用の可能性に関する研究 : ファミリー向け住宅を利用したシェア居住の促進に向けて(選抜梗概,住宅ストック(3),オーガナイズドセッション,建築経済・住宅問題)
- 著者
- 丁 志映 大森 一樹 小林 秀樹
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-1, 都市計画, 建築経済・住宅問題 (ISSN:13414534)
- 巻号頁・発行日
- no.2008, pp.1401-1404, 2008-07-20
1 0 0 0 センチピードグラスの生育と栽培法
- 著者
- 広田 秀憲 小林 正義 関東 良公 上田 一之
- 出版者
- 日本芝草学会
- 雑誌
- 芝草研究 (ISSN:02858800)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.125-130, 1987
- 被引用文献数
- 1
著者らの観察ではセンチピードグラスは新潟市の気象環境の下でも10数年は生きるものと考えられ, 耐寒性はバーミュダグラスとほぼ同じ程度に強く, 冬の極値が12°F (-11℃) 以上の気温で生育する。晩秋の霜枯れしたあと生育を停止する。年平均気温13℃の地域を北限としているため, 限界地帯では年によりかなり冬枯れするが, すべて枯死することはなく春になれば再び旺盛に生育を始める。<BR>ほふく茎は2次茎も3次茎も太く, 葉幅も3~4mmと芝草の中では広い方である。芝地としては管理しやすい草種である。病虫害にも強い。早春と秋にモグラの害を蒙ることがありモグレスなどの忌避剤をまく必要がある。<BR>本草種の用途としては, ゴルフ場のラフ, 公園の植込みの間, 運動場のフィールドや観覧席, あるいは道路, 堤塘などにおける平面や斜面の緑化などに普及性が高い。ほふく茎のもつ被覆力, 各節からの旺盛な発根力をもつと種々の方面に活用したいものである。<BR>なお, 本草種は飼料としての価値はあまり高くないとみられているが, 平準的な季節生産性を利用して兎, 羊など中小動物による放牧利用の可能性がまだ残されている。