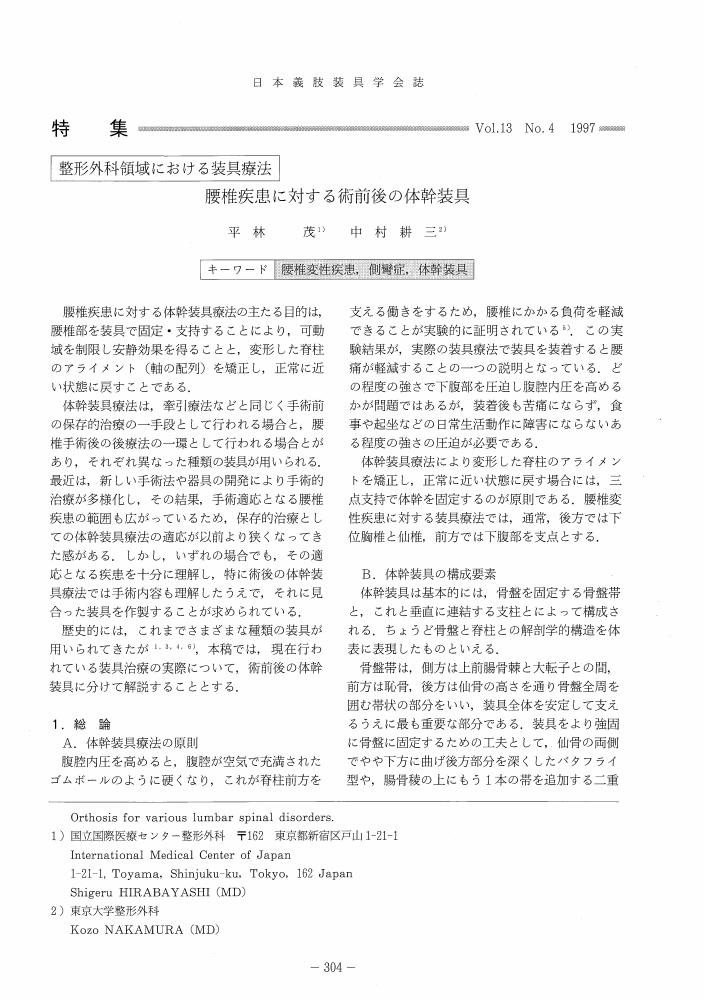1 0 0 0 孝経喪親章不読の慣行について
- 著者
- 林 秀一
- 出版者
- 岡山大学法文学部
- 雑誌
- 岡山大学法文学部学術紀要 (ISSN:04713990)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.1-7, 1964-03
1 0 0 0 IR 教育思想に向けたSpiritual Exercise : 「生き方としての哲学」の再考へ
- 著者
- 林 洋輔
- 出版者
- 大阪教育大学
- 雑誌
- 大阪教育大学紀要. 人文社会科学・自然科学 = Memoirs of Osaka Kyoiku University (ISSN:24329622)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.71-79, 2020-02
本論文においては,20世紀フランスの哲学者・哲学史家であるピエール・アド(1922-2010)が中心となって提唱された「生き方としての哲学Philosophy as a Way of Life」--その実質は「精神の修練Spiritual Exercise」--が教育思想として捉え直されることの可能性が明らかにされた。アドにおいて,哲学とは「生き方」およびその実現である。彼によれば,哲学を学ぶことは生き方を選ぶことと同義である。というのもアドが論じた古代哲学において,任意の生き方を選ぶことは同時に任意の「学派」に入門することを意味しており,その学派で学ばれるのが「精神の修練」と呼ばれるエクササイズだからである。各学派によってその実質は異なるものの,「精神の修練」では自らの生を変容させる知恵の獲得が目指されている。それゆえ「哲学の生を歩むこと」とは自らの完全な変容を期して知恵を求める営みである。アドの議論を精査していくことにより,ある生き方を決意した者が入門した学派において哲学者より「精神の修練」を通じて自らの生き方を創る,との過程を確認できる。それゆえ,学習者が哲学者となる過程は「精神の進歩」の方法とも捉えうるものであって,その進歩において学習者は自らを「精神の修練」によって教育する。「精神の修練」とは学習者が任意の学派において哲学者により手解きを受け,獲得された知恵の内面化によって変容を期するものである。この観点において「精神の修練」とは,学習者がそれによって哲学に拠る生き方を創る点において,教育思想と密接なつながりを有することが明らかとなる。
1 0 0 0 早期関節リウマチにおける手指・手首関節エコーの特徴と有用性
- 著者
- 高島 千絵 平田 祐子 平林 弘美 増田 友子
- 出版者
- 一般社団法人 日本超音波検査学会
- 雑誌
- 超音波検査技術抄録集
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.234, 2010
1 0 0 0 IR 卵膜外リバノール液注入に依る姙娠中絶法
1 0 0 0 IR M-3SII 型ロケットにおけるテレメータ・コマンド・集中電源
- 著者
- 林 友直 横山 幸嗣 井上 浩三郎 橋本 正之 河端 征彦 大西 晃 大島 勉 加藤 輝雄 瀬尾 基治 日高 正規
- 出版者
- 宇宙科学研究所
- 雑誌
- 宇宙科学研究所報告. 特集: M-3SII型ロケット(1号機から3号機まで)(第1巻) (ISSN:02859920)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.141-171, 1991-06
M-3SII型ロケットでは, M-3S型と異なり, 新たに装備されたサブブースタSB-735の性能計測等のために, サブブースタにテレメータ送信機を搭載した。また, サブブースタの分離状況を画像伝送するため第2段計器部に画像伝送用テレメータ送信機を搭載し, さらに3号機では新たに開発された第3段モータの性能計測のために, 第3段計器部を設けてテレメータ送信機を搭載する等の大幅なシステム変更がなされている。搭載テレメータ送信機で新規に開発されたのは, 画像伝送用テレメータ送信機で, M-3SII型ロケットの試験機であるST-735ロケットで予備試験を行い, 地上追尾系を含めて総合的に性能の確認を行ったのち, M-3SII型1号機から本格的に搭載された。地上系では, 第2段モータの燃焼ガスが通信回線に大きな障害をもたらす等の問題が生じ, 2号機から高利得の18mパラボラアンテナを使用し, 従来の高利得16素子アンテナに対する冗長系を構成した。また, 第3段目の機体振動計測データ等を伝送していた900MHz帯テレメータは3号機から送信周波数がS帯へ変更されたのに伴い, 地上受信アンテナとしてはこれまで使用していた3mφパラボラアンテナをやめ衛星追跡用10mφパラボラアンテナを使用する事となった。データ処理系では, 計算機によるデータ処理が本格化し, 姿勢制御系, 計測系, テレメータ系のデータ処理のほか, 従来のACOSやRS系へのデータ伝送に加えM管制室へもデータ伝送が出来るようになった。コマンド系では, 1∿2号機は従来と同様であるが, 3号機から第1段の制御項目等を増やす必要からトーン周波数を増し, コマンド項目を3項目から6項目にし, さらに操作上の安全性を向上させた。集中電源は, 充電効率や管理の点等から見直しをはかり, 従来M-3S型で用いられていた酸化銀亜鉛蓄電池に替わりニッケルカドミウム蓄電池が使用されるようになった。資料番号: SA0167008000
1 0 0 0 OA 遷移金属窒素錯体を利用した触媒的窒素固定法の開発
- 著者
- 西林 仁昭
- 出版者
- 錯体化学会
- 雑誌
- Bulletin of Japan Society of Coordination Chemistry (ISSN:18826954)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.49-55, 2018-05-31 (Released:2018-08-24)
- 参考文献数
- 22
This paper describes our recent progress in catalytic nitrogen fixation by using transition metal-dinitrogen complexes as catalysts. Novel reaction systems for the catalytic transformation of molecular dinitrogen into ammonia and hydrazine undermild reaction conditions have been achieved by the molybdenum-, iron-, cobalt-, and vanadium-dinitrogen complexes as catalysts. New findings presented in this paper may provide a new approach to the development of economical nitrogen fixation in place of energy-consuming Haber-Bosch process.
1 0 0 0 スカビオ-サの生育に及ぼす播種期・長日及び温度処理の影響
- 著者
- 谷川 孝弘 小林 泰生 坂井 康弘
- 出版者
- [福岡県農業総合試験場]
- 雑誌
- 福岡県農業総合試験場研究報告 B(園芸) (ISSN:02863030)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.p29-34, 1994-02
1 0 0 0 OA 交感神経遮断剤(βブロッカー)が心理面及び身体面に及ぼす影響(原著)
- 著者
- 中林 愛恵 今岡 佐織 槇原 貴子 鈴宮 淳司 廣瀬 昌博
- 出版者
- 日本診療情報管理学会
- 雑誌
- 診療情報管理 : 日本診療情報管理学会誌 (ISSN:18837972)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.37-41, 2020-10
1 0 0 0 2階建てオープンバスから見た都市景観の分析
- 著者
- 飯田 マリ 大澤 義明 小林 隆史
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 = Papers on city planning (ISSN:1348284X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.385-390, 2011-10-25
- 参考文献数
- 10
世界の観光地で活躍している2階建てオープンバスは、屋根がなく、視点が高い場所に位置する特徴から、歩行や自動車とは異なった景色を楽しむことができる。本研究では、様々な都市で適用できるように、数理的モデルを用いて、2階建てオープンバスからの景観評価を次の二つの観点を用いて行った:(1)街並み全体を「面」で眺め、その構成要素を徒歩の場合と比較することで、どれだけ「非日常的な景色」が見られるか。(2)東京スカイツリーなど街並みの中の「点」に注目し、バス移動に伴い変化する視線方向を分析することで、首振りによる「視対象の見やすさ」がどう変化するか。主要な分析結果は以下の2つである:(1)高い視点場を持つ2階建てオープンバスは走行車線を工夫することで、効果的な非日常的な景色を演出できる。(2)進行方向の決まっているシークエンス景観であることから、カーブでの首振りが観光スポットへの注目の妨げになる。以上より、複数車線を持つ、カーブの少ない観光都市は2階建てオープンバスの導入に適しているといえる。
- 著者
- 小林 好和
- 出版者
- 札幌学院大学人文学会
- 雑誌
- 札幌学院大学人文学会紀要 (ISSN:09163166)
- 巻号頁・発行日
- no.83, pp.123-136, 2008-03
物証文の理解における中心的課題の一つとして,前向き推論,逆向き推論を合むような読み手の推論過程があげられる。本研究では,推論をテクストから省かれた重要な部分的情報を読み手が既有情報をもとに予期することと仮定する。本研究の目的は物語作品『ごんぎつね』を用い,その「一次読み」の過程における推論の特質を検討することである。国語科教材であるこの作品を用いた調査を小学校3年生141名に対して実施した。そのうち,この物語を初めて読む児童は79名(56%)であり,本研究は彼らに限定し分析を行なった。方法として物語の結末を削除したテクストを用い,彼らの理解内容,物語の結末の作証(予期推論),彼らの推論の物語展開への統合に関するQ/A法によるプロトコルデータを得た。本研究の結果から以下のことが示唆された。この作品の"一次読み"において,3年生では主人公(ごん)の視点に固定して読もうとすること,したがって「同情の枠組み」をもとにしてこの理解を構成する傾向が示された。その上で,彼らの多くが主人公(ごん)はもう一人の登場人物(兵十)と最後には仲良くなるという予期推論をおこなった。したがって,原文の結末(兵十がくりを待ってきたごんを撃つ)を彼らが構成した理解に直ちに統合することは容易ではなかった。そこで授業場面においては,「兵十はごんをどうみていたか」といった他の登場人物(兵十)の視点をとるような読みの方略を示す必要があると推察された。
1 0 0 0 OA マイクロフォンアレイとロボット聴覚を用いた野鳥の歌行動観測と生態理解への試み
本研究は、マイクロフォンアレイとロボット聴覚を用いて鳥類の歌コミュニケーションを自動観測し、歌の種類と位置情報から鳥個体間で行われる歌を介した相互作用を明らかにすること、そしてその知見を野鳥の生態理解へ応用することを目的とした。当該システムの活用により、森林と草原という異なった自然環境下で、これまでの観測手法では容易に得られなかった位置情報付きの音声データの収集が実現した。さらに鳥類の音声データの収集やその解析効率、再現検証性が向上した。またこれらの音声データの解析により、観測対象種の個体間において、各個体が同時に鳴くことを避ける時間的重複回避行動が明らかになった。
1 0 0 0 OA 三環系抗うつ薬中毒と急性呼吸不全
- 著者
- 林田 敬 藤島 清太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.172-175, 2011-04-01 (Released:2011-10-05)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 神経難病専門病院における栄養サポートチームの取り組みと今後の栄養療法の展望について
- 著者
- 木田 耕太 林 健太郎 清水 俊夫
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.260-263, 2020 (Released:2020-04-24)
- 参考文献数
- 15
神経変性疾患を中心とした神経難病患者の栄養障害は疾患および嚥下障害,呼吸障害,運動麻痺,筋強剛,不随意運動,運動失調など種々の症状や疾患およびその病期によるエネルギー代謝の変容などのため患者ごとに多様である.神経難病患者の栄養療法には多専門職種の知識・経験の共有に基づいた個々の患者に対するオーダーメイドのサポートが必要である.しかしながら外科・内科領域と比して,脳神経内科領域では栄養管理のエビデンスの蓄積は未だ十分でない.神経難病専門病院における栄養サポートチーム(nutrition support team; NST)の活動,および活動を通じて得られた知見について述べる.
1 0 0 0 OA 家庭飼育犬の洗浄頻度に関する衛生学的研究
- 著者
- 久永 晃資 岩田 剛敏 池内 隆 五十嵐 章紀 足立 邦明 林谷 秀樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.54-57, 2004-01-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 9
生活空間を共有する人と犬が快適に生活するために, どのくらいの頻度で犬を洗浄したらよいかを検討するために, 犬の被毛の脂質の成分や量を調べるとともに, これらが洗浄前後でどのように変化するかを経時的に観察した. その結果, 犬被毛の脂質は脂肪酸, コレステロールおよびステロールエステル, ワックスエステル, グリセロールエステルなどのエステル類で構成されており, 特にエステル類は脂質の80%以上を占めていた. また, 犬被毛の脂質量は洗浄直後に洗浄前の約60%にまで減少したが, 72時間後には洗浄前のレベルまで回復した. そして, 洗浄後72時間が過ぎる頃から動物臭が感じられるようになった. これらの結果から, 衛生的な観点からみると, 室内犬の洗浄は3~4日に1回くらいの割合で行うことが適当と考えられる.
1 0 0 0 OA 座談会 : SFにおけるAI(<特集>SFとAI)
- 著者
- 東野 司 森岡 浩之 林 譲治 松原 仁 大澤 博隆 栗原 聡 山下 倫央
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.5, pp.534-541, 2014-09-01 (Released:2020-09-29)
1 0 0 0 OA 整形外科領域における装具療法 腰椎疾患に対する術前後の体幹装具
1 0 0 0 光変調O/W用ディスクの成膜条件検討 : 画像情報記録
- 著者
- 川野 敏史 橋本 高志 小林 喜光
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.15, pp.13-17, 1992