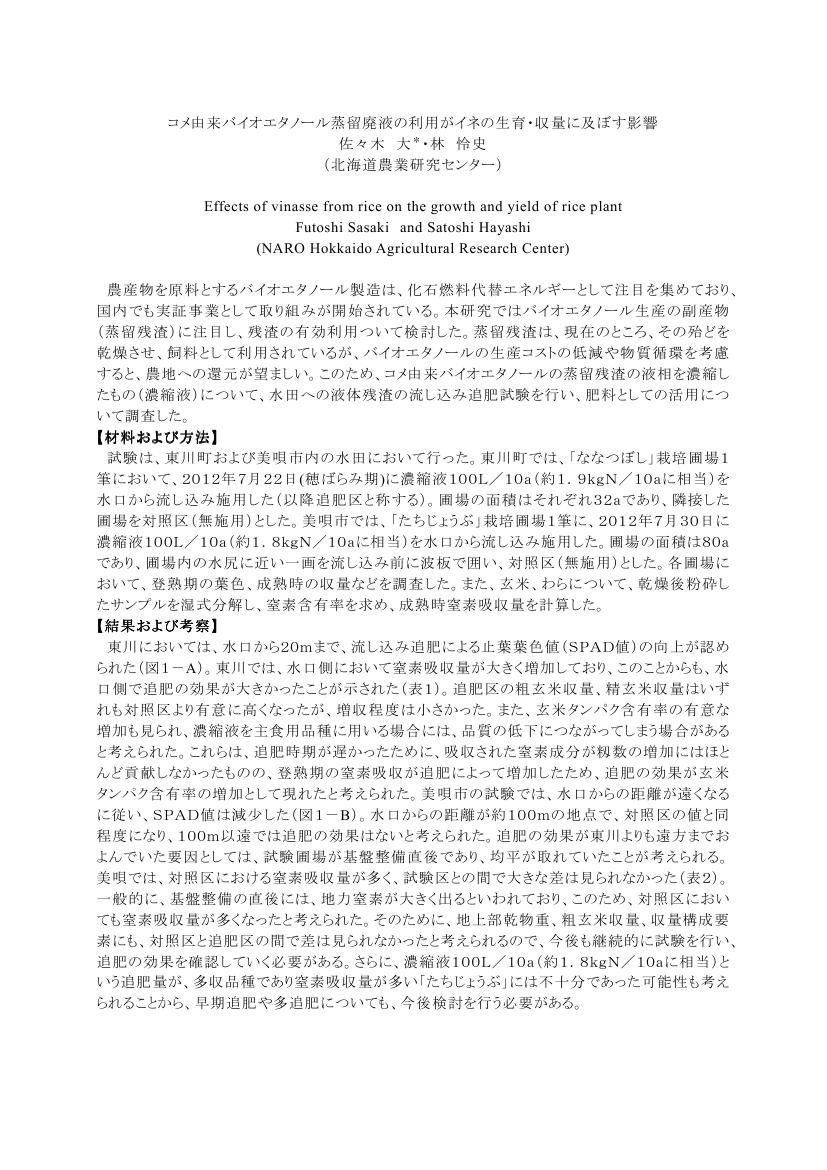1 0 0 0 IR ミツバチの連合学習に対する電磁波・変動磁場の影響
- 著者
- 畑中 恒夫 小林 史尚 宮崎 隼人 小林 史尚 コバヤシ フミナオ Kobayashi Fuminao 宮崎 隼人 ミヤザキ ハヤト Miyazaki Hayato
- 出版者
- 千葉大学教育学部
- 雑誌
- 千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:13482084)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.349-353, 2008-03
- 被引用文献数
- 3
電化生活が進むにつれ,そこから発生する電磁波にさらされる機会が増え,電磁波の影響が心配されている。この電磁波が動物の学習行動に影響を及ぼす例が報告されているが,矛盾する報告もある。そこで,下等な昆虫のミツバチを用い,単純な連合学習である花の匂いと,蜜を吸う吻伸展反射の条件づけを行い,電磁波の影響を調べた。市販のマウス駆除器から出る複合された低周波の電磁波に曝露すると,連合学習の学習率が低下した。超低周波の電磁波は磁場成分が生体に作用すると考えられるので,50Hz,200Hz,300Hzの変動磁場に曝露すると,200Hzの変動磁場で学習率が低下し,超低周波電磁波は学習を阻害することがミツバチでも実証された。一方,定常強磁場下では学習率が増加し,磁場や超低周波電磁場はミツバチの磁気受容器を介して学習行動に影響する可能性が示唆された。Several studies performed in rodents have suggested that spatial learning can be impaired by electromagnetic field exposure, but some inconsistent results have been reported. So, we used lower order insect, honeybees, and studied the effects of electromagnetic fields on a simple and typical association learning of flower odor with proboscis extension reflex to nectar. Learning performance was impaired by low frequency complex electromagnetic fields radiated from a rodent control device. Then we exposed honeybees to 50Hz, 200Hz or 300Hz AC magnetic fields during their trainings. 200Hz magnetic field decreased learning proficiency. On the other hand, a strong and constant magnetic field enhanced the learning performance. These results indicate that extremely low frequency electromagnetic field can effect on the emotion of honeybees via magneto receptors.
1 0 0 0 OA 高年齢まで生存し得たファロー四徴症の2症例 : 日本循環器学会第105回関東甲信越地方会
- 著者
- 鬼倉 俊一郎 小林 良子 上松瀬 勝男 橋田 潤 坂元 一雄 石川 淳一 藤林 陽三 上松瀬 悠 瀬戸 博美 斉藤 文雄 梶原 長雄
- 出版者
- 社団法人日本循環器学会
- 雑誌
- Japanese circulation journal (ISSN:00471828)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, 1983-06-01
1 0 0 0 OA 恋愛における告白の状況と個人差 (シャイネス・社会的スキル) に関する研究
- 著者
- 栗林 克匡
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.11-19, 2002-03
1 0 0 0 OA コメ由来バイオエタノール蒸留廃液の利用がイネの生育・収量に及ぼす影響
- 著者
- 佐々木 大 林 怜史
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会講演会要旨集 第236回日本作物学会講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.210, 2013 (Released:2013-09-08)
- 著者
- 兒玉 隆之 中林 紘二
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.A3O1045-A3O1045, 2010
【目的】脳内神経活動に伴う局所脳血液供給量の増加が報告(Roy, 1890)されて以来、さまざまな脳機能イメージングを用いた脳機能評価が報告されてきた。中でも、近赤外線分光法(Near infrared spectroscopy; NIRS)は、局在神経活動と相関する毛細血管の血行動態変化を反映することが示唆されており(Yamamoto, 2002)、脳機能評価には非常に有用である。しかし、原理的に空間分解能が低く、脳深部を含めて脳機能の局在を細かく決定することには困難を要する。そこで本研究では、表情のもつ情動刺激による課題を用いて、精神生理学的指標である事象関連電位(ERPs)P300成分の脳波・脳磁場解析プログラムLORETA(Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography)による神経活動源推定と、NIRSによる脳血流量(Oxy-Hb)変動の同時測定を行い、時間的空間的解析による詳細な脳機能評価を試みる。<BR>【方法】対象は、健常ペイドボランティア20名(男性9名、女性11名、平均年齢27.5±4.1歳)。測定デザインはブロックデザインを用い、Taskを4回(Rest5回)施行した。Task時の課題には、情動的作用を有するヒトの「泣き顔」および「笑い顔」を標的刺激(出現率30%)、「中性」表情(出現率70%)をコントロールとした視覚オッドボール課題を用いた。測定方法は、脳波電極を国際10-20法に基づき、average referenceによりFp1・Fp2・F7・F3・Fz・F4・F8・T3・C3・Cz・C4・T4・T5・P3・Pz・P4・T6・O1・O2・Ozの部位へ装着、NIRS(日立メディコ社製, ETG-4000)も同法に基づきT3T4を端点とした3×5のプローブ(左右44チャンネル)を装着し、神経活動電位測定とOxy-Hb測定を同時に記録測定した。得られたERPsデータをもとに、Microstate segmentationによるP300成分出現時間域を算出後、LORETAによる課題施行時の脳神経活動解析を行い、Task時のOxy-Hb変動をNIRSにより検討した。<BR>【説明と同意】総ての被験者に、測定前に研究内容を説明し書面にて同意を得た。尚、本研究は久留米大学倫理委員会の承認を得て行った。<BR>【結果】Microstate segmentationの結果から、P300出現時間域は、「泣き顔」刺激課題時361~476ms、「笑い顔」刺激課題時367~482msとなり、LORETA解析では、「中性」、「笑い顔」に比べ「泣き顔」の刺激課題時に扁桃核、前頭前野で有意に高い神経活動を認めた(p<0.05)。さらに、NIRSにおいても、「笑い顔」より「泣き顔」の刺激課題時に前頭前野におけるOxy-Hbの増加を認めた。<BR>【考察】本研究は、脳機能を詳細に評価するため、LORETA解析による神経活動についての時間的空間的分解能と、NIRSによる脳血流動態の同時測定を行った。結果、前頭前野が担う認知機能は表情のもつ情動的作用の影響を受けることが強く示唆された。また、NIRSが脳神経系の電気的興奮過程を反映したものであることが明らかとなり、脳機能評価としてのマルチモーダルモニタリングとして有用であることが示唆された。<BR>【理学療法学研究としての意義】脳機能評価において、非侵襲的脳機能計測法であるLORETA解析とNIRSの同時測定は、詳細な時間的空間的解析の一助として理学療法学研究において有用であると考える。
- 著者
- 丸尾 はるみ 橋本 景子 下田 恵子 島貫 金男 中山 徹 山口 博明 椎貝 典子 内村 公昭 三ツ林 隆志 赤坂 徹 前田 和一 岡田 文寿 鈴木 五男
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7, pp.621-630, 1990
- 被引用文献数
- 7
1988年, 小児気管支喘息の長期予後と予後に影響する因子を明らかにするため, 1,592名(男1,038, 女554)を対象としてアンケート調査を行った.調査時の年齢は平均20歳(観察期間は平均12年)であり, 長期予後は緩解が75.6%, 軽快が18.2%, 不変が4.0%, 悪化が0.9%, 死亡が1.3%であった.発症年齢は平均2.7歳であり, 20年前の報告と比べて約1歳低年齢化していた.治癒年齢は男子が平均13.0歳, 女子が12.3歳であった.発症年齢が2歳以下, 発症から初診までの期間が10年以上, 初診時の重症例, 入院歴のある者, 食物アレルギーの有る者の緩解率は不良であった.食物アレルギーが有る者は喘息発症年齢が約1歳低く, 初診時の重症例, 乳児期湿疹のある例, 喘息以外のアレルギー疾患を2つ以上合併している例が多かった.このような乳児喘息例を難治性喘息のハイリスク児としてとらえ、綿密な指導と経過観察が必要であると考えられた.
- 著者
- 藪田 慎司 中田 兼介 千嶋 淳 藤井 啓 石川 慎也 刈屋 達也 川島 美生 小林 万里 小林 由美
- 出版者
- The Mammal Society of Japan
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.195-208, 2010-12-30
哺乳類の生態や行動に関する野外調査には,しばしば複数の調査者の協力が必要となる.多くの哺乳類は寿命が長く行動範囲が広いからである.このようなチーム研究を維持するには,各メンバーのデータを集約保存し,メンバー全員で共有するシステムが必要である.本論文では,ゼニガタアザラシ(<i>Phoca vitulina stejnegeri</i>)の個体識別調査を支援するために開発したシステムについて報告する.このシステムは2つのデータベースからなる.野外で撮影された写真を管理する写真データベースと,識別された個体についての情報や観察記録を管理する個体データベースである.システムはインターネット上に置かれ,メンバーは,どこからでも新しいデータを登録でき,また登録済みデータを研究のため利用することができる.近い将来,本システムは以下のような研究に貢献すると期待される.上陸場間の移動行動の研究,生活史パラメーター(齢別死亡率,出産間隔等)の推定,個体数の推定,社会構造の研究,等である.<br>
- 著者
- 宮林 常崇
- 出版者
- 高等教育研究会
- 雑誌
- 大学職員ジャーナル (ISSN:13429647)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.64-67, 2013
1 0 0 0 OA 新しい局面を迎えたオープンアクセスと日本のオープンアクセス義務化に向けて
- 著者
- 林 和弘
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター
- 雑誌
- 科学技術動向 (ISSN:13493663)
- 巻号頁・発行日
- no.142, pp.25-31, 2014-01 (Released:2014-02-13)
公的資金を得た研究成果に誰でもアクセスできるようにするオープンアクセス(OA)は、電子ジャーナルの進展と共に広がりを見せ、その存在感を増してきた。 OAは学術ジャーナルの寡占と価格高騰問題から生まれたとも言えるが、現在はオープンサイエンスなどオープンイノベーションを生み出す新しい研究開発環境の構築や研究開発投資の費用対効果を上げるために重要な要素と考えられている。こうした背景から、研究成果のOA義務化の動きが近年世界レベルで加速し、多くの国や研究機関において義務化ポリシーが策定されている。 一方、OAと親和性が高く科学の発展が期待される分野だけではなく、知財や国益などの観点からOAが馴染まない分野や事情も存在する。政策面から一律のOA化を短絡的に行うことは慎重を要し、研究者と研究者コミュニティの理解と協働が求められる。当面は科学技術振興機構(JST)で始まった研究助成対象に関するOA義務化を論文から進め、日本学術会議や日本学術振興会等を軸とした研究者による議論を深めることで、日本の事情と時機に合ったOA 化を推進し、新しい情報流通形態に基づく研究基盤の構築を促す必要がある。
1 0 0 0 OA オープンアクセスを踏まえた研究論文の受発信コストを議論する体制作りに向けて
- 著者
- 林 和弘
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター
- 巻号頁・発行日
- pp.19-25, 2014-07 (Released:2014-09-12)
1 0 0 0 OA 岡山県妹尾方言におけるジャとナの含意
- 著者
- 高山 林太郎
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.317-333, 2011-09-30
論文 Articles
1 0 0 0 国際安全規格における人間/機械安全作業システムの定式化
- 著者
- 森貞 晃 小林 孝之 蓬原 弘一
- 出版者
- 日本信頼性学会
- 雑誌
- 日本信頼性学会誌 : 信頼性 (ISSN:09192697)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.163-179, 2004-04-01
- 被引用文献数
- 6
本論文では機械安全に関する国際規格上での人間/機械安全作業シテムの扱いをインタロック構造として定式化する。まず人間と機械が協調して作業を行うシステムで人間側と機械可動部側の作業状態を各々3通りに分けて、その結果として生じる人間/機械間の組み合わせ状態での安全確保論理をインタロック構造として定式化する。本論文で示すインタロックシステムは機械側の作業状態に対して再起動防止制御の機能をもつ。このため、機械側の作業実行状態において人間側が確実に安全状態に固定されるようなインタロックシステムと人間側が必ずしも安全状態に固定されないままで機械側は作業実行中とみなされる状態を継続するようなインタロックシステムを考えることができる。前者を相互インタロックシステム、後者を自己確認型インタロックシステムと呼んで両者の各々を定式化して示す。
- 著者
- 林 智一 上野 徳美
- 出版者
- 大分大学高等教育開発センター
- 雑誌
- 大分大学高等教育開発センター紀要 (ISSN:18842682)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.1-11, 2009-03
- 被引用文献数
- 1
医療・臨床心理学教育における映画教材の有効性について検証するため、某大学医学部生に対して映画『フライド・グリーン・トマト』を用いた授業を実施し、質問紙調査を行った。その結果、映画視聴が授業テーマへの関心を高め、理解を促進するなどの効果が見られた。また因子分析の結果、本作品の「映画教材活用効果」として、授業テーマへの理解・関心の深まり、映画の多様な見方・学習、ドラマ性、洞察・共感、わかりやすさ、同一視の6因子が抽出された。さらに授業時間の配分や映画選定など、今後の課題についても検討した。
1 0 0 0 IR 熱ふく射に関するKirchhoffの法則の実験的検証(熱工学,内燃機関,動力など)
- 著者
- 牧野 俊郎 若林 英信
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学會論文集. B編 (ISSN:03875016)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.769, pp.1406-1411, 2010-09-25
- 被引用文献数
- 2
This paper discusses the Kirchhoff's law on thermal radiation. The logic of derivation of the law is reconsidered, first. Then, spectra of normal emittance ε_N and normal incidence hemispherical reflectance R_<NH> are measured on surfaces whose microstructure changes in a non-equilibrium experimental system to examine the validity of the complementary relation between ε_N and R_<NH>, which is the suggestion of the Kirchhoff's law. As the results of the examination, it is illustrated experimentally on a variety of surfaces that the complementary relation is valid within an experimental uncertainty. Provided this conclusion is admitted, the followings are suggested. If a surface is designed so that it does not reflect a narrow spectral region of radiation to any direction and reflects the other spectral regions of radiation much over the hemisphere, then the surface can be a new spectrally-functional emitter of radiation. It is also suggested that thermal radiation emitted at a surface is considered as the emission of plane waves at the surface rather than as the emission of spherical waves by electric dipoles.
1 0 0 0 周術期管理における看護師の業務拡大に関する意識調査
- 著者
- 伊藤 雅治 遠山 保次 千葉 はるみ 中村 仁 西田 博 田林 晄一
- 出版者
- 一般社団法人日本外科学会
- 雑誌
- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.4, pp.219-224, 2009-07-01
- 被引用文献数
- 7
1 0 0 0 OA 札幌農学校の文部省への移管と維持資金
- 著者
- 秋林 幸男 門松 昌彦 夏目 俊二 西本 肇 根本 晶彦
- 出版者
- 北海道大学高等教育機能開発総合センター
- 雑誌
- 高等教育ジャーナル (ISSN:13419374)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.92-110, 1999
- 著者
- 小林 祥 長谷川 智彦 安田 達也
- 出版者
- 日本脊椎脊髄病学会
- 雑誌
- Journal of spine research : official journal of the Japanese Society for Spine Surgery and Related Research (ISSN:18847137)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.11, pp.1780-1783, 2011-11
1 0 0 0 OA 高衝撃粉砕による秋田スギからのバイオエタノール製造 プロセスの低コスト化の検討
- 著者
- 遠田 幸生 竹村 卓也 佐藤 和美 沓名 潤子 伊藤 新 高橋 武彦 小林 淳一 郷地 元博
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第23回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.387, 2012 (Released:2013-07-08)
バイオエタノール製造前処理技術歯車型粉砕媒体を水平振動式加振機で駆動する省エネルギー型の高衝撃粉砕機を開発している。本粉砕機で処理した粉末は、従来糖化率が高く、同時糖化発酵においても発酵阻害がなどの特徴をもってい。しかしながら、製造コスト40円/Lを達成するためには、酵素の費用の削減、30~40 wt/vol%の高濃度粉末スラリーの同時糖化発酵後のエタノール回収の効率化などが必要である。 そこで本報告では、製造プロセスのコスト削減を図るため、酵素を回収して再利用、30~40 wt/vol%の高濃度粉末スラリーの同時糖化発酵後のエタノール回収に関する検討を行った。そのバイオエタノール製造プロセスの低コスト化を図る一環として、エタノール回収、酵素回収の検討を行った結果、エタノール回収率は95vol%以上、酵素回収率は約50%を達成できる見通しが得られた。