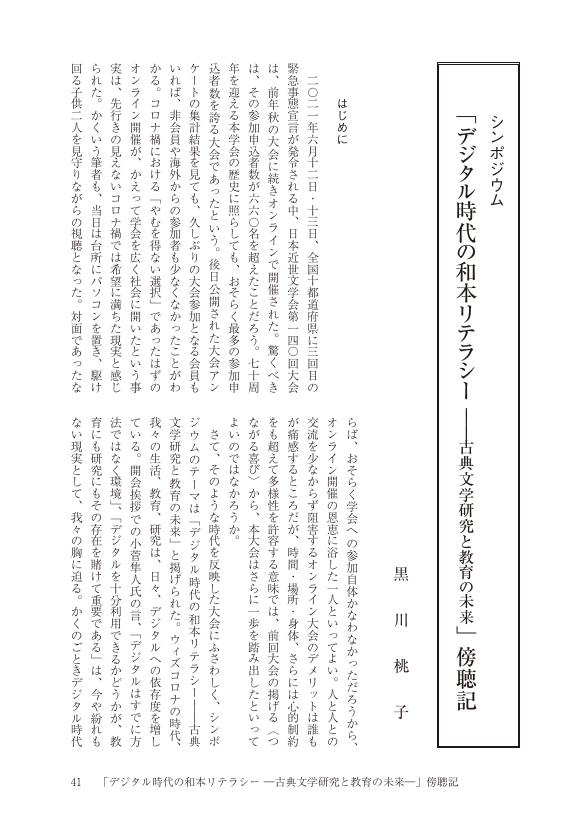6 0 0 0 OA シンポジウム 「デジタル時代の和本リテラシー ――古典文学研究と教育の未来」傍聴記
- 著者
- 黒川 桃子
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, pp.41-50, 2022 (Released:2022-07-31)
6 0 0 0 OA マイコプラズマ感染による髄膜炎尿閉症候群を伴う髄膜脳炎
- 著者
- 横山 桃子 美根 潤 松村 美咲 束本 和紀 岸 和子 竹谷 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.35-37, 2019 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 10
マイコプラズマは中枢神経合併症を認めることがあるが, 髄膜炎尿閉症候群の症例は検索する限り認めない. 症例は14歳男子. 発熱, 頭痛, 嘔吐が出現, 髄膜刺激症状を認め, 咽頭のマイコプラズマLAMP法陽性, 髄液細胞数と蛋白の増加より, マイコプラズマに関連した無菌性髄膜炎の診断で入院とした. Minocyclineを投与後尿閉が出現したため, 髄膜炎尿閉症候群と診断して, ステロイドパルス療法を追加した. 発熱, 頭痛, 嘔吐は改善したが, 傾眠傾向が出現した. 覚醒時脳波で徐波を認めたため, 髄膜脳炎と診断し, ガンマグロブリン療法を開始した. その後, 意識状態は改善し, 尿閉も12日間で軽快し, 後遺症なく, 退院した. 本症例はマイコプラズマに対する免疫応答により, 髄膜炎尿閉症候群, 髄膜脳炎を発症したと考えられた. マイコプラズマはself-limitedな疾患であり, 治療の効果と, 自然軽快との判別が難しい場合も多いが, 後遺症を残す重症脳炎の場合もある. 本症例の経験から, マイコプラズマに関連した髄膜炎尿閉症候群に対し, 早期のガンマグロブリン療法を考慮する必要があると思われた.
6 0 0 0 OA 梶井基次郎「器楽的幻覚」 : 知覚の変容と音楽・一九二〇年代の諸相から
- 著者
- 山田 桃子
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.81-94, 2013-05-15
Previous studies have shown that the series of concerts Kajii mentions in his "Kigaku-teki genkaku" were given by a French pianist, Henri Gil-Marchex(1894-1970), who visited Japan in 1925. Although Kajii's essay may appear to be merely testimony to his presence at a historic musical event in modern Japan, what the author tries to convey has deeper implications. This paper argues that Kajii was referring to historical transformations of the subject of perception. Kajii's text depicts two completely different reactions he had at a concert. While he notes that he listened attentively to a sonata, and that that was a moving experience, he also writes that listening to modern French musical selections at the same concert inevitably caused his focus to self-destruct, resulting in hallucinations. The contrast between the two musical experiences corresponds to the contrast in musical compositions between the classical and modern music of the West. Kajii, however, focuses on the transformation undergone by the perceiving subject. It is important to understand the transformation of the perceiving subject, delineated as a reaction to Western musical performance, in the larger context of the nascent mass consumer culture of the time.
5 0 0 0 OA シアノバクテリア
- 著者
- 広瀬 侑 佐藤 桃子 池内 昌彦
- 出版者
- 北海道大学低温科学研究所
- 雑誌
- 低温科学 (ISSN:18807593)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.9-15, 2009-03-31
シアノバクテリアは真正細菌の中で独自の分類群を構成するが,非常に多様で生態学的にも重要である.またモデル生物として研究が非常に進んでいる.研究材料として代表的な種を選んでその特徴を概説する.
5 0 0 0 OA 高齢肺炎患者における骨格筋量指数と退院時普通食経口摂取の検討
- 著者
- 天白 陽介 守川 恵助 今岡 泰憲 武村 裕之 稲葉 匠吾 楠木 晴香 橋爪 裕 廣瀬 桃子 鈴木 優太 畑地 治
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.327-333, 2020-12-25 (Released:2020-12-25)
- 参考文献数
- 22
近年,サルコペニアと摂食嚥下機能障害の関連性について注目されており,骨格筋量の減少は摂食嚥下機能障害の要因となると報告されている.本研究は骨格筋量の指標である骨格筋量指数(以下 SMI)が高齢肺炎症例の退院時普通食経口摂取可否を予測する因子となるかを検討することとした.対象は肺炎の診断名で当院に入院した101名(84.3±9.5歳 男性/女性:63/38)とした.普通食経口摂取の基準は退院時Functional-oral-intake-scale(以下 FOIS)6以上とした.評価項目は言語聴覚士介入時に合わせて評価した.対象を退院時FOISの値で2群に分類し,検討した.群間比較の結果では体重,Body mass index,Mini-Mental State Examination,除脂肪量,SMIにおいてFOIS6以上群が有意に高い結果であった.ロジスティック回帰分析ではSMIが独立した因子として抽出された. Receiver Operatorating Characterristic curveでは男性 5.8 kg/m2,女性 4.3 kg/m2がカットオフ値として算出された.SMIは高齢肺炎症例の退院時普通食経口摂取可否を予測する因子である可能性が示唆された.
5 0 0 0 OA 道路上の糞を探す踏査で明らかになった屋久島のニホンザルの全島分布(2017‐2018年)
- 著者
- 半谷 吾郎 好廣 眞一 YANG Danhe WONG Christopher Chai Thiam 岡 桃子 楊木 萌 佐藤 侑太郎 大坪 卓 櫻井 貴之 川田 美風 F. FAHRI SIWAN Elangkumaran Sagtia HAVERCAMP Kristin 余田 修助 GU Ningxin LOKHANDWALA Seema Sheesh 中野 勝光 瀧 雄渡 七五三木 環 本郷 峻 澤田 晶子 本田 剛章 栗原 洋介
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- pp.36.014, (Released:2020-11-30)
- 参考文献数
- 23
We studied the island-wide distribution of wild Japanese macaques in Yakushima (Macaca fuscata yakui) in May 2017 and 2018. We walked 165.4 km along roads and recorded the location of 842 macaque feces. We divided the roads into segments 50 m in length (N=3308) and analyzed the effect of the areas of farms and villages or conifer plantations around the segments and also the presence of hunting for pest control on the presence or absence of feces. We divided the island into three areas based on population trend changes over the past two decades: north and east (hunting present, population decreasing); south (hunting present, no change) and west (hunting absent, no change). According to conditional autoregressive models incorporating spatial autocorrelation, only farms and villages affected the presence of feces negatively in the island-wide data set. The effect of hunting on the presence of feces was present only in the north and east and the effect of conifer plantations was present only in the west. Qualitative comparisons of the census records from the 1990s with the more recent census indicated that feces were no longer found in the private land near the northern villages of Yakushima, where macaques were previously often detected in the 1990s. In other areas, such as near the southern villages or in the highlands, macaques were detected both in the 1990s and in 2017-2018. Our results further strengthen the possibility that the macaques have largely disappeared around the villages in the northern and eastern areas. Since the damage of crops by macaques has recently reduced considerably, we recommend reducing hunting pressure in the north and east areas and putting more effort into alternative measures such as the use of electric fences.
- 著者
- 橋本 律夫 上地 桃子 湯村 和子 小森 規代 阿部 晶子
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.837-845, 2016 (Released:2016-12-28)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3 7
Card placing test(CPT)は我々が開発した新しい視空間・方向感覚検査である.被験者は3 × 3格子の中央に立ち,周囲の格子に置かれた3種類の図形カードの位置を記憶し,自己身体回転なし(CPT-A)または回転後(CPT-B)にカードを再配置する.自己中心的地誌的見当識障害患者ではCPT-AとCPT-Bのいずれも低得点,道順障害患者ではCPT-A得点は正常範囲でCPT-Bが低得点であった.自己中心的地誌的見当識障害患者では自己中心的空間表象そのものに障害があり,道順障害患者では自己中心的空間表象と自己身体方向変化の情報統合に障害があると考えられた.
5 0 0 0 トランスジェンダーとは:その歴史, その可能性
- 著者
- 渡部 桃子
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.36, pp.75-89, 2002
- 著者
- 河野 桃子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- no.104, pp.77-95, 2011
4 0 0 0 IR 過疎山村における高齢者の生活活動と社会関係 -秋田県上小阿仁村を事例として-
- 著者
- 佐藤 桃子
- 出版者
- 秋田大学
- 雑誌
- 秋大地理 (ISSN:02865785)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.13-16, 2006-03-22
- 著者
- 堀内 義隆 下條 尚志 川上 桃子 青木(岡部) まき 池上 健慈
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.61-80, 2022-12-15 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 3
3 0 0 0 OA 高齢者における歩行中の運動制御と転倒との関連
- 著者
- 山縣 桃子 建内 宏重 市橋 則明
- 出版者
- 日本基礎理学療法学会
- 雑誌
- 日本基礎理学療法学雑誌 (ISSN:21860742)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.1-7, 2021-03-08 (Released:2021-03-09)
Our body has more elements such as joints and muscles than needed to perform any activities of daily living, including gait. As an approach to the problem of motor redundancy, the principle of abundance was suggested. The principle views the apparently redundant design of the body as a useful and crucial mechanism stabilizing different performance variables in a task-specific way. There are many papers based on this idea using the framework of the uncontrolled manifold (UCM) hypothesis. The UCM hypothesis assumes that the central nervous system acts in an abundant space of elemental variables and organizes in that space a subspace corresponding to a stable value of a performance variable. The UCM method has been developed for various actions, including multi-joint reaching, standing, and gait, and used for different subjects (e.g., younger adults, older adults, patients with neurological impairment). Using the method, we explored if segment configurations contributing to the stability of swing foot and center of mass are related to falling risk in older adults. With this paper, we introduce our previous studies as well as the basic concept of motor redundancy and the principle of abundance.
3 0 0 0 OA 糖尿病を合併する統合失調症患者の治療の実態と血糖コントロール困難の要因
- 著者
- 石橋 照子 岡村 仁 飯塚 桃子 Teruko ISHIBASHI Hitoshi OKAMURA Momoko IITSUKA
- 雑誌
- 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス研究紀要 (ISSN:18824382)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.1-8, 2010-09-30
100床以上の精神科病床を持つ20の公立病院に入院中の統合失調症患者で、糖尿病を併せ持つ193名を対象とした。糖化ヘモグロビンの値により、対象をコントロール不良群と良好群のグループに分け、糖尿病の治療環境や血糖コントロールが困難と思われる要因を比較・分析した。その結果、2群の治療環境に有意差はみられなかった。また、血糖コントロール困難の要因のうち、「自制困難」「精神症状の悪化」が血糖コントロールに強く影響していたことから、精神症状の安定に配慮しつつ、自己コントロール感を高め、自制できるよう支援していく関わりが重要であることが示唆された。
3 0 0 0 OA 音楽と懐かしさの関連についての包括的研究
- 著者
- 宇佐美 桃子 Momoko Usami
- 出版者
- 金城学院大学
- 巻号頁・発行日
- 2022-03-18
2021年度
3 0 0 0 OA 飼育下トラにおける環境エンリッチメントの有効性及び来園者による影響の検証
- 著者
- 岡 桃子 山梨 裕美 岡部 光太 松永 雅之 平田 聡
- 出版者
- 動物の行動と管理学会
- 雑誌
- 動物の行動と管理学会誌 (ISSN:24350397)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.107-116, 2019-09-30 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 25
飼育下の大型ネコ科動物で問題とされている常同歩行の発現には環境エンリッチメント(以下エンリッチメント)の有無や来園者の影響など複数の要因が絡んでいると考えられるが、複合的な検討は行われていない。そこで本研究ではエンリッチメントの有効性及び来園者数と気温がトラの行動に与える影響について検証した。京都市動物園で飼育されているアムールトラ3頭を対象とし、 3分毎の瞬間サンプリングを用いて行動を記録した。放飼場内に設置するエンリッチメントの種類が多いと、トラの常同歩行頻度は有意に減少し(P < 0.05)、エンリッチメントの利用頻度が有意に増加した(P < 0.01)。複数のエンリッチメントの設置はトラの常同歩行の抑制に効果的であり、探索行動や捕食行動等多様な行動を引き出す上で有用であることが示唆された。また来園者の存在によって、トラの休息頻度が増加、エンリッチメントの利用頻度が低下する可能性があると考えられた。
3 0 0 0 IR 長崎大学文教キャンパスに生活するノネコに見られる社会的集会
- 著者
- 土肥 昭夫 篠崎 桃子 寺西 あゆみ 伊澤 雅子
- 出版者
- 長崎大学
- 雑誌
- 長崎大学総合環境研究 (ISSN:13446258)
- 巻号頁・発行日
- pp.45-57, 2007-08
Leyhausen (1979) observed that feral cats gathered at regular gathering sites and only sat for a long time usually in the evening, and he named this curious cat behavior as "social gathering". Up to date, no one has studied and discussed on the "social gathering", that was considered to play on any role in the social systems of feral cats. We have frequently observed a number of the gatherings and the gathering sites of the feral cats lived in the campus of Nagasaki University. Nine of eleven gathering sites were used by the respective regular membership of the feral cats that shared a common home range regard as a rigid group territory. The spacing patterns of home range and the social systems were so similar with the group territory called the "feeding group", which was organized by the cats have a kin-relation (Izawa et al.1982) However, the "gathering group" in the campus widely differed from the "feeding group" in that the most of the member of a "gathering group" in the campus were originated by non-relation individuals, which sheltered into the campus from the surround urban districts and the high traffic density areas. Consequently, we found that the "social gathering" had filled an important role of accelerating to recognize and to accept each other as the member for the common group territory preservation.
3 0 0 0 OA 〈論文・報告〉割れないシャボン玉の開発と割れなくなるメカニズムの解明
- 著者
- 笛田 和希 山本 七彩 横山 遥 手嶋 日菜子 五十川 奈穂 柴田 航志 中原 涼花 乘次 優希奈 宮川 光林 田中 聖子 平野 貴士 上野 桃子 藤戸 文子 高嶋 綾香 菅野 憲一
- 出版者
- 近畿大学産業理工学部
- 雑誌
- かやのもり:近畿大学産業理工学部研究報告 = Reports of Faculty of Humanity-Oriented Science and Engineering, Kindai University (ISSN:13495801)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.15-20, 2016-07-15
We investigated long-lasting bubbles by mixing commercially available reagents. The features of the soap bubbles depended on the composition of the detergent, polymer, and other chemical components. Soap bubble containing sucrose, sodium alkyl ether sulfate (AES)- detergent and PVA laundry starch gave a spherical shape on various solid surfaces, including concrete, asphalt, tile, and grass after landing. We revealed that the low surface tension of the bubble was not the singular reason for its long lifetime. The lifetime of the film tended to be prolonged with decreasing humidity.
3 0 0 0 OA 片脚立位時の非支持脚挙上方向の股関節角度の相違が支持脚筋活動に与える影響
- 著者
- 會田 萌美 武井 圭一 奥村 桃子 平澤 耕史 田口 孝行 山本 満
- 出版者
- 公益社団法人 埼玉県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.25-28, 2016 (Released:2016-03-17)
- 参考文献数
- 7
【目的】本研究では,片脚立位における非支持脚拳上方向の股関節角度の相違に着目し,支持脚筋活動に与える影響を明らかにすることを目的とした。【方法】男子大学生13名を対象に,片脚立位姿勢(非支持脚股関節中間位,外転20度・45度,屈曲30度・90度)を保持させ,支持脚の大殿筋,中殿筋,大腿筋膜張筋,腓腹筋内側頭の筋活動を測定した。4筋における股関節中間位と外転位,股関節中間位と屈曲位の肢位間の筋活動を比較した。【結果】非支持脚を外転方向へ挙上した片脚立位では,角度の増大に伴い中殿筋に有意な筋活動の増加を認めた。外転45度・屈曲90度の片脚立位では,股関節中間位の片脚立位に比べ,中殿筋・大殿筋の有意な筋活動の増加を認めた。【結論】Closed Kinetic Chainでの筋力トレーニングとしての片脚立位は,股関節外転により支持脚中殿筋の筋活動を鋭敏に増加させ,外転45度・屈曲90度では股関節周囲筋の筋活動を増加させる特徴があると考えられた。
3 0 0 0 OA 大規模データを使った診療の見える化
- 著者
- 東 尚弘 岩本 桃子 中村 文明
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.10, pp.672-675, 2015 (Released:2015-10-25)
- 参考文献数
- 2
がん医療の均てん化はがん対策の大きな課題である. そのためには医療の質の測定・把握が必要であるが, データ源として最も信頼の置ける診療録からの採録は作業負担への懸念から, 限界は許容しつつ院内がん登録とDPC (diagnosis-procedure combination) データをリンクしたデータによる指標の測定が始まった. 両データをリンクするためには病院内で共通の匿名番号をつける必要があるが, データの標準化も十分ではなく, さまざまな困難があった. 専用のソフトで作業を自動化し, ソフトも各種課題に対処して改良を重ねることで, 2012年症例では232施設からデータの収集が可能であった. 今後は, 参加病院のがん診療の質の向上と, がん対策の効果的推進の両方にこのデータを活用していく体制構築を行っていく.
3 0 0 0 OA ステロイドおよびシクロスポリンが有用であったTAFRO症候群の1例
- 著者
- 森澤 紀彦 佐藤 博之 松山 桃子 林 直美 安達 章子 佐藤 順一 横尾 隆 雨宮 守正
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.12, pp.2432-2440, 2016-12-10 (Released:2017-12-10)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
TAFRO症候群は,血小板減少(thrombocytopenia),腔水症(anasarca),発熱(fever),骨髄線維症(myelofibrosis),腎機能障害(renal dysfunction),臓器腫大(organomegaly)を特徴とする.症例は66歳,男性.7カ月前に血小板数減少を指摘され,約1カ月前より腹痛,胸腹水貯留が生じた.前医入院後に腎機能障害が出現し,当院転院となり,TAFRO症候群と診断した.比較的急峻な経過を辿るもステロイドおよびシクロスポリンによる治療で改善した.血小板減少を伴う腎機能障害の鑑別にTAFRO症候群を挙げることが肝心である.