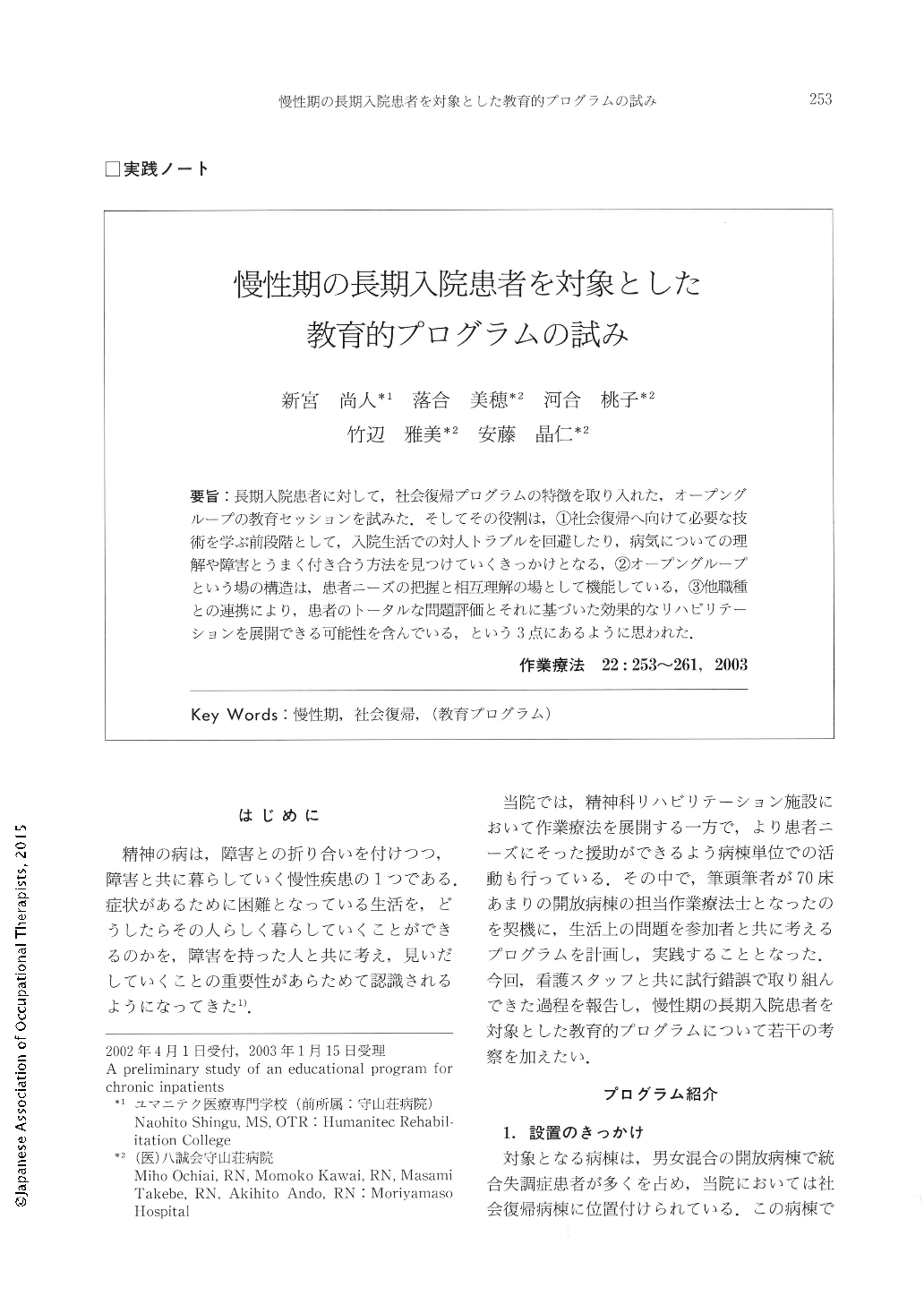1 0 0 0 OA 教育思想家は「科学(Wissenschaft)」をどう考えてきたか?(コロキウム4)
1 0 0 0 OA UI-Filler:シナリオに基づく対話型UI設計支援ツール
- 著者
- 草野 孔希 中谷 桃子 大野 健彦
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.1016-1025, 2014-02-15
本研究ではシナリオを用いたユーザインタフェース(UI)設計を支援するツール,UI-Fillerを提案する.ユーザにとって使いやすいUIを実現するには「誰が,どのような目的で,どのように使うか」といった,ユーザの振舞いを熟慮しながら繰り返しUIを設計することが重要である.そこで,振舞いを物語のようにシナリオとして記述することで,特別な知識がなくてもユーザ像を具体的にイメージすることが可能となる.しかし,従来のシナリオに基づく設計手法には,1.複数の利用シナリオが考えられるインタラクティブシステムにおいて,シナリオどうしの関係性やトレードオフを加味しながらUIを設計することは難しい,2.設計したUIを評価しながら繰り返し改善する際に,シナリオとUIとの対応関係を維持することが難しい,という2つの難点がある.そこで,UI-Fillerはシナリオの階層化およびタグ付けを用いたシナリオの分析と管理の支援,および分析結果の可視化によってUIの反復設計を支援する.
- 著者
- 平野 桃子 柳与 志夫 東 由美子 数藤 雅彦
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.115-118, 2019-03-15 (Released:2019-06-01)
- 参考文献数
- 2
紙でのみ発行されていた過去の新聞記事のデジタル化とその活用策を検討することを目的に、2017年に地方紙デジタル化の状況を把握するためのアンケート調査を行なった。本発表では、上記の調査結果から浮き彫りになった課題・問題点を、(1)法制度的・倫理的、(2)社会的、(3)技術的、(4)経済的・制度的課題の4項目に整理し、各項目について、過去及び現在のデジタル化記事を今後活用していくための課題抽出を行なった。
- 著者
- 羽賀 里御 浦辺 俊一郎 深澤 桃子 加藤 亜輝良 松沢 翔平 加藤 基子 檜山 英己 栗井 阿佐美 南雲 三重子 尾崎 美津子 古森 くみ子 清水 美智江 水品 伊津美 山本 茉梨恵 白鳥 恵 巽 亮子 倉田 康久 兵藤 透
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.9, pp.465-470, 2020 (Released:2020-09-28)
- 参考文献数
- 13
当院はCOVID-19感染者の多い神奈川県にある無床外来維持血液透析クリニックである. 透析患者は学会指針のマスク着用, 手洗い等の標準予防策を遵守し通院している. 今回, 血液透析患者1例がCOVID-19に罹患していることが判明した. この普段からの標準予防策に加えて, 発生から2週間, 感染者が出た透析時間帯の患者は時間帯を固定, 同一メンバーとし, 不要不急の検査, 受診, 手術は延期し, 感染防御対策を行うこと (集団的隔離透析) を補完的に加えることで, 二次感染が防止できたと考えられる事例を経験した. 特にマスク, 手洗い等の普段からの学会指針の基本を遵守することが二次感染防止に非常に有効と考えられた.
- 著者
- 池田 裕美 山口 剛史 小平 桃子 Bahry M. A. Chowdhury V. S. 安尾 しのぶ 古瀬 充宏
- 出版者
- Japanese Society of Pet Animal Nutrition
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.47-58, 2017-04-10 (Released:2017-05-02)
- 参考文献数
- 35
ジャンガリアンハムスター(以下、ジャンガリアン)とロボロフスキーハムスター(以下、ロボロフスキー)はともにドワーフハムスターと呼ばれ同属でありながら、ロボロフスキーはヒトに慣れにくく多動性を示す。これまでの研究により、ジャンガリアンに比してロボロフスキーでストレス感受性が高いのではないかと仮説を立て、多動性とストレス感受性との関連性を解明することを目的とした。野生のドワーフハムスターは群れで生活するために単離ストレスがかかりやすいのではないかと考え、単離飼育を用いた。ジャンガリアンとロボロフスキーの3週齢雄を群飼で馴化した後、群飼と単飼の2つのグループに分けた。3種類の行動試験を実施し、行動量、不安様行動および社会的行動を測定した。その後得られた海馬および小脳のサンプルを用いて、L型ならびにD型アミノ酸およびモノアミンの分析を行い、さらに、血漿中コルチゾール含量の測定も行った。その結果、単飼開始初期の行動試験においては、ロボロフスキーの多動性が不安様行動を反映している可能性が得られたものの、その後の行動試験ではストレスによる影響はみられなかった。このことから、ハムスターに対し単離は弱いストレスであり、両者の行動量ならびに脳内アミノ酸およびモノアミン代謝にはほとんど影響を及ぼさないことが示唆された。
1 0 0 0 OA 子どもを亡くした家族のグリーフケアプログラムの開発~語りのアクションリサーチ~
- 著者
- 濱田 裕子 藤田 紋佳 瀬藤 乃理子 木下 義晶 古賀 友紀 落合 正行 賀来 典之 松浦 俊治 北尾 真梨 笹月 桃子 京極 新治 山下 郁代
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2014-04-01
子どもを亡くした家族の悲嘆に関するケアニーズを明らかにし、アクションリサーチによって悲嘆に対するサポートプログラムを作成することを目的に研究を実施した。子どもを亡くした家族に個別インタビューを行った結果、子どもの疾患や年齢によって、家族のケアニーズの特徴は異なったものの、共通していたのは【子どものことをなかったことにしたくない】、【子どもの事を知ってほしい】、【ありのままの自分でよいことの保証】、【気持ちを表出できる場がほしい】などであった。グリーフケアプログラムの試案として、フォーカスグループインタビューを4回、グリーフの集いを1回実施するとともに、グリーフサポートブックを作成した。
1 0 0 0 OA 宗教性の測定 : 国際比較研究を目指して
- 著者
- 横井 桃子 川端 亮
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.79-95, 2013-06-15 (Released:2017-07-18)
従来の国際比較研究では、「教会出席」や「神との関係」といったキリスト教中心につくられた変数が宗教性を測るものとして用いられてきた。グローバル化する現代において、日本の宗教性を欧米のこれらの変数で正しく測ることは喫緊の課題となっている。本稿では、統計数理研究所の国民性調査の中の「宗教的な心は大切か」という質問文を日本人の宗教性を測るものとし、様々な社会意識や行動との関連を検討した。その結果、欧米の先行研究で検証されていたボランティア行動や利他的行動、投票行動、伝統的意識や社会的責任感に「宗教的な心」が影響を及ぼすことが分かった。日本における「宗教的な心」を用いて測定された宗教性が、欧米で用いられてきた従来の変数で測られるそれと操作的に同じはたらきをする可能性が示唆された。今後、「宗教的な心」が欧米の調査データでも検証されることで、さらにこの項目の有効性が明らかになるだろう。
1 0 0 0 OA タクシー運転者における健康起因事故の予防対策についての実態調査
- 著者
- 一杉 正仁 山内 忍 長谷川 桃子 高相 真鈴 深山 源太 小関 剛
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.50-57, 2016 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
職業運転者における健康起因事故予防のために行うべき指導および啓発内容を具体的に明らかにするために、栃木県タクシー協会に所属する全タクシー運転者2,156人を対象に、無記名自記式のアンケート調査を実施した。844人から調査用紙が返送され(回収率は39.1%)、平均年齢は60.7歳であった。所属事業所の保有車両台数は30台未満(中小規模)が60.4%、30台以上が39.6%(大規模)であった。乗務前に体調が悪くても運転したことがある人は有効回答の28.5%であり、この割合は大規模事業所の運転者で有意に高かった。運転した理由として、運転に支障がないと判断したこと(59.0%)、収入が下がること(57.9%)が多かった。運転中に体調が悪くなったことがある人は有効回答の32.6%であり、その時、会社に申告して運転をやめた人が55.3%、しばらく休んでから運転を続けた人が26.5%、そのまま運転を続けた人が14.6%を占めた。体調が悪い時は運転を控えるよう指導された人は有効回答の76.0%、体調が悪い時に言い出しやすい職場環境であると回答した人は83.9%であり、いずれも事業所の規模による差は認められなかった。また、自身の健康と運転について、会社でしっかり管理してほしいと回答した人が34.0%を占め、27.2%の人がより頻回の健康診断受診を希望していた。健康起因事故の背景と予防の重要性が会社の規模によらずタクシー業界に十分浸透していないこと、厳しい労働環境がタクシー事業所全体に共通しているため、健康起因事故の予防を推進する経済的余裕がないことが分かった。健康起因事故を予防できるように、運転者自身が体調不良によるリスクを認識し、健康管理に対する意識の持ち方・知識を高めていくこと、これを事業所がサポートするシステムを構築することが重要である。
1 0 0 0 OA 詳細な誤情報が虚記憶に及ぼす影響:共同想起場面で誤情報が他者によって示された場合
- 著者
- 星野 祐司 山田 桃子
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.153-164, 2008-02-29 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 30
見ていない項目に関する詳細情報が虚再生に及ぼす影響について検討した.実験参加者は対になって6つの場面の画像を見た.半数の参加者には,残りの半数の参加者が見ていない3つの独自項目が提示された.引き続き行われた共同再生テストでは,2名の参加者が各場面に含まれていた項目を口頭で報告した.項目条件では項目の名前についての再生が参加者に求められた.詳細条件では項目の名前,色,形,場所を再生することが参加者に求められた.したがって,共同想起において独自項目を見ていない参加者は独自項目に関する誤情報を聞く可能性があった.共同想起の終了後,個別再生テストが実施され,再生項目に対してremember/know判断を求めた.項目条件における独自項目についての虚再生の頻度は詳細条件における虚再生と同程度であった.項目条件では虚再生に対するremember判断が観察されたが,詳細条件では観察されなかった.これらの結果についてソースモニタリングの観点から考察した.
1 0 0 0 OA 紙おむつを利用した災害時用マイ・トイレの提案
- 著者
- 植竹 桃子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.148-157, 2014 (Released:2015-01-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
In order to be prepared for natural disasters and develop an effective self-sufficient emergency body waste management system, the author devised a personal emergency toilet that uses disposable diapers that are readily available on the market and tested it under various conditions. The addition of 200 cm3 of wood pellets sold as cat litter to each toilet unit was found to be effective in preventing the toilet from producing ammonia gas and emitting a foul smell. An oxygen-based bleaching agent for clothes was not very effective in preventing them, especially during the hot summer season. Spraying the toilet about six times with the agent after use was found to be the most effective. This disposable diaper-based personal toilet is cheaper than ordinary emergency toilets on the market, and the materials are easily available. Based on the results, the author proposes adopting disposable diaper-based personal toilets to prepare for natural disasters.
1 0 0 0 OA 変わっていく大学図書館と広報:図書館広報の可能性
- 著者
- 森嶋 桃子
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, pp.34-41, 2009-03-31 (Released:2017-11-08)
大学図書館は厳しい環境の変化に直面しており,利用者の図書館に対する認識は十分でない。大学図書館が積極的に自らのプレゼンス(存在)を主張するためには,従来の図書館広報を見直す必要がある。広報のターゲットとしてステークホルダー(利害関係者)の存在を意識し,マーケティング手法の導入によって対象のニーズを把握することで,図書館に対する認知と支援を獲得することが可能となる。あわせて,北米研究図書館協会(ARL)による調査報告と米国図書館協会(ALA)によるキャンペーンについて紹介する。
1 0 0 0 大学のハラスメント相談における心理職の専門性
1 0 0 0 慢性期の長期入院患者を対象とした教育的プログラムの試み
要旨:長期入院患者に対して,社会復帰プログラムの特徴を取り入れた,オープングループの教育セッションを試みた.そしてその役割は,①社会復帰へ向けて必要な技術を学ぶ前段階として,入院生活での対人トラブルを回避したり,病気についての理解や障害とうまく付き合う方法を見つけていくきっかけとなる,②オープングループという場の構造は,患者ニーズの把握と相互理解の場として機能している,③他職種との連携により,患者のトータルな問題評価とそれに基づいた効果的なリハビリテーションを展開できる可能性を含んでいる,という3点にあるように思われた.
- 著者
- 會田 萌美 武井 圭一 奥村 桃子 平澤 耕史 田口 孝行 山本 満
- 出版者
- 公益社団法人 埼玉県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.25-28, 2016
【目的】本研究では,片脚立位における非支持脚拳上方向の股関節角度の相違に着目し,支持脚筋活動に与える影響を明らかにすることを目的とした。【方法】男子大学生13名を対象に,片脚立位姿勢(非支持脚股関節中間位,外転20度・45度,屈曲30度・90度)を保持させ,支持脚の大殿筋,中殿筋,大腿筋膜張筋,腓腹筋内側頭の筋活動を測定した。4筋における股関節中間位と外転位,股関節中間位と屈曲位の肢位間の筋活動を比較した。【結果】非支持脚を外転方向へ挙上した片脚立位では,角度の増大に伴い中殿筋に有意な筋活動の増加を認めた。外転45度・屈曲90度の片脚立位では,股関節中間位の片脚立位に比べ,中殿筋・大殿筋の有意な筋活動の増加を認めた。【結論】Closed Kinetic Chainでの筋力トレーニングとしての片脚立位は,股関節外転により支持脚中殿筋の筋活動を鋭敏に増加させ,外転45度・屈曲90度では股関節周囲筋の筋活動を増加させる特徴があると考えられた。<br>
1 0 0 0 OA 女性の月経周期と体内水分量に関する研究 : 生体インピーダンス法を用いて(報告)
- 著者
- 佐藤 美幸 作田 裕美 坂口 桃子
- 出版者
- 滋賀医科大学
- 雑誌
- 滋賀医科大学看護学ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.63-66, 2008-03-15
1 0 0 0 OA シュタイナー教育における「再受肉」論 : 二つの「個性」概念に着目して
- 著者
- 河野 桃子
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.1-9, 2012-03-10
Es gibt ab und zu eine Tendenz, nur die Praxis der Waldorfpädagogik zu beachten und die Diskussion über den Gedanken von R.Steiner, der eine Grundlage für die Praxis ist, zu tabuisieren. Es leitet sich von der dualistischen Komposition seines späteren mystischen Gedanken her. In dieser Abhandlung wird versucht, eine positive Bedeutung zu zeigen, auch seinen Gedanken in Betracht zu ziehen, um die Praxis besser auszulegen. Dabei thematisieren wir insbesondere einen "Effekt", den sein Gedanke über "Reinkarnation"(damit auch über "Persönlichkeit" und "Individualität") ermöglicht. Am Ende ergänzen wir diesen "Effekt" mit der Intention zur monistischen Erkenntnis, die Steiner ganze Zeit erhalten hat.
- 著者
- 飯島 弘貴 青山 朋樹 伊藤 明良 山口 将希 長井 桃子 太治野 純一 張 項凱 喜屋武 弥 黒木 裕士
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, 2016
【はじめに,目的】変形性膝関節症(膝OA)の病態に即した理学療法の実現のためには,その病態の理解や力学的負荷に対する生体組織の生物学的な応答を明らかにすることが不可欠である。2015年,我々はラット膝OAモデルに対する運動刺激が膝OAの予防に貢献することを報告した。そこで,本研究では,運動刺激の効果をさらに詳細に検討する目的で,異なる強度の運動刺激が関節軟骨と軟骨下骨に与える影響を,関節面の領域別に明らかにすることを目的とした。【方法】本研究はThe Animal Research Reporting In Vivo Experiments(ARRIVE)guidelinesに準じて計画,実施された。12週齢のWistar系雄性ラット30匹の右膝関節に外科的処置(前脛骨半月靭帯切離)を施し,内側半月板不安定性(DMM)モデルを作成した。その後,8週間の自然飼育を行うDMM群(n=10)と,早期膝OAの状態となる術後4週時点から1日30分,週5日間,4週間のトレッドミル走行を行うmoderate群(12m/分,n=10),intense群(21m/分,n=10)の3群に分類した。術後8週時に膝関節を摘出し,脛骨側内側関節面の関節軟骨,軟骨下骨を組織学的手法,力学的手法,およびmicro-CTを用いて領域別(前方および後方)に評価し,3群間で比較した。統計学的有意水準は5%とした。【結果】脛骨内側関節面後方領域を組織学的に観察すると,DMM群では関節軟骨および軟骨下骨中の死細胞を含む変性像が観察されたが,moderate群の変性像はDMM群よりも軽度であり,軟骨変性重症度の評価であるOARSI scoreはDMM群の約50%であった(DMM群,中央値:10.5,範囲:9-12;moderate群,中央値:5,範囲2-9;<i>P</i>=0.025)。同領域のmicro-CT所見では,DMM群では嚢胞状の骨吸収領域が多数観察されたが,moderate群の骨吸収領域の最大直径はDMM群の約70であった(DMM群,平均値:547.1μm,95%信頼区間[CI]:504.7-589.5;moderate群,平均値:375.9μm,95%CI:339.3-412.5;<i>P</i><0.001)。力学的手法を用いて圧縮応力に対する関節軟骨の歪みを評価すると,後方領域ではDMM群は正常軟骨の215%であったのに対して,moderate群では160%に抑性された(DMM群,平均値:65.7μm,95%CI:60.7-71.3;moderate群,平均値:49.1μm,95%CI:39.1-59.1;<i>P</i>=0.045)。しかしながら,前方領域における変性に関しては,DMM群とmoderate群の間で統計学的有意差はなかった。また,intense群では,OA進行予防効果が乏しいだけでなく,micro-CT所見上での軟骨下骨の骨吸収領域の最大直径は,むしろDMM群よりも28%増大した(平均値:700.7μm,95%CI:614.1-787.3;<i>P</i><0.001)。【結論】本研究は,運動刺激による膝OAの進行予防を期待する場合には,運動強度の調整が必要であることを示した。また,中等度レベルの運動によるOA進行予防効果が主荷重部に限局して確認されたことから,運動刺激による膝OA進行予防効果は力学的負荷が加わる領域に特異的に生じる可能性がある。
- 著者
- 飯島 弘貴 青山 朋樹 伊藤 明良 山口 将希 長井 桃子 太治野 純一 張 項凱 喜屋武 弥 黒木 裕士
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, 2015
【はじめに,目的】変形性膝関節症(膝OA)は膝関節痛やこわばりを主訴とする代表的な運動器疾患である。その病態の中心は関節軟骨の摩耗・変性であるが,近年では病態の認識が改まり,発症早期より生じる軟骨下骨の変化が,関節軟骨の退行性変化を助長している可能性が指摘されるようになった。我々も同様の認識から,半月板損傷モデルラットを作成し,その早期から軟骨変性と軟骨下骨嚢胞が共存していることを明らかにした(Iijima H. <i>Osteoarthritis Cartilage</i> 2014)。理学療法を含む非薬物治療は,膝OAの疼痛緩和を目的とした治療戦略の大きな柱であるが,このような早期膝OAの病態を考慮した,OA進行予防策に関する研究蓄積は乏しい。また,病態モデル動物を用いた研究において,歩行運動が関節軟骨の退行性変化を予防しうる,という報告は散見されるが,そのメカニズムは不明であった。そこで,我々はこれらの課題に対して,早期の病態に関与する軟骨下骨変化を歩行運動によって抑制することが,膝OA進行予防に寄与するのではないかと着想し,これまで不明であった,運動による膝OA進行予防メカニズムの解明へと研究を進めてきた。本研究では,我々が報告した半月板損傷モデルラットを使用し,疑似的に早期膝OAの状態を作り出し,歩行運動が軟骨下骨変化に与える影響を評価し,軟骨変性予防効果との関連性を検討した。【方法】12週齢のWistar系雄性ラット24匹に対して,内側半月板の脛骨半月靭帯(MMTL)を切離する内側半月板不安定性モデルを作成した。MMTLの切離は右膝関節のみに行い,左膝関節に対しては偽手術を施行し,対照群とした。その後,術後8週間に渡り自然飼育を行うことで,OAを発症・進行させるOA群(n=8)と,早期膝OAの状態となる術後4週時点からトレッドミル歩行(12m/分,30分/日,5日/週)を行う運動群(n=8)の2群に分類した。時系列変化を評価するため,術後4週まで飼育する介入前群(n=8)を設定した。主な解析対象および群間の比較は,MMTLを切離した全群の右膝関節とし,対照群とも比較した。解析内容は,μ-CT撮影および組織学的手法を用いて,4週間にわたる歩行運動介入の効果を検討した。μ-CT撮影所見より軟骨下骨嚢胞の最大径を評価し,組織学的解析では破骨細胞マーカーである酒石酸耐性酸フォスファターゼ(TRAP)染色とともに,骨細胞死数,軟骨下骨損傷度(0-5点)を評価した。また,軟骨変性重症度(0-24点)を評価し,軟骨下骨損傷度との関連性の評価としてSpearmanの順位相関係数を算出した。【結果】μ-CT所見では介入前から脛骨内側関節面にて軟骨下骨嚢胞が確認されたが,運動群では最大嚢胞径が縮小し,介入前およびOA群よりも有意に低値を示した(<i>P</i><0.01)。組織学的所見では,軟骨下骨嚢胞内にTRAP陽性破骨細胞が多数観察され,直上の関節軟骨が嚢胞内に落ち込む所見が介入前群では30%で確認された。OA群ではその後悪化し,80%で確認されたが,運動群では0%であった。併せて,介入前およびOA群では多数の骨細胞死が観察されたが,運動群ではいずれも軽度であり(<i>P</i><0.01),軟骨下骨損傷度は介入前およびOA群よりも有意に低値を示した(<i>P</i><0.05)。軟骨変性重症度は,運動群で最も低値を示し(<i>P</i><0.05),軟骨下骨損傷との間に強い相関を認めた(<i>P</i><0.01,r=0.91)。【考察】半月板損傷後に発症した早期膝OAに対する緩徐な歩行運動は,骨細胞死の減少とともにTRAP陽性破骨細胞活性に起因する軟骨下骨嚢胞を縮小させることが明らかになった。つまり,半月板損傷後に生じた損傷軟骨下骨は可逆的な状態にあり,自然飼育のみでは進行する一方,歩行運動によって治癒することを示している。軟骨下骨の損傷により形成された陥没は,関節軟骨に加わるひずみを増大させる要因となるだけでなく,関節軟骨-軟骨下骨間の炎症性サイトカインの交通を介してOAを進行させることが知られている。したがって,軟骨下骨の治癒が歩行運動によってなされることで,その直上の軟骨に加わる力学的,化学的ストレスを緩和させ,膝OAの進行予防に一部寄与しうることが示唆された。【理学療法学研究としての意義】膝OAに対する従来の理学療法は,摩耗・変性した関節面へ加わる応力を,分散あるいは減弱させることを主目的としてその進行予防に寄与してきたため,歩行運動のような運動負荷を治療手段とするという考え方は希薄であった。本研究結果は,半月板損傷後の早期膝OAに対する一定の運動負荷がOA進行予防に寄与する可能性を提示し,そのメカニズムの一部を病態モデル動物を使用して病理組織学的にはじめて明らかにしたものである。
- 著者
- 飯島 弘貴 青山 朋樹 伊藤 明良 長井 桃子 山口 将希 太治野 純一 張 項凱 秋山 治彦 黒木 裕士
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに,目的】変形性膝関節症(OA)の病変の主体は関節軟骨であるが,加えて軟骨下骨の独立した変化を伴うと認識され,半月板切除後に予後不良でTKAに至った者の多くは軟骨下骨の骨折を伴っていたと報告されている。近年のOAモデル動物を使用した実験では,早期から軟骨下骨の変化が生じることで軟骨変性を助長する現象が明らかとなっている。したがって,早期からの軟骨下骨の変化を抑えることはOAの病態に対する理学療法戦略として重要である。OAモデル動物に対する緩徐なトレッドミル走行は軟骨の変性予防効果があることが報告されているが,軟骨下骨の変化を捉えた研究は存在しない。本研究ではOAを惹起する半月板不安定モデルラットを使用し,早期からの緩徐な走行運動は軟骨変性の予防効果だけでなく,軟骨下骨変化の予防効果もあると仮説を立て,病理組織学的に検証を行った。【方法】12週齢の雄性Wistar系ラットに対してOAモデル(内側半月板不安定モデル)を作成した。右膝関節にOA処置を行い,左膝関節に対しては偽手術を行った。作成したOAモデルラットを自然飼育のみ行う群(右膝:OA群,左膝:対照群)と緩徐な歩行を行う群(右膝:OA+運動群,左膝:運動群)の2群に無作為に分類した。運動条件は12m/分,30分/日,5日/週とし,飼育期間は術後1,2,4週間とした(各群n=5)。各飼育期間終了後に安楽死させ,両膝関節を摘出した後,軟骨下骨変化の評価としてmicro-CT撮影を行った。その後作成した組織切片に対して,HE染色による組織形態の観察と免疫組織化学的手法を用いてCol2-3/4c,MMP13,VEGFの発現分布の評価を行った。軟骨変性重症度の評価に関しては,膝関節前額断の内側脛骨軟骨を内側,中央,外側の3領域別に分類し,OARSI scoreを使用して軟骨変性の評価を行った。統計学的解析はstudent t検定及びANOVAを行い,ANOVAで有意差が見られた場合には多重比較としてTukeyの検定を行った。統計学的有意水準は5%とした。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は所属施設動物実験の承認を得て実施した。【結果】OA群とOA+運動群の2群間でOARSI scoreを比較すると,1,2週時点では有意差は見られなかったが,4週時点では中央,外側領域においてOA+運動群で有意に軟骨変性重症度が小さかった(中央:4wOA群;16.1±1.5,4wOA+運動群;10.3±3.3,外側:4wOA群;6.6±1.8,4wOA+運動群;3.3±0.7)(<i>P</i><0.01)。OA群,OA+運動群は1,2,4週のいずれの時点でも対照群,運動群よりも有意に軟骨変性重症度が高かった(<i>P</i><0.01)。II型コラーゲンの断片化を検出するcol2-3/4cはOA群と比較してOA+運動群で陽性領域が小さかった。micro-CT上で軟骨下骨を観察すると,1週時点からOA群では主荷重部である中央領域に骨欠損が観察され,時間依存的に骨欠損の大きさが増大していったが,OA群とOA+運動群で骨欠損の大きさに明らかな差は認めなかった。HE所見では軟骨変性が重症である領域と骨欠損領域が一致し,骨欠損領域は骨髄中に含まれる血球系の細胞とは異なる線維軟骨様の組織で埋め尽くされており,VEGFやMMP13の陽性所見が確認された。全ての結果に関して,対照群と運動群では明らかな差異を認めなかった(<i>P</i>>0.05)。【考察】OAモデルラットに対する緩徐な走行運動は軟骨変性の予防効果は示したが,軟骨下骨の変化を抑性することはできず,仮説は棄却された。軟骨下骨骨折領域の細胞には血管性の因子であるVEGFや軟骨破壊因子であるMMP13の発現が確認されたことから,軟骨の変性は軟骨下骨骨折によって助長されうるが,運動療法が軟骨変性予防効果を示した背景として,軟骨下骨変化以外の軟骨破壊プロセスを抑性したことが考えられる。本研究で用いた運動条件はラットの生理的な歩行速度であり,より高い運動強度を用いた実験では軟骨破壊を促進することを我々は過去に報告したことを踏まえると(Yamaguchi S, Iijima H, et al 2013),軟骨の破壊プロセスを生物学的に抑性するためには運動強度や量に注意を払う必要があることも示された。【理学療法学研究としての意義】軟骨下骨の骨折は半月板切除後早期から主荷重領域に生じるが,緩徐な走行運動を早期から行っても軟骨下骨の骨折を悪化させることなく軟骨変性を予防する効果があり,OAの進行予防に対して理学療法が有効であることを示唆するものである。