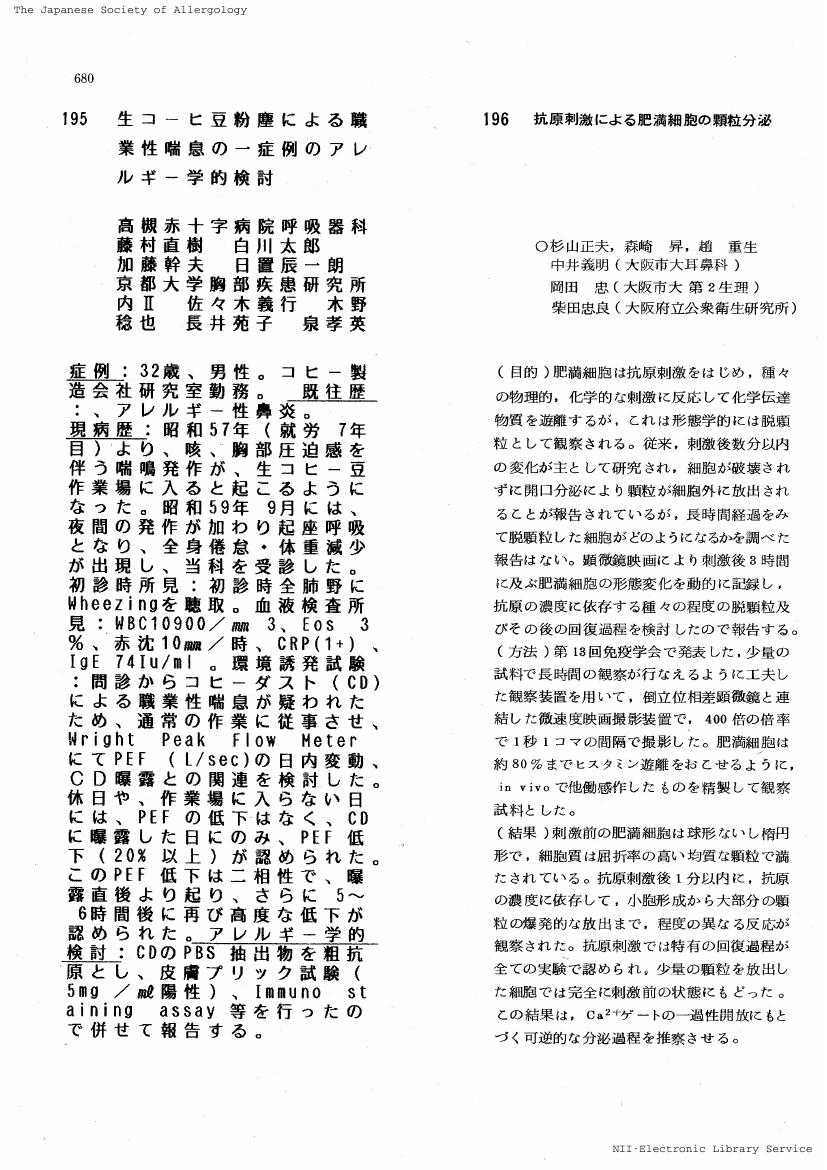1 0 0 0 OA ウェルビーイング志向の価値共創とその分析視点
- 著者
- 白肌 邦生 ホー バック
- 出版者
- サービス学会
- 雑誌
- サービソロジー論文誌 (ISSN:24355763)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1-9, 2018 (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 58
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to propose viewpoints for analysing well-being oriented value co-creation. We firstly explain the concept of transformative service research: TSR which centres on consumer well-being in service and discuss its importance in serviceology as well as service marketing. Based on the systematic literature review, this paper divided into four categories of TSR studies by using two axes of “resource scarcity and resource development” and “micro and meso-macro”. We analysed two Japanese transformative service cases which include capability development in both micro and meso-macro level as the final value of service, thereby proposing additional perspectives for analysing about the resource integration for well-being oriented value co-creation.
1 0 0 0 OA 中頭蓋窩くも膜のう胞破裂後の硬膜下血腫/水腫にTBIRDを合併した乳児例
- 著者
- 君和田 友美 林 俊哲 白根 礼造 冨永 悌二
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経外科学会
- 雑誌
- 小児の脳神経 (ISSN:03878023)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.414-418, 2022 (Released:2023-01-30)
- 参考文献数
- 12
右中頭蓋窩くも膜のう胞破裂後に硬膜下血腫/水腫を来し,けいれん重積型(二相性)急性脳症に類似の病態であるinfantile traumatic brain injury with a biphasic clinical course and late reduced diffusion(TBIRD)を併発した1乳児例を報告した.新生児/乳幼児急性硬膜下血腫後に脳腫脹を来す一因として,我々脳神経外科医はTBIRDを十分理解しておく必要がある.
1 0 0 0 OA 195 生コーヒー豆粉塵による職業性喘息の一症例のアレルギー学的検討
1 0 0 0 OA 相分離生物学で理解するプリオンの存在意義
- 著者
- 西奈美 卓 白木 賢太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.4, pp.192-200, 2020-04-05 (Released:2020-09-14)
- 参考文献数
- 64
プリオンは遺伝情報をもたずに感染するタンパク質のことをいう.プリオン病は18世紀には文献として確認されていた疾患である.当時,ヒツジの個体間で感染する神経変性疾患として確認されていた.この疾患は脳組織に海綿状の異常がみられるため,伝達性海綿状脳症(TSE)と総称されていた.20世紀の半ば,放射線生物学者のTikvah Alperらは,核酸を損傷させることができる放射線をもちいてTSEに照射したところ,TSEに耐性があったことから感染因子が核酸ではない可能性を疑っていた.1982年になり,Stanley Prusinerらは,核酸を特異的に壊す5つの処理とタンパク質を不活性化する処理による結果を比較することで,TSEは核酸をもたずに感染するという仮説を発表した.タンパク質の立体構造の変化が感染するという“タンパク質単独仮説”である.この感染因子は,核酸をもつウイルスやプラスミド,ウイロイドなどと区別するためにプリオン(proteinaceous infectious particles)と名付けられた.しかし,プリオンの概念は,“核酸を介して情報を伝達する”という分子生物学のセントラルドグマに反するほか,“タンパク質の天然構造はそのアミノ酸配列にしたがって熱力学的に最も安定な構造をとる”という,アンフィンセンのドグマにも従わず,長いあいだ科学の世界に受け入れられなかった.プリオンの概念が大きく進歩したのは,1994年の酵母プリオンUre2やSup35の発見であった.出芽酵母S. cerevisiaeでは,メンデルの法則にしたがわない奇妙な遺伝現象が知られていた.Reed Wicknerらは,その現象が哺乳類プリオンの概念で説明ができるのではないかと提唱したのである.その後,いくつかの研究グループによって,Sup35の構造変化が酵母の表現型を変化させることが証明されていった.酵母プリオンは感染の評価が速やかにでき,また,ヒトへの感染も起こらないため,扱いやすい研究モデルになった.そして,酵母には他にもプリオンがあること,原核生物であるボツリヌス菌もプリオンをもつことなどがわかっていった.このようにして,プリオンの概念は,原核生物から真核生物まで進化的に保存されていることが明らかとなったのである.その間にも,プリオンに似た機構で神経変性疾患を引き起こすプリオン様タンパク質の発見や,概念としてのプリオンに迫るアミロイドの研究が著しく発展した.しかし,疾患に関わる可能性のあるプリオンの現象が,なぜ多様な生物種にわたり進化的に保存されているのだろうか?最近の相分離生物学の台頭によって,プリオンの存在理由をうまく説明できる仮説が登場している.何億年も前に別の種に分かれた出芽酵母S. cerevisiaeと分裂酵母S. pombeのどちらにも保存されてきたプリオンタンパク質として,Sup35がある.Sup35は翻訳を終結させる働きがある.酵母が飢餓状態に陥ると細胞内が酸性になるが,そのときSup35は不可逆な凝集体の形成を防ぐために液–液相分離して液滴を形成することがわかった.つまり,Sup35のアミロイドを形成してプリオンを引き起こす領域は,同時に,液滴を形成して細胞の飢餓ストレスに応答するために働いていたのである.このように,タンパク質の溶液物性に還元して生命現象を理解するのが相分離生物学の見方である.
1 0 0 0 OA 1942-43 年のルネ・シャール ―死の準備をする詩人―
- 著者
- 白石 幸作
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会関東支部
- 雑誌
- 日本フランス語フランス文学会関東支部論集 日本フランス語フランス文学会関東支部 (ISSN:09194770)
- 巻号頁・発行日
- pp.41-54, 2020 (Released:2021-08-19)
1 0 0 0 OA プラズマ照射した種籾への催芽処理の効果
- 著者
- 古閑 一憲 和田 陽介 徐 鉉雄 板垣 奈穂 白谷 正治 橋本 昌隆 小島 昌治
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理学会学術講演会講演予稿集 第78回応用物理学会秋季学術講演会 (ISSN:24367613)
- 巻号頁・発行日
- pp.1811, 2017-08-25 (Released:2022-10-29)
1 0 0 0 OA 0から1を創造したNANDフラッシュメモリ
- 著者
- 白田 理一郎 作井 康司
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.11, pp.644-654, 2023-11-01 (Released:2023-11-01)
- 参考文献数
- 24
(株)東芝を代表とする日本がNANDフラッシュメモリの技術革新を牽引(けんいん)した結果,iPhoneなどのスマートフォン,USB,SDカード,SSD(Solid State Drive)と広く応用されている.NANDフラッシュメモリは,小型で軽量,静音性に優れ,衝撃に強く,電源を切ってもデータを保持するという優れた特性を有している.NANDフラッシュメモリが発明されなければ,パソコンやスマートフォンの普及が遅れ,デジタル社会への転換も起こらなかったかもしれない.1980年代に東芝でたった10名のグループで研究開発を始めたNANDフラッシュメモリは,2022年には10兆円のビジネスに到達し,今やNANDフラッシュメモリの無い世界は想像できない.
- 著者
- 日方 希保 諸橋 菜々穂 樽 舞帆 鈴木 雄祐 中村 智昭 竹田 正裕 桑山 岳人 白砂 孔明
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.127-134, 2021-12-24 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 13
ミナミコアリクイ(Tamandua tetradactyla)は異節上目有毛目アリクイ科コアリクイ属に分類される哺乳類の一種である。コアリクイの計画的繁殖には,基礎的な情報の蓄積による繁殖生理の解明が必要である。これまでミナミコアリクイの妊娠期間中の血中ホルモン変動に関しては,1個体で1回分の妊娠期間についての報告がされているが,同一個体で複数回の妊娠期間中のホルモン変動に関する報告は存在しない。本研究では,同一雌個体のミナミコアリクイに対して長期間における経時的な採血(約1回/週)を実施し,同一雌雄ペアで合計6回の妊娠期間における血漿中プロジェステロン(P4)またはエストラジオール-17β(E2)濃度の測定を実施した。全6回の妊娠期間中のP4濃度測定の結果から,妊娠期間は156.8±1.7日(152~164日)と推定された。各時期のP4濃度は,妊娠前では0.6±0.1 ng/ml,妊娠初期(妊娠開始~出産100日以上前)では13.2±1.8 ng/ml,妊娠中期(出産50~100日前)では28.1±4.3 ng/ml,妊娠後期(出産日~出産50日前)では48.2±11.8 ng/mlであった。出産後のP4濃度は0.4±0.1 ng/mlと出産前から急激に低下した。血漿中E2濃度は妊娠初期から出産日に向けて徐々に増加した。また,妊娠期間前後で6回の発情周期様の変動がみられ,P4濃度動態から発情周期は45.5±2.4日(37~52日)と推定された。以上から,ミナミコアリクイの同一ペアによる複数回の妊娠中における血漿中性ステロイドホルモン動態を明らかにした。また,妊娠初期でP4濃度上昇が継続的なE2濃度上昇よりも先行して観察されたことから,P4濃度の連続的な上昇を検出することによって早期の妊娠判定が可能であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 第XIII因子
- 著者
- 一瀬 白帝
- 出版者
- 一般社団法人 日本動脈硬化学会
- 雑誌
- 動脈硬化 (ISSN:03862682)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.9, pp.533-538, 1996-04-10 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA ランサムウェアに対する一対策とその実装
コンピュータウイルスとかつて呼ばれたマルウェアの登場とその被害発生からほぼ半世紀,インターネットの隆盛とともマルウェアの被害はさらに深刻に,そして広範囲に渡るようになった.現在でもマルウェアへの対策はサイバー社会の安全安心に対して不可欠かつ最重要な課題なのである.ここ数年,ランサムウェアと呼ばれる,サーバやパソコンを含む端末デバイス上のデータを暗号化し,その復号鍵を質に,対価(身代金)を要求するマルウェアが流行している.<br>ランサムウェアは暗号化に際して,安全性が証明された外部の暗号ライブラリ等を利用して,公開鍵暗号方式と共通鍵暗号を組み合わせたハイブリット暗号方式で強固にデータを暗号化する.そのため,ランサムウェア感染後に暗号化されたデータを復号するのは困難である.<br>本研究では,ランサムウェアの感染時,その暗号化プロセスに対してDLLインジェクションすることで暗号化に用いられる暗号鍵を意図的に任意の秘匿鍵にすり替え,暗号化データの復号を容易にする手法について紹介する.さらに前述の機能実装とその評価についておこなった.
1 0 0 0 OA 稀な抗Ku抗体を保有した1症例
- 著者
- 山本 加代子 池部 晃司 白井 和美 笹谷 真奈美 水野 誠士 川尻 なぎさ
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.83, 2007 (Released:2007-12-01)
今回、外科領域の術中検査として検査した際に全てのパネルセルと反応する不規則性抗体が検出され、精査の結果、高頻度抗原に対する抗Ku抗体を保有した症例を経験したので報告する。高頻度抗原に対する抗体を保有する場合、ほとんどすべてのパネルセルと反応し陽性となるため、一般病院での同定や抗原陰性血の確保は困難である。このような場合、血液センターとの情報交換や連携が重要となり、主治医との迅速かつ的確な連絡を改めて示唆された1症例である。 <症例>患者 : 66歳 女性 妊娠歴あり 2子出産経験あり 現病歴:2006年12月 胃部不快感出現 2007年1月 食欲低下、体重減少のため他院受診 2007年2月1日 胃癌精査のため当院外科紹介受診 2月13日 膵臓、胃十二指腸摘出手術のため、輸血に備え、 タイプ&スクリーニング実施 既往歴:特になし <結果>ABO式血液型 O型 Rh式血液型 (+) 不規則性抗体(カラム凝集法)Pegクームス法、フィシン法 (2+)~(3+)陽性 抗体同定用パネルセルにて、Pegクームス法 自己対照以外すべて(3+)~(4+)陽性 レクチンH(3+)の反応 在庫MAP3本とのクロスマッチ Pegクームス法(4+) 上記の結果より、高頻度抗原に対する抗体の保有を疑い、広島県赤十字血液センターに精査を依頼した。その結果、ABO式、Rh式以外その他の血液型検査をさらに実施したところ、Kell式血液型がK-k-、Kp(a-b-),Js(a-b-)であり、抗Ku血清と患者血球との反応が陰性であることから、稀な血液型K0が疑われた。また、O型K0血球と患者血清との反応を確認したところ、生食法、ブロメリン法、Pegクームス法すべてにおいて陰性であったため、血清中には抗Ku抗体の存在があると考えられた。 <まとめ> 全てのパネルセルと反応することから高頻度抗原に対する抗体を疑い、血液センターに連絡し、精査と適合血の確保を依頼した。抗Ku抗体の存在が確認され、適合血が広島に解凍赤血球4単位あるとの連絡があった。主治医には高頻度抗原に対する抗体を保有しているため、適合血の確保が容易ではないことや、解凍赤血球の使用について説明した。高頻度抗原に対する抗体の同定は、一般病院では困難なため、血液センターとの情報交換や速やかな血液製剤供給体制のための連携が重要となると思われた。また今回の場合、術中および時間外に対応した症例であり、タイプ&スクリーニングの事前検査の重要性を再認識し、同定不能な時の適切な対応ができるマニュアルを備えておくことが重要と思われた。
本研究では,高等学校の共通教科「情報」および大学の一般情報教育において,主体的・対話的で深い学びを実現するために,体験的な学びを通して情報の科学的な理解を促進する教材と授業内外の学習活動を効果的に活用した授業モデル,ならびに多様な学びを対象とした自己調整学習支援環境を設計・開発し,その効果を検証することを目的とする。この目的を達成するために,(1)共通必履修科目「情報I」を対象に,体験的な実習教材および反転授業を取り入れた授業モデルの開発と評価,(2)新学習指導要領を踏まえた大学の一般情報教育の授業設計,(3) 多様な学習活動データに基づく自己調整学習支援環境の開発と評価に取り組む。
1 0 0 0 OA 生体親和性高分子PEGの弱い相互作用と、それを起点とする生体応答の解明
- 著者
- 白石 貢一
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.122-130, 2022-03-25 (Released:2022-06-25)
- 参考文献数
- 34
生体親和性ポリエチレングリコール(PEG)の製剤における有用性は周知の事実であるが、一方でPEGがもたらす生体応答に関心が高まっている。生体親和性を示すPEGの性質とPEGがもたらす抗PEG抗体産生という、一見すると、相反する性質は何によってもたらされているのだろうか。PEGは生体分子と弱いながらも相互作用を示すことが知られてきており、より特異的なPEGと抗PEG抗体という2つの分子の関係に着目すると、特異的相互作用と特異的相互作用に基づく、不可逆的な結合という2つの異なる相互作用に着目する必要がある。本稿では、PEGと抗PEG抗体との関係と、新たなアプローチの紹介を含めて概説する。
1 0 0 0 OA 腐骨除去により口腔鼻腔瘻孔を生じた骨軟化症の1例
- 著者
- 青野 淳子 遊佐 浩 石上 敏幸 白土 貴之 鬼澤 浩司郎 吉田 廣
- 出版者
- Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.179-182, 2002-03-20 (Released:2011-04-22)
- 参考文献数
- 12
A rare case of osteomalacia with an oronasal fistula developing after sequestrectomy is presented. The patient was a 45-year-old woman who was referred to our hospital because of an intractable ulcer at the midline of the hard palate. She had an edentulous maxilla and wore a poorly fitting complete maxillary denture. Oral examination showed ulceration with a sequestrum under the prosthesis. Removal of the sequestrum extending from the oral cavity to the nostrils resulted in an oronasal fistula of the hard palate. The case was finally diagnosed as osteomalacia based on the results of radiographic and serum chemical examinations. In this patient, continuous pressure caused by the poorly fitting maxillary denture induced the sequestrum in the hard palate, which was thin and fragile because of osteomalacia.
1 0 0 0 OA 外来「非自己」遺伝子の発現を抑制する仕組み
- 著者
- 白山 昌樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.534-540, 2013-08-01 (Released:2014-08-01)
- 参考文献数
- 21
小分子 RNA (small RNA) と呼ばれる非コードRNAは,標的RNAを検索することでRNA干渉 (RNAi) において中心的な役割を担う.しかしながら,これまでの研究から,小分子RNAのもつ役割はRNA干渉にとどまらず,ヒトを含む多くの生物で, 個体の発生や分化,がん化などの多彩な生命現象 に密接に関与していることが明らかとなってきた.ここでは,小分子RNAが「非自己」RNAを認識する仕組みについて最新の知見を交えながら解説する.
1 0 0 0 OA スプリンターネットを巡る議論
- 著者
- 実積 寿也 前村 昌紀 白畑 真 堀越 功 小宮山 功一朗 水越 一郎
- 出版者
- 一般財団法人 情報法制研究所
- 雑誌
- 情報法制レポート (ISSN:24356123)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.52-71, 2023-03-31 (Released:2023-08-29)
1 0 0 0 OA ドクツルタケ中毒による昏睡型急性肝不全に対し急性血液浄化療法を併用し救命しえた1症例
- 著者
- 吉田 省造 岡田 英志 土井 智章 中島 靖浩 鈴木 浩大 田中 卓 福田 哲也 北川 雄一郎 安田 立 水野 洋佑 宮﨑 渚 森下 健太郎 牛越 博昭 竹村 元三 白井 邦博 豊田 泉 小倉 真治
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.129-135, 2015 (Released:2015-02-28)
- 参考文献数
- 24
症例は50歳代の男性, キノコ狩りに行きキノコを焼いて食べた翌日に下痢・嘔吐などの消化器症状を自覚し近医を受診. 血液検査にて肝逸脱酵素上昇を認め入院となった. 翌日の採血で肝逸脱酵素の著明な上昇 (AST 5,000台, ALT 5,000台) を認め, 当院に搬送となった. 問診によりドクツルタケ摂取による肝障害を疑った. 入院当日より肝性脳症を認め, 昏睡型急性肝不全と診断. 挿管・人工呼吸管理として, 肝不全治療と同時に毒素除去, 高分子除去を目的として急性血液浄化療法を行った. 入院5日後に肝性脳症は改善し呼吸状態は良好で抜管, 経過良好にて入院9日後に転院となった. ドクツルタケ中毒における血液浄化療法は否定的な意見が多いが, 今回は肝不全を呈したドクツルタケ中毒に対し, 血液浄化療法を行い救命し得た. ドクツルタケの中毒を疑った場合には, 早急な血液浄化療法が有効である可能性が高いと考えられた.
1 0 0 0 OA 近代文化のハイブリッド化と民主化 N・ガルシア=カンクリーニの理論を手掛かりに
- 著者
- 白石 真生
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.75-91,178, 2012-06-30 (Released:2015-05-13)
- 参考文献数
- 28
This paper examines the theory of hybridization formed by the Mexican cultural theorist Néstor García Canclini. My aim is to highlight the analytical implications that Latin American hybrid cultures have for cultural studies in general, through clarifying the theoretical and political significance of hybridization analyzed in Hybrid Cultures. In the first chapter, I briefly explicate the analytical significance of García Canclini’s theory of hybridization. In the second chapter, I overview the conceptual constellation of popular cultures in British cultural studies and reexamine it from the vantage point of Latin American cultural studies. By doing this, it becomes clear that careful attention must be paid to the ambiguity of both popular cultures and mass culture, and that their interaction must be a focus of cultural analysis. In the third chapter, I take up the phenomenon of hybridization which now blurs the oppositional schema of modern culture. According to García Canclini, hybridization is propelled, on the one hand, by the capacity for appropriation of popular culture, and, on the other, through the mediating force of mass culture which transcends the boundaries and disrupts the purity of modern culture. In the fourth chapter, I locate the possibility of cultural democratization in the hybridization of cultures which is often seen as contamination or degradation. In the fifth and final chapter, I demonstrate the faults of anti-essentialist criticism of hybridity. By so doing, I posit specifically the theoretical possibility of Garcia Canclini’s theory. Although hybridization of cultures is not specific to Latin American societies, only there has it developed to such an extent that it almost breaks down the hierarchy of modern culture. It is the specific potentiality of Latin American modernity to fight against the hegemony of Culture.
1 0 0 0 OA 帝王切開術における癒着防止剤セプラフィルム®の効果に関する検討:前方視的コホート研究
- 著者
- 信正 智輝 池田 真規子 黄 彩実 別宮 史子 白神 碧 松井 克憲 高石 侑 増田 望穂 松尾 精記 安堂 有希子 佐藤 浩 田口 奈緒 廣瀬 雅哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.282-288, 2022 (Released:2022-09-09)
- 参考文献数
- 20
[目的]セプラフィルム®の帝王切開術における癒着防止効果を前方視的に検討した. [方法]初回帝王切開術を当科で施行し,今回2回目の帝王切開術を予定している症例を対象とした.臨床背景,癒着の程度,および母児の転帰をセプラフィルム®使用群と非使用群で比較検討した. [結果]初回,2回目とも当科で帝王切開術を施行した136例から,初回帝王切開術を妊娠32週未満に実施した14例と今回の帝王切開術で術中の癒着評価記録が行われなかった4例を除く118例を解析対象とした.解析対象の118例を初回帝王切開術時セプラフィルム®使用群(46例)と非使用群(72例)で比較検討した.セプラフィルム®使用群で大網-腹壁間,あるいは子宮-大網間に2度以上の癒着を有するものは有意に少なかった.執刀-児娩出時間,総手術時間,術中出血量,臍帯動脈血pHに差は認めなかった. [結論]セプラフィルム®による大網が関連する中等度以上の癒着を抑制する効果を認めたが,母児の臨床転帰に差は認めなかった.