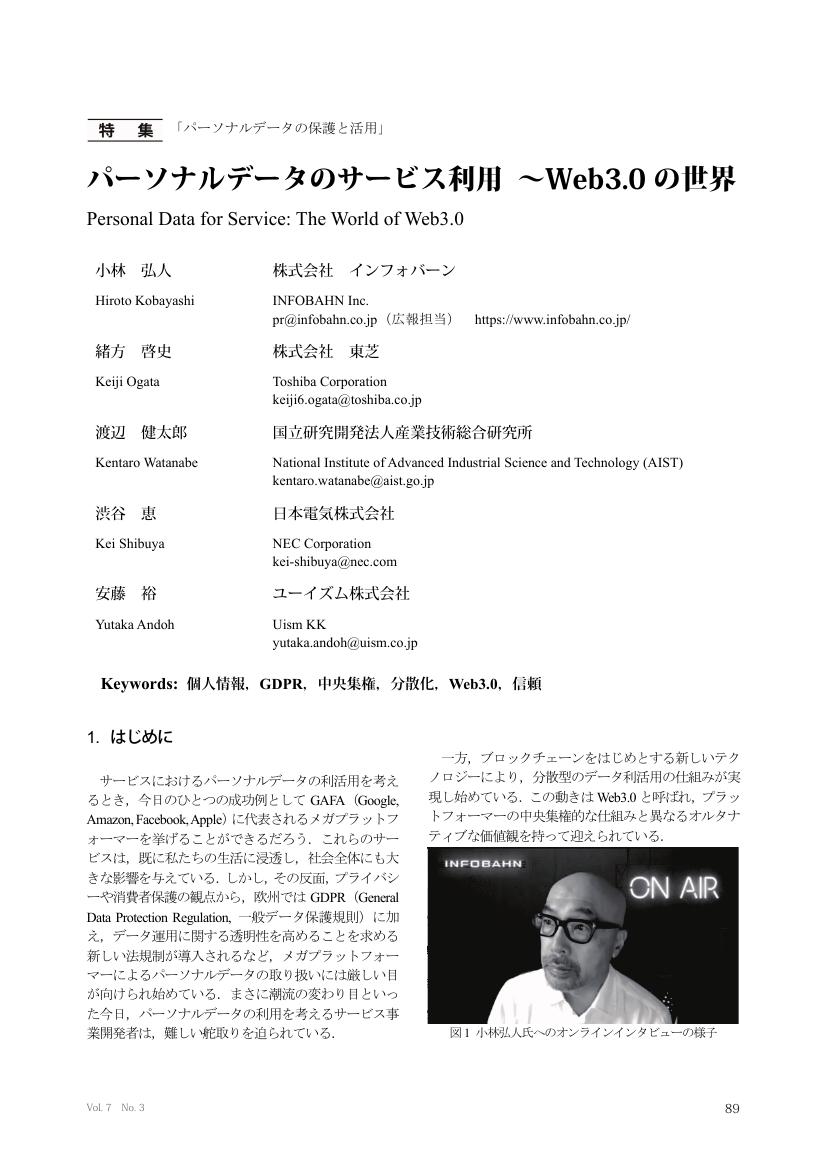1 0 0 0 OA 自然知能が提示する究極のエネルギー変換、光合成
- 著者
- 畠山 允 緒方 浩二 中村 振一郎
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.223-229, 2018-10-31 (Released:2019-10-31)
- 参考文献数
- 27
植物とシアノバクテリアの酸素発生中心について筆者らの考究と理論計算の結果を紹介する.特に酸素発生と水分解は光誘起電荷分離の結果として生じるという観点から,正電荷の担体たる正孔がプロトンに変換される事実を焦点にして酸素発生中心を議論する.酸素発生中心を形作る原子軌道や内外の水素結合ネットワークが如何にして電荷を整流するか,その滲み出しの詳細理解に迫る試みの一端として筆者らの古典分子動力学計算と量子化学計算により得られた骨子を述べる.
- 著者
- 永野 みどり 緒方 泰子 徳永 恵子 石久保 雪江 石田 陽子
- 出版者
- 一般社団法人 日本創傷・オストミー・失禁管理学会
- 雑誌
- 日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌 (ISSN:1884233X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.293-304, 2014 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 34
褥瘡対策体制における皮膚・排泄ケア認定看護師(以降WOCNと略す)の「病院全体の褥瘡ケアの質に対する主観的影響力」と「褥瘡発生率」に関連する褥瘡対策の構造的な要件や効果的な取り組みを明らかにする目的で、同意を得た425病院に対し、WOCNとその直属上司である看護管理者宛に、質問紙調査を実施した。回答の欠損が少ない200床以上の急性期病院166施設を分析対象とした。 「WOCNの褥瘡ケアの質に対する主観的影響力」に関連する要件として、「WOCNの臨床経験が21年以上」であるというWOCNの個人属性が強く関連していた。「院長の部門間調整」や「認定看護管理者として認定されている看護管理者」「看護管理者のWOCNへの評価」といった管理者の関与に関連があり、その重要性が示唆された。「WOCNの情報発信力」で「褥瘡ケアの質に対する主観的影響力」が強まり、それにより病棟看護師の「医療関連機器圧迫創傷」や「褥瘡対策チームとの連携」の意識が高まると考えられた。 「褥瘡発生率」に有意に関連する取り組みは、「WOCNの褥瘡保有死亡患者の把握」「WOCNの褥瘡のケア技術への自信」「地域の開業医との信頼関係」であった。「十分なWOCNの数」「病棟看護師の医療関連機器圧迫創傷への認識」「OT/PTの関与」も関連していた。 WOCNの「病院全体の褥瘡ケアの質に対する主観的影響力」を成果指標とすることで、「褥瘡発生率」には反映できない部分の褥瘡対策の質が把握できると推察された。
1 0 0 0 OA 予防薬として五苓散を用いた片頭痛の1症例
- 著者
- 緒方 裕一 濵田 高太郎 平井 慎理
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.345-346, 2020-10-25 (Released:2020-10-28)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 外来血液透析患者におけるカルニチン代謝障害の現状についての検討
- 著者
- 松坂 貫太郎 緒方 浩顕 山本 真寛 伊藤 英利 竹島 亜希子 加藤 雅典 坂下 暁子
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.389-396, 2019 (Released:2019-11-08)
- 参考文献数
- 16
血液透析患者では,摂取不足,腎での生合成の減少や透析療法による除去などのためにカルニチンが極めて高頻度で欠乏すると報告されており,カルニチン欠乏がさまざまな腎不全合併症(エリスロポエチン抵抗性貧血,低左心機能や筋痙攣等)に関与することが想定されている.本研究ではカルニチン代謝障害の実態を検討するため,カルニチン静脈投与の有効性を検証する前向き観察研究(「透析患者の合併症に対するL-カルニチン静注製剤の有効性の検討」)に登録された昭和大学横浜市北部病院およびその関連施設の外来血液透析患者501名に対して,血中カルニチン分画を測定し,その関連因子を横断的に検討した.主要評価項目として遊離カルニチン(Free)濃度とアシルカルニチン濃度/Free濃度(A/F比)を解析した.Free濃度を3群間(充足群(36≦Free≦74µmol/l),不足群(20≦Free<36µmol/l),欠乏群(Free<20µmol/l))に分類したところ,充足群は全体のわずか8.4%であり,A/F比も>0.4が98.8%と,ほとんどの患者がカルニチン代謝障害を合併していた.Free濃度とA/F比それぞれに関連する因子を多変量解析で検討したところ,カルニチン代謝障害と血清尿素窒素濃度(SUN),透析歴,性別,アルブミン,リンや標準化タンパク異化率(nPCR)との間に有意な関連がみられた.一方,血液透析療法の差異(血液透析と血液ろ過透析)は,カルニチン代謝障害に関連していなかった.興味深いことに,ともに栄養状態,タンパク摂取状況の指標とされるSUNとnPCRがFree濃度との関連では全く反対の関連性を示したことである.透析患者におけるカルニチン代謝障害の病態生理について更なる検討が望まれる.
1 0 0 0 OA インフリキシマブ二次無効の機序と対策,治療方針
- 著者
- 金井 隆典 松岡 克善 久松 理一 岩男 泰 緒方 晴彦 日比 紀文
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.3, pp.364-369, 2012 (Released:2012-03-05)
- 参考文献数
- 20
インフリキシマブ治療はクローン病治療に革命をもたらしたといっても過言ではない.しかし,治療経過中に効果が減弱するいわゆる二次無効について国内外で活発に議論がなされている.本邦でも,2011年,インフリキシマブの10mg/kgへの増量が承認され,二次無効症例に対して直接的な対処が可能になった.しかし,10mg/kg増量ですべての二次無効症例が再び8週間隔の維持治療で寛解を維持できるまで効果が回復するとは限らない.また,本邦では2番目に登場したアダリムマブとの治療優先に関する議論,アダリムマブ増量の議論,さらには本邦オリジナルな白血球除去療法,栄養療法との併用など,長期の寛解維持を達成させるための適切な薬剤選択,適切な増量のタイミングを明らかにすることが重要である.
1 0 0 0 OA 児童虐待は犯罪現象か福祉課題か? —大学生ならびに専門職の心的表象—
- 著者
- 緒方 康介 籔内 秀樹 反中 亜弓 吉田 花恵
- 出版者
- 日本犯罪心理学会
- 雑誌
- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.31-42, 2022-01-31 (Released:2022-02-21)
- 参考文献数
- 17
The purpose of this study was to examine mental representations with respect to child abuse and neglect. In particular, we focused on whether child maltreatment is more strongly associated with being a crime or a welfare issue. Study I included 220 university students and 44 correctional experts. They were made to rate the extent to which five practical psychologies were related to five child clinical issues. Multi-dimensional scaling (MDS) showed that (1) child maltreatment posited between Psychology for Human Services (PHS) and Forensic and Criminal Psychology (FCP) in university students, and (2) child abuse and neglect was close to PHS in correctional experts. Study II consisted of 46 university students who were measured twice, before and after a lecture regarding child abuse and neglect. Individual analysis of the MDS results revealed that knowledge about child maltreatment could make PHS closer to but remain the closest between FCP and child abuse and neglect. Study III included 197 university students who were required to select the better procedure (social welfare or forensic) for maltreated children. We found that they reported significantly more of the former than the latter and concluded that university students have a mental representation of child abuse and neglect being a crime, not a welfare issue.
1 0 0 0 線形時相論理モデル検査の分割統治による並列化
- 著者
- 緒方 和博
- 出版者
- 北陸先端科学技術大学院大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
我々の生活を便利にするシステムは高信頼であるべきだ。さもなければ、多額の財産を失う等の多大な不便をこうむることになる。システムを高信頼にするために使うことのできる技術のひとつはモデル検査である。システムが期待される要件を満たすかどうかを自動で検証出来る。しかし、システムの到達可能状態空間が大きくなり過ぎてモデル検査不能になる問題が起こる。本研究計画では、到達可能状態空間を複数の部分空間に分割し、各々の部分空間でモデル検査を行えるようにすることでこの問題を緩和することを試みる。加えて、複数の部分空間に対するモデル検査を同時並列に実行することでモデル検査の効率化も試みる。
1 0 0 0 OA 独居高齢者への災害対策の情報提供における研究
- 著者
- 西尾 美登里 坂梨 左織 木村 裕美 久木原 博子 緒方 久美子 古賀 佳代子
- 出版者
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会
- 雑誌
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 (ISSN:13451537)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.23-28, 2018-05-19 (Released:2021-03-15)
福岡市の高齢者における地域の災害避難場所の認知について, 実態調査を行い, 独居高齢者への災害支援のありかたについて検討した. 地域包括ケアシステムと介護の啓発を目的とした集会の参加者258 名を分析対象とし, 基本属性, フォーマルな相談窓口の認知と活用の有無, 活用している相談窓口数, 地域の避難場所の認知, 楽しみの有無, 情緒的支援, 自尊感情尺度について調査した. 分析は同居群と独居群の2群の差のカテゴリ変数にはχ2 検定, 連続変数にはMann–Whitney U 検定行い群間差を検定した. その結果, 独居高齢者は同居者がいる高齢者より有意に高齢で, 公の相談窓口を知らず, 相談談窓口数が少なく, 避難場所を知らず, 楽しみを有さず, 情的支援を受けていなかった. 都市部における高齢者への災害支援を充実させるためには, 特に独居高齢者が情的な交流のある生活の中で, 楽しみながら社会活動ができる場づくりを行う必要がある. また, 災害支援の情報提供は,社会活動ができる場で行うことが有益であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 虚弱高齢者における転倒リスクの評価・予測に関する研究 記述式の評価用紙を用いて
- 著者
- 緒方 悠一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会 九州ブロック会
- 雑誌
- 九州理学療法士学術大会誌 九州理学療法士学術大会2021 (ISSN:24343889)
- 巻号頁・発行日
- pp.71, 2021 (Released:2022-02-03)
【目的】簡易的な方法で転倒リスクを評価・予測する【はじめに】要介護状態の主要な原因の一つである転倒1)は、諸々の要因が相互に影響することが知られており2)転倒リスクを評価することは極めて重要である。そこで、記述式の評価用紙を用いて簡易的に転倒リスクを評価・予測できる方法を検討した。【対象および方法】対象は、社会医療法人玄州会パワーリハビリセンター利用中の42 名とした。全員が地域支援事業対象者であった。対象者には本研究の内容を十分に説明し、紙面にて同意を得た。なお、本研究は、当法人の倫理審査委員会の承認を得て実施した。å 方法は記述式の評価用紙を用いた。転倒リスクについては、高齢者の転倒リスク簡易評価表3)を用い、7点以上を高い群、6点以下を低い群とした。評価スケールは服薬中の薬数、HLS-14、Home-ExerciseBarrierSelf-EfficacyScale、生活の広がり、転ばない自信、自宅での入浴動作、休まずに歩ける距離、人とのつながり、Motor Fitness Scale(以下、MFS)を使用した。なお、統計学的解析はSPSS で二項ロジスティック分析を用い、有意水準は5% とした。【結果】二項ロジスティック分析の結果、転倒リスクに有意な関連因子としては、MFS(オッズ比0.704、95% 信頼区間0.539-0.920)が抽出され、その他の項目に関して有意性は得られなかった。また、判別の的中率は77.1%、Hosmer とLemeshow の検定による有意確率0.7 であった。【考察】MFS は、衣笠らが開発した要介護認定リスクを予測するツールである。細川らは、体力検査を行わなくても転倒の発生を予知できる可能性があると述べている。4)本研究では、地域支援事業対象者42 名に対し記述式の評価用紙にて回答を得た。その結果、MFS が転倒リスクを予測する指標となることが示唆された。転倒に関する大規模研究のレビューを行ったルベンスタインは、筋力低下、バランス欠如、歩行障害、移動障害、ADL 障害は殆どすべての研究で一致した危険因子であると述べている5)。MFS は移動、筋力、バランスなどの身体機能を主に評価しており、ルベンスタインが述べた危険因子と考えられる要因を全て評価できるため有意性が出たのではないかと考える。【まとめ】MFS を使用し転倒リスク評価を行った結果、有用性のある指標であると考えられる。また記述式の評価となるため、転倒予防教室において理学療法士1名が対応できる参加人数の拡大が期待できる。【文献】1)厚生労働省「国民生活基礎調査」2019 年2)日本転倒予防学会誌Vol.3 No3:5-10 20173)鳥羽研二他 日老医誌2005:42:346-3524)細川 徹,長崎 浩,衣笠 隆・他:高齢者におけるMotor Fitness Scaleと体力測定との関係.厚生省長寿科学総合研究,1998, 135-1385)Rubenstein LZ:Falls.In:Yoshikawa TT eds. Amebula-tory Geriatric Care:1993【倫理的配慮,説明と同意】本研究の立案に際し、事前に所属施設の倫理審査委員会の承認を得た。(承認日2019 年9 月2 日)。また研究の実施に際し、対象者には本研究の内容を十分に説明し、紙面にて同意を得た。
1 0 0 0 食物アレルギー患者へのエピペン®処方症例の検討
- 著者
- 佐藤 さくら 田知本 寛 小俣 貴嗣 緒方 美佳 今井 孝成 富川 盛光 宿谷 明紀 海老澤 元宏
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.187-195, 2007-06-01 (Released:2007-12-26)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 4 2
アナフィラキシー補助治療薬のエピペン®が我が国で発売され,2004年5月から2005年10月まで当科で同薬を処方した食物アレルギー患者は50名(男33名,女17名,0.3mg:15名,0.15mg:35名)に上る.対象の平均年齢は6.8歳でアトピー性皮膚炎合併が78%,気管支喘息合併が52%であった.原因食品摂取時に呼吸器症状を96%,皮膚症状を92%に認めた.アナフィラキシー症例は48例で,食物アレルギー発症時の臨床型は36例が“食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎”,即時型症状8例,食物依存性運動誘発アナフィラキシー4例であった.アナフィラキシーを起こした理由は,初回,2回目以降も誤食によるものが最多であった.アナフィラキシー反復例は31例で,複数抗原に対してアナフィラキシーを起こした例や原因不明例も存在した.今回の処方50例中実際に使用された例は1例あり,17歳のナッツアレルギー患者において使用され著効していた.医師,コメディカルにおいてまだ認識が不十分なエピペンであるが,アナフィラキシーを起こす可能性のある食物アレルギー児に対して保護者と相談の上で処方していくべきである.
1 0 0 0 OA 佐藤超函数論に基づく数値積分 (現象解明に向けた数値解析学の新展開 II)
- 著者
- 緒方 秀教
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.2037, pp.57-60, 2017-07
手術侵襲・麻酔薬が、自然免疫において中心的な役割を持っている食細胞(単球・マクロファージ、好中球)の機能に与える影響を検討することが今回の研究目的である。食細胞の機能活性化はミトコンドリアによるエネルギー産生によるところが大きい。ミトコンドリアの呼吸鎖により産生されるATPは、食細胞機能を活性させることが近年報告されている。そこで、ミトコンドリアのエネルギー産生、活性化、形態に与える手術侵襲・麻酔薬の影響を検討することにした。麻酔薬が単球、好中球のミトコンドリア機能に与える影響について検討した。様々な濃度の局所麻酔薬(リドカイン、メビバカイン、ブプバカイン、ロビバカイン)とともに、健常成人から採取した末梢血から分離した単球、好中球を数時間培養した。培養後、貪食能、細胞内ATP濃度測定、蛍光標識されたマーカーによるミトコンドリア機能評価、ミトコンドリア形態評価をおこなった。リドカインは、貪食能を有意に低下させた。更に、リドカインは、細胞内ATP濃度や、ミトコンドリア膜電位をコントロールに比べて、有意に低下させ、アポトーシスをひきおこした。他の局所麻酔薬は、このような作用は認められなかった。リドカインは、ミトコンドリア機能を低下させて、自然免疫を抑制する作用があることがわかった。更に、静脈麻酔薬について、同様の研究を行った。プロポフォールは、濃度依存性に好中球ミトコンドリア機能を低下させる傾向が見られたが、有意な差は認められなかった。また、手術中の胸部硬膜外麻酔により、上腹部開腹術で、周術期の自然免疫能低下を抑制するかどうか調べた。手術侵襲により、TNF産生能、貪食能は有意に低下したが、殺菌能は低下しなかった。胸部硬膜外麻酔でも、全身麻酔と同様に、手術侵襲による自然免疫能低下がおこった。好中球アポトーシス及びミトコンドリア機能に関しては、個人差が大きく、現在も研究中である。
1 0 0 0 OA 抜歯後出血を契機として明らかとなった慢性播種性血管内凝固症候群の1例
- 著者
- 太田 美穂 松原 良太 川野 真太郎 大部 一成 緒方 謙一 中村 誠司
- 出版者
- 日本口腔内科学会
- 雑誌
- 日本口腔内科学会雑誌 (ISSN:21866147)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.47-51, 2014 (Released:2015-09-06)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 2
抜歯後出血は局所的要因に起因することが多いが,出血性素因から生じる場合もある。本報告は,80歳代女性の抜歯後出血を契機に明らかとなった慢性播種性血管内凝固症候群(DIC)の1例である。血液検査でDICに起因する止血凝固異常と診断され,トロンボモジュリン製剤投与にてDICは改善したが,その原因となる基礎疾患は認められなかった。治療終了後は経過観察を行っているが,DICの再燃なく経過良好である。
1 0 0 0 OA 人生の最終段階における医療に関する自己決定権と法制度設計 ~刑事法的視点から~
- 著者
- 緒方 あゆみ
- 出版者
- 中京大学法務研究所
- 雑誌
- 中京ロイヤー = CHUKYO LAWYER
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.1-22, 2022-03-01
1 0 0 0 OA Supra-annular MVR を行った乳幼児の2例
- 著者
- 重久 喜哉 松葉 智之 上田 英昭 緒方 裕樹 井本 浩
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会
- 雑誌
- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.157-161, 2018-07-15 (Released:2018-08-09)
- 参考文献数
- 4
乳幼児の僧帽弁疾患で僧帽弁形成術が困難な症例では僧帽弁置換術(MVR)が必要となるが,弁輪より過大な人工弁を用いてMVRを行うためには大きさの違いを解消するための工夫を要する.今回われわれはSungらの方法を参考にし,expanded polytetrafluoroethylene(ePTFE)graftを人工弁のスカートとして使用した弁輪上部僧帽弁置換手術(Supra-annular MVR)を2例の乳幼児に施行した.症例1は1歳4カ月,6.7 kg,Shone症候群,僧帽弁狭窄症,パラシュート僧帽弁,大動脈縮窄症,心室中隔欠損症の男児.大動脈縮窄症修復術,心室中隔欠損閉鎖術後に僧帽弁狭窄症が顕在化しMVRを行った.症例2は5カ月,4.9 kg,多脾症,中間型房室中隔欠損症,左側房室弁閉鎖不全症の女児.3カ月時に心内修復術を行ったが,術後徐々に左側房室弁狭窄兼閉鎖不全症が進行し弁置換術を施行した.いずれの症例も術後の人工弁機能は良好であり,今回行った方法によるSupra-annular MVRは乳幼児の狭小な僧帽弁輪に対し有用な手術手技と考えられた.
1 0 0 0 OA フラボノイドのスギ花粉症に対する有効性
- 著者
- 田中 敏郎 平野 亨 河合 麻理 萩原 圭祐 有光 潤介 桑原 裕祐 嶋 良仁 緒方 篤 川瀬 一郎
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会総会抄録集 第36回日本臨床免疫学会総会抄録集 (ISSN:18803296)
- 巻号頁・発行日
- pp.98, 2008 (Released:2008-10-06)
アレルギーの有病率を高めている一環境要因として、抗酸化物質の摂取不足や不適切な脂質の摂取など食生活の変化が注目されている。フラボノイドは、抗酸化作用、抗アレルギー作用(肥満細胞や好塩基球からの化学伝達物質、サイトカイン分泌、CD40リガンドの発現を抑制)を有する機能性物質であり、フラボノイドの摂取がアレルギー症状の軽減や予防法となり得るのか、臨床研究を施行した。平成19~20年度にかけて、プラセボ対照二重盲検群間比較試験により、フラボノイド(酵素処理イソケルシトリン一日100mg)のスギ花粉症状に対する有効性を、症状スコア、血中サイトカイン、IgE及び抗酸化指標にて検討した。平成19年度においては、花粉飛散後より試験を開始(治療試験)、平成20年度には、花粉飛散前より試験(予防試験)をそれぞれ8週間行った。両試験において、総症状スコアはフラボノイド摂取群で抑制される傾向にあり、眼症状に関しては、統計学的有意にフラボノイド摂取群で抑制されていた。IgEやサイトカイン(TARC以外)値は試験前後で変化を認めなかったが、酸化物質(hexanoyl-lysineやoxidized LDL)はフラボノイド群で低下傾向を示した。以上の事は、適切なフラボノイドの摂取がアレルギー疾患に対する補完代替療法や予防法となる可能性を示唆する。
- 著者
- 緒方 康介 籔内 秀樹 反中 亜弓 吉田 花恵
- 出版者
- 日本犯罪心理学会
- 雑誌
- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.31-42, 2022
<p>The purpose of this study was to examine mental representations with respect to child abuse and neglect. In particular, we focused on whether child maltreatment is more strongly associated with being a crime or a welfare issue. Study I included 220 university students and 44 correctional experts. They were made to rate the extent to which five practical psychologies were related to five child clinical issues. Multi-dimensional scaling (MDS) showed that (1) child maltreatment posited between Psychology for Human Services (PHS) and Forensic and Criminal Psychology (FCP) in university students, and (2) child abuse and neglect was close to PHS in correctional experts. Study II consisted of 46 university students who were measured twice, before and after a lecture regarding child abuse and neglect. Individual analysis of the MDS results revealed that knowledge about child maltreatment could make PHS closer to but remain the closest between FCP and child abuse and neglect. Study III included 197 university students who were required to select the better procedure (social welfare or forensic) for maltreated children. We found that they reported significantly more of the former than the latter and concluded that university students have a mental representation of child abuse and neglect being a crime, not a welfare issue.</p>
1 0 0 0 LC/MS/MSによる屋久島ニホンザル糞便中の代謝物測定
<p>次世代シーケンサーを用いた野生動物糞便細菌の網羅解析が盛んに行われている。宿主の生活を反映した細菌叢構成の差異を検出することができるようになったものの,解析対象が「PCR増幅された16S rRNA遺伝子の部分配列に基づく不十分な系統情報」にすぎないため,宿主の生理状態に直接影響する腸内環境を知ることはできない。近年,分子量データーベースの充実からHPLCやCEと質量分析を組み合わせた化合物の網羅解析が発達し,腸内細菌叢が産生する代謝物を網羅的に解析することが可能となった。これを一般にメタボローム解析と呼ぶが,野生動物の生理研究や生態研究における本解析手法の有用性を報告する。屋久島西部林道上の2地域(川原と鹿見橋)で,群れを異にするニホンザル計5頭の糞便を採取した。2検体を除き排泄直後に採取し,全量をドライアイス上で直ちに凍結した。1検体は,前日の排泄糞で発見後直ちに凍結した。もう1検体は,2分割してそれぞれ排泄直後と1時間放置後に凍結した。解凍後,Matsumotoら(<i>Sci Rep</i> <b>2</b>: 233)の方法で前処理し測定試料とした。LCMS-8060(島津製作所)にPFPPカラムを装着し,0.1%ギ酸水溶液と0.1%ギ酸アセトニトリル溶液を移動相としてイオンペアフリー条件のグラジエント分析を行った。遊離アミノ酸のほか,ヌクレオチド, ヌクレオシド、核酸塩基などの核酸代謝物,TCA回路に関わる有機酸等全体で63成分が検出された。PCA解析を行うと,川原の古い糞,川原の新鮮糞,鹿見橋新鮮糞の3つにクラスターが分離した。前日由来の糞の水溶性成分は変化していたが,新鮮糞の水溶性成分については1時間放置の影響はなかった。鹿見橋周辺の群れから採取した糞は川原で採取した糞よりも必須アミノ酸が少なく,逆に核酸代謝産物濃度が高い傾向が見られた。</p>
1 0 0 0 OA パーソナルデータのサービス利用 ~Web3.0の世界
1 0 0 0 IR 語彙知識マップを用いた多読用絵本推薦システム
- 著者
- 滝井 健介 フラナガン ブレンダン 緒方 広明
- 出版者
- 情報処理学会 教育学習支援情報システム(CLE)研究会
- 雑誌
- 第32回教育学習支援情報システム研究発表会(CLE32)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.6, 2020-11-27
外国語としての英語学習において,多読が様々な言語スキルにもたらす学習効果は広く理解されている.また,教育や学習における授業・教材の推薦システムは多数開発されているが,学習効率の向上や個人レベルでの推薦の実現を目指したものは多くない.本研究では,様々な概念を関連するもの同士で繋いだ知識マップを活用した,多読用の絵本推薦システムを提案する.これは,学習者の英語の学習効率の向上と個人の英語スキルに合った推薦を目指すものである.また,本システムが学習者の英語スキルにもたらす影響を調査するための実験方法についても提案する.