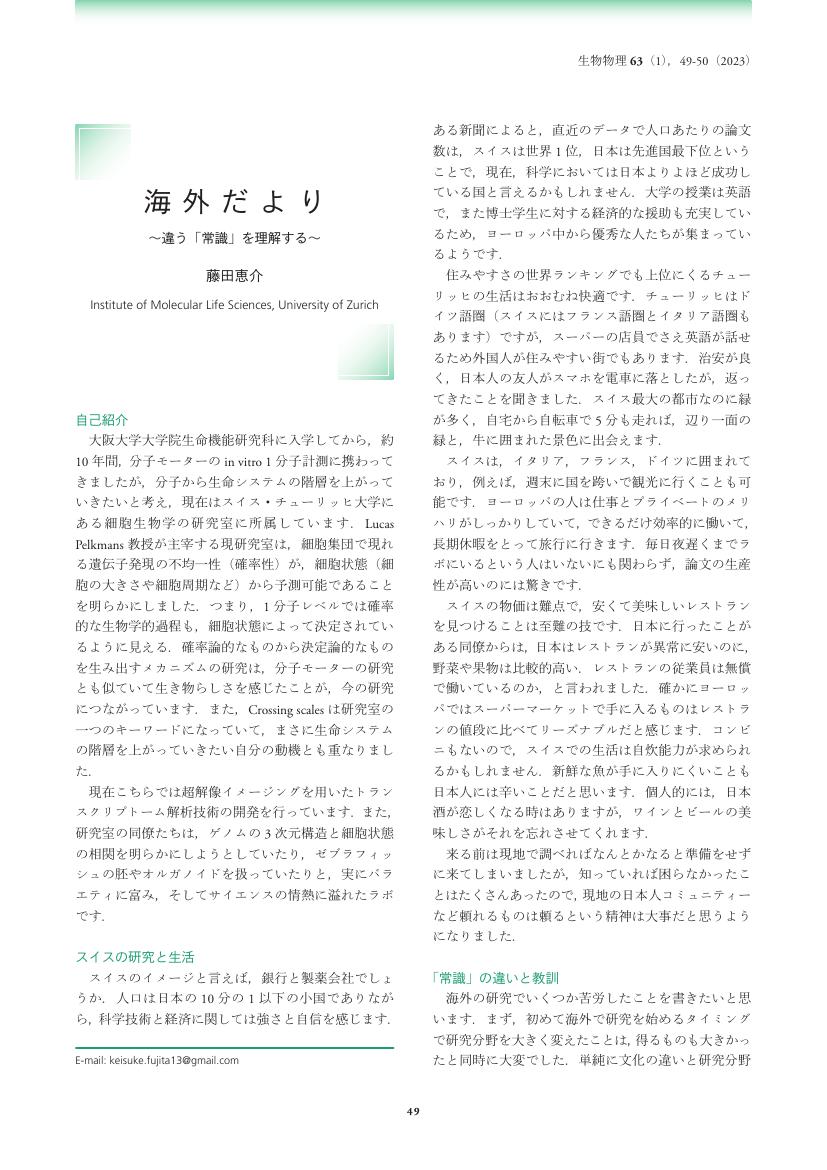4 0 0 0 OA 日本語能力試験における点字冊子試験のユニバーサル化に向けた基礎的研究
2 0 0 0 OA 清涼飲料水が象牙質の硬度に与える影響
- 著者
- 藤田 恵未 犬飼 順子 中垣 晴男 向井 正視
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.280-285, 2013-04-30 (Released:2018-04-06)
- 参考文献数
- 21
多様化した生活習慣や高齢社会に伴い口腔内に象牙質が露出した者は多い.しかし象牙質の酸蝕症と飲料の関係は明確ではない.本研究では飲料が象牙質の酸蝕に与える影響を歯の酸蝕症の評価方法の一つであるヌープ硬さにより検討した. ヒト象牙質をオレンジジュース,グレープフルーツジュース,ヨーグルト飲料,炭酸飲料,蒸留水の5種試験飲料に浸漬し,経時的に試料のヌープ硬さを測定した.また,浸漬30分後の試料は二次電子像観察を行った.結果は経時的に一元配置分散分析およびTukey HSDの多重比較を行った. 各飲料別のヌープ硬さは浸漬2分後は飲料間に有意差はなく,5分後では蒸留水とグレープフルーツジュース間,および蒸留水と炭酸飲料間で有意差があり,15分後では蒸留水と炭酸飲料間,蒸留水とオレンジジュース間,および蒸留水とヨーグルト飲料間に有意差が認められた.また,30分後では飲料間では有意差は認められなかったものの,すべての飲料は蒸留水と有意差があり,二次電子像も異なっていた. 象牙質はエナメル質と比較して結晶構造や化学的性状が異なり硬度が小さく,耐酸性が低いため,pH値の低い飲料に浸漬すると飲料の種類によらず速やかに脱灰が開始し,飲料間のヌープ硬さに有意差がなかったと考える.したがって,清涼飲料水は象牙質の酸蝕症の要因となるため,象牙質の露出した者には象牙質の酸蝕症予防として,緻密な歯科保健指導が必要であると考える.
2 0 0 0 OA 女子上半身原型製図法の変遷 (第2報) 第二次大戦後から1970年まで
- 著者
- 藤田 恵子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.33-42, 2001-01-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 45
The purpose of this study is to clarify the historical changes in drawings of the upper trunk of women from the end of the Second World War to 1970. This period is often called the dressmaking boom. One hundred fifty-four basic patterns for women's upper trunks were extracted from 129 books, including sewing publications, textbooks, and nine different kinds of magazines, all of which were published between 1946 and 1975. Then the changing process of the patterns was analyzed. The results are as follows : Many methods of basic pattern making were published in magazines and textbooks for high schools. Therefore, the use of basic patterns for dressmaking took root among ordinary people in this period.In particular, the “Bunka style” and “Doreme style” basic patterns became well-known with the increasing number of sewing schools and monthly fashion magazines.After 1966, drawings which covered the shoulder and breast swell three-dimensionally started to appear.Based on this research this period can be called the “Period of Establishment of Basic Pattern Making of Women's Upper Trunks.”
2 0 0 0 OA 明治前期の男子服技法書におけるThe Tailor’s guide
- 著者
- 笹﨑 綾野 藤田 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.11, pp.739-745, 2018 (Released:2018-12-01)
- 参考文献数
- 55
This report aims to clarify how the methods of measurement in the drafting method of The Tailor's Guide by C. Compaing and L. Devere were interpreted and received in men's clothing technique manuals of the early Meiji era, through its translation, “A Teacher's Guide to Western Sewing.” Based on C. Compaing and L. Devere's book and the original book by G. Compaing, improvements in the process and features of the measurement charts, measured items, and the graduated measurement techniques were shown. The sources of The Tailor's Guide were tailors in France, and their techniques were reaching maturity. In particular, the selected measurement items and the graduated measures were the cornerstones for the improvement of clothing designs from individual sizes to a general-purpose design. In men's clothing technique manuals of the early Meiji era, the techniques of The Tailor's Guide were partially used, but were not accompanied by the knowledge and technology required to introduce them fully. The Tailor's Guide was positioned as a textbook aimed at introducing techniques to the general public.
2 0 0 0 OA 幕末から明治維新期の日仏両国関係からみた男子服意匠の経緯と実態
- 著者
- 徳山 孝子 打田 素之 木谷 吉克 笹崎 綾野 中村 茂 森田 登代子 藤田 恵子 山村 明子 刑部 芳則
- 出版者
- 神戸松蔭女子学院大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2014-04-01
礼服・軍服などの男子服意匠の導入に関わる幕末から明治維新期にかけての日仏間の交流の経緯と実態の一端を明らかにした。①明治天皇の御正服の意匠とAICP校に現存する絵型の比較検証から、礼服などの男子服意匠の導入がフランス支援による事が判った。②訪仏した日本人との交流が深かった洋裁店「オゥギャラリードパリ(S・ブーシェ)」は、男子服の発祥経路の一つとして指摘できた。③ナポレオン3世から徳川慶喜に贈呈された軍服、軍帽等の軍装品に関して、仏軍が定める詳細な仕様書などの資料が得られた。④The Tailor’s guideの技法は『西洋縫裁(裁縫)教授書』を介して伝えられたことが判った。
2 0 0 0 IR Webによる日本語プレイスメントテストの開発 : 外国人留学生の受け入れ拡大にむけて
- 著者
- 藤田 恵 平山 紫帆 栗田 奈美 金庭 久美子 数野 恵理
- 出版者
- 立教大学ランゲージセンター
- 雑誌
- 立教大学ランゲージセンター紀要 (ISSN:13448226)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.77-83, 2017-01
2 0 0 0 OA 重力健康科学に基づく「身心一体科学」の提案
- 著者
- 跡見 順子 清水 美穂 秋光 信佳 廣瀬 昇 跡見 友章 長谷川 克也 藤田 恵理 菊池 吉晃 渡邊 敏行 竹森 重 中村 仁彦 井尻 憲一 吉村 浩太郎 高野 渉 神永 拓 江頭 正人
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 挑戦的萌芽研究
- 巻号頁・発行日
- 2011
1Gという重力への適応を通して地球上で進化してきた人間は、動くことで重力を活用して身体を賦活化し、健康な状態を維持することができる。新しい健康科学イノベーション"重力健康科学"研究では、生命科学、脳科学、理学療法学、機器開発者が連携し、これまで皆無だった"ホメオスタシス範囲の評価系構築"に向けた研究に取り組んだ。いかに自重支持を行いながら運動し転倒しないようにするか?細胞と身体をつなぐ緊張性収縮のダイナミック制御システムを研究することが鍵でありかつ可能であることを、この萌芽的研究が明らかにした。
1 0 0 0 OA 拡張BDI論理TOMATOes による協調行為のモデル化と応用
- 著者
- 新出 尚之 高田 司郎 藤田 恵
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.13-24, 2011 (Released:2011-01-06)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 3
In multi-agent environments, to model cooperations among autonomous agents, many notions such as mutual beliefs and joint intentions, recognition of possibilities to achieve a goal with cooperation, and team formations, should be formally represented. In the traditional BDI logics, it is hard to treat them uniformly. We show the way to treat them uniformly using the fixed-point operator of the extended BDI logic \ omatoes. We also give some examples to apply it to the proof of some behaviors of multi-agent systems.
1 0 0 0 OA 山岳地域に設置されたダウンウィンド風車における吹上効果の評価
- 著者
- 大竹 悠介 近藤 勝俊 藤田 恵美 小垣 哲也 櫻井 健一
- 出版者
- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会
- 雑誌
- 風力エネルギー学会 論文集 (ISSN:24363952)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.23-30, 2021 (Released:2021-12-15)
A downwind turbine whose rotor surface is located on the leeward side with respect to the tower is expected to operate with high efficiency in up-flow wind. In addition, it is expected that a large amount of up-flow wind will be shown in mountainous areas that are common in Japan. Therefore, the wind conditions around the downwind turbine installed in the mountainous area were measured by Doppler LiDAR, and the wind turbine performance in the up-flow wind was evaluated. As a result, it was confirmed that the power of the wind turbine tends to improve as the flow inclination angle becomes larger and closer to the wind turbine tilt angle.
1 0 0 0 OA Enterocolic lymphocytic phlebitisの1例
- 著者
- 中川 暢彦 阪井 満 村井 俊文 末岡 智 篠塚 高宏 藤田 恵三 露木 琢司 中島 広聖
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.113-117, 2018 (Released:2018-08-01)
- 参考文献数
- 14
症例は74歳の男性.深夜に急激に生じた腹痛を主訴に当院救急外来を受診した.腹部膨満を認め,上腹部に腹膜刺激症状を認めた.腹部造影CT検査では,横行結腸に著明な浮腫性肥厚と周囲脂肪識の濃度上昇を認めた.NOMIによる腸壊死を疑い,緊急手術を施行した.術中所見では,肝彎曲部からの横行結腸および間膜に著明な浮腫と発赤を認めたが,壊死や穿孔の所見は認めなかった.肉眼的に正常な回腸末端から横行結腸中央部までの右半結腸切除術を施行した.病理組織学的検査では静脈を主体にリンパ球浸潤を認め,一部では静脈閉塞も認めた.動脈には炎症所見を認めず,enterocolic lymphocytic phlebitis と診断した.術後経過は良好で術後第9病日に退院し,以降再発は認めていない.今回,稀なenterocolic lymphocytic phlebitis を経験したので報告する.
- 著者
- 津山 真拡 劉 笛 藤田 恵美子 亀田 豊 清水 宗茂
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- pp.NSKKK-D-23-00033, (Released:2023-06-09)
本研究では, 国内の異なる海域で採取し, 製造された3種類 (沖縄県産, 伊豆大島産, 徳島県産) の国産食塩に含まれる大きさが20µm以上のMPの存在について, 顕微FT-IRを用いた分析を行った. その結果, すべての食塩にPPおよびPEが存在していた. ほかにも, 4種類のMPが確認され, FT-IRでの検出が困難であった微小なMPが食塩中に存在することを明らかにした. また, ほとんどのMPは粒子状であり, 大きさは29~459µmと幅広く存在していた.
1 0 0 0 OA 海外だより ~違う「常識」を理解する~
- 著者
- 藤田 恵介
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.49-50, 2023 (Released:2023-03-25)
1 0 0 0 OA 04生-12-口-12 身体活動改善への天然素材:卵殻膜
- 著者
- 藤田 恵理 清水 美穂 跡見 友章 長谷部 由紀夫 跡見 順子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集 第70回(2019) (ISSN:24241946)
- 巻号頁・発行日
- pp.155_3, 2019 (Released:2019-12-20)
身体は細胞と細胞が分泌する細胞外マトリクスからなる。老化や慢性炎症状態にある組織ではコラーゲンなどの細胞外マトリクスが沈着・線維化する。線維化した固い皮膚は身体の移動性を制限し日常の不活動の原因になりうるので、身体運動にとって重要である。卵殻膜は古くから東洋において皮膚治療への民間薬として使用されてきた。そこで我々は、可溶化卵殻膜を女性の皮膚に塗布したところ、腕の弾力性や顔のしわを有意に改善することを見出し、可溶化卵殻膜を塗布したマウス皮膚ではIII型コラーゲンが有意に増加した。さらに、特殊なMPCポリマーに結合した可溶化卵殻膜を付けた培養皿上でヒト皮膚線維芽細胞を培養する実験系を設計し、可溶化卵殻膜環境ではIII型コラーゲンなどの若い乳頭真皮を促進する遺伝子が誘導された。若い皮膚と同様のIII型/I型コラーゲン比(80%:20%)のゲルはI型コラーゲン100%ゲルよりも高い弾性をもたらし、そのゲル上のヒト皮膚線維芽細胞は高いミトコンドリア活性を示した。卵殻膜はIII型コラーゲン等の細胞外マトリクスの発現を誘導し、組織弾性の喪失を減少させることにより、身体活動を改善するために使用することができると考えられる。
- 著者
- 河住 有希子 浅野 有里 北川 幸子 藤田 恵 秋元 美晴
- 出版者
- 日本語教育方法研究会
- 雑誌
- 日本語教育方法研究会誌 (ISSN:18813968)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.64-65, 2016
We analyze a teacher diary of Japanese-language lessons given to visually-impaired learners, and find differences between teaching for the sighted and that for the visually-impaired. We gave Japanese supplementary classes from April to July 2016 in an educational institution where visually-impaired foreign students were enrolled. We wrote and shared the diary, which shows confusion of the learners seen in the introduction of vocabulary and sentence patterns and in oral practices, and also shows items of learning difficult for the teachers to give explanations. Through the analysis of the diary, this research will make clear the items with difficulties unique to visually-impaired learners and will provide classroom solutions.
1 0 0 0 OA 1970年代から1990年代まで
- 著者
- 藤田 恵子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.31-41, 2002-01-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 27
In this study, the high school textbooks of 88 volumes of six companies, and ten kinds of magazines of eight companies were analyzed, in order to clarify the features of the changes from the 1970s to the 1990s in drawing methods of the upper trunk of women.(1) At this time, ready-to-wears became popular among ordinary people, homemade clothes and order-made suits both decreased in number.(2) In most high school textbooks, the short measurement methods disappeared in the 1980s and the proportional method of the Bunka style came to appear in the 1990s.(3) The number of magazines which printed patterns began to decrease from the 1970s, and four magazines that carried many patterns were discontinued from the end of the 1980s to the beginning of the 1990s.(4) Since the kind and number of basic patterns were selected, this time can be called the “Selection Time of Basic Pattern Making of Women's Upper Trunks.”
1 0 0 0 OA 女子上半身原型製図法の変遷
- 著者
- 藤田 恵子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.415-423, 2000-05-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 57
In this study, 200 basic patterns in 176 books and magazines were used to survey the historical changes in drawings of the upper trunk of women. These books and magazines were extracted from among 375 sewing publications, textbooks, teacher's manuals, three kinds of women's monthly magazines, and a stylebook, which were published from the beginning of the Meiji era to 1945. The results are as follows : At first, basic patterns were drawn based on mainly breast size to make the upper trunk of girls' dresses at the end of the Meiji era. Thereafter, patterns which could be used for both children and women were created. Then patterns specially designed for women were developed. After 1935, basic patterns were adopted in school curriculums at elementary schools and by women's magazines, and the use of basic patterns for dress making became standard practice among ordinary people. Therefore, basic patterns contributed to the spread of Western dress in Japan. Drawings for women were partly influenced by men's pattern making and Kimono cutting methods. In addition, drawings designed to cover the complicated curves of shoulders and breast swells began to emerge in this period.
- 著者
- 大薗 修一 藤田 恵里子
- 出版者
- 日本リメディアル教育学会
- 雑誌
- リメディアル教育研究 (ISSN:18810470)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.45-55, 2021-06-01 (Released:2021-06-10)
- 参考文献数
- 27
本研究の目的は,日本の大学生英語学習者における英文理解時の語義検索行動が,辞書の種類や英語の習熟度によってどのように影響を受けるかを明らかにすることである。参加者(印刷辞書群とスマホ・オンライン辞書群)に,英文中の目標語の適切な意味を選択させる英文語義検索タスクを実施した。その結果,印刷辞書群とスマホ・オンライン辞書群の間には差は見られなかったが,英語熟達度上位群の方が下位群よりも高得点を得たことが示された。特に,スマホ・オンライン辞書の下位群は,意味選択ではなく品詞選択でミスをする傾向があることが示された。また,英語熟達度の低い学習者は辞書に記載されている最初の意味を選択する可能性がある。このことから,指導者は辞書に記載されているすべての意味に目を通すように指導するだけでなく,文中の目標語の品詞にも注意を向けさせるべきであることが示唆された。
- 著者
- 跡見 順子 清水 美穂 藤田 恵理 跡見 綾 東 芳一 跡見 友章
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集 第70回(2019) (ISSN:24241946)
- 巻号頁・発行日
- pp.155_1, 2019 (Released:2019-12-20)
本発表では、講義と実践を組み合わせた運動生理学的教育プログラムの開発について報告する。地球重力場で進化した動物の仲間であり直立二足歩行を獲得した人の姿勢・身体運動は、他の動物と異なり、すべてを反射で行うことはできない。立位の重心に相応する部位は「丹田」と呼ばれ、武術では体幹コントロールのポイントとする。身体重心のトレーニングは、生理学的には随意運動により体幹の筋群をコントロールすることが可能である。しかし、体幹の深部筋を対象にした研究は方法上難しいので少ない。また体幹・脚・足・の連携制御により軽減される膝や腰等の関節痛予防のための姿勢やバランスの体育教育プログラムはきわめて少ない。本研究では、高校生70名、大学生・大学院生総勢50名を対象に、運動の脳神経系の連携機序や力学応答する細胞の基本特性などについての講義および仰臥位で自分自身の手で腹部を触り、触覚を感知し、自ら行う腹側の筋群・脚・足のエクササイズを毎日実践してもらった。その結果、身体的要素(姿勢、上体起こし回数、ジグザグ歩行回数等)の有意な増加や改善、および意識的要素(目覚め・寝つきのよさ、前向き)の改善がみられた。
1 0 0 0 OA 明治維新期におけるフランスからの男子服意匠の導入の歴史
本研究は我が国の洋装文化形成の最初期において、礼服・軍服などの男子服意匠の導入に大きな影響を与えた幕末から維新期にかけての日仏間の交流の実態と意義を明らかにすることを目的とする。そのため、パリの服飾専門学校、AICP校*に現存する日本由来の資料を手掛かりに、幕末の将軍徳川慶喜と明治天皇の洋装に関連する資料を調査・収集し、日仏関係者による交流の具体的経緯と男子服意匠の導入経過の解明を目指した。その結果、軍事博物館(パリ)などの調査から、ナポレオンⅢ世から寄贈された慶喜の軍服、明治天皇の礼服の意匠、慶喜の実弟昭武と関わるパリのテーラーなどに関する事実が明らかになった。*Académie Internationale de Coupe de Paris