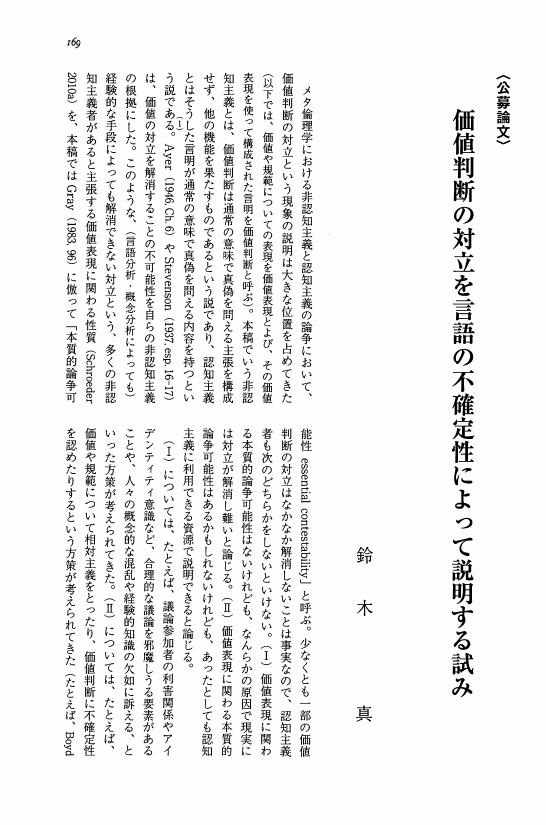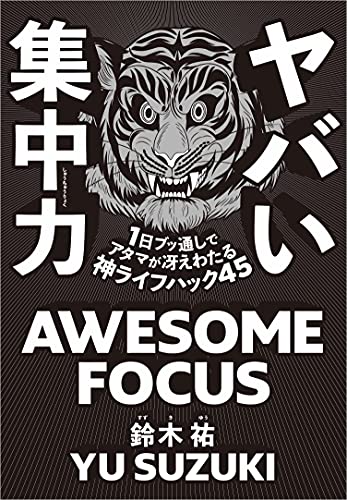1 0 0 0 OA 価値判断の対立を言語の不確定性によって説明する試み
- 著者
- 鈴木 真
- 出版者
- 関西倫理学会
- 雑誌
- 倫理学研究 (ISSN:03877485)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.169, 2016 (Released:2018-03-15)
1 0 0 0 218. 男女神経性食思不振症の恋愛経過(摂食障害IV)
- 著者
- 武田 綾 鈴木 健二
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, 1994
- 著者
- 田中 重好 鈴木 聖敏
- 出版者
- 地域安全学会
- 雑誌
- 地域安全学会論文報告集
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.35-44, 1992
1992年9月28日午後5時から7時にかけて,津軽地方を強風とともに襲った台風19号は、東北電力弘前営業所管内の85.0%にのぼる世帯を停電させた。本研究は、停電に関連した情報の流れを整理し、停電をめぐる「情報ニーズと情報提供」の問題にしぼって、経験的に検討した。今回の台風災害の経験を踏まえて、今後、どういった情報提供がなされるべきなのかを、考えておきたい。第1は、高度情報化社会を迎えて、災害時ではあれ、情報ニーズはきわめて高いという事実を確認すべきである。第2は、電話社会との関連の問題である。これまで、災害時にはさまざまな形で、電話が輻輳し、混乱をきたすことが指摘されてきた。しかしながら、この対策が、電話会社によるトラヒック制御という観点からのみ取り上げられて、地域のコミュニケーション・シムテムの設定という観点が不足していた。電話の輻輳をラジオ放送が低減することは可能であるはずであり、これが可能となれば、本当に必要な情報は電話をとおして連絡できるようになる。第3に、こうしたコミュニケーション・システムという観点は、今後、公共機関からマスメディアをとおして住民に情報を伝達するという一方向モデルではない、さまざまな形のフィードバック回路を組み込んだモデルを構想してゆくことにつながるはずである。最後に、そのさい、各メディア間を、いかに「仕切る」かが重要な課題となる。たとえば、ラジオは災害情報の地域内の流れを「仕切る」可能性をもっている。「ラジオが災害情報の地域内の流れを『仕切る』」とは、具体的にいえば、たとえば次のようなことが考えられる。東北電力に殺到した住民からの電話のうち、特定のものに関しては連絡を自粛してもらうように呼びかける(一般的呼びかけ型)とか、地域ごとの復旧見通しをきめ細かくラジオで放送することにより、電話での問い合わせの一部を減少させる(情報提供型)とか、停電を強いられている住民に対して補完的手段をとるように呼びかけることにより、停電による生活障害や心理的負担感を軽減する(補完的手段提示型)といったやり方である。
1 0 0 0 OA アンケート調査を越えて ―自然言語処理や機械学習を用いたログデータの活用を模索する―
- 著者
- 村瀬 俊朗 王 ヘキサン 鈴木 宏治
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.16-30, 2021-09-20 (Released:2021-10-15)
- 参考文献数
- 103
理論を構成する抽象概念の変数化は,実証を行う上で重要な作業である.経営学者はアンケート調査を活用して概念の抽出を行ってきたが,データの大規模化や時系列での取得が困難であるため,一部の理論の検証が難しい.このデータに関する問題を解消するために,自然な人の行動の記録であるログデータの活用方法を模索する必要がある.そのため,本稿では自然言語処理と機械学習を応用したログデータの活用方法を検討する.
1 0 0 0 明治維新と修験道
- 著者
- 鈴木 正崇
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.2, pp.131-157, 2018
<p>修験道は、江戸時代には民衆の中に神仏混淆の形態で深く定着していたが、新政府による慶應四年(明治元年)のいわゆる神仏判然令以後、急速に崩壊へと向かった。神仏判然令で最も甚大な影響を被ったのは権現に社僧や別当として奉仕してきた修験道であり、その解体は神道国教化を進める新政府から見て必然であった。修験は政府の指令に基づき、寺院として存続する、復飾(還俗)して神主になる、帰農するなどの選択を迫られた。そして、明治五年に出された修験宗廃止令によって天台宗か真言宗への帰属を迫られて事実上、解体された。本稿は明治維新に大変動を被った修験道に関して、神仏判然令の及ぼした影響を修験道の本山と在地修験の双方から広く考察する。在地修験では東北の法印様の歴史的変化を考察し、本山では羽黒、吉野、英彦山の事例を中心に、神と仏の分離の展開を比較検討する。最後に学術用語として神仏習合と神仏分離の概念について再検討する。</p>
1 0 0 0 IR IRT診断テストを活用した日本語力調査
- 著者
- 大島 龍彦 鈴木 薫 永井 靖人
- 出版者
- 名古屋学芸大学
- 雑誌
- 名古屋学芸大学研究紀要.教養・学際編 = The Journal of liberal arts, Nagoya University of Arts and Sciences (ISSN:13498452)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.73-82, 2014-02
The academic competence of college students has recently seen diversification in Japan, more specifically the lack of language ability as a medium of academic learning. Teachers are required to accurately comprehend the academic language proficiency of their students, without any useful tests that have the ability to measure Japanese competence in a valid and reliable way. The purpose of the research is to find an optimal way to measure learners' Japanese proficiency, which could be easily administered in daily classroom situations. The Japanese vocabulary IRT test was adopted, and given to 196 college students, with data being statistically analyzed and compared with those of the nationwide research. It was also collated to indicate differences among three departments the participants belonged to. Although the average score of the participants was higher than that of the nationwide research, a lack of sufficient vocabulary for academic learning was observed in 10-20% of participants. Moreover, the data was compared with that of the English vocabulary IRT test given in the same investigation. Results indicated that there wasn't any significant correlation between Japanese and English proficiency.
1 0 0 0 IR 個人間取引(Eコマース)における諸問題( 1 ) : ノークレームノーリターン特約の効力
- 著者
- 鈴木 宏昌
- 出版者
- 東海大学総合社会科学研究所
- 雑誌
- 東海大学総合社会科学研究 (ISSN:24338362)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.37-40, 2019-03-20
- 著者
- 神戸 嘉一 武田 美加子 土屋 公幸 吉松 組子 鈴木 仁 鈴木 莊介 矢部 辰男 中田 勝士 前園 泰徳 阿部 愼太郎 石田 健 谷川 力 橋本 琢磨
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.289-299, 2013
クマネズミはthe <i>Rattus rattus</i> species complexとも称され,複数の種からなる種複合体である.日本には古くに移入した東アジア地域起源の<i>Rattus tanezumi</i>(2n=42)に加え,新規に移入したインド地域が起源の<i>R. rattus</i>(2n=38)の2系統が存在する.本研究ではこれらクマネズミ系統の日本列島における分布および移入の歴史を把握することを試みた.毛色関連遺伝子<i>Mc1r</i>(954 bp)をマーカーとし,奄美大島産を含む36個体の塩基配列データを新規に収集し,既存の配列データと合わせ,日本列島の17地点,さらに比較対象として用いたパキスタン産を含め,総計133個体のデータを基に系統学的解析を行った.その結果,小樽,小笠原諸島および東京の3地域で<i>R. rattus</i>型が認められ,これらの地点では<i>R. tanezumi</i>型とのヘテロ接合体も存在した.これらの結果から,既存系統への浸透交雑が一部の市街部,港湾部および離島で進行している実態が明示された.一方,琉球列島の自然林では,<i>R. rattus</i>型の<i>Mc1r</i>ハプロタイプは認められなかった.これは,新たな外来系統<i>R. rattus</i>の定着や浸透交雑を起こさない何らかの要因が存在する可能性を示唆する.琉球列島には独自の<i>Mc1r</i>配列の存在も認められ,他地域とは遺伝的に分化した集団として位置づけられる可能性も示唆された.<br>
1 0 0 0 ハンセン病動物モデルの歴史と高血圧ヌードラットの特徴
- 著者
- 與儀 ヤス子 藤村 響男 鈴木 幸一
- 出版者
- 日本ハンセン病学会
- 雑誌
- 日本ハンセン病学会雑誌 = Japanese journal of leprosy (ISSN:13423681)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.3, pp.197-204, 2008-09-01
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
1873年のらい菌発見から長い年月に渡って多くの研究者がらい菌の動物移植実験に尽力してきたが、1960年の Shepard による foot-pad 法の開発後はめざましい成果が残された。T-Rマウス、無胸腺 (ヌード) マウスのらい菌動物移植への導入、また、アルマジロ、チンパンジーやマンガベイサルの自然発症例が報告され、ハンセン病が人畜共通伝染病であることがその後のわずか十数年で確認された。増菌されたらい菌は大量菌を必要とする分野への供給に役立ち、らい菌の動物移植研究の成果はハンセン病医学に大きく貢献した。われわれがらい菌増殖用の tool として開発したコンジェニック高血圧ヌードラット (SHR. F344-Foxn1<sup><i>rnu</i></sup>) はIL-10産生能が高く、らい菌に対する感受性能が優れていた。本ヌードラット (<i>rnu/rnu</i>) に接種されたらい菌は接種部および非接種部位に肉眼的らい性腫瘤を作りながら増殖、全身化していく独特のらい菌感染像を呈すことから、ヒトL型ハンセン病患者の実験モデル動物として有用であり、同腹仔有胸腺ラット (<i>rnu/+</i>) では、らい菌感染後24時間目頃から、らい菌特異的免疫機構の成立を示唆する像が観察され、6ヶ月後には、リンパ球に幾重にも取り囲まれて、らい菌が殺菌され排除される像が観察されたことから、らい菌の宿主からの防御機構を研究する動物モデルとしてヌードラットとともに有用である。
1 0 0 0 狐と翁と人骨をめぐる冒険
- 著者
- 鈴木 紗耶香
- 出版者
- 渋沢栄一記念財団
- 雑誌
- 青淵 (ISSN:09123210)
- 巻号頁・発行日
- no.870, pp.33-35, 2021-09
- 著者
- 紙谷 博子 梅垣 宏行 岡本 和士 神田 茂 浅井 真嗣 下島 卓弥 野村 秀樹 服部 文子 木股 貴哉 鈴木 裕介 大島 浩子 葛谷 雅文
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.98-105, 2018-01-25 (Released:2018-03-05)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 2
目的:認知症患者のQOL(quality of life)について,本人による評価と介護者による代理評価との一致に関する研究はあるが,在宅療養患者のためのQOL評価票をもちいて検討したものはない.本研究の目的は,主介護者などの代理人に回答を求めるQOL評価票の作成と,本人の回答との一致性について検討することとした.方法:この研究は在宅患者の観察研究である.我々が開発した,4つの質問からなるQOL評価票であるQOL-HC(QOL for patients receiving home-based medical care)(本人用)に基づいて,QOL-HC(介護者用)を作成した.また,QOL-HC(本人用)とQOL-HC(介護者用)を用いて,患者本人と主介護者から回答を求め,それぞれの質問への回答の一致率についてクロス集計表を用いて考察した.また,合計得点についてはSpearmanの順位相関係数を求めた.結果:質問1「おだやかな気持ちで過ごしていますか.」,質問2「現在まで充実した人生だった,と感じていますか.」,質問3「話し相手になる人がいますか.」,質問4「介護に関するサービスに満足していますか.」について,本人と介護者の回答の一致率は,それぞれ52.3%,52.3%,79.5%,81.8%であった.また,QOL-HC(本人用)合計点とQOL-HC(介護者用)合計点について有意な弱い相関を認めた(Spearmanのρ=0.364*,p=0.015).結論:本人と介護者による評価とに50%以上の一致率をみとめ,合計点について有意な相関をみとめた.介護者による評価を参考にできる可能性はあるが,評価のかい離の要因およびQOL-HC(介護者用)の信頼性の検討が必要である.
1 0 0 0 LC-MS/MSを用いた植物毒18成分の一斉分析法の開発
- 著者
- 大石 晃史 永富 康司 鈴木 康司
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.108-112, 2019
- 被引用文献数
- 6
<p>飲料中への意図的な植物毒の混入を想定し,LC-MS/MSを用いた植物毒一斉分析法を開発した.分析対象には日本で中毒事例の多い,もしくは過去に事件に用いられた植物毒18成分を,分析試料にはビール,焼酎,ブレンド茶,缶コーヒー,乳性飲料を選択した.分析成分の抽出および精製にはQuEChERS法を用いた.バリデーション試験の結果,日内精度,真度,回収率について良好な結果が得られた.いずれの成分も5~200 ng/mLの範囲で良好な直線性を示し(<i>r</i>>0.990),低濃度での検出が可能となった.</p>
1 0 0 0 階段や坂を歩ける大腿義足膝継手 NAL-Knee の開発
- 著者
- 二宮 誠 増田 勝也 鈴木 光久 後藤 学 石松 隆和
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 = Bulletin of the Japanese Society of Prosthetic and Orthotic Education, Research and Development (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.228-236, 2008-10-01
- 参考文献数
- 4
膝の機能を持たない大腿切断者が, 大腿義足で交互歩行による坂や階段のスムーズな昇降を行うためには, 膝継手に設けた油圧シリンダーを制御する必要がある. つまり, 階段の上りでは膝が任意の角度で屈曲ストップし, 階段の下りでは膝のイールディングが行われなければならない. 今回我々は, その必要な制御機能を持つ膝継手を開発した. 最初は2個のソケット内センサーによる随意制御を考えたが, 最終的には足部の接地状況を, 膝下のリンク機構によりシリンダーに伝えるバウンサー機構を考案した. この膝継手NAL-Knee により, バッテリー等も必要なく, 平地の自由な速度での歩行や, 坂, 階段の交互昇降が可能となった.
- 著者
- 鈴木 郁
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.379-388, 1995-12-15
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 8 2
パーソナルコンピュータ上で心拍変動性を実時間かつ高い時間分解能で解析することを目的に, オクターブバンド分析に基づく方法を用意した. 本方法では, 心電図の信号からR波に同期したパルスを生成するハードウエア (R波検出装置) と, ディジタルバンドパスフィルタ4組により各帯域ごとのパワーを求めるソフトウエアを用いる. 解析結果としては, 各帯域ごとのパワー, およびそれらの重みつきの和である心拍変動性指標値が得られる. なお本方法は多少の変更により, テープに記録されたホルター心電図の信号にも適用可能である.<br>文字列検索作業および高次系手動制御を課題とする, VDT作業を用いた実験で得られた心電図の信号に, 本方法を適用した. 本論文では解析方法の詳細について述べ, また上述の適用例に基づき精神的負担の評価方法としての適性にも触れる.
1 0 0 0 OA グラフカットによる異常値耐性のある陰関数曲面生成法
- 著者
- 長井 超慧 大竹 豊 鈴木 宏正
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.7, pp.2308-2317, 2011-07-15
コンピュータグラフィクスやCADを代表とする多くの分野で,表面メッシュは,実在する3次元物体(実物体)の形状を表現する目的で多用され重要な役割を果たしている.実物体から表面メッシュを得る手法の1つに,物体表面のスキャンなどで得られる点群データを入力として,その形状を等値面として持つスカラー場を構築し,その等値面を近似するポリゴンメッシュを生成するものがある.この手法はスキャンデータに一般的に含まれるノイズに比較的頑健であるものの,異常値や大きいノイズを含むデータに対し適用すると過剰な面を含むなど,元の物体形状とまったく異なる表面メッシュが生成されることがある.本稿では,等値面による近似手法の代表的な方法であるPartition of Unity(PU)に大域的手法であるグラフカットを組み合わせることで,異常値を含むデータに対する頑健性を高めた表面メッシュ生成法を提案する.
1 0 0 0 OA 海馬細胞外Zn2+流入を介した神経細胞内Zn2+動態制御の破綻による認知機能障害
1 0 0 0 IR 「現代文学と魔法の絨毯(アレゴリ-)--文学史の中の<天皇>」栗坪良樹
- 著者
- 鈴木 貞美
- 出版者
- 早稲田大学国文学会
- 雑誌
- 国文学研究 (ISSN:03898636)
- 巻号頁・発行日
- no.111, pp.p101-104, 1993-10