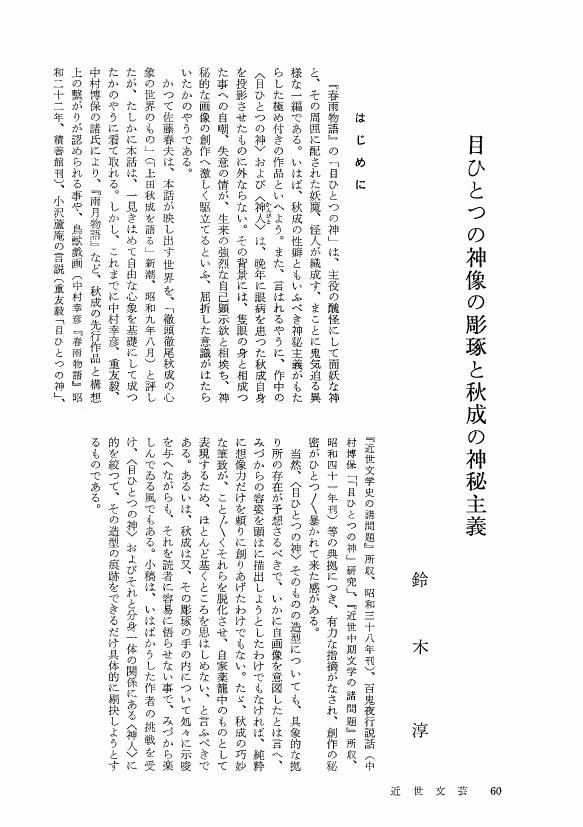1 0 0 0 OA 目ひとつの神像の彫琢と秋成の神秘主義
- 著者
- 鈴木 淳
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.60-70, 1981 (Released:2017-04-28)
- 著者
- 坪井 志朗 三村 康広 山崎 基浩 鈴木 雄 西堀 泰英
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.1405-1412, 2021-10-25 (Released:2021-10-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
新型コロナウイルスの感染防止による新しい生活様式によって、テレワークやオンライン会議が普及し、職場と居住地が必ずしも近くにある必要はなくなる等、我々の暮らしを大きく変えている。地方都市や郊外地域の居住意向が向上し、職場にとらわれない居住選択ができるようになった一方、地方都市移住や田舎暮らしを適切な地域に誘導しなければ、単なる都市のスプロールとなり、都市の広域化が懸念される。本研究では、愛知県豊田市をケーススタディとして、コロナ禍における地方都市の人口動態の変化と居住地選択の意向変化を分析した。その結果、人口動態について転入者数の減少により人口減少へとなっていること、コロナ禍前後で居住地選択の考え方が変わっていることが指摘できた。
1 0 0 0 IR フランス革命期の王族・貴族への眼差しの変化 : 私生活と政治的批判
- 著者
- 鈴木 球子
- 出版者
- 信州大学総合人間科学系
- 雑誌
- 信州大学総合人間科学研究 = Shinshu University journal of arts and sciences (ISSN:24327719)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.98-109, 2021-03
信州大学総合人間科学研究 15 : 98-109(2021)
1 0 0 0 OA 日本の社会的養護とホスピタリズムの動向
- 著者
- 美馬 正和 堀 允千 鈴木 幸雄
- 出版者
- 北海道文教大学
- 雑誌
- 北海道文教大学論集 = Journal of Hokkaido Bunkyo University (ISSN:13454242)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.135-146, 2021-03-15
本稿では日本の社会的養護の改善を促し,家庭養護や施設養護の重要性を確認する契機となったホスピタリズム論争に焦点を当て,先行研究では深く論究されていないホスピタリズム論争の整理を行い,その成果と問題点及び課題を明らかにした.その結果,ホスピタリズム論争の成果は,日本で初めて本格的な施設養護の養護論が議論され,3 つの養護理論が誕生したことである.だが,深い議論が伴わないままで終結していた.そのことによって,職員を含めた全体的な議論になっていなかったのであった.今後の課題としては,永続的な親機能に対する科学的知見を蓄積することであった.
1 0 0 0 清代徽州府の宗族と村落 : 歙県の江村
- 著者
- 鈴木 博之
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.4, pp.557-578,656-65, 1992
This paper is a case study describing the local lineages of the Jiang 江 village, She 歙 xian during the Ming and Qing periods. The points are following below. The Jiang lineages gained the advantage in this district socially and economically, and the people believed that the lineage's destiny was under the influence of geomancy, feng-shui 風水. From this point of view, the Jiang lineages and others tried to conserve the environment of the mountainous region against the move by the foreign settlers to develop minerals and commercial agriculture, on a backdrop of opposition arising due to continuing stratification among the lineage members. The festival organization called she-hui 社会, shen-hui 神会, si-nui 祀会, etc. was founded on a sublineage basis, including slaves, zhong-po 庄僕, in the Jiang village and Qing-yuan 慶源 village Wu-yuan 〓源. But the sublineages were not equal one another and the qualification to participate in the festival was limited according to social and economical differences. It's well known that the areas were the hometowns of Hui-Chou (Hsin-an) merchants. Segments of the Jiang lineages extended their business activities to the cities in Jiangnan, especially Yang-zhou 揚州, which was famous as a salt merchant center. But local lineages were not formed in Yang-zhou, rather the merchant segments based their relationships on the original lineages. This presented a precarious position for outside merchants. The connection with the hometown was a sort of insurance against the natural features of the region which would protect them and their descendants.
1 0 0 0 2フレームオフセット変調多重技術を用いた帯域圧縮方式の検討
- 著者
- 矢島 亮一 金次 保明 鈴木 正一 加藤 久和
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.41, pp.13-18, 1989-08-31
- 著者
- 鈴木 満弥
- 出版者
- メディカルレビュー社
- 雑誌
- 介護支援専門員 (ISSN:13448404)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.16-22, 2009-01
- 著者
- 金子 郁容 松井 孝治 細野 豪志 鈴木 寛 大西 健丞 内海 成治
- 出版者
- 国際ボランティア学会
- 雑誌
- ボランティア学研究 = Journal of volunteer studies (ISSN:13459511)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.67-83, 2015
1 0 0 0 OA 脳卒中によるPure motor monoparesis
- 著者
- 佐藤 美佳 長田 乾 鈴木 明文
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.396-401, 2005-09-25 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 12
脳卒中によりPure motor monoparesis(PMM)を呈した症例について,急性期の頭部MRI拡散強調画像を用いて検討した.5年間の脳梗塞,脳出血連続症例3226例中,PMMは32例(約1%;上肢26例,下肢6例)で,31例は脳梗寒,1例のみ脳出血であった.上肢のPMMの責任病巣は,放線冠や半卵円中心や中心前回に,下肢のPMMは内包後脚―放線冠後部に多く認められた.9例で2つ以上の多発性の病巣を認めた.発症機序による検討では,動脈原性塞栓8例(25%),心原性塞栓7例(21.9%)と約半数が塞栓性機序であった.抗血小板,抗凝固療法を開始したが,約2.9年の観察期間において7例(21.9%)が脳梗塞を再発した.PMMは,小梗塞でも塞栓性機序が稀ではなく,再発のリスクも考え,的確な診断と治療が必要である.
1 0 0 0 OA ニューコーム問題と逆因果律 ―「プロテスタンティズムの倫理」のフォーマライゼーション―
- 著者
- 鈴木 譲
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.331-344, 2000-10-30 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 15
本稿では、これまで主に哲学者、論理学者の間で議論されて来たニューコーム問題を数理社会学の観点から論ずる。ニューコーム問題とは、予言者の存在を仮定したパラドックス的設定の下での意思決定の問題である。予言者の能力によってこの問題の性質は大きく異なるが、本稿ではいわゆる予言者の完全性を仮定した場合に議論を限定し、この問題を2つの観点から論じる。第一は数理論理的な観点、特に公理系の無矛盾性の観点である。結論としては、ニューコーム問題は合理的意思決定の問題としてはそもそも決定不可能な命題であり、因果律の方向が本質的に重要であることを示す。因果律はその方向に応じて、順因果律と逆因果律の2種類を考えることが出来る。第二は社会学的観点であり、前述の数理論理的観点から得られた定式化を社会現象に応用することを試みる。この応用の具体例として、Weberのプロテスタンティズムの倫理のフォーマライゼーションを行い、カルヴィニズムにおける信徒の意思決定が逆因果律の論理に対応していることを示す。
1 0 0 0 OA シクロデキストリン残基を有する高分子膜によるアミノ酸の光学分割
- 著者
- 石原 一彦 鈴木 七美 松井 清英
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.3, pp.446-451, 1987-03-10 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 22
高分子膜を透過させることによりDL-アミノ酸を光学分割することを目的として,側鎖に分子包接能を有するβ-シクロデキストリン残基を導入した高分子を合成し,これから得られる高分子膜のアミノ酸透過性を検討した。フェニルアラニンを透過させた場合,L-体の透過速度がD-体にくらべて大きく,その透過係数比は1.40であった。トリプトファン,ヒスチジンを透過させた場合も同様の傾向となった。また,シクロデキストリン残基のかわりにグルコース残基を有する高分子膜を用いた場合は,アミノ酸の光学異性体間で透過係数に差は認められない。さらにβ-ジグロデキストリンを橋かけした樹脂に対するフェニルアラニンの吸着量は,L-体にくらべてD-体の方が多くなる。これらのことから,シクロデキストリン残基とアミノ酸とが高分子膜中で相互作用し,とくにD-体との相互作用が強いため拡散性が抑制され,透過係数に差が生じたと考えられる。また,DL-アミノ酸を透過物質として光学分割を試みたところ,膜透過とまりL-体が濃縮きれ,フェニルアラニンの場合,その組成比はL/D=61.7/38.3となった。
1 0 0 0 環境発電技術の展望
- 著者
- 鈴木 雄二
- 出版者
- 日本AEM学会
- 雑誌
- 日本AEM学会誌 (ISSN:09194452)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.339-342, 2014
- 被引用文献数
- 11
Unlike low-cost massive energy sources for grid systems, energy harvesting is a high-added-value power generation technologies, in which small power can be extracted from energy sources in the environment. Energy harvesting technologies will make an important contribution to autonomous devices including wireless sensor nodes by providing battery-less long-lived power source. Recently, significant efforts have been paid in the country and abroad toward various applications such as building energy management system.
1 0 0 0 たん白結合能阻害因子からみた各種血液浄化療法の比較検討
- 著者
- 佐中 孜 葛西 浩美 早坂 勇太郎 鈴木 利昭 久保 和雄 須藤 尚美 阿岸 鉄三 杉野 信博 太田 和夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.88-91, 1983
腎の排泄機能不全によって、体内に蓄積する蛋白結合能阻害因子(PB-Ix)は、他の物質と競合して、アルブミンと結合すると考えられている。今回の研究によって、馬尿酸および2a, 2bと命名された中分子物質と同定したPB-Ixは、HD、HFよりHDFによって比較的容易に除去された。但し、PB-Ix活性という観点からみると、それらの血液浄化法では、その改善を計ることができず、CAPDのみが活性値を正常値の近くまで回復させることができた。
1 0 0 0 long RP' tachycardia—上室性頻拍の新しい概念
long RP' tachycardiaとは,いわゆる上室性頻拍のなかで,頻拍中のP波の出現時相が,先行するQRS(R)波よりも,それにひき続くR波に近接するタイプの頻拍のことをいい,したがって,R-P'/P'-Rの比が1よりも大きい頻拍のことである.この際,P'波と表記するのは,この心房波の由来が洞性のものではなく,異所性P波ないしは逆伝導性P波であることを示すためである. 本タイプの頻拍が注目をひくようになったのは,1967年,Coumelがその心電図的,電気生理学的特徴を報告してからである1).
1 0 0 0 家族内に発生した前立腺癌の検討
- 著者
- 中田 誠司 増田 広 佐藤 仁 清水 信明 鈴木 和浩 今井 強一 山中 英壽 斉藤 浩樹 中村 敏之 加藤 宣雄 高橋 修 矢嶋 久徳 梅山 和一 篠崎 忠利 大竹 伸明 関原 哲夫 猿木 和久 鈴木 慶二
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.9, pp.1483-1487, 1995-09-20
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2 2
(背景と目的) 同一家系内に発生した前立腺癌患者の臨床病理学的特徴について検討した.<br>(対象と方法) 親子または兄弟に発生した7組 (14例, 親子2組, 兄弟5組) の前立腺癌患者 (F群) と, 1987~1993年の間に群馬県およびその近郊の病院で, 未治療の状態で発見された前立腺癌患者1,741例 (G群) を比較検討した. 両群の平均年齢が異なるため, 生存率は相対生存率を求めた.<br>(結果) 診断時年齢は, F群が54~86歳まで分布し, 平均68.1±8.5 (S. D.)歳, G群が47~97歳まで分布し, 平均74.2±8.3歳で, F群で平均年齢が低い傾向であった. 臨床病期, 組織学的分化度は, F群で早期癌の占める割合が高く, 低分化癌の占める割合が低い傾向であった. 予後は, 3年および5年相対生存率はF群で82.4%, 57.6%, G群で84.3%, 73.9%で, 5年の時点ではF群の生存率が低い傾向であったが, 全体的には両群の間にほとんど差はみられなかった. F群では死因の明らかな6例のうち4例 (66.7%) が前立腺癌死であるのに対し, G群では死因の明かな398例のうち前立腺癌死は224例 (56.3%) であった.家系の病歴に関しては, F群で前立腺癌の2人を除いた他の癌患者がいたのは6家系中3家系であった.<br>(結論) 家族性前立腺癌は, 診断時年齢が若く, 早期癌が多く, 低分化癌が少ない傾向であった.
1 0 0 0 OA 男性養護教諭の仕事に対する意識と体験に関する質的研究
- 著者
- 鈴木 春花 朝倉 隆司
- 出版者
- 日本健康相談活動学会
- 雑誌
- 日本健康相談活動学会誌 (ISSN:18823807)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.29-40, 2018-03-20 (Released:2021-07-07)
- 参考文献数
- 37
本研究は、性別意識に着目して、男性養護教諭の仕事の意識と体験の特徴を明らかにした。 男性養護教諭4名を対象とし、約1時間程度の半構造化インタビューを実施した。分析は、テーマ分析の方法を参考に、共著者間で協議して進め、基本的問題意識とデータの読み込みから、5つのテーマを設定してカテゴリーを生成した。 性別意識が現れたカテゴリーは、《養護教諭を目指した理由・動機》《養護教諭としての職業観》では、【男性でもなれるという思い】【専門性と性別は無関係】であるという認識のカテゴリーであった。男性の《養護教諭としての仕事上の体験》では【男性養護教諭に対するバリアへの挑戦】【少数派男性ゆえの孤独感と存在価値】【中年期の男性養護教諭イメージの不確定さからくる不安と期待】【子供が持つ羞恥心への理解】【セクハラの危険性の認知と予防策】【性別を超えた対人職の倫理】と特徴的なカテゴリーを見出した。《うまく働ける要因》では、【学校のニーズ】【男女の複数配置】【普通と思う受け入れ姿勢】という職場の条件、【本人のポジティブな性格】という本人の要因を見出した。《男性養護教諭の存在意義》に関しても、【子供に養護教諭の選択肢を与えることができる】【キャリア教育の一翼を担う】【これまでの当たり前を問い直すことができる】【多様なニーズへの対応ができる】のように、男性養護教諭の立場から養護教諭のあり方を問い直すカテゴリーを見出した。
1 0 0 0 OA オオズアリのメジャーワーカーにおける採餌と栄養貯蔵,および表現型可塑性
- 著者
- 横田 智 山尾 僚 鈴木 信彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.252-263, 2012-10-05 (Released:2018-09-21)
ワーカー多型の進化とその生態学的意義を解明するために,ワーカーに二型(メジャーおよびマイナーワーカー)がみられるオオズアリの分業体制を定量的に解析すると共に,メジャーの重要性が高い餌条件下で,カースト比やメジャー形態の可塑的変化が生じるのかを検証した.室内でサイズの異なる餌(大きい餌:フタホシコオロギ成虫,小さい餌:大きい餌を凍結粉砕したもの)を与え,餌場に現れたワーカーの個体数やメジャー比,行動様式,餌の解体の有無などを観察した.大きな餌を与えた場合,メジャーが餌場に多く現れ,マイナーが運搬行動に従事し,メジャーが解体行動に従事するという明確な分業がみられた.メジャーがいるコロニーでは,ほとんど場合餌が解体されたのに対し,メジャー不在のコロニーでは解体が生じたのはわずかであり,いずれも女王によるものであった.63日間,大きな餌を与えたコロニーと小さな餌のみを与えたコロニーのメジャー比及びメジャーの頭幅を比較したところ,メジャー比には違いはみられなかったが,頭幅には餌の大きさに相関した違いが生じた.腹部に栄養を貯蔵したメジャーがいるサブコロニー,貯蔵していないメジャーがいるサブコロニー,メジャーがいないサブコロニーをそれぞれ飢餓条件に置いて生存率を記録した結果,貯蔵したメジャーがいるコロニーが最も生存期間が長かった.以上の結果から,オオズアリの採餌におけるワーカーの明確な分業体制とメジャーによる食物貯蔵機能が明らかになり,メジャー形態の可塑的変異も確認された.メジャーカーストは餌の解体や栄養貯蔵に重要な役割を担っており,餌資源の獲得や維持に大きく貢献していると考えられた.
- 著者
- 鈴木 崇 横瀬 正英
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.8, pp.578-584, 2007
日本ではスピリッツという酒類の概念は一般的には, ウオッカやジンなどを指すが, 欧米では蒸留酒一般を, 広くスピリッツと呼ぶ場合が多い。世界各国の酒類制度は, それぞれの国の歴史や文化に影響を受けながら変遷して来ており, 言わば酒類制度は, その国の酒類に関する歴史, 文化の裏返しであるとも言える。著者らは, カナダのケベック州のスピリッツを中心にした酒類制度を, 行政, 酒税制度, 組織, 許認可, 歴史など, 多面的な角度から調査した。現在の欧米の酒類制度と日本の酒類制度を文化や歴史を踏まえて比較するうえで, 参考になる調査となっている。
1 0 0 0 OA exo-3-ホルミル-3-メチルショウノウの合成
- 著者
- 鈴木 洸次郎 谷相 美智 毛利 智代 藤山 亮治 清岡 俊一
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.2, pp.257-259, 1987-02-10 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
exo-3-Formy1-3-methylcamphor was synthesized by a following route, for the purpose of asymmetric alkylation of glycine.Methyl 3-methyl-3-camphorca rboxylates [4] were obtained by the methylation of methyl 3-camphorcarboxylate [3] with sodium hydride and methyl iodide in good yield. The products were separated into two parts by treating with ligroine, i. e. a crystalline part [4a](mp 88-48.5°C) and an oily one [4b]. It was found that the structure of [4a] was determined as exo-3-carboxylate and that of [4b] was as endo-one by the analyses of their NMR data. The reduction of [4a] with LiAlH4 gave diol[5] And exo-3-formy1-3-methylcampho r was obtained as a slightly unstable liquid (bp 123°C/13 mmHg, [α]D20 162.5°) by the oxida-tion of [5] with Collins' reagent.