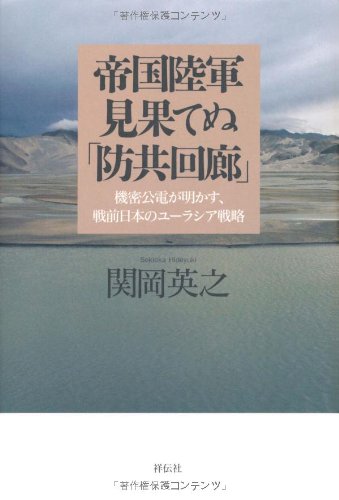10 0 0 0 OA サルコペニアを有する高齢胃癌患者に対する新しい取組み
- 著者
- 山本 和義 永妻 佑季子 福田 泰也 西川 和宏 平尾 素宏 鳥山 明子 中原 千尋 宮本 敦史 中森 正二 関本 貢嗣 藤谷 和正 辻仲 利政
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.175-182, 2017 (Released:2018-02-22)
- 参考文献数
- 16
加齢に伴う筋力,身体機能の低下と定義されるサルコペニアは各種疾患でその概念が普及し,治療アウトカムにおける影響が盛んに報告されている.われわれも高齢胃癌患者におけるサルコペニア症例が非サルコペニア症例にくらべて術前摂取エネルギー量,タンパク質量が有意に少なく,サルコペニアが胃癌術後の重篤な合併症発生の独立したリスク因子であることを報告している.つぎのステップとして,初診時にサルコペニアと診断された65 歳以上の高齢胃癌術前患者を対象にして,エクササイズとしてハンドグリップ,ウォーキング,レジスタンストレーニング,栄養介入として1 日28kcal/kg(IBW)のエネルギー量と1.2g/kg(IBW)のタンパク質の摂取およびβ-hydroxy-β-methylbutyrate(HMB)の補充を推奨する,「術前栄養+エクササイズプログラム」を作成・実践しているので,その概要について報告する.
10 0 0 0 新潟地方に産するテツギョの形態と倍数体
- 著者
- 関谷 伸一 本間 義治
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- 動物分類学会誌 (ISSN:02870223)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.53-60, 1975-10-30
佐渡を含む新潟県内の各地から採集したテツギョ44尾について,若干の外部ならびに内部の形態形質を調べ,さらにそのうち12尾については染色体を観察した。その結果,尾鰭の長さは,フナに似て短かいものから,体長の半分に達するものまであり,全長/体長の比は,1.38〜1.65の値を示した。得られたテツギョの大半は3倍体で,3n=153であり,これらの腸型はキンブナないしナガブナに固有のA型であった。一方,佐渡の2地点より得た2倍体のテツギョの腸型は判定不能であり,その複雑さより,キンギョとフナの雑種でないかと考えられた。2倍体のテツギョは両性よりなるが,3倍体はすべて雌であり,しかも2倍体や3倍体のフナと混生していた。また,地方差を比較するために,魚取沼蛮のテツギョ2尾の染色体を詞べたところ,染色体数約100の2倍体であった。
10 0 0 0 OA 疥癬診療ガイドライン(第3版)
- 著者
- 日本皮膚科学会疥癬診療ガイドライン策定委員会 石井 則久 浅井 俊弥 朝比奈 昭彦 石河 晃 今村 英一 加藤 豊範 金澤 伸雄 久保田 由美子 黒須 一見 幸野 健 小茂田 昌代 関根 万里 田中 勝 谷口 裕子 常深 祐一郎 夏秋 優 廣田 孝司 牧上 久仁子 松田 知子 吉住 順子 四津 里英 和田 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.11, pp.2023-2048, 2015-10-20 (Released:2015-10-22)
- 参考文献数
- 185
Here, we present our new guideline for the diagnosis and treatment of scabies which we, the executive committee convened by the Japanese Dermatological Association, developed to ensure proper diagnosis and treatment of scabies in Japan. Approval of phenothrin topical use under the National Health Insurance in August 2014 has contributed to this action. Permethrin, a topical anti-scabietic medication belonging to the same pyrethroid group as phenothrin, is already in use worldwide. For making proper diagnosis of scabies, following three points should be taken into consideration: clinical findings, detection of the mite(s) (Sarcoptes scabiei var. hominis), and epidemiological findings. The diagnosis is confirmed when the mites or their eggs are identified by microscopy or by dermoscopy. As we now have a choice of phenothrin, the first line therapy for classical scabies is either topical phenothrin lotion or oral ivermectin. Second line for topical treatment is sulfur-containing ointments, crotamiton cream, or benzyl benzoate lotion. Gamma-BHC ointment is no more provided for clinical use. If the patient is immunosuppressed, the treatment option is still the same, but he or she should be followed up closely. If the symptoms persist, diagnosis and treatment must be reassessed. For hyperkeratotic (crusted) scabies and nail scabies, removal of thick scabs, cutting of nails, and occlusive dressing are required along with topical and/or oral treatments. It is important to apply topical anti-scabietic lotion/cream/ointment below the neck for classical scabies or to the whole body for hyperkeratotic scabies, including the hands, fingers and genitals. For children and elderlies, it is recommended to apply treatment to the whole body even in classical scabies. The dosage for ivermectin is a single oral administration of approximately 200 μg/kg body weight. It should be taken on an empty stomach with water. Administration of a second dose should be considered at one-week with new lesions and/or with detection of mites. Safety and effectiveness of combined treatment with topical and oral medications are not yet confirmed. Further assessment is needed. Taking preventative measures is as important as treating those infected. It is essential to educate patients and healthcare workers and conduct epidemiological studies to prevent further spread of the disease through effectively utilizing available resources including manpower, finance, logistics, and time. (Jpn J Dermatol 125: 2023-, 2015)
10 0 0 0 OA 写真計測により捉えた2008年岩手・宮城内陸地震における地表面の変位量の分布
- 著者
- 神谷 泉 小荒井 衛 関口 辰夫 佐藤 浩 中埜 貴元 岩橋 純子
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.5, pp.854-874, 2013-10-25 (Released:2013-10-31)
- 参考文献数
- 31
SAR interferometry is widely used for dense measurements of surface displacements caused by earthquakes, but the method cannot be applied if displacements are too large. The near-epicentral area of the Iwate–Miyagi Nairiku Earthquake in 2008 is an inapplicable case. Therefore, we applied photogrammetry to measure surface displacement caused by the earthquake. The maximum horizontal and vertical displacements were found to be 5.3 m and 2.9 m, respectively. We recognized three lines where displacement changes abruptly. The displacement distribution is like that of a reverse fault along the first line (A–B), an east-rising fault along the second line (F–G–H; west of line A–B), and a left-lateral fault along the third line (B–C; between line A–B and line F–G–H). The earthquake source fault reaches or approaches the ground surface at line A–B, with slippage decreasing toward the ground surface. The fault-like large surface deformation found north of the Aratozawa Dam is on the first line. The fault-like deformation was caused by the motion of the earthquake source fault, and the relative displacement of the fault-like deformation was enlarged by local causes. A gravitational mass movement found north of the fault-like deformation is one cause. Because the width of the rising area is small, only 3.5 km, at the southwestern side of line B–C, the slip of the earthquake source fault is mainly distributed near the ground. Line F–G–H suggests the existence of a geological structure that causes the abrupt changes of vertical displacement without a horizontal displacement, for example a high-angle fault. We assumed: (1) the slip on the main fault is distributed only in a shallow area at the southern part of the main fault and only in a deep area at the northern part; and, (2) the difference of slip caused two lateral faults between southern and northern parts. The assumption qualitatively explains many observation results, such as why there is an abrupt change of horizontal displacement along line B–C and why line F–G–H has a convex part to the east. We found a correlation between the occurrence of large landslides and abrupt changes of displacement, in other words large surface strain. The following mechanisms are possible causes of the correlation: (1) stress from surface strain increased large landslides; (2) faults (not only the main fault) may exist under the focused areas, rupture of faults caused both large surface strain and large seismic motion, and seismic motion induced large land slides. We also found that landslides and slope failures occurred densely over the slipping area on the main fault, based on the assumptions in the previous paragraph. Because photogrammetric measurements need interactive observations, we could avoid observations on possible embanking areas. Because photogrammetry allows intensive measurements at interesting areas, we revealed a two flexure-like distribution of vertical displacement. Therefore, photogrammetry is an effective method for measuring surface displacement caused by an earthquake.
9 0 0 0 OA 自転車の通行方法と事故の危険性について-歩道のある単路部での検討-
- 著者
- 横関 俊也 萩田 賢司 矢野 伸裕 森 健二
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.5, pp.I_1095-I_1104, 2016 (Released:2016-12-23)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3 3
本研究では,千葉県東葛地域を対象として,通行方法別に分類した自転車の遭遇台数調査のデータと自動車と自転車間で発生した事故の統計データを用い,自転車の通行方法別に事故率の比較を行った.その結果,進行サイドでの比較では,車道における自転車の右側通行の危険性は左側通行の2.8倍高くなった.歩道においても同様に自転車の右側通行の危険性は左側通行の2.7倍高いという結果になった.また,通行位置による比較では,自転車の歩道走行(左側通行・右側通行)と比較した車道走行(左側通行)の危険性は3.0倍となり,車道走行の危険性が高くなっていた.以上により,自転車に通行方法を遵守させるためにも,より安全な自転車の車道走行環境を形成していく必要性が示唆された.
9 0 0 0 OA 駿河敬次郎医師とキリスト教
- 著者
- 関 智征 Tomoyuki SEKI
- 出版者
- フェリス女学院大学
- 雑誌
- フェリス女学院大学キリスト教研究所紀要 (ISSN:24239127)
- 巻号頁・発行日
- vol.08, pp.103-109, 2023-03
9 0 0 0 自転車走行空間における自転車通行方向別の交通量と事故特性の比較
- 著者
- 萩田 賢司 横関 俊也
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.I_493-I_506, 2019 (Released:2019-12-26)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
平成29年の全国の交通事故統計により,自転車専用走行空間や歩道,横断歩道,路側帯等における通行方向別(右側通行/左側通行)の自転車事故発生割合を集計し,先行研究で調査された通行方向別自転車交通量と比較した.交差点では通行方向別の自転車事故件数に大きな差はなかったが,単路の歩道では,自転車交通量は左側通行がやや多い傾向にあったものの,自転車事故は右側通行の割合が非常に高かった.また,自転車の左側通行が原則である自転車専用通行帯や路側帯においても,右側通行自転車が関与した 事故が約40%であり,自転車専用通行帯等の通行方向別自転車交通量より高い割合であった.右側通行自転車は交差側自動車に見落とされやすいと推察され,自転車交通量と比較して自転車事故が多く発生している傾向にあることが窺えた.
9 0 0 0 OA 脳脊髄液漏出症の臨床像 -自験例を中心に-
- 著者
- 大隣 辰哉 大田 慎三 関原 嘉信 西原 伸治 大田 泰正 佐藤 倫由 田中 朗雄
- 出版者
- 産業医科大学、産業医科大学学会
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.231-242, 2015-09-01 (Released:2015-09-12)
- 参考文献数
- 25
脳脊髄液漏出症は特発性または時に外傷性に発症し,起立性頭痛や誘因のない慢性硬膜下血腫(CSDH)の原因となる稀な疾患である.我々はこの連続20例の治療経験があり,この疾患の現状と問題点も含め報告する.2006年4月から2014年3月までにCTミエログラフィー(CTM)または脊髄MRIで硬膜外髄液漏出を確認した連続20例(女性11例,年齢44.7±12.1歳,22-65歳)の臨床的特徴を後ろ向きに調査した.症状は,起立性頭痛のみが10例,起立性頭痛にCSDH合併が6例,体位と無関係の頭痛にCSDH合併が4例であった.治療は,2例で直達術での縫合またはフィブリン糊による瘻孔閉鎖を施行した.14例で硬膜外自己血パッチ(EBP)を施行(うち1例は上記直達術),後半9例は血管内カテーテルを用いた腰椎からの単回アプローチでの広範囲EBPを施行した.穿頭血腫ドレナージ施行の1例を含む残る5例は,輸液のみで治療した.症状が頭痛のみの10例中9例は,この消失または軽減が得られた.CSDHを合併した10例は,1例で穿頭血腫ドレナージ後に輸液のみで治療,9例でドレナージ後にEBPを施行して全例再発を抑制できた.脳脊髄液漏出症はいまだ病態が不明だが,CTMおよび脊髄MRIにて的確に診断し,点滴加療が無効,起立性頭痛が高度またはCSDHを繰り返す症例には,血管内カテーテルを用いた広範囲EBPでほぼ治癒可能とわかった.
9 0 0 0 ECMPの拡張によるハードウェアロードバランサの提案
本研究では,Equal Cost Multi-path (ECMP) を拡張することで既存の ECMP の欠点を解消した新しいロードバランス手法を提案する.一般的なハードウェアルータの持つ ECMP 機能はトラフィックをフローごとに複数のネクストホップに分散することができる.つまり ECMP をそのままロードバランサとして利用できれば,専用の機材を導入するのと比較してコスト面,運用面における負荷が少ない.しかし ECMP は,フローのハッシュ値とネクストホップ数によってパケットの転送先を決定するため,ネクストホップとなるサーバの数が増減した場合,既存のコネクションが異なるサーバに届き切断されるという問題がある.本研究では,この問題を解決するため ECMP を拡張した ECMP with Explicit Retransmission (ECMP-ER) を提案する.ECMP-ER は Layer-3 の ECMP を基礎としており,既存の経路制御プロトコルで動作する.その上で ECMP-ER では,ルータが ECMP の経路について,現在のネクストホップに加えて過去のネクストホップ情報も保持する.サーバの増減時に異なるサーバに届いたフローのパケットは,サーバがルータへ再送し,さらにルータが過去のネクストホップを参照して再送することで最終的に適切なサーバへ転送される.本研究では ECMP-ER を P4 スイッチを用いて試作し評価した結果,ECMP では 20% 以上のコネクションが切断される状況においても,ECMP-ER は全てのコネクションを維持したままトラフィックを分散できることを確認した.
9 0 0 0 OA COVID-19をめぐるメディア・コミュニケーションとその課題
- 著者
- 田中 幹人 石橋 真帆 于 海春 林 東佑 楊 鯤昊 関谷 直也 鳥海 不二夫 吉田 光男
- 出版者
- 公益財団法人 医療科学研究所
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.71-82, 2022-04-28 (Released:2022-05-26)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
新興感染症であるCOVID-19に対処する中では,日々更新されるリスク知識を社会で共有し,また政策から個々人のレベルに至るまでリスクを判断していく必要があった。このリスク情報の流通と議論の場となってきたのは,もちろんメディアである。本稿では,我々の研究結果を基に,まず情報の送り手である新聞報道の傾向を振り返り,また情報の受け手である日本のメディア聴衆の相対的リスク観を把握する。そのうえで,ソーシャルメディアを含むオンラインメディア上でのコミュニケーションの成功例,失敗例を確認し,そこから教訓を得る。更にマス/オンラインメディアが複雑に絡み合う中で,COVID-19禍を通じて明らかになった感染者差別,ナショナリズム,懐疑論や隠謀論といった問題を確認したうえで,コミュニューション研究の知見を踏まえて,リスクのより良い社会共有に向けた方針を提示することを目指す。COVID-19という災害は,新興感染症として私達の医療・社会制度の刷新を求めているのみならず,コミュニケーションを通じたリスク対応のあり方についても大きな変革を求めているのである。
9 0 0 0 OA 座談会 : 日本における日本政治思想研究の現状と課題
- 著者
- 矢後 勝也 平井 規央 小沢 英之 佐々木 公隆 谷尾 崇 伊藤 勇人 遠藤 秀紀 中村 康弘 永幡 嘉之 水落 渚 関根 雅史 神宮 周作 久壽米木 大五郎 伊藤 雅男 清水 聡司 川口 誠 境 良朗 山本 以智人 松木 崇司
- 出版者
- 公益財団法人 自然保護助成基金
- 雑誌
- 自然保護助成基金助成成果報告書 (ISSN:24320943)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.233-246, 2020-01-10 (Released:2020-01-10)
- 参考文献数
- 11
シカの急増に伴う林床植生の食害により国内で最も絶滅が危惧されるチョウと化したツシマウラボシシジミの保全を目的として,a)保全エリアでの実践的な保護増殖活動,b)保全エリア候補地の探索に関する活動,c)希少種保全と農林業との連携に関する活動,の大きく3つの課題に取り組んだ.保護増殖活動では,環境整備やシカ防護柵の増設により保全エリアの改善を試みた他,現状の環境を把握するためにエリア内の林床植生および日照・温度・湿度を調査した.今後の系統保存と再導入のために越冬・非越冬幼虫を制御する光周性に関する実験も行った結果,1齢幼虫から日長を感知する個体が現れることが判明した.保全エリア候補地の探索では,本種の好む環境を備える椎茸のホダ場30ヶ所を調査し,良好な環境を保持した11ヶ所のホダ場を見出した.保全と農林業との連携では,アンケート調査から多くの地権者や椎茸農家の方々は本種の保全に好意的なことや,本種を育むホダ場で生産された椎茸のブランド化に賛成で,協力可能であることなども明らかとなった.
9 0 0 0 OA XI.中性子の利用 1.RI製造
- 著者
- 関根 俊明
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.9, pp.670-674, 1997-09-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 11
9 0 0 0 IR 沖縄ジュゴン対ラムズフェルド事件米国連邦地裁決定訳と解説 : 沖縄ジュゴンと法の支配
- 著者
- 関根 孝道
- 出版者
- 関西学院大学
- 雑誌
- 総合政策研究 (ISSN:1341996X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.165-197, 2005-09-20
On March 2, 2005, the United States District Court Nothern District of California gave an epochmaking decision. The decision held: in light of the many similarities between the lists generated by the Japanese Law for the Protection of Cultural Properties and the U.S. National Historic Preservation Act ("NHPA"), the Japanese Law is an "equivalent of the National Register" under the NHPA within the meaning of section 470a-2 thereof; since the Okinawa dugong is protected under Japanese Law on the basis of its cultural significance to the Okinawan people, section 470a-2 of the NHPA can apply to the Okinawa dugong, an animal protected for cultural, historical reasons under a foreign country's equivalent statutory scheme for cultural preservation; while section 470a-2 applies to "any federal undertaking outside the United States", it can as a matter of law apply to the undertakings alleged by plaintiffs in that case because plaintiffs have alleged and provided evidence to show that the contested actions and decisions were undertaken by the U.S. Department of Defense and thus constitute a federal undertaking which may directly and adversely affect a property, the Okinawa dugong; since the case at issue deals with a statute, unlike the NEPA, explicitly demonstrates Congress's intent that it apply abroad where a federal undertaking promises to have direct or adverse effects on protected foreign properties, the cort must construe section 470a-2 in accordance with the statutory text-to preclude enforcement as a blanket rule based on the act of state doctrine would empty section 470 of any meaning; since the record before the court does not currently describe an "official act of a foreign sovereign perfomed within its own territory," but rather a process intertwined with U.S. Department of Defense decision-making, the court evaluates the actions of a federal agency for the act of state doctrine not being implicated. This decison is extremely significant mainly for the Okinawa dugong protection and U.S. military facilities issues here in the future.
9 0 0 0 OA 日本の家庭を隅々までつないだ黒電話
- 著者
- 鈴木 利雄 川治 健一 関口 理希 石川 智士 伊藤 智博 立花 和宏
- 出版者
- 科学・技術研究会
- 雑誌
- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.123-1128, 2016 (Released:2016-07-07)
関東大震災をきっかけに固定電話網の整備のためにダイヤル式電話機と自動交換機の技術のニーズは生まれ、黒電話が産声を上げた。終戦を経て高度成長期に黒電話の完成版600型が世に姿を表した。電電公社がダイヤル自動化100 %を目指す中、日本はオイルショックの狂乱物価に見舞われた。黒電話の製造コストを下げるため、完成されたと言われた黒電話600型をさらに改善することを余儀なくされた。山形大学工学部電気工学科を卒業して間もない鈴木を中心として山形県米沢市の田村電機で黒電話601A型ダイヤル開発が行われた。新しく開発された黒電話601A型は日本の家庭を電話で隅々までつないだといっていい。本稿はその開発の状況がいかがなものであったか時代背景とともに書き残すものである。
9 0 0 0 OA 単為生殖型肝蛭(日本産肝蛭)はどこからきたか?その起源と日本国内における分布について
- 著者
- 関(市川) まどか 城間 友子 正力 拓也 林 慶 板垣 匡
- 出版者
- 日本家畜臨床学会 ・ 大動物臨床研究会
- 雑誌
- 産業動物臨床医学雑誌 (ISSN:1884684X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.133, 2014-11-14 (Released:2014-12-10)
9 0 0 0 東日本大震災における「避難」の諸問題にみる日本の防災対策の陥穽
- 著者
- 関谷 直也
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集F6(安全問題) (ISSN:21856621)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.I_1-I_11, 2012
- 被引用文献数
- 5
日本の防災対策は「想定」を前提とした訓練,ハザードマップ,防災教育や災害時の情報伝達などの手段で避難を促すというソフト対策に過度に重点が置かれている.<br> 結果,ありとあらゆるところに想定を設け,それにのっとって対策を整えるという「想定主義」に陥っている.そして避難についても,現実的な解を見つけるというより「原則車避難禁止」「危機意識をもって急いで逃げれば被災は回避できる」といった避難の課題を人々の防災意識に帰結する「精神主義」が跋扈している.また,あらゆる災害対策の前提となる被災の原因の検証についても,メディアで言われていることや思い込みで仮説を構築し,そこから改善策を検討・導出してしまう「仮説主義」に陥っている.だが,実際に調査検証が進むに従って,そもそも仮説自体が誤っているといったことが多くみられる.<br> これら日本の防災対策の問題点は東日本大震災を踏まえても何も変わっていない.「想定」を重視するのではなく行動の規範を考えること,精神論だけを強調するのではなくハード対策とソフト対策のバランスという原点に立ち返ること,メディアの論調や思い込みではなく,予断を持たず,徹底的に東日本大震災の被災の現実に,科学的実証的に向き合うことが求められる.