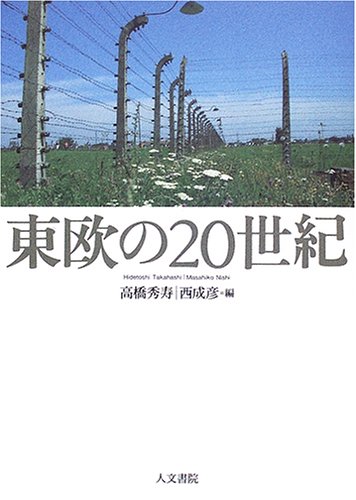1 0 0 0 OA 全国の介護保険レセプトを用いた在宅介護のフォーマルケア時間推計
- 著者
- 佐藤 幹也 田宮 菜奈子 伊藤 智子 高橋 秀人 野口 晴子
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.287-294, 2019-06-15 (Released:2019-06-21)
- 参考文献数
- 22
目的 全国の介護報酬明細個票(介護保険レセプト)から介護サービス利用額を利用時間に換算し,在宅要介護者のフォーマルケア時間を要介護度別に推計して在宅介護の公平性を検討した。方法 調査対象は2013年6月に介護保険在宅介護サービス(居宅系サービスと通所系サービスを合わせた狭義の在宅介護サービス,および短期入所サービスに細分化)を利用した全国の65歳以上の要介護者(要介護1-5)2,188,397人である。介護報酬の算定要件に基づいて介護保険サービスのサービス項目ごとにケア時間を設定し,利用者ごとに1か月間の利用実績を合算して得られたケア時間を30で除したものを1日当たりのフォーマルケア時間として,これを男女別に層化した上で要介護度別に集計した。結果 居宅系サービスと通所系介護サービスの狭義の在宅介護サービスおよび短期入所サービスを合算した1日当たりの総フォーマルケア時間は,要介護1で男性97.4分と女性112.7分,要介護2で118.3分と149.1分,要介護3で186.9分と246.4分,要介護4で215.2分と273.2分,要介護5で213.1分と261.4分であった。短期入所サービスのフォーマルケア時間は要介護度とともに増加したが,短期入所を除いた狭義の在宅介護サービスのフォーマルケア時間は要介護3で頭打ちとなり要介護4-5ではむしろ減少した。狭義の在宅サービスをさらに居宅系介護サービスと通所系介護サービスに細分化すると,前者は要介護度に応じて増加したが,後者は要介護3で頭打ちとなっていた。結論 在宅介護サービスの利用量を時間の観点から評価した本研究の結果からは,介護ニーズが増大する要介護4-5の在宅要介護者でむしろフォーマルケアの供給が減少しており,介護保険制度によるフォーマルケアは必ずしも介護ニーズに対して公平ではないことが分かった。在宅介護の公平性を保ちつつ介護保険制度の持続可能性を高めるためには,高要介護度者に対して時間的効率性の高い在宅介護サービスを推進するなどして高要介護度者のフォーマルケア時間を増加させるような施策を推進する必要があると考えられた。
1 0 0 0 OA S-netを用いた海域総合解析
- 著者
- 内田 直希 東 龍介 石上 朗 岡田 知己 高木 涼太 豊国 源知 海野 徳仁 太田 雄策 佐藤 真樹子 鈴木 秀市 高橋 秀暢 立岩 和也 趙 大鵬 中山 貴史 長谷川 昭 日野 亮太 平原 聡 松澤 暢 吉田 圭佑
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2019年大会
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-14
沈み込み帯研究のフロンティアである前弧の海域下において,防災科学技術研究所は新たに日本海溝海底地震津波観測網(S-net)を構築した.S-netは東北日本の太平洋側の海岸から約200kmの範囲を海溝直交方向に約30km,海溝平行方向に50-60km間隔でカバーする150点の海底観測点からなり,その速度と加速度の連続データが,2018年10月より2016年8月に遡って公開された.観測空白域に設置されたこの観測網は,沈み込み帯の構造およびダイナミクスの解明に風穴をあける可能性がある.本発表ではこの新しいデータを用いた最初の研究を紹介する.まず,海底の速度計・加速度計の3軸の方向を,加速度計による重力加速度および遠地地震波形の振動軌跡を用いて推定した.その結果,2つの地震に伴って1°以上のケーブル軸周りの回転が推定されたが,それ以外には大きな時間変化は見られないことがわかった.また,センサーの方位は,5-10°の精度で推定できた.さらに得られた軸方向を用い,東西・南北・上下方向の波形を作成した(高木・他,本大会).海底観測に基づく震源決定で重要となる浅部の堆積層についての研究では,PS変換波を用いた推定により,ほとんどの観測点で,350-400mの厚さに相当する1.3 – 1.4 秒のPS-P 時間が観測された.ただし,千島-日本海溝の会合部海側と根室沖の海溝陸側では,さらに堆積層が厚い可能性がある(東・他,本大会).また,雑微動を用いた相関解析でも10秒以下の周期で1.5 km/s と0.3 km/sの2つの群速度で伝播するレイリー波が見られ,それぞれ堆積層と海水層にエネルギーを持つモードと推定された(高木・他,本大会).さらに,近地地震波形の読み取りによっても,堆積層およびプレート構造の影響を明らかにすることができた.1次元および3次元速度構造から期待される走時との比較により,それぞれ陸域の地震の海溝海側での観測で3秒程度(岡田・他,本大会),海域の地震で場所により2秒程度(豊国・他,本大会)の走時残差が見られた.これらは,震源決定や地震波トモグラフィーの際の観測点補正などとして用いることができる(岡田・他,本大会; 豊国・他,本大会).もう少し深い上盤の速度構造もS-netのデータにより明らかとなった.遠地地震の表面波の到達時間の差を用いた位相速度推定では,20-50sの周期について3.6-3.9km/sの位相速度を得ることができた.これはRayleigh波の位相速度として妥当な値である.また,得られた位相速度の空間分布は,宮城県・福島県沖の領域で周りに比べて高速度を示した(石上・高木,本大会).この高速度は,S-netを用いた近地地震の地震波トモグラフィーからも推定されている.また,このトモグラフィーでは,S-netの利用により海溝に近い場所までの速度構造がよく求まることが示された(豊国・他,本大会).雑微動解析によっても,周期30秒程度の長周期まで観測点間を伝播するレイリー波およびラブ波を抽出することができた.これらも地殻構造の推定に用いることができる(高木・他,本大会).また,海域の前弧上盤の構造についてはS-net 観測点を用いたS波スプリッティング解析によって速度異方性の特徴が明らかになった.プレート境界地震を用いた解析から,速いS波の振動方向は,海溝と平行な方向を向く傾向があり,マントルウエッジの鉱物の選択配向や上盤地殻のクラックの向きを表している可能性がある(内田・他,本大会).プレート境界においては,繰り返し地震がS-net速度波形によっても抽出できることが示された.プレート境界でのスロースリップの検出やプレート境界の位置推定に役立つ可能性がある(内田・他,本大会).さらに,S-net加速度計のデータの中には,潮汐と思われる変動が観測されるものもあり,プレート境界におけるスロースリップによる傾斜変動を捉えられる可能性があるかもしれない(高木・他,本大会).以上のように,東北日本の前弧海洋底における連続観測について,そのデータの特性が明らかになるとともに,浅部から深部にわたる沈み込み帯の構造や変動についての新たな知見が得られつつある.これらの研究は技術的にも内容的にもお互いに密接に関わっており,総合的な解析の推進がさらなるデータ活用につながると考えられる. 謝辞:S-netの構築・データ蓄積および公開に携わられた皆様に感謝いたします.
- 著者
- 桑村 常彦 高橋 秀男 三柴 三郎 小野 正寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌 (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.1973, no.12, pp.2370-2377, 1973
- 被引用文献数
- 1
ペンタエリトリットの女直n-アルキルエーテル,(ROCH2) .C(CH20H)4-x (x=1~3, R=C3~C rs)への酸化エチレン(EO)重付加により,ポリオキシエチレン(POE)似非イオン性界面活性剤を合成し,疎水部におけるアルキル総炭素数(N)の等しい既知非イオン活性剤との比較のもとに,その曇り点(Cp),表面張力(rCMC), CMCにおよぼす熟瓜構造およびポリエーテル型連結部の影響について検討した。<BR>(1)一般に疎水部のアルキル鎖数(A)の増加はCp,7 CMCを低下, CMCを増大させるが, Aが2と3でのrcMc, CMCの差異は少ない。 Aが3の場合,rcMcはRがC3からC6の範囲で変化しない。Aが2以上,とくec 3の場合, CMCの対数とNの関係は直線ゆらはずれ,上方 型曲線となる。<BR>(2)同一系列,同一HLBd(DaviesのHLB値)では高級同族体ほど高いCpを示す。(3)連結部のエーテル型酸素は見かけ上親水牲に寄与しない。(4)POE鎖数(P)の多い系列はHLB,から予想されるよりかなり低いCpを示す。 P 2では,一般にEO付加数の増加とともにlogCMCが直線的に減少し,その傾きはPおよびRの大きいほどいちじるしい。<BR>以上の結果について,主としてPOE鎖の配置状態,水和性の観点から論議した。
1 0 0 0 MEGの臨床応用の現状とガンマ帯域活動解析の最新知見
- 著者
- 石井 良平 池澤 浩二 カヌエト レオニデス 高橋 秀俊 中鉢 貴行 疇地 道代 栗本 龍 岩瀬 真生 武田 雅俊
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 脳と精神の医学 = Brain science and mental disorders (ISSN:09157328)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.199-206, 2009-09-25
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA [史料紹介] 「田中穣氏旧蔵典籍古文書」所収の記録類について
- 著者
- 高橋 秀樹
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.35-44, 1997-03-28
本稿は修訂の上『国立歴史民俗博物館資料目録[1]田中穣氏旧蔵典籍古文書目録[古文書・記録類編]』(国立歴史民俗博物館、2000年)に解題として再録されている
1 0 0 0 OA 自閉症スペクトラム児の聴覚性驚愕反射に関する神経生理学的検討
- 著者
- 高橋 秀俊 中鉢 貴行 森脇 愛子 武井 麗子 飯田 悠佳子 荻野 和雄 神尾 陽子
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.229-234, 2013 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 26
自閉症スペクトラム障害(ASD)では,知覚処理の非定型性について知られており,低次の知覚処理機能と高次の機能との関連の脳内基盤の発達的変化を明らかにすることは,ASDの病態形成メカニズムを理解する手がかりとなりうると考えられる。聴覚性驚愕反射(ASR)は,精神医学領域におけるトランスレーショナル・リサーチにおいて,国内外で広く研究されている。今回我々は, ASD 児 10名とそうでない児童34名を対象に,ASR検査を実施した。聴覚刺激として,65 ~ 110dB まで 5dBきざみで10段階の音圧の聴覚刺激を提示した。さらに,対人応答性尺度で評価された定量的自閉症特性との関連も検討した。ASD 児では,ASRの潜時が延長しており,微弱な刺激に対するASR が亢進しており,これら ASR の指標は,いくつかの自閉症特性と相関した。ASR の指標が, ASDの病態解明に関して有用である可能性が示唆された。
1 0 0 0 P-188 動物実験による子宮移植の基礎的検討.
- 著者
- 岡本 一 西田 正人 林 陽子 和田 篤 田中 奈美 高橋 秀元 川崎 彰子 久保 武士
- 出版者
- 社団法人日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp."435(S-359)", 2000-02-01
1 0 0 0 IR 千葉大学における英語教育 : 回顧と現状と展望1994-2005
- 著者
- 星野 惠津夫 井上 美貴 高橋 秀徳
- 雑誌
- 漢方の臨床 (ISSN:0451307X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.7, pp.1033-1041, 2008-07-25
- 著者
- 星野 惠津夫 井上 美貴 高橋 秀徳
- 雑誌
- 漢方の臨床 (ISSN:0451307X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.8, pp.1175-1182, 2008-08-25
- 著者
- 重福 隆太 松永 光太郎 田村 知大 小澤 俊一郎 松尾 康正 高橋 秀明 松本 伸行 奥瀬 千晃 鈴木 通博 伊東 文生
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.2, pp.263-272, 2016-02-05 (Released:2016-02-05)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
今回,口腔内常在菌であるStreptococcus intermediusによる化膿性肝膿瘍を経験し,その感染経路の検索で早期胃癌を診断した.胃低酸状態ではStreptococcusを中心とした胃細菌叢が形成され,さらに糖尿病,高齢など粘膜免疫低下を呈する病態が存在する場合,上部消化管疾患が細菌の侵入経路となる可能性があり十分に留意すべきである.
1 0 0 0 レタス芽生えの低pHによる根毛形成-細胞骨格系の役割
- 著者
- 川原 愛子 高橋 秀典 井上 康則
- 出版者
- 日本植物生理学会
- 雑誌
- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.771, 2005
中性培地(pH6)で育てたレタス芽生えを酸性培地(pH4)に移すと根毛形成を行なう。この根毛形成には、細胞長軸に対して垂直に配向していた表皮細胞の表層微小管(CMT)の配列が崩壊することが必須である。CMT配向のランダム化はオーキシンにより引き起こされ、エチレンはオーキシンの効果を増強させる。本研究では、表皮細胞のアクチンフィラメント(MF)が根毛形成にどう関与しているのか調べた。<br>pH4培地にサイトカラシンBまたはジャスプラキノライドを添加してMFの重合、脱重合を阻害すると根毛形成は抑制された。この時の根毛形成阻害はIAAまたはエチレン前駆体ACCを添加しても回復しなかった。また、pH6でMFの重合、脱重合を阻害すると根毛形成は阻害されたが、CMTランダム化は引き起こされた。このCMTランダム化はオーキシン拮抗阻害剤PCIBまたはエチレン生合成阻害剤AVGを添加しても阻害されなかった。さらに、pH6培地にコルヒチンを添加し、CMTを脱重合させると根毛形成は誘導されたが、ここにPCIBまたはAVGを添加すると根毛形成は抑制された。AVGによる根毛形成阻害はIAA添加により回復したが、PCIBによる阻害はACC添加では回復しなかった。<br>以上のことから、低pHによる根毛形成には、MFの重合・脱重合、CMTの垂直配向の崩壊、オーキシンが必要だとわかった。
1 0 0 0 IR ニュートンと幾何学的精神 : エウクレイデス『ポリスマタ』の復元 (数学史の研究)
- 著者
- 高橋 秀裕
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1257, pp.48-63, 2002-04
1 0 0 0 OA 頂芽優勢が消失したシロイヌナズナnoah突然変異体の単離および解析
- 著者
- 渡辺 明夫 百目木 幸枝 軸丸 裕介 笠原 博幸 神谷 勇治 佐藤 奈美子 高橋 秀和 櫻井 健二 赤木 宏守
- 出版者
- 日本植物生理学会
- 雑誌
- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集 第52回日本植物生理学会年会要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.0053, 2011 (Released:2011-12-02)
多くの植物種では頂芽の成長が優先され側芽の成長が抑えられる頂芽優勢と呼ばれる機構が働き、全体の草型が制御される。私たちは主茎や側枝が長期間伸長を続け、最終的に鳥の巣のような姿となるシロイヌナズナ変異体を見いだした。解析の結果、この独特の草姿は、全ての枝の茎が頂芽優勢による抑制をのがれ長期間伸長を続けることに主な原因があり、一枝当りの分枝数は極端には増加していないことが分かった。頂芽優勢を免れて全ての茎が伸長を続ける表現型は単一の劣性変異に起因していたため、この原因変異をnoah (no apical dominance in branch hierarchy)と名付け、noah変異体の特異な草姿形成機構の解明を試みた。 主茎や側枝の伸長を詳細に調べた結果、WTの茎では茎頂から約1.5 cmほど下部を中心に幅広い領域が伸長していたのに対し、noah変異体の茎では茎頂から約0.5 cm以内の狭い領域のみが伸長していた。茎の細胞伸長が茎中を極性輸送されるオーキシンにより引き起こされると考えると、上記の結果は変異体の茎中のオーキシン分布が著しく変化していることを意味していた。そこでオーキシン濃度を詳細に測定した結果、変異体の茎のオーキシン分布はWTのものと著しく異なっていた。このため、noah変異体では茎中のオーキシンの極性輸送が著しく撹乱されていることが推察された。
1 0 0 0 遠隔指示の一方式-KT方式
- 著者
- 近藤 正夫 高橋 秀俊
- 出版者
- 運輸技術研究所
- 雑誌
- 運輸技術研究所報告 (ISSN:05006627)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.163-171, 1953-04
- 著者
- 古賀 実芳 日高 千鶴乃 廣田 薫 平馬 直樹 高橋 秀実
- 出版者
- 社団法人日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋醫學雜誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, 2006-05-31
- 著者
- 深田 和浩 藤野 雄次 網本 和 井上 真秀 高石 真二郎 牧田 茂 高橋 秀寿
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに】Pusher現象は,非麻痺側上下肢で接触面を押し,他動的な姿勢の修正に対し抵抗する現象であり,その評価と治療は重要である。Pusher現象を客観的に評価するための方法として,Karnathらが開発したScale of Contraversive Pushing(以下,SCP)が一般的に用いられ,測定再現性や妥当性が良好であることが報告されている。このSCPは,Pusher現象の診断において感度や特異度が優れているものの,Pusher現象の回復の変化における敏感度が低いことが指摘されている。この点に関して,Pusher現象の経時的変化を鋭敏に捉えるためのスケールとして,D'Aquilaらは,Burke Lateropulsion Scale(以下,側方突進スケール)を開発した。この側方突進スケールは,寝返り・座位・立位・移乗・歩行の5項目で構成され,0~17点の範囲でPusher現象の重症度を評価するものであり,ADLやバランスとの関連が高いことが報告されている。しかしながら,新たに開発された評価法は,基準関連妥当性の検証が必要とされるが,従来のPusher現象に対するスケールとの関連を検討した報告はない。そこで本研究の目的は,発症早期のPusher現象例に対して,側方突進スケールと従来のPusher現象に対するスケールとの基準関連妥当性を検証することとした。【方法】対象は,当院に入院し理学療法を処方されたテント上の脳血管障害患者のうち,SCPにてPusher現象ありと診断された25例(年齢66.8±15.5歳(平均±SD),性別:男性19例・女性6例,全例右手利き,左片麻痺17例・左片麻痺8例,測定病日17.3±7.0日,SIAS 26点(中央値),半側空間無視21例)とした。取り込み基準は,JCS1桁かつ全身状態が安定していることとし,Pusher現象の診断には,Bacciniらの方法に従ってSCPの各下位項目>0(合計≧1.75)を採用した。脳損傷部位は,脳梗塞:中大脳動脈領域8例・内頚動脈領域6例・前大脳動脈領域1例,脳出血:皮質下4例・被殻3例・視床3例であった。評価は,理学療法を開始後,座位・起立練習が可能となった段階で実施し,側方突進スケール,SCP,Pusher重症度分類を同日に測定した。各スケールの評価は,当院の脳卒中チームに勤務している経験年数4年目以上のPT3名が実施した。側方突進スケールとSCP,Pusher重症度分類との関連については,Pearsonの積率相関係数を用いて検討し,統計処理にはSPSSver16を用い,有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮】本研究は当院の倫理審査委員会の承認を得て実施し,事前に本人もしくは家族に本研究の内容を説明し,同意を得た。【結果】側方突進スケール,SCP,Pusher重症度分類の合計得点はそれぞれ8.5±2.7点,3.7±1.4点,3.4±1.3点であった。側方突進スケールは,SCPとPusher重症度分類との間にそれぞれ強い正の相関(r=0.821,0.858,P<0.01)を認めた。【考察】本研究により,側方突進スケールは,SCPとPusher重症度分類のいずれとも強い相関があることが明らかとなった。側方突進スケールは,従来のスケールにはない寝返りや移乗の項目が含まれているが,SCPやPusher重症度分類と同様に座位・立位を中心に評価している点やPusher現象に特異的な他動的な姿勢の修正に対する抵抗に重きを置いているため,強い相関が得られたことが推察される。以上のことから,発症早期のPusher現象例における側方突進スケールの基準関連妥当性が示され,Pusher現象を客観的に評価し,経時的変化を捉えるためのツールとしての臨床的な有用性が示唆された。【理学療法学研究としての意義】側方突進スケールは,従来のスケールでは評価できないPusher現象の特性や回復の変化をより詳細に捉えることが可能であり,急性期からの戦略的な治療を考える上で有用な指標となることが期待される。
1 0 0 0 広視野7点AF対応CMOSリニア型オートフォーカスセンサ
- 著者
- 高橋 秀和 山下 雄一郎
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.28, pp.1-6, 2001-03-16
- 参考文献数
- 8
当社一眼レフカメラEOS KissIIIとEOS7の広視野7点AFを実現させるために, 新たなCMOSリニア型AFセンサの開発を行った.本センサは新開発のユニティゲイン型のセンサアンプとフィードバッククランプ型のノイズ除去回路を搭載することにより, センサ信号の高S/N化とワイドダイナミックレンジ化, 更にAGC制御の高精度化を実現している.また, 各種周辺回路のオンチップ化とCOBパッケージによるローコスト小型化も同時に実現している.
1 0 0 0 『山槐記』古写本の解題と翻刻
- 著者
- 石田 実洋 遠藤 珠紀 尾上 陽介 高橋 秀樹
- 出版者
- 東京大学史料編纂所
- 雑誌
- 東京大学史料編纂所研究紀要 (ISSN:09172416)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.76-92,図巻頭1枚, 2017-03