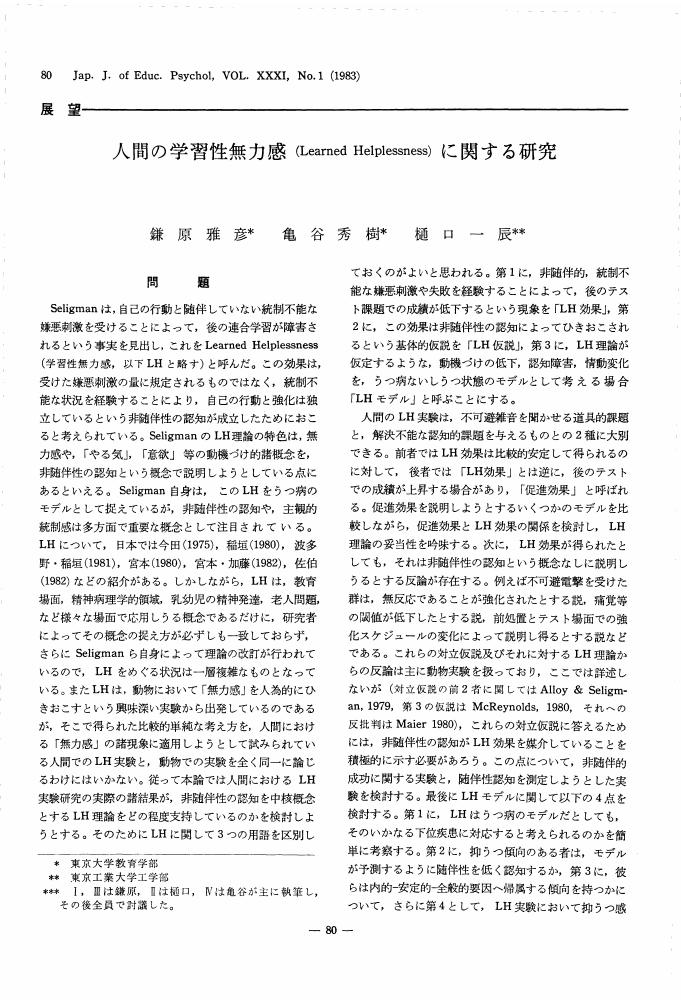11 0 0 0 OA 「居場所」の心理的機能の構造とその発達的変化
- 著者
- 杉本 希映 庄司 一子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.289-299, 2006-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 9 7
本研究では,「居場所」の心理的機能の構造とその発達的変化について検討した。「居場所」の心理的機能の構造を分析するために, 自由記述により得られた居場所の選択理由と先行研究を検討して作成した尺度を用いて, 小・中・高校生を対象に調査を行った。その結果,「居場所」の心理的機能には, 「被受容感」「精神的安定」「行動の自由」「思考・内省」「自己肯定感」「他者からの自由」の6因子があることが明らかとなった。「居場所」を他者の存在により,「自分ひとりの居場所」「家族のいる居場所」「家族以外の人のいる居場所」に分類した結果, 小学生では「家族のいる居場所」, 中・高校生では「自分ひとりの居場所」が多いことが明らかとなり, 発達段階により選択される「居場所」が異なってくることが示された。この3分類により心理的機能の比較分析を行った結果, それぞれの「居場所」の固有性が明らかとなった。
11 0 0 0 OA 学習方略は教科間でいかに転移するか
- 著者
- 植阪 友理
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.80-94, 2010 (Released:2012-03-27)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 27 17
自己学習力の育成には, 学習方略の指導が有効である。中でも, 複数の教科で利用できる教科横断的な方略は, 指導した教科以外でも活用できるため有用である。指導された学習方略を他の教科や内容の学習に生かすことは「方略の転移」と呼べる。しかし, 方略の転移については, 従来, ほとんど検討されてきていない。そこで本研究では, 方略の転移が生じた認知カウンセリングの事例を分析し, 方略の転移が生じるプロセスを考察する。クライエントは中学2年生の女子である。非認知主義的学習観が不適切な学習方法を引き起こし, 学習成果が長期間にわたって得られないことから, 学習意欲が低くなっていた。このクライエントに対して教訓帰納と呼ばれる学習方略を, 数学を題材として指導し, さらに, 本人の学習観を意識化させる働きかけを行った。学習方法の改善によって学習成果が実感できるようになると, 非認知主義的学習観から認知主義的学習観へと変容が見られ, その後, 数学の異なる単元や理科へ方略が転移したことが確認された。学習方略を規定する学習観が変容したことによって, 教科間で方略が転移したと考えられた。また, 学習者同士の教え合いが多いというクライエントの学習環境の特徴も影響したと考えられた。
10 0 0 0 OA これからのギフティッド研究と実践の発展のために
- 著者
- ⻆谷 詩織
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.184-205, 2023-03-30 (Released:2023-11-11)
- 参考文献数
- 188
2021年から文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」が開催されるなど,ギフティッド児の理解とその支援の必要性が広く認識され始めている。本稿は,ギフティッドの的確な理解と,それに基づく今後の教育心理学分野における研究や実践の発展を目的とする。まず,世界的に共通理解のなされているギフティッドの定義と特性を押さえる。次に,日本における関連研究を概観する。その上で,ギフティッド研究や実践に取り入れると有効と思われる観点を4つあげる。まず,(1)ギフティッド児であれば誰もが特別な支援を要するわけではないという点を確認した上で,誰が支援を要するのかを明確にする。また,(2)ギフティッドの判定や診断の問題と,当該ギフティッド児が身を置く教育環境において特別な支援やプログラムを要するか否かとを分けて考える必要性を論じる。関連して,(3)ギフティッド判定において,その子に潜在的な才能があるかどうかとそれを発揮できるかどうかは分けて検討することの重要性を論じる。最後に,(4)現行の教育制度や実践に存在するギフティッド教育の要素を活かす可能性について論じる。
- 著者
- 内田 奈緒 水野 木綿 植阪 友理
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.145-158, 2023-06-30 (Released:2023-06-14)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 1
本研究では,研究者が効果的な語彙学習方略について明示的に指導し,教師が通常授業で方略使用を支援する方略指導実践を行った。その実践を通して,高校生の方略使用の変化と,変化の個人差の背景にあるプロセスについて検討した。実践では,高校1年生1クラス33名を対象に,英単語を他の情報と関連づけながら学習する方略について指導した。指導の効果について,実践開始前の4月から実践開始後の7月,2月にかけて,指導した関連づけ方略の使用が継続的に増えていた。また,指導後方略を普段の学習でよく使うようになった生徒3名とあまり使うようにならなかった生徒2名にインタビューを行った。その結果,方略を使うようになった生徒は,指導を受ける前にもともと自分が使用していた方略の問題を認識し,それと相対化して新たな方略の有効性を認知していた。一方,あまり使うようにならなかった生徒は,指導前の学習について具体的な問題は認識せず,新たな方略について感覚的に,あるいは外的資源に依存して有効性を認知していた。研究者と教師が連携する方略指導の有効性および,元の学習方略と新たな学習方略を相対化することの重要性が示唆された。
10 0 0 0 OA 望まない思考の抑制と代替思考の効果
- 著者
- 木村 晴
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.115-126, 2004-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 15 10
不快な思考の抑制を試みるとかえって関連する思考の侵入が増加し, 不快感情が高まる抑制の逆説的効果が報告されている。本研究では, 日常的な事象の抑制が侵入思考, 感情, 認知評価に及ぼす影響を検討した。また, このような逆説的効果を低減するために, 抑制時に他に注意を集める代替思考方略の有用性を検討した。研究1では, 過去の苛立った出来事を抑制する際に'代替思考を持たない単純抑制群は, かえって関連する思考を増加させていたが, 代替思考を持つ他3つの群では, そのような思考の増加は見られなかった。研究2では, 落ち込んだ出来事の抑制において, 異なる内容の代替思考による効果の違いと, 抑制後の思考増加 (リバウンド効果) の有無について検討した。ポジティブな代替思考を与えられた群では, 単純抑制群に比べて, 抑制中の思考数や主観的侵入思考頻度が低減していた。しかし, ネガティブな代替思考を与えられた群では, 低減が見られなかった。また, ネガティブな代替思考を与えられた群では, 単純抑制群と同程度に高い不快感情を報告していた。代替思考を用いた全ての群において, 抑制後のリバウンド効果は示されず, 代替思考の使用に伴う弊害は見られなかった。よって, 代替思考は逆説的効果を防ぎ効果的な抑制を促すが, その思考内容に注意を払う必要があると考えられた。
10 0 0 0 OA 縦断データ分析のはじめの一歩と二歩
- 著者
- 荘島 宏二郎 宇佐美 慧 吉武 尚美 高橋 雄介
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.291-298, 2017-03-30 (Released:2017-09-29)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 4
10 0 0 0 OA 心理的敏感さに対するレジリエンスの緩衝効果の検討
- 著者
- 平野 真理
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.343-354, 2012-12-30 (Released:2013-06-04)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 6 4
本研究の目的は, 「生得的にストレスを感じやすい」というリスクを, レジリエンスによって後天的に補うことができるかを検討することであった。18歳以上の男女433名を対象に質問紙調査を行い, 心理的敏感さと, 資質的レジリエンス要因(持って生まれた気質の影響を受けやすい要因)・獲得的レジリエンス要因(後天的に身につけやすい要因)の関係を検討した。分散分析の結果, 心理的敏感さの高い人々は資質的レジリエンス要因が低い傾向が示されたが, 獲得的レジリエンス要因については敏感さとは関係なく高めていける可能性が示唆された。次に, 心理的敏感さから心理的適応感への負の影響に対する各レジリエンス要因の緩衝効果を検討したところ, 資質的レジリエンス要因では緩衝効果が見られたものの, 獲得的レジリエンス要因では主効果のみが示され, 敏感さというリスクを後天的に補える可能性は示されなかった。また心理的敏感さの程度によって, 心理的適応感の向上に効果的なレジリエンスが異なることも示唆され, 個人の持つ気質に合わせたレジリエンスを引き出すことが重要であることが示唆された。
- 著者
- 赤松 大輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.419-438, 2022-12-30 (Released:2022-12-30)
- 参考文献数
- 83
現在,教科固有の見方・考え方や,教科を超えた資質・能力を育む重要性が指摘されている。こうした問題意識を踏まえ,本稿では,学習に対する学習者の信念である学習観に着目し,教科・領域という観点から,学習観をはじめとした学習者の信念に関する知見の整理と展望を行った。特に,認識的信念研究と学業的自己概念研究で想定される信念の階層的構造に着目した。まず,信念の領域固有性に関する理論モデルである認識論の統合的領域理論(Muis et al., 2006)のモデルに基づき,先行研究を領域横断型研究と領域特定型研究に分類した。先行研究を整理・展望することを通して,近年は教科や学習全般のみではなく,教科で扱われる具体的なトピックや日常生活を含むより全般的な信念といった新たな階層の信念が取り上げられ,階層に応じて信念の機能や可変性に差異がある可能性が示唆された。次に,学業的自己概念研究では,教科の連続的な関係性や階層の異なる信念間の影響の方向性に関する知見が多くみられた。最後に,これらの知見を学習観研究のモデルに統合することで,特定領域で形成された学習観が他の領域に広がっていくという新たなモデルを提案した。
10 0 0 0 OA 高校生の英語学習における学習動機と学習方略
- 著者
- 堀野 緑 市川 伸一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.140-147, 1997-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 11 15
This study explored the structures of learning motives and strategies, and examined a model positing that motives affected strategy selection, which in turn influenced performance in English learning of high-school students. Six scales for learning motives were employed, which had been made through a classification of students' free responses. Correlation analysis revealed that the six scales could be divided into two groups, i. e.,“content-attached” and “content-detached” motives. On the other hand, factor analysis showed that learning strategies for English words were classified into the following three: organization, imaging, and repetition. The content-attached motives correlated significantly with each of the strategies, but the content-detached motives did not. Moreover, only the organization strategy had a significant effect on performance which was represented by three scores in an achievement test. That was consistent with theories and experimental findings in cognitive psychology, and supported the effectiveness of organization strategies in verbal learning. It was concluded that content-attached motives were needed to use organization strategies, and that the framework of so-called “intrinsic motivation” should be reexamined.
- 著者
- 小倉 千加子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.110-111, 1984
10 0 0 0 OA 授業中の私語に関する集団規範の調査研究
- 著者
- ト部 敬康 佐々木 薫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.283-292, 1999-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 7 2
本研究の目的は, 授業中の私語の発現程度とそこに存在している私語に関するインフォーマルな集団規範の構造との関係を検討することであった。中学校・高校・専門学校の計5校, 33クラス, 1490名を対象に質問紙調査が実施され, 私語に関するクラスの規範, 私的見解および生徒によって認知された教師の期待が測定された。私語規範の測定は, リターン・ポテンシャル・モデル (Jackson, 1960, 1965; 佐々木, 1982) を用いた。また, 調査対象となった33クラスの授業を担当していた教師によって, 各教師の担当するクラスの中で私語の多いクラスと少ないクラスとの判別が行われ, 多私語群7クラスと少私語群8 クラスとに分けられた。結果は次の3点にまとめられた。(1) 多私語群においては少私語群よりも相対的に, 私語に対して許容的な規範が形成されていたが,(2) 生徒に認知された教師の期待は, クラスの規範よりはるかに私語に厳しいものであり, かつ両群間でよく一致していた。また,(3) クラスの私語の多い少ないに拘わらず, 「規範の過寛視」 (集団規範が私的見解よりも寛容なこと) がみられた。これらの結果から, 私語の発生について2つの解釈が試みられた。すなわち結果の (1) および (2) から, 教師の期待を甘くみているクラスで私語が発生しやすいのではなく, 授業中の私語がクラスの規範と大きく関わっている現象であると考察され, 結果の (3) から, 生徒個人は「意外に」やや真面目な私的見解をもちながら, 彼らの準拠集団の期待に応えて「偽悪的」に行動する結果として私語をする生徒が発生しやすいと考察された。
10 0 0 0 OA リアクションペーパーの記述の質を高める働きかけ
- 著者
- 小野田 亮介 篠ヶ谷 圭太
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.115-128, 2014 (Released:2015-03-27)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 7 3 1
本研究では, 大学の講義型授業において使用されているリアクションペーパー(以下 RP)に着目し, 授業者の働きかけとRP記述の関係について検討を行った。まず, 予備調査を実施し, 学生が「RPをどのようなツールとして捉えているか(RP観)」に関する質問紙尺度を作成した。その結果, 学生のRP観としては, 「内容記憶志向」, 「記述訓練志向」, 「理解度伝達志向」, 「私的交流志向」の4因子が抽出された。次に, 本実験として, 1)授業者以外の読み手に, 自分の記述が読まれることを予期させる「読み手追加予期介入」と, 2)授業者が学生の記述した質問に対して補足説明を行うなど, RPの内容をいくつか抽出して応答を行う「授業者応答介入」を2つの大学で実施し, その効果を比較検討した。その結果, 授業者応答介入は用語の確認などの「低次質問」を抑制し, 授業内容をさらに深める「高次質問」の記述を促進することが示された。ただし, RP観との交互作用を検討した結果, 内容記憶志向の高い学生に対しては, 低次質問の抑制効果は見られないことが示された。一方, 高次質問の促進効果は, 私的交流志向が極端に高い学生を除き, 多くの学生に見られることが示された。
- 著者
- 山森 光陽 徳岡 大 萩原 康仁 大内 善広 中本 敬子 磯田 貴道
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.297-316, 2021-09-30 (Released:2021-11-16)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 4
クラスサイズ及び目標の提示と達成状況のフィードバックの頻度による,小学校第4, 5学年の2年間にわたる社会科の学力の変化の違いを検討した。第4, 5, 6学年開始前後の標準学力検査の結果を児童個別に結合したパネルデータに,第4, 5学年時のクラスサイズ,目標の提示と達成状況のフィードバックの頻度を連結したパネルデータのうち,第4, 5学年間で学年学級数の変動が起こらなかった50校,1,672名の児童を分析対象とした。第4学年,第5学年の各1年間,第4, 5学年の2年間の,過去と後続の学力の違いに対するクラスサイズ,目標の提示と達成状況のフィードバックの頻度,及びこれらの交互作用の影響を,児童,クラス,学校の3レベルを仮定したマルチレベルモデルによる分析を行った。その結果,第4, 5学年の2年間で見ると,在籍したクラスのサイズが小さく,かつ目標の提示と達成状況のフィードバックの頻度が高い学級担任による指導を受け続けた場合,過去の学力が相対的に低い児童については,これ以外の場合の児童と比べて後続の学力が高いことが示唆された。
10 0 0 0 OA 入学前の大学生活への期待と入学後の現実が大学適応に及ぼす影響 —文系学部の新入生を対象として—
- 著者
- 千島 雄太 水野 雅之
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.228-241, 2015 (Released:2015-11-03)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 5 5
本研究の目的は, 大学入学前に持っていた複数の領域に渡る大学生活への期待と, 実際に経験した大学生活に関して探索的に把握し, 大学適応への影響について実証的に明らかにすることであった。文系学部の大学生84名を対象とした予備調査によって, 大学生活への期待と現実に関して探索的に検討し, それぞれ項目を作成した。続いて, 文系学部の新入生316名を対象とした本調査を行い, 探索的因子分析の結果, 大学生活への期待は, “時間的ゆとり”, “友人関係”, “行事”, “学業”の4つの領域が抽出された。対応のあるt検定の結果, 全ての領域において期待と現実のギャップが確認された。さらに, 大学環境への適応感とアパシー傾向を従属変数とした階層的重回帰分析を行った。その結果, “時間的ゆとり”と“友人関係”において, 期待と現実の交互作用が認められ, いずれにおいても現実得点が高い場合に, 期待得点はアパシー傾向と負の関連が示された。特に, 期待したよりも時間的ゆとりのある大学生活を送っている場合に, アパシー傾向が高まることが明らかにされ, 大学における初年次教育の方向性に関して議論された。
10 0 0 0 OA 実学(サイヤンス)する教育心理学
10 0 0 0 OA 教科教育に心理学はどれだけ迫れるか (1)
- 著者
- 西林 克彦 宮崎 清孝 麻柄 啓一 市川 伸一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.198-202, 2012 (Released:2013-01-16)
- 被引用文献数
- 1
10 0 0 0 OA 両親の夫婦間葛藤に対する青年期の子どもの認知と抑うつとの関連
- 著者
- 川島 亜紀子 眞榮城 和美 菅原 ますみ 酒井 厚 伊藤 教子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.353-363, 2008-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 5 8
本研究は, 青年期の子どもがいる家族を対象に, 両親の夫婦間葛藤が子どもによる両親間葛藤認知を媒介として子どもの抑うつ傾向と関連するかどうかを検討することを目的として実施された。父親, 母親, および子どもを対象に, 質問紙調査を実施し, 両親回答による夫婦間葛藤の深刻さ評価と子ども回答による両親間葛藤認知, 父母への情緒的つながり, および抑うつ傾向を測定した。その結果, 男女ともに両親間葛藤が深刻なほど葛藤への巻き込まれ感が強まり, さらに両親の夫婦間葛藤に対する自己非難や恐れの認知につながっていた。男子については, こうした自己非難や恐れの認知が抑うつに関連していたが, 女子についてはこうした相関は見られなかった。一方, 両親間葛藤の深刻さは両親への情緒的つながり, 特に, 父親への情緒的つながりにより強い関連が見られた。抑うつとの関連では, 同性の親との情緒的つながりが重要であることが明らかになった。母親による夫婦間葛藤認知は子どもの葛藤認知に有意に関連していたが, 父親のそれは有意ではなく, いずれも子どもの抑うつ傾向とは直接関連しなかった。
9 0 0 0 OA 音声化と内声化が文章の理解や眼球運動に及ぼす影響
- 著者
- 森田 愛子 髙橋 麻衣子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.12-25, 2019-03-30 (Released:2019-12-14)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 3 1
本研究の目的は,文章の読解時に,音声化と内声化が文章理解や眼球運動にどのような影響を及ぼすかを検討することであった。黙読時に内声化を行う程度の個人差により,文章理解や眼球運動が異なるかを併せて検討した。実験1では,大学生24名に文章を読ませ,文章内容問題と逐語記憶問題に解答させた。音読,黙読,すべてを内声化する黙読(内声化強制),なるべく内声化しない黙読(内声化抑制)の4条件を設けた。内声化強制条件と内声化抑制条件を比較した結果,内声化によって逐語的な情報を保持しやすくなることが明らかになった。実験2では,大学生23名に,逐語記憶問題を課さずに同様の実験を行った結果,内声化を抑制すると文章内容問題の成績が低下し,内声化が文章理解に寄与することが示唆された。ただし,通常の黙読時に内声化を多く行う者とあまり行わない者に分けて成績や眼球運動のパターンを比較したところ,内声化をあまり行わない者の場合,内声化を抑制しても文章内容問題の成績の低下が比較的小さかった。また,このような読み手は内声化を多く行う者より黙読時の理解成績が高く,黙読時に視線を自由に動かす読み方を有効に利用できていることが示唆された。
9 0 0 0 OA 概念変化はなぜ生じにくいのか ―仮説的判断を阻害する要因としての自己完結的推論―
- 著者
- 佐藤 誠子 工藤 与志文
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.135-148, 2021-06-30 (Released:2021-07-21)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2 2
本研究は,既有知識の変化の困難さについて学習者の推論過程の側面から検討するものである。従来の合理的モデルに従えば,既有知識が変化するには,誤概念など既有知識からの「直観的判断」とルールに基づく「仮説的判断」とが同等におこなわれ,それらが比較対照される必要があるが,実際には後者の判断に困難があることが佐藤・工藤(2015)により示されている。これらを踏まえ,本研究では三角型四角形(三角形の直観的イメージに近い四角形)の分類課題を取り上げ,大学生を対象に仮説的判断の重要性とその方法を教授する授業をおこなうことで,課題に対する判断の転換がみられるかどうかを検討した。その結果,①推論の出発点を直観的判断にしか置けず,それを支えるための説明を生み出す方向にしか推論が展開されない「自己完結的推論」が存在すること(研究1,研究2),②仮説的判断を推論の俎上に載せることができれば,自己完結的推論が抑制され,双方を比較対照する検証過程に持ち込める可能性が高まること(研究2)が示された。これらの結果から,従来の誤概念修正ストラテジーの効果および概念変化達成のための教授学習条件を再考した。
9 0 0 0 OA 人間の学習性無力感 (Learned Helplessness) に関する研究
- 著者
- 鎌原 雅彦 亀谷 秀樹 樋口 一辰
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.80-95, 1983-03-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 110
- 被引用文献数
- 3 1