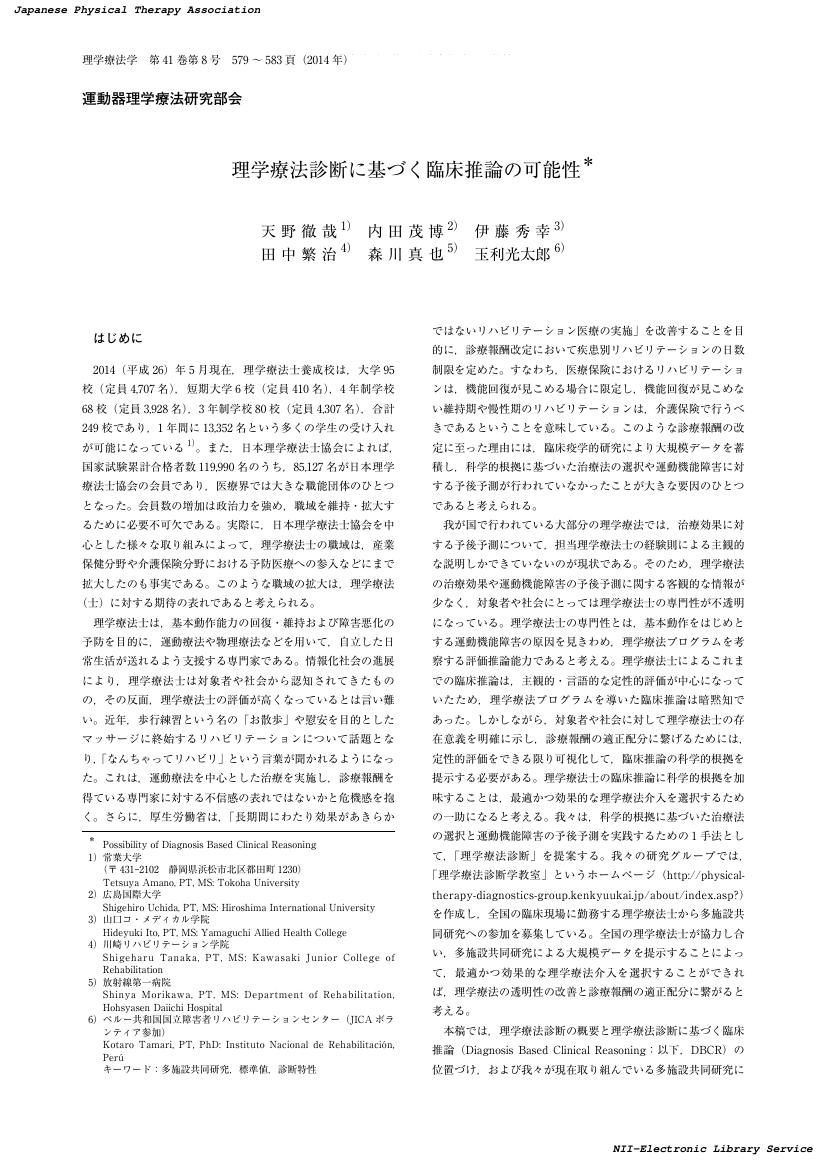1 0 0 0 OA 看護系教育課程を持つ大学における疫学・生物統計学教育の実態調査
- 著者
- 田中 司朗 山口 拓洋 大橋 靖雄
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.66-75, 2005 (Released:2014-08-06)
- 参考文献数
- 13
目的 看護系教育課程を持つ大学において疫学・生物統計学の授業を担当している教官の背景,講義・実習内容など疫学・生物統計学教育の実態と,教官の感じている問題点を調査し,教官の背景と,講義内容・感じている問題点に関連があるか検討した。対象と方法 看護系教育課程を持つ大学における疫学・生物統計学教育の実態について,国公立大学62校および私立大学27校(計89校)の疫学・生物統計学の授業を担当している教官を対象に自記式調査票を用いて調査を行い,対象校89校のうち回答の得られた50校61通を本研究の対象とした。結果 疫学・生物統計学を専門としている教官は20%と少なく,疫学・生物統計学に関係した学会の所属割合も低かった。また,教官の感じている問題点として,良い教科書・実習用の教材・問題集がなく,とくに看護に関する実例を挙げた教科書が望まれている事,教官やチューターの人数が不足している事,学生の意欲,数学やパソコン・情報処理の能力が足りない事が挙げられた。講義内容については「統計における基本概念」や「統計解析」のうちの基本的な分野に関しては90%前後の,「疫学における基本概念」や「医学・疫学研究デザイン」については70%前後の大学で講義されている事などがわかった。結論 疫学・生物統計学の授業を担当している教官の専門分野や所属学会などの背景,感じている問題点,講義・実習・卒業論文指導の内容などが明らかになった。疫学・生物統計学を専門としている教官が講義している大学は少なく,工学部・薬学部・理学部数学科などの他学部所属の教官に頼っている事や教科書に対する要望が強い事,学生に学ぶ意欲や数学とパソコン・情報処理の能力が足りないと感じている教官が多い事が示唆された。これらは看護教育における疫学・統計学教育のあり方を考える上で貴重な資料になりうると考えられる。
1 0 0 0 OA 超対称性とGauge Hierarchy
- 著者
- 坂井 典佑
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.376-381, 1982-05-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 7
超対称性(supersymmetry)はボース粒子とフェルミ粒子とを結ぶ対称性である. この入門的概説を行う. またその魅力ある理論的動機のひとつとして, gauge hierarchy問題解決の可能性について紹介する. 素粒子の大統一理論では極端に大きさの異なる質量スケールが共存していなければならない(gauge hierarchy). これに対称性から自然な説明を与える試みのひとつとして超対称性は最近再び注目されている. 現在までの実験では未だ超対称性を支持する証拠は見つかっていない. しかしもしもgauge hierarchyを超対称性で解決する考えが正しければ, 次世代の加速器で種々の新現象が見つかるかも知れない.
- 著者
- 柴山 由理子
- 出版者
- 早稲田大学大学院社会科学研究科
- 雑誌
- 社学研論集 (ISSN:13480790)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.90-104, 2010-09-25
1 0 0 0 OA 直腸がん肛門温存手術患者の術後の排便障害と対処法の関連
- 著者
- 藤田 あけみ
- 出版者
- 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌 (ISSN:18820115)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.49-59, 2018 (Released:2019-12-05)
- 参考文献数
- 17
本研究の目的は、直腸がん肛門温存手術(ISR、LAR)患者の術後の排便障害と対処法を明らかにし、看護介入を検討することである。対象者は、直腸がんのためISRとLARを施行した外来受診患者91名であった。肛門温存手術後の排便障害に応じて、食生活に関する対処法として、「辛い味は控える」 「繊維食は控える」や肛門局所に関する対処法として、肛門の洗浄・清拭」 「肛門部の軟膏」 「パット・オムツをあてる」が多く行われていた。その他に、「骨盤底筋運動」 「規則正しい生活」 「腹部腰部のマッサージ」 「整腸剤内服」の対処法が多く行われていた。性別では女性に、就業状況では、術後は楽な仕事に移行した人や術後は無職となった人に、食生活に関する対処法が多かった。排便障害に応じて食生活の対処法を指導する際は、性別、就業状況などを把握し詳細に指導する必要がある。また、肛門局所の対処法である「パット・オムツをあてる」を指導する際は、パットやオムツの使い方、自尊感情を支える支援が必要である。 排便障害のある患者への看護介人として、自己のセルフ・ケア能力を発揮して対処行動がとれるよう排便障害の症状や経過を説明し、自己の状況を受容し目標をもてるように働きかけることが重要であると考えられた。
1 0 0 0 OA 改正日本商法詳解
- 著者
- 平井繁男, 垂水善太郎 著
- 出版者
- 駸々堂
- 巻号頁・発行日
- 1899
1 0 0 0 OA 織物税解説 : 非常特別税法
- 著者
- 池田 貴儀
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.219-223, 2005-05-01 (Released:2017-05-25)
- 被引用文献数
- 2
会議録は, 研究者が最新の研究動向を知るための情報源であり, 図書館が収集すべき重要な資料にもかかわらず入手が困難とされている。その会議録について, 日本原子力研究所図書館では, 現在, 約1万9千件を収集し研究者に提供している。本稿では, 主として, 学協会からの会議情報の入手, 国際原子力情報システム(INIS)データベースの利用, 研究者からの情報入手といった会議録の収集手法を紹介した。また, 日本原子力研究所が研究報告書として刊行する会議録JAERI-Confのシリーズについても触れている。
1 0 0 0 OA 観光地のごみ処理対策事例
- 著者
- 副田 俊吾
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会誌 (ISSN:18835864)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.191-200, 2015-05-31 (Released:2021-06-14)
- 参考文献数
- 14
観光旅行は私達の余暇の楽しみの一つであり,特に宿泊を伴うような観光は家族や友人にとって一大行事であり,人々の絆を深める大切な機会でもある。このため,観光地はさまざまな「おもてなし」の工夫を凝らして観光客の想い出づくりを援けるとともに,観光収入を得て,地域経済を支えている。一方,観光地を訪れる人々にごみとし尿は必ず附随するものであり,その処理は受け入れる観光地にとっての負担となっている。 本稿では,国内外の観光地,あるいは観光地を抱える自治体等の観光ごみに対する考え方や取組事例を紹介し,観光インフラの一つとしてのごみ処理対策のあり方について概略を述べる。
1 0 0 0 OA 昭和基地管理棟の建設 (1)基本設計
- 著者
- 半貫 敏夫 小石川 正男 平山 善吉 佐野 雅史 佐藤 稔雄 Toshio Hannuki Masao Koishikawa Zenkichi Hirayama Masashi Sano Toshio Sato
- 雑誌
- 南極資料 = Antarctic Record (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.61-102, 1993-03
昭和基地建設の歴史的経緯をふまえて, 基地建物の現状と計画的な建物更新の必要性およびその概要を述べた。次いで昭和基地に建つ南極観測用建物の設計・製作に関する制約条件を整理し, これまでに昭和基地で試みられてきた極地建築システムについて概観した。国立極地研究所観測協力室の立案による昭和基地整備計画の最初の事業として企画された「管理棟」の基本構想をまとめるまでの経緯と基本設計の概要を紹介し, 建築・防災・構法などの新しい試みについて解説した。また, これからの南極観測用建築のありかたについても言及した。
1 0 0 0 OA 多変量解析法の概説, 特に主成分分析, 重回帰分析, 判別分析を中心にして
1 0 0 0 OA 桃の民俗誌 : そのシンボリズム(その二)
- 著者
- 王 秀文
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.123-158, 1999-06-30
本稿は、「桃の植物文化誌」につづいて、桃の生命力をめぐる伝承を調べ、分析したものである。桃の生命力に関する伝承は、古く中国の『詩経』「桃夭」などの歌謡に現われ、それは主に桃の花・実・葉をもって年ごろの娘の結婚を祝福したものであるが、季節が冬から春に変わろうとするとき、何よりも早く花が咲き、うっそうとした葉が茂り、木いっぱいに実がなる桃のイメージを受けて生まれた感覚であろう。そのため、桃は強い生命力を持つものとして、農耕を迎える三月三日の祭りと融合され、「桃太郎」の話を生み出し、さらに不老長寿の仙果として仰がれた。このような数多くの伝承において、桃に基本的に陰気に対抗して陽気を復帰させ、生命の蘇生・誕生を象徴し、さらに観念的に女性の生殖力と結びつき、多産・豊饒や生命の不滅への期待が託されているものとみられる。
1 0 0 0 OA 黒潮と日本人の遭遇史(第二部):近世の和書と洋書にもとづく論考
- 著者
- 川合 英夫
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 海の研究 (ISSN:09168362)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.181-203, 1994-06-30 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 102
- 被引用文献数
- 1
After the national isolation policy was established in 1639, the building of large ships and ocean navigation were prohibited in Japan. Thus, it is difficult to find old books describing the Kuroshio. By searching and deciphering early books, however, I have found some historical descriptions and illustrations about the Kuroshio. By examining these records, coupled with records in the Western books, I have reached the following conclusion. The term "Kuroshio" originated from a local word "Kurose River", used within inhabitants of the Izu Islands, which indicated a branch of the actual Kuroshio flowing over the Izu Ridge. About 1800 it became meaning the Kuroshio south of the Tokaido District, and became popular among Japanese people by the fashion of publishing maps, local geography, accounts of trips and novels. However, a view of fragmental currents at that period might interrupted the recognition of the Kuroshio as a long current. From the end of the 18th century to the mid 19th, the Western collected information about Japan's geography published by the Japanese and made surveys and analyses of the Kuroshio on the occasion of cruises to ask for establishment of commercial relationship with Japan. Before the Meiji Restoration (1868), the term "Kuroshio" had already turned to an international word, which meant the entire Kuroshio, by the international diffusion of information about the Kuroshio. However, the undersanding of the Kuroshio by the Japanese was not practical as shown in Kanrin Maru journals by them.
1 0 0 0 OA 日本海岸地理研究に就て
- 著者
- 金田 楢太郎
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.189-194, 1893-04-25 (Released:2010-10-13)
- 著者
- 桑田 俊明
- 出版者
- 日本考古学協会 ; 1994-
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.43-53, 2018-10
1 0 0 0 おうさまとくつやさん : とんちばなし
1 0 0 0 縄文~弥生における水利用形態と生業・生産様式に関わる考察
- 著者
- 渡会 由美
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 環境システム研究 (ISSN:09150390)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.345-354, 1997
In Japanese Islands, the irrigated agriculture, which was the historical turning point for the relation between nature and human, started between the Jomon and Yayoi periods.<BR>The purpose of this article is to study the change of the ancients living and production styles and their society system from the viewpoint of the natural environment especially for the water utilization. Then, the economy system for the modern society will be discussed incomparison to the ancient society system.<BR>Here are summary from this article:<BR>(1) The economy system in the Jomon period was constant economy that people hunt or reap as much as they need, which differs from growth economy that assumes surplus production occurred after the Yayoi period.<BR>(2) The society and economy in the Jomon period balanced as long as the amount of natural resources required was kept within the reproducible one.
- 著者
- 安田 博幸
- 出版者
- 武庫川女子大学
- 雑誌
- 武庫川女子大学紀要 自然科学編 (ISSN:03872076)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.279-285, 1967-03
1 0 0 0 OA 理学療法診断に基づく臨床推論の可能性
- 著者
- 天野 徹哉 内田 茂博 伊藤 秀幸 田中 繁治 森川 真也 玉利 光太郎
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.579-583, 2014-12-20 (Released:2017-06-10)
1 0 0 0 OA ベトナムの大学生のための日本の会社法入門
- 著者
- 得津 晶 ヴ・ティ・リン・チ
- 出版者
- 東北ローレビュー編集委員会
- 雑誌
- 東北ローレビュー = Tohoku Law Review (ISSN:21884587)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.65-79, 2022-03-31