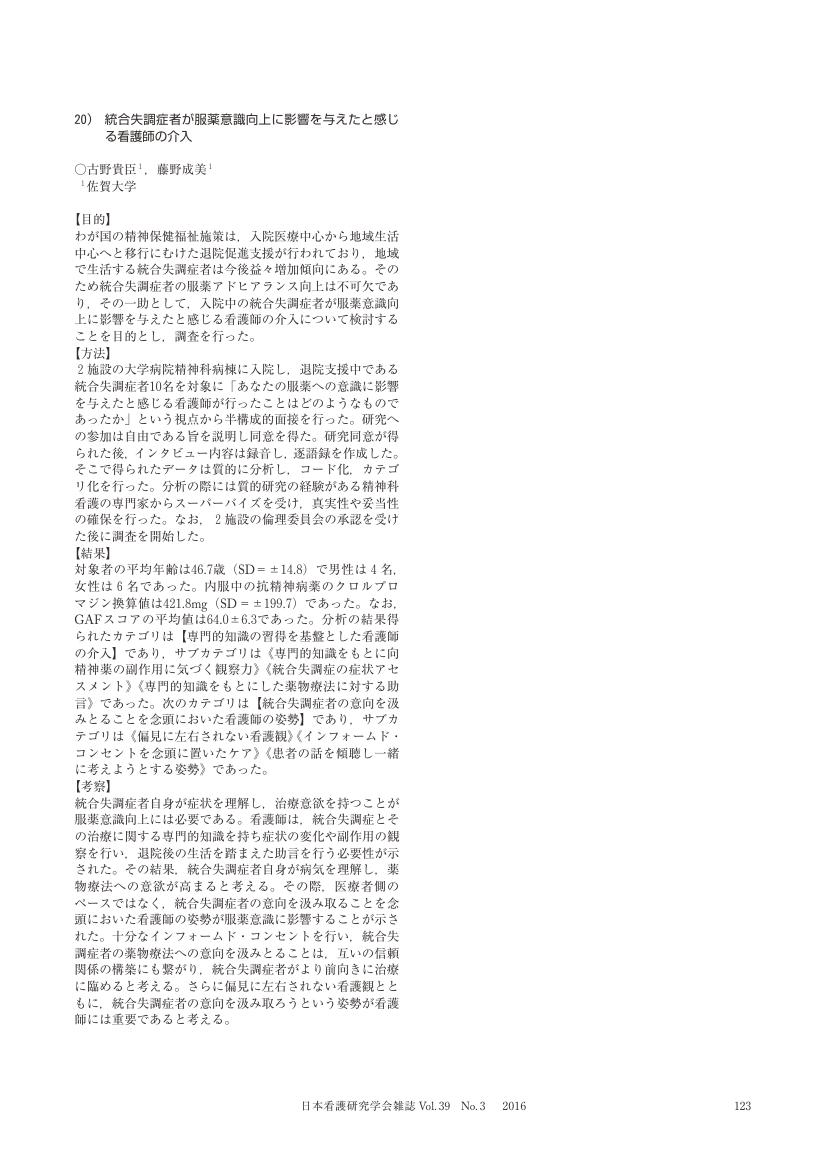- 著者
- 吉田 晴世
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.308-311, 2016 (Released:2018-02-06)
- 参考文献数
- 13
In this article, “We-mode theory” is discussed from the viewpoint of social cognition. Furthermore, the mental conditions that should be observed in the relationship between We-mode and non-humans, not humans, will also be examined. Ideas of how a deep understanding of others should be created will be introduced, based on the theory of interactionism seen in social cognition. The possibility of human and non-human coexistence should also be illustrated; i.e., the possibility of coexistence between the human-like robot “Astro Boy” and the disc-shaped vacuum cleaner robot “Roomba”.
1 0 0 0 自然言語処理技術の最近の動向:超並列自然言語処理
- 著者
- 苫米地 英人
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.7, pp.768-770, 1992-07-15
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 OA 中世における瑞泉寺の規模と特質について
- 著者
- 野村 俊一
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.580, pp.189-196, 2004-06-30 (Released:2017-02-09)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1 1
The purpose of this paper is clarify the scale and feature of Zuisenji temple in the medieval ages. A summary will be given as foUows : 1. Zuisenji temple which Muso Soseki established was a small-scale life space centering on hojo. This life space is similar with the environment where it is located in the back part of Gosan of south Sung or Kamakura of the same age. 2. If based that kyochi of zen sect temple concentrated in the circumference of hojo in future.'Zuisenji temple is positioned as a forerunner of the environment which suited composing gatha. 3. When Gido Shushin became "juji", the scale of Zuisenji temple was expanded aiming at "jissatu" for expansion of denomination. Consequently, the scale near the so-called composition of "sichido garan" was realized. 4. Each descent of the scale and social background of Zuisenji temple corresponded mostly.
1 0 0 0 OA 鉄道沿線における郊外住宅地の開発と地域イメージの形成
- 著者
- 土井 勉 河内 厚郎
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.1-13, 1995-06-09 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 3
Hanshin area, especially the area along Hankyu Line, is considered one of the best residential area image in Kansai district of Japan.In this study, we have analyzed this positive evaluation of Hanshin area, focusing on the suburb along Hankyu Line, and some projects developed by Hankyu Corporation.As the result, there were three factors identified in the area along Hankyu Line- good natural environment, human factors (ex. Ichizo Kobayashi, founder of Hankyu Corporation), and development of modern life style. Cultural activities and businesses based on these three factors contributed to establish a good area image of the suburbs.
1 0 0 0 OA 20)統合失調症者が服薬意識向上に影響を与えたと感じる看護師の介入
- 著者
- 古野 貴臣 藤野 成美
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.123, 2016-07-29 (Released:2018-07-19)
1 0 0 0 OA 資源, 環境問題と新聞用紙
- 著者
- 木村 実
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.11, pp.969-972, 2009-11-15 (Released:2012-08-24)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 東亜同文書院の中国語教育と私
- 著者
- 宮田 一郎
- 出版者
- 愛知大学東亜同文書院大学記念センター
- 雑誌
- 同文書院記念報 (ISSN:21887950)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.79-88, 2012-03-30
愛知大学東亜同文書院大学記念センター資料の富山展示会・講演会テーマ「東亜同文書院大学から愛知大学へ ー最後の校舎呉羽分校ー」日時 展示会:2011年9月17日(土)~18日(日)10:00~18:00 講演会:2011年9月17日(土)13:30~16:30場所 富山国際会議場2階会議室
- 著者
- 西 正孝 山西 敏彦 林 巧
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.115-120, 2004-02-28
- 参考文献数
- 36
<p> 核融合炉開発は進展し, 国際熱核融合実験炉ITERの工学設計が完成して建設活動を始めるべく準備が進められている。現在, 開発を進めている核融合炉は重水素とトリチウムを燃料とするが, トリチウムは放射性気体であり, また, 天然には稀少であるため, 核融合炉内で消費量に見合う量の生産を行う。このため, トリチウムの有効利用とその取り扱いに係る安全を確保するトリチウム・システムの開発は核融合炉の実現に必要不可欠である。本稿では, 核融合炉のトリチウム・システムについて, ITERのトリチウム・システムの設計とその技術基盤を中心に紹介するとともに, 今後の課題について述べる。</p>
1 0 0 0 OA 公的統計調査に基づいた孤立関連指標についての考察
- 著者
- 蓋 若琰 西村 幸満 斉藤 雅茂 桜井 良太 泉田 信行 Ruoyan GAI Yukimitsu NISHIMURA Masashige SAITO Ryota SAKURAI Nobuyuki IZUMIDA
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- IPSS Working Paper Series = IPSS Working Paper Series (ISSN:24341207)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.1-22, 2022-03
1 0 0 0 核融合炉トリチウム水処理システムの研究開発動向
- 著者
- 山西 敏彦 岩井 保則 磯部 兼嗣 杉山 貴彦
- 出版者
- プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 = Journal of plasma and fusion research (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.6, pp.545-559, 2007-06-25
- 参考文献数
- 36
核融合炉施設は核融合を起こす燃料として,放射性物質であるトリチウムガスおよび副次的に生じる高濃度トリチウム水を大量に取り扱う施設であり,施設内に設ける燃料循環システムにて処理を行い,燃料サイクルを施設内に閉じてしまうことが必要となる.したがって,核融合炉の安全確保と燃料サイクルの確立を目指す上で,トリチウム水の処理は鍵となる技術である.本報では,ITERにおけるトリチウム水処理システムの開発経緯,第一壁冷却水やブランケット冷却水の処理までを見通した核融合原型炉に向けた水処理総合システムの研究開発状況を紹介する.
1 0 0 0 OA 日本におけるアパレル産業の成立 -マーケティング史の視点から
- 著者
- 木下 明浩
- 出版者
- 立命館大学経営学会
- 雑誌
- 立命館経営学 = 立命館経営学 (ISSN:04852206)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.191-215, 2009-11
1 0 0 0 OA 労働時間と自由時間・「余暇」
- 著者
- 山田 定市
- 出版者
- 北海道大学教育学部社会教育研究室
- 雑誌
- 社会教育研究 (ISSN:09130373)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.1-12, 1990-02
1 0 0 0 OA 社会科と社会科学 : 高島善哉の発言を中心に
- 著者
- 佐藤 弘
- 出版者
- 山梨学院生涯学習センター
- 雑誌
- 大学改革と生涯学習 : 山梨学院生涯学習センター紀要 (ISSN:13489712)
- 巻号頁・発行日
- vol.第21号, pp.31-43, 2017-03-29
1 0 0 0 OA つなぎの違いによるそば切りの経時的変化
- 著者
- 堤 ちはる 山岸 純子 本山 百合子 三橋 扶佐子 吉中 哲子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.373-381, 1990-11-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 4
The texture parameters and the characteristics of tissues of the four kinds of buckwheat noodles with different thickenings, SOBANERI, flour, yam (ICHO-IMO), and egg used in each buckwheat. Their time changes were observed.The four kinds of buckwheat needles were stored at the temperature of 20°C and 5°C during the experiment, and time changes were evaluated by the sensory test and observed by using a scan type electron microscope.1) Buckwheat noodles with flour used as thickening Right after boiling it, ductile fracture and the maximum rupture energy and distortion were seen. Though the change on standing was big, it was hard to be cut compare with the other three kinds. This phenomenon correlates with the result of the sensory test.2) Buckwheat noodles with egg used as thickening Right after boiling it, its hardness is the biggest and the time change low. The actual hardness correlates with the result of the sensory test.3) Tomotsunagi and Imotsunagi noodles Both the hardness and rupture energy were small. Therefore, they seemed to be cut easily.4) By the observation with an electron microscope, the change at the preservation time and temperature became slow by using TSUNAGI.
1 0 0 0 OA 頭頸部化学放射線治療後に多発う蝕を生じ口腔管理に苦慮した1例
- 著者
- 新垣 理宣 勝良 剛詞 小林 大二郎 道 泰之 北本 佳住 依田 哲也 倉林 亨
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
- 雑誌
- 歯科放射線 (ISSN:03899705)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.53-57, 2022 (Released:2022-04-06)
- 参考文献数
- 14
Introduction: Radiation-induced dental caries is a late oral adverse event that should be considered after head and neck radiotherapy. However, there are no clinical guidelines for dental management after head and neck radiotherapy. We report a case of multiple dental caries that developed after head and neck radiotherapy in a patient in whom symptomatic treatment was challenging. Case: A 67-year-old male was referred to our department with difficulty with oral intake secondary to occlusal insufficiency. He had a history of radiotherapy for hypopharyngeal carcinoma, and nearly all of his teeth only had residual roots. We found multiple carious teeth, including in areas outside of the radiation field. We designed a temporary denture in coordination with a dental office; however, it was difficult to extract all of the patient’s teeth. The patient was followed-up; however, he died of esophageal cancer. Conclusion: Radiation-induced dental caries can even occur in teeth outside of the radiation field. In such cases, continuous preventative measures, such as oral care, are important, even before the start of radiotherapy.
1 0 0 0 OA カトリック大学のキャンパス・ミニストリー における福音宣教の在り方
- 著者
- 加藤 美紀
- 出版者
- 学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学
- 雑誌
- 仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.1-16, 2022-03-01 (Released:2022-04-08)
1 0 0 0 OA 美術解剖学から見たウマのポーズ表現
- 著者
- 柴田 眞美
- 出版者
- Japanese Society of Equine Science
- 雑誌
- Japanese Journal of Equine Science (ISSN:09171967)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.45-54, 1993-09-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 12
本研究では,体表のレリーフ表現について調べた前報に引き続いて,古今東西の造形作例(267作例)に描かれたウマのポーズについて,独自の指標を用いて実際のウマの歩行運動中の位相と比較し,その表現方法の特性について検討した。 分析指標を作成するために,数頭の実馬に各種の歩行運動をさせ,それをVTRカメラで撮影した。その映像からウマの動作を1コマ毎(30Hz)に作図し,こたらの位相を着地肢の組合せによって分類し,作例分析のための指標とした。各作例について,そこに描かれたウマの着地肢の組合せ,四肢の配置パターン,そして全体の姿勢,の3つの視点から分析指標と照合し,描かれた歩法とその四肢の位相を判定した。 その結果,全体の83%にあたる222作例が,分析指標のいずれかの位相に分類する事ができた。また,描写頻度の高さから判断して,造形上で好まれるポーズは,次に示すグループとして捉えることができた;両後肢で立ち上がっているポーズ,対角前後肢が着地している速歩のポーズ,四肢全てが地から離れているリーピングギャロップもしくは同じ位相の飛越のポーズ,1方の前肢と両後肢が着地している常歩のポーズ,両後肢が着地しているリーピングギャロップもしくは同じ位相の飛越のポーズ,の5ポーズ,あるいはこれらに類似したポーズである。一方,造形表現上であまり用いられないポーズは,四肢すべてが着地している駈歩のポーズ,両前肢と一方の後肢が着地している常歩もしくは同じ位相の駈歩のポーズ,対角前後肢が着地している駈歩もしくは同じ位相の襲歩のポーズ,両前肢が着地しているリーピングギャロップもしくは同じ位相の飛越のポーズ,一方の前肢が着地している襲歩,同じ位相のリーピングギャロップ,もしくは同じ位相の飛越のポーズであった。 さらに,時代あるいは地域別にその作例を検討した結果,美術解剖学の分野で「詩的真実」と呼ばれている「造形表現と実体との相違」について考察する際に大変興味ある問題がいくつか提示された。
1 0 0 0 OA 迅速骨結合性、高強度骨結合性、歯肉上皮接着性を併せ持つチタンインプラントの創製
1 0 0 0 OA ―総説―ウマの歩行運動の分析
- 著者
- 徳力 幹彦
- 出版者
- Japanese Society of Equine Science
- 雑誌
- Japanese Journal of Equine Science (ISSN:09171967)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-10, 1992-03-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 84