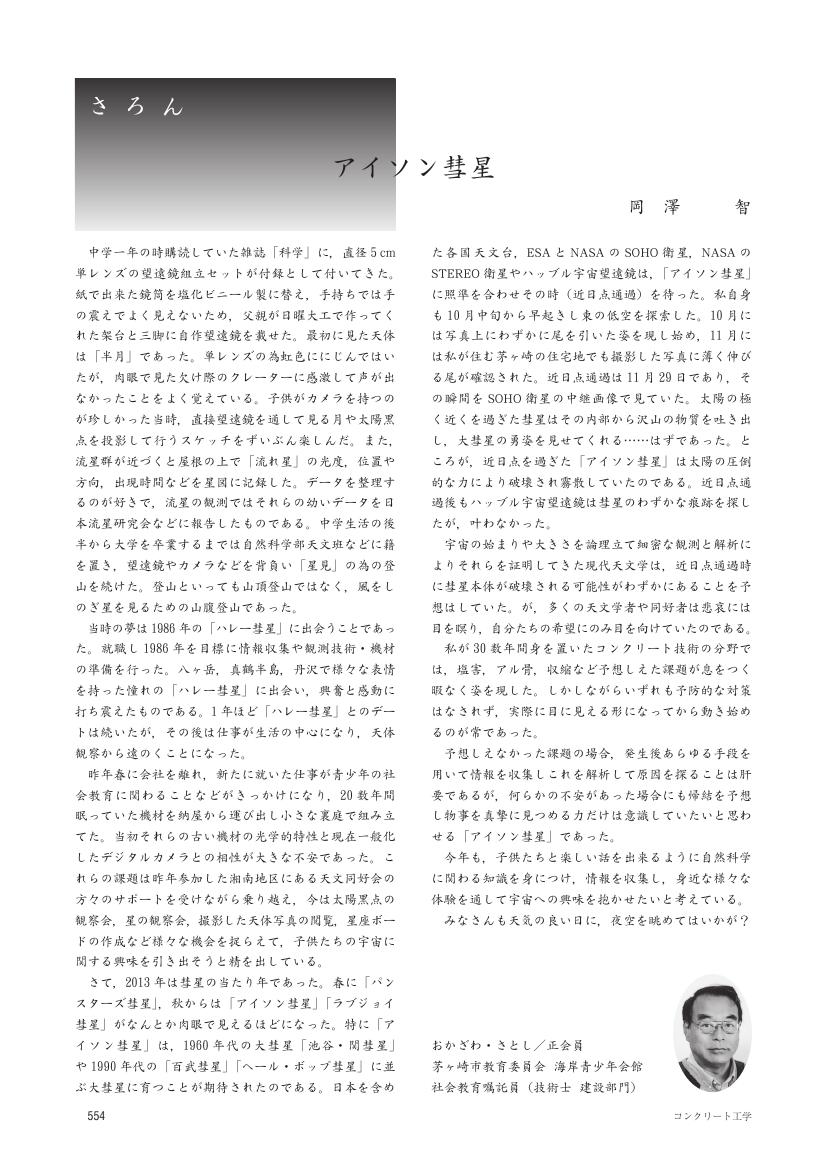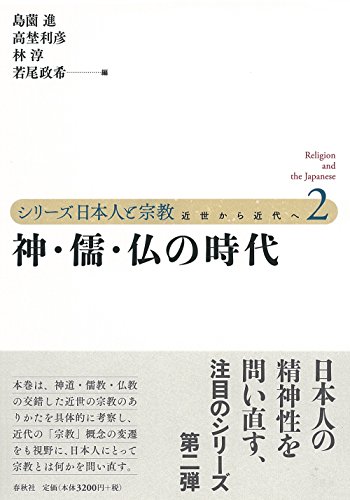1 0 0 0 OA 品種分化をめぐって : 古典園芸植物のドメスティケーション
- 著者
- 仁田坂 英二 Eiji Nitasaka
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館調査報告 = Senri Ethnological Reports (ISSN:13406787)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, pp.409-443, 2009-03-31
1 0 0 0 OA 神経栄養因子様低分子化合物 T-817MA の統合失調症治療薬としての可能性
- 著者
- 上原 隆 住吉 太幹 倉知 正佳
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.154-160, 2015 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 34
統合失調症の病態は未だ明らかでなく,予防法および根治的治療法は開発されていない。神経発達障害と神経変性による脳の形態学的変化が,統合失調症の病態生理に関与する可能性が指摘され,症状が顕在化する以前(前駆期)にすでに生じているとされる。特に parvalbumin 陽性ガンマアミノ酪酸(GABA)介在神経細胞の障害が統合失調症の認知機能障害に関与していると考えられている。ゆえに,これらの形態学的変化に作用する薬物が,統合失調症の予防・根治療法につながると期待される。神経栄養因子様作用を有する低分子化合物である T-817MA は神経突起伸展の促進作用や酸化ストレス抑制作用を有し,アルツハイマー病などの神経変性疾患の治療薬として開発された薬物である。われわれは統合失調症モデル動物における形態学的,行動学的異常を,T-817MA が改善することを見いだした。これらの所見は,T-817MA が統合失調症の予防的・根治的治療薬として有望なことを示唆する。
1 0 0 0 OA 都市再生特別地区におけるソフト分野の公共貢献の実態に関する研究 東京都を事例として
- 著者
- 山崎 正樹 櫻井 澄 根上 彰生
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.297-302, 2013-10-25 (Released:2013-10-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 2
本研究は、施行から約10年が経過し、一定の事例が蓄積されてきた都市再生特別地区におけるソフト分野の公共貢献に着目し、東京都を対象とした提案・実施状況の実態の調査及び課題と改善方策の考察を行った。2012年8月現在における、東京都で提案されたソフト貢献を整理した結果、全24事例のうち22事例、貢献内容としては64件が提案され、種別としては「都市や街の魅力の向上」に寄与するものが約4割を占めることが明らかになった。次に提案されたソフト貢献の実現状況の把握のために、稼働済事例を対象に開発事業者・運営事業者及び東京都へのヒアリング調査を行った結果、東京都と開発事業間で提案内容実施にかかる協定が締結されており、全ての事例でソフト貢献が実現されていることが確認できた。運営形態は事業者が自ら運営事業を行う「自主型」が約6割、運営委託を行う「誘致型」約4割であり、概ねの事例で建築物稼働日より1年前には運営主体が決定している。しかし、素案上の「イメージ」を実現できない事例や、都決時以降に追加されたソフト貢献が評価されない事例、ソフト貢献の有効的な利活用が事業者の努力次第となること等の課題もみられた。
1 0 0 0 現代的想像力と「声のキャラ」--初音ミクについて
- 著者
- 井手口 彰典
- 出版者
- 鹿児島国際大学福祉社会学部
- 雑誌
- 福祉社会学部論集 (ISSN:13466321)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.18-32, 2010-10
1 0 0 0 OA 不全心における収縮障害の細胞内メカニズム −SERCA2aを中心として−
- 著者
- 草刈 洋一郎 平野 周太 本郷 賢一 中山 博之 大津 欣也 栗原 敏
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.2, pp.87-93, 2004 (Released:2004-01-23)
- 参考文献数
- 25
正常の心臓は律動的な収縮·弛緩を繰り返し,全身に絶え間なく血液を送り出している.これは,細胞内Ca2+-handlingを中心とした興奮収縮連関が規則正しく行われている結果である.一方で興奮収縮連関が破綻すると,収縮不全や拡張不全が招来されることが明らかになってきた.心筋細胞内Ca2+handlingの調節には多くのタンパク質が関わっているが,中でも筋小胞体のCa2+ポンプであるSERCA2a(心筋筋小胞体Ca2+-ATPase)が中心的な役割を果たしている.近年,分子生物学的手法を用いて,SERCA2aを心筋に選択的に過剰発現させると,心肥大や心不全になりにくいことが指摘されている.しかし,これまでの遺伝子変異動物を用いた研究では主として慢性心不全に関する研究は多いが,急激に起こる心機能の低下の原因に関する研究は少ない.そこで,今回我々は,SERCA2a選択的過剰発現心筋を用いて,急性の収縮不全や拡張不全を起こす病態時に,SERCA2aの選択的機能亢進により細胞内Ca2+-handlingと収縮調節がどのような影響を受けるのかについて調べた.急性収縮不全をきたす病態として,呼吸性(CO2)アシドーシスを用いた.アシドーシスならびにアシドーシスからの回復時における細胞内Ca2+と収縮張力を,SERCA2a過剰発現心筋と正常心筋とで比較した.アシドーシス時の収縮抑制に対しても,またアシドーシスからの回復時の収縮維持に関してもSERCA2a過剰発現心筋は正常心筋よりも収縮低下が抑制された.この結果は虚血性心疾患の初期などでおこるアシドーシスによる収縮不全に対して,SERCA2aの選択的発現増加による細胞内Ca2+-handlingの機能亢進が有用であることを示唆している.
- 著者
- Yoshio KIKU Yuya NAGASAWA Fuyuko TANABE Kazue SUGAWARA Atsushi WATANABE Eiji HATA Tomomi OZAWA Kei-ichi NAKAJIMA Toshiro ARAI Tomohito HAYASHI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.9, pp.1505-1510, 2016 (Released:2016-10-01)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 15 18
Staphylococcus aureus (SA) is a major cause of bovine mastitis, but its pathogenic mechanism remains poorly understood. To evaluate the role of lipoteichoic acid (LTA) in the immune or inflammatory response of SA mastitis, we investigated the gene expression profile in bovine mammary epithelial cells stimulated with LTA alone or with formalin-killed SA (FKSA) using cap analysis of gene expression. Seven common differentially expressed genes related to immune or inflammatory mediators were up-regulated under both LTA and FKSA stimulations. Three of these genes encode chemokines (IL-8, CXCL6 and CCL2) functioning as chemoattractant molecules for neutrophils and macrophages. These results suggest that the initial inflammatory response of SA infection in mammary gland may be related with LTA induced chemokine genes.
- 著者
- Kihei Magishi Tomoko Matsumoto Yutaka Shimada Tohru Ikeguchi
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (ISSN:21854106)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.343-348, 2022 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 22
Word co-occurrence networks (WCNs) are a major tool used to analyze languages quantitatively. In a WCN, the vertices are words (morphemes), and the edges connect n consecutive words in a sentence on the basis of the n-gram. Most studies use WCNs transformed at n=2. In this study, we investigated the changes in the structural features of WCNs when n increases using four types of documents for eight languages. We found that WCNs with n≧ 3 reflect features of the languages that do not appear when n = 2 and that some structural features evaluated by network measures depend on the text data.
1 0 0 0 OA 飛田穂洲の野球信念と物語の生成
- 著者
- 高橋 豪仁
- 出版者
- 奈良教育大学
- 雑誌
- 奈良教育大学紀要. 人文・社会科学 (ISSN:05472393)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.99-108, 2002-10
How have the narratives about high-school baseball been generated? It is assumed that Tobita Suisyu (1886-1986) is an important person to answer the question because of his career. He was famous for his "Senbon Nokku" when he was the first coach of the baseball club of Waseda University, and he had been writing about student baseball for 40 years as a journalist. That is why he has been called the Father of Student Baseball. The purpose of this study is to clarify his principles about baseball by studying the contents of his selected masterpieces. As a result we found the following principles of his baseball philosophy: vengeance, unselfishness, moral cultivation, hard training based on the code of the samurai, amateurism, communal spirit, Yakyu-dou as religious belief, spirit of fortitude and manliness, frugal life, carelessness about appearance and so on. When we classify the media of sport by the scale of hotness and coolness, the hottest media are printing ones and the coolest media are sport events that are the actual sport plays in stadiums. TVs and radios are located midway between them. According to this scheme, it can be said that Tobita's narratives had been spread through the hot media such as newspapers and magazines. Though all of his narratives do not exist as ideology of the student of baseball, some of them are still alive nowadays. Some narratives are deposited in people's mind, and those narratives are reinforced when people see the "events" based on the existing narratives in their mind. It may be suggested that the narratives of sport are generated through circulation between "narratives" and "events.
1 0 0 0 OA アイソン彗星
- 著者
- 岡澤 智
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.6, pp.554, 2014 (Released:2015-06-01)
1 0 0 0 OA 知っておきたい関連領域のトピックス ―小児のウイルス性肺炎―
- 著者
- 堤 裕幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.11, pp.1454-1456, 2016-11-20 (Released:2016-12-15)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- KONDO Osamu FUKASE Hitoshi FUKUMOTO Takashi
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.2, pp.85-100, 2017
- 被引用文献数
- 8
<p>Considering the geographical setting of the Japanese archipelago at the periphery of the Asian continent, regional variation in Jomon phenotypes can be interpreted as an outcome of population history. In this paper, we focused on regional variation in the Jomon craniofacial morphology and assumed that the observed regional differences were a reflection of the formation process of the Jomon population, which is a mixture of intrinsic expansion of an initial population with extrinsic influence of hypothetical gene flow. Compiled craniometric data from archeological site reports indicate that Jomon skulls, especially in the neurocranium, exhibit a discernible level of northeast-to-southwest geographical cline across the Japanese archipelago, placing the Hokkaido and Okinawa samples at both extreme ends. A quantitative genetic approach using an R-matrix method indicates that the cranial parts of the neurocranium and mandible exhibit a proportionately larger regional variation, the former of which confirms a trend of geographical cline and reveals the respective region presumably having different population histories with their respective local backgrounds. The following scenarios can be hypothesized with caution: (a) the formation of Jomon population seemed to proceed in eastern or central Japan, not western Japan (Okinawa or Kyushu regions); (b) the Kyushu Jomon could have a small-sized and isolated population history; and (c) the population history of Hokkaido Jomon could have been deeply rooted and/or affected by long-term extrinsic gene flows.</p>
1 0 0 0 OA マダニにおける血管拡張物質の遺伝子水平伝搬
- 著者
- 岩永 史朗
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.149-151, 2018-09-25 (Released:2018-10-25)
1 0 0 0 OA 『月氷奇縁』の成立
- 著者
- 大高 洋司
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.25.26, pp.35-49, 1976 (Released:2017-04-28)
1 0 0 0 OA Five new species of the genus Trichotichnus from Taiwan (Coleoptera, Carabidae, Harpalini)
- 著者
- 伊藤 昇
- 出版者
- 大阪市立自然史博物館
- 雑誌
- 大阪市立自然史博物館研究報告 = Bulletin of the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786675)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.1-13, 2022-03-31
台湾のツヤゴモクムシ属(Gen. Trichotichnus)のleptupus species groupのうち,Trichotichnus lulinensisおよび近似2既知種の図示とともに,次の5新種を報告する:Trichotichnus(Trichotichnus)alessmetanai N. Ito, sp. nov. from Mt. Yushan [玉山], T. (T.)fumiakii N. Ito, sp. nov. from Tayulin [大萬領],T(. T.)similaris N. Ito, sp. nov. from Tsuifen [翠峰], T(. T.)lishanensis N. Ito, sp. nov. from Mt. Lishan [梨山],T. (T.)nitidipennis N. Ito, sp. nov. from Sungkang [松崗]. T. alessmetanai は,2021年8月にご逝去された,ハネカクシ研究の世界的権威でいらっしゃったカナダの Dr. Aleš Smetana氏に因む.氏は多くの研究材料を著者の研究のために供与くださった.ご生前の多大なご功績称賛と標本ご供与への深謝の意を表して献名した.
- 著者
- 解良 澄雄
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.10, pp.1796-1797, 1991-10-20 (Released:2017-11-29)
1 0 0 0 神・儒・仏の時代
- 著者
- 島薗進 [ほか] 編
- 出版者
- 春秋社
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- 馬田 敏幸 法村 俊之
- 出版者
- 一般社団法人 日本放射線影響学会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第51回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.202, 2008 (Released:2008-10-15)
p53野生型マウスにトリチウム水一回投与によるβ線照射、あるいはセシウム-137γ線をシミュレーション照射法(トリチウムの実効半減期に従って線量率を連続的に減少させながら照射)により3Gyの 全身照射を行ったとき、T細胞のTCR遺伝子の突然変異誘発率は、γ線では上昇しなかったがトリチウムβ線では有意に上昇した。この差異の原因がp53の活性量の違いにあるのかを明らかにするために、次の実験を行った。8週齢のC57BL/6Nマウスの腹腔内に、270MBqのトリチウム水を注射し19日間飼育した。この間にマウスは低線量率で3Gyの被ばくを受けることになる。γ線はシミュレーション照射法で7日間照射し、その後12日間飼育した。飼育最終日にマウスに3Gy(0.86 Gy/min)照射し、4時間後に脾臓を摘出しT細胞分離用とアポトーシス解析のためのタネル法の試料とした。ウェスタンブロット法によりp53の発現量とリン酸化p53の存在量を比較した。p53の活性量とアポトーシス活性を現在解析中であり、突然変異の除去機構について考察を行う。
1 0 0 0 OA β線による皮膚発がんの発生率と発生時期はp53遺伝子の存在状態に依存
- 著者
- 大津山 彰 岡崎 龍史 法村 俊之
- 出版者
- 一般社団法人 日本放射線影響学会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第50回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.35, 2007 (Released:2007-10-20)
p53遺伝子野生マウスでは、p53依存ならびに非依存性修復能により損傷DNAの修復が行われ、修復不能損傷はp53依存アポトーシスによって細胞ごと排除され、放射線催奇形の実験では低線量放射線(LDR)域でほぼ完全に奇形発生が抑えられる。一方p53遺伝子KOマウスではp53非依存性の修復しか働かず、LDR照射であっても奇形発生は完全に押さえられない。このp53による生体防御機構の一端は放射線での奇形発生のみならず、発がんにも関与すると考えられる。もし野生マウスで、LDR照射でがんが発生せず、KOマウスで高率に生じるとすれば、放射線発がんで常に問題となるしきい値存在の有無がこの機構によって解釈できる。p53遺伝子が野生、ヘテロ、KOマウスの背部皮膚を円盤型β線線源(15Gy/min.)で週3回反復照射をマウスの生涯に渡り行った。実験群は各マウス1 回当り照射線量2.5Gy群と5.0Gy群とした。発生した腫瘍は組織学検査ならびに、DNA抽出後p53遺伝子についてSSCPによる突然変異とLOHの解析を行った。KOマウスでは生存期間内に腫瘍の発生はなかった。ヘテロマウスでは2.5Gy群で8/21、5.0Gy群で25/45の腫瘍発生がみられ、野生マウスでは2.5Gy群で8/22、5.0Gy群で6/33の腫瘍発生がみられ発がん開始時期もヘテロマウスより約150日遅れた。ヘテロマウスの腫瘍のうち14/23例でLOHがみられたが、突然変異はなかった。野生マウスでは7/9例に突然変異がみられ、LOHは3/9例にみられた。p53遺伝子の存在状態は明らかに放射線による発がん率と発生時期に影響し、放射線で生じる変異の型がp53遺伝子の存在状態によって異なることが理由であると考えられた。
1 0 0 0 OA 舞踏生態学
- 著者
- 河本 英夫 海野 敏 鈴木 信一
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター (「 エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ) 事務局
- 雑誌
- 「エコ・フィロソフィ」研究 = Eco-Philosophy (ISSN:18846904)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.141-185, 2022-02
1 0 0 0 IR 高大接続における早期履修制度の類型 : Advanced Placementと類似制度
- 著者
- 西川 潤
- 出版者
- 京都大学学際融合教育研究推進センター地域連携教育研究推進ユニット
- 雑誌
- 地域連携教育研究 = Journal of education and research for regional alliances (ISSN:24332356)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.108-114, 2018-09
In Japan, there are moves to implement and disseminate Advanced Placement by the college board. The Japanese government is also beginning to consider creating similar programs and the system which high school students acquire college credits is drawing attention. However, there are cases where the accelerated learning system, which is a general name for such systems, and Advanced Placement which is only one of its forms are being confused, causing inaccurate understanding. Considering this situation, this paper aims to clarify the relative features of Advanced Placement by grasping the types of accelerated learning system in the U.S. and Japan. As a result, the existing accelerated learning system in Japan was able to be understood by two axes: (1) "Open-Closed, " (2) "overseas oriented (studying abroad)-domestic oriented." Advanced Placement belongs to "Open-overseas oriented" and draws a clear line from the existing system that is domestic oriented. Through this analysis, it reconfirmed the importance of not looking at all of the accelerated learning systems as similar cases, but classifying and understanding them separately.