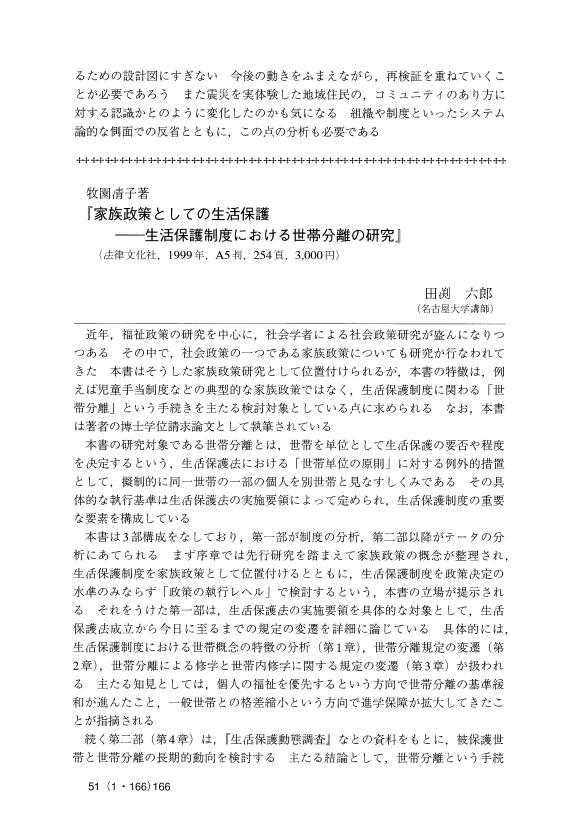- 著者
- 新井
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経エレクトロニクス (ISSN:03851680)
- 巻号頁・発行日
- no.808, pp.65-72, 2001-11-05
- 被引用文献数
- 2
DVDの次世代を狙う光ディスクを製品化するときが迫っている。緊張感が増す中,装置や媒体メーカーは低コスト化技術の確立に心血を注ぎ始めた。その傾向は,2001年10月16日〜19日に台湾台北市で開催された光ディスクの国際会議「International Symposium on Optical Memory(ISOM)2001」注1)の講演にもはっきり表れた(表1)。
2 0 0 0 OA 漢魏詩における寓意的自然描寫 : 曹植「吁嗟篇」を中心に
- 著者
- 龜山 朗
- 出版者
- 中國文學會
- 雑誌
- 中國文學報 (ISSN:05780934)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.1-28, 1980-04
2 0 0 0 IR 公民舘の休校日開放(2001秋)に関する調査報告
- 著者
- 織田 揮準 中西 智子 廣岡 秀一
- 出版者
- 三重大学
- 雑誌
- 三重大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 (ISSN:13466542)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.11-20, 2003-03
平成14年度から学校週5日制度がスタートした。学校週5日制の完全実施によって、児童生徒の学校内で過ごす時間が減少し、児童生徒の生活の場が学校から家庭、地域社会へと変化する。しかし、家庭や地域社会の休校日における児童の受け入れ態勢(受け皿)の不備による学力低下、非行の低年齢化がさらに進行するのではないかと危惧する意見がある。本研究によって、学校週5日制度導入のための試行期間であった平成13年度秋に三重県下の公民館が実施した「休校日における小学校および公民館の児童向け開放の実態」に関する調査結果から、子どもの居場所として公民館がどのような機能を果たしたか、公民館開放の阻害要因は何かなどの実態が明らかにされた。本研究成果が、学校週5日制時代における地域密着型公民館のあり方を創造する話し合いや協議のきっかけとなり、その資料として役立てば幸いである。
2 0 0 0 ブール代数アプローチによる質的比較
1.異なる分野の調査データに適用するという研究目的については、歴史社会学、社会運動論、組織社会学、社会心理、社会行動などにかかわるデータの分析を行った。具体的には、農民暴動、ボランティア団体、社会的属性と意識、援助行動、携帯電話への不快感、出産意向などの分析をおこない、ブール代数アプローチが多様な分野およびテーマに応用可能であることを示した。2.調査方法の異なるデータへ適用するという研究目的については、事例データのみでなく、歴史的資料データ、既存データのメタ分析、クロス表データ、ヴィネット調査データ、手紙データなど多様な調査データへの応用方法を提示し、ブール代数アプローチを様々な調査データへ応用可能にした。3.理論の定式化および理論比較への適用という研究目的については、演繹的に理論モデルを構築する手法によって、役割概念を理論的に再定式化する成果が得られた。そこでは、役割の階統性・可視性による役割構造分析という、役割理論にたいする新たな分析を提示した。4.数理モデルとして拡張するという研究目的については、論理演算の明示化、確率モデルとの比較、真理表データの2値化基準の検討などを行い、数理モデルとして拡張していくための基礎的検討を行った。これらでは、データの多様性の欠如や、矛盾のある行などの方法論的問題にたいする対処策を提示した。以上のように本研究では、方法論的な基礎的検討(上記4.)、発展的応用方法の開発(上記2.および3.)、そして実質的研究への応用(上記1.)を行った。とくに実質的研究へ応用にかんしては、意識や行動における主観的論理や主観的状況定義にブール代数分析が有効であることがわかった。
2 0 0 0 IR 地域における起業促進の一類型 : アルプス電気盛岡工場が醸成した起業家精神
- 著者
- 五十嵐 伸吾
- 出版者
- 法政大学地域研究センター
- 雑誌
- 地域イノベーション (ISSN:18833934)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.89-104, 2012
我が国、特に地方における産業活性化あるいは雇用創出の担い手として、新規開業企業群(スタートアップ企業)への期待は大きい。しかし、これまで地域において起業促進政策が顕著な成功を見た例は少ない。岩手県は県内総生産、失業率などの指標で他県と比較すると決して恵まれているとは言えない。岩手県下のある企業しかも一つの工場から40余りのスタートアップ企業が誕生 し、しかもほぼすべてが生存している。このような事例は他に類を見ない。本稿では、このアルプス電気盛岡工場の事例を分析することによって、どのような経緯によって起業を促進する組織文化が形成されたのかを明らかとする。それが地域における起業促進政策に対する一助と なることを期待する。The Japan government and especially local government have expected to emerging start- ups as the role of industrial activator and job creator. However, such policies for promoting entrepreneurship have not been a significant successful. The indicates of Iwate Prefecture, for example, Gross Prefecture Product (GPP) and Unemployment rate show that Iwate Prefecture is not better than the others. More than forty start-up companies were founded from only the Morioka Factory of Alps Electric Co., Ltd. Almost all of them are alive so far. Similar cases aren't seen. This paper analyzed the case of the Morioka Factory of Alps Electric Co., Ltd, and revealed how the organizational culture that promotes entrepreneurship was generated there. I hope that it will give some suggestions which contribute to the economic policy for promoting entrepreneurship in the region.
- 著者
- 杉原 たまえ
- 出版者
- 日本農村生活研究会
- 雑誌
- 農村生活研究 = Journal of the Rural Life Society of Japan (ISSN:05495202)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.31-38, 2002-03-01
2 0 0 0 四国のヒノキ人工林において台風が落葉動態に及ぼす影響
- 著者
- 稲垣 善之 倉本 惠生 深田 英久
- 出版者
- 森林総合研究所
- 雑誌
- 森林総合研究所研究報告 (ISSN:09164405)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.103-112, 2010-09
- 被引用文献数
- 1
四国地域の標高の異なる2つのヒノキ林において、間伐区と対照区を設定し、落葉量の動態を5年間評価した(2002-2006年)。この地域には2004年に多くの台風が接近したが、この年の年間落葉量は台風前(2002-2003年)の1.17-2.25倍の値を示した。台風の影響は高標高域で低標高域よりも大きく、間伐区で対照区よりも大きかった。一方、台風後(2005-2006年)の年間落葉量は、台風前(2002-2003年)の1.05-1.41倍を示した。台風の影響は間伐林分で大きかったものの、台風後の回復は間伐区と対照区の間に差が認められなかった。高標高域では2004年の落葉時期(落葉が年間量の50%に達する時期)が早い傾向が認められた。一方、低標高域では2004年の落葉時期は変化せずに落葉期間(落葉が年間量の10%から50%に達するまでの期間)が長かった。この結果は、台風に対する落葉の反応が標高によって異なることを示す。すなわち、高標高域では、台風後直ちに落葉するが、低標高域では台風後にすぐには落葉せず、しばらく経過してから徐々に落葉した。これらの結果、ヒノキ人工林において台風後に落葉生産は速やかに回復しており、台風後に新しい葉の生産が急速に増加することが示唆された。
2 0 0 0 OA 植民地下朝鮮における淑明高等女学校 : 抗日学生運動を中心に
- 著者
- 太田 孝子
- 出版者
- 岐阜大学
- 雑誌
- 岐阜大学留学生センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.23-43, 2003-03
淑明高等女学校は,1906年5月,朝鮮李王家の高宗皇帝妃と日本人淵沢能恵の協力によって,朝鮮人女子のために京城に創設された女学校である。植民地下の朝鮮において,朝鮮人と日本人の協力によって創られた私立高女は淑明高女が唯一のものである。しかし,日本人教師が多かったこともあり,朝鮮人女子のために創られた当初の理念や目的と,実際の学校運営の間にはしばしば齟齬(そご)をきたすことがあり,朝鮮教育史に残るような同盟休校事件(「'27淑明抗日盟休運動」)を始めとする抗日学生運動が幾度となく起こった。本稿では,淑明高女で起こった抗日学生運動関連の史資料を検証することによって,運動の目的と実態,運動を巡っての日本人教師,朝鮮総督府の反応を明らかにし,植民地下の女子中等教育が内包する課題を指摘した。
2 0 0 0 国際物理オリンピックへ向けた研修(教育に関する一言)
- 著者
- 杉山 忠男
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, 2009-03-15
2 0 0 0 Web ページの信頼性の自動推定
- 著者
- 福島 隆寛 内海 彰
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 : journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.239-249, 2007-06-15
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 11 1
本論文では,Web ページに記載されている情報の信頼性(Web ページの信頼性)を,そのWeb ページやそこに含まれているテキストのさまざまな特徴から推定する手法を提案する.提案手法は,信頼性判断に影響を与える各特徴が推定対象のWeb ページで成立しているかどうかを自動判定する処理と,成立すると判断された特徴からそのWeb ページの信頼度を求める処理から構成される.どのような特徴が信頼性判断に影響を及ぼすかについては,アンケート調査を実施して,68個の特徴とWeb ページの信頼性への影響度を得た.本研究では,それらのうちの40個の特徴(信頼性の尺度)の成立を自動判定する手法を開発した.また信頼度を計算する手法として,影響度の総和を取る方法とSupport Vector Machineを用いた機械学習により信頼度を求める手法を開発した.そして,評価実験を通じて,信頼性の尺度の判断処理の有効性と信頼できる/信頼できないページの二値分類に対する提案手法の有効性を確認した.
2 0 0 0 OA <論文>やなせたかしと短大生
- 著者
- 矢口 裕康
- 出版者
- 宮崎女子短期大学
- 雑誌
- 宮崎女子短期大学紀要 (ISSN:02898748)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.A29-A43, 2003-03
- 著者
- 千葉 緑 加藤 貴司 ビスタ ベッドB. 高田 豊雄
- 出版者
- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会
- 雑誌
- 情報科学技術フォーラム講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.607-610, 2009-08-20
2 0 0 0 OA 構築主義的家族研究の動向
- 著者
- 田渕 六郎
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.117-122, 2000-07-31 (Released:2009-09-03)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 2
本稿は、近年の家族研究において注目されている構築主義的研究の動向を紹介することを目的とする。ここで構築主義的研究とは、以下で述べる意味で「構築主義的」な理論枠組みを採用していると考えられる研究を指す。関連する研究動向の紹介としては、拙稿 (田渕, 1996, 1998) のほかに、構築主義的家族研究を代表する研究であるGubrium and Holstein (1990) の訳書「あとがき」に訳者等による紹介があり、宮坂 (1999) や土屋 (1999) も関連する実証研究の動向を整理している。本稿は研究動向の紹介を網羅的に行う紙幅を欠くため、紹介はこれら先行研究に挙げられている文献と重複しないものを優先していることをお断りしておきたい。
2 0 0 0 OA 牧園清子著『家族政策としての生活保護-生活保護制度における世帯分離の研究』
- 著者
- 田渕 六郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.166-167, 2000-06-30 (Released:2009-10-19)
2 0 0 0 OA 中央日本のネオテクトニクスと伊豆小笠原弧
- 著者
- 竹内 章
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.4, pp.540-551, 1991-08-25 (Released:2010-11-18)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 7 6
Central Japan has been tectonically situated at a triple juncture among Izu-Bonin, Northeast Japan, and Southwest Japan Arcs. Neotectonics of central Japan is geohistorically reexamined with the special reference to the results of ODP Leg126 transect of Izu-Bonin Arc. Three major points are claimed as follows:(1) The tectonic belt along eastern margin of Japan Sea (EMJS) is characterized by severe compressional deformation including thrusts and folds have developed within the Miocene rifted trough, Uetsu sedimentary basin, by a tectonic reversal which occurred at the end of Miocene around 6 Ma. Since then, the belt have behaved as a newly formed plate boundary between Eurasia and North America Plates.(2) During the period of 2.8-1.4 Ma, a bimodal volcanism occurred at the both flanks of the southern Hida Mountain Range. Area of such explosive acidic volcanism was bounded by a rift-like depression zone called “Omine Rift” was formed along the north-central segment of Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line. This means that backarc rifting of Izu-Bonin arc forced the above colliding boundary between Northeast Japan and Southwest Japan to expand.(3) As for plate tectonic frame-work in central Japan, two possibilities are pointed out based on contemporal changes throughout central Japan.a) An eastward motion of Southwest Japan (EUR) has started at about 6 Ma, which immediately caused the jump of plate boundary from central Hakkaido to the EMJS following the tectonic reversal in the inner Northeast Japan arc.b) Philippine Sea plate has changed the direction of its movement from North-northeast to West-southwest around 3.5 Ma, which activated the backarc rifting of Izu-Bonin arc.
2 0 0 0 OA ファシズムの武器となった考査委員会
- 著者
- 日本共産党宣伝教育部 編
- 出版者
- 暁明社
- 巻号頁・発行日
- 1949
2 0 0 0 OA 書評
- 著者
- 田渕 六郎
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.78-79, 2005-02-28 (Released:2009-08-04)
2 0 0 0 OA 福祉社会の基盤を問う―ソーシャル・キャピタルとソーシャル・サポート
- 著者
- 三重野 卓 田渕 六郎
- 出版者
- 福祉社会学会
- 雑誌
- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.4, pp.21-26, 2007-06-23 (Released:2012-09-24)