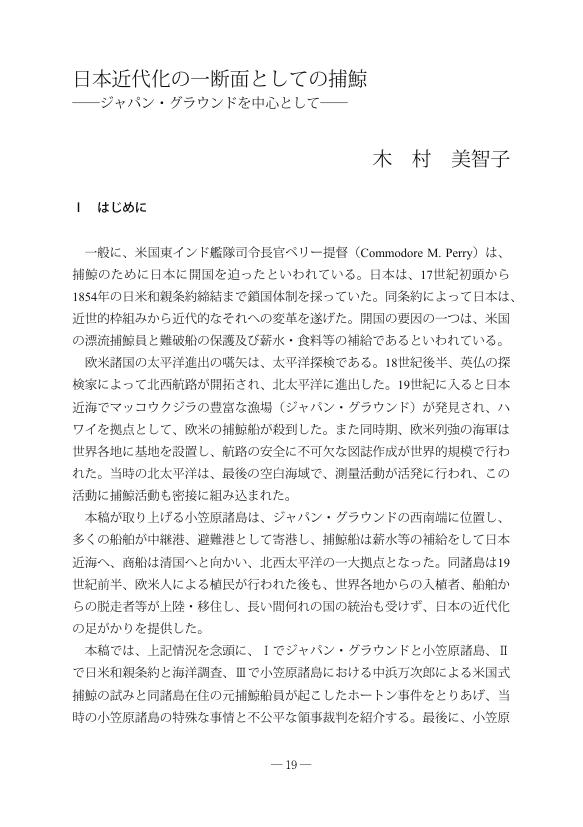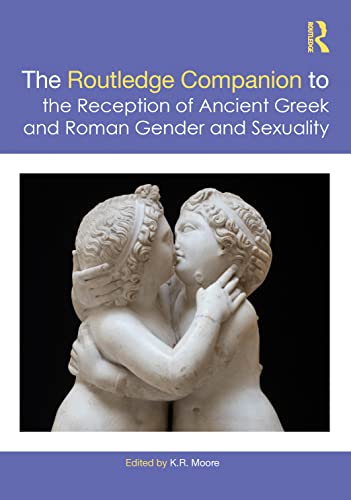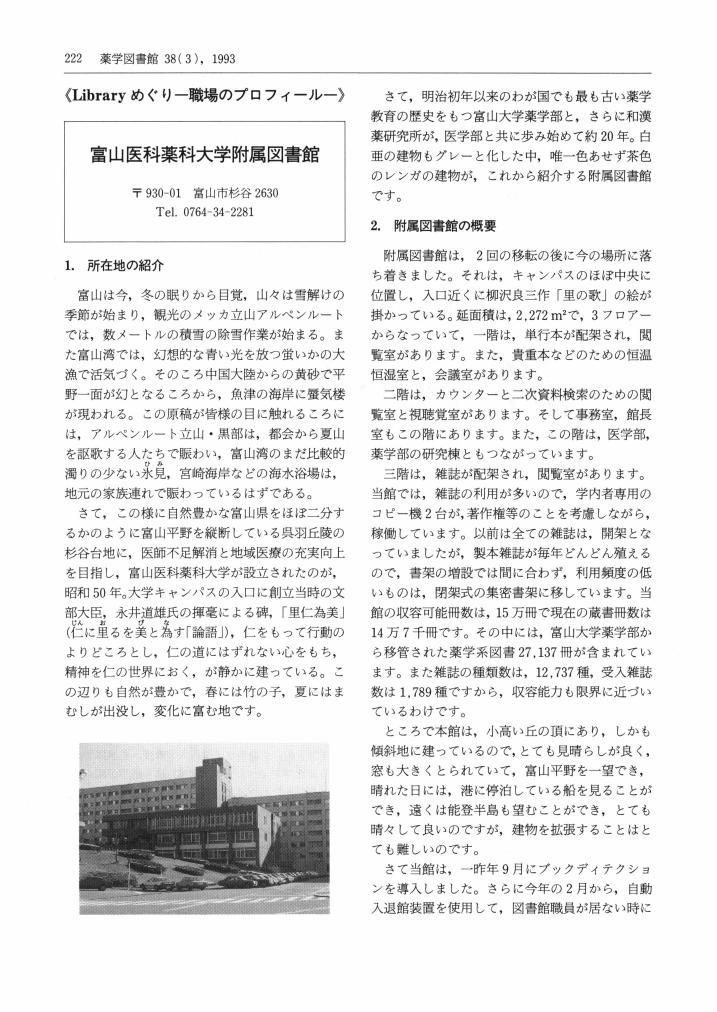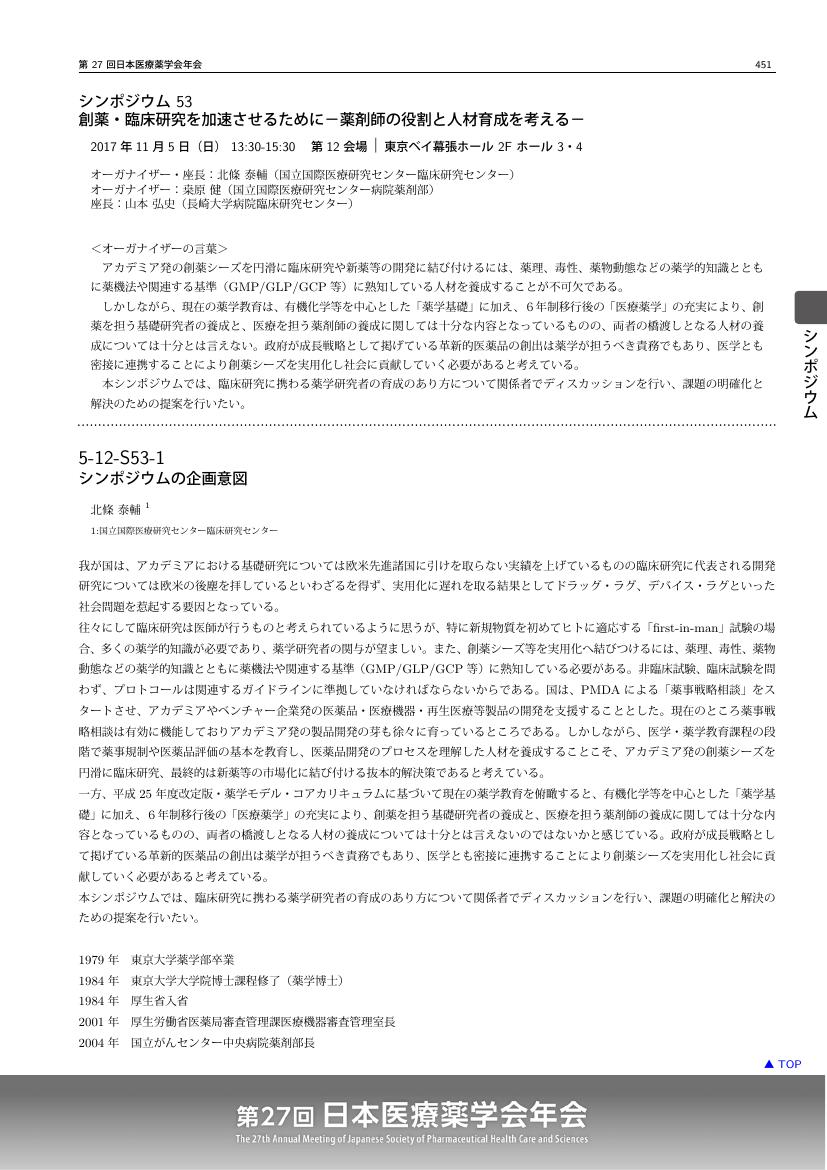- 著者
- 北川 純一 高辻 華子 高橋 功次朗 真貝 富夫
- 出版者
- 日本味と匂学会
- 雑誌
- 日本味と匂学会誌 (ISSN:13404806)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.143-149, 2013 (Released:2018-05-30)
「おいしさ」にとって重要な要素である「のどごし」の形成には、咽頭・喉頭領域の感覚が深く関与していると考えられる。しかしながら、咽頭・喉頭領域の感覚についての研究報告はあまり多くない。本稿では、これまでの研究によって明らかにされた咽頭および喉頭領域を支配する神経(舌咽神経咽頭枝と上喉頭神経)の味覚応答特性ついて紹介するとともに、近年、盛んに研究されているTRPチャネルファミリーとのどごし感覚の関連性を検討する。さらに、健康的な生活を過ごすために大切な摂食(嚥下)機能に対する咽頭・喉頭領域からの求心性情報の役割について考察する。
1 0 0 0 OA 日本近代化の一断面としての捕鯨 ─ジャパン・グラウンドを中心として─
- 著者
- 木村 美智子
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.19, 2018 (Released:2018-07-14)
- 著者
- edited by K.R. Moore
- 出版者
- Routledge
- 巻号頁・発行日
- 2023
1 0 0 0 OA 自家和合性を示すリンゴ同質四倍体品種の結実特性と花粉管伸長特性
- 著者
- 安達 義輝 小森 貞男 星川 義真 田中 紀充 阿部 和幸 別所 英男 渡邉 学 壽松木 章
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- Journal of the Japanese Society for Horticultural Science (ISSN:18823351)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.402-409, 2009 (Released:2009-10-23)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 30 34
リンゴを含むバラ科に属する種は自家不和合性を有しているが,多くの種では倍数化によって打破される報告がある.リンゴで同質四倍体品種とその倍数化前オリジナル二倍体品種を用いて,交雑和合性試験および花粉管伸長調査を行った.同質四倍体品種が自家結実性を示し,同質四倍体品種花粉が自家受粉およびオリジナル二倍体品種雌ずいにおいて和合性を誘導した.一方,オリジナル二倍体品種花粉を同質四倍体品種に交配した場合には不和合性を示したことから,同質四倍体品種の自家和合性誘導の原因は花粉側にあることが示唆された.また,自家受粉の花粉管伸長は同質四倍体品種が最も大きく,次いで二倍体,三倍体の順であった.二倍体および三倍体品種の花粉管は雌ずいの倍数性とは無関係に伸長が抑制されるのに対し,同質四倍体品種の花粉管は他家受粉には及ばないが不和合花粉管よりも有意に伸長する中間的な伸長度を示した.交雑試験と花粉管伸長調査の結果から,同質四倍体品種の自家和合性は花粉側にあることが判明した.さらに,倍数化による花粉管伸長度の増大ではなく,自家不和合性機構が打破されている可能性が示された.
1 0 0 0 OA Libraryめぐり 富山医科薬科大学/白鳥製薬(株)
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.222-226, 1993-07-31 (Released:2011-09-21)
1 0 0 0 OA チーグラー法ポリエチレンについて
- 著者
- 須田 純吉
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.8, pp.617-626, 1956-08-15 (Released:2013-03-05)
1 0 0 0 OA 低温環境用リチウムイオン電池の開発
- 著者
- 白方 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.12, pp.717-720, 2018 (Released:2018-12-12)
1 0 0 0 OA 創薬・臨床研究を加速させるために
- 著者
- 北條 泰輔 桒原 健 山本 弘史
- 出版者
- Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences
- 雑誌
- 日本医療薬学会年会講演要旨集 (ISSN:24242470)
- 巻号頁・発行日
- pp.451-456, 2017-11-03 (Released:2019-03-23)
1 0 0 0 OA 情報の部分性とフレーム問題の解決不能性
- 著者
- 松原 仁 橋田 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.6, pp.695-703, 1989-11-20 (Released:2020-09-29)
The frame problem is very important in the context of knowledge representation of both humans and computers. The present paper discusses the frame problem for humans from a viewpoint of artificial intelligence. A major claim here is that the frame problem is unsolvable for humans as well. This claim is supported by several examples. Another major claim is that from a viewpoint of partiality of information, the frame problem must be discussed generally in a wide sense of the term, instead of being subdivided into the problem of description and the problem of processing. The unsolvability of the frame problem for humans should not be regarded as a limitation of human intelligence. Contrariwise, the flexibility of human intelligence is possible thanks to the fact that they cannot solve the frame problem; i. e., the fact that they make mistakes from time to time.
1 0 0 0 OA 重力波を聞き,電磁波を見る : 電磁波対応天体(最近の研究から)
- 著者
- 久徳 浩太郎 仏坂 健太
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.319-323, 2014-05-05 (Released:2019-08-22)
重力波による全く新しい天文学-重力波天文学-の幕開けが手の届くところに迫っている.一般相対論で予言される時空の計量の波である重力波は,ブラックホールや中性子星のような強重力天体が激しく運動するときに効率良く放射される.そのためこれら強重力天体,通称コンパクト天体が対をなした連星が重力波を放射しながら合体する「コンパクト連星合体」は,最も有望な重力波源である.重力波の直接観測は間違いなく物理学の一つの金字塔となり,さらに強重力場の観測による一般相対論の検証や原子核以上の密度を持つ中性子星内部の観測など,重力波天文学によって初めて可能になる様々な展開が期待される.その幕を開く鍵になるのが重力波源からの電磁波放射,すなわち重力波源の電磁波対応天体の観測である.重力波の検出は質的に新たな挑戦であり,初検出を確実にするには他の状況証拠の存在が望まれる.その点で電磁波は,古来の肉眼による夜空の可視光観測から,現在では電波からガンマ線まで,幅広く宇宙の観測に用いられてきた信頼のおける手段である.そのため,連星が合体するときに特徴的な電磁波が放射され,それを観測できれば,連星が合体しているという確かな証拠を得て,重力波の検出をより確実にできる.では,連星が合体するとき本当に,またされるとしてどのような電磁波が放射されるのだろうか?電磁波対応天体は近年大きな注目を集めており,理論研究が急速に進展している.一つの確実に近い知見は,連星の合体に伴って中性子星から物質が放出されると,様々な機構での電磁波放射が期待できるということである.そのため,連星合体に伴って起こる質量放出の様子を調べることは,電磁波対応天体の定量的な理論予言のために不可欠である.我々は数値相対論シミュレーションを用いて,中性子星を含むコンパクト連星の合体では,太陽質量の0.1-10%程度の物質が光速の10-30%で放出される可能性が高いことを,一般相対論での定量的な計算として初めて示した.電磁波対応天体の理論モデルによれば,これだけの物質が放出されれば,それに付随して十分に観測可能な明るい放射が期待できる.たとえば,放出された物質の中でr過程元素合成と呼ばれる過程により非常に重い中性子過剰核が合成され,放射性崩壊して温度が上がるために増光が起こる「巨新星」や,放出された物質が宇宙に存在する希薄な物質と衝突して,シンクロトロン放射を起こす「コンパクト連星合体残骸」などが電磁波対応天体の有望な候補となる.我々の質量放出の研究とほぼ同時期,2013年の6月に,巨新星と見られる増光現象が初めて観測された.我々は質量放出の結果に放射輸送のシミュレーションを組み合わせ,観測された現象が巨新星の理論予言と整合することを明らかにした.この一例の観測は決定打ではないが,重力波源の電磁波対応天体として,巨新星を始めとする理論的な予言が現実のものとなる蓋然性が高まったといえる.同時に,理論予言に過ぎなかった電磁波対応天体の探査に多大な観測能力が投入されたことは,この分野が注目を集めていることの証左となろう.
1 0 0 0 OA 医学科における「症例報告の書き方」教育法の模索
- 著者
- 柿坂 庸介
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.209-215, 2023-04-25 (Released:2023-09-07)
- 参考文献数
- 21
筆者は医学科生に対し2013年より「症例報告の書き方」講義と執筆指導を開始した. 講義では, まず症例報告の教育的意義 (疾患理解, 論理的思考, 発信力ならびに臨床推論力の向上) を強調する. ついで新規点ならびに臨床的意義を明確にする重要性を示す. 次に執筆過程を4分割しそれぞれに目的と具体的行動を設定し, 実症例を提示しながら解説する. 執筆指導では症例報告における「要修正部位に対し資料を示しながら, 具体的な訂正法を提示する」介入により, 医学領域の作文学修における転移を促す教育法を模索している. 講義のアーカイブ化と学生の自律的成長を促す環境構築により, 本教育は持続可能な医学教育文化となりうる.
1 0 0 0 OA 音声生成の生理学的背景 (<特集>音声)
- 著者
- 本多 清志
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.9-14, 1991-12-25 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 親しい男性どうしの話し方―『日常』自然談話への出現状況
- 著者
- 小林 美恵子
- 出版者
- 現代日本語研究会
- 雑誌
- ことば (ISSN:03894878)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.21-38, 2021-12-31 (Released:2021-12-31)
- 参考文献数
- 11
映画『何者』などで男子大学生どうしの親密さを表すものとして、中性化しないいわば「男性特有」の話し方(形式)が存在する。このような話し方が自然談話ではどのように現れるかを『談話資料・日常生活のことば』において検討した。その結果、全体では1/5程度の男性話者がこのような話し方をしていること、特に20代と60・70代にめだつことがわかった。その理由は対話の相手との関係(親しさなど)によると考えられる。また、特に高年代では使用のバリエーションや現れ方が多様で、映画に現れる高年代の男性のことばや話し方とは必ずしも同じようではないということもわかった。
1 0 0 0 OA 液体ナトリウムの発火および燃焼現象の研究
- 著者
- 北川 徹三 小木曾 千秋
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.31-36, 1968-03-15 (Released:2018-11-08)
1 0 0 0 OA 哺乳類の冬眠と季節性のからだの変化
- 著者
- 山口 良文
- 出版者
- 低温生物工学会
- 雑誌
- 低温生物工学会誌 (ISSN:13407902)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.11-15, 2020 (Released:2020-09-01)
Mammalian hibernation is a strategy to survive during harsh winter with severe hypothermia and immobility state. It has attracted many researchers for a long time but still remains to be elucidated. Studies in obligate hibernators such as ground squirrels, chipmunk, and bears have revealed that they undergo systemic body remodeling in a season-dependent manner prior to hibernation. By contrast, a facultative hibernator, Syrian hamster, can hibernate in an environment-dependent manner; when they are exposed cold and short photoperiod condition for several months, they begin to hibernate. This inducible hibernation allows researchers to study mechanisms and significance of hibernation under a laboratory condition, whereas exact nature of systemic body remodeling for hibernation in Syrian hamsters remain unclear yet. Using histology and exhaustive gene expression analyses, we compared summer-like hamsters and winter-like hamsters and found that Syrian hamsters extensively remodel white adipose tissues during a pre-hibernation period. Particularly, simultaneous up-regulation of gene expression in both lipid catabolisms and lipid anabolisms takes place in winter-like hamsters, which is a unique property of Syrian hamsters, a“food-storing” hibernator who ingests food stored in the nest during hibernation season.
1 0 0 0 コダーイのシステムによるソルフェージ教授法
- 著者
- セーニ・エルジェーベト著 羽仁協子訳
- 出版者
- 全音楽譜出版社
- 巻号頁・発行日
- 1971
1 0 0 0 OA 紹介
- 著者
- 渡辺 金一
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.40, 1966 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 神武天皇 (じんむてんのう) : 伝記による日本の歴史物語
- 著者
- 保田與重郎作 柳井愛子絵
- 出版者
- 全日本家庭教育研究会
- 巻号頁・発行日
- 1982
1 0 0 0 OA 近江国筑摩御厨における自然環境と漁撈活動 : 湖岸の御厨の環境史
- 著者
- 佐野 静代
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, pp.85-108, 2006-12-20
古代の御厨における漁撈活動の実態を解明するためには,「湖沼河海」の各々の御厨を取り巻く自然環境の分析が不可欠である。自然環境の分析には,地形・気候的条件とともに,その上に展開する「生態系」,特に魚類を中心とした生物相の考察が含まれる。魚類の生態と行動(生活史・食性・場所利用など)は,古代にも遡及しうるものであり,当時の地形と漁撈技術段階との照合によって,魚種ごとの捕獲原理や漁獲時期が推定可能となる。このようにして各御厨で行われた漁法が明らかになれば,「湖沼河海」の御厨ごとの漁撈活動と,贄人の生活形態の相違が浮かび上がってくるはずである。本稿では,古代の琵琶湖に設けられた筑摩御厨を対象として,当時の地形・生息魚種の生態・漁撈技術段階を照合し,その生活実態について検討した。筑摩御厨では,春の産卵期に接岸してくるフナと,春~初夏に琵琶湖から流入河川に遡上してくるアユを漁獲対象としており,贄人の漁撈活動は,地先水面での地引網漁+上り簗漁というきわめて定着的な漁法によっていたことがわかった。御厨現地での生活実態としては,水陸の移行帯において漁撈と農耕が分かちがたく結びついた「漁+農」複合型の生業形態であったと推定される。琵琶湖岸の古代の御厨においては,漁撈のみに尖鋭化した特権的専業漁民の姿は認めがたく,古代の贄人の生活実態は,網野善彦が提起した「船による移動・遍歴を生活の基本とする海民」像とは,異なるものといえる。生業を指標とする集団の考察には,現地の環境条件との照合が不可欠であり,網野の提起した「非農業民」概念もこのような視点から再検討されるべきと考える。