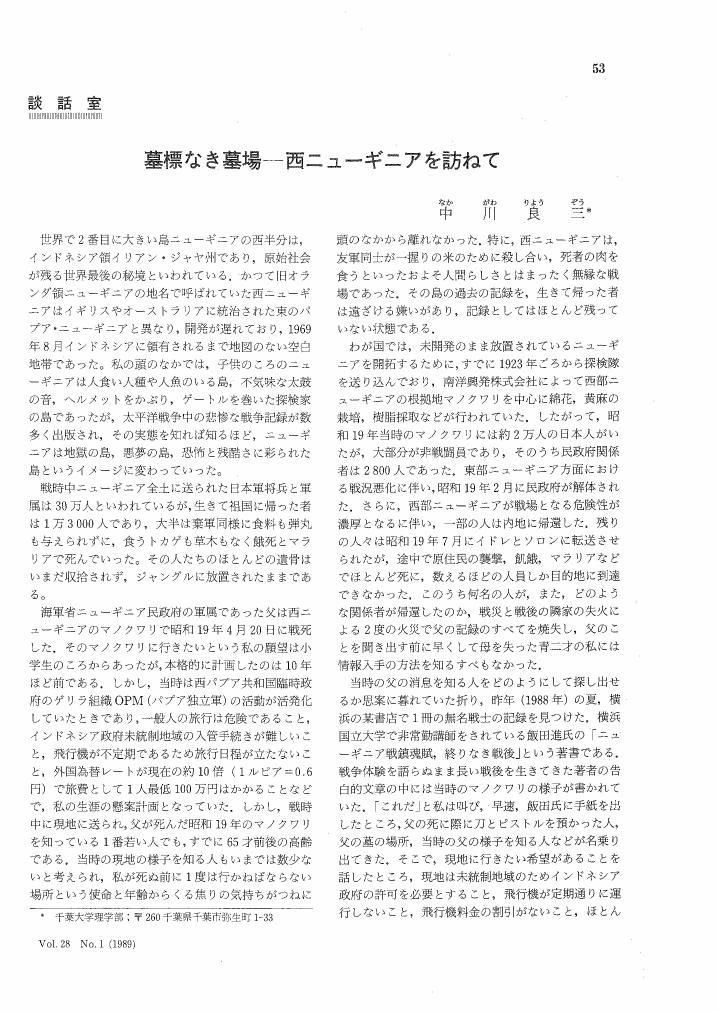1 0 0 0 OA 最先端の研究開発 日本原子力研究開発機構 第3回 原子科学の最先端を拓く
- 著者
- リカルド オルランディ 廣瀬 健太郎 矢板 毅 山上 浩志 家田 淳一 神戸 振作 石川 法人
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.280-284, 2020 (Released:2020-11-01)
- 参考文献数
- 6
東京電力福島第一原子力発電所事故対応では,燃料デブリと闘う未知の領域への挑戦が待っている。安全性の向上や廃棄物問題の解決も必須だ。さらに放射線利用にはイノベーションを誘起する先端技術も求められる。日本原子力研究開発機構の原子力科学研究部門には3つの研究センターがあり,これらの問題に対応するため先端的な研究,基礎基盤研究や応用研究を行っている。
1 0 0 0 OA 実相観入(温故創新)
- 著者
- 久保田 紀彦
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.6, pp.446-449, 2011-06-20 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 富山県のリゾートホテルでみられたトコジラミの大発生とその駆除記録
- 著者
- 谷口 敬敏 黒田 昭吉 渡辺 護
- 出版者
- 日本ペストロジー学会
- 雑誌
- ペストロジー学会誌 (ISSN:09167382)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.53-58, 2003-05-30 (Released:2019-07-11)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 5
自閉症スペクトラム(ASD)は社会不適応に至る症例も多く、その一因として感覚特性の影響、中でも聴覚特性の影響が指摘されている。聴覚特性には「選択的聴覚注意障害」と「聴覚過敏」があり、支援に違いがあるが、臨床的に区別が困難な例が多い。聴覚情報処理障害(APD)は「聴力は正常であるが、聞き取りにくさが生じる」一群で、社会的不適応になる例が散見される。本研究の目的は、心理検査、APDの検査である聴覚検査などを組み合わせることで、ASDの聴覚特性の特徴を詳細に検討し、概念を整理することである。最終的には聴覚特性に起因する社会不適応への支援を検討することが目的である。
1 0 0 0 OA 「主体的・対話的で深い学び」を実現する環境教育 -社会科教育の視点から-
- 著者
- 水山 光春
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境教育学会
- 雑誌
- 環境教育 (ISSN:09172866)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.3_25-32, 2017 (Released:2018-03-10)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 母乳の長所と限界
- 著者
- 水野 克己
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.672-675, 2023 (Released:2023-04-20)
- 参考文献数
- 36
はじめに 哺乳動物であるヒトが出産したわが子を母乳で育てることは,ごく“ふつう”のことである.しかし,女性が身近で子育てをしている様子を見たり,育児にかかわったりすることなく自身の妊娠出産を迎えることが一般的となった現代では,母乳育児が“ふつう”のこととはいい難くなった.母乳には子どもをいろいろな疾病から守る作用があり,母乳の成分研究を経て,特定の母乳成分と疾病との関連についても明らかになってきている.今後,特定の母乳成分を取り出して人工乳に添加し,疾病予防につなげるというトランスレーショナルリサーチも発展していくだろう. 将来を左右する受精から2歳の誕生日までのthe first 1,000 daysは母乳栄養が望ましい(生後6カ月以降は母乳で不足する栄養を固形食で与える).これはmicrobiomeやepigeneticsの研究からも明らかになってきている.つまり,研究から得られたエビデンスは母乳育児を推奨するものであり,私たち医学者が,母親を根拠のない迷信に基づいた母乳育児の押し付けから守り,母乳育児を“ふつう”のこととして行えるようサポートすることはマストと考える. もちろん,人工栄養を選択せざるを得ない場合,人工乳を補足しなければならない場合もある.そのような場合も母親の思いを傾聴したうえで,子どもの健康を守れるよう情報提供をしなければならない.母親に情報提供する際には,母乳育児で問題となりやすいこととその対処方法を母親にわかりやすく伝えることも欠かせない.
1 0 0 0 OA 高齢者総合機能評価をがんの治療方針の決定に生かす
- 著者
- 森井 和彦 福永 智栄 多田 俊史 中村 進一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本病院総合診療医学会
- 雑誌
- 日本病院総合診療医学会雑誌 (ISSN:21858136)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.214-222, 2023-05-31 (Released:2023-10-19)
がんの治療方針は staging や performance status に基づいて決定されることが多いが,高齢者の場合は平均余命が短く,複数の併存疾患や加齢による脆弱性を認めることがあるため, 高齢者総合機能評価(comprehensive geriatric assessment;CGA)を行わないで治療を始めるのは危険である。高齢者の脆弱性は日常的診療では拾い上げが不完全であり,CGAでの評価が望ましい。多忙な日常診療ではまず G8 Screening tool で脆弱性の疑われる高齢者をスクリーニングして,該当者に CGA を行うのが効率的である。CGAでは検証されたツールを用いて,instrumental activities of daily living(IADL),併存疾患,転倒,栄養状態,化学療法の毒性の予測,がん以外の要因による平均余命, 薬剤関連の問題,認知障害,うつ病,社会的支援システムの不足などを評価する。近年使用頻度が増えている免疫チェックポイント阻害剤の 有益性・有害性の予測にもCGAが有効かどうかは,今後の課題である。
1 0 0 0 OA 心停止蘇生後の脳循環動態
- 著者
- 新井 達潤
- 出版者
- Okayama Medical Association
- 雑誌
- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.1-2, pp.21-36, 1977-02-28 (Released:2009-03-30)
- 参考文献数
- 59
Ventricular fibrillation was induced in fifteen monkeys by electric stimulation using a bipolar intracardiac pacemaker electrode which was inserted through a femoral vein. The monkeys were defibrillated and resuscitated after several minutes. Cerebral blood flow (CBF), intracranial pressure (ICP) and EEG were monitored continuously. CBF autoregulation was checked regularly before and after ventricular fibrillation to study the relation between it and other parameters such as CBF, ICP, EEG.Fifteen monkeys were divided into two groups, a burr-hole group and a no burr-hole group. ICP was measured in the burr-hole group (10 monkeys). The purpose of having two groups was to ascertain the effect of a burr-hole (artificial injury in the skull and dura) on the parameters CBF, EEG and autoregulation. CBF was measured with electromagnetic flowmeter at internal carotid artery.The conclusion of the experiment was as follows;(1) Autoregulation was lost in all monkeys after resuscitation. In the monkeys which had had autoregulation before cardiac arrest, the autoregulation recovered in three (no burr-hole group) to five (burr-hole group) hours after resuscitation, if resuscitation took place within five minutes. In the monkeys whose autoregulation had already been lost before cardiac arrest, it did not return despite successful cardiac resuscitation.(2) Immediately after resuscitation, BP, ICP and CBF increased for 20-60 minutes. In the monkeys who had no recovery of autoregulation after resuscitation, the rate of increase of ICP was much larger than those whose autoregulation recovered, and at the peak of ICP, the CBF decreased. Impairment of autoregulation itself, indicates that the ballance of circulatory dynamics of the brain is easily impaired by noxious stimulation such as hypoxia.(3) In the monkeys with recovery of autoregulation, general status was good after resuscitation but in the monkeys without recoverey, symptomes of increased ICP were seen and the prognosis was poor.(4) Six minutes of cardiac arrest would appear to be the upper limit for monkeys to survive after resuscitation.(5) Before ventricular fibrillation, corresponding changes in the CBF and the frequency of the EEG wave recorded, but after resuscitation the frequency of the EEG wave decreased despite an increase in CBF. This is probably the same mechanism as occures in the “luxury perfusion syndrome”.There was no relation between EEG and autoregulation, but when EEG showed dominant slow or flat waves, there was no autoregulation.
1 0 0 0 OA 良好な生活習慣の医療費抑制効果についての統計分析
- 著者
- 山本 信一 井上 麻央 米山 高生
- 出版者
- 生活経済学会
- 雑誌
- 生活経済学研究 (ISSN:13417347)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.53-64, 2017 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 5
The aging population has resulted in the percentage of GDP allocated to healthcare costs reaching about 10%, and further increases are expected. To manage this issue, the Ministry of Health, Labor, and Welfare is attempting to improve the population's lifestyle and to moderate healthcare cost increases by conducting medical checkups and providing health guidance for lifestyle improvements. The study data comprise medical prescriptions and medical examinations of 24,725 people who have developed diabetes and 13,453 people who have developed high blood pressure (data from the Japan Medical Data Center). Based on a multiple regression analysis, we compare people with good lifestyle habits and people with bad lifestyle habits to examine how the increases in their healthcare costs changed as a result of their diagnoses. For people who developed diabetes, those who properly controlled their BMI and LDL cholesterol levels, refrained from smoking and drinking, and exercised regularly (i.e., practiced good lifestyle habits) were able to maintain satisfactory medical examination results (diabetes). Based on these results, we prove statistically that the increase in healthcare costs is less for people who keep good lifestyle habits, even if they develop diabetes. Similarly, people who developed high blood pressure and practiced good lifestyle habits were able to maintain satisfactory medical examination results (high blood pressure). Again, the increase in the healthcare costs for this group was less, even if they developed high blood pressure, although, in this case, exercising regularly was not a relevant factor.
1 0 0 0 OA 森林植生の違いを考慮した太陽光発電システムの土地利用影響評価
- 著者
- 野田 英樹 奥野 喜裕 伊坪 徳宏
- 出版者
- 日本LCA学会
- 雑誌
- 日本LCA学会誌 (ISSN:18802761)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.172-188, 2015 (Released:2015-11-09)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
Objective. Photovoltaic (PV) power systems are considered an essential component of environmental friendly society. However, the land area required for generating unit amount of power by PV system is larger than that for an equivalent coal-fired power system. In Japan there has been some instances of PV power systems being installed in forest areas. Therefore, the purpose of this study is to explore the impact of PV power systems on Japanese forests. Forest vegetation is classified into the 13 types used in the “Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling 2 (LIME2)” methodology. This will allow us to establish the relationship between the reduced CO2 emissions of a PV power system and the system’s impact on forest by way of land use, compared with those of coal-fired power system.Results and Discussion. The environmental impact of a PV power system installed on a roof was calculated as 6.3% of the impact of a coal-fired power system. In contrast, placing the PV power system in oak or pine forest had a substantially greater environmental impacts, of 76.7% and 99.9% respectively. Following sensitivity analysis, it became apparent that the area required by a PV power system per generated unit of power is the most important factor. For example, with regard to the oak forest, the environmental impact of the PV power system can be reduced from 99.9% to 74.2% by decreasing the area required per generated unit of power from 15,200m2/MW to 11,000m2/MW. A further improvement of 5.8% can be achieved by planting grass under PV panels.Conclusions. LIME2 damage factors were used to classify land use impact for 13 vegetational types of Japanese forest. From the calculated results, it is clear that the environmental impact of PV power system land use on a forest should not be disregarded; however, the level of that impact will depend on the vegetational classification. Furthermore, reducing the utilization rate of the PV power system is an effective way to lessen the impact of land use.
1 0 0 0 ホルモンおよびフェロモンによる生殖の調節
我々は主としてアカハライモリ(Cynops pyrrohogaster)の生殖行動に関与するホルモンおよびフェロモンの同定、およびはたらきに的をしぼって研究を行った。その結果以下のような結果を得た。生殖期に雄イモリは生殖可能な雌イモリの前で尾をさかんに振りフェロモン(ソデフリン)を放出し、精子塊を放出してそれを雌の総排泄口よりとり込ませて体内受精をさせる。尾をさかんに振る行動はプロラクチン(PRL)とアンドロゲンでひきおこされることがわかった。この場合PRLは中枢、おそらくpreoptic recess organおよび/またはnucleus infundiblaris dorsalisに作用することが脳室内投与およびプロラクチン受容体の免疫組織学的研究より明らかになった。一方アルギニンヴァソトシン(AVT)は上記求愛行動の発現をたかめることが明らかにされた。この場合AVTはVlaレセプターを介することが薬理学的実験からわかった。一方イモリの求愛フェロモン(ソデフリン)には前駆体タンパクが存在することがソデフリンをコードするcDNAのクローニングによりわかった。更にこのタンパクのmRNAレベルはPRLとアンドロゲンによりたかめられることもわかった。一方雌のソデフリンに対する反応に関する研究では、ソデフリンは主として雌の鋤鼻上皮で受容されること、ソデフリンに対する雌の鋤鼻上皮の反応性はPRLとエストロゲンにより支えられていること、雄鋤鼻上皮も上記ホルモンによって反応性がたかまるが雌のそれにくらべてはるかに低いことが明らかにされた。アカハライモリと同族異種のシリケンイモリ(C.ensicauda)雄もソデフリンに相当する10箇のアミノ酸残基よりなるペプチドフェロモン(シリフリン)を有することがわかった。しかし両フェロモンはそれぞれ同種の雌にしか有効でなく、種特異性があり、おそらくこれが生殖隔離に寄与していることが示唆された。今後フェロモン受容体の特定をめざす。
1 0 0 0 OA ROHAN:テキスト音声合成に向けたモーラバランス型日本語コーパス
- 著者
- 森勢 将雅
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.9-17, 2022-12-25 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 24
本論文では,テキスト音声合成の中でも特にEnd-to-End音声合成時代に向けた大規模日本語コーパスROHANを提案する。ROHANは常用漢字すべてを網羅しつつ,日本語文章では出現しにくいモーラを一定数含めるモーラバランスを重視している。オリジナルのコーパス文4,600文を22のサブセットとして構築しており,パブリックドメインのライセンスで公開している点も,本コーパスの特色である。本論文では,ROHANの設計コンセプトと具体的な作成手順を示し,各モーラの出現回数やコーパス文の平均モーラ数などの解析結果を示す。モーラ出現頻度に関するエントロピー,及び音素の拡張エントロピーによる評価から,既存のコーパスよりもモーラ・音素バランスに優れていることも示す。
1 0 0 0 OA ソフィ・カルの芸術に向けて
- 著者
- 松本 良輔
- 出版者
- 成城大学フランス語フランス文化研究会
- 雑誌
- AZUR (ISSN:21887497)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.57-75, 2023-03-15 (Released:2023-04-12)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA H∞制御と非線形適応制御機構を有するアクティブサスペンション
- 著者
- 深尾 隆則 山脇 明 足立 紀彦
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.11, pp.1034-1039, 2001-11-30 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 14
The control technique which combines H∞ control with adaptive nonlinear control is applied to the active suspension system which is divided into two parts: a main car body part and a hydraulic actuator part. The H∞ control design is used for the body part where the frequency response property is important to improve the ride quality of the automobiles, and the adaptive nonlinear control design is used for the actuator part with the high nonlinearities and the parametric uncertainties which is required to transmit the power to the main body adequately because it gives large effects on the control result. These two design methods are combined by a modified version of backstepping which is a powerful tool for nonlinear control and adaptive control. Finally some simulation results are provided to confirm the usefulness of our method.
我々は、細胞間接着分子カドヘリンに骨芽細胞分化制御機能があることを報告する。各種間葉系細胞株におけるカドヘリンの発現を調べた結果、各細胞株はそれぞれが独特なカドヘリンの発現様式を持っており、骨芽細胞系譜では、OBカドヘリン(カドヘリン-11)およびNカドヘリンを発現していることがわかった。同一細胞において複数種のカドヘリンが発現することの意味を調べるために、頭頂骨骨芽細胞と同程度にOBおよびNカドヘリンを発現させたL細胞(L-OB/N)ならびに、それぞれ単独で発現させたL細胞(L-OB,L-N,L-MOCK)を作製した。細胞染色の結果、OBとNカドヘリンは、それぞれが独立してアドヘレンスジャンクションに局在し、共に細胞接着に寄与していると考えられた。また、L-OB/Nにおいては骨芽細胞分化マーカーであるALP,Osteocalcinの発現誘導および骨芽細胞分化のマスター遺伝子であるCbfalの発現上昇が確認された。L-OBでは微弱ながらALPの発現が確認でき、L-N,L-MOCKでは全くそれら発現は確認されなかった。以上のことよりOBカドヘリンは骨芽細胞分化を方向付けし、Nカドヘリンはその作用を増強すると考えられた。NIH3T3においても同様の実験を試みたところALP,Osteocalcinの発現誘導は確認出来なかったが、FGFR2の発現が上昇し、L-OB/Nにおいても同様に発現上昇が確認された。FGFR2は、突然変異が骨格系に多くの異常を示し、Osteopontin発現上昇以前の骨芽細胞前駆細胞において発現することから、骨芽細胞初期分化に重要であると考えられている。これらのことより、OBとNカドヘリンは、未分化な骨芽細胞前駆細胞の細胞分化運命を決定していると考えられる。今回の結果は、複雑な細胞間相互作用が複数種のカドヘリンのよる細胞間認識の結果であると共に、細胞間認識による細胞分化決定機構の存在を示唆するものである。
1 0 0 0 OA 大学図書館の蔵書数
- 著者
- 黒木 努
- 出版者
- 日本図書館情報学会
- 雑誌
- 図書館学会年報 (ISSN:00409650)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.54-64, 1967 (Released:2023-07-29)
Increasing university students and the establishments of more universities are the current of the world. The Japanese colleges and universities are no exception. Each college and universities has own history, and its scale or structure is various. We cannot grasp likeness among universities. It is important to render these universities a library service without the declining of its quality in a period of sudden growth and expansion. Many university librarians consider quality matters more than quantity in the estimating of book collections. The present author regards quantity as serious as quality. There are five standards for college and junior college libraries in Japan. Those standards use only student body for estimating size of college library collection. College library has an obligation to cater for faculty as well as students. Accordingly, it is not reasonable to estimate the size of book collection based only upon the student body. The quantitative standard of college libraries must be estimated based on the factors; departments of instruction, the course of study, faculty and the student body, etc. The author tried to find out the formula to estimate the minimum size required for an college library, combinding each factor. The standards for the blueprint of college and university libraries should be revised according to needs of the times. College librarians should show the satisfactory standards of quantity for accrediting agency and appropriating authorities.
1 0 0 0 OA 駄洒落を用いた授業動画集中力向上システムの提案
- 著者
- 三浦 温樹 澤田 隼 桂田 浩一 大村 英史
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.4T2GS1003, 2023 (Released:2023-07-10)
昨今のコロナ禍の影響により,オンラインや動画による授業を受ける頻度が急激に高まった.オンラインや動画による授業は場所を選ばずに受けられるため,自室などの誘惑の多い環境で受けることが多い.このような環境下では,ついスマートフォンで通知を確認したり,部屋にある授業と関係のない本や漫画を手に取ってしまったりなど,授業への集中力が欠如しがちになる.この問題を解決するために,本研究では駄洒落を用いて授業に集中させるシステムを提案する.駄洒落は言葉遊びの一つで,その楽しさやおかしさから聴取者の注意を引く.この機能を利用し,提案システムでは授業における重要な単語から駄洒落を生成し,ユーザの注意を授業動画に引きつけ集中力を向上させることを目指す.提案システムの検証実験により集中に関する一定の効果が得られたことを確認した.
1 0 0 0 OA 薬学教育6年制の導入
- 著者
- 田中 克平
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬剤学会
- 雑誌
- 薬剤学 (ISSN:03727629)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.326-331, 2004 (Released:2019-05-10)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- Kenji Imamura Kuniko Saito Kugatsu Sadamitsu Hitoshi Nishikawa
- 出版者
- Information and Media Technologies Editorial Board
- 雑誌
- Information and Media Technologies (ISSN:18810896)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.834-856, 2014 (Released:2014-12-15)
- 参考文献数
- 20
This paper shows how to correct the grammatical errors of Japanese particles made by Japanese learners. Our method is based on discriminative sequence conversion, which converts one sequence of words into another and corrects particle errors by substitution, insertion, or deletion. However, it is difficult to collect large learners' corpora. We solve this problem with a discriminative learning framework that uses the following two methods. First, language model probabilities obtained from large, raw text corpora are combined with n-gram binary features obtained from learners' corpora. This method is applied to measure the accuracy of Japanese sentences. Second, automatically generated pseudo-error sentences are added to learners' corpora to enrich the corpora directly. Furthermore, we apply domain adaptation, in which the pseudo-error sentences (the source domain) are adapted to the real error sentences (the target domain). Experiments show that the recall rate is improved using both language model probabilities and n-gram binary features. Stable improvement is achieved using pseudo-error sentences with domain adaptation.
1 0 0 0 OA 墓標なき墓場一西ニューギニアを訪ねて
- 著者
- 中川 良三
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.53-56, 1989-02-15 (Released:2017-10-31)