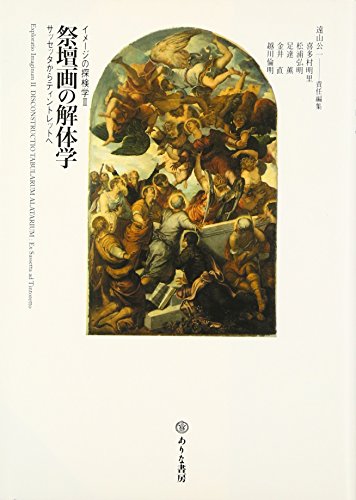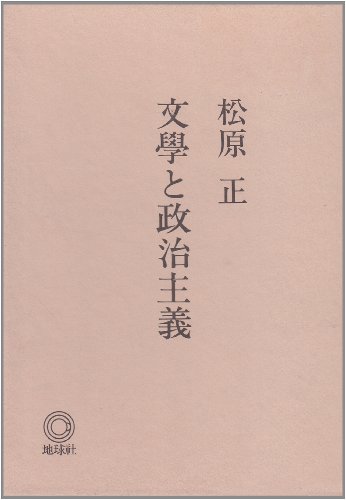1 0 0 0 OA 選ばれる都市
- 著者
- 清水 千弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本計画行政学会
- 雑誌
- 計画行政 (ISSN:03872513)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.21-26, 2022-08-15 (Released:2022-11-28)
- 参考文献数
- 13
What kind of economic impact do international mega-events such as the Olympic Games have on the host city? When the decision was made to host the Tokyo 2020 Olympics, an increase in the number of foreigners visiting Japan was expected to boost consumption. Since this consumption included accommodation in hotels and other facilities, there was a rush to build hotels. Furthermore, investment in infrastructure, such as the development of transport networks, accelerated. Such events can often be measured through changes in the property market. What did this mega-event leave behind in the host city when observed in a comparison of pre- and post-event periods? This paper focuses on international capital flow in the property market and examines the expected effects.
1 0 0 0 OA トラマドールからヒドロモルフォンにオピオイドスイッチ後に重篤な呼吸抑制が生じた1症例
- 著者
- 金澤 慧 野里 洵子 佐藤 信吾 髙橋 萌々子 入山 哲次 三宅 智
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.119-122, 2022-06-25 (Released:2022-06-25)
- 参考文献数
- 13
II型呼吸不全を合併した下咽頭がんの患者に,ヒドロモルフォンを投与したところ重大な呼吸抑制を認めた症例を経験したため報告する.症例は,下咽頭がんによる左頚部リンパ節転移,左肩甲骨転移,肺転移,肝転移を認める77歳男性.痛みと呼吸困難の症状緩和目的で緩和ケア病棟へ入棟した.ヒドロモルフォン経口徐放性製剤4 mg/日導入後,重大な呼吸抑制が生じた.ナロキソン投与にて呼吸状態は改善し,以降オピオイドの使用を控えることで呼吸抑制は認めなかった.呼吸不全や肝腎機能等の臓器障害の合併症のある終末期の患者では,全身状態をより慎重に評価し,薬物代謝能力の低下による生体内利用率の増加等を考慮して,投与量や投与方法を注意深く検討する必要があると考える.
1 0 0 0 OA 苛性ソーダによる口腔化学損傷の1例
- 著者
- 青柳 信好 黒田 卓 大石 建三 佐野 寿哉 連 利隆
- 出版者
- Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.481-485, 2007-08-20 (Released:2011-04-22)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
We report a case of serious injury to the oral mucosa resulting from the ingestion of a chemical agent.The severity of chemical injury to tissue depends on several factors, including the amount of agent involved, theduration of exposure, and the location of the affected site. It is important to immediately identify the cause ofchemical burns and to administer treatment quickly as damage will continue even after the chemical agent hasbeen removed.A 32-year-old man with schizophrenia swallowed sodium hydroxide in an attempt to commit suicide and wasbrought to our emergency room. An oral examination showed bilateral erosion of the buccal mucosa, soft palate, tongue, and lips. A tracheotomy was performed because of airway stenosis. The patient was instructed to garglewith azulene sodium sulfonate and to apply ointment on his lips. After 2 weeks, his condition improved and he wasdischarged from the hospital. Scar revision and skin grafting were performed as the patient was unable to movehis tongue for 5 months because of scar contracture of the sublingual region.
- 著者
- Kyoko Tanaka Hideto Goto Motofumi Tsubakihara Takeshi Kaneko
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.121-122, 2017-01-01 (Released:2017-01-01)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 倉上 和也 長瀬 輝顕 神宮 彰 和氣 貴祥
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会
- 雑誌
- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.252-259, 2014 (Released:2014-06-25)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 1
アルカリ性薬物の誤飲による咽喉頭食道炎は,粘膜びらん,壊死,瘢痕狭窄などさまざまな病態を呈し,致死的な状況となりうる。アルカリ性薬物誤飲例の報告自体が稀であるが,喉頭蓋脱落を観察した症例は文献的にはない。今回われわれは,95%水酸化カリウム誤飲により生じた腐食性咽喉頭食道炎に対し,長期入院および手術的加療を行い救命し得た症例を経験したので,詳細な咽喉頭所見の経過を含め報告する。症例は39歳男性。飲酒後にアルカリ性パイプ洗浄剤を誤飲し,嘔吐,振戦様痙攣をしているところを家人に発見され,当院急患室へ救急搬送された。声門狭窄は認めなかったものの,中下咽頭,舌根部,披裂部,喉頭蓋に粘膜の腐食性変化を認めた。全身麻酔下に気管切開術を施行し,集中治療室にて人工呼吸管理を行った。喉頭浮腫や粘膜炎は徐々に軽快したものの,第37病日より喉頭蓋の脱落を認め,喉頭蓋はほぼ完全に脱落した。脱落後は,喉頭蓋基部で周囲組織と癒着し,発声および経口摂取が不能な状態になった。第175病日に咽頭喉頭食道摘出術および有茎空腸による再建,永久気管孔形成術を施行した。2年経過した現在,重大な有害事象の出現を認めず,社会復帰し,経過観察中である。
1 0 0 0 祭壇画の解体学 : サッセッタからティントレットへ
- 著者
- 遠山公一責任編集 遠山公一 [ほか] 著
- 出版者
- ありな書房
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 OA 鷄卵中の硫酸態硫黄(第1報) 新鮮鷄卵中透析性硫酸態硫黄
- 著者
- 野並 慶宣
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.681-685, 1959 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 15
鶏卵中の硫酸基の結合形態を定量的に検討するため,卵黄,卵黄膜及び卵白の全硫酸態硫黄を定量し,次に卵黄,卵白中の弱い結合状態にある硫酸基を透析,稀釈により遊離する硫酸イオンより検討した.また卵黄,卵白の全硫酸態硫黄の1年間にわたる産卵季節による変化を検討した.これらの結果より次のことを明らかとした. (1)ムチンを主成分とする卵黄膜の硫酸基含有量は高く,また卵黄中にエーテル可溶脂質と結合する硫酸基はない. (2)卵黄は生鮮物中19mg%の硫酸態硫黄を含み,このうち蛋白質と強く結合するものは1mg%,遊離状態またはこれに近い弱い結合状態にあるものは8mg%で他は蛋白質と弱い結合をする. (3)卵白は生鮮物中7.0mg%の硫酸態硫黄を含むが,このうち3.5mg%は遊離または弱い結合状態で存在する. (4)鶏卵の硫酸態硫黄含有量の“ふれ”は卵黄より卵白において大である.
1 0 0 0 OA 正念場を迎えた行政改革
- 著者
- 田中 秀征
- 出版者
- 公益社団法人 日本不動産学会
- 雑誌
- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.25-31, 1998-03-30 (Released:2011-06-15)
- 著者
- Berenyce González-Marín María Elena Calderón-Segura Ana Karen González Pérez Luis Gerardo Moreno Ciénega
- 出版者
- The Japanese Society of Toxicology
- 雑誌
- Fundamental Toxicological Sciences (ISSN:2189115X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.81-88, 2021 (Released:2021-07-27)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1
Movento® 240SC and Envidor® 240SC are new insecticide derivatives of tetramic acid belonging to a keto-enol pesticide family. However, few studies have reported genotoxic effects in nontarget organisms. In the present study, the genotoxic effects of Movento® 240SC and Envidor® 240SC on Drosophila melanogaster ovaries were analyzed using the alkaline comet assay. Simultaneously, we determined the LD50 for both insecticides. Virgin females were exposed to food at three sublethal concentrations (11.2, 22.4, 37.3 mg/L) of Movento® 240SC and (12.3, 24.6, 41.1 mg/L) of Envidor® 240SC for 72 hr. As a negative control group, females were exposed to food without insecticides, and as a positive control group, females were exposed to 17.5 mg/L bleomycin under the same experimental conditions. We analyzed three genotoxic parameters, tail length, tail moment, and tail intensity, in ovarian cells. The results showed that 11.2 mg/L Movento® 240SC insecticide significantly increased the tail intensity mean in ovarian cells compared with the negative control. However, 22.4 and 37.3 mg/L Movento® 240SC significantly increased tail length and tail moment means compared with the negative control. Envidor® 240SC insecticide at 12.3, 24.6, 41.1 mg/L significantly increased the three genotoxic parameters in ovarian cells compared with the negative control. The LD50 values of Movento® 240SC and Envidor® 240SC insecticides were 79.1 mg/L and 78.0 mg/L, respectively. The genotoxic response of the two keto-enol pesticides was dependent on the concentration of each pesticide. The results demonstrated that Movento® 240SC and Envidor® 240SC keto-enol insecticides are genotoxic agents in D. melanogaster ovaries.
1 0 0 0 OA モンゴルの女子大学生の飲み物の飲用実態と意識 ―ウランバートル出身者と地方出身者の比較―
- 著者
- 早川 史子 岡崎 章子 韓 順子
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.260-265, 2006 (Released:2007-01-30)
- 参考文献数
- 16
2003年10月~12月, モンゴルのウランバートル出身の女子大学生306名と地方出身の女子大学生283名を対象に飲み物調査を実施し, 次のことが明らかになった。 1. ウランバートル出身者と地方出身者の間で湯の飲用頻度がもっとも高いことは共通していた。しかし湯以外の飲み物の飲用状況は両者間で異なり, 前者では紅茶やコーヒーの飲用頻度が高く, 地方出身者ではスーティツァイ, ハルツァイの飲用頻度が高かった。 2. コーヒーは食事と食事の間に飲まれる頻度が高かったが, 紅茶は食事に付随した飲み物として定着していることが明らかになった。 3. ウランバートル出身者に比べると地方出身者ではスーティツァイに対する嗜好性が高く, 紅茶に対する嗜好性が低かったことによって, 飲み物の嗜好性に差が認められた(p<0.001)。 4. 来客時および団欒時の飲み物としてスーティツァイに対するイメージが両群とももっとも高かったが, 地方出身者の方がより高かったことと紅茶に対するイメージがウランバートル出身者の方がより高かったことによって, 両者間における来客時および団欒時の飲み物に対するイメージに有意差が認められた(p<0.001)。 5. 紅茶やコーヒーに対して嗜好性を示した者でも来客時や団欒時には伝統的飲料であるスーティツァイをイメージする者が多かった。
1 0 0 0 OA コイ科魚類Xenocypris argenteaの骨学的研究
- 著者
- 籔本 美孝 坂本 陽子 刘 焕章
- 出版者
- 北九州市立自然史・歴史博物館
- 雑誌
- 北九州市立自然史・歴史博物館研究報告A類(自然史) (ISSN:13482653)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.69-86, 2010-03-31 (Released:2021-05-05)
- 参考文献数
- 31
The osteological description and illustrations of the cyprinid fish Xenocypris argentea from Taoyuan, Hunan Province and Guixi, Jiangxi Province, China are provided for studies on fossil cyprinid fishes found in East Asia and Japan including Iki Island, Nagasaki Prefecture, with brief comparison to a cultrin species, Hemiculter leucisculus and some other xenocyprinin genera and species.
1 0 0 0 OA 静脈血栓塞栓症治療の最前線
- 著者
- 山本 剛
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.5, pp.370-374, 2018 (Released:2018-05-25)
- 参考文献数
- 12
近年, 本邦においても静脈血栓塞栓症 (venous thromboembolism : VTE) の治療に直接作用型経口抗凝固薬 (direct oral anticoagulant : DOAC) が選択可能となった. VTEの初期治療方針は早期の予後リスクに基づいて決定する. 肺塞栓症によるショック例には血栓溶解療法を行う. 非ショック例には抗凝固療法を行うが, その方法として, (1) 未分画ヘパリンやフォンダパリヌクスの非経口薬からワルファリンへ橋渡しする従来法, (2) 非経口薬投与後にDOACの1つであるエドキサバンへ切り替える方法, (3) DOACのリバーロキサバンあるいはアピキサバンを初期強化用量にて開始し, その後維持量にて投与する単剤治療法がある. DOACを用いた抗凝固療法は, 従来治療の欠点を補い, 投与レジメンの標準化, 初期からの外来治療が可能になるなど, VTE管理の適正化をもたらした.
1 0 0 0 OA 検診マンモグラフィの読影:デジタルマンモグラフィの読影
- 著者
- 白岩 美咲 遠藤 登喜子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本乳癌検診学会
- 雑誌
- 日本乳癌検診学会誌 (ISSN:09180729)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.122-127, 2016 (Released:2018-06-27)
- 参考文献数
- 11
マンモグラフィ(MG)は,乳がん検診において死亡率減少効果がある有用なmodality であるが,40歳代については,乳がん発見の感度が50歳以上の年代と比較すると低いこと,偽陽性率が高いことも知られている。この一因に,40歳代の乳腺濃度が高いことがあり,対策として超音波検診の導入とともにデジタルMG(DMG)の活用が考えられる。DMG は,米国のtrial で,50歳以下の女性,不均一高濃度・高濃度乳房で精度が高いことが報告されている。日本でも近年,MG のデジタル化とモニタ診断が急速に進んでおり,2015年の日本乳がん検診精度管理中央機構MG 指導者研修会のアンケートでは,DMG が95%,モニタ診断経験が79%であった。一方,モニタ診断経験者の画素サイズ認識率は75%であり,また全国のMG 読影認定医のDMG ソフトコピー診断講習会受講率は13%であった。米国では,DMG 読影医にはDMG の講習受講が必須とされているが,日本ではその規定はない。読影医個人の検診精度管理指標もなく,読影医がDMG の特徴を理解して,その利点を引き出す読影ができているか,知るすべはない。40歳代のMG 検診に対する日米の動向の紹介とともにDMG・モニタ診断を活用した精度の高いMG 読影のために,いま何が必要なのか,具体的な読影の方法やDMG の新技術であるDigital breast tomosynthesis の話題を含めて,検討したいと思う。
1 0 0 0 佛教大学総合研究所紀要
- 著者
- 佛教大学総合研究所 [編]
- 出版者
- 佛教大学総合研究所
- 巻号頁・発行日
- 1994
- 著者
- 筑波大学比較民俗研究会 [編集]
- 出版者
- 筑波大学比較民俗研究会
- 巻号頁・発行日
- 1990
1 0 0 0 OA リハビリテーション医療における転倒予防
- 著者
- 北村 新 大高 洋平
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.269-274, 2021-03-18 (Released:2021-07-03)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
リハビリテーション医療の過程では,活動量の増大と安全は常にトレードオフの関係にあり,いかに転倒を予防しながら患者の活動性を高めるかは重要な課題である.医療機関において,双方のバランスを保ちながら患者を支援していくうえでは,センサーやアセスメントツールを用いて未然に転倒や外傷を防ぐ「ブレーキ」の視点と,患者個人に起因する内因性リスクを調整しながら病棟単位で積極的に活動を促していく「アクセル」の視点が求められる.一方で,従来の医療安全対策の効果に関するエビデンスは少なく,機会費用を見直す必要があることも指摘されている.今後は,最新の科学技術を導入することで,より効率的な転倒予防の実現が期待される.
1 0 0 0 OA 公共施設建設に伴うワークショップの成果の市民自身による検証に関する研究
- 著者
- 重永 真理子 中川 純 勝又 英明
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.72, pp.964-969, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
- 参考文献数
- 7
The purpose of this paper is to propose a tool to verify the results of workshops and to make consensus by citizens. Analyze of the citizens’ comments of the workshop of the public facility from the viewpoints of characters, images of space, rules and consciousness proved importance of variety, multi-purpose, flexibility and of citizens’ interest in participation. Based on these results, the proposal of verify-sheet is framed. The requirements of the public facility are systematized from the point of building condition and citizens’ behavior, and judgment point for citizens are added. Participation of professionals is necessary for this process.
- 著者
- 髙橋 幸子 松井 豊
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.2, pp.181-187, 2023 (Released:2023-06-25)
- 参考文献数
- 30
This study was designed to clarify the process by which a favorable work environment before a disaster affects work stressors and stress responses of local government employees recovering from a natural disaster caused by an earthquake, heavy rains, or localized landslides. The results of a cross-sectional questionnaire survey conducted with 943 employees engaged in disaster response work in two disaster-stricken local governments indicated that 8.6 % of the employees were at high risk for post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms and 6.0 % were likely to have mood and anxiety disorders. A path analysis revealed that a more favorable pre-disaster work environment resulted in more positive engagement with citizens and less negative engagement after the disaster, as well as less work-related relationship difficulties. However, experiencing work-related relationship difficulties, heavier workloads, and a lack of a sense of self-control in their work led to stronger PTSD symptoms and mood and anxiety disorders. These results suggest that favorable work environments, as a pre-disaster preparedness measure, might mitigate the work stressors associated with recovery work and thus reduce stress responses.