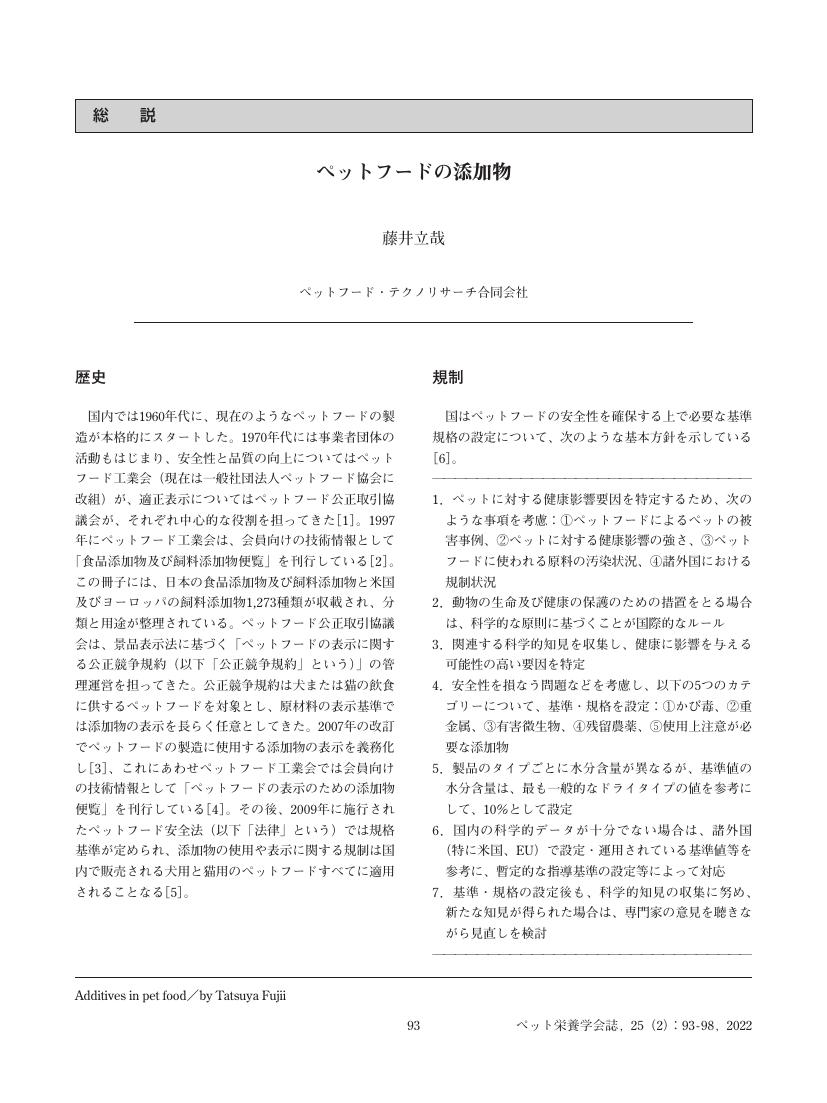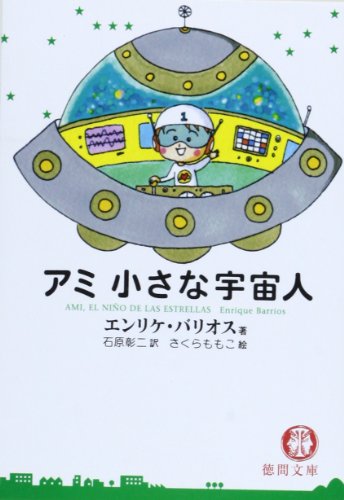1 0 0 0 OA 顔面皮脂量の部位差について
- 著者
- 高橋 きよみ 村松 宜江
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.17-24, 2002-03-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3 1
従来から顔面で皮脂の多い部分は, 額, 鼻, 顎とされTゾーンと呼ばれているが, これらと現実の化粧くずれは必ずしも一致していない。そこでわれわれはこの検証を行うため, 美容スタップを対象とした意識調査や顔面各部位の皮脂測定および皮脂分泌状態の観察を行った。その結果, 顔面を19部位に分割することで, 個人の皮脂ランクパターンが表現できることを確認した。次に化粧仕上がりおよび化粧くずれに対する乳液の影響を顔面各部位で評価したところ, その部位の皮脂ランクによりプァンデーションの付着量に差があり化粧くずれ印象も異なることを確認した。これらの結果よりわれわれは, 皮脂量の多い鼻, 眉間, 頬上内側および顎の部位を一括してIゾーンと呼ぶことがふさわしいと考えた。また, ベースメイクを行う際には, 各自の各部位の肌性に合ったモイスチャー品のタイプの選択および使用量の調整を考慮すべきであると考えた。
- 著者
- 岡 松彦
- 出版者
- Hokkaido University
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-25
北海道大学. 博士(医学)
1 0 0 0 OA 第17回国際クマ会議を終えて
- 著者
- 山﨑 晃司
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.225-230, 2006 (Released:2007-02-01)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 清水 誠 薩 秀夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.11, pp.555-563, 2004-11-20 (Released:2017-10-10)
- 参考文献数
- 36
食品中の栄養素や機能性成分が体内に吸収される場として小腸上皮はもっとも重要である. 小腸における吸収(物質輸送)の効率を変化させれば, 体内に入る栄養素の量をコントロールすることができる. 近年開発が急速に進んでいる特定保健用食品の中には, 腸管における栄養素吸収を制御することを主要なメカニズムとする製品も多い. 糖の消化吸収を抑え血糖値の上昇を抑制する食品, コレステロールの吸収を抑えて血清コレステロールレベルを制御する食品, 中性脂肪の消化吸収を抑えて肥満を予防しようという食品, ミネラルの腸管吸収を促進する食品など, 腸管における栄養素の消化吸収を制御することは, 生活習慣病の予防のための簡単でかつ実効性の高い戦略と認識され, 利用されている. また, 腸管上皮は食品成分をはじめとする腸管内容物と直接接触する組織であり, 食品成分の影響を受けやすい組織でもあると推定される. 物質の吸収のみならず, 食品成分が持つさまざまな情報を受容し, それに応答する組織としても腸管上皮は興味深い.
1 0 0 0 OA 論文)「美意識」についての研究 -「美道論」受講における学生の美意識変化-
- 著者
- 富田 知子 神山 資将 及川 麻衣子 木村 康一 永松 俊哉
- 出版者
- 学校法人 山野学苑 山野美容芸術短期大学
- 雑誌
- 山野研究紀要 (ISSN:09196323)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.11-18, 2022 (Released:2023-03-31)
美意識とは、「美」に対する感覚や判断力を意味するが、その概念は地域や風土、あるいは文化や歴史などによって、様相に違いがあると言われている。1)これまで富田らは日本での美容に関する「美意識」のあり方について調査を行い、年齢や立場によってその捉え方が違うことを示してきた。まず日常生活の中で自身の思う美意識と実生活の一致について、学生と高齢者を比較した場合、高齢者の「自身が思う美意識」と「実生活」との一致が強く示唆された。2)次に理美容師の「美意識」についての検討では、年代によってとらえ方に違いがみられた。このことから、教育や経験によって「美意識」を獲得していくことが推測できる。今回、山野美容芸術短期大学の美容教育の核となる授業「美道論」に注目し、その受講前後での「美意識」の捉え方を比較検討した。
1 0 0 0 開講十周年記念誌 : 新しいスポーツ文化の創造
- 著者
- 鹿屋体育大学開講十周年記念事業特別委員会編
- 出版者
- 鹿屋体育大学
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 IR 埋蔵文化財発掘調査機関における熱中症予防対策実施状況
- 著者
- 井奈波 良一 黒川 淳一 井上 真人
- 出版者
- 一般社団法人日本職業・災害医学会
- 雑誌
- 日本職業・災害医学会会誌 = Japanese journal of occupational medicine and traumatology (ISSN:13452592)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.225-231, 2013-07-01
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 話題 遺跡発掘現場の労働負担--夏期の熱中症対策
- 著者
- 井奈波 良一
- 出版者
- 労働科学研究所出版部
- 雑誌
- 労働の科学 (ISSN:00357774)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.10, pp.626-629, 2006-10
- 著者
- 杉山 富士雄
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文教大学国際学部紀要 = Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University (ISSN:09173072)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.39-52, 1999-10-01
In South-East Asia, one can see the phenomena at work with the Japanese company's investments accompanying a technological transfer to local workers and managers. Why does a Japanese company invest in this area? How does a Japanese company's manager recruit his staffs? How does he educate and train a lot of workers in the time of his factory beginning to operate? To investigate these problems, I went to South-East Asian countries and had an interview with managing-directors of a Japanese company.\n 1980年代後半からの急速な円高を契機として、日本企業は生産拠点を東南アジアに移転し、グローバルな経営展開で、生産技術及び日本的な生産管理方式を現地に定着させる努力をしてきた。しかし、日本で開発された技術や生産方式を東南アジアに移転するためには、これまで様々な阻害要因に直面しなければならなかった。そして今後は、現地の経済成長にともない新たなボトル・ネックに直面することが予想される。そのような中で、より一層現地サイドの希望するような技術移転を進めるためには、現地社会との共生をめざした経営の現地化・ローカライゼーションがこれまで以上に必要とされる。 そこで、日本企業が何故当該地域に進出したのか、現地でどのように人材を募集し、どのような方法で育成しているのか、また技術移転をどのように開始し、どのくらいのレベルまで推進してきたのか、企業内で生産管理および品質管理を行うために、どのような訓練および人材育成をしているのか、経営の現地化をどのように実施しているか、現在どのような阻害要因に直面して技術移転が進まなくなっているのか、今後技術移転を進めるうえでの課題は何か、というような問題点を考察するために、東南アジアに生産拠点を持ち、ほとんどの製品をシンガポール経由で世界市場に輸出するT社の事例研究を行った。 T社は、マレーシアのマラッカやインドネシアのバタム島に工場を持ち、シンガポールのオフィスを資材調達の拠点とするパソコン周辺機器メーカーである。それは、現在の東南アジアの経済成長を支える輸出志向型産業の典型である。T社の個別事例研究を取り上げることで、アジアに進出する日本の多国籍企業に対する、現地政府の外資優遇措置やインフラ整備策、親会社のアジア経営戦略、さらには日本的経営の現地での定着可能性などを特徴的に解明する糸口になると思われる。 筆者は、1999年3月にシンガポール、マラッカ、バタムの現地調査に赴き、3か国それぞれのT社現地法人社長にインタビューを行った。以下の内容は、それを基に筆者が論文として体裁を整えたものである。なお、本研究は、日本私立学校振興・共済事業団の学術振興研究資金助成を受けて行われた。
1 0 0 0 OA 固体王水を用いた使用済み触媒からの白金回収に関する基礎的研究
- 著者
- 吉村 彰大 松野 泰也
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.23-29, 2019-01-01 (Released:2018-12-25)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 11 10
In this paper, a novel method for recovering platinum using molten FeCl3-KCl system as “dry aqua regia” is presented. The method consists of the dissolution of platinum by molten FeCl3-KCl system and the recovery of dissolved platinum by the solvent leaching of frozen FeCl3-KCl, using the different solubility between platinum compounds and iron compounds for the solvents. Platinum dissolution was conducted in the molten FeCl3-KCl system at 585-655 K. The maximum dissolution rate of platinum was 0.45 mol・m−2・h−1, which is fast enough compared with the hydrometallurgy process using aqua regia or electrochemical dissolution process in ionic liquid. And dissolved platinum recovered as K2(PtCl6) by the solvent leaching of frozen FeCl3-KCl using water or ethanol. This “dry aqua regia” process have a number of advantages, including low energy consumption, easy operation and low toxicity of chemicals compared with pyrometallurgy process and hydrometallurgy process, as recycling process of platinum.
- 著者
- 大野 晃治 福井 大祐
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.11-16, 2021-03-31 (Released:2021-06-11)
- 参考文献数
- 18
ゴマフアザラシ(Phoca largha),24歳齢,雌が慢性の吐出,嘔吐,食欲不振を示した。ミダゾラムとブトルファノールによる鎮静下で造影CT検査を行ったところ,食道と肝臓およびその周囲に多発する腫瘤が認められ,剖検と病理組織検査により,肝臓と膵臓への転移を伴う食道原発の扁平上皮癌(SCC)と診断した。鰭脚類の造影CT検査の報告は少なく,本症例は食道SCCの生前診断につなげるための貴重な報告である。
1 0 0 0 OA 生・死・死後の色のイメージ ―美大生への質問紙調査から―
- 著者
- 久保田 力
- 出版者
- 印度学宗教学会
- 雑誌
- 論集 = RONSHU (ISSN:09162658)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, 2011-12-31
1 0 0 0 OA ヌカカの長距離飛翔とウイルス感染症の媒介
- 著者
- 梁瀬 徹
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第63回日本衛生動物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.32, 2011 (Released:2014-12-26)
Culicoides属ヌカカ(以下、ヌカカ)によって媒介されるアカバネウイルスやアイノウイルス、チュウザンウイルスは反芻動物に感染し、流産、早産、死産、先天異常(いわゆる異常産)を起こす。我が国では、これらのアルボウイルスによる牛の異常産の流行がしばしば起こり、畜産業に多大な損耗を与えている。また、同様にヌカカによって媒介されるブルータングウイルスやシカ流行性出血熱ウイルス、牛流行熱ウイルスは世界中に広く分布し、反芻動物に急性の疾病を起こす。低緯度地域では、年間を通じて感染サイクルが維持されるため、これらのアルボウイルスは常在化していると思われる。しかし、高緯度地域ではヌカカの成虫の活動は冬期にはみられないため、ウイルスは越冬せず常に低緯度地域から保毒ヌカカが侵入することにより、アルボウイルス感染症の流行が起こると考えられている。国内で毎年行われている、未越夏の子牛を用いたアルボウイルスの侵潤状況の調査においても、各種アルボウイルスに対する抗体陽転は夏期に西日本から始まり、東に拡大することが明らかになっている。また、過去50年にわたり国内で分離されたアカバネウイルスの遺伝子解析の結果、流行年によって遺伝子型が異なることが示され、流行ごとに新たに国外からウイルスが侵入していると考えられる。下層ジェット気流が大陸から日本に流れる梅雨期に、東シナ海上でアルボウイルスの主要な媒介種のひとつと考えられるウシヌカカが捕集されていることは、保毒ヌカカの国外からの侵入の可能性を示唆している。現在、我々の研究グループでは、九州西側に設置した吸引型大型トラップによりヌカカの捕集を行い、気象解析データとの比較から、国外からの飛来の可能性の有無について調査を行っている。また、国内外で捕集されたヌカカのミトコンドリア遺伝子を解析して、飛来源の推定に利用することを試みており、現在までに得られたこれらの知見を紹介する。
1 0 0 0 OA ペットフードの添加物
- 著者
- 藤井 立哉
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.93-98, 2022-10-10 (Released:2022-10-31)
- 参考文献数
- 31
- 著者
- 高森 暁子
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 支部統合号 (ISSN:18837115)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.473-488, 2011-01-20 (Released:2017-06-16)
1 0 0 0 概念辞書から自動構築した概念階層に基づく画像分類
- 著者
- 山崎 禎晃 伊東 聖矢 大原 剛三
- 雑誌
- 第29回画像センシングシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- 2023-05-16
1 0 0 0 OA <論文>『かぶき・をどり・女形』 : 所作事源流考
- 著者
- 増子 博調
- 出版者
- 山野美容芸術短期大学
- 雑誌
- 山野研究紀要 (ISSN:09196323)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.27-38, 1998-03-25
歌舞伎狂言のなかで,舞踊によって構成される演目(だしもの)を「所作事」という。所作事成立の当初はもっぱら女形のレパートリーであったが,後に(宝暦以後)立役も舞踊劇を演じるようになる。所作事の原形は阿国以来の歌舞伎踊にあり,はじめは容色を売りものにする女たちによるエンターテイメントに過ぎなかった。幕府の相次ぐ禁止令で女かぶき(若衆かぶき)から野郎かぶきに移った歌舞伎踊は,女性の役がらを演じる女形に引継がれ,従来のように性の魅力で観客を集める代りに,所作事としての演技力-芸の力で人気を獲ちとる方向に進むのである。当時ようやく劇芸術の体裁を整えた元禄かぶきにおいて,所作事は「狂言の花」と謳われ,幾多の名手が現われて歌舞伎劇の中核を形成する華麗な舞踊劇に成長して行く。所作事の声価をこのように高めた女形の役者たちは,役がらの純粋性を保つために「女」に徹する生活と心構えを崩さず,かつての女かぶきを上回る「女の色気」を漂わせて観客を悩殺したのである。彼らのこうした努力によって所作事の振りに盛りこまれた工夫の跡を,『舞曲扇林』等の歌舞伎資料を手がかりにして,紙幅の許す範囲で模索し,検証した。
1 0 0 0 アミ小さな宇宙人
- 著者
- エンリケ・バリオス著 石原彰二訳 さくらももこ絵
- 出版者
- 徳間書店
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 OA Zebrafish imaging reveals hidden oncogenic–normal cell communication during primary tumorigenesis
- 著者
- Yukinari Haraoka Mai Miyake Tohru Ishitani
- 出版者
- Japan Society for Cell Biology
- 雑誌
- Cell Structure and Function (ISSN:03867196)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.113-121, 2023 (Released:2023-06-16)
- 参考文献数
- 61
Oncogenic mutations drive tumorigenesis, and single cells with oncogenic mutations act as the tumor seeds that gradually evolve into fully transformed tumors. However, oncogenic cell behavior and communication with neighboring cells during primary tumorigenesis remain poorly understood. We used the zebrafish, a small vertebrate model suitable for in vivo cell biology, to address these issues. We describe the cooperative and competitive communication between oncogenic cells and neighboring cells, as revealed by our recent zebrafish imaging studies. Newly generated oncogenic cells are actively eliminated by neighboring cells in healthy epithelia, whereas oncogenic cells cooperate with their neighbors to prime tumorigenesis in unhealthy epithelia via additional mutations or inflammation. In addition, we discuss the potential of zebrafish in vivo imaging to determine the initial steps of human tumorigenesis.Key words: zebrafish, imaging, cell-cell communication, cell competition, EDAC, senescence, primary tumorigenesis
- 著者
- 菅原 麻衣子 髙橋 儀平 野口 祐子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.799, pp.1688-1698, 2022-09-01 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 6
According to the enforcement of the Discrimination Prohibition Act in 2016 and the amendments to the Barrier-Free Act between 2018 and 2020 in stages, the improvement of physical accessibility in cities and the promotion of social participation of people with disabilities have been expected in Japan. However, children with disabilities and their parents still often face social obstacles and the details are not clear. Therefore, this paper reveals the features of physical/attitudinal obstacles in cities and proposes methods of accessibility improvement through the analysis of a questionnaire to all the parents of three special schools in the municipality of X.