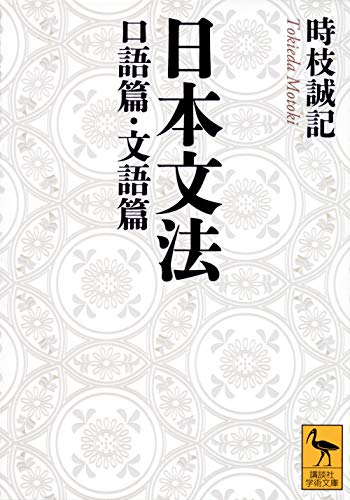1 0 0 0 OA ぺた語義:中高生情報学研究コンテストの意義と第4回の審査の様子
1 0 0 0 OA 富士山の登山者数の上限設定に対する登山者の意向
- 著者
- 山本 清龍
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集 Vol.30(第30回環境情報科学学術研究論文発表会)
- 巻号頁・発行日
- pp.73-78, 2016 (Released:2016-11-28)
- 参考文献数
- 19
本研究では,登山者数の上限設定に対する検討が行われている富士山を事例として取り上げる。研究目的は,①登山者の属性,登山特性を把握した上で,登山者数の上限設定に対する意向を明らかにすること,②登山者の属性,登山特性,登山者数の上限設定に対する意向の関係性から,登山者数の上限設定を検討する際の論点を整理し考察すること,の2点である。その結果,富士登山者の属性は,年齢が20~40代で77%を占め,登山目的では御来光を見ることが72%,頂上まで登ることが71%で最も多かった。また,登山者数の増加が自然と文化に悪影響を及ぼすという意識は登山者数の上限設定の賛否に関係していた。
- 著者
- Masatoshi Iwamura Satoru Ide Kenya Sato Akihisa Kakuta Soichiro Tatsuo Atsushi Nozaki Tetsuya Wakayama Tatsuya Ueno Rie Haga Misako Kakizaki Yoko Yokoyama Ryoichi Yamauchi Fumiyasu Tsushima Koichi Shibutani Masahiko Tomiyama Shingo Kakeda
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2022-0112, (Released:2023-03-16)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4
Purpose: Brain MRI with high spatial resolution allows for a more detailed delineation of multiple sclerosis (MS) lesions. The recently developed deep learning-based reconstruction (DLR) technique enables image denoising with sharp edges and reduced artifacts, which improves the image quality of thin-slice 2D MRI. We, therefore, assessed the diagnostic value of 1 mm-slice-thickness 2D T2-weighted imaging (T2WI) with DLR (1 mm T2WI with DLR) compared with conventional MRI for identifying MS lesions.Methods: Conventional MRI (5 mm T2WI, 2D and 3D fluid-attenuated inversion recovery) and 1 mm T2WI with DLR (imaging time: 7 minutes) were performed in 42 MS patients. For lesion detection, two neuroradiologists counted the MS lesions in two reading sessions (conventional MRI interpretation with 5 mm T2WI and MRI interpretations with 1 mm T2WI with DLR). The numbers of lesions per region category (cerebral hemisphere, basal ganglia, brain stem, cerebellar hemisphere) were then compared between the two reading sessions.Results: For the detection of MS lesions by 2 neuroradiologists, the total number of detected MS lesions was significantly higher for MRI interpretation with 1 mm T2WI with DLR than for conventional MRI interpretation with 5 mm T2WI (765 lesions vs. 870 lesions at radiologist A, < 0.05). In particular, of the 33 lesions in the brain stem, radiologist A detected 21 (63.6%) additional lesions by 1 mm T2WI with DLR.Conclusion: Using the DLR technique, whole-brain 1 mm T2WI can be performed in about 7 minutes, which is feasible for routine clinical practice. MRI with 1 mm T2WI with DLR enabled increased MS lesion detection, particularly in the brain stem.
- 著者
- Mami Ishikuro Taku Obara Keiko Murakami Fumihiko Ueno Aoi Noda Masahiro Kikuya Junichi Sugawara Hirohito Metoki Shinichi Kuriyama
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.127-135, 2023-03-05 (Released:2023-03-05)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 5
Background: The present study analyzed the relation of disaster exposure prior to pregnancy with maternal characteristics and obstetric outcomes.Methods: The participants were 13,148 pregnant women recruited from 2013 to 2017. The women were classified into three groups by the severity of housing damage caused by the Great East Japan Earthquake of 2011: group A, house was not destroyed/did not live in the disaster area; group B, half/part of the house was destroyed; and group C, house was totally/mostly destroyed. Maternal characteristics, hypertensive disorders of pregnancy (HDP), gestational diabetes mellitus (GDM), and gestational weeks were obtained using questionnaires and medical records. Multiple logistic regression analyses were performed to investigate the relation between disaster exposure and maternal characteristics, HDP, and GDM. A structural equation model was applied to investigate the relation of disaster exposure with HDP and gestational weeks.Results: The homes of about 11% of the women were totally/mostly destroyed. For groups B and C compared with those in group A, the adjusted ORs for HDP were 1.04 and 1.26 (P for trend = 0.01), and for GDM were 0.89 and 1.14 (P for trend = 0.9), respectively. Pre-pregnancy body mass index (BMI) mediated 23.2% of the relation between disaster exposure and HDP. Disaster exposure was associated with gestational weeks.Conclusion: Disaster exposure at least 2.5 years before pregnancy was found to be associated with maternal characteristics and the prevalence of HDP. Pre-pregnancy BMI mediated the relation between disaster exposure and the prevalence of HDP, and gestational weeks were reduced through HDP.
1 0 0 0 OA 偽性血小板減少症を呈した母子例
- 著者
- 大野 恭太 平井 利可子 長谷川 和範 高橋 利和 大橋 一 山本 欣宏 橋本 泰樹 松森 良信 筒泉 正春 大石 哲也 辻本 大治 志村 利之
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.6, pp.1091-1093, 1999-06-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
29歳の初回妊娠の女性が検診にて血小板数の異常低値を発見されEDTA (ethylene diamine tetraacetic acid)依存性偽性血小板減少症と判明し女児を出産した.この出生女児においても出生直後には母親と同様のEDTA依存性の偽性血小板減少症が認められたが1年8カ月後には消失していた.本例における母子発生の機序として抗血小板抗体の経胎盤性移行を推定して.
1 0 0 0 OA 人生を何度もループしたらパンデミックは抑えられるか?
- 著者
- 瀬名 秀明 浅田 稔
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 年次大会 予稿集 第12回 年次大会 (ISSN:27586480)
- 巻号頁・発行日
- pp.9, 2022 (Released:2023-03-20)
- 著者
- 鈴木 優作
- 出版者
- 「夢野久作と杉山3代研究会」事務局 ; 2013-
- 雑誌
- 民ヲ親ニス : 「夢野久作と杉山3代研究会」会報
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.207-218, 2016
1 0 0 0 OA 木材の3次元的深絞り加工(第1報) 半固定板目材の開発と単板からのスピーカーコーン成形
- 著者
- 中村 晋平 二村 伸一 前野 和也 葭谷 耕三 棚橋 光彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本木材学会
- 雑誌
- 木材学会誌 (ISSN:00214795)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.178-185, 2011-05-25 (Released:2011-05-28)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
木材の3次元成形技術は国産針葉樹材の利用拡大および,プラスチック代替資源としての木材利用に大きく寄与できる可能性を持つ技術の一つである。しかし,これまでに原料として用いられて来た半固定材はR方向に圧縮を加えた柾目材のみであり,木目の美しさ等を最大限に生かすことが出来なかった。本研究では,2段階の圧縮工程を経ることにより陥入を生じることなくT方向へ木材を圧縮することを実現し,湿潤条件下において100%程度の伸び率を有する板目材を得ることに成功した。また,まさ目材および板目材の半固定材を成形し,これらを原料として木材単板からのスピーカーコーンの成形を試みた。0.4 mm厚および0.5 mm厚の柾目材を用いた場合80%程度の成形成功率を示し,板目材を用いた場合でも50%程度の成功率を示した。音圧周波数特性の測定の結果,これらが市販ウッドコーンに匹敵する音響特性を有することが示された。
1 0 0 0 OA フランス革命における平原派指導者 : カンボンの場合
- 著者
- 小林 良彰 Yoshiaki Kobayashi
- 出版者
- 同志社大学商学会
- 雑誌
- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5-6, pp.171-192, 1979-03-15
研究
1 0 0 0 自由選挙の原則を理論的に再構成するための棄権の自由の再定義
1 0 0 0 OA 須川亜紀子『2.5次元文化論 舞台・キャラクター・ファンダム』(青弓社,2021年)
- 著者
- 臼井 直也
- 出版者
- 日本アニメーション学会
- 雑誌
- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.73-76, 2022-03-31 (Released:2023-02-01)
1 0 0 0 IR 看護師の裁量権拡大に対する訪問看護利用者の家族が抱く認識
- 著者
- 大釜 信政 中筋 直哉
- 出版者
- ヒューマンケア研究学会
- 雑誌
- ヒューマンケア研究学会誌 (ISSN:21872813)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.1-10, 2014
本研究は、在宅医療現場における看護師の裁量権拡大について、訪問看護事業所サービス利用者の家族認識を明らかにすることを目的とした。 455 名の家族に対して質問票を配布し、300 名から有効回答を得た。その後、質問票に回答した家族の中から5 名を抽出し、半構成的面接調査を実施した。 この調査結果から、看護師が行う診療に対する家族の認識としては、条件付きでこれを容認できる意向や、また、この理由等が明らかとなった。そして、利用者が置かれる診療環境、家族の性別、世代的特徴といった要因に大きく左右されることのない、医療サービスに対する普遍的な価値観や経験的見地に基づきながら、看護師が行う診療に対する認識へと繋がっている旨が示唆された。
- 著者
- 石崎 久義 野末 道彦 Ilmari Pyykko
- 出版者
- Japan Society for Equilibrium Research
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.255-262, 1991 (Released:2009-10-13)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
The postural control system is considered to be comprised of vestibular, visual and proprioceptive endo-organs. When a person stands on a moving platform, changes of the center of gravity are measured and analyzed as displacements of vertical force on the platform constructed on the strain gauge principle. The vestibular endo-organ perceives the change of head movement and responds to velocity and acceleration of head movement. Also the visual system detects a moving target and responds to velocity. The proprioceptive system responds to changes of displacement of the center of gravity and the distention of the muscle spindles of the calf muscles. Postural control was studied in 48 healthy volunteers and 18 very old subjects with posturography and 20, 40, 60, 80, 100 Hz vibration to the calf muscles, which send misleading signals to the central nervous system. The purpose of this investigation was to determine the kind of postural testing to be used in healthy volunteers and very old persons. The postural control system was analzsed with cumulative recordings of position, velocity and acceleration. Postural control was amazingly stable in healthy subjects. However, variance of velocity and acceleration were greater in very old persons with and without vibration. Postural instability in the elderly was interpreted as a deterioration of many sensory organs : visual, vestibular and proprioceptive endo-organs.Vestibular endo-organs are well known to be a major part of the control system at times of sudden perturbation, and reciprocal sensory systems are well constituted to keep postural control. It is impossible to explore further which one of these parameters is primarily responsible for postural control and to what degree because of good correlation between velocity and acceleration values. At least in the vestibular system, the acceleration parameter has a major function in posture control.
1 0 0 0 日本文法 : 口語篇・文語篇
- 著者
- 下楠 昌哉 シモクス マサヤ Masaya SHIMOKUSU
- 雑誌
- 静岡文化芸術大学研究紀要 = Shizuoka University of Art and Culture bulletin
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.23-31, 2003-03-31
本論では、ブラム・ストーカー(1847-1912)の初期の小説作品である『蛇峠』(1890)、『ドラキュラ』(1897)、『海の神秘』(1902)における風景描写と、登場人物たちが利用する交通機関との関係性を扱う。鉄道の登場とその速度、および一九世紀半ばのイギリス本土における鉄道網の確立と旅行の大衆化は、ヴィクトリア時代の人々の視覚に重大な変容をもたらし、風景を見る者から隔絶した次々と移り変わる「パノラマ」として捉える感覚を、人々に遍く実装させるに至った。ストーカーの三作品はどれも旅行者を主人公としており、それらの作品における風景描写は、風景とそれをまなさす者との間の断絶と、その断絶を生み出した列車の速度の影響をはっきりと表象している。テクノロジーの発展と人間の知覚の変容との関係性を記録したメディアとして、ストーカーの小説を読み込んでゆくこと。それが本論で試みられているプラクシスである。
- 著者
- 牛垣雄矢
- 出版者
- 東京学芸大学学術情報委員会
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. II (ISSN:18804322)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.49-64, 2015-01-30
1 0 0 0 「意識の場」理論と心理臨床の実践的研究
- 著者
- 大野 暢亮
- 出版者
- 社団法人 可視化情報学会
- 雑誌
- 可視化情報学会誌 (ISSN:09164731)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.152, pp.3-7, 2019 (Released:2019-04-26)
- 参考文献数
- 13
没入型のバーチャルリアリティ装置であるCAVE装置で大規模なデータの可視化を実現した.興味領域の抽出と自動詳細度設定機能をVFIVEと呼ばれるCAVE装置用の対話的可視化ソフトウェアに実装した.興味領域の選択は,CAVE装置の中で対話的かつ直感的に行うことができる.この自動詳細度設定機能は,等値面表示などのスカラーデータの可視化手法では,興味領域の大きさにかかわらず常に一定の解像度のデータをもとに可視化を行うことを可能にする.流線表示などのベクトルデータの可視化手法では,興味領域の大きさに応じて流線の解像度を調節する.本機能を用いて大規模なデータを実際に可視化することで,大規模データの対話的な可視化が可能なことを確認した.
1 0 0 0 OA ゾラン・ディミッチ来日講演 : カタストロフィと人間性 : 若さについて
- 著者
- ディミッチ ゾラン
- 出版者
- 首都大学東京人文科学研究科
- 雑誌
- 人文学報. フランス文学 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- vol.481, pp.105-118, 2013-03-25
1 0 0 0 OA SuperDARN HFレーザーによる高緯度電離圏Pc3-4脈動現象に関する研究
- 著者
- 新海 雄一 シンカイ ユウイチ Yuichi SHINKAI
- 出版者
- 総合研究大学院大学
- 巻号頁・発行日
- 2004-03-24
地球磁気圏では様々な電磁流体波が存在する。この中で、周期が10秒~150秒(6.6mHz~100mHz)の脈動はPc3-4地磁気脈動に分類され、昼側の磁気圏および地上で頻繁に観測される現象である。頻繁に観測されるこの脈動を本論文では古典的Pc3-4脈動と呼ぶ。古典的Pc3-4脈動は地球磁気圏前面のBowshock上流のイオンサイクロトロン不安定性によって発生し、それが磁気圏シース領域を経て、地球磁気圏内に伝播してきていると考えられている。しかし、磁気圏シース領域内でのPc3-4脈動の特性はあまり明らかになっていない。また、地上の磁力計や電離圏の観測から、Pc3-4脈動の強度が磁気圏シース領域とつながっていると考えられる高緯度カスプ域で最大となることが報告されているが、その伝播機構についてもあまり明らかにされていない。本研究では、磁気圏シース領域と電離圏カスプ域を含む高緯度電離圏でのPc3-4脈動を同時に観測し、その現象の特性を詳しく解析・研究することにより、Pc3-4脈動の発生・伝播機構を明らかにすることを目的としている。<br /> この目的の為に、南北両極域の広域電離圏を観測するSuperDARN HFレーダーと磁気圏シース領域を観測するGEOTAIL衛星との同時特別観測を企画・実施した。この特別観測では、SuperDARN HFレーダーはPc3-4脈動を検出するために特定のビームのみを高時間分解能モードで観測した。特別観測は2002年1月から2003年3月までの間、GEOTAIL衛星がSuperDARN HFレーダーの視野下を通過する軌道に合わせて7回実施した。また、2003年からは、CUTLASSレーダーではステレオモードを用い、グローバルスキャン観測も同時に実施している。その結果、2002年2月12日と2003年2月17日に明瞭なPc3-4脈動を観測することができ、その詳細な解析・研究を行った。<br /> 2002年2月12日の観測では、これまでのHFレーダー観測では報告されていないPc3-4脈動現象がCUTLASS Iceland Eastレーダーで観測された。この脈動の周波数は16.4mHz~19.7mHz(約50秒~60秒)であり、波数は5~9と小さかった。波数が小さい脈動は地上でも同様な地磁気脈動が観測されることが知られている。しかし、地上に存在する地磁気観測点では同じ周期の磁場変動は観測されなかった。また、エコーパワーがドップラー速度と同様に周期的に変動し、相互の位相差が90゜であった。この脈動現象に、過去の研究でPc3-4脈動の発生・伝播機構であると考えられている磁力線共鳴を適用した場合には、本観測で得られている脈動の特徴を十分に説明することはできなかった。そのため、エコーパワーが周期的な変動をしていることと、1keV以下の電子のフラックスがエコー領域内で増加したことから、本観測で得られた電離圏電場脈動は、Pc3-4脈動によってmodulateされた電子フラックスの振込みによって励起された電離圏電場の変動であると考えた。その結果、地上磁場との相関や、エコーパワーとドップラー速度の位相差、および脈動の伝播方向について説明することができた。このため、観測された電離圏電場脈動は、古典的なPc3-4脈動ではなく、電子の振込みによって発生した電場変動であると結論した。<br /> 2003年2月17日に行われた観測では、より明瞭なエコーを得るために、CUTLASS HFレーダーの視野内にあるEISCATヒーターによる電離圏加熱実験も合わせて行った。その結果、地磁気の南北方向を視野とするCUTLASS Finlandレーダーにおいては周波数が13.1mHz~16.4mHz(約60秒~75秒)の明瞭なPc3-4脈動が観測された。一方、地磁気の東西方向を視野とするCUTLASS Iceland Eastレーダーでは、同じ加熱領域から周波数が~4.7mHz(約212秒)のPc5脈動が同時に観測された。この特性は、Pc3-4脈動は南北方向に偏った振動を、Pc5脈動は東西方向に偏った振動をしていることを示唆している。このPc3-4脈動は波数が50~100と大きく、この電離圏脈動に対応する地磁気脈動は地上の地磁気観測点で観測されていなかった。一方、Pc5脈動は波数が~10であり、多くの地磁気観測点で観測されていた。また、この二つの脈動の開始時刻にはずれがあり、異なる発生機構による脈動が同一磁力線上に存在していたことを示唆している。このPc3-4脈動の発生機構は、脈動の特性がGiant Pulsation(Pg)とよく似ていることから、pgと同じドリフト共鳴が候補にあげられる。この脈動は、位相の空間的変動が、ある時間を境に、位相遅れが低緯度側方向から高緯度側方向へと変化が逆転する特徴を持っていた。この位相変化の特性に関しては、同時に観測されたPc5脈動の位相変化から、プラズマ圏境界付近における急激なプラズマ密度の増加によるAlfven速度の減少によって説明できる。<br /> 以上のことから、本研究によって観測された2例の高緯度電離圏電場Pc3-4脈動は、これまでに地上や衛星で多くの観測・研究が行われてきている発生頻度の高い古典的なPc3-4脈動とは異なった特徴を持つ別なタイプの脈動であることが、電離圏でのHFレーダーの観測によって初めて明らかになった。<br /> 以下、本論文の構成について述べる。論文は5章から構成されている。第1章では、地球磁気圏における脈動現象、および、これまでのPc3-4脈動に関する研究結果について概説し、本論文の目的と意義を述べた。第2章では、本研究に使用した観測機器について述べた。本論文で使用している極域電離圏の電場データは、CUTLASSレーダー、SENSU Syowa Eastレーダー、Kerguelenレーダーによって観測されたものである。さらに、宇宙空間でのデータとしてGEOTAIL衛星を使用し、地上磁場データとしてIMAGE磁場観測チェーン、SAMNET磁場観測チェーン、Iceland Tjornes観測点、Jan Mayen観測点、南極Davis基地観測点を使用した。第3章では、観測の詳細と得られたデータの解析結果、および、観測された脈動現象の特徴について述べた。第4章では、本観測で得られたPc3-4脈動の考察を行った。第5章は、本研究のまとめである。