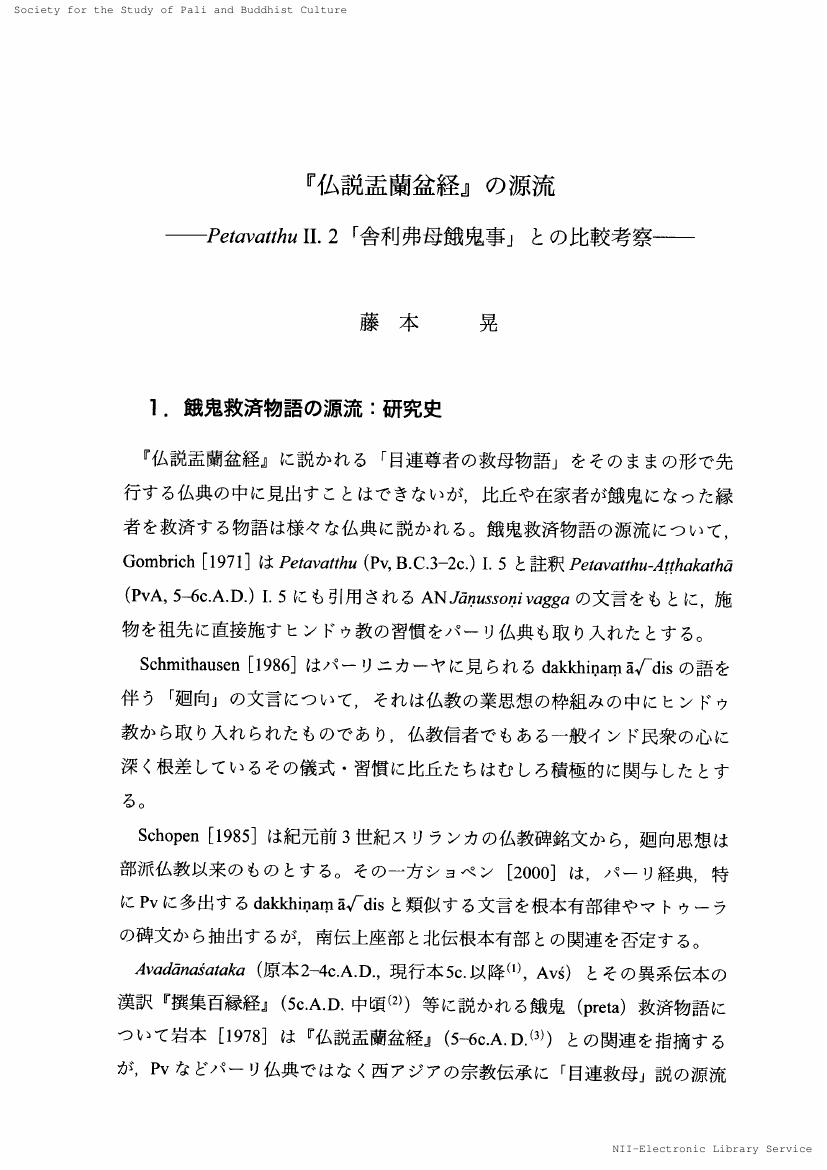38 0 0 0 OA 薩摩半島(鹿児島県本土)と徳之島・与論島(奄美群島)から得られた北限更新を含むタツウミヘビの記録
- 著者
- 是枝 伶旺 久木田 直斗 日比野 友亮 本村 浩之
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.28-34, 2023-08-28 (Released:2023-08-29)
- 著者
- 髙橋 裕子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.5-18, 2016-10-20 (Released:2017-11-10)
本稿では、2015年12月に開催されたジェンダー史学会年次大会シンポジウム「制度のなかのLGBT- 教育・結婚・軍隊」での報告を纏めるとともに、セブンシスターズの5女子大学が女子大学としての大学アイデンティティを重視しながらも、もはや「女性」という「性別」を一枚岩的に捉えることができなくなってきた現状を紹介する。さらに、とりわけ誰に出願資格があるのかを決定する判断の背景にある、女子大学自体の大学アイデンティティの問題を考察しつつ、2014年から15年にかけて発表された新たなアドミッションポリシーを概観した。この問題は、いわば21世紀に女子大学が直面しているもう一つの「共学」論争とも言える。20世紀後半に経験した「共学」論争との違いはどこにあるのか、その点にも着目しながら、性別二元論が女子大学における入学資格というきわめて現実的な問題としてゆらぎをみせていることとともに、米国における今日の女子大学の特色をあぶり出すことを試みた。トランスジェンダーの学生や、ノンバイナリーあるいはジェンダー・ノンコンフォーミングというアイデンティティを選び取る学生が増えていることは、女子大学が、「常に女性として生活し、女性と自認している者を対象とする」高等教育機関であるとあえて明示しなければならなくなったことに反映されている。それにも拘わらず女子大学のミッションが、すなわちその必要性や存在意義がよりいっそう強く再確認されていることに注目した。女性が社会で、そして世界で、多様な分野で参画できる力と自信を、大学時代に身に付ける場として、女性がセンターに位置づく経験をする教育の必要性が、このトランスジェンダーの学生の受け入れを巡ってのディスカッションを通していっそうクリティカルに再確認されたとも言える。大学教育という実践の場において、ジェンダー的に周縁に位置するセクシュアルマイノリティの学生をめぐって、アドミッションポリシーを文書化し、具体的に「女子大学」と名乗るのかどうか、さらには「よくある質問(FAQ)」で「女性とは誰のことなのか」という質問に詳細にわたって回答し、ジェンダー的に流動的な(gender fluid) 学生に対応しているこの局面に、21世紀のアメリカにおけるセブンシスターズの女子大学が果たしている新たな先駆的役割を見て取れる。
38 0 0 0 OA 日本人正常精巣の重量およびサイズについての検討 第1報
- 著者
- 田坂 登美 平賀 聖悟 北村 真 飯田 宜志 黒川 順二 飛田 美穂 佐藤 威
- 出版者
- 社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.9, pp.1506-1510, 1986-09-20 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 8
最近, 日本人の精巣重量およびサイズ等に関して検討を行なった報告は, ほとんど見られない. 今回, われわれは, 747例の変死体剖検症例を対象として, そのうちの651例について精巣重量とサイズの検索を行なった.重量, 厚さはp<0.01で右の方が大きく, 20~49歳の平均精巣重量は左14.53±4.07g, 右15.35±4.26g, 平均サイズは左長径4.51±0.64cm, 短径3.04±0.43cm, 厚さ1.43±0.3cmで, 右長径4.53±0.61cm, 短径3.05±0.4cm, 厚さ1.55±0.33cmであった. また両側精巣とも重量, 長径, 短径で30歳代が最大との結果が得られた.
38 0 0 0 OA JCS 2022 Guideline on Perioperative Cardiovascular Assessment and Management for Non-Cardiac Surgery
- 著者
- Eiji Hiraoka Kengo Tanabe Shinichiro Izuta Tadao Kubota Shun Kohsaka Amane Kozuki Kazuhiro Satomi Hiroki Shiomi Toshiro Shinke Toshiyuki Nagai Susumu Manabe Yasuhide Mochizuki Taku Inohara Mitsuhiko Ota Tetsuma Kawaji Yutaka Kondo Yumiko Shimada Yohei Sotomi Tomofumi Takaya Atsushi Tada Tomohiko Taniguchi Kazuya Nagao Kenichi Nakazono Yukiko Nakano Kazuhiko Nakayama Yuichiro Matsuo Takashi Miyamoto Yoshinao Yazaki Kazuyuki Yahagi Takuya Yoshida Kohei Wakabayashi Hideki Ishii Minoru Ono Akihiro Kishida Takeshi Kimura Tetsuro Sakai Yoshihiro Morino on behalf of the Japanese Society Joint Working Group
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-22-0609, (Released:2023-08-10)
- 参考文献数
- 439
- 被引用文献数
- 7
38 0 0 0 OA 4. 前庭電気刺激を利用した平衡感覚インタフェース
- 著者
- 安藤 英由樹 渡邊 淳司 前田 太郎
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.837-840, 2008-06-01 (Released:2010-06-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4
38 0 0 0 OA 琉球諸島におけるクビワオオコウモリの分布の変遷
- 著者
- 中本 敦
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.267-284, 2017 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 120
- 被引用文献数
- 2
琉球諸島におけるこれまでのクビワオオコウモリの地理的分布に関する情報を整理し,分布の変遷としてまとめた.クビワオオコウモリの生息する琉球諸島は,熱帯を中心に多様化しているオオコウモリ類においては分布の北限にあたる.このような分布の辺縁部は,時に生存が困難であり,一般に分布境界があいまいな地域になることが予想される.特に飛翔能力を有するコウモリ類においては分布境界を超える島嶼間の移動が比較的簡単に生じるだろう.本研究の結果,1)クビワオオコウモリは,自然分散と局所絶滅を繰り返しており,経時的に分布範囲がかなり変化していること,2)少なくとも沖縄諸島個体群(亜種オリイオオコウモリ)の個体数と分布は,現在増加・拡大傾向にあること,3)いくつかの島の個体群(特に基準亜種エラブオオコウモリ)は,八重山諸島からの人為的な輸送に起源する可能性があることが明らかとなった.動物の分布の変遷はこれまでに予想された以上に短期間に広い範囲で起こっており,一部は過去の人為的な輸送の影響を強く受けている可能性が示唆された.今後,少なくともクビワオオコウモリの保護に関しては,現在進行中の分布変化に加え,人為的な移入などの歴史的な背景を含めて,総合的に議論していく必要がある.
38 0 0 0 OA 性染色体がXX型を呈した男子の1例
- 著者
- 森 義則 水谷 修太郎 園田 孝夫 古山 順一
- 出版者
- 社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.279-285, 1969 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 3
Recently we encountered a male bearing a XX sex chromosome constitution. The patient is a 25-year-old unmarried male. He complained of loss of sexual potency. He is 154cm in height and 50Kg in weight. No gynecomastia was noted. There were no webbed neck and no cubitus valgus. The external genitalia appeared normal in size. A small testis measuring 2×1.5×1.5cm was felt in both scrotal sacs. An exploratory laparotomy failed to reveal any female internal sexual organs. No urogenital sinus was detected. Histology of both testes showed no spermatogenesis. The basement membrane of seminiferous tubules showed hyalinization. In interstitial tissue, clusters of Leydig cells were observed.Sex chromatin was positive in cells of buccal mucosa smears. Chromosomal analysis was performed in peripheral blood, skin and testis. The majority of cells are found to contain 46 chromosomes including a pair of apparently normal XX sex chromosomes in these three tissues. It was concluded that, this patient, although phenotype is a male, has normal female karyotype.
38 0 0 0 OA 便移植
- 著者
- 山田 知輝
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.811-816, 2016 (Released:2016-06-20)
- 参考文献数
- 39
再発性のClostridium difficile感染症(CDI)に対して便移植を行い90%近い治癒率が得られたとする RCTが発表され、注目を集めている。CDIは抗菌薬使用により、正常腸内細菌叢が減少し、菌交代現象が起こり増殖したClostridium difficileが毒素を産生し腸炎を発症させる病態であり、便移植は健常者(ドナー)から得た腸内細菌叢を含む糞便を投与することで、健康状態の腸内細菌叢を復元し、これを治癒しようとするものである。現在ではその適応や、ドナーの選定・スクリーニング、便の準備や投与方法につき、定まりつつあるがまだ十分ではなく、かつ安全性の問題もある。アメリカでは「便の銀行」が設立され、事前にスクリーニングされた、若くて健康なドナーの便の貯蓄により、より多くのケースで便移植ができるような体制ができつつある。今後は安全性を高めた製剤も開発中であり、日本も含め、その使用がさらに広がる可能性がある。
- 著者
- Kenichi Komabayashi Junji Seto Shizuka Tanaka Yu Suzuki Tatsuya Ikeda Noriko Onuki Keiko Yamada Tadayuki Ahiko Hitoshi Ishikawa Katsumi Mizuta
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.413-418, 2018-11-30 (Released:2018-11-22)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 28 35
The incidence of modified measles (M-Me), characterized by milder symptoms than those of typical measles (T-Me), has been increasing in Japan. However, the outbreak dominated by M-Me cases has not been thoroughly investigated worldwide. The largest importation-related outbreak of measles with genotype D8 occurred in Yamagata Prefecture, Japan, from March to April 2017. This phenomenon was observed after Japan had achieved measles elimination in 2015. We confirmed 60 cases by detecting the genome of the measles virus (MeV). Among the cases, 38 were M-Me and 22 were T-Me. Thirty-nine (65.0%) patients were 20–39 years of age. Three out of 7 primary cases produced 50 transmissions, of which each patient caused 9–25 transmissions. These patients were 22–31 years old and were not vaccinated. Moreover, they developed T-Me and kept contact with the public during their symptomatic periods. Considering that M-Me is generally caused by vaccine failure, some individuals in Japan may have insufficient immunity for MeV. Accordingly, additional doses of measles vaccine may be necessary in preventing measles importation and endemicity among individuals aged 20–39 years. Furthermore, to accurately and promptly diagnose individuals with measles, particularly those who can be considered as primary cases, efforts must be exerted to detect all measles cases using epidemiological and genetic approaches in countries where measles elimination had been achieved.
38 0 0 0 OA 『仏説孟蘭盆経』の源流 : Petavatthu II.2「舎利弗母餓鬼事」との比較考察
- 著者
- 藤本 晃
- 出版者
- パーリ学仏教文化学会
- 雑誌
- パーリ学仏教文化学 (ISSN:09148604)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.47-54, 2003-12-20 (Released:2018-09-01)
38 0 0 0 OA H-IIロケット失敗の原因とその教訓
- 著者
- 今野 彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本高圧力技術協会
- 雑誌
- 圧力技術 (ISSN:03870154)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.335-344, 2003 (Released:2003-12-30)
- 参考文献数
- 2
H-II launch vehicle, the large Japanese launcher placing a 4000kg class satellite into GTO, failed in the two flights of No. 5 and No. 8, after the successful 29 flights from N-I to H-II. Both failures were caused by malfunction of the cryogenic engine, the second stage engine LE-5A or first stage engine LE-7, respectively. The incidents, the causes, and the corrective actions of these failures are reported in detail in this paper. The failures brought us the precious experiences and a lot of lessons and learn. Important lessons are related with small amount of products such as a launch vehicle, which happen to fail for uneven quality by handcraft. To solve this problem, it is noted that critical manufacturing process should be distinguished to control very important characteristics of products, and that all specifications on critical processes should be determined on well-grounded technical data. In development phase, the design margin of important characteristics should be assured by testing the varied nature within defined specifications. H-IIA flew successfully in its maiden flight on August 29, 2001 to put LRE (laser Ranging Experiment) into GTO precisely. The author believes that this success results from great efforts of many engineers and researchers who learned the precious lessons of H-II failures. Rocket technology will make progress to be matured by a lot of lessons and learn from failure.
- 著者
- Shotaro Hoi Masaya Ogawa Chishio Munemura Tomoaki Takata Hajime Isomoto
- 出版者
- Tottori University Medical Press
- 雑誌
- Yonago Acta Medica (ISSN:13468049)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.300-305, 2023 (Released:2023-05-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 4
Atypical anti-glomerular basement membrane (GBM) nephritis is a slowly progressive characterized by linear deposition of immunoglobulin (Ig) G in the GBM without circulating anti-GBM antibodies or lung involvement. There is no established therapy for this disease, and efficacy of the immunosuppressive treatment is questionable. A few cases of atypical anti-GBM nephritis have been reported after administration of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mRNA vaccine. Classic anti-GBM disease has also been reported after the administration of the second dose of the SARS-CoV-2 vaccine. Herein, we present the case of a SARS-CoV-2 vaccine-induced atypical anti-GBM nephritis that developed after the first dose and was unresponsive to immunosuppressive therapy. A 57-year-old Japanese woman developed edema 11 days after the first dose of the SARS-CoV-2 mRNA vaccine. She developed nephrotic-range proteinuria and microscopic hematuria. Renal biopsy revealed endocapillary proliferative glomerulonephritis with linear IgG deposition. However, electron-dense deposits were not detected on electron microscopy. The patient tested negative for circulating anti-GBM antibodies and was diagnosed with atypical anti-GBM nephritis. Although steroids and mizoribine were administered, the patient’s renal function deteriorated. In conclusion, atypical anti-GBM nephritis may have earlier onset than the classic anti-GBM disease. Given its uncertainty of effectiveness, immunosuppressive agents should be carefully used for SARS-CoV-2 mRNA vaccine-induced atypical anti-GBM nephritis.
38 0 0 0 OA 脊柱と椎骨の形態学
- 著者
- 犬塚 則久
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.239-245, 2014 (Released:2017-05-11)
- 参考文献数
- 8
The spinal column of a human body must support the weight of the upper half of the body including the head and the upper limbs, befitting to the bipedal upright posture. Vertebral bodies of the lower lumbar are larger than the upper one for this support. Since the ventral side of the spinal column has a thorax, cervical and lumbar lordoses are indispensable to bring the center of gravity close to a centroidal line. Therefore, the thickness of the inferior lumbar vertebrae are greater ventrally, and an intervertebral disk is thick, and wedge-shaped. Since the weight shifts forward and backward as to the standing and the sitting position, the angle of a pelvis must be changed, and a sacrum and lumbar vertebrae cannot be unified. The lumbar vertebrae at the time of a walk should take the rotational shear, between an upper-limb-thorax block and a lower-limb-pelvis block, since they can hardly rotate due to the dissociation of the center of the rotary axis and the actual center of the vertebral bodies. The situation results in propensity for disk herniation or compressive fractures.
- 著者
- 浅原 正和
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.387-390, 2017 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 6
日本遺伝学会用語編集委員会が新たに遺伝学用語の和訳を策定し,2017年9月に用語集を発刊した.日本遺伝学会はこれに基づいて文科省に教科書の用語変更を求めていく方針だという.今回改訂された用語には,遺伝学以外の分野で用いられる用語も含まれる.中でも,進化学や生物多様性分野における最重要用語の一つである「variation」はこれまで「変異」と訳されてきたが,これを「(1)多様性,(2)変動」と訳すように変更し,「変異」は「mutation」の訳語として用いるように変更するという.しかし,歴史を紐解けば,variationの訳語としての「変異」は遺伝学そのものが誕生する以前から使われてきた.また,「変異」という用語は多くの派生語があり,現在も哺乳類学を含む,遺伝学以外の様々な自然史分野で広く使われている.このように広い分野で継続して使われてきた「変異」という日本語の意味する対象が突然variationからmutationに変更されてしまうと,これまで蓄積されてきた日本語文献について誤読が生じかねない.以上のように,variationの訳語変更は歴史的な正当性を欠き,学術的にも混乱を招きかねず,日本語という言語の価値を保つ上で問題がある.そのため,今後もvariationの訳語として,伝統的に用いられ,現在も広く使われている「変異」という訳語を残すことが望ましいと考えられる.
38 0 0 0 OA スギ花粉米の最近の研究開発状況
- 著者
- 髙野 誠
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.82-86, 2019 (Released:2019-06-26)
- 参考文献数
- 4
We have developed the vaccine rice for cedar pollen allergy and have been trying to commercialize it since then. At first, we aimed to commercialize it as food for specified health use, but the Ministry of Health, Labour and Welfare had a different opinion. Then, we had made efforts to bring it out as the medicine by consulting with Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA). However, any pharmaceutical companies embarked on this challenging project. Now, we are trying to accumulate the evidence in clinical studies in collaboration with medical institutions. Hopefully, a new functional food category between medicine and food will be established in near future and the vaccine rice will be approved as a functional food by receiving a big boost from patients suffer from pollinosis.
38 0 0 0 OA 甲状腺超音波検査で発見される微小癌の取扱い
- 著者
- 志村 浩己
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.82-86, 2018 (Released:2018-08-24)
- 参考文献数
- 14
東日本大震災の半年後より,福島県において小児・若年者に対する甲状腺超音波検診が開始されたのに伴い,他の地域においても甲状腺に対する関心が高まっており,甲状腺超音波検査が行われる機会が増加していると考えられる。また,近年の画像診断技術の進歩に伴い,他疾患のスクリーニングや診断を目的とした頸動脈超音波検査,胸部CT,PET検査などでも甲状腺病変が指摘されることも増加している。成人において甲状腺超音波検査を実施することにより,0.5%前後に甲状腺癌が発見されうることが報告されている。これらのうち,微小癌に相当する甲状腺癌には生涯にわたり健康に影響を及ぼさない低リスク癌も多く含まれていると考えられている。従って,甲状腺検診の実施に当たっては,高頻度に発見される結節性病変の精査基準あるいは細胞診実施基準をあらかじめ定めてから行うべきであろう。甲状腺微小癌の超音波所見としては,比較的悪性所見が乏しいものから,悪性所見が揃っている一見して悪性結節と考えられるものまで多様性に富む。日本乳腺甲状腺超音波医学会では,結節の超音波所見に基づく甲状腺結節性病変の取り扱い基準を提唱しており,日本甲状腺学会の診療ガイドラインにおいてもこれが踏襲されている。この基準により,比較的低リスクの微小癌は細胞診が行われないことになり,比較的高リスクの微小癌のみが甲状腺癌として臨床的検討の俎上に載ることになる。本稿においては,微小癌の診断方針について現状の基準について議論したい。
38 0 0 0 OA バーテンダーから「バーテンダー」へ —カテゴリー内の移動とその意義—
- 著者
- 関 駿平
- 出版者
- 日本労働社会学会
- 雑誌
- 労働社会学研究 (ISSN:13457357)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.1-18, 2022 (Released:2023-04-05)
- 参考文献数
- 36
This paper aims to examine the case in which mobility within the same occupational category statistically has important implications for an individual. This paper examines this case using the occupation of the bartender as a case study. This paper focuses on bartenders who experienced mobility from “casual” bar to “authentic” bar. In this paper, the careers of 26 bartenders were investigated. This paper analyzes a selection of that data, particularly the narratives of bartenders who experienced mobility within the same category. The results revealed that mobility within the same category could sometimes have different meanings in terms of individual subjectivity. Bartenders positioned their experiences in what they called “casual” bars primarily as a motivator or a starting point for their labor to authentic bars.
38 0 0 0 OA 都市近郊林における餌付けが滑空性哺乳類に与える影響:大胆行動および捕食イベントの観察をもとに
- 著者
- 渡辺 恵 嶌本 樹 渡辺 義昭 内田 健太
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- pp.2127, (Released:2022-10-20)
- 参考文献数
- 34
近年、野生動物への餌付けは、個体の行動や生物間相互作用の変化を引き起こすなど、生態系への影響が危惧され始めた。そのため、生物多様性保全の観点から、一部の地方自治体では、餌付け行為を規制する動きが見られる。しかし、国内において餌付けが与える影響を調べた研究は、大型の哺乳類を始めとした一部の生物に限られているなど、未だ限定的である。本調査報告では、滑空性の哺乳類であるエゾモモンガへの餌付けの捕食リスクへの影響を明らかにすることを目的に、北海道網走市の餌台が設置された都市近郊林におけるルートセンサスにより、 1.餌台の利用頻度と、 2.自然由来の餌と人為由来の餌を利用する場合の行動の比較(採食中の滞在高さと一か所の滞在時間)、 3.聞き取り調査も加えてイエネコやキタキツネなどの捕食者の出現と捕食事例について調査を行った。調査の結果、エゾモモンガは餌台を頻繁に利用していた。人為由来の餌を利用する場合は、自然由来の食物を利用する場合よりも、採食中の滞在高さが有意に低く、一か所の滞在時間が有意に長かった。また、聞き取りから調査した冬に餌台周辺でイエネコによる捕食があったことがわかった。餌台を介した餌付けは、エゾモモンガの採食行動を変化させ、捕食リスクを高めることに繋がると考えられる。今後は、餌付けによる生態系への影響を評価するために、餌台のある地域とない地域での比較など、更なるモニタリングが必要だろう。
38 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科診療所でのグラム染色検査によってもたらされた抗菌薬の選択・使用の変化 : 予備的検討
- 著者
- 前田 雅子 前田 稔彦 松元 加奈 森田 邦彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.335-339, 2015 (Released:2015-12-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3
目的 : 診療時グラム染色検査の導入が抗菌薬の使用動向に影響を及ぼすかを検討することを目的とした.方法 : グラム染色導入前後での抗菌薬の種類・使用量の動向, 診療経過の動向を後方視的に調査した.結果 : 抗菌薬処方頻度 (100 人当たり) は, マクロライド系は20.9件 (2006年) から3.6件 (2012年) , 第三世代セフェム系は7.9件 (2005年) から2.4件 (2012年) に減少の一方, ペニシリン系は1.6件から3.9件に増加した. それにともなって1人当たりの抗菌薬消費額が約1/5に低下した. 小児急性副鼻腔炎患者50人当たりの抗菌薬不使用患者数は9倍に増加した一方, 治療期間中に抗菌薬2種類以上を処方された患者数は26名から9名に減少し, 治癒に要した日数は約6日間短縮された.結論 : グラム染色導入がよりよい抗菌薬使用につながる取り組みとなる可能性が示唆された. 多施設での研究的取り組みによる評価の必要性が考慮される.
- 著者
- Vytautas Kulvietis Violeta Zalgeviciene Janina Didziapetriene Ricardas Rotomskis
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.225, no.4, pp.225-234, 2011 (Released:2011-11-03)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 47 55
Nanoparticles (NP) are organic or inorganic substances, the size of which ranges from 1 to 100 nm, and they possess specific properties which are different from those of the bulk materials in the macroscopic scale. In a recent decade, NP were widely applied in biomedicine as potential probes for imaging, drug-delivery systems and regenerative medicine. However, rapid development of nanotechnologies and their applications in clinical research have raised concerns about the adverse effects of NP on human health and environment. In the present review, special attention is paid to the fetal exposure to NP during the period of pregnancy. The ability to control the beneficial effects of NP and to avoid toxicity during treatment requires comprehensive knowledge about the distribution of NP in maternal body and possible penetration through the maternal-fetal barrier that might impair the embryogenesis. The initial in vivo and ex vivo studies imply that NP are able to cross the placental barrier, but the passage to the fetus depends on the size and the surface coating of NP as well as on the experimental model. The toxicity assays indicate that NP might induce adverse physiological effects and impede embryogenesis. The molecular transport mechanisms which are responsible for the transport of nanomaterials across the placental barrier are still poorly understood, and there is a high need for further studies in order to resolve the NP distribution patterns in the organism and to control the beneficial effects of NP applications during pregnancy without impeding the embryogenesis.