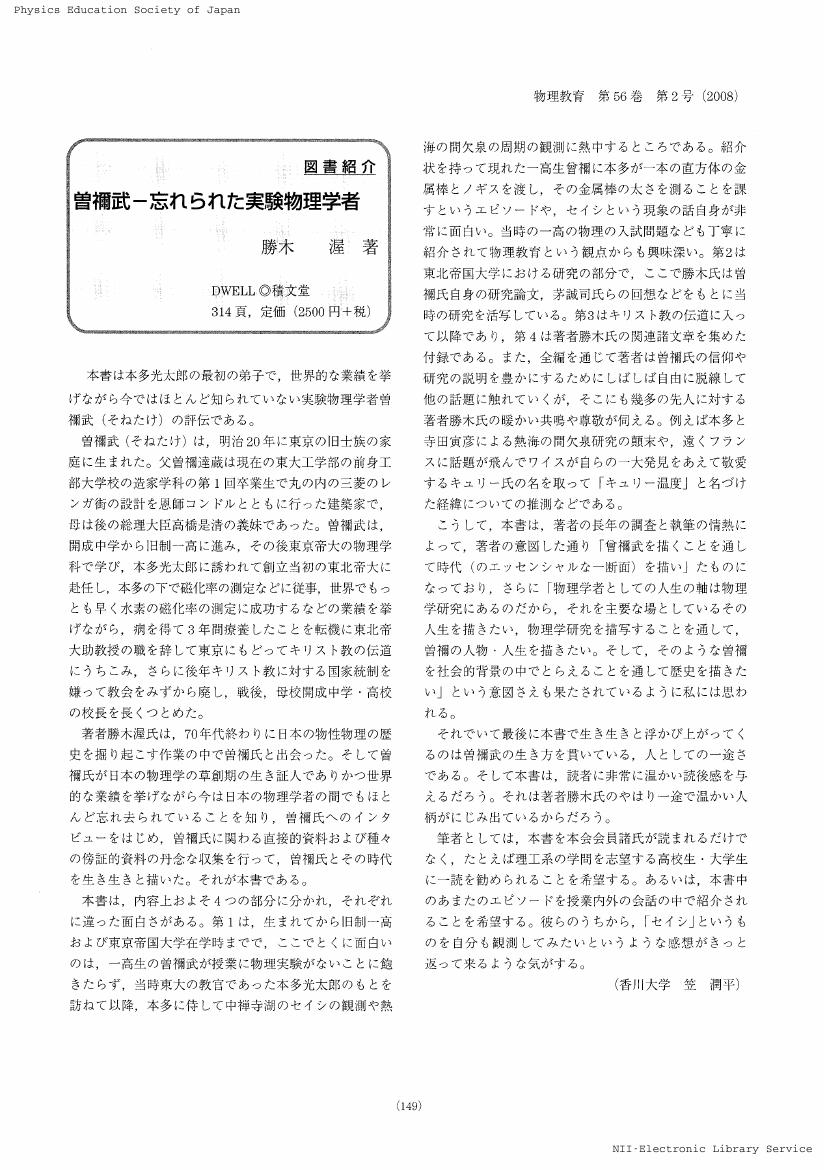1 0 0 0 IR 看護系大学職員に必要な能力開発に向けたプログラム構築と検証(第一報文献検討)
- 著者
- 飯野 矢佳代 中井 伸治
- 出版者
- 広島国際大学総合教育センター
- 雑誌
- 広島国際大学総合教育センター紀要
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.73-88,
本研究の目的は、文献レビューを通して看護教員に「求められる能力」の特徴を明らかにすることである.医学中央雑誌WEB版を用い「看護教員」「能力」に関する18件の文献を分析対象とした.結果,看護教員に求められる能力のコアカテゴリーは「教育実践能力」「看護実践能力」であり,「教育実践能力」のサブカテゴリーは, 1)指導技術2)学生理解3)コンピテンシーの発揮4)調整能力,「看護実践能力」サブカテゴリーは,1)看護過程の展開・応用2)ベッドサイドケア3)医療支援4)健康生活支援5)人間尊重6)健康環境調整7)健康問題査定能力であった. 教育実践能力,看護実践能力ともに,学生・患者家族をありのまま受け止め,根気強く支える「人間性」,どの場面でも倫理的立ち振る舞いを意識する,保健医療福祉への権利意識を持ち合わせる「倫理観」,看護実践がいい方向へ進むよう,研究成果の収集と実践への活用「自己研鑽」,看護方法の改善・看護学発展への探求「研究」が必要という結果が見い出された.
- 著者
- 田中 秀典 武方 壮一
- 雑誌
- 教育・学生支援センター紀要
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.1-6, 2021-03
- 著者
- 尾谷 悠介 嶽山 洋志 山本 聡 薬師寺 恒治 中瀬 勲
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集 (ISSN:1348592X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.1-4, 2020
新型コロナウィルスの流行に伴い、日本国内では不要不急の外出の自粛や県境をまたぐ移動の自粛など、ライフスタイルの変化が見て取れる。本研究では、このような状況下での公園が果たす役割について、主に利用実態と利用者意識から捉えることとした。その結果、新型コロナウィルスの流行の影響を避ける来園者は都市部よりも郊外の公園を選択する傾向があること、集団利用を自粛し個人で出来るレクリエーションに行動が変化していること、遊具の利用が両公園で減少していることなどがうかがえた。今後は、これまでの禁止や自粛が中心の対策から、個人で出来るレクリエーションの推進など、実施可能な活動を発信する必要がある。
- 著者
- 古川原 明子
- 出版者
- 龍谷大学法学会
- 雑誌
- 龍谷法学 (ISSN:02864258)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.569-582, 2013-10
- 著者
- Shohei Otomo Akihiko Terada Yu-You Li Kazuya Nishitoba Fumiaki Takakai Kunihiro Okano Naoyuki Miyata Shuhei Masuda
- 出版者
- Japan Society on Water Environment
- 雑誌
- Journal of Water and Environment Technology (ISSN:13482165)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.139-152, 2021 (Released:2021-06-10)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
In full-scale sewage treatment plants, long-term and high-frequency monitoring is required to mitigate nitrous oxide (N2O) emissions. In this study, the profile of the dissolved N2O concentration in a full-scale oxidation ditch reactor was investigated to determine the variation of the N2O emission factor. It was found that the concentration of dissolved N2O depended on microbial activity, which is affected by water temperature, dissolved oxygen concentration, and the dimensional relationship between the rotator and the inflow point. In the reactor, higher transcription levels of amoA mRNA and lower transcription levels of clade II type nosZ mRNA may be associated with N2O production. The emission factor for removed dissolved inorganic nitrogen presented a mean value of 0.86% and a median of 0.19%. When N2O production was promoted, gasification from the water surface was the most significant emission source, accounting for 52% of the total N2O emitted, on average. The N2O emission factor was often lower than 0.01% during stable operation; however, this factor was subject to sudden increases caused by nitrite accumulation.
1 0 0 0 OA NLP2021 の振り返りと,年次大会のこれから
- 著者
- 金山 博
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.318-320, 2021 (Released:2021-06-15)
1 0 0 0 OA 尾瀬車道建設問題を踏まえた国立公園管理運営における合意形成過程の一考察
- 著者
- 中澤 圭一 土屋 俊幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究(オンライン論文集) (ISSN:1883261X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.69-79, 2017-05-17 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 145
- 被引用文献数
- 1
In the early 1960s, a new road construction plan that was to run through the lakefront of Ozenuma—the core area of the National Park of Oze—was brought into question for its anticipated environmental impact. The Ministry of Health and Welfare, then in charge of national park administration, revised the plan to circumvent the core area; however, the construction work was terminated in 1971 by political intervention. This study identifies factors that led to the termination and examines issues that arose in the consensus building process of implementing collaborative management of the National Park. In regard to the stakeholders, two observations are drawn: 1) the importance of conducting a stakeholder analysis to identify those who should take part in the consultative process, and 2) the need to hold a clear vision of the sustainable use of natural resources in the area and to engage those who may have little say in this process. It is also worth noting the specialist who participated in the planning. His commitment to achieve the two purposes of national parks, protection and use, seems to have blinded him from seeing the regional stakeholders’ vision and desire of protecting the ‘atmosphere’ of the Oze area.
- 著者
- 古田 公男
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経情報ストラテジ- (ISSN:09175342)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.10, pp.60-63, 1998-11
グループ企業でトップクラスの好業績を維持する中京コカ・コーラボトリング。昨年3月に三菱商事から社長に就任した古田公男氏は,わずか1年半で情報化を全社に広めた。 情報技術を活用した組織のフラット化に自ら率先して取り組み,「直行直帰体制」の導入で中高年社員の自立を促す。情報化を経営の大きな柱に掲げられていますが,その目的は何ですか。
1 0 0 0 OA インターネットにみる今日のシャーマニズム : 霊性のネットワーキング
- 著者
- 塩月 亮子 佐藤 壮広
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.79-88, 2003-03-30 (Released:2018-02-07)
1 0 0 0 多重の読みを持つ宣命コーパスの構築
- 著者
- 呉 寧真 池田 幸恵 須永 哲也 小木曽 智信
- 雑誌
- じんもんこん2020論文集
- 巻号頁・発行日
- no.2020, pp.253-260, 2020-12-05
1 0 0 0 理研BRCから提供する新規植物リソースについて
理化学研究所バイオリソースセンター実験植物開発室は文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)「シロイヌナズナ/植物培養細胞・遺伝子」の中核機関として植物材料の収集・保存・提供を行っている。平成20年度は新たなリソースとして理研植物科学研究センターが開発したシロイヌナズナFOXライン種子の提供を開始した。またヒメツリガネゴケ、ポプラ、タバコの遺伝子材料の追加公開や形質転換培養細胞の公開準備を進めている。このほかデータベースの更新情報や公開を予定しているリソースの準備状況、更には2010年6月に横浜市で開催予定の21st International Conference on Arabidopsis Researchの概要について報告する予定である。
1 0 0 0 OA レキシコンの獲得における制約の役割とその性質(<小特集>「言語獲得」)
- 著者
- 今井 むつみ 針生 悦子
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.31-40, 2003-01-01 (Released:2020-09-29)
- 著者
- 小山 政子
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.15-21, 2008
財団法人日本医薬情報センター (JAPIC) 附属図書館では1997年に図書館システムを導入し, 2005年12月より所蔵情報, 新着情報などを「図書館検索メニュー」として公開しています。また, 2006年9月には, 医学・薬学関係の学会・地方会などの開催予定情報を収載した「医学・薬学関連学会開催情報検索」を追加公開しました。今回はJAPICのホームページの中から, 附属図書館が管理している上記のサイトについて, 公開にいたるまでの経緯とその内容について紹介させていただきます。医療関係者の皆様の日常業務にご活用いただければ幸いです。
1 0 0 0 神楽・東遊の新研究
- 著者
- 今井 優
- 出版者
- 武庫川女子大学
- 雑誌
- 武庫川女子大学紀要 文学部編 (ISSN:03895823)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.p13-35, 1983
1 0 0 0 埼玉県の地震災害と被害想定
- 著者
- 角田 史雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.3, 2006
1.荒川地震帯 寄居以南の荒川下流域では、流路ぞいに1649年」(慶安)、1855年(江戸)、1931年(西埼玉)、1968年(東松山)の被害地震(M;マグニチュード=7_から_6)が、ほぼ直線的に配列し、これを荒川地震帯と呼称する。この地震帯の南東延長には、東京湾北部断層と中部千葉の6つの被害地震の震央が分布する。 2.首都圏東部と同西部における被害地震の交互発生 上に述べた被害地震(浅発_から_中深発地震群)の発生深度は50_から_90kmであるが、首都圏西部の富士火山帯ぞいの被害地震(極浅発地震群)の発生深度は30km以浅である。過去400年間では、これら2つの群の被害地震が、交互に発生するケースがめだつ。 3.富士火山帯でのマグマ活動と被害地震の活動との関係 一般に、現在における地変エネルギーの主な放出様式を噴火と地震とすれば、1回あたりの地震の最大Meは、噴火のMv=5_から_6ていどにあたるエネルギーを放出するといわれる。これに基づいて、過去100年間における富士火山帯_から_首都圏での噴火・鳴動・被害地震などの時系列でまとめると、伊豆諸島で噴火の北上(最長20年で、おおよその周期が15_から_6年)→三宅島または大島での噴火の1_から_2ねんごの東関東における極浅発地震の発生→その1_から_2んえごの東関東における浅発_から_中深発地震の発生、という規則性が認められる。 4.震害には、地盤破壊をともなわない強震動震害と、ともなう液状化震害とがある。このうち前者は、被害地震の震央域と、平野の基盤面の断層・段差構造の直上に現れやすい。埼玉県では、過去に、荒川地震帯ぞいの区域、東部の中川流域(とくに清水・堀口(1981)による素荒川構造帯の活断層ゾーン)、関東山地北縁の活断層分布域などに発現した。 5.埼玉県の液状化震害 液状化は、地盤の構成物、地下水の水位レベル、揺れによる地下水圧の急上昇などの条件にしたがって発現する。過去の液状化事例は、利根川中流低地_から_中川流域でよく知られる。 6.震害予測 強震動震害は4.で述べた事例の再発を予測しておく必要がある。液状化震害は、じょうじゅつしたもの以外、神戸の震災例などから、台地区域において地下水面下にある人口地盤の液状化、河川近傍の傾斜した地下水面をもつ区域にpける、地盤の側方移動などを考慮した予測を確立する必要がある。
1 0 0 0 イベリア・インパクト論再考 : イエズス会の軍事的性格をめぐって
- 著者
- 清水 有子
- 出版者
- 校倉書房
- 雑誌
- 歴史評論 (ISSN:03868907)
- 巻号頁・発行日
- no.773, pp.78-97, 2014-09
1 0 0 0 OA 高pHにおける澱粉の糊化
- 著者
- 平島 円 奥野 美咲 高橋 亮 磯部 由香 西成 勝好
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成28年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.50, 2016 (Released:2016-08-28)
【目的】澱粉のpHを13よりも高くすると,加熱せずに糊化(アルカリ糊化)が起こることはよく知られている。しかし,こんにゃくや中華麺などの食品に含まれるアルカリ性物質の濃度はアルカリ糊化を起こすほど高くない。そこで本研究では,食品中でみられる高pHの範囲内で澱粉の糊化および澱粉糊液の粘度に及ぼすpHの影響について検討した。【方法】澱粉にはタピオカ澱粉(松谷ゆり8,松谷化学工業(株))およびコーンスターチ(コーンスターチY,三和澱粉工業(株))を用い,その濃度は3.0,4.0および20wt%とした。また,澱粉の糊化はNa塩の影響を受けることから,アルカリの影響についてのみ検討できるよう,Sørensen緩衝液を用いてNa濃度を一定とし,pHを8.8–13.0に調整した。アルカリ無添加の澱粉をコントロール(pH 6.5付近)とした。20wt%の澱粉を用いてDSC測定を,また,3.0wt%および4.0wt%の澱粉を用いて粘度測定,顕微鏡観察,透過度測定を行い,澱粉の糊化および澱粉糊液の特性について検討した。【結果】pHを8.8–12程度まで高くすると,タピオカ澱粉およびコーンスターチの糊化温度およびエンタルピーは,コントロールよりもわずかに高かった。すなわち,食品で扱われる高pHの範囲内では,いずれの澱粉も糊化は起こりにくくなるとわかった。その影響を受けて,pHを11程度まで高くしたタピオカ澱粉およびコーンスターチ糊液の粘度はコントロールよりも低かった。しかし,pHを12よりも高くすると,糊化温度とエンタルピーはコントロールよりも低く,常温で澱粉粒子内の結晶構造が壊れるとわかった。したがって,pHを12よりも高くすると,澱粉の糊化は起こりやすくなり,澱粉粒子からのアミロースやアミロペクチンの溶出量が多く,糊液の粘度と透過度は高くなるとわかった。 以上の結果より,食品にみられるアルカリ性の程度(pH12以下)では澱粉の糊化が起こりにくくなるとわかった。
- 著者
- 岩﨑 啓子 出口 雄也 長岡(浜野) 恵 長岡 寛明 野村 秀一
- 出版者
- 日本食品化学学会
- 雑誌
- 日本食品化学学会誌 (ISSN:13412094)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.65-68, 2010-04-14 (Released:2017-01-27)
- 参考文献数
- 8
A high performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of malic acid, acetic acid, citric acid, amygdalin, benzyl alcohol, benzaldehyde, and benzoic acid in pickled Japanese apricots (Umeboshi) was developed. TSKgel ODS-100s was used as the separation column, and the mixture of 0.1% phosphoric acid and methanol was used as mobile phase. Detection wavelength was at 210nm. All compounds were eluted within 30 minutes. In three commercial pickled Japanese apricots, 4μg/g -46mg/g of malic acid, acetic acid, citric acid and benzyl alcohol, benzaldehyde were detected. In the pickled Japanese apricots, amygdalin was detected.
- 著者
- 笠 潤平
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.149, 2008-06-10 (Released:2017-02-10)
1 0 0 0 OA 北海道方言の語誌的研究から : 「アズマシクナイ」ということば
- 著者
- 夏井 邦男
- 出版者
- 北海道教育大学
- 雑誌
- 語学文学 (ISSN:02868962)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.45-53, 2002-03