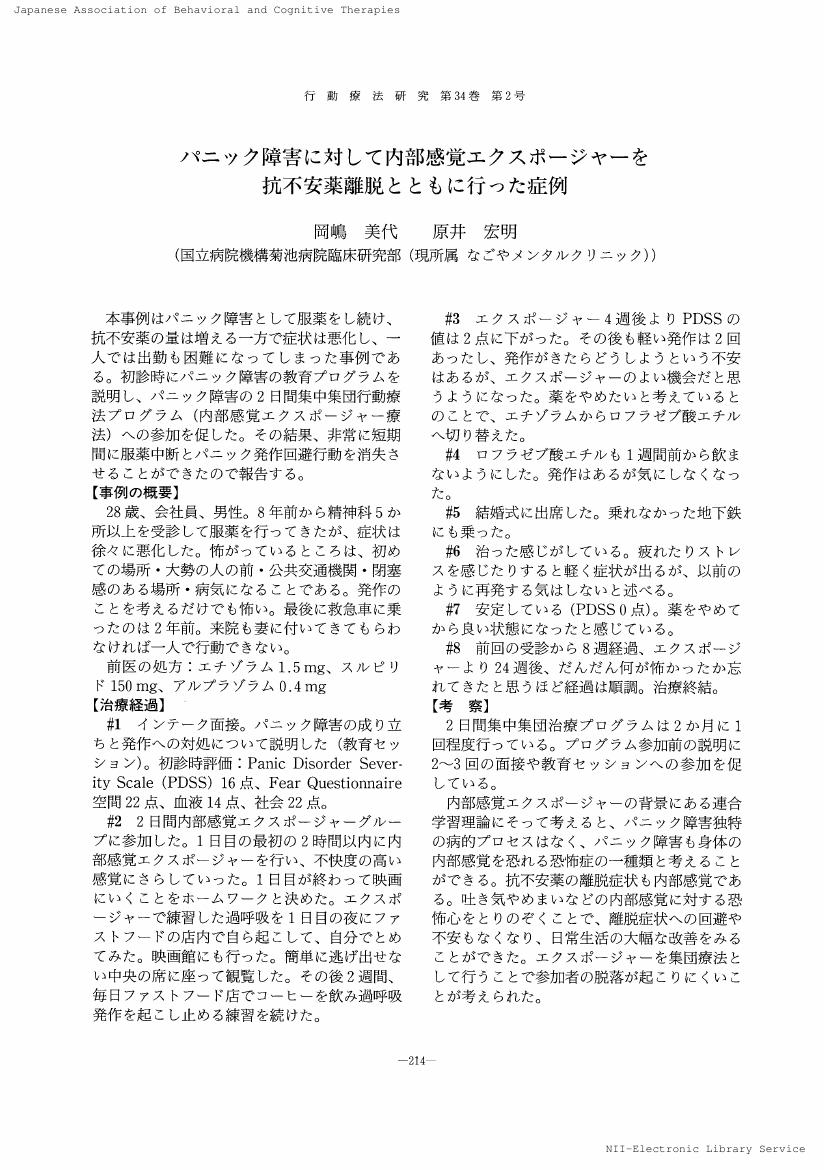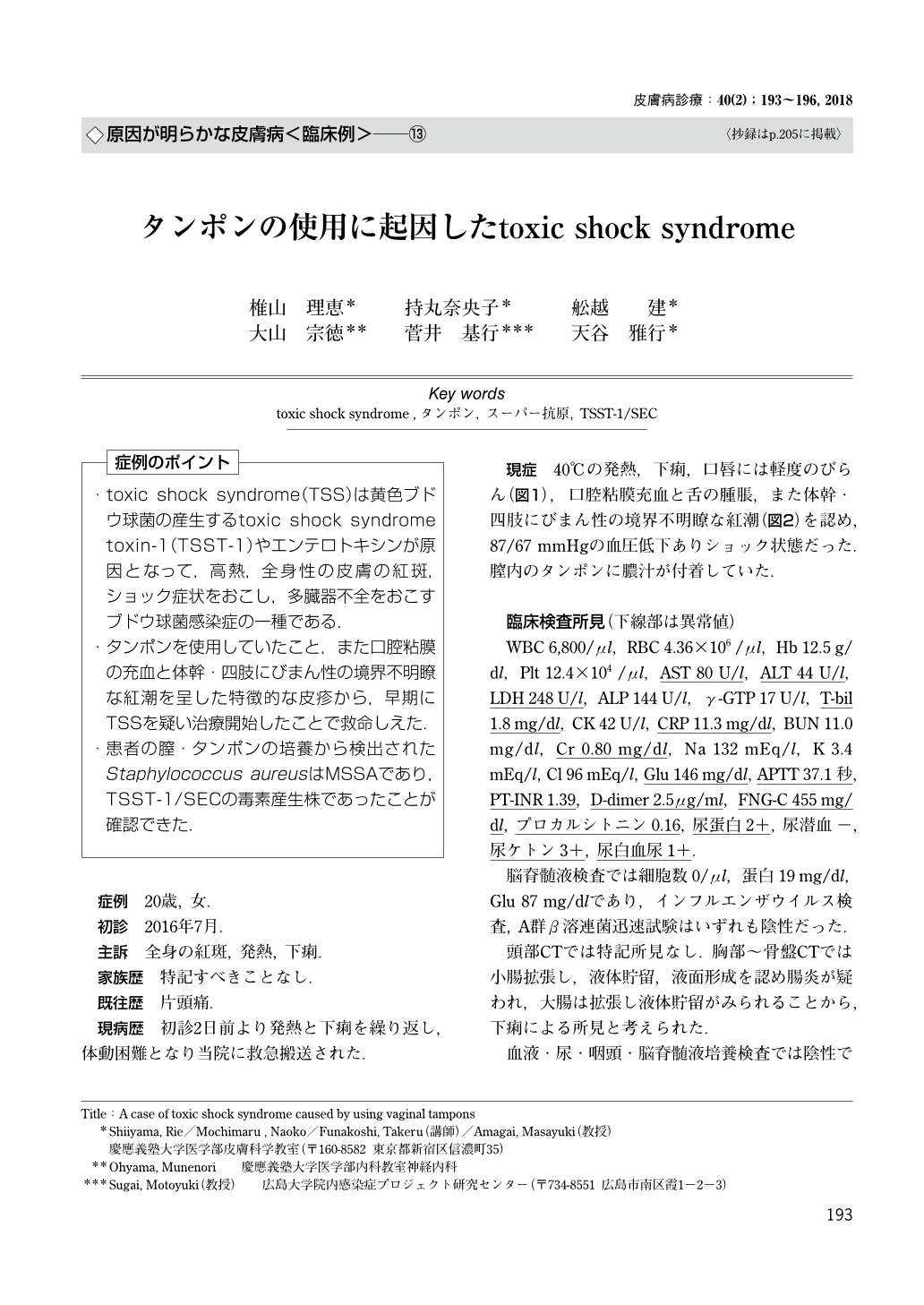- 著者
- 王 志安 Wang Zhi-an
- 出版者
- 駒澤大学法学部
- 雑誌
- 駒澤法学 (ISSN:13476599)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.70-22, 2016-01
1 0 0 0 IR 国際法における近代中国の成立 : その領域観念の歴史的変遷を中心に(1)
- 著者
- 王 志安 Wang Zhi-an
- 出版者
- 駒澤大学法学部
- 雑誌
- 駒澤法学 (ISSN:13476599)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.140-81, 2015-03
1 0 0 0 IR 先住民,植民地支配,脱植民地化--国際連合先住民権利宣言と国際法
- 著者
- 清水 昭俊 Akitoshi Shimizu
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館研究報告 (ISSN:0385180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.307-503, 2008
2007 年9 月に国際連合(国連)総会は国際連合先住民権利宣言を採択した(国連総会決議61/295)。国連がその公的な意思として採択し表明した初めての先住権に関する包括的な規定である。国連の下部組織である作業部会がこの宣言の最初の草案を起草したのは1993 年だった。総会が決議するまでに14 年もの間隔があるのは,宣言の内容について国連加盟国が合意に達するのに,それだけ長期間を要したからである。その間,国連の外部では,1993 年の起草案は先住権に関する事実上の0 0 0 0 国際標準として機能してきた。国際法の専門家のみならず,先住民運動の活発な諸国では一般の間で,さらに国際機関や各国政府においてさえも,そのように受けとめられてきた。さらに,先住民組織はその運動を通してこの文書の影響力を高めてきた。この文書は事実上,先住民自身が発した一つの宣言―「1993 年宣言」と呼ぶべきもの―と見ることができる。これら状況的条件に加えて,この1993 年宣言は,先住権をその根拠とともに包括的に述べる均整のとれた構成と,よく練られた法的言語の表現によって,それ自体が説得力に富む文書である。1993 年宣言は2007 年決議に対しても,それを評価する標準となりえている。1993 年宣言を参照すれば,2007 年決議が多くの修正を受けたものであること,その修正は加盟国政府の国内先住民に対する利害と懸念を反影したものであることが,判明する。 この論文で私は,2007 年決議ではなく1993 年宣言を取り上げて,宣言が先住権を要求するその構造を分析する。分析の焦点は三つのテーマ,つまり,先住民としての権利,民としての基本的権利,復権のための国際的および国内的な制度的枠組みである。要求する権利の全体は,一つの独自の民に保障されるべき「民の集合的生命権」を構成する。この権利を先住民は拒絶されてきた。1993 年宣言は条文で先住民の権利を網羅している。それが可能だったのは,先住民の歴史経験を総括して「民族絶滅と文化絶滅」と認識するからである。1993 年宣言は国際法規を目指した文書であり,そこに述べる権利要求は,民としての集合的生命権の要求を初めとして,先住民に関わる既存の国際法の体系に変革を要求する。しかし,2007 年決議はこの種の変革を達成してはいない。逆に国連加盟国は,条文の文言を操作することによって,1993 年宣言の権利要求の構造を曖昧にすることに成功している。2007 年決議はもはや先住民の歴史経験「民族絶滅と文化絶滅」に言及してはいない。 論文の第二の課題として,国際法において先住民が彼らの権利を奪われ,彼らの存在が不可視にされた歴史を,歴史を遡る方向で追跡する。とりわけ国連と国際労働機構(ILO)が採択した国際法規が考察の焦点である。その後の歴史で先住民を不可視にした分岐点は,1950 年代初めにベルギー政府の主張した所謂「ベルギー・テーゼ」をめぐる論争だった。このテーゼによってベルギー政府は,国連の脱植民地化の事業について多数の加盟国が選択しつつあった実施形態に,異議を唱えた。「反植民地勢力」に対抗して,ベルギー・テーゼは国連の脱植民地化の事業の基底にある特性を暴いていった。ベルギー政府が全ての「非自治の先住の民0 0 0 0 」に平等の処遇を要求したのに対し,国連は脱植民地化の対象を「非自治の地域0 0 」つまり欧米宗主国の海外植民地に限定した。ベルギー・テーゼによれば,「反植民地勢力」が追求する脱植民地化のモデルはラテンアメリカ諸国の「革命」経験だった。それは,植民地が宗主国支配から解放される一方で,国内に先住民に対する植民地支配を持続させるモデルであり,実際,1950 年代以降に独立したアジア・アフリカの多くの新興国が,このモデルに従って,国内に先住民支配を持続させた。この国連による脱植民地化が再定義した国家像は,国内に先住民支配が埋め込まれた構造の国家だった。 国連の素通りした「非自治の」先住民を対象として,ILO は107 号条約を採択し,「統合」政策を推進しようとした。107 号条約は,「先住0 0 」諸人口に法的定義を与えた最初の国際法である。植民地征服という歴史的起点に言及して「先住0 0 」諸人口を捉えるこの「ILO 定義」は,その後の先住民に関する概念的な思考に影響力を発揮し,先住民自身の先住民に関する思考でさえ拘束した。107 号条約は国家に「後見」役を与え,「被後見」の先住民を「より発達した国民共同体」に統合することによって,国家に先住民「文化絶滅」政策を推進させようとする。ILO の統合政策は植民地主義の第二次世界大戦後における形態である。 1993 年宣言は,国連とILO による脱植民地化の政策を含めて,植民地支配の歴史からの回復を要求する。この論文で行う先住民の権利の歴史的考察は,共通に受け入れられている「先住民」の定義について,見直しが必要であることを示唆する。先住民の決定的な示差的特徴として,植民地征服に言及することは不適切である。1993 年宣言は,国家その他の外的エイジェントによる「先住民」の定義と認定を,拒否している。「先住民」の定義と認定は先住民自身の自己決定権に属すべきである。それと同時に,1993 年宣言は先住民を,「民族絶滅と文化絶滅」を被らされてきた民と描いている。1993 年宣言は先住民に対する呼びかけを含意してもいる。1993 年宣言は先住民運動の用具であるに留まらず,運動自体の容器でもある。
1 0 0 0 IR 人類の歴史と国際法
- 著者
- 宮崎 繁樹
- 出版者
- 明治大学法律研究所
- 雑誌
- 法律論叢 (ISSN:03895947)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.625-638, 1966-03
1 0 0 0 日本の「蕎麦」をテーマにした地域連携の食教育
<BR>【目的】本学が立地する東京都港区芝界隈は、江戸時代より東京湾の魚場として食産業の中心地である。そこで、芝落語会および芝青色申告会青年部との地域連携により、庶民の食べ物として「蕎麦」をテーマとし、栄養士を目指す本学の学生を対象に食教育を展開した。「蕎麦」という食材について、落語鑑賞による食文化的視点と「蕎麦打ち」による調理科学的視点を通して、食材を生かした料理の美味しさの探究を目指し、その文化および調理性について理解することを目的とした。<BR>【方法】食教育として (1)「落語鑑賞」(2)「手打ちそばの体験」(3)「蕎麦粉を使ったお菓子作り」を展開した。対象は、本学食物栄養科の学生に選択授業として実施した。(1)「落語鑑賞」(2)「手打ちそばの体験」において、食文化的視点では落語家の瀧川鯉之助氏により、演目の「時蕎麦」を鑑賞させた。調理科学的視点では、「蕎麦粉」についての解説と芝地区の蕎麦打ち職人さんの実演を受講させた後、その場で打ち立ての「蕎麦」を試食させた。学生の評価は、「かわら版」としてまとめさせた。また、(3)「蕎麦粉を使ったお菓子作り」では、「蕎麦粉を使ったお菓子」を調理学研究室のゼミ履修学生と試作検討し、芝地区活動として「蕎麦」の普及を目指した。<BR>【結果】体験授業後、意識調査(n=74)を行った結果、「落語を聴いて興味をもった」が約80%を占め、手打ち蕎麦については「打ち立て蕎麦を試食して美味しかった」と、多くの学生が、「蕎麦」の文化・美味しさに関しての意識の向上が認められた。また、蕎麦の風味を生かした焼き菓子を試作し、「第4回ふれ愛まつりだ、芝地区」に参加した。
1 0 0 0 OA 内村鑑三と文学
- 著者
- 武田清子
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学図書館公開講演集
- 巻号頁・発行日
- no.7, 1993-03
1 0 0 0 日本の政党
- 著者
- 自由民主党[編]
- 出版者
- 自由民主党広報委員会出版局
- 巻号頁・発行日
- 1979
1 0 0 0 左向きの物体画像は右向きの物体画像よりも好まれる
- 著者
- 水原 啓太 柴田 春香 入戸野 宏
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.87, 2021
<p>左右対称な物体において,正面から見た画像よりも,斜めを向いた画像のほうが好まれる (Nonose et al., 2016)。斜め向きの画像は,物体についての多くの情報を表すため,見た目が良く感じられると考えられている。本研究は,左右対称な物体の画像において,物体の左右の向きが物体の選好に与える影響について検討することを目的とした。オンライン実験で,左右の向きのみが異なる日常物体100個の画像を対提示し,見た目が良いほうの画像を強制選択してもらった。画像は物体が正面を向いた状態から,鉛直軸に関して左右のどちらかに30°回転した画像と,それを左右反転した画像であった。その結果,左向きの物体を選好する割合は平均61.2%であり,有意に偏っていた。物体ごとに検討しても左向きよりも右向きのほうが有意に好まれた物体はなかった。この結果について,物体の操作可能性や左方光源優位性の観点から考察した。</p><p></p>
1 0 0 0 OA 防振ゴムの設計法
- 著者
- 関口 久美
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学會論文集 (ISSN:00290270)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.173, pp.85-95, 1961-01-25 (Released:2008-03-28)
- 参考文献数
- 7
The mechanical properties of rubber vibration isolators depend on the amplitude, frequency, temperature, inclination and mean stress, and have remarkable shape effect. When designing, not only such properties but also the kinds of rubber, the conditions of vulcanization, the influences of blending and coating of different rubbers as to the characteristics of materials have to be considered. Furthermore, the deformation of rubber under usual stress is not infinitesimal. The author has continued calculations and experiments in view of the theory of viscoplasto-elasticity advanced by Prof. Sawaragi and strength of materials. And now it becomes possible to calculate the apparent modulus and spring constant by the successive approximation method. From such results a rational method to design rubber vibration isolators is contrived, considering terms above mentioned as much as possible. In this method using nomographs, design can be expedited with a high accuracy.
1 0 0 0 OA 「水割りウイスキー」の開発
- 著者
- 輿水 精一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.3, pp.162-166, 1995-03-15 (Released:2011-09-20)
ウイスキーを水で薄めて飲む飲酒スタイルは日本独自のものであり, アルコール代謝能力の弱い日本人が高アルコール飲料を飲むために考えだした飲酒法と言える。これまでは飲む直前に水で割るため混濁などは問題にならなかったが, いざ, 水割りの状態で商品化すると, もろもろの問題が派生してくることがわかった。水割りウイスキーの開発に携わられた筆者にその経緯を解説していただいた。新商品が新たな需要を掘り起こし, ウイスキー市場の活性化に役立つことを期待したい。
1 0 0 0 OA ウイグルとハザクの女性の民族衣裳
- 著者
- 木曽山 かね Kisoyama Kane キソヤマ カネ
- 出版者
- 東京家政大学
- 雑誌
- 東京家政大学研究紀要 2 自然科学 (ISSN:03851214)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.181-187, 1984
- 著者
- 岡嶋 美代 原井 宏明
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.214, 2008-05-31 (Released:2019-04-06)
1 0 0 0 OA シンポジウム「弱視治療の実際と問題点」 弱視の治療法-文献的考察
- 著者
- 根本 加代子
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.67-80, 1998-07-10 (Released:2009-10-29)
- 参考文献数
- 76
弱視と弱視治療に関する先人の業績を回顧することは、私たちが臨床の場で出会う多くの問題や疑問に答える糸口が得られることである一方では、私たちが同じ知識基盤を共有し、同じ学術用語を用いて、討論をすることで、お互いがより深く理解し合えるのであるこのような同じ知的背景の中から、私たちがより良い治療法や新しい訓練法の創造、そして、従来からの訓練治療にたいする学術的批判をも可能とし、その改善に繋がるのである。今回まとめた内容について以下に記す。弱視の病態に関する基礎的研究(弱視のニューロンの基礎)。弱視治療に用いられる遮蔽法についての神経生理学的考察。日本における弱視の頻度は約2.3%と推定される。器質弱視の訓練は視力回復の可能性があることを前提とし、訓練終了の時期を明確にする。遮蔽治療が困難な時、ペナリゼーションは有効である。間歇遮蔽か終日かの選択は症例の症状に基づき決定される。アトロピン遮蔽は重篤な健眼視力低下をもたらすことがある。点眼中は瀕回の視力チェックを要する。健常視力かそれに近い回復が得られる年齢的限界は15歳前後である。なんらかの回復が期待できる年齢の限界は不明である。弱視治療訓練終了判定基準としては視力の向上した者は交代固視でき、さらに不同視弱視では中心窩抑制が取れ、両眼開放視力が等しくなった時をもってする。また、治癒効果が得られない判定は終日遮蔽にて連続3回の検診でも視力が不変の時をもってする。健眼失明者の弱視眼の30%に0.3~1.0(3ライン以上)の改善が見られた症例とそのメカニズムの考察。L-dopaあるいはciticolineで抑制暗点の縮小や視力の向上が見られるが、副作用の除去、効果の持続、作用機序の解明が不十分であり、これらの解析が進すめば、新しい治療法が生まれる可能性があること。
1 0 0 0 タンポンの使用に起因したtoxic shock syndrome
<症例のポイント>toxic shock syndrome(TSS)は黄色ブドウ球菌の産生するtoxic shock syndrome toxin-1(TSST-1)やエンテロトキシンが原因となって、高熱、全身性の皮膚の紅斑、ショック症状をおこし、多臓器不全をおこすブドウ球菌感染症の一種である。タンポンを使用していたこと、また口腔粘膜の充血と体幹・四肢にびまん性の境界不明瞭な紅潮を呈した特徴的な皮疹から、早期にTSSを疑い治療開始したことで救命しえた。患者の腟・タンポンの培養から検出されたStaphylococcus aureusはMSSAであり、TSST-1/SECの毒素産生株であったことが確認できた。
- 著者
- Tsuneo Nakajima
- 出版者
- U.M.I. (University Microfilms International)
- 巻号頁・発行日
- 1989
- 著者
- 中島 恒雄
- 出版者
- 東京福祉大学
- 雑誌
- 東京福祉大学研究紀要 (ISSN:13475940)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-23, 2002-06
- 著者
- 中島 恒雄
- 出版者
- 朝日新聞社
- 雑誌
- 朝日ジャ-ナル (ISSN:05712378)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.46, pp.p90-93, 1975-10-24
- 著者
- 中島 恒雄
- 出版者
- 電気評論社
- 雑誌
- 電気評論 (ISSN:02855860)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.11, pp.11-17, 2000-11
- 出版者
- 北隆館
- 雑誌
- 地域ケアリング (ISSN:13450123)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.1-4, 2008-01