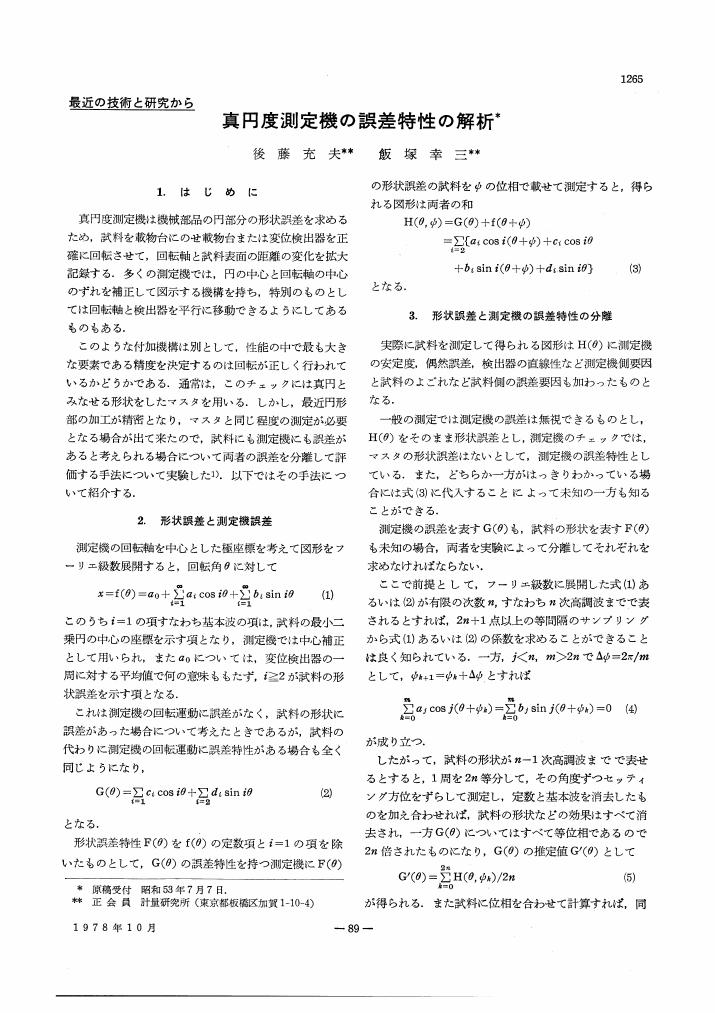1 0 0 0 確率論的手法による臨界安全基礎実験
本研究の目的は, 原子炉燃料臨界安全モニターの開発にあり, 昭和57〜59年度の3年間に引き続き, Cf-252利用の3検出器雑音法を実際的方法を目指して改善, 確立することである. この方法では, Cf内蔵の検出器1個と, 中性子検出器2個を体系周辺に配置し, これらの検出器出力の相互, または自己パワースペクトルを信号処理によって得る. これらの量から作った比(スペクトル比)を確率過程論によって体系の中性子増倍率に関係付ける.本研究3年間の主な成果を以下に列記する(1)上述のスペクトル比が, 見かけ上, 如何に検出器配置に依存するか予測する理論式を導き, 実験における検出器配置に対して指針を得た.(2)この式を, 原研のTCA装置で実験的に検証することを試み, 一部のデータで理論式と一致する傾向を得た.(3)モデル化円柱体系に対するモンテカルロ法シミュレーションコードを作成し, スペクトル比の検出器位置依存性に関し, 上記(1)の理論式の妥当性を明らかにした.(4)同じモンテカルロ法コードにより, Cf中性子源強度に対する, スペクトル比の依存性を調べ, この依存性が少いという結論を得た.(5)相互干渉系(2コニツト体系)への本方法の適用を考え, 2点炉近似に基ずく理論式の導出を行った.(6)遅発中性子がスペクトル比に及ぼす効果を定量的に調べ, 10Hz以上の周波数域では, この効果は考慮する必要がないと結論できた.今後は, a.上記(2)の実験の続行, b.再処理燃料中に必ず存在するプルトニウムの核分裂が, 結果に及ぼす影響の検討, c.測定統計改善のための検出器改善, d.同じく統計改善のためのCf以外の外部中性子源使用の効用検討 などの課題がある.
1 0 0 0 OA 2020年度薬学部新入学生へのオンライン教育 ―学部への信頼と帰属意識をどう育てるか?
- 著者
- 安原 智久 串畑 太郎 上田 昌宏 栗尾 和佐子 曽根 知道
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-058, (Released:2021-01-29)
- 参考文献数
- 4
新入生は,単に学力的な教育をうけるだけではない.高校生から大学生への転換を自覚し,自律的な学習活動姿勢を身に着けていく過程である.ディスカッションやプレゼンテーションなどの能動型学習へ挑戦し,成功体験を得ることで積極的な学習習慣を育んでいく期間である.この期間の教育は,新入生の大学への印象を大きく左右する.自らの大学への帰属意識や満足感を持つかどうかは,この時期に提供される教育の質に大きな影響を受けると考えられる.入学直後に学生が持つ学部への印象は,学習への取り組みを高次学年に及ぶまで左右する要因になり得る.以上,新入生へ入学後に提供する教育は,単なる基礎学力の養成だけではなく,薬剤師を目指す学習意欲を育むうえで極めて重要となる.COVID-19の影響により,新入生が経験するはずであった学習面以外での大学からの支援が,基本的にすべてオンラインとなった環境でどのように展開していったかを記していく.
1 0 0 0 OA 鎌倉中・後期の摂津渡辺党遠藤氏について : 「遠藤系図」をめぐって
- 著者
- 生駒 孝臣 Takaomi Ikoma
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.18-34, 2002-09-10
1 0 0 0 IR 症例報告 ジピベフリンの点眼が有効であった眼瞼下垂の1例
- 著者
- 北川 清隆 柳沢 秀一郎 山田 哲也 三原 美晴
- 出版者
- 富山大学医学会
- 雑誌
- 富山大学医学会誌 (ISSN:18832067)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.27-29, 2006
両眼瞼下垂を訴えた59歳,女性に対し,alpha adrenergic agonistである5%フェニレフリン及び1%アプラクロニジンの点眼試験を行ったところ,眼瞼下垂は改善した。alpha adrenergic agonistである0.1%ジピベフリンの点眼で加療したところ両眼瞼下垂は改善した。眼瞼下垂を来たす症例において,alpha adrenergic agonistである0.1%ジピベフリンの点眼が有効な場合があると思われた。
1 0 0 0 OA 野生のデモクラシーについて
- 著者
- 土佐 弘之
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.168, pp.168_131-145, 2012-02-29 (Released:2014-03-31)
- 参考文献数
- 52
Marx-Leninism had justified its proletariats' dictatorship and had suppressed anarchism under the pretext of promoting emancipation from the oppression and exploitation of capitalism. Anarchism gradually re-emerged while oppression by Stalinism became conspicuous. Following the collapse of state socialism, neo-liberalism became hegemonic and rapid de-regulation brought in social polarization, which foregrounded the crisis of the electoral representative democracy as well as contradictions of capitalism. Responding to the crisis of the competitive democracy and neoliberal capitalism, new anarchism began to emerge including Zapatista insurgency (1994) and direct actions in Seattle (1999) or in New York (2011). Although some scholars also begin to examine its implications of new anarchism in the global politics, it is still remain marginalized in IR.This article will explore the politics of new anarchism in the context of global democratization beyond the territorial sovereignty system. First we critically examine the intricate relation between Hobbesian realism and anarchy by focusing upon the marginality of anarchism in the mainstream IR. Second we probe the current crisis of competitive representative democracy and emerging new anarchist movements by examining the incompatibility between the territorial state sovereignty and deepening of democracy. Third we probe implications of democracy against the state, savage democracy, by re-examining an argument on society against the state in the political anthropology. Last we examine the (im-)possibilities that anarchism would play a role of ‘democracy as a movement’ to promote ‘democracy as an institution’ such as electoral representative democracy beyond the limits of state sovereignty.As the global financial crisis indicates, the states cannot control a flow of powers effectively and tend to be shaken by its excess liquidity. While a growing flow of powers aggravates the crisis of the representative democracy based upon the territorial sovereignty, new anarchism begins to constitute a part of globalization from below by aiming to minimize domination. It is certain that the history of anarchism has continued to be a history of losers except a few cases of temporal autonomous zones such as the Paris commune (1871). However it is also certain that philosophical anarchism provides a valuable foundation for promoting global democracy by activating savage democracy.
1 0 0 0 OA 剣道における「先々の先」と「後の先」ついて
- 著者
- 三橋 秀三
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.41-43, 1974-11-30 (Released:2012-11-27)
- 著者
- 柴田 眞理子 尾島 俊之 阿相 栄子 中村 好一 岡井 崇 戸田 律子 北井 啓勝 林 公一 三砂 ちづる
- 出版者
- 日本母性衛生学会
- 雑誌
- 母性衛生 (ISSN:03881512)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.374-383, 2005-07
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
妊娠, 出産における医療, 助産に関して, 実施したほうがよいか否か, 議論のある20項目について, 助産師の考え方や実態を明らかにすることを目的として, 日本助産学会, 日本母性衛生学会の名簿から無作為抽出した1, 807人を対象に自記式郵送調査を行った。その結果, 実施に賛成で重要性も高い事項は, 授乳時間を定めない, 塩分制限, 産婦の希望による分娩時の体位決定であり, 低い事項はルーチンな会陰切開, 会陰縫合を通常の縫合よりも1針多めに行う, 入院時洗腸などであった。80%以上の症例での実施割合が高い事項は, 砕石位での分娩, 分娩第2期に仰臥位にする, 授乳時間を定めない, 点滴をするであった。実施時の考慮事項では, 妊産婦や児の身体状況, 施設の方針, 妊産婦の希望の順であった。今後の方針をみると, 母乳育児や分娩体位などでは, 積極的に進めていくや減らしていきたいを支持し, 薬剤使用, 医療処置などでは, 現状維持を支持していた。以上から, 妊娠, 出産における医療, 助産の実践に関しては, 助産師の立場からのエビデンスの蓄積と, それに基づいた適切な実施を検討していくことの必要性が示唆された。
1 0 0 0 IR CT逐次近似法による再構成画像の画質評価 (第108回成医会葛飾支部例会)
- 著者
- 越智 美紀 金子 智明 千田 真大 松田 直子 飯髙 晃治 岩田 真 オチ ミキ カネコ トモアキ チダ マサヒロ マツダ ナオコ イイダカ コウジ イワタ マコト Ochi Miki Kaneko Tomoaki Chida Masahiro Matsuda Naoko Iidaka Koji Iwata Makoto
- 雑誌
- 東京慈恵会医科大学雑誌 (ISSN:03759172)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.5, pp.120, 2015-09-15
- 著者
- 山下 裕 古後 晴基 西上 智彦 東 登志夫
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.101-106, 2018-10-16 (Released:2018-10-19)
- 参考文献数
- 32
【目的】慢性頸部痛患者における破局的思考や運動恐怖感が能力障害に関連する因子かどうか検討した。【方法】3ヶ月以上頸部痛を有する外来患者99名(外傷性35名,非外傷性64名)を対象とした。評価項目は,Neck Disability Index(NDI),安静時・運動時疼痛強度,疼痛持続期間,破局的思考,運動恐怖感とした。Mann-Whitney U 検定を用いて発症起点の有無における評価項目を比較した。また,Stepwise 法による重回帰分析を用いてNDI に関連する項目を検討した。【結果】外傷性頸部痛患者と比較して非外傷性頸部痛患者は年齢,疼痛持続期間において有意に高値を示したが,その他の項目に有意な差は認められなかった。NDI と関連する項目は,破局的思考と安静時・運動時疼痛強度であった。【結論】慢性頸部痛患者においては,外傷性か非外傷性に関わらず破局的思考が能力障害に関連することが明らかとなった。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.634, pp.34-39, 2016-02-22
3号機カバー建設3号機原子炉建屋では、2011年9月から始まったがれき撤去が終わり、いよいよ燃料取り出し用カバーの設置に移る。なるべく人手を介さずにカバーを構築できるよう、設計と施工が一体となって計画を練り上げた。 東京電力福島第一原子力発電所の南…
- 著者
- 大谷 奨
- 出版者
- 日本教育行政学会
- 雑誌
- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.135-151, 2007-10-12 (Released:2018-01-09)
There were many cases where towns which ran girls' high schools or middle schools changed these schools into prefectural secondary schools in the early Showa era in Hokkaido. The purpose of this paper is to point out the characteristics of these processes, analyzing their description in official documents kept by the National Archives of Japan. The results of this research were as follows: 1 Firstly, the authorities of towns established practical courses in girls' high school because it was able to open these without their own schoolhouses. At the same time they made a financial effort to construct independent buildings for these schools. 2 After the completion the schoolhouse, they immediately applied for a change of their school to that of an ordinary girls' high school supported by the Hokkaido prefectural government (Do-Cho). 3 Finally, they tried to change the founder of the school from a town-run by the prefectural government and the Do-Cho accepted their application. This means that the acquisition of the prefectural secondary school in the town by essentially by donation. 4 This method to obtain a prefectural school was also used in the case of town-run middle schools. The local authorities tried again to get prefectural middle schools by such donations. Even into the postwar period, many municipalities opened high schools themselves and several years later gave the school buildings and facilities to the prefecture. This was important not only in terms of providing secondary education but also to attract prefectural organizations to support for education.
1 0 0 0 IR PHSを用いた無線遠隔画像診断の試み
- 著者
- 小口 和浩 村瀬 澄夫 金子 智喜 滝沢 正臣 角谷 眞澄 Oguchi Kazuhiro Murase Sumio Kaneko Tomoki Takizawa Masaomi Kadoya Masumi オグチ カズヒロ ムラセ スミオ カネコ トモキ タキザワ マサオミ カドヤ マスミ
- 出版者
- 日本医学放射線学会
- 雑誌
- 日本医学放射線学会雑誌 (ISSN:00480428)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.12, pp.686-687, 2001-10-25
- 著者
- 井口 知子
- 出版者
- 日本私立大学連盟
- 雑誌
- 大学時報 = University current review (ISSN:02881748)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.395, pp.82-85, 2020-11
- 著者
- 安藤 寿康
- 出版者
- 日本私立大学連盟
- 雑誌
- 大学時報 = University current review (ISSN:02881748)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.395, pp.74-81, 2020-11
- 著者
- 日本学生相談学会
- 出版者
- 日本私立大学連盟
- 雑誌
- 大学時報 = University current review (ISSN:02881748)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.395, pp.68-73, 2020-11
- 著者
- 石垣 琢麿
- 出版者
- 有斐閣
- 雑誌
- 書斎の窓 = The window of author's study
- 巻号頁・発行日
- no.672, pp.64-68, 2020-11
1 0 0 0 OA 戦後の「新教育」と学力低下問題 久保舜ー著『算数の学カ―学力低下とその実験』 をめぐって
- 著者
- 岡部 進
- 出版者
- 一般社団法人 数学教育学会
- 雑誌
- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1-2, pp.41-67, 1986 (Released:2020-08-07)
1 0 0 0 OA 洗たく洗剤から見るGSC
- 著者
- 松本 泰正
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.56-59, 2017-02-20 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 6
洗たく洗剤の開発にLCA(ライフサイクルアセスメント)を取り入れ,洗たくのすすぎを1回にすることで,消費者とともに洗たくに関わる環境負荷低減を実現した。社会の変化を先取りして環境性能,洗浄性能を同時に満足させるイノベーションがどのように生まれたのかを紹介する。
1 0 0 0 OA 真円度測定機の誤差特性の解析
- 著者
- 後藤 充夫 飯塚 幸三
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.526, pp.1265-1267, 1978 (Released:2009-06-30)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 1 1