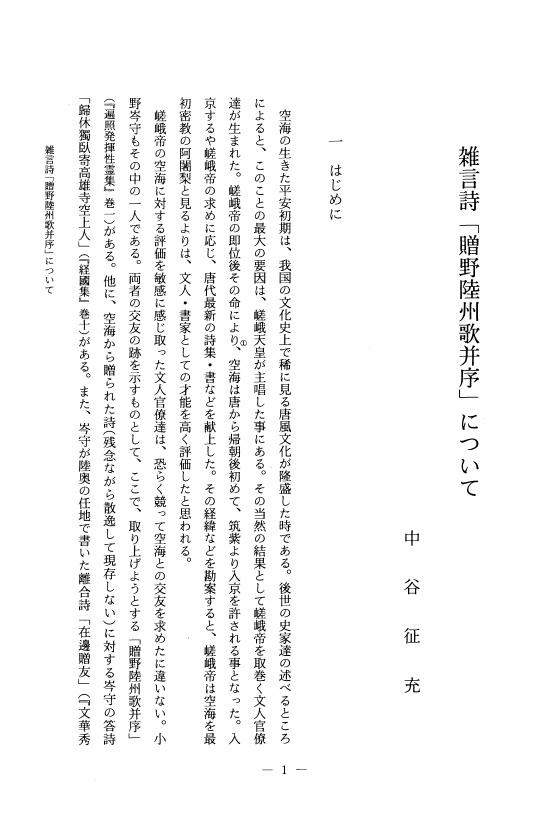7 0 0 0 OA 演色評価数はどのようにして算出するか
- 著者
- 向 健二
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.3, pp.202-205, 2003-03-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 4
7 0 0 0 OA 規制目的二分論の二分論
- 著者
- 齊藤 正彰
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.1-22, 2023-05-31
7 0 0 0 OA 機能障害を改善するための関節可動域評価の工夫
- 著者
- 東藤 真理奈 福本 悠樹
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.51-58, 2022 (Released:2022-12-23)
- 参考文献数
- 25
Evaluation is a very important part of the process of providing physical therapy. After selecting movements based on the patient’s daily activities and narrowing down the problematic joint movements based on movement observation, it is necessary to evaluate the patient and to establish the functional impairment. Sometimes there are cases where problematic joint range of motion can be deduced from the movement, but no range-of-motion measurement method exists. The patient may be diagnosed with joint range of motion limitation based on movement observation, and treatment may be developed, but no change in movement is observed. In this section, we introduce methods for evaluating joint range of motion with awareness of the axis of motion, and explain how to evaluate external rotation of the lower leg together with an explanation of the correct interpretation of the motion.
7 0 0 0 OA 野村不動産における創発的戦略形成プロセス PMOの開発事例を中心に
- 著者
- 富田 純一 藤本 隆宏 賀来 高志 宇佐美 直子 菊池 嘉明 石原 弘大 藤田 大樹 吉田 敏
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- pp.0200417a, (Released:2020-08-20)
- 参考文献数
- 11
本稿の目的は、野村不動産株式会社が手掛けた「Premium Midsize Office」と呼ばれるオフィスビルの開発事例分析を通じて、同社の戦略形成プロセスを検討することにある。同社は、1フロア1テナントという中規模サイズでありながらハイグレードなオフィスビル市場をいち早く開拓した。同社はなぜそうした潜在市場を掘り当てることができたのか。事例分析の結果、同社の創発的な戦略形成プロセスが明らかにされる。
7 0 0 0 OA 雑言詩「贈野陸州歌井序」について
- 著者
- 中谷 征充
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.214, pp.1-18, 2005-03-21 (Released:2010-03-12)
7 0 0 0 OA 化粧と感情の心理学的研究概観
- 著者
- 阿部 恒之 高野 ルリ子
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.338-343, 2011-09-25 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1 2
化粧に関する心理学的研究は,1980年代から盛んになってきた.化粧は慈しむ化粧(スキンケア)と飾る化粧(メーキャップ・フレグランス)に大別されるが,感情に及ぼす影響に関する研究は,そのいずれもが高揚と鎮静をめぐるものであった. 喩えるなら,メーキャップによって心を固く結んで「公」の顔をつくって社会に飛び出し,帰宅後にはメーキャップを落とし,スキンケアをすることで心の結び目を解いて「私」の顔に戻るのである.すなわち,化粧は日常生活に組み込まれた感情調節装置である.
7 0 0 0 OA 事前登録研究:自己呈示の内在化に自己呈示は必要か――自己欺瞞による代替説明可能性の検討
- 著者
- 上田 皐介 山形 伸二
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.39-41, 2023-06-07 (Released:2023-06-07)
- 参考文献数
- 6
We examined whether people’s trait increases when asked to impress others with that trait. Participants (N=422) reported their extraversion/introversion and social desirability of extraversion and introversion. After 7 to 10 days, we asked them to write a self-introduction that gave either an extraverted or introverted impression, depending on their condition. Their extraversion/introversion was measured before the self-introduction. Results indicated that (1) only extraversion was rated desirable, (2) a trait to be presented increased in both conditions, and (3) there was a greater effect on extraversion, suggesting that internalization of self-presentation occurred even without self-presentation, especially for socially desirable traits.
7 0 0 0 OA 「LRAの基準」を使い倒す
- 著者
- 安念 潤司
- 出版者
- 中央ロー・ジャーナル編集委員会
- 雑誌
- 中央ロー・ジャーナル = Chuo Law Journal (ISSN:13496239)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.139-167, 2020-12-20
受験界で広く知られる「LRAの基準」について、薬事法違憲判決が述べているところをできるだけ厳密に再構成し、その上で、2012年の司法試験(論文式)の憲法の問題(設問は、筆者が適当に修正した)に適用する手順を解説した。
7 0 0 0 OA 国際子ども図書館児童文学連続講座講義録
- 著者
- 国立国会図書館国際子ども図書館
- 出版者
- 国立国会図書館
- 巻号頁・発行日
- vol.平成25年度, 2014-10-15
- 著者
- 田城 文人 鈴木 啓太 上野 陽一郎 舩越 裕紀 池口 新一郎 宮津エネルギー研究所水族館 甲斐 嘉晃
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.22-40, 2017-02-28 (Released:2017-02-28)
- 参考文献数
- 146
- 被引用文献数
- 10
More than 1,300 species of fishes have been reported from the Japanese side of the Sea of Japan. However, occurrence records for a great number of these species are not documented by voucher specimens, rendering estimates of the diversity of fishes from this region unclear as to their reliability. Given this situation, ichthyologists at the Maizuru Fisheries Research Station of Kyoto University are central to a research group aiming to provide a more reliable estimate of the diversity of the fish fauna of this region that is based on a reproducible data such as voucher specimens. Here we provide some biogeographic (24 species) and taxonomic (2 species) notes as a preliminary report towards this goal. As a result of new biogeographical findings, 10 species are confirmed from this region for the first time, and the distributional ranges of 14 other species are extended to the east. Most of these 24 species are not residents in the Sea of Japan, rather they are migratory species likely to have drifted from the southward via the Tsushima Warm Current. An unidentified congrid species, Ariosoma sp. and an undescribed cynoglossid species, Symphurus sp., were collected off Kyoto Prefecture. Exact identification of the former species, and a description and formal naming for the latter species, will be the subject of studies conducted in the near future.
7 0 0 0 OA 三崎魚市場に水揚げされた魚類- XIX
- 著者
- 山田 和彦 工藤 孝浩 瀬能 宏
- 出版者
- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)
- 雑誌
- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.35, pp.41-44, 2014 (Released:2022-04-17)
The ichthyofauna of Sagami Bay was surveyed on the basis of landed fishes on Misaki Fish Market. Although 593 fish species had been recorded since 1986, we newly added seven species in this report. Among the above seven species, Minous pusillus of them is new to the bay.
- 著者
- Takashi Hayashi
- 出版者
- The Japanese Society for Mathematical Economics
- 雑誌
- 数理経済学会誌 (ISSN:24363162)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.23-37, 2022 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 16
Given the direct conflict between envy-freeness and Pareto efficiency when individuals have unequal labour skills, we examine what are attainable when we choose to insist on envyfreeness.
7 0 0 0 OA 少年期における三島由紀夫のニーチェ体験
- 著者
- 高山 秀三
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.281-316, 2015-03
三島由紀夫は少年期からニーチェを愛読し,大きな影響を受けた。ニーチェと三島には,女性ばかりに取り囲まれた環境で幼少期を過ごしたという共通性がある。女性的な環境で育った人間が自身のうちなる女性性と戦うなかで生れたニーチェの哲学は,受動性や従順,あるいは柔弱さなどのいわゆる女性的なものに対する嫌悪を多分に含んでいる。それは思春期の自我の目覚めとともに男性的な方向に向けて自己改造をはじめていた三島の気持に大いにかなうものだった。戦時中,十九歳のときの小説『中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃』は三島自身がニーチェのつよい影響のもとで書いたことを認める作品である。無差別的な大量殺人を行なう「殺人者」の思いを日記体でつづったこの小説にあって,「殺人者」はその「殺人」によって,失われていた生の息吹を取り戻す。この「殺人」は三島が目指す危険な芸術の比喩であると同時に殺人という悪そのものである。ここには幼少期以来,攻撃性の発露を妨げられ,健全な生から疎外されているという意識に苦しみつづけてきた三島の,生を回復するための過激な覚悟が反映している。そしてこの覚悟は,三島と同様に女性に囲まれた幼少期を送り,自分の弱さと世界における局外者性の意識に苦しみながら,男性的なヒロイズムをもって自分を乗り越えていく思想を語りつづけたニーチェの戦闘的な著作への共感から生れている。
7 0 0 0 OA 機能分化社会におけるリスク、信頼、不安
- 著者
- 徳安 彰
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.68-75, 2016 (Released:2020-03-09)
本稿は、福島原子力第一発電所の事故のような社会全体に影響のおよぶリスク問題を題材にして、ルーマンの社会システム理論に依拠して問題の構図を記述し、科学技術とリスク・アセスメントの関係、リスク・アセスメントへの非専門家の参加について論じる。現代社会における複雑性の増大は、機能分化した社会構造をもたらした。複雑性の増大は、複雑性の縮減メカニズムとして象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアを生み出すとともに、システム信頼を生み出した。複雑性の増大は、可能な選択肢を増大させ、選択の自由/選択の強制をもたらすとともに、選択の結果として損害が生じうる状況つまりリスクを生み出した。さらに複雑性の増大は、不安の増大と緩和の要求を生み出した。科学技術のリスク・アセスメントは、科学システムにおける専門知識を駆使して行われるが、科学的知識には本質的な不定性があるから、つねに厳密で頑健なリスク評価ができるとはかぎらない。他方で、科学技術の採用や規制の政策決定は、政治システムの問題である。政治システムそのものは、科学的な真/非真を判断できないから、科学システムの結論を導入しながら、集合的意思決定を行わなければならない。民主主義的な手続きと科学や政治に対する信頼を重視すれば、リスク・アセスメントや政策決定には非専門家の参加が不可欠だが、それは非専門家自身が意思決定者としてリスクをとることを意味する。
7 0 0 0 OA 高度さらし粉の火災および爆発危険性
- 著者
- 上原 陽一
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.94-100, 1977-04-15 (Released:2018-05-31)
次亜塩素酸カルシウム70%を含む高度さらし粉の火災および爆発に関する基本的な性質を知るために,熱的特性,発火温度,衝撃および摩擦感度,起爆性などについて測定を行った. 高度さらし粉は約180℃で酸素を放出しながら分解し,発熱するので,有機物などの可燃性物質との混合物は,この温度に達すると発火し.いったん着火すると火炎は急速に伝ぱし,火災を拡大する.衝撃, 摩擦に対してはそれほど鋭敏ではなく,雷管起爆試験によっても,この物質だけでは起爆しないが,有機物と混合すると感度は上昇し,黒色火薬級の威力を示す.高度さらし粉の危険性として,一般に発火のしやすさと火災拡大の速さが重要である.
- 著者
- 久保田 康裕
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学 (ISSN:03896633)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.43-49, 2022-12-28 (Released:2023-05-29)
- 参考文献数
- 6
自然保護区の拡大による生物絶滅の抑止効果は,「保護区を設置する場所」に依存する。一方,保護区は土地・海域の利用に関する法的規制を伴うため,保護区を拡大できる場所は,社会経済的に制限される。陸や海の空間計画には,生物多様性保全と社会経済的利用の調和が求められる。したがって,自然共生の理念を基に,ある空間を経済的に利用しつつ保全も副次的に達成するOECM によって,民間主導の保全事業を推進することは有望である。しかし,保全の実効性を担保するという観点では,OECM の難易度は低くなく,保全政策としては共同幻想に終わる可能性もある。生物多様性保全を目的としたOECM を長期的に駆動させる原動力として,生物多様性ビッグデータ・テクノロジープラットフォームが重要である。
7 0 0 0 OA デルマトーム図
7 0 0 0 OA 武術家甲野善紀の技のバイオメカニクス的解明
- 著者
- 吉福 康郎
- 出版者
- 人体科学会
- 雑誌
- 人体科学 (ISSN:09182489)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.25-34, 2005-11-30 (Released:2018-03-01)
- 著者
- 小林 昭博 Akihiro Kobayashi
- 雑誌
- 関西学院大学キリスト教と文化研究 = Kwansei Gakuin University journal of studies on Christianity and culture (ISSN:13454382)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.35-52, 2009-03-31
- 著者
- Ryuta Kawashima Rui Nouchi Taisuke Matsumoto Yasunori Tanimoto
- 出版者
- Society of Automotive Engineers of Japan, INC
- 雑誌
- International Journal of Automotive Engineering (ISSN:21850984)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.73-76, 2014 (Released:2016-03-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
We investigated whether riding a motorcycle in daily life has beneficial effects on the cognitive functions of healthy subjects. Twenty-two healthy right-handed men, who had a significant break from riding, participated in this study. They were randomly assigned to either the intervention or control group. The intervention group was asked to ride a motorcycle in their daily life for two months. The intervention group showed improvement of their visuospatial cognition compared with the control group. Results of this study indicate that riding a motorcycle in daily life could have beneficial effects in returning riders.