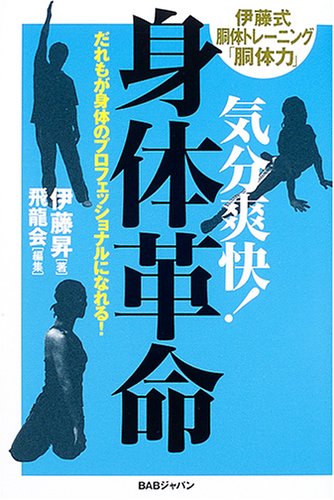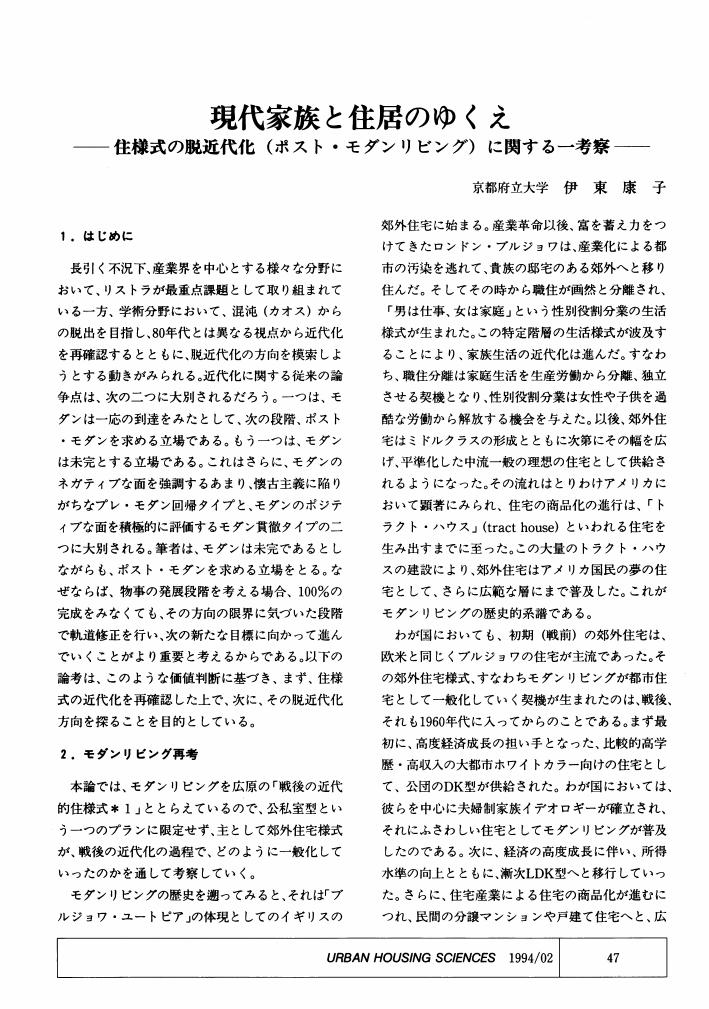1 0 0 0 OA 「針切」の書法研究
1 0 0 0 OA 交通環境における自転車の走行状況と交通事故発生要因について
- 著者
- 松井 靖浩 及川 昌子 一杉 正仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.11-19, 2016 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 9
都市部における自転車の走行状況を明確にすることで、交通事故発生メカニズムを解明し、交通安全対策を行うための基礎資料に資することを目的とする。本稿では、最初に朝の通勤時間帯に信号機のない交差点における自転車乗員の行動特性を分析した。その結果、自転車の交差点進入時の平均走行速度は3.09m/sであった。また、進行方向に向かって道路中央より左側と道路の左路側帯を走行する自転車乗員が86%を占め、多くの自転車が道路の左側を走行していることが分かった。ただし、この交差点の左角には建物があり、交差道路を行き交う車両、自転車、歩行者が自転車乗員には死角となり、交差点進入直前まで認識が困難な環境であった。このように、道路の左側を走行する自転車がある程度の走行速度を保ち、安全確認をせずに交差点に進入する自転車乗員の行為は、とくに走行音を伴わない電気自動車や自転車が接近した場合、出会頭による車両等との衝突事故の起因になり得ることが予想される。次に、車両に搭載したドライブレコーダより取得できるニアミスデータを用い、車両と自転車との接近状況を分析した。車両と自転車との接近状況について、死亡事故とニアミスを調査した結果、いずれの事象も車両が直進し、前方を自転車が横断する事例が最も多い傾向にあった。本結果から、ニアミスデータは事故状況を把握する上で活用可能であると考えられる。そこで、ニアミス事象において車両が直進し自転車が横断するケースに着目し、衝突予測時間(TTC)を算出した。その結果、建物や車両などの物陰から自転車が飛び出す場合のTTCは、障害物なしの状態で飛び出す場合のTTCと比べ有意に短いことが判明した。これら2つの結果より、自転車乗員、車両運転者共に建物などの障害物により見通しが悪く、相手を認識できない場合、出会い頭での交通事故に至る可能性が極めて高くなることが推察される。今後、本分析結果に基づき、自転車専用のカーブミラー等の新規設置により視界が改善されることが望まれる。さらに、自転車検知型被害軽減装置の開発や保護性能評価手法において、本分析結果が反映されることが期待される。
- 著者
- 小崎 道雄 飯野 久和 岡田 早苗 関 達治
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.193-198, 2000
ラオスは周辺諸国のタイやインドネシアなどに比べて, まだ近代化の波にそれぽど洗われてなく, 古くからの生活文化を残している。今回は, そのラオスにおける酒と麹について解説していただいた。
- 著者
- 伊藤昇著 飛龍会編集
- 出版者
- BABジャパン出版局
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 OA 現代家族と住居のゆくえ 住様式の脱近代化 (ポスト・モダンリビング) に関する一考察
- 著者
- 伊東 康子
- 出版者
- 公益社団法人 都市住宅学会
- 雑誌
- 都市住宅学 (ISSN:13418157)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.6, pp.47-51, 1994-06-30 (Released:2012-08-01)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 女性性器の単純ヘルペスウイルス初感染における抗体推移に関する研究
- 著者
- 小泉,佳男
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科學會雜誌
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, 1999-02-01
女性性器の単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)又は2型(HSV-2)の初感染における血清抗体(IgM, IgG)の推移をELISAを用いて検討した. HSV感染初期におけるIgM抗体の陽性率は第5〜7病日でHSV-1は53.3%, HSV-2は28.6%, 第11〜15病日ではHSV-1, HSV-2ともに100%であり診断的意義は高いと思われた. IgM抗体価の平均的な推移はHSV-1, HSV-2感染ともに2〜3週をピークとして徐々に低下したが症例ごとにみるとIgM抗体価の推移が三つのパターンに分けられることが判った. つまり2〜3週をピークとして低下する群, ピーク以降も低下しないで8前後の1%値を続ける群, 抗体価は上昇しないで2前後の低い値のまま持続する群の3群である. IgM抗体が8前後の高値のまま持続する群は, HSV-1感染例に比べてHSV-2感染例の方が有意に多かった. IgG抗体の陽性率は第5〜7病日ではHSV-1感染例とHSV-2感染例でそれぞれ13.3%と0%, 第11〜15病日でそれぞれ93.3%と62.5%となりHSV-2の方が陽転率が低かったが有意差はなかった. IgG抗体はIgM抗体よりも出現はやや遅れ, IgM抗体にはやや劣るものの診断的価値はあると思われた. IgG抗体はHSV-1, HSV-2ともに3週頃まで上昇したが, 抗体価は低く3カ月目まで臨床的にヘルペス既往のない妊婦や再発を繰り返す性器ヘルペス患者よりも遥かに低い値で推移した.
1 0 0 0 OA pioneerは一人で十分? ーインゲンゾウムシの幼虫にみる2つの戦略ー
- 著者
- 大塚 康徳 徳永 幸彦
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第51回日本生態学会大会 釧路大会
- 巻号頁・発行日
- pp.284, 2004 (Released:2004-07-30)
インゲンゾウムシの幼虫の豆への侵入率は幼虫が1頭しか存在しないときよりも複数頭存在している場合の方が高い侵入率を示す。これには幼虫が豆に侵入する際の方法が2通り存在することが深く関わっている。2通りの方法とは「自ら豆に穴を開けて豆に侵入する方法」と「他の幼虫によってすでに開けられた穴を利用して豆に侵入する方法」である。自ら穴を開けて豆に侵入した幼虫をpioneer、すでに開いていた穴を利用して豆に侵入した幼虫をfollowerと呼ぶ。pioneerとfollowerをわける大きな要因は豆の表皮にあり、豆の表皮が存在しない状態の侵入率は豆の表皮が存在する場合の侵入率を大きく上回る。そこでpioneerとfollowerをより厳密に次のように定義した。pioneerとは豆の表皮を食い破って豆に侵入した個体であり、followerとは表皮を食い破らずに豆に侵入した個体である。過去の研究や著者の実験から幼虫はすでに開いている穴を好んで利用しており、pioneerとして豆に侵入できる幼虫も好んでfollowerとして豆に侵入していた。しかし、少なくとも1頭はpioneerにならなければどの個体も豆に侵入することができない上に、1個の豆という限られた資源に多数個体が侵入すれば当然資源が枯渇し個体数の減少につながる。よってインゲンゾウムシの幼虫の豆への侵入行動は、他の幼虫の存在に依存した戦略行動といえる。今回の研究では資源量は無視して問題を単純化し、豆への侵入に限定して幼虫が複数等存在するときの幼虫の最適戦略、つまり最適なpioneerの比率について実験を行った。また、pioneerとして豆に侵入できる幼虫も好んでfollowerとして豆に侵入していたこと、そして少なくとも1頭がpioneerにならなければ全個体が豆に侵入できずに死んでしまうということからインゲンゾウムシの豆への侵入行動をn人のチキンゲームとしてとらえモデルを作成した。
1 0 0 0 自助・共助と,公助との連携を考える:―つないでゆくことの重要性―
- 著者
- 和田 一範
- 出版者
- 水利科学研究所
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.100-120, 2018
<p>防災の基本は,自助・共助・公助である。自助・共助・公助を語るにあたっては,自助・共助と,公助との連携を考えることが重要である。 自助・共助は,災害に際して,単に避難をするだけではない。また,これを支援する公助も,単に公的な支援の拡充という視点で展開するのではなく,自助・共助側からの発信を受けて,これに応える形で施策を展開してゆく,真の協働のパートナーとしてとらえてゆくことが重要である。 自助・共助側からの自主的な取り組みにこそ,大きな意味と効果がある。公助の推進にあたっては,自助・共助から発信する必要性に基づく,公的な支援,公助の展開をシステム化する。 自助・共助と,公助との連携を社会システム化し,継承してゆくことが重要である。 上杉鷹山の三助,武田信玄の竜王河原宿,信玄堤の神輿練り御幸祭と三社御幸の故事から,これらの教訓をひもとき,つないでゆくことの重要性を再認識する。</p>
1 0 0 0 444. 高松市南部のクレーター状構造の成因と水理地質
- 著者
- 石井 秀明 長谷川 修一
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, 1994
1 0 0 0 53. 高松市クレーターは隕石の衝突跡か
- 著者
- 長谷川 修一 石井 秀明
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, 1995
1 0 0 0 高松クレーターの成因と地下水
- 著者
- 長谷川 修一
- 出版者
- 地下水技術協会
- 雑誌
- 地下水技術 (ISSN:09164154)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.10, pp.1-8, 2007-10
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 高松にダム7杯分の地下水:阻石クレータか,カルデラ跡か
- 著者
- 川崎 憲介
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.6, pp.376, 1995
1 0 0 0 P04 四国高松南部のクレータの構造(ポスター講演)
1 0 0 0 高松南部のクレーター状構造
- 著者
- 河野芳輝
- 雑誌
- 地震学会1991年秋季大会講演要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.99, 1991
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 高松クレーター論争の検証
- 著者
- 長谷川 修一
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用地質学会
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.336-344, 2010-02-10
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
高松クレーターは, 重力探査によって発見された伏在陥没構造で, 高松平野南部の仏生山町を中心に直径約4km, 深さ千数百mの規模と推定されている. 高松クレーターをめぐっては, 1994年から約10年間, その成因と渇水時の地下水源としての利用について論争が続いた. 高松クレーター論争は, 学会における議論により, 「夢」と「ロマン」と「渇水の切り札となる水源」として, マスメディアの報道が先行した特異な事例である. また, 高松クレーターの報道によって, 行政が水源調査を行い, 民間会社が温泉事業に投資し, 市民が地域おこしの題材とするなど, 単なる科学論争を超えた社会現象になった. 本稿では, 高松クレーターに関する論争と新聞報道を検証し, 応用地質学の市民生活に貢献のあり方を考察した. 高松クレーターでは, 日本初の隕石衝突孔なら, 地底湖があればと市民に期待をいだかせる報道に対して応用地質学の論理展開を軸に表層地質, 物理探査およびボーリング試料の分析・試験データに基づき繰り返し反論・説明することによって, 一方的な科学情報による地元の混乱と科学者や技術者の信用失墜を未然に防止することができた.
1 0 0 0 OA 女子大生の咀嚼筋活動度と咀嚼能力の関係
- 著者
- 松田 秀人
- 出版者
- 学校法人滝川学園 名古屋文理大学
- 雑誌
- 名古屋文理短期大学紀要 (ISSN:09146474)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.13-17, 2001-03-31 (Released:2019-07-01)
咀嚼筋(咬筋と側頭筋前部)の活動度と咀嚼能力の関係を調べた.女子大生(19〜20歳)126人を対象として, 咀嚼能力を咀嚼能力測定ガムで測定した結果, 咀嚼能力が強い群が18名, 咀嚼能力が標準の群が92名, 咀嚼能力が弱い群が16名であった.各群の咀嚼筋の活動度を皮膚温の上昇度として把握した.皮膚温はサーミスター温度計で測定した.皮膚温の測定部位は, 咬筋中央部(左右)と側頭筋前部(左右)の合計4ヶ所とした.皮膚温測定中の咀嚼は, 咀嚼ガムを用い, 各自の一定のリズムで10分間咀嚼させた.その結果咀嚼能力が強い群は, 普通群や弱い群に比べて皮膚温の上昇度が有意に高いことがわかった.したがって, 咀嚼能力が強い群ほど咀嚼筋の活動が高く, 咀嚼能力が低い群ほど咀嚼筋の活動が低いことが判明した.
1 0 0 0 OA 房総半島南部から相模湾及び伊豆海嶺上の親潮中層水の分布
- 著者
- 野秋 誠治
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.94-99, 2020-06
- 著者
- 川上 真理
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.91-93, 2020-06
1 0 0 0 災害アーカイブ : 資料の救出から地域への還元まで[白井哲哉著]
- 著者
- 天野 真志
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.74-80, 2020-06