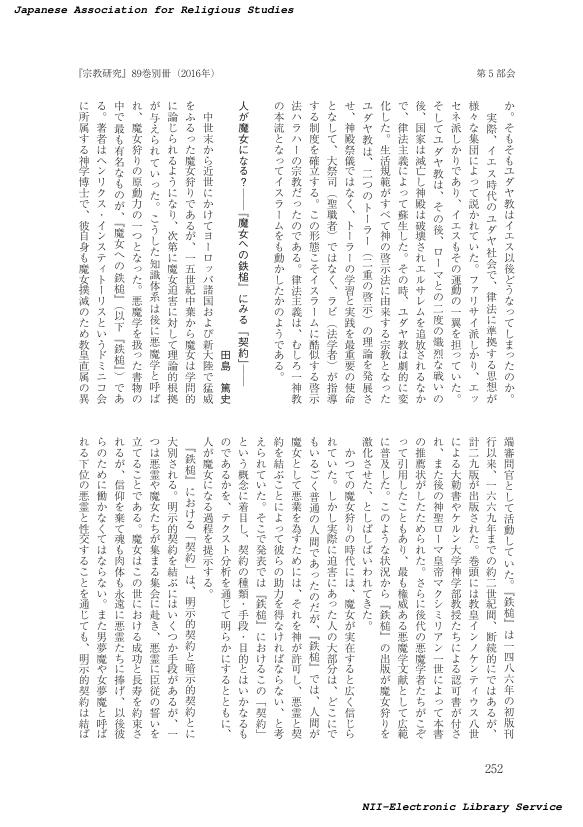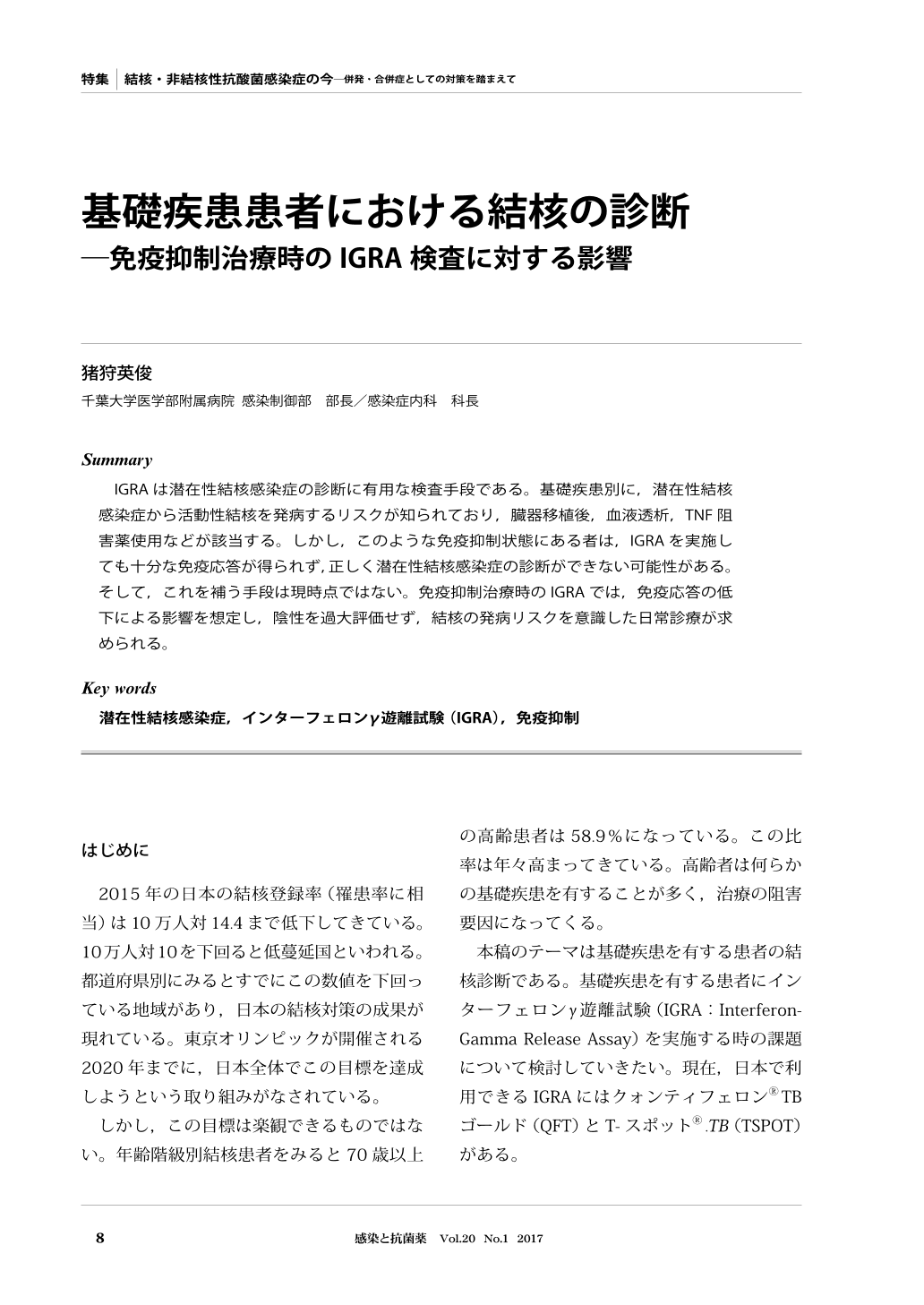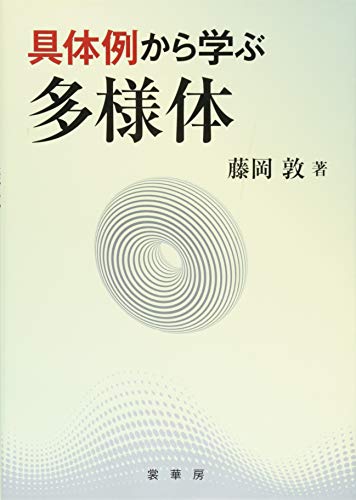1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1917年03月10日, 1917-03-10
1 0 0 0 OA ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化とその保護と継承
- 著者
- 江原 絢子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.320-324, 2015 (Released:2015-09-05)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 移築過程からみる明治期滋賀院の特徴について
- 著者
- 小柏 典華
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.773, pp.1547-1555, 2020
- 被引用文献数
- 1
<p> This study seeks to examine, through the analysis of historical materials, the reconstruction process of the SHIGA-IN temple built during the Meiji period, after being burned down in 1877. This study used historical materials from the Eizanbunko Library.</p><p> </p><p> The paper is organized as follows:</p><p> 1. "A restoration figure" that sheds light on the precincts' composition in the Meiji-period, modern era.</p><p> 2. It was followed by the temple's functions and precincts' composition in Edo-period, early modern era.</p><p> 3. According to the outline of the reconstruction process, "Nikai-syoin" was relocated from SEIKAN-IN temple, "Oku-noma" from GOKURAKUBO temple, "Omote-noma" from HOUMAN-IN temple, "Daidokoro" from KEISOKU-IN temple, and "Butsuden" from ZIGENDO temple.</p><p> 4. All of the historical buildings are arranged skillfully, especially considering the fact that the difference of altitude in the precincts is marked by "Ishigaki, " that is, stone high wall. The others include change of direction and three-dimensional arrangement of the historical buildings in a small precinct.</p><p> 5. The historical buildings in the Meiji-period still exist.</p><p> 6. A new function for the utilization of the minimum remodeling process was added.</p>
1 0 0 0 OA 悲劇と統計 : スターリンは本当にそんなことを言ったのか?
- 著者
- 沼野 充義
- 出版者
- 現代文芸論研究室
- 雑誌
- れにくさ : 現代文芸論研究室論集
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.13-18, 2010-12-27
エッセイ
1 0 0 0 科学計量学と評価 (特集 「科学を評価する」を問う)
- 著者
- 調 麻佐志
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.16-28, 2013-07
- 著者
- 田島 篤史
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.Suppl, pp.252-253, 2016-03-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 田尻 絵里 重黒木 彩乃 畑本 陽一 吉村 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.269-279, 2020 (Released:2020-05-29)
- 参考文献数
- 30
異なるエネルギーの清涼飲料水の摂取が朝食と1日の食事摂取量に及ぼす影響, および習慣的な身体活動と補償効果の関連を検討することを目的とし, 無作為クロスオーバー試験 (エネルギーのある甘味料入り清涼飲料水 ; sweetener群 (以下, S群) ; 225 kcal vs. エネルギーのない人工甘味料入り清涼飲料水 ; artificial sweetener群 (以下, AS群) ; 0 kcal) を実施した. 対象者は月経後2週間以内の女性16名 (平均21.6±0.5歳) とした. 飲料摂取前, 摂取後0, 20, 40, 60, 120, 150分に血糖測定と主観的食欲を評価し, 飲料摂取後60分に自由摂食の朝食を提供した. 150分以降は自由生活とし, その後1日のエネルギー摂取量を評価した. さらに, 対象者は実験日を除く任意の1週間加速度計付活動量計を装着し習慣的な1日の身体活動を評価した. AS群はS群と比較して朝食摂取前までの血糖値は有意に低かった (p<0.010) が, 朝食後の飲料摂取後120分では有意に高かった (p=0.004). 主観的食欲は飲料摂取後60分のときAS群が有意に高かった (p=0.034). 一方, 飲料のエネルギーを含む朝食及び1日の総エネルギー摂取量はAS群よりS群で有意に高く (p<0.010), エネルギー摂取量の補償効果は認められなかった. 習慣的な身体活動量と補償効果の間には有意な相関関係は認められなかった. 本研究より, 異なるエネルギーの清涼飲料水の摂取は血糖値と主観的食欲に影響するが, その後の食事摂取量には影響しないことが示唆された.
- 著者
- 澤村 美幸
- 出版者
- 東北大学大学院文学研究科東北文化研究室
- 雑誌
- 東北文化研究室紀要 (ISSN:13430939)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.87-79, 2010-03-30
1 0 0 0 鎌倉市由比ヶ浜地域出土中世人骨の刀創
- 著者
- 平田 和明 長岡 朋人 星野 敬吾
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological science. Japanese series : journal of the Anthropological Society of Nippon : 人類學雜誌 (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.1, pp.19-26, 2004-06-01
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3 14
鎌倉市の由比ヶ浜地域には大量の中世人骨が出土している静養館遺跡,由比ヶ浜南遺跡(単体埋葬墓),中世集団墓地遺跡(No. 372)および材木座遺跡の4遺跡があり,これらの出土人骨の刀創の特徴を比較検討した。刀創受傷率は材木座遺跡が最も高く65.7%であり,次に静養館遺跡が6.6%で,中世集団墓地遺跡は1.4%,由比ヶ浜南単体埋葬人骨は1.3%であった。刀創人骨のうちの斬創が占める割合は,静養館遺跡が100%,由比ヶ浜南遺跡が66.6%,中世集団墓地遺跡が75.0%,材木座遺跡が2.7%であった。一方,掻創が占める割合は材木座遺跡が82.3%で圧倒的に高く,中世集団墓地遺跡は2個体だけで25.0%,静養館遺跡と由比ヶ浜南遺跡の出土人骨には掻創は認められなかった。由比ヶ浜地域(前浜)は主として14世紀に中世都市鎌倉の埋葬地として使用されたと考えられるが,遺跡間および同一遺跡内の各墓抗間においても人骨の埋葬形態に差異があることが明らかであり,今後の広範囲な分野から更なる解析・検討が必要である。<br>
IGRAは潜在性結核感染症の診断に有用な検査手段である。基礎疾患別に、潜在性結核感染症から活動性結核を発病するリスクが知られており、臓器移植後、血液透析、TNF阻害薬使用などが該当する。しかし、このような免疫抑制状態にある者は、IGRAを実施しても十分な免疫応答が得られず、正しく潜在性結核感染症の診断ができない可能性がある。そして、これを補う手段は現時点ではない。免疫抑制治療時のIGRAでは、免疫応答の低下による影響を想定し、陰性を過大評価せず、結核の発病リスクを意識した日常診療が求められる。
- 著者
- 中小路 駿逸
- 出版者
- 追手門学院大学文学部アジア文化学科
- 雑誌
- アジア文化学科年報 (ISSN:13448331)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.32-42, 2002-11
1 0 0 0 看護師における共依存傾向とその影響についての検討
- 著者
- 森 秀美 長田 久雄
- 出版者
- 日本ヒューマン・ケア心理学会
- 雑誌
- ヒューマン・ケア研究 (ISSN:18812945)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.46-54, 2006-08
1 0 0 0 OA 第35回日本医学教育学会大会予稿集
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.Supplement, pp.12-78, 2003-07-25 (Released:2011-08-11)
1 0 0 0 OA 膵島所見を観察しえた緩徐進行1型糖尿病の一例―過去の報告例とまとめ―
- 著者
- 佐々木 衛 東 宏一郎 小澤 裕理 森本 二郎 鈴木 裕也 丸山 太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.187-191, 2011 (Released:2011-04-22)
- 参考文献数
- 8
症例は診断時58歳,男性.1988年,体重減少を主訴に近医を受診し糖尿病と診断された.当院に教育入院し,SU薬で良好なコントロールを得たが,1990年より血糖コントロール不良となり,1991年にインスリンを導入された.1990年の保存血清でGAD抗体が1.112(cut off値:0.02)と陽性であることが判明し,緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM)と診断された.2007年にはインスリン分泌が枯渇状態となり,GAD抗体は14.9 U/mlと減少した.同年に大腸癌が発見され,手術時に患者,家族の承諾を得て膵生検を施行した.膵組織所見は,膵島面積が減少し,正常膵島はほとんど認められなかった.β細胞はほとんど消失し,明らかな膵島炎を認めず,1型糖尿病長期経過例の膵組織所見と類似していた.過去に報告されたGAD抗体陽性の膵組織所見と比較すると,高抗体価の場合には臨床的,組織学的に1型糖尿病と類似する点が多かった.
1 0 0 0 OA 糖尿病罹病期間30年で集学的治療にて寛解した糖尿病性腎症の1例
- 著者
- 安孫子 亜津子 磯江 つばさ 宮内 和誠 本庄 潤 上堀 勢位嗣 滝山 由美 伊藤 博史 長谷部 直幸 羽田 勝計
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.197-202, 2007 (Released:2009-05-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
症例は73歳男性で糖尿病罹病期間は約30年.1999年から尿タンパク陽性を指摘.2002年1月に尿中アルブミン1604 mg/gCreであり,その後他院の腎臓内科に下腿浮腫で入院時,尿蛋白1.2 g/日,24 hrCcr 68 ml/分であった.血糖は経口薬内服するもコントロール不良,血圧もアンジオテンシン受容体拮抗薬でコントロール不良であり,同年10月当院を紹介される.このとき随時尿の尿中アルブミンは773 mg/gCre, 神経障害,増殖網膜症も合併.2003年5月急性心筋梗塞発症.入院時,尿中アルブミン167 mg/gCre, 24 hrCcr 71 ml/分.インスリン治療を導入し,降圧薬の増量,抗血小板薬やスタチンも開始となる.退院後,血糖コントロールはHbA1c 7%前後で経過.1年後に尿中アルブミンは約50 mg/gCre, 2年後には12 mg/gCreに減少した.糖尿病罹病期間が長く,その他の合併症があっても,集学的治療で腎症の3期から1期への寛解がみられた.
1 0 0 0 OA 最新の電磁モータ
- 著者
- 百目鬼 英雄
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.7, pp.744-747, 2003-10-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 川井 彩音 熊谷 道夫
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2019年大会
- 巻号頁・発行日
- 2019-05-17
1. はじめに ミクラステリアス・ハーディは近年琵琶湖で発見された外来種のプランクトンであり2016年に琵琶湖で大発生し、2017年には小康状態となったが、2018年には再び大増殖した。 ミクラステリアス・ハーディは緑藻類ホシミドロ目ツヅミモ科ミクラステリアス属に位置付けられる。2つの半細胞で構成され、中央部に深い切れ込みがあり、この半細胞の側裂部は6本に見えるが大きく分けると3組の椀状突起からなっている。琵琶湖でもよく見られるミクラステリアス・マハブレッシュワレンシスと比較するとやや椀状突起が細くて、長いのが特徴である(一瀬諭 2016)。 これまでにミクラステリアス・ハーディの形状(大きさの計測)・鉛直分布(クロロフィルa濃度)・沈降速度について調べてきた。ミクラステリアス・ハーディが急激に増えたのは、近年の水温上昇と関連があるかもしれないと考えたので、本研究ではミクラステリアス・ハーディの水温依存性について培養実験を行った。2. 方法 キャピラリーを用いて試験管にミクラステリアス・ハーディを10個体ずつ入れ、その試験管を水温の違う水槽に入れ、1日おきに5回、全体で10日間の計測を行った。試験管の水には琵琶湖の水を100㎛でろ過したものを使用した。さらに、水槽ろ過装置を用いて水槽内に穏やかな水の動きを発生させ試験管を常時小さく揺らし続けた。◎準備したもの水槽3つ、試験管15本、試験管立て3つ、温度計、ミクラステリアス・ハーディ150個体、水温コントローラー2台、水槽ろ過装置3つ、キャピラリー琵琶湖の水1.5L(100mL×15本)、顕微鏡(実体顕微鏡・光学顕微鏡)3. 結果 ・2日目…室温:10個体 25℃:14個体 30℃:10個体 ・4日目…室温:14個体 25℃:27個体 30℃:18個体 ・6日目…室温:43個体 25℃:28個体 30℃:22個体 ・8日目…室温:28個体 25℃:12個体 30℃:22個体 ・10日目…室温:12個体 25℃:21個体 30℃:108個体 2日目から4日目にかけて25℃が14個体、27個体と順調に増え続けていたが、6日目に室温(18℃)が14個体から43個体と急激に増加した。30℃では8日目までは他の水温に比べて大きくは増殖しなかったが、10日目に大きく増殖した(8日目との個体差86個体)。また、クンショウモの仲間がとても多く増殖していた(20ml中に1047個体)。室温(18℃)では最初、増加傾向にあったものの6日目を境に減少した。100mlのサンプル1本を計測するのに3時間程度かかり、3本を計測しきるのにかなり時間がかかってしまった。4. 考察 ミクラステリアス・ハーディには水温によって増加の傾向が大きく異なる特性が見られることが分かった。ただ、試験管によって栄養の量が少しずつ違い、増殖スピードがずれた可能性があり、個々の試験管の個体数が変化したのかもしれない。30℃の試験管の8日目から10日目に大きく増殖したことから、増え続ける可能性がるため、10日目以降も調べてみたいと思った。30℃の試験管に多くクンショウモが増殖したことから、クンショウモの適性水温に近いのではないかと推測できた。5. 今後の展望 培養実験で個体数が減少するとは予想出来なかったので今後、深く突き詰めたいと思う。さらに、30℃の試験管でクンショウモが大きく増殖した原因を調査してみたい。また、今年は琵琶湖の呼吸ともいわれる全循環が各地点で十分に行われていないので、鉛直分布調査や観察を続け、ミクラステリアス・ハーディだけでなく琵琶湖のプランクトンやそれを取り巻く環境に及ぼす影響について調査していきたい。さらに、観察していく中で稀に見る奇形のミクラステリアス・ハーディの割合も調査してみたいと、とても興味をもった。沈降実験についても新たな実験方法を模索中であり、実験と同時にミクラステリアス・ハーディの体積なども調査できたらよいと思う。