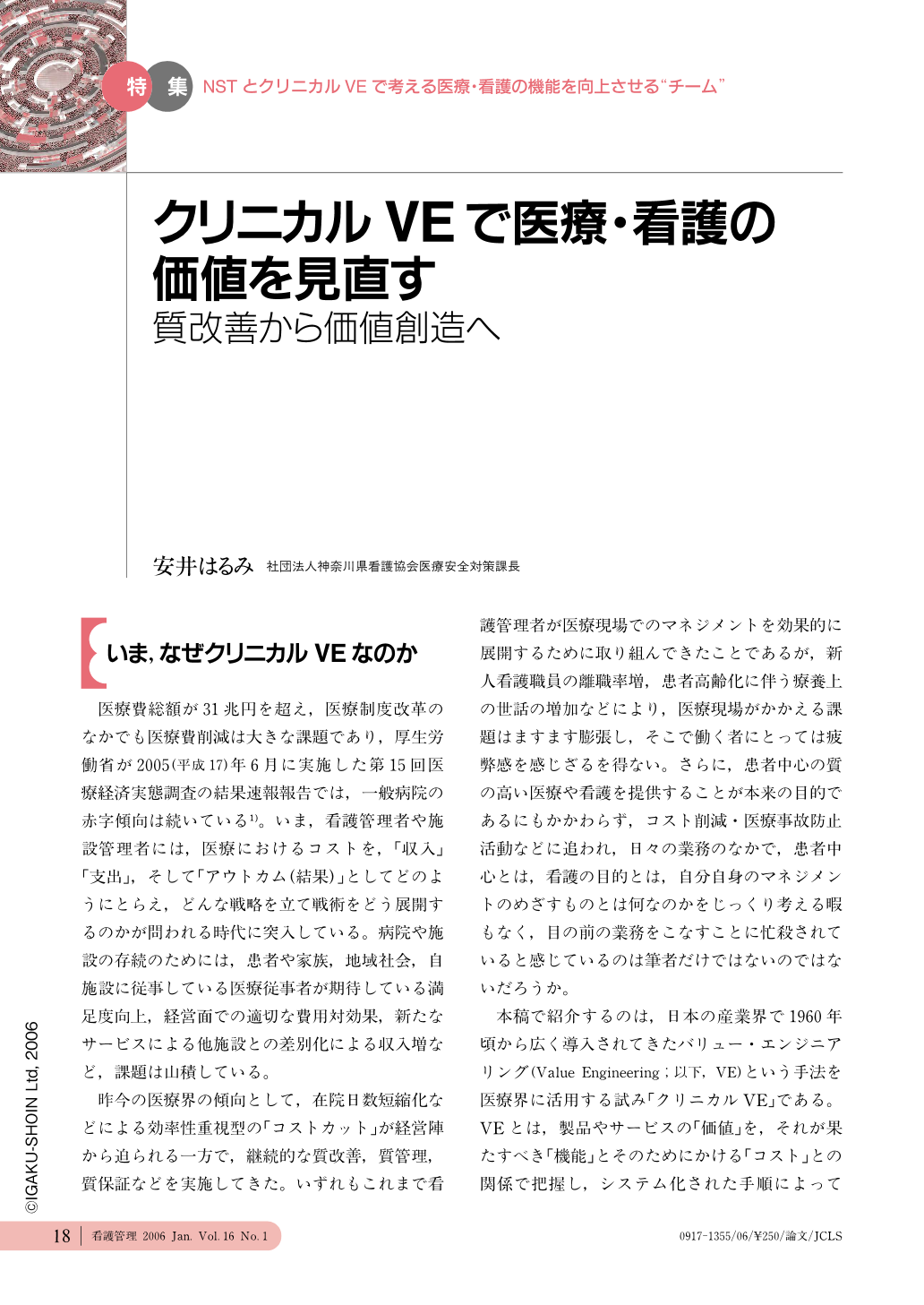1 0 0 0 OA 日本画と古代蛇信仰 ― 民俗学から見つめる日本画の隠れた本質 ―
- 著者
- 山﨑 宏
- 雑誌
- 桜美林論考. 人文研究 = The journal of J. F. Oberlin University. Studies in humanities (ISSN:21850690)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.223-237,
1 0 0 0 クリニカルVEで医療・看護の価値を見直す―質改善から価値創造へ
いま,なぜクリニカルVEなのか 医療費総額が31兆円を超え,医療制度改革のなかでも医療費削減は大きな課題であり,厚生労働省が2005(平成17)年6月に実施した第15回医療経済実態調査の結果速報報告では,一般病院の赤字傾向は続いている1)。いま,看護管理者や施設管理者には,医療におけるコストを,「収入」「支出」,そして「アウトカム(結果)」としてどのようにとらえ,どんな戦略を立て戦術をどう展開するのかが問われる時代に突入している。病院や施設の存続のためには,患者や家族,地域社会,自施設に従事している医療従事者が期待している満足度向上,経営面での適切な費用対効果,新たなサービスによる他施設との差別化による収入増など,課題は山積している。 昨今の医療界の傾向として,在院日数短縮化などによる効率性重視型の「コストカット」が経営陣から迫られる一方で,継続的な質改善,質管理,質保証などを実施してきた。いずれもこれまで看護管理者が医療現場でのマネジメントを効果的に展開するために取り組んできたことであるが,新人看護職員の離職率増,患者高齢化に伴う療養上の世話の増加などにより,医療現場がかかえる課題はますます膨張し,そこで働く者にとっては疲弊感を感じざるを得ない。さらに,患者中心の質の高い医療や看護を提供することが本来の目的であるにもかかわらず,コスト削減・医療事故防止活動などに追われ,日々の業務のなかで,患者中心とは,看護の目的とは,自分自身のマネジメントのめざすものとは何なのかをじっくり考える暇もなく,目の前の業務をこなすことに忙殺されていると感じているのは筆者だけではないのではないだろうか。
1 0 0 0 OA 水俣病に対する責任―発生・拡大・救済責任の問題をめぐって―
- 著者
- 丸山 定巳
- 出版者
- 環境社会学会
- 雑誌
- 環境社会学研究 (ISSN:24340618)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.23-38, 2000-10-31 (Released:2019-03-12)
水俣病問題には発生・拡大・補償救済の遅れという重大な3つの責任問題がある。そして,それぞれに原因企業に加え行政や医学それに地域社会などが深く関わってきた。原因企業チッソ(株)は,生産至上主義に徹し安全性を無視した経営を行ってきた。唯一の巨大企業として地域社会に君臨し,環境を私物化してそれを長期にわたって破壊し,ついには水俣病被害を発生させてしまった。行政もそうした企業の操業を容認し,環境破壊を未然に防止する規制を講じなかった。地元地域社会には,チッソの企業活動をコントロールする社会的勢力は存在しなかった。水俣病の発生が公的に確認された後の初期の調査で,それが魚介類を介していること,そしてその魚介類を有毒化している原因として工場排水が指摘されたにも関わらず,いずれの面でも対策が怠られた。チッソも行政も,有効な排水対策を怠った。地域社会も,チッソの操業を擁護する立場から排水規制の動きを牽制した。加えて,漁獲の法的禁止措置も講じられなかった。その一方で,原因工程の生産規模は拡大されていったために,さらに被害を拡大させてしまった。補償救済問題においても,チッソは当初は責任を認めず低額で処理した。公式に責任が確定した後は,チッソに自力補償能力がなくなり,代わって行政が「認定医学」を利用して補償対象者を制限したため,長期にわたり大量の被害者が放置される状態が続いた。現在,地元地域社会では,過去を反省して「もやい直し」をキーワードにした地域の再生が目指されているが,「チッソ運命共同体意識」からの解放が鍵となっている考えられる。
1 0 0 0 OA 水俣病認定患者の健康と生活の実態に関する調査研究,1999
- 著者
- 牛島 佳代 北野 隆雄 二塚 信
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.395-400, 2003-09-15 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 2
Objectives: To clarify the needs and to consider establishing a social support system for patients with Minamata disease (MD), or methylmercury poisoning, by investigating their health and socioeconomic conditions.Methods: The total number of people certified as having MD in May 1999 by the Kumamoto and Kagoshima Prefecture Government Committees on MD was 2265. We sent two questionnaires to 917 individuals who were surviving at that time, which corresponded to 40.5% of the total number of MD patients. The first survey sought information on the individual's health-seeking behavior, and the second survey was about their socio-economic conditions and requirements for welfare and medical care in the future.Results: The average age among male patients was 68.0±13.2yrs (n=477) and that among female patients was 71.2±13.0yrs (n=440). The response rates were 45.7% (n=416) for the first questionnaire and 38.6% (n=354) for the second questionnaire. Among the MD patients, 71.7% judged their health condition to be ‘bad’ or ‘very bad’, and 97.4% received medical treatments that included acupuncture or moxacautery and massage. Regarding the activity of daily living (ADL), which includes ‘communicating’, ‘walking’, ‘eating’, ‘use of toilet’, ‘dressing’ and ‘taking a bath’, the rates of ‘independent’ were relatively low among those under 49yrs and those over 75yrs compared with the other age groups. Many individuals emphasized that they had anxiety about their health and health care in the future.Conclusion: We concluded that the quality of life (QOL) of MD patients was low. It is important to consider developing a social support system for MD patients.
1 0 0 0 競走馬調教法 : 濠洲の馬は人と語る
- 著者
- ウイリアム・マグリツヂ [著]
- 出版者
- 東京競馬倶楽部
- 巻号頁・発行日
- 1928
- 著者
- Satoru Yokoi
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.16A-001, (Released:2020-05-15)
- 被引用文献数
- 4
Given vigorous mean diurnal variation (MDV) of cumulus convection and surface wind over coastal waters of Indonesian Maritime Continent, surface sensible and latent heat fluxes (SHF and LHF) are expected to also exhibit significant MDV. However, it is difficult to grasp characteristics of MDV of these fluxes due to lack of surface observation data. Recently, two intensive observation campaigns were conducted off the west coast of Sumatra Island in boreal winter, which offer us a unique opportunity to examine the characteristics of convection and the fluxes. This study analyzes these observations to reveal that the MDV of both SHF and LHF has considerable amplitude compared with the average. The MDV of SHF is primarily caused by that in surface air temperature, which is due to the MDV of the convection. As for LHF, the MDV is primarily caused by that of surface wind speed, in which both the MDV of convection and sea/land breezes play roles. Furthermore, there are qualitative differences in the MDV of the fluxes between the two campaign periods, which can be explained from the viewpoint of differences in phase and intensity of MDV of convection and the sea/land breezes.
1 0 0 0 OA 官僚の政治的コントロールに関する数量分析の試み
- 著者
- 建林 正彦
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.201-227,353, 2005-11-10 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 17
This article examines the relationship between politicians and bureaucrats in postwar Japan. The author argues that the governing Liberal Democratic Party (LDP) has manipulated bureaucrats' policy preferences towards the LDP's ideal position by using “ex ante control” such as recruitment and promotion policy. With the framework of the principal-agent model, the author claims that the spurious autonomy of Japanese bureaucrats can be interpreted as the outcome of successful control over bureaucrats' preferences by LDP politicians. The paper provides evidence with a quantitative analysis of surveys conducted in 1976-77 and 2001-2002. For example, the closer the policy preference of the bureaucrat is to the ideal position of the LDP, the wider he tends to find his discretion.
1 0 0 0 電場を用いた誘導自己組織化による動的パターン形成制御法の開発
本研究は,電子線により誘導されるナノ電場(バーチャル電極)を用いて分子間の静電相互作用などの分子間力を操作することにより,ソフトマターがつくる自己組織化構造を動的に誘導する制御インタフェースを構築することを目的としている.本年度は,人工脂質二重膜の流動性パターニングや相分離ドメイン構造の誘導への応用について研究を行った.DOPC(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine),DPPC(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine),コレステロールと蛍光標識された脂質を含む脂質二重膜を自発展開法によって厚さ100 nmの窒化ケイ素(SiN)膜上に形成し,SiN薄膜を介して加速電圧2.5 kVの電子線を間接的に照射したときの蛍光強度の変化を計測した.その結果,電子線の照射領域において蛍光強度の減少が見られ,電子線照射終了後には蛍光強度の急速な回復が見られた.これは,電子線による電場によってSiN薄膜の表面エネルギーが変化したことにより,脂質分子がSiN薄膜上から脱離したあと,照射領域外から脂質分子が再展開したためであると考えられる.さらに,蛍光強度の回復が見られたあとドメイン構造の成長が観察された.コレラ毒素Bサブユニットが特異的に吸着する糖脂質を混ぜて同様の実験をした結果,成長したドメイン構造においてコレラ毒素Bサブユニットの吸着量が多くなり,このドメイン構造が液体秩序相であることを示唆する結果が得られた.以上の結果から,人工脂質二重膜の流動性を電子線によるバーチャル電極により制御することで,人工脂質二重膜のドメイン構造を動的に誘導できることが実証された.開発された制御インタフェースは人工脂質二重膜を用いたデバイスのラピットプロトタイピングなどへ応用できると考えられる.
1 0 0 0 OA 権藤成卿の思想構造
- 著者
- 井田 輝敏 Terutoshi Ida 九州国際大学法学部
- 雑誌
- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.6, pp.432-390, 1998-02-01
1 0 0 0 OA ディジタルゲームにおける人工知能技術の応用(<特集>ゲームAI)
- 著者
- 三宅 陽一郎 Youichiro Miyake
- 雑誌
- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.44-51, 2008-01-01
1 0 0 0 OA 化学合成細菌と物質フロー:生物地球化学と生態学の交差点
- 著者
- 瀬戸 繭美
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 地球化学 (ISSN:03864073)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.185-193, 2017-12-25 (Released:2017-12-25)
- 参考文献数
- 56
Biogeochemistry is the study of how organisms alter the earth's surface geochemical processes. Meanwhile, ecosystem ecology is the study of how materials and energy flow and are stored among organisms and environments. Although there is significant crossover between these two fields, some research topics are not overlapped. For instance, chemoautotrophic microorganisms that harness energy from redox reactions and gain carbon from inorganic carbon substances are of geochemical interest because of their catalytic effects on biogeochemical reactions, whereas those communities have not seemed to get much ecological attentions. Two reasons can potentially explain this; 1) the main target organisms in ecology have been flora and fauna, and their carbon storage and cycling is a cornerstone concept of ecosystem ecology; 2) the difficulty in oveservation and isolation of chemoautotrophic microorganisms have long inhibited the progress of their ecological understanding. In bringing together the biogeochemical and ecological perspectives, however, recent studies have accelerated our understanding the interactions between the ecology of chemolithoautotrophs and material flows for the last decade.
1 0 0 0 竹友藻風小見 : 前田純孝の周辺(1)
- 著者
- 佐藤 隆一
- 出版者
- 大阪城南女子短期大学
- 雑誌
- 大阪城南女子短期大学研究紀要 (ISSN:03884929)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.1-19, 2011
- 著者
- 西脇 暢子
- 出版者
- 日本大学経済学部産業経営研究所
- 雑誌
- 日本大学経済学部産業経営研究所所報 (ISSN:02884437)
- 巻号頁・発行日
- no.68, pp.50-54, 2011-03
1 0 0 0 IR 「下衆の詞には、かならず文字あまりたり」考
- 著者
- 安東 大隆
- 出版者
- 別府大学国語国文学会
- 雑誌
- 別府大学国語国文学
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.18-22, 1986-12
1 0 0 0 OA 吸水性樹脂の保水剤としての利用
1 0 0 0 IR 「悟浄歎異」をめぐって : 中島敦の方法確立期
- 著者
- 濱川 勝彦
- 出版者
- 松蔭女子学院大学
- 雑誌
- 文林 = Bunrin (ISSN:02886170)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.25-49, 1971-03-20
1 0 0 0 弔辞・訃報 夢のある仏教学--追悼・平川彰先生
- 著者
- 加藤 純章
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度学仏教学研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.727-731, 2003-03
1 0 0 0 OA 調整的音楽療法(RMT)の実践と展望-マインドフルネスとの関連性-
- 著者
- 國吉 知子 Tomoko KUNIYOSHI
- 雑誌
- 神戸女学院大学論集 = KOBE COLLEGE STUDIES
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.65-80, 2013-12-20
調整的音楽療法(RMT)とは、受動的音楽療法の一つで、音楽を聴取する間、意識を「音楽」「身体」「思考・感情・気分」に偏りなく向け続けることで、誤った緊張を調整するものである。これまでの研究から、RMTは自己覚知の亢進や脱中心化に有効であることがわかってきている。しかし、RMTは意識の適切な使い方についての一種のメンタルトレーニングであるため、特に初心者にとってMRTの内的課程は複雑で理解されにくいように思われる。本稿では新しくRMTを実施しようと考える実践者に役立つMRT実施上の留意点を含め、実際的な手順について詳細な解説をおこなった。また、これまでのRMTについての研究を概観し、今後のRMT研究についての方向性を示唆した。さらに、RMTの方法や内的プロセスとの比較からマインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)との関連について言及するとともに、マインドフルネス・エクササイズを取り上げ、RMTとの類似性について検討した。