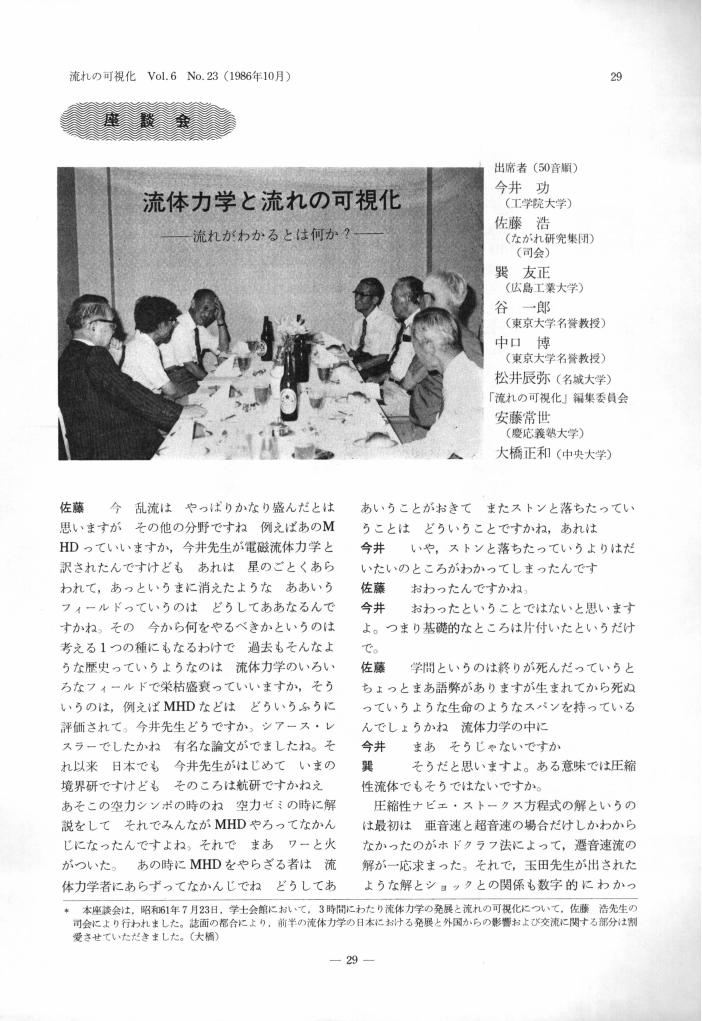3 0 0 0 OA 日本型オムニチャネルの特質と理論的課題
- 著者
- 近藤 公彦
- 出版者
- 日本商業学会
- 雑誌
- 流通研究 (ISSN:13459015)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.77-89, 2018 (Released:2018-03-31)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 1 2
ICTの発展を背景に,小売業の新たな成長モデルとしてオムニチャネルが大きく注目されている。オムニチャネルは歴史的に,電子商取引,クリック&モルタル,マルチチャネル,クロスチャネルから発展し,消費者にシームレスな買い物経験を提供するための統合的なチャネル管理を中心的な課題としてきた。オムニチャネルは米国のそれを標準型として研究されてきたが,その態様は各国の小売環境のもとでの企業の成長プロセスに規定される。米国型オムニチャネルが単一業態オムニチャネルを基本としているのに対し,日本型オムニチャネルは複数の業態から構成される多業態オムニチャネル,およびロジスティクス・ハブとしての店舗ネットワークの2つから特徴づけることができる。この日本型オムニチャネルを理論的に研究する際,多業態オムニチャネル,オムニチャネル・オペレーション,チャネル・コンフリクトとカニバリゼーション,オムニチャネル小売企業の出自,オムニチャネル行動のプロセス,オムニチャネル・ショッパーの特性,定性的・定量的アプローチ,および国際比較の8つの重要な課題が指摘される。
3 0 0 0 OA IoT プラットフォーム市場の高付加価値化
- 著者
- 高橋 浩
- 出版者
- 特定非営利活動法人 横断型基幹科学技術研究団体連合
- 雑誌
- 横幹 (ISSN:18817610)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.39-50, 2019 (Released:2019-04-12)
- 参考文献数
- 22
IoT has attracted attention as a method for transferring the non-digital world to the digital world. And the launch of the IoT platform is generalized for entry into this field. However, the launch of the business based on the IoT platform has not been scaled and there is a big difference compared with the platform business by GAFA and the sharing economy represented by Uber, Airbnb. Meanwhile, it is anticipated that IoT equipment popularization will reach 20 billion by 2020. There is a big gap between these two situations. Therefore, in this paper, I explore the cause of the above gap and consider solutions for high added value specific to IoT field. Focus mainly on scaling the IoT system, such as appropriate choice of platform governance and trade-offs.
3 0 0 0 OA ATPのエネルギーとはなにか?
- 著者
- 児玉 孝雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.094-095, 2010 (Released:2010-03-30)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- Yasuaki Takeji Hiroki Shiomi Takeshi Morimoto Yutaka Furukawa Natsuhiko Ehara Yoshihisa Nakagawa Takao Kato Junichi Tazaki Eri Toda Kato Hidenori Yaku Yusuke Yoshikawa Tomohisa Tada Michiya Hanyu Kazushige Kadota Tatsuhiko Komiya Kenji Ando Takeshi Kimura CREDO-Kyoto PCI/CABG Registry Cohort Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-19-0980, (Released:2020-01-29)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 7
Background:The effect of diabetes mellitus (DM) status on the long-term risk for heart failure (HF) in patients undergoing coronary revascularization has not been adequately evaluated.Methods and Results:In this study, 15,231 patients who underwent coronary revascularization in the CREDO-Kyoto Registry Cohort-2 were divided into 2 groups according to DM status (DM group: n=5,999; Non-DM group: n=9,232). The DM group was further divided into 2 groups according to insulin treatment (insulin-treated DM [ITDM]: n=1,353; non-insulin-treated DM [NITDM]: n=4,646). The primary outcome measure was HF hospitalization. The cumulative 5-year incidence of HF hospitalization was significantly higher in the DM than non-DM group (11.0% vs. 6.6%, respectively; log-rank P<0.0001), and in the ITDM than NITDM group (14.6% vs. 10.0%, respectively; log-rank P<0.0001). After adjusting for confounders, the increased risk of HF hospitalization with DM relative to non-DM remained significant (hazard ratio [HR] 1.47, 95% confidence interval [CI] 1.30–1.67, P<0.0001), whereas the risk associated with ITDM relative to NITDM was not significant (HR 1.17, 95% CI 0.96–1.43, P=0.12).Conclusions:The adjusted long-term risk for HF hospitalization after coronary revascularization was significantly higher in DM than non-DM patients, regardless of revascularization strategy, but did not differ between ITDM and NITDM patients.
3 0 0 0 OA 大学新入生に対するアサーション・トレーニングの効果
- 著者
- 安達 知郎 安達 奈緒子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.317-329, 2019-12-30 (Released:2020-01-24)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 5
大学入学時,学生は新しい環境への適応,新たな自己像の確立という2つの課題と直面する。これらの課題に学生が向き合えるよう予防的に支援することが重要である。本研究の目的は,大学新入生に対してアサーション・トレーニングを実施した場合,実施しなかった場合に比べ,自己主張,他者尊重,視点取得,怒り表現,適応感,アイデンティティ,自己受容に正の影響がみられるか,および,アサーションに対する効果とそれ以外に対する効果との間に関連がみられるかを検討することであった。大学新入生を介入群28名,対照群33名に振り分け,質問紙調査をトレーニング実施直前,実施直後,2ヶ月後,6ヶ月後に実施した。分析対象者は介入群,対照群ともに最後まで調査協力が得られた26名であった。分散分析の結果,自己主張,怒り表現,適応感,アイデンティティ,自己受容に中から大の効果がみられた。最後に,結果をアサーション・トレーニングの理念,大学生の対人関係の特徴といった観点から考察した。
3 0 0 0 OA 農薬代謝におけるグルタチオンS-トランスフェラーゼの役割
- 著者
- 宍戸 孝
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.Special, pp.465-473, 1978-12-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1 1
This review summarizes recent research on the metabolism of pesticides by GSH conjugation, the role of this reaction in pesticide selectivity in mammals and plants, and characteristics of GSH S-transferases. GSH conjugation occurs with organophosphorus insecticides, γ-BHC, organothiocyanate insecticides, s-triazine herbicides, thiocarbamate sulfoxides, fluorodifen, EDB and monofluoroacetic acid. GSH S-transferases are widely distributed in mammals, birds, fishes, insects, plants and microorganisms. The highest activity is found in the mammalian liver and microorganisms are low activity. Plant enzymes are very stable. GSH S-transferases from mammals and insects comprise a group of enzymes which have overlapping substrate specificities. Chemical structures possessing an electrophilic center, high SN reactivity, and the reactive center of low electron density can conjugate readily. The formation of a GSH conjugate destroys the biocidal properties of the parent molecule. The function of GSH S-transferases may be regarded as biological protection against electrophilic foreign compounds which have the capacity to bind to biological molecules with nucleophilic centers. The qualitative and quantitative differences in GSH S-transferases distributed in various organisms are closely associated with insecticide or herbicide selectivity and insecticide resistance. Dichloroacetamide antidotes act in corn to induce GSH and GSH S-transferase, resulting in rapid detoxication of thiocarbamate sulfoxides.
3 0 0 0 OA 鏡像認知の論理
- 著者
- 小亀 淳
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.319-337, 2005 (Released:2009-10-16)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
Current explanations for the mirror reversal problem assume in common left and right symmetry and⁄or the three dimensional rotation about a vertical axis as the necessary condition. However, it is possible to prove that such theories include logical contradiction because of confusing understanding of the meaning of reversal on images of various objects placed in front of the plane mirror. To obtain right answer, first of all, we should have correct understanding about what is the true meaning of the mirror reversal problem itself, and also should understand different cognitive methods of the reversal of direction. A new reliable solution of the problem independent of these two assumptions (symmetry and rotation) is proposed using a new definition of our right and left based on the clockwise or counterclockwise rotation. In addition, by a “vision coordinate system” or “head axes” which can be physically defined, the logic explaining the mirror reversal becomes simpler and broadly available for sophisticated cases of human mirror images
3 0 0 0 OA 社会目標としてのコミュニティ
- 著者
- 倉沢 進
- 出版者
- コミュニティ政策学会
- 雑誌
- コミュニティ政策 (ISSN:1348608X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.35-51, 2008 (Released:2013-03-28)
- 被引用文献数
- 1
本稿の主たる論点は、以下の3点である。(1)1960 ~ 70年代のコミュニティ政策の経緯と背景 (1969年の国民生活審議会コミュニティ小委員会の成立・報告の経緯、背景としての社会開発、日本の状況に対する適用、自治省コミュニティ研究会の成立と各界の反応など)。(2)自治省コミュニティ研究会の論議と施策の展開(特に施設計画と活動計画、センター設置の制度化・全国配置をめぐる都市工学者と社会学者の意見の相違など)。(3)1970年代コミュニティ政策の評価と社会学の寄与 (親交的コミュニティと自治的コミュニティ (問題解決型)、センター建設への矮小化、専門処理システムと相互扶助システムの理論など)。
3 0 0 0 OA 骨粗鬆症の危険因子としての慢性の精神的ストレス
- 著者
- 東 華岳 安達 泰弘 林 春樹 久保 金弥
- 出版者
- The University of Occupational and Environmental Health, Japan
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.245-253, 2015-12-01 (Released:2015-12-13)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 14 37
骨粗鬆症は骨量の減少と骨質の劣化が特徴で,骨折しやすくなるもっとも一般的な代謝性骨疾患である.超高齢社会の到来を受け,骨粗鬆症は大きな社会問題になっている.一方,生体はつねにさまざまなストレスにさらされ,その生理機能に影響を及ぼしている.最近の研究によれば,慢性の精神的ストレスがさまざまなシグナル経路を介し骨粗鬆症の危険因子である.本総説では,慢性の精神的ストレスと骨粗鬆症との関連性について,最近の進展状況を概説する.中枢神経系,特に視床下部による骨代謝調節機構の存在が明らかにされてきた.ヒトおよび動物研究によると慢性の精神的ストレスが視床下部-下垂体-副腎皮質系,交感神経系,および内分泌・免疫系への影響を介して骨量を低下させ,骨質を悪化させる.噛む動作にはストレス緩和作用があることが証明されている.噛む動作は,ストレス誘発神経内分泌反応を弱め,ストレス性骨量減少を改善する.したがって,噛む動作は,慢性の精神的ストレスに関連する骨粗鬆症の予防・治療において,有用なアプローチになりうる.また,慢性の精神的ストレス,噛む動作と骨粗鬆症との相互関係についてのメカニズムも考察した.慢性の精神的ストレスは視床下部-下垂体-副腎皮質系と交感神経系を活性化させ,性ホルモンと成長ホルモンを抑制し,炎症性サイトカインを増加させ,骨形成の抑制と骨吸収の促進により最終的に骨量減少を引き起こす.
- 著者
- Kenji Suetsugu Hiroshi Hayakawa
- 出版者
- The Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.205-208, 2019-10-31 (Released:2019-11-28)
The discovery of Spiranthes hongkongensis S. Y. Hu & Barretto (Orchidaceae) on Ishigaki Island, Japan, during herbarium studies in KPM is reported. Previously, S. hongkongensis was reported only from China (Guangdong, Hong Kong, Taiwan), and Malaysia (Borneo). Spiranthes hongkongensis is morphologically similar to S. australis, but is distinguishable by the membranous, narrow, truncate rostellum attached to the middle of the pollinia without a viscidium, shorter column and distinctly 3-lobed stigma.
3 0 0 0 OA 両大戦間期のアルジェリア植民地体制
- 著者
- 宮治 一雄
- 出版者
- Japan Association for African Studies
- 雑誌
- アフリカ研究 (ISSN:00654140)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.18, pp.7-14, 1979-03-30 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 11
- 著者
- Kyoung-Sim Jung Hwi-Young Cho Tae-Sung In
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.940-944, 2016 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 10 26
[Purpose] This study examined the effects of trunk exercises performed on an unstable surface on trunk muscle activation, postural control, and gait speed in stroke patients. [Subjects] Twenty-four participants with stroke were recruited in this study and randomly distributed into experimental (n = 12) and control groups (n = 12). [Methods] Subjects in the experimental group participated in trunk exercises on the balance pad for 30 min, five times a week for 4 weeks; those in the control group performed trunk exercises on a stable surface for 30 min, five times a week for 4 weeks. Trunk muscle activation was measured by using surface electromyography, and trunk control was evaluated with the Trunk Impairment Scale (TIS). Gait speed was measured with the 10-Meter Walk Test. [Results] Activity of the external and internal oblique muscles in the experimental group was significantly higher than that in the control group. The TIS score of the experimental group showed significantly greater improvement than did that of the control group. The 10-Meter Walk Test (10MWT) score also significantly improved in the experimental group. [Conclusion] Trunk exercises on an unstable surface improve trunk muscle activation, postural control, and gait speed in patients with hemiparetic stroke.
3 0 0 0 OA 推論と判断の等確率性仮説:思考の対称性とその適応的意味
- 著者
- 服部 雅史
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.408-427, 2008 (Released:2010-02-15)
- 参考文献数
- 61
- 被引用文献数
- 8
Many fallacies and biases in human reasoning and judgment have been reported individually, but their relationships have rarely been argued, and we are still far from a unified psychological theory of thinking. In this paper, equiprobability is proposed as a key concept in human thinking from a Bayesian probabilistic perspective. The importance of the equiprobability assumption, together with the rarity assumption and a tendency to seek information, is suggested from the results of our probabilistic approaches to various tasks. These tasks include deduction, induction, and probability judgment, including the Wason selection task, covariation assessment, hypothesis testing, and base-rate neglect. People seem to have a general tendency to assume the equiprobability of any two target events they encounter. Using ideas obtained from studies of inference in animals and in people with schizophrenia, the adaptive implications of symmetrical inference, based on its relationships with the phylogenetic origins of human creativity, language, and social intelligence, are discussed.
3 0 0 0 OA 流体力学と流れの可視化
3 0 0 0 OA 健康でいきいきと働くために:ワーク・エンゲイジメントに注目した組織と個人の活性化
- 著者
- 島津 明人
- 出版者
- 日本心身健康科学会
- 雑誌
- 心身健康科学 (ISSN:18826881)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.20-22, 2017-02-01 (Released:2017-02-22)
- 参考文献数
- 14
3 0 0 0 OA 地域の大学にメガ=ジャーナルの“迎撃”は可能か
- 著者
- 鈴木 晃志郎
- 出版者
- 地域生活学研究会
- 雑誌
- 地域生活学研究 (ISSN:21869022)
- 巻号頁・発行日
- vol.04, pp.3-11, 2013 (Released:2017-09-07)
- 参考文献数
- 21
地域生活学研究会の年報『地域生活学研究』は、大学図書館のリポジトリを活用し、大学の内外、専門のいかんを問わず幅広く寄稿できる実験的な電子ジャーナルとして新たな出発を遂げようとしている。本論文は、当該誌刊行の今日的意義について、特に近年急速に台頭しているメガ=ジャーナルへの批判的検討を踏まえて述べるとともに、メガ=ジャーナルの長所を包含する形で研究機関(とりわけ地方国立大学)における電子ジャーナルのあり方を探り、実践的な地域貢献の実験場として、『地域生活学研究』がもつ可能性についての提言をおこなうことを目的とする。
3 0 0 0 OA 深宇宙探査機の自律化とその検証
- 著者
- 高玉 圭樹 中谷 一郎
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.488-493, 2003-07-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 森 久栄 黒田 研二
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.138-150, 2019-03-15 (Released:2019-03-26)
- 参考文献数
- 21
目的 これまで報告されていない乳児院・児童養護施設での食物アレルギー児の在籍状況および食物アレルギーの給食対応の実態を明らかにし,ガイドライン・マニュアル等の有無別に比較する。方法 全国の乳児院・児童養護施設に自記式アンケート調査を郵送した。回収数は394(乳児院107,児童養護施設287)施設,回収率は53.6%であった。有病率等の実態把握には,人数記載のある392施設を集計対象とした。ガイドライン・マニュアル等の有無との関連の検討には,食物アレルギー児がいる230施設を解析対象とした。ガイドライン・マニュアルの有無を目的変数に,アナフィラキシーショックなどのアレルギーに関連する事象の有無ならびに給食対応との関連をフィッシャーの正確確率検定および多変量ロジスティック回帰分析で検討した。結果 392施設の食物アレルギーの有病率3.31%であった。「医師の診断書等がない児童」,「アレルギー情報が未確認のまま入所した児童」,「入所時情報と事実に相違のあった児童」は,アレルギー児童の約20%~50%と高率で在籍し,入所時点での情報が把握しにくい現状がうかがわれた。 230施設のうち何らかのガイドライン等を用いている施設は25.0%,明文化された申し合わせ事項を含めても32.1%しかなかった。「施設種別」を調整変数とし,ガイドライン等による取り組みを行っている施設のオッズ比をみると,医師の診断書がない児童がいる(0.35),情報収集のための統一書式がある(5.04),定期的な更新をしている(2.85),ヒヤリハット・誤食時の報告を課している(2.49)の項目で有意であった。また,過去にアナフィラキシーショックを起こした児童がいる(9.72),アレルギー情報が未確認のまま入所した児童がいる(3.12)についても関連が強かった。結論 給食対応についてガイドライン等を用いていた施設では,情報収集書式の整備や情報の更新,ヒヤリハット・誤食の報告などでルール化された取り組みを行っていた。ガイドライン等のある方がアナフィラキシーショックを起こした児童や入所時に情報未確認の児童がいる施設が多かったが,調査時では医師の診断書を得ているなど,入所後に適切な対応がなされているものとうかがわれた。
3 0 0 0 OA 中国のスギ花粉症
- 著者
- 殷 敏 三好 彰 程 雷 白川 太郎 榎本 雅夫 嶽 良博 彭 解人 阮 標 今野 昭義 佐橋 紀男
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.6Supplement2, pp.625-629, 1999-11-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
1995年より中国南部の3つの省 (江蘇省・広東省・雲南省) において、1660名の小中高校生と2167名の大学生を対象に、視診・ 問診・ スクラッチテストから成る鼻アレルギー疫学調査が実施された。また1998年春には南京医科大学第一付属医院耳鼻咽喉科外来にて、鼻アレルギー症例の臨床的観察が行われた。疫学調査からは、スクラッチテストで3.8%の被験者がスギ花粉に対して陽性であることが、またスギ花粉症の頻度は0.26%であることが判明した。スギ花粉症はまぎれもなく中国に存在するが、まだその頻度は低い。スギ花粉飛散量とともに、社会的背景要因の関与が原因として推測されている。
- 著者
- Yuzuki SHINJI Tatsuki TSUJIMORI Tatsuhiko KAWAMOTO
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.6, pp.302-307, 2019 (Released:2020-01-22)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 2
Late Paleozoic Yunotani eclogites in the Itoigawa–Omi area of the Hida–Gaien Belt were subjected to a blueschist–facies recrystallization and deformation after the peak eclogite–facies metamorphism. We studied fluid inclusions in quartz domains of different metamorphic stages in the retrograde eclogite. Coarse–grained quartz filling pressure shadow of porphyroblastic garnets contains transgranular fluid inclusions (Group–I) with high salinity [6.0–8.0 eq mass% NaCl, with a mean value 7.2 ± 0.6 eq mass% NaCl (n = 12)]. In contrast, transgranular fluid inclusions in later stage quartz–rich band (Group–II) in parallel to a penetrative foliation developed in matrix are characterized by lower salinity [1.1–5.8 eq mass% NaCl, with a mean value 3.4 ± 1.2 eq mass% NaCl (n = 12)]. The occurrences of fluid inclusion trails suggest that each group corresponds to the fluids entrapped prior to the blueschist–facies recrystallization and the fluids entrapped during the blueschist–facies stage, respectively. The Group–II fluid inclusions formed at blueschist–facies conditions support the idea that aqueous fluids in the subduction channel have a salinity similar to seawater (~ 3.5 eq mass% NaCl). Moreover, the Group–I fluid inclusions indicate a possibility that aqueous fluids at the eclogite–facies depth in subduction channels possess a salinity higher than seawater.