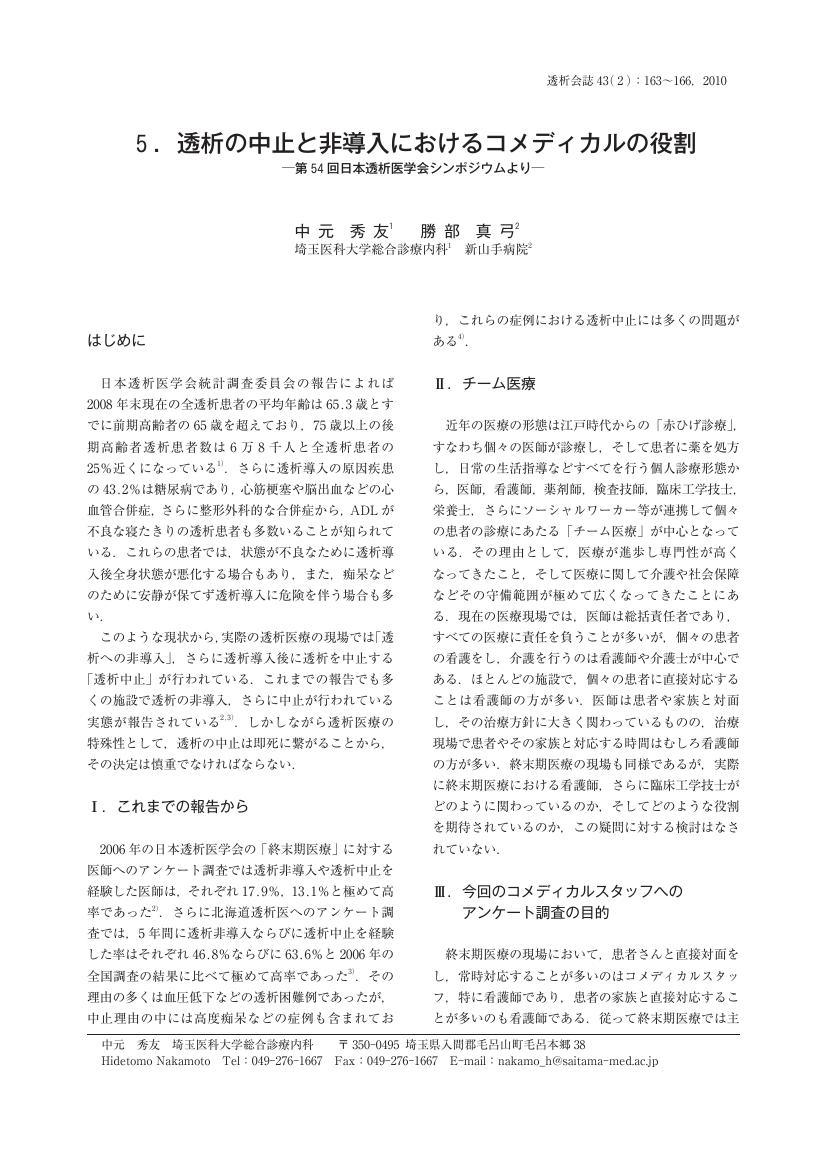3 0 0 0 OA 日本航空(JAL)の再建に見る「経営者 稲盛和夫の経営哲学」
- 著者
- 今井 祐
- 出版者
- 日本経営倫理学会
- 雑誌
- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.263-272, 2015-01-31 (Released:2017-08-08)
Mr. KAZUO INAMORI who has two success stories in KYOCERA Corporation and KDDI Corporation in business expansion was nominated as a chairman of JAL which went into bankruptcy in 2010. In JAL he applied successfully INAMORI's philosophy consisting of (1) leadership education, (2) making the new management philosophy, and (3) the profit management system so-called "Amoeba" management. It is important that his decision criteria should be based on sound truths and principles, such as the morality and ethics that answer to "What is the right thing for me, as a human being, to do?" I tested theoretically INAMORI's philosophy based on (1) the analysis of Ph.D. Iwao Taka on JAL, (2) the leadership theory of Ph.D. Atsushi Aoyama, and (3) the ethical arrangement in work- place of Ph.D. Nobuyuki Demise etc. The conclusion is that INAMORI's philosophy can effectively and widely be applied to the companies that are under rebirth from bankruptcy, loss, and low profit for a long time etc..
3 0 0 0 OA 柳生新陰流源流考
- 著者
- 岡田 一男
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.14-20, 1978-03-05 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 11
Mune-yoshi Yagiyu got acquainted with Hide-tsuna Kami-izumi in 1563 (A. D.). At that time, Mune-yoshi was thirty-five years old and he was commonly acknowledged that he was one of the greatest swordsmen ever known. But, realizing that Hide-tsuna's talents was supreme far ever, he hoped to become a pupil of Hide-tsuna, and he studied under Hide-tsuna.Later, Mune-yoshi was qualified for the teacher of Kage-Style by Hide-tsuna.I have some questions as follows, what style he had learned before.I suppose as follows.Yagiyu-shin-kage-ryu-engi which was transmitted to the Yagiyu family in 0-wari district was suggested him to belong Shin-to Style, and the annals of the Yagiyu family in Edo district was suggested him to belong Toda Style.Shin- kage Style is said that was added to new idea to Kage Style that was created by Iko-sai Aisu. I think that it had not a simple progress, but especially Yagiyushin-kage Style was performed a merit of Shin-to Style, Toda Style and various styles. Then I would like to know and study more about those relation by the comparison the literature on this subject.
3 0 0 0 OA 榊原家池之端屋敷跡と旧岩崎家茅町邸
- 著者
- 加藤 元信
- 出版者
- 日本庭園学会
- 雑誌
- 日本庭園学会誌 (ISSN:09194592)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.7, pp.11-25, 1999-03-31 (Released:2011-05-20)
- 参考文献数
- 39
3 0 0 0 OA 先天性心疾患外科治療: 最近の動向と今後の展望
- 著者
- 井本 浩
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.7, pp.843-844, 2011 (Released:2012-11-15)
3 0 0 0 OA 地理教育国際憲章 : 1992年8月制定 : 国際地理学連合・地理教育委員会編
- 著者
- 中山 修
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.104-119, 1993 (Released:2017-04-27)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 風の塔の形は, どのようにして決まったのか
- 著者
- 田村 幸久
- 出版者
- Japan Association for Wind Engineering
- 雑誌
- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.97, pp.73-79, 2003-10-31 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 3
3 0 0 0 OA ゴム技術の発展について ―自動車タイヤはなぜ黒いのか??―
- 著者
- 編集委員会
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.12, pp.387-389, 2011 (Released:2012-03-27)
3 0 0 0 OA 奄美大島で捕獲された種不明のコウモリ類
- 著者
- 浅利 裕伸 木元 侑菜
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.67-71, 2018 (Released:2018-07-31)
- 参考文献数
- 15
鹿児島県奄美大島の学校校舎内においてコウモリ類の目撃情報があったことから,2017年10月に捕獲調査を行ない,雄2個体のコウモリ類を捕獲した.外部形態の特徴から,奄美大島においてこれまで記録がない種であると判断した.捕獲個体の外部形態は日本国内に生息する種のうち,クロオオアブラコウモリに類似していたものの,種を同定することはできなかった.放獣した個体の音声はFM-QCF型を示し,ピーク周波数は平均35.35 kHzであった.奄美大島南西部の海岸で飛翔する種不明のコウモリ類が発する音声も同様のピーク周波数であったため,捕獲個体と飛翔個体が同一種であることが示唆された.
3 0 0 0 OA モンゴル・ウランバートルのゲル地区における住まいの変容と継承
- 著者
- 滝口 良 坂本 剛 井潤 裕
- 出版者
- 一般財団法人 住総研
- 雑誌
- 住総研研究論文集 (ISSN:21878188)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.173-184, 2017 (Released:2017-08-10)
都市定住のなかで遊牧の住文化が継承されているウランバートルの周辺居住区(ゲル地区)において住居と住民の生活史の調査を実施し,当該地区固有の住文化について検討した。ゲル地区の住文化として(1)ハシャーという居住ユニット,(2)移動式ゲルとセルフビルド住宅,(3)割り込み居住といった要素が明らかになり,家庭環境の変化に応じた家屋の増改築や共同居住,移動を行う柔軟な住文化が浮かび上がった。さらにアンケート調査の結果,上記の住文化の要素がゲル地区の近隣関係や地域改善に向けた住民の意図に影響を与えることが明らかとなり,現行のゲル地区のコミュニティ開発にあたり地域固有の住文化を考慮する必要性が示唆された。
3 0 0 0 OA タットン塩型複塩の結晶作り(小・中・高のページ)
- 著者
- 山本 勝博
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.375, 1994-05-20 (Released:2017-07-11)
3 0 0 0 OA 4.肥満とアトピー性皮膚炎, アレルギー性鼻炎
- 著者
- 楠 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.8, pp.984-989, 2017 (Released:2017-09-14)
- 参考文献数
- 25
3 0 0 0 OA 5.透析の中止と非導入におけるコメディカルの役割
- 著者
- 中元 秀友 勝部 真弓
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.163-166, 2010-02-28 (Released:2010-03-26)
- 参考文献数
- 9
3 0 0 0 OA バイオフィードバック指標としての皮膚コンダクタンス変化と皮膚電位活動の比較
- 著者
- 梅沢 章男 黒原 彰
- 出版者
- 日本バイオフィードバック学会
- 雑誌
- バイオフィードバック研究 (ISSN:03861856)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.29-36, 1994-07-31 (Released:2017-05-23)
Previous biofeedback studies concerning electrodermal activities have used either skin conductance (SC) or skin potential (SP). This study was designed to investigate the temporal correspondence between SC and SP and to determine the most suitable indicator for electrodermal biofeedback studies. SC and SP were recorded simultaneously in 24 subjects under the mirror drawing test. The following results were obtained : (1) Intrasubject correlation coefficients between total amplitudes per minute of skin conductance response (SCR) and of skin potential response (SPR) were significant in all subjects, whereas correlations between skin conductance level (SCL) and skin potential level (SPL) were significant in only 17 subjects (70.8%). Correlations between SCL and SPL were low or significant negative in subjects showed a positive SPL shift caused by a burst of positive SPRs. (2) Although SCR and SPR, phasic components of EDA, showed a marked increase in total amplitude in the first half of the experiment, but a gradual decreasing of responsiveness was found in the latter half. On the other hand, SCL and SPL, tonic components of EDA, showed consistent responsiveness throughout the experiment. (3) Latency of changes in SPL were significantly longer than changes in SCL. These results suggest that SCL is the most suitable indicator for electrodermal biofeedback studies.
3 0 0 0 OA 透析の見合わせに関する刑法的許容性の根拠の検討
- 著者
- 竹口 文博 中野 広文 菅野 義彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.9, pp.561-569, 2016 (Released:2016-09-29)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
透析医にとって, 透析の見合わせが刑法上許容されるのかは重要な関心事である. 透析の見合わせは, 不作為といえるところ, 医師は患者との診療契約に基づく刑法上の作為義務を負っていることから, 不作為犯に問われる可能性がある. このため, 刑法的許容性の問題は, 生じた作為義務が解除される要件は何かという形で問題となる. 透析見合わせの正当化根拠は, 患者の自己決定権に基づく透析拒否権に求められる. したがって, 患者の透析拒否の意思表示を要件として作為義務が解除され, 透析の見合わせは刑法の規定する「人を殺した」行為に当たらず許容される. 患者本人に意思決定能力がない場合には, もし患者に意思決定能力があれば透析を受け入れないであろう, と他者が代行判断することが許容されるかが問題となるが, 意思決定能力がない患者でも, 患者の現在の推定的意思に基づく透析拒否権を尊重すべきであり, 慎重にされた場合には代行判断を許容すべきである.
- 著者
- Takashi Yamauchi Hiroshi Takano Hiroaki Miyata Noboru Motomura Shinichi Takamoto
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, pp.131-136, 2019-03-08 (Released:2019-03-08)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
Background: The aim of this study was to determine adequate indication for transcatheter aortic valve replacement (TAVR). We analyzed risk factors of surgical aortic valve replacement (SAVR) not only for mortality, but also for morbidity, including long hospital stay (≥90 days) and patient activity at discharge, in patients who underwent SAVR for aortic stenosis (AS). Methods and Results: Using the Japan Adult Cardiovascular Surgery Database (JCVSD), 13,961 patients with or without coronary artery bypass grafting who underwent elective SAVR for AS were identified from January 2008 to December 2012. The hospital mortality rate was 3.1%. The percentage of patients who had long hospital stay (≥90 days) and who had moderately or severely decompressed activity at discharge (modified Rankin scale ≥4) was 2.9% and 6.5%, respectively. Eleven and 20 preoperative predictors of hospital mortality and morbidity, respectively, including long hospital stay and compromised status at discharge, were identified. Based on these risk factors, the risk model predicted hospital mortality (area under the curve [AUC], 0.732) and morbidity (AUC, 0.694). Conclusions: Using JCVSD, a risk model of SAVR was developed for AS. This model can identify patients at high risk not only for mortality, but also for mortality and morbidity, including long hospital stay and status at discharge.
3 0 0 0 技術情報を用いた他社コア技術の特定手法開発
- 著者
- 三沢 岳志 砂原 めぐみ 田村 隆生 三橋 敬憲 矢部 悟
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.94-98, 2019-02-01 (Released:2019-02-01)
技術戦略や事業戦略を策定する上で重要であるコア技術について,技術情報を用いて特定する手法を開発した。対象企業の特許情報からFIを技術区分として生存特許シェアと自社引用比率を用いてコア技術領域を絞り込み,テキストマイニングでその候補を抽出した後,非特許情報を使って具体的にコア技術を特定する。最後に論文や雑誌,Webなどの広範な非特許情報を用いてコア技術の検証を行う。コア技術の抽出及び特定の手法としては,技術や特許に詳しくないスタッフでも利用可能と考えられることから有用な方法であると考える。さらに,この手法を使う際に留意すべき点も検討した。
3 0 0 0 OA わが国における研修医のストレス要因の探索的研究
- 著者
- 木村 琢磨 前野 哲博 小崎 真規子 大滝 純司 松村 真司 尾藤 誠司 青木 誠
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.383-389, 2007-12-25 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 15
欧米では, 研修医のストレスは燃え尽き症候群や抑うつの原因となり, 研修プログラムからの脱落や非倫理的な診療などにつながると報告され, ストレス要因への対策がなされている.最近わが国でも, 研修医の過酷な労働条件や過労死などが問題となっているが, わが国における研修医のストレス要因を検討した報告は少ない.1) 10施設の研修医25人を対象に, フォーカス・グループ・インタビューを実施し, わが国における研修医のストレス要因を探索した.2) 研修医のストレス要因として, 一人の人間としてのストレス要因, 新米社会人としてのストレス要因, 未熟な研修中の医師としてのストレス要因の3つを抽出した.3) 3つのストレス要因をそれぞれ生活ギャップ, 社会人ギャップ, プロフェッション・ギャップと名づけ, 研修医のストレス要因を, 医学生時代と医療現場とのギャップがもたらす産物として描出した.4) わが国の研修医の様々なストレス要因が明らかになったが, 研修中の未熟な医師としてのストレス要因は, わが国特有であった.5) 安全で効果的な研修を行うために, これらのストレス要因を考慮した研修医のストレスへの対策が望まれる.
- 著者
- Yue ZHAO Masato MORITA Tetsuo SAKAMOTO
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- pp.18P480, (Released:2019-02-15)
- 被引用文献数
- 5
- 著者
- 小口 和代 才藤 栄一 馬場 尊 楠戸 正子 田中 ともみ 小野木 啓子
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.383-388, 2000-06-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 55 121
131名の機能的嚥下障害患者の「反復唾液嚥下テスト」(the Repetitive Saliva Swallowing Test: RSST)と嚥下ビデオレントゲン造影(videofluorography:VF)所見を比較し,RSSTの妥当性を検討した.RSSTはVF所見と相関が高く,カットオフ値として3回/30秒間が妥当であると思われた.誤嚥の有無の判別に関する感度と特異度は,0.98,0.66と,感度が非常に高かった.摂食・嚥下障害の診断・評価としては,まずRSSTでスクリーニングを行い,3回/30秒間未満の場合はさらに詳細な病歴,身体所見をとり,必要と判断されればVFを行い,治療方針を決定するのが適当である.
3 0 0 0 OA 非協力ゲーム(発展編)
- 著者
- 横尾 真 岩崎 敦 櫻井 祐子 岡本 吉央
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.3_39-3_53, 2012-07-25 (Released:2012-09-25)
本編では非協力ゲーム(発展編)として,非協力ゲームの均衡概念で最も重要なものであるナッシュ均衡について詳しく述べる.2人ゼロサム標準形ゲームでは,プレイヤが選択可能な純粋戦略の個数に関する多項式時間でナッシュ均衡を計算できる.しかしながら,プレイヤが交互に行動を繰り返し選択するような複雑なゲームでは純粋戦略の個数が膨大となる.本編では,このような複雑な2人ゼロサムゲームの均衡を計算する例として,ポーカー等のカードゲームにおいてナッシュ均衡を計算するアルゴリズムを紹介する.一方,一般の有限2人標準形ゲームでは,ナッシュ均衡が多項式時間で計算可能かどうかが分かっていない.しかしながら,ナッシュ均衡の存在自体は証明されているので,PやNPのような判定問題に関する概念は,ナッシュ均衡計算問題の難しさを議論するためには適切ではない.本編では,ナッシュ均衡計算問題の難しさを議論する際に有用な問題のクラスであるPPAD,およびPPAD完全性について解説する.