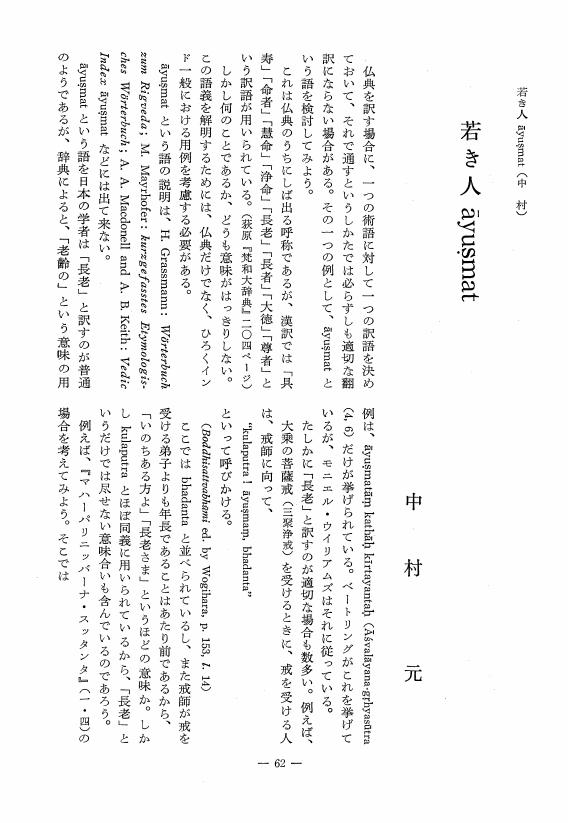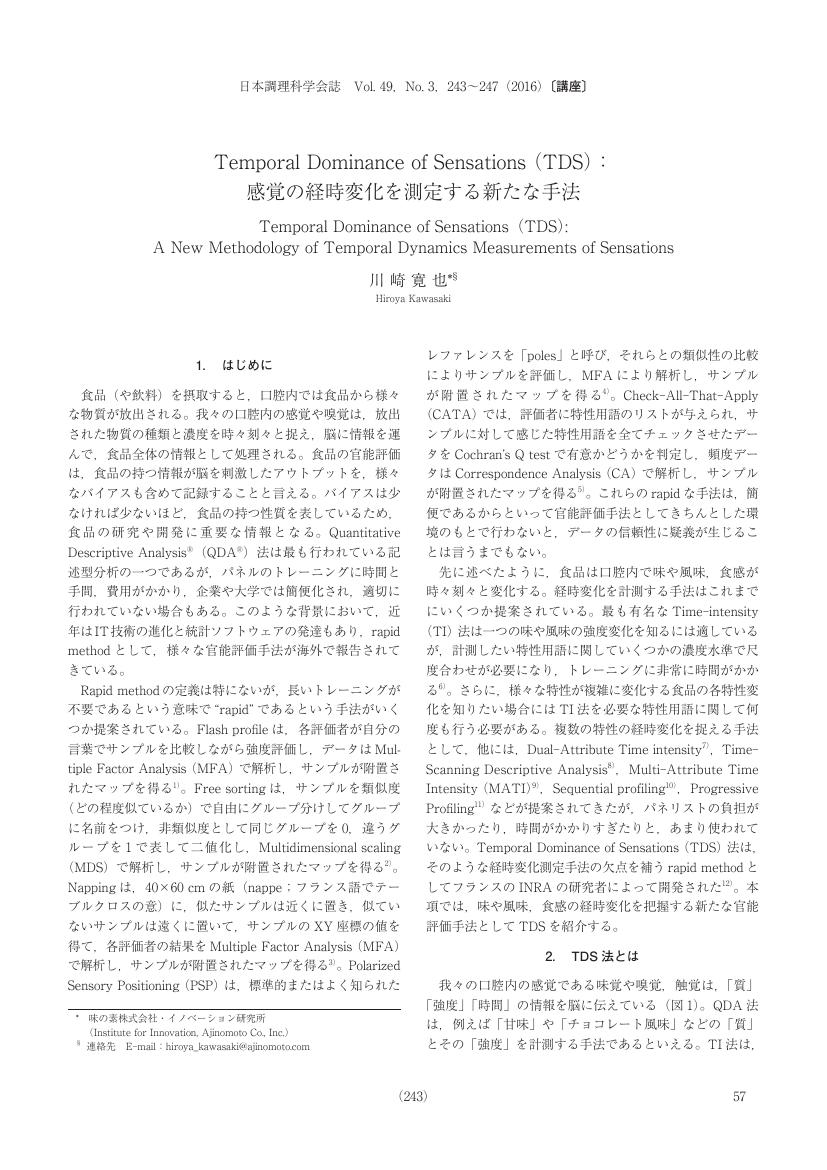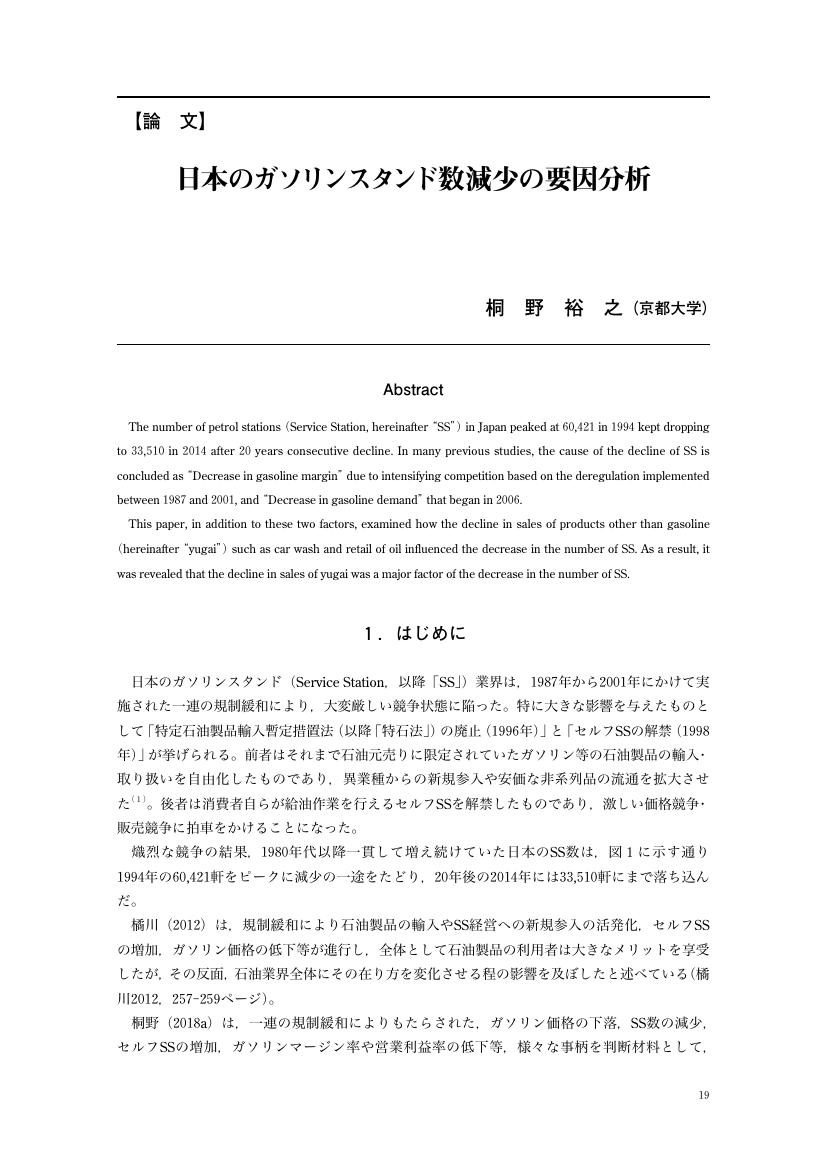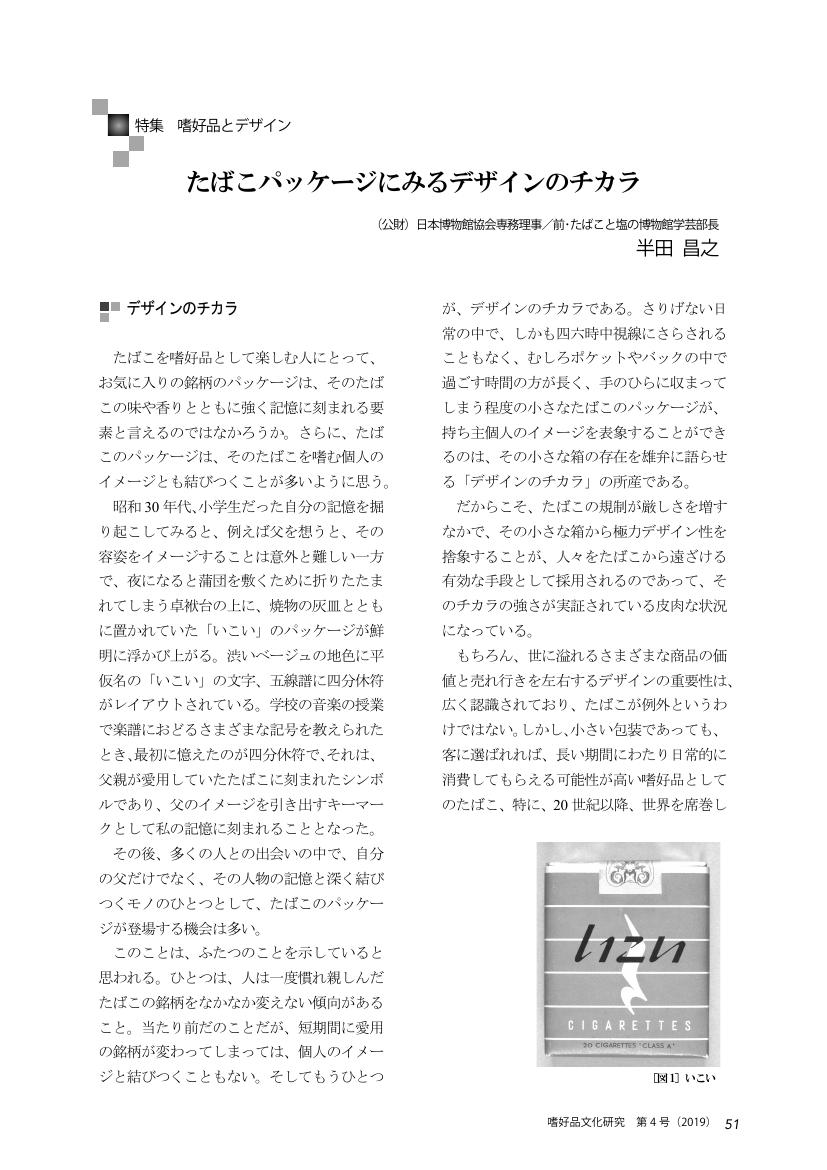2 0 0 0 OA 長野県中央山地におけるニホンツキノワグマの食性
- 著者
- 高田 靖司
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.40-53, 1979-06-30 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3
長野県中央山地にある, カモシカ特別保護区と旧扉入山辺休猟区において主に調査をした。1975年8月下旬から1977年12月初旬までに得られた, 135個のツキノワグマの糞の内容と採食活動痕を分析し, 6月中旬から12月初旬までの食性を明らかにすることができた。ツキノワグマは雑食性であるが, 植物性食物に強く依存している。6月から7月には動物性食物が重要であるが, 8月から10月には動物性食物とともに植物性食物に強く依存するようになり, 11月から12月には一層植物性食物に強く依存する。動物性食物の大半は昆虫類で占められ, アリ類 (Formicidae) , 特にアカヤマアリの成虫が重要である。次いでハチ類 (VespidaeとApidae) の成虫がよく利用された。アリ類は全期間に出現し, 最も基本的な動物性食物である。ハチ類は9月~12月まで出現した。哺乳類では, ノウサギとニホンカモシカが食べられたが, 出現頻度は低い。植物性食物では, 液果・核果類と堅果類が重要である。液果・核果類は, 8月から12月初旬まで出現し, 10月中旬までは重要な地位を占めるが, それ以後その地位を失う。堅果類は9月下旬から12月初旬まで出現し, この時期のツキノワグマにとって最も重要な食物である。液果・核果類では, アケビ類, 次いでタラノキが, 堅果類ではミズナラが最もよく利用された。この3年間ではミズナラに隔年結果現象がみられ, 1976年秋は不作であったが, 1977年の秋は豊作であった。この現象はツキノワグマの食性に影響し, 1976年にはミズナラがほとんど利用されなかったが, 1977年にはよく利用された。ツキノワグマを保護するためには, ミズナラを初め, 多様な構成樹種をもった広葉樹林を維持する必要がある。
- 著者
- 宇野 芳史
- 出版者
- 日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会会誌 (ISSN:21880077)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.184-192, 2020-11-20 (Released:2020-11-20)
- 参考文献数
- 33
急性咽頭炎,急性扁桃炎は日常診療において頻繁に遭遇する上気道疾患の一つである.「抗微生物薬適正使用の手引き」では,原因微生物としてウイルスが大半で,抗菌薬治療の適応となる細菌感染はA群β溶血性連鎖球菌のみが重要であり,A群β溶蓮菌迅速抗原検査または細菌培養検査でA群β溶蓮菌が検出されなかった症例に対しては抗菌薬投与による治療は不要としている.また投与する抗菌薬はAmoxicillinを中心としたペニシリン系抗菌薬が第一選択としている.しかし,実際の臨床の場においてはA群β溶蓮菌感染症であってもβラクタマーゼ産生菌との混合感染などによりペニシリン系抗菌薬での除菌失敗例,重症例でペニシリン系抗菌薬の投与で効果が期待できず,他の抗菌薬(ニューキノロン系抗菌薬,第3世代セフェム系抗菌薬等)の投与が必要と考えられる症例もある.他の耳鼻咽喉科感染症と同様,急性咽頭炎・急性扁桃炎においても重症度判定及びその重症度に従った抗菌薬の選択という考え方が重要である.また投与する抗菌薬はペニシリン系抗菌薬を第一選択としつつ,他の抗菌薬の選択も柔軟に考慮する必要がある.
2 0 0 0 OA ミノウスバの羽化・性比・飛しょう・温度反応および成虫の寿命
- 著者
- 田村 正人
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.166-168, 1985-05-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4 2
年1化性のミノウスバは比較的低温適応性の昆虫で(田村・大内,1977),早いものは4月下旬頃より夏期休眠に入り(田村・小見山,1976),低温・短日下で休眠消去(ISHII et al., 1983)した蛹は日増しに気温が低下する10月下旬∼11月中旬の午前8∼10時に集中して羽化する。しかしながら,この時期の気温はほぼ昼間が15∼20°C,夜間が10∼15°Cであり,探雌のための雄成虫の飛しょう活動には15°C以上が必要なため,昼間活動性であることは本種の生存上きわめて有利であり,適応的であると考えられる。
2 0 0 0 OA 若き人 ayusmat
- 著者
- 中村 元
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.62-66, 1983-12-25 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA 院外心肺停止傷病者に対するアドレナリン投与間隔の社会復帰に与える影響
- 著者
- 田中 勤 玉木 昌幸 田中 秀之 渡辺 徹 村上 宏 八幡 えり佳 田中 敏春
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.551-558, 2020-08-31 (Released:2020-08-31)
- 参考文献数
- 7
背景:心肺停止傷病者に対するアドレナリン投与は3〜5分間隔が推奨されているが,実際に病院前での投与間隔について調査検討した報告例は少ない。目的:新潟市の院外心肺停止傷病者に対するアドレナリン1筒目と2筒目の投与間隔が社会復帰に影響するか検討した。方法:新潟市消防局のウツタインデータを用い,2011〜2015年の院外心肺停止傷病者において心原性心停止でかつ病院前で2筒投与された傷病者を対象に初回投与時間の中央値と投与間隔5分未満群と5分以上群とに分け,社会復帰率,心拍再開率,短期生存率を解析した。 結果:対象の院外心肺停止傷病者は134例で5分未満群は37例,5分以上群は97例。社会復帰は各々7例と2例で5分未満群が多かった(p<0.05)。結語:投与間隔が5分未満である症例では社会復帰例が多く,適正な投与間隔でアドレナリン投与を行うことが院外心肺停止傷病者の社会復帰率改善に寄与する可能性がある。
2 0 0 0 OA Study on the Influence of Temperature of Extruder Head on the Strength of the FDM 3D Printing Model
- 著者
- Hiroki Endo Takashi Umeno
- 出版者
- Fuji Technology Press Ltd.
- 雑誌
- Journal of Robotics and Mechatronics (ISSN:09153942)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.767-771, 2017-08-20 (Released:2018-11-20)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 5
This paper reported the tensile strength of the difference of modeling condition on the FDM (Fused Deposition Modeling) 3D printer. The FDM 3D printer is rapidly spread with the end of patent protection in 2009. The FDM models mainly use the prototyping part and art, because that models have low strength. This time we paid attention to that actual models weight is lighter than designing models weight to conduct study on strength. And we investigated the cause of the phenomenon of decrease of polymer extrusion by replacing with the injection molding method. The tensile test proved that the strength of model can be improved by the kind of extruder head. This paper reported influence of the cooling in the supply part of extruder head and temperature of the polymer on the strength of FDM 3D models.
2 0 0 0 OA 川崎病の治療経過中に認められた偽性高カリウム血症の1乳児例
- 著者
- 杉本 圭 千葉 幸英 鏑木 陽一郎 金子 裕貴 鶴田 敏久 永田 智
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.1, pp.7-12, 2019-02-25 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 11
A 3-month-old girl was diagnosed with Kawasaki disease 4 days after onset and intravenous immunoglobulin (IVIG) treatment was started on the same day. Because IVIG therapy was ineffective, a combination of IVIG and prednisolone was administered on day 6. On day 9, the patient had hyperkalemia (6.5 mEq/L) without electrocardiographic abnormalities. The serum potassium level measured in blood collected in heparinized tubes was within normal range. We diagnosed pseudohyperkalemia leading to leukocytosis and thrombocythemia, attributable to coagulation system activation and increased release of potassium from leukocytes and/or platelets. Serum potassium levels in patients with potential hyperkalemia under these conditions may require greater consideration.
- 著者
- 川崎 寛也
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.243-247, 2016 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 6
2 0 0 0 OA 芸術の進化的起源
- 著者
- 齋藤 亜矢
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.6, pp.754-761, 2018-11-01 (Released:2020-09-29)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- Yasuhiro Oda Yoichiro Ikeda Hiroyuki Abe Akinori Hashiguchi Kazuhito Hatanaka Toshihiro Sawai Tetsuo Ushiku Masaomi Nangaku
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.1117-22, (Released:2023-04-28)
- 参考文献数
- 3
An 84-year-old man developed a membranoproliferative glomerulonephritis pattern of injury, and the most likely cause detected during a workup was monoclonal IgG-λ in the urine and serum. Predominant IgG and λ light chain deposition was confirmed only by immunofluorescence using formalin-fixed, paraffin-embedded tissue and not by immunohistochemistry. A smaller and non-linear dynamic range of immunohistochemistry makes it less quantitative than immunofluorescence staining and may explain why immunohistochemistry failed to detect the light chain restriction. This case suggests that immunohistochemistry may not serve as a substitute for immunofluorescence on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue in detecting masked monoclonal immunoglobulin deposits, although further research is warranted.
2 0 0 0 OA 慣習性が学習者の間接発話行為の理解に与える影響
- 著者
- 張 麗
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.167, pp.31-45, 2017 (Released:2019-08-26)
- 参考文献数
- 20
本研究は,1)慣習性が学習者の間接発話行為の理解に与える影響,2)慣習的間接発話行為と非慣習的間接発話行為とに分けて,理解に困難が生じる原因を検討した。本研究では,JFL中国人上級日本語学習者24名を対象に,語用論聴解テストを用いて慣習性が理解の正確さと速さに与える影響を調査した。その結果,慣習的間接不同意発話行為は非慣習的間接不同意発話行為より理解されやすく,また反応時間が短いことがわかった。また,学習者の理解に困難が生じる原因を明らかにするため,語用論聴解テスト後に刺激再生法を用いて,学習者の理解プロセスを調べた。その結果,慣習的間接不同意発話行為が理解困難な原因は,「キーワード」が利用できないことであるが,非慣習的間接不同意発話行為が理解困難な原因は,「パラ言語情報」,「談話状況」,「背景知識」,「話者の意図」といった文脈情報が把握できていないことが推察された。
2 0 0 0 OA 植物資源中の被食防御物質タンニンの分布:哺乳類のタンニン摂取の潜在的可能性について
- 著者
- 大森 鑑能 阿部 奈月 細井 栄嗣
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.193-214, 2023 (Released:2023-08-03)
- 参考文献数
- 94
植物は消費者による摂食を回避するために様々な被食防御物質を含んでいる場合がある.そのひとつであるタンニンは渋みの成分であり,消費者に対してタンパク質の消化率を減少させたり,消化管に損傷を与えたりするなど有害な影響を及ぼす.しかしタンニンは植物界に広く分布しているとされながら,日本ではその分類学上の分布情報は限られていた.本研究は植物界におけるタンニンの分布をスクリーニングすることを目的として,117科349種の植物のタンニン含有率を調査した.その結果,哺乳類の採食記録のある植物を含む174種(49.9%)でタンニンが検出された.哺乳類のタンニンを含む植物資源に対する選択性や生理学的な応答については未だ不明な点が多く,今後哺乳類の詳細な食性研究と共に,植物と消費者間の相互作用に関する生理学的な研究の発展が期待される.
2 0 0 0 OA 家畜の従順性と社会的認知能力の関連
- 著者
- 永山 博通 小出 剛
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.127-135, 2019 (Released:2019-12-18)
- 参考文献数
- 37
Social behavior is a conspecific interaction and plays an important role in the survival of animals. In contrast, while heterospecific interaction largely refers to predator ― prey interaction, occasional instances of cooperative behavior can be found, for example, the interaction between domesticated animals and humans. Domestication involves breeding animals for generations to familiarize them with humans without fear. A major behavioral characteristic of domesticated animals is tameness which is divided into two categories. One is reluctant to avoid humans (passive tameness) and the other actively approaches humans (active tameness). Until now, however, little is known about the genetic, behavioral and neurological basis of these two categories of tameness. Here, we briefly review genetic and neurological research on tameness. Next, we explore the relationship between tameness and social cognitive skills of domesticated animals, such as dogs. Finally, we discuss the possibility of the same brain regions being used in both conspecific and heterospecific interactions.
2 0 0 0 OA マヌ法典にあらわれた相続
- 著者
- 田邊 繁子
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1956, no.6, pp.28-63,en1, 1956-03-30 (Released:2009-11-16)
- 被引用文献数
- 1 1
Die nicht zur Beackerung an die Gemeindeglieder überwiesenen Stücke, kurz alles was nicht getheilt worden war, gehörten zur gemeinen Mark. Nach der Einbringung der Ernte erhielten auch die Äcker Allmendecha-rakter. Das Markrecht war eine Pertinenz des im markrechtigten Dorfe besessenen Hauses and Hofes. Wohnstatt and Ackerland sind mit dem gehorten Markrecht als ein Ganzes betrachtet and ebenfalls Hufe genannt worden. Daher hat es immer nur so viele Berechtigungen gegeben, als vollberechtigte Häuser and Höfe in den Dorfschaften vorhanden waren. Mit den Hausern and Höfen hat indessen auch die Anzahl der Markre-chten gewechselt.Die Antheile an der gemeinen Mark and die Markberechtigungen waren ursprünglich in einer and derselben Mark verhältnissmäßig gleich groß. Die Größe der Berechtigung richtet sick wesentlich offenbar, wie die Größe des Besitztums selbst, nach dem Bedürfnisse eines jeden Genossen. Durch spätere Ansiedlungen, Veräußerungen and Theilungen hat sick jedoch dieser ursprüngliche Stand der Dinge gänzlich verändert. Dazu kamen nun noch die Veräußerungen and Theilungen der einzelnen Höfe and der mit ihnen getrennten Marktheile in halbe and viertels Were, in gauze, halbe, drittels, viertels and sechstels Gewelden and Rotten, dann die Vereinigung oft sehr vieler Marktheile in einer and derselben Hand, wodurch die ursprüngliche Gleichheit der Berechtigung völlig vernichtet worden ist. Dieser gänzlich veränderte Zustand führte zu neuen Anor-dnungen und Einrichtungen. Die Art and Weise der Benutzung der ungetheilten Mark wurde von der Gemeinde genau regulirt, die Größe der Rechtigung nicht mehr nach dem Bedürfnisse eines jeden Genossen, sondern ein für alle Mal bestimmt oder jedes Jahr wieder neu bestim-mt, oder auch auf ein bestimmtes Quantum fixirt.Beisassens Marknutzung war eine bloße Begünstigung. Erst seit dem 16ten and 17ten Jahrhundert, hat sich dieses geändert, indem nun in manchen Dorfern auch die Kotter and anderen Beisassen als Gemeinde-genossen betrachtet worden sind.
- 著者
- 澤田 俊也
- 出版者
- 日本教育政策学会
- 雑誌
- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.154-168, 2020 (Released:2020-10-01)
The purpose of this paper is to examine the commitment of Senior Specialists for Curriculum and School Inspectors in revising Course of Studies, focusing on elementary social studies in 1958. Previous studies indicate the existence of Senior Specialists for Curriculum and School Inspectors, but donʼt reveal their concrete involvement in revising Course of Studies. The findings of this study are as follows. First, it is clear that School Inspectors submitted a draft revision independently of the Senior Specialists for Curriculum and took a strong initiative in revising Course of Studies as needed. Second, this paper indicates that the Senior Specialists for Curriculum and School Inspectors committed the revision process with not only their specialties but also their interests and preferences. Regarding their interests, it is clear that they resisted the abolition of their own subjects making full use of their specialties in order to avoid losing their jurisdictions. About their preferences, it is revealed that they justified their validity using their specialties in discussing concrete contents of the draft revision.
2 0 0 0 OA 日本のガソリンスタンド数減少の要因分析
- 著者
- 桐野 裕之
- 出版者
- 日本流通学会
- 雑誌
- 流通 (ISSN:09149937)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.45, pp.19-31, 2019 (Released:2020-07-29)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 医療観察法の対象者に対する家事および調理技能の獲得に向けた作業療法介入
- 著者
- 山元 直道 古賀 誠 野村 照幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.638-646, 2023-10-15 (Released:2023-10-15)
- 参考文献数
- 19
医療観察法の対象者の中には,精神疾患以外に知的障害や認知機能障害の併存が認められ,家事や調理の基本的技能の低さから生活が安定せず病状悪化につながる事例も多い.本事例にも知的障害と認知機能障害が認められ,健康や生活に無関心で不健康な生活を続けていた.作業療法や外泊訓練を通して,健康管理と家事や調理の技能獲得に向け,本事例が遂行できた内容に対して肯定的なフィードバックを用いて効率的な見本の提示や助言を行った結果,健康管理や生活技能の改善が図れた.医療観察法下における本事例への健康管理や生活技能への介入は,社会生活への価値を高めると共に再他害行為防止に作用し,社会復帰につながると考える.
2 0 0 0 OA 当院における墜落分娩16例の検討
- 著者
- 張本 姿 綱掛 恵 平井 雄一郎 小西 晴久 藤本 英夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.476-480, 2021 (Released:2021-12-10)
- 参考文献数
- 13
医療機関の集約化に伴い墜落分娩が生じる懸念がある.今回我々は2015年から2020年までに当院で経験した墜落分娩を,それぞれ後方視的に検討した.対象期間の総分娩数は3,678例,うち墜落分娩は16例(0.44%)であった.墜落分娩症例の自宅から当院までの距離は中央値28.5kmであった.初産婦1例,経産婦15例で,産科既往症では墜落分娩3例,切迫早産2例,早産1例の既往を認めた.児娩出から当院到着までの時間は中央値11.5分で,児は胎児異常による死産1例,低体温症5例,呼吸障害4例,多血症3例を入院時に認め,入院中4例が黄疸で光線療法を施行した.検討の結果,様々な状況で墜落分娩は生じていた.分娩前の墜落分娩リスクの把握や指導,墜落分娩が切迫している際の適切な指示や生じた際の対応について妊婦や救急隊へ指導を行うことで,墜落分娩を増加させない,あるいは墜落分娩での合併症を減らすことが大切である.
2 0 0 0 OA たばこパッケージにみるデザインのチカラ
- 著者
- 半田 昌之
- 出版者
- 嗜好品文化研究会
- 雑誌
- 嗜好品文化研究 (ISSN:24320862)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.4, pp.51-59, 2019 (Released:2022-07-29)
2 0 0 0 OA 世界の側弯症学校検診―歴史的背景と昨今の情勢―
- 著者
- 黒木 浩史
- 出版者
- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会
- 雑誌
- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.11, pp.1346-1353, 2023-11-20 (Released:2023-11-20)
- 参考文献数
- 38
側弯症学校検診は1963年にアメリカのミネソタ州で開始され,その後,世界中に側弯症学校検診モデルが拡散した.2018年までに出版された文献をもとにした調査で,側弯症学校検診の実施が確認できた国は本邦を加え23ヶ国で,うち4ヶ国(イギリス,ノルウェー,カナダ,オーストラリア)では,現在中止されていた.検診方法の多くは前屈テストであり,スコリオメーター,モアレ,シルエッターでの評価を単独であるいは併用し実施している国々もあった.各国の検診の有効性に関する考え方については,肯定が16ヶ国,否定が4ヶ国,合意なしが3ヶ国であった.国家レベルでの検診の法制化に関し,本邦以外で確認が取れた国はなく,検診実施国であっても自治体ごとで違いがあるなど,国ごとに状況は様々であると推測された.以上より,検診意義に関する意見の統一がなされていない中,各国独自に,検診の導入を判断し,それぞれのシステム,方法で検診事業を運営している現状が明らかとなった.またここ最近,これまで側弯症学校検診に関する報告のなかったロシアからも側弯症学校検診に関する総説が発刊されており,側弯症学校検診に対する国際的な方向性は前向きであると考えられる.