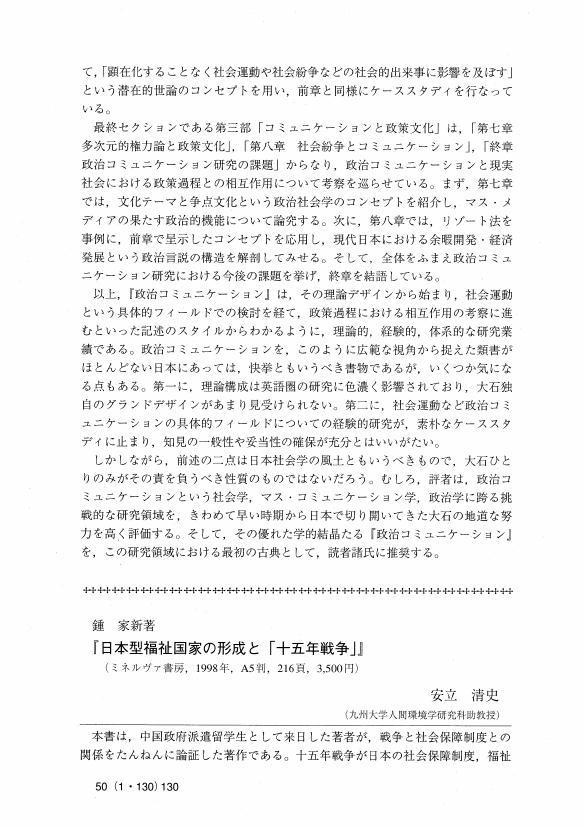1 0 0 0 OA 量子集合論の確率解釈の研究
量子論理に基づく集合論である量子集合論の研究は,論理学的方法で量子論を再構築し,量子論の確率解釈を拡張することを目指している。量子論理には含意結合子の選択に任意性があり,その標準化や個別化が長年の問題とされてきた。本研究では,含意結合子の選択による量子集合論の差異に着目し,量子集合論の移行原理が成立する多項式定義可能な2項演算がちょうど6種類あることを証明し,そのうち実質含意と呼ばれる3種に対して,量子集合論で定義される量子物理量の順序関係の確率解釈の差異を明らかにし,実験的検証可能な特徴付けを与えた。この研究により数学基礎論と物理学の新しい境界領域の展開と量子情報技術への応用が期待できる。
1 0 0 0 IR 生体試料中薬毒物の迅速分析システム
- 著者
- 内海 兆郎
- 出版者
- 広島大学
- 雑誌
- 広島大学医学雑誌 (ISSN:00182087)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.145-153, 2002-12-28
日本中毒学会「分析のあり方検討委員会(現分析委員会)」による,分析結果が治療に有用とされる15品目の中毒起因物質のうち,テオフィリンを除外した14品目について,臨床現場で得られる少量の生体試料からどれだけ迅速に何種類の検査が可能であるかについて検討した。本システムを構築するにあたり,生体試料を分析対象とした検査法のなかった有機リン系農薬,アセトアミノフェンは独自に開発し,環境検査用に市販されている検出キット(メタノール,青酸化合物,ヒ素化合物)は,生体試料に適用できるよう検討した。その結果,市販されていた5種のキット,独自に間発した2種の検出キットと2種の反応系によって,試料(尿および血清)1mlから14品目の中毒起因物質を1名の検査者が2時間で推定できた。また,実際の中毒4例に本システムを用いたところ,中毒起因物質の推定が可能であった。それぞれの検査法は注意点や改良点がいくつかあるが,臨床現場で得られる少量の試料から中毒起因物質の推定が可能となり,治療方針を決定するうえで有用であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 知覚·痛覚定量分析装置
- 著者
- 井関 雅子 榎本 達也 山口 敬介
- 出版者
- 一般社団法人日本医療機器学会
- 雑誌
- 医療機器学 (ISSN:18824978)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.213-216, 2010 (Released:2010-12-24)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 論文翻訳 カント『宗教論』における悪の普遍性
- 著者
- ブッフハイム トマス 木阪 貴行
- 出版者
- 国士館大学哲学会
- 雑誌
- 国士館哲学 (ISSN:13432389)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.147-165, 2014-03
1 0 0 0 OA 小特集「安全保障・防衛をめぐる諸課題」<緒言>
- 著者
- 廣瀬淳子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.793, 2017-02
1 0 0 0 第44回国際溶接学会ハーグ大会出席報告
- 著者
- 粉川 博之
- 出版者
- 社団法人日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.12, 1991-12-01
- 著者
- 松田 緝
- 出版者
- 札幌大学
- 雑誌
- 経済と経営 (ISSN:03891119)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.17-41, 1989-06
- 著者
- 諸田 實
- 出版者
- 神奈川大学
- 雑誌
- 商経論叢 (ISSN:02868342)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.33-70, 1993-08
1 0 0 0 OA 去る者は日ヶに疎し
- 著者
- 伴野 雄三
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.1-1, 1976-01-10 (Released:2009-02-09)
- 著者
- 野田 美里 武田 美恵
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 東海支部研究報告集 (ISSN:13438360)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.569-572, 2013-02-18
1 0 0 0 IR フォークナーの人間肯定への態度と『自転車泥棒』評価の問題
- 著者
- 花本 金吾
- 出版者
- 立正学園女子短期大学英語英文科研究室
- 雑誌
- 英米学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.56-71, 1966
- 著者
- 中津 継夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.4, pp.209-219, 1995-04-01
- 被引用文献数
- 4
ビスコクラウリン型アルカロイド製剤であるセファランチンのマウス脾臓内マイトジェン誘導ヒスチジン脱炭酸酵素(HDC)活性増強効果とサイトカイン産生増強効果について検討した.セファランチンはリポポリサッカライド(LPS)による脾臓内HDC活性誘導を正常マウスと同様にT細胞機能欠損マウスならびにT,B細胞機能欠損マウスで増強した.したがって,セファランチンの増強効果はT,B細胞を介さずとも生じることが明らかにされた.セファランチンはマクロファージのHDC活性ならびにサイトカイン産生を増強した.ヒスタミンはマクロファージのサイトカイン産生を誘導したが,LPS誘導のサイトカイン産生はヒスタミン受容体拮抗剤ジフェンヒドラミン,シメチジンでは影響されなかった.また,HDCの阻害剤αフルオロメチルヒスチジンにより,ムPS誘導のサイトカイン産生ならびにセファランチン添加時のサイトカイン産生は抑制された.以上の結果より,ヒスタミンはマクロファージのサイトカイン産生に促進的に作用し,この作用はマクロファージの細胞内外のヒスタミンで制御されていることが示唆された.また,セファランチンのサイトカイン産生増強効果においてもヒスタミンが関与していることが示唆された.
- 著者
- 油布 佐和子
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, pp.23-38, 2010-06-30
教職における病気休職者増加を説明する理論が見当たらない理由の一一つは,教職を公務労働(教育公務員)として認識する視点が欠落していることによる。本論文では,第一に,感情労働論・ケアワーク論を手がかりに,共同体で営まれていた<人を育てる>という活動が職業となることについての問題を,クライアントとの関係という点から検討する。そこでは,教育的な関係や言説において,絶えず情緒や感情が重視されることの理由が示される。第二に,そうした子どもとの教育的関係が,公務員として雇われて働く「労働過程」のなかにおかれていることに起因する問題を,感情労働論の議論を借りて考察する。そして第三に,現在の新自由主義的な改革の中で,公務員改革の一貫として進められている教職の様々な改革が,教師の教育活動を変容させていること,しかしながら第四に,こうした趨勢に対応する抵抗主体としての教員集団が存在していないことの問題を指摘する。病める教師の増加は,教育という活動を共同体的な「教師-子ども関係」の認識にとどめ,「教育労働」に無自覚であることや,「小さな国家」への移行によって教育労働が変容しているという現状を認識できないことのなかで,自らに過重に責務を負わせたことから生じているといえる。教育社会学における教師研究は,教師がこうした状況や構造を侑緻する視点を提供するという点で,他の教師研究と差異化して展開されるべきだろう。
1 0 0 0 大殿筋の筋活動:ブリッジ動作及び立ち上がり動作の筋活動量について
- 著者
- 厚川 和哉 尾脇 重信 児玉 尚子 矢野 幸彦
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.A1099-A1099, 2008
【目的】ブリッジ動作は大殿筋やハムストリングスの筋力強化を目的として幅広く用いられている。しかし、我々は大殿筋の筋特性として、1.殿筋筋膜等を介して様々な筋と筋連結している、2.遅筋線維が多く関節を動かす推進力としての働きが少ない、3.神経支配比が大きく筋紡錘密度が低い等の知見を得、ブリッジ動作を用いての大殿筋の筋力強化訓練としての有効性に疑問を抱いた。さらに先行研究において、表面筋電図を用いてブリッジ動作における大殿筋の筋活動量を測定したが、被験者間に著しい差を認め、ブリッジ動作においては大殿筋以外にも他の筋群が作用している可能性が示唆された。以上をふまえ、本研究ではすでに測定したブリッジ動作に加え、同筋の活動が強く影響されるADL動作として立ち上がり動作を用い、筋活動量を測定し、大殿筋に対する筋力強化訓練としてのブリッジ動作の有効性をさらに研究していくことを目的とした。<BR>【方法】被験者は19名(平均年齢28.1±4.3)の健常成人とし、右大殿筋に表面筋電図を貼付。測定肢位はA.左側臥位で右下肢をスリングで吊り上げ、背側から徒手的に骨盤を固定し、股関節の関節運動が生じないように被験者に指示し、等尺性収縮を5秒間保持させる。B.座位で股関節90°膝関節100°の状態から動作速度5秒間で立ち上がりを行うこととした。以上2条件を設定し、BIMUTUS VIDEO(キッセイコムテック)を用いてA.は筋電図波形から中央の3秒間、B.は離殿時からの中央3秒間の積分値を算出し、肢位の違いによる筋活動の差の比較、個人の筋活動の比率を比較し検討を行った。<BR>【結果及び考察】先行研究においては、側臥位とブリッジ動作の比率には0.5~6.6倍の幅を認め、χ2値より有意な差が認められた。側臥位と立ち上がり動作の比率は0.9~1.7倍で、有意な差が認められなかった。以上の結果から立ち上がり動作時における大殿筋の作用向上の目的で筋力強化を行う場合にはブリッジ動作よりも側臥位での選択的収縮を行うほうがより効果的であることが示唆された。さらに、ブリッジ動作では過剰な筋活動が行われている事が示され、動作獲得を目的とする訓練では、大殿筋の筋特性を踏まえ、感覚入力を与えながら訓練を行っていく必要があると考えられる。<BR>
1 0 0 0 OA 音声分析によるマスク着用時のコミュニケーション方法についての検討
- 著者
- 佐藤 成美 山内 さつき 高林 範子 石井 裕
- 出版者
- 岡山県立大学保健福祉学部
- 雑誌
- 岡山県立大学保健福祉学部紀要 = BULLETIN OF FACULTY OF HEALTH AND WELFARE SCIENCE, OKAYAMA PREFECTURAL UNIVERSITY (ISSN:13412531)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.45-55, 2015-03-12
本研究の目的は、マスク着用による音声への影響と話し手の音声の特徴が聞き手の聞き易さにどう影響しているかを、音声分析により明らかにすることである。音声実験では、被験者6 名に日常生活会話と同程度に話す「標準音声」、大きく・はっきり・ゆっくりと、を意識して話す「明確音声」をマスク非着用時と着用時で録音した。次に聴取実験では、別の被験者10 名に録音した音声を聞かせ、どちらが聞き易いか【声の大きさ・声の高さ・話す速度・間隔・アクセント】を基準に評価させた。その結果、マスク着用時の「標準音声」と「明確音声」の声の大きさには、有意な差は認められなかった。これは、マスク着用により発声が妨げられたことによるものと考えられた。また、聞き易い音声とは声の大きさだけではなく、抑揚をつけ話す速度も遅くすることが聞き易い音声にとって必要な項目であり、マスク着用時の円滑なコミュニケーションに繋がるという示唆が得られた。
1 0 0 0 インターネット情報検索における知識構築を促進させるメタ認知の検討
- 著者
- 吉岡 敦子
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.115-123, 2007
- 被引用文献数
- 2
インターネット情報検索は,検索テーマに関する既有知識と検索したサイトから得られる知識を体系化させながら検索を進めていくことから,本研究では,インターネット情報検索を知識構築過程と捉えて,知識構築を促すメタ認知とメタ認知活性化のための支援の効果について,特徴的な事例を挙げて質的に検討した.その結果から,「検索テーマについての既有知識や検索経験を検索のリソースにするためのメタ認知」と「サイトの文書から有効な情報を得て検索のリソースにするためのメタ認知」が有効なことが明らかになった.求める情報を得ることができた検索者は,これらのメタ認知を促して確認したり理解するなどの認知活動を行っている一方,求める情報を得ることができなかった検索者は,メタ認知を活性化できないために判断できず迷っていることが示唆された.また,これらのメタ認知を促す支援を与えることの有効性も示唆された.今後の課題として,検討した事例数が少ないことから,量的なデータにもとづいた分析を行うことと,本研究で与えた支援だけでは効果がみられなかった検索者に対する支援方法について解明することが挙げられる.
1 0 0 0 OA 日本語発話における言いよどみ現象の分類と特徴づけ
- 著者
- 田中 敏
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.213-218, 1981-11-20 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 31
The purpose of this study was to classify and characterize hesitation phenomena in Japanese speech. Twenty college students were asked to make a story about a series of pictures. The types of hesitation which were also found in English speech were identified in the stories. Then they were analyzed further in terms of the kinds of lexical unit and the location in a sentence. The major results were as follows: (a) repetitions and false starts occurred at nouns more frequently than at the members of Jodoshi-Joshirui (one of functional word classes) and (b) significantly larger parts of both filled and unfilled pauses were located between phrases than within them. Finally, functional role of each type in speech production was discussed.
1 0 0 0 OA 鍾 家新著『日本型福祉国家の形成と「十五年戦争」』
- 著者
- 安立 清史
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.130-132, 1999-06-30 (Released:2009-10-19)
1 0 0 0 OA 主機潤滑油サンプタンク設計マニュアル
- 著者
- 機関第三研究委員会
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.12, pp.752-758, 1993-12-01 (Released:2010-05-31)
This paper shows the design manual of main engine lubricating oil sump tank.