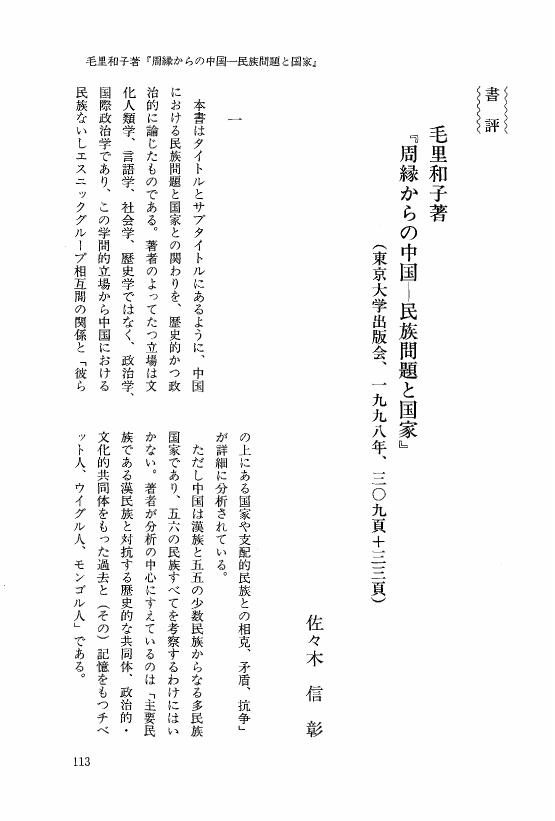1 0 0 0 OA 黒鉛炉原子吸光法を用いる底質中のリンの定量
- 著者
- 久保田 敏夫 内田 圭一 植田 俊夫 奥谷 忠雄
- 出版者
- 公益社団法人日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.381-383, 1988-07-05
- 被引用文献数
- 3
Simple and rapid determination of phosphorus in sediment was studied by graphite furnace (GF) AAS using a phosphorus hollow cathode lamp (P-HCL). A Zr-treated graphite tube was used for GF. For each analytical procedure a 20 mm^3 of 1% Zr solution was injected into the graphite tube and then a 10 mm^3 of sample solution containing P was injected. Digestion procedure was as follows : The sediment sample of 0.2 g was decomposed with HNO_3-HClO_4-HF, then the digest was evaporated to dryness. The residue was dissolved with 3 cm^3 6 M HCl, and diluted to 50 cm^3, and P was determined by GF-AAS. All the values obtained by the proposed method agree well with the reference value (Pond sediment, NIES No. 2) and those by Molybdenum Blue spectrometry (River sediment and Submarine sediment).
1 0 0 0 OA 毛里和子著『周縁からの中国―民族問題と国家』
- 著者
- 佐々木 信彰
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.113-117, 1999 (Released:2014-09-15)
1 0 0 0 AEを用いたシールド工事の音響診断システム
- 著者
- 吉野 広司 秩父 顕美
- 出版者
- 公益社団法人地盤工学会
- 雑誌
- 土と基礎 (ISSN:00413798)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, 1997-03-01
1 0 0 0 徹底理解! スマートグリッド(前編)自然エネ活用と省エネを両立
- 著者
- 山根 小雪
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経エコロジー (ISSN:13449001)
- 巻号頁・発行日
- no.124, pp.82-84, 2009-10
米オバマ大統領が景気対策法で45億ドルもの予算を計上したのを契機に、世界的な「スマートグリッド」ブームが沸き起こっている。"賢い電力網"は電力インフラの姿を変え、新ビジネスを生み出す革新性を秘める。 スマートグリッドとは、電力網にIT(情報技術)を付加し、高度化した電力網のことだ。
- 著者
- 吉川 誠司
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ネットビジネス (ISSN:13450328)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.208-211, 2000-08
個人間売買でのトラブルや迷惑メール、果てはネットストーカーの調査まで、様々な問題の相談に乗り、解決の手助けをしてくれるボランティアサイト「WEB110」。その生みの親である男は、被害総額90億円の国際詐欺事件「N-BILL事件」の解決で活躍したネット界の名探偵である!。
- 著者
- 松井 麻吏奈 満田 成紀 福安 直樹 松延 拓生 鯵坂 恒夫
- 雑誌
- 研究報告デジタルコンテンツクリエーション(DCC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.15, pp.1-6, 2015-01-19
携帯端末へのセンサ搭載やビッグデータへの関心の高まりからセンサアプリケーションと連携したソーシャルメディアが増加している.しかし,炎上やネットストーカーといった情報公開範囲に起因する問題も増加している.本研究の目的は,センサアプリケーションと連携したソーシャルメディアの開発を行う場合の,情報公開基準フレームワークの提案である.関連研究から抽出した情報公開に関する問題点を元にチェックリストを作成し,そのチェックリストを既存のソーシャルメディアに適用することにより,チェック項目に対して必要と考えられる機能についての考察を行った.その結果を一般化することにより,開発するソーシャルメディアの機能から必要となる情報公開に関する機能を提示する情報公開基準フレームワークの検討・考察を行った.
1 0 0 0 クリンカアッシュの緑化基盤としての利用が樹木へ及ぼす影響
- 著者
- 鈴木 武志 坂 文彦 渡辺 郁夫 井汲 芳夫 藤嶽 暢英 大塚 紘雄
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF REVEGETATION TECHNOLOGY
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 = Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.325-331, 2009-11-30
- 被引用文献数
- 1
石炭灰の発生量が増加傾向にある現在,その有効利用が一層求められている。石炭灰のうちクリンカアッシュ(以下CA と称す)は,フライアッシュと比較して粒径が粗く飛散のおそれもないため,土壌の代替としての大量利用が期待されるが,利用に際してはホウ素過剰障害の可能性が示唆されている。本研究では,CA を主材料とする緑化基盤で緑化樹木のポット試験を行い,CA の緑化基盤としての有効性を検討した。緑化基盤材料には,CA,真砂土,ピートモス(以下PM と称す)を用い,CA 試験区(CA とPM を混合)をCA 95 %区,CA 90 %区,CA 80 %区の3 区,対照として真砂土にPM を10% 混合したものを設定し,樹木は,アラカシ,ウバメガシ,シャリンバイ,トベラ,マテバシイの5 種を用いて,約7 ケ月間のポット試験を行った。<BR>作製した緑化基盤の化学性,物理性は対照区と比較して有意な差はほとんど無かった。また,国内の法律に照らし合わせると,これらの材料の重金属類濃度は安全であった。緑化樹木の生育に関しては,5 樹種とも,樹高(H),幹直径(D)から表されるD<SUP>2</SUP>H の試験期間中の生長率および試験終了時の新鮮重に,試験区間で有意な差はみられなかった。また,CA 試験区の樹木葉中ホウ素含量は,シャリンバイ以外の4 樹種で対照区に対して高い傾向を示したが,生育障害は確認されず,他の金属類に関しても異常な値は認められなかった。これらのことから,本研究に用いたCA を緑化基盤として大量利用することは十分可能であると考えられるが,実際の利用の段階では,CA ごとの性質の違いを検討していく必要がある。
1 0 0 0 OA 宇治拾遺物語註釈
- 著者
- 三輪杉根, 三木五百枝 註釈
- 出版者
- 誠之堂
- 巻号頁・発行日
- 1904
1 0 0 0 IR 被災者から見た臨床心理士活動の評価 : 被災地におけるアンケート調査から
- 著者
- 大崎 園生 今村 友木子 木原 英里子 小泉 奈央
- 出版者
- 愛知淑徳大学心理学部論集編集委員会
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集. 心理学部篇 (ISSN:2185520X)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.31-44, 2016
- 著者
- 川﨑 瑞穂
- 出版者
- 日本風俗史学会
- 雑誌
- 風俗史学 : 日本風俗史学会誌 (ISSN:13441140)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.45-65, 2013-07
本研究は、日本語の単語間の連想関係をマッピングして語彙知識の特徴を検討するものである。そのため、本研究の中心は、大規模日本語連想語データベース(JWAD)の構築を継続している(Joyce,2005a,2005b,2005c,2005d,2005e,2006,2007;Joyce&Miyake,2008)。連想語に関する質問紙調査を行って連想反応を収集し、連想反応の適切さによってコード化して、ターゲット単語に対して集合での延べ数・異なり数を集計するなどのような整理して漣想反応データをJapanese word association databaseの第一版(JWAD-V1)として公開した(Joyce,2005;2006;2007)。JWAD-V1は、反応者の50名、2,099のターゲット単語に対して、合計104,800の連想反応からなっている。複雑な連想ネットワークを明確にすること及び意味空間での階層構造を視覚化することの方法として、本研究は、大規模日本語連想語データベース(JWAD)に基づいた語彙連想マップの作成、または、JWADの連想ネットワーク表象にグラフクラスタリング方法を発展させた(Joyce&Miyake,2007,2008;Miyake&Joyce,2007a,2007b,in press;Miyake,Joyce,Jung,&Akama,2007)。グラフ理論やネットワーク分析結果、JWADの連想ネットワーク表象は、スケールフリーとスパース性の構造的な特徴を持っていることが明らかになった。語彙連想マップの開発にとって、連想反応の集合とグラフクラスタリングから得られる単語のクラスタリングは、有益な比較材料となりうる。語彙マップの発展・応用を検討する研究として、専門語の学習方法におけるバイリンガル語彙マップの有効性を示唆する結果が得られた日本語習得の研究(Joyce,Takano,&Nishina,2006;Takano,Joyce,&Nishina,2006,2007)、日本語辞書編集の研究(Joyce,2005b,2005d,2006;Joyce&Srdanovic,accepted)、日本語文字体系の研究(Joyce,2007)など行った。
1 0 0 0 画家・福沢一郎と地質学 : 画集『秩父山塊』から
- 著者
- 本間 岳史
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)
- 巻号頁・発行日
- no.72, pp.83-91, 2014-06-27
- 著者
- 川崎 瑞穂
- 出版者
- 日本オーラル・ヒストリー学会
- 雑誌
- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.107-123, 2013-09-11
In the Arakawa-Shiroku area (located in the City of Chichibu, Saitama Prefecture), there are old kagura (a Shinto-based folk performing arts particular to the location), called "Shinmeishakagura". Because of the lack of documentation, the understanding of kagura's history is difficult. Yadenji Hamanaka (one of the successors of this performance tradition) holds much knowledge of the traditional past. This paper will explain the traditions and shed light on some interesting aspects of kagura. Concerning the understanding of the successors, kagura is known to get its influences from kabuki, and many successors of kagura performance understood this. In the research of this paper, I clarify that kagura contains a very complicated background of influences. This result leads us to the conclusion that there is a stratified structure in the successors' understandings of their art.
1 0 0 0 OA 回内の動きと制限要因について
- 著者
- 米ヶ田 宜久 高濱 照 壇 順司 国中 優治
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.CbPI2248, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】前腕の回内の可動域測定は、近位橈尺関節と遠位橈尺関節に加え手関節の可動性を含めた角度にて測定している。また、高齢者に多発する橈骨遠位端骨折後に問題となる前腕の可動域制限を考える上で、日常生活上、最もよく使用される回内の可動域を正確に測定することが重要であり、可動域を改善するためには、橈骨と尺骨での純粋な回内運動とその制限因子を把握する必要がある。今回、前腕の軸回旋のみの可動性を”真の回内”と位置づけ、通常の可動域と区別し可動域測定の指標となる角度を算出した。さらに回内の動きを制動する要因について、遺体解剖の所見により検討した。【方法】対象は健常人55名(男性30名、女性25名、年齢21.13±2.84歳)、110肢とした。回内の可動域測定方法は、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会の測定方法に基づき、上肢下垂位から肘関節を90°屈曲し、基本軸を上腕骨、移動軸を手指伸展した手掌面にて測定した。また、可動域の制動となる要因を、熊本大学医学部形態構築学分野の遺体、左右14肢を用い測定・観察を行った。まず健常人での回内可動域を測定し、次に回内を制動する可能性の高い回外筋に着目し、切断前後の可動域の差を測定した。測定方法は健常人と同じ方法を用いた。尚、手関節の可動性はほとんどなかった。また関節包・靭帯のみを残した標本を作成し制動要素を観察した。さらに橈骨粗面が尺骨に衝突し制動要因となるかを観察した。その後、健常人の真の回内を測定した。方法は、上肢下垂位から肘関節を90°屈曲し、基本軸を上腕骨、移動軸を尺骨頭背側面の最も高い部位とリスター結節背側面の最も高い部を結ぶ線にて測定した。検定には全てt検定を用いた。【説明と同意】対象者には本研究の参加に際し、事前に研究の内容を説明し、同意を得た上で実施した。また、生前に白菊会にて同意を得ている遺体を用いた。【結果】回内の可動域は108.72±16.17°、男性106.53±17.44、女性111.36±14.22°であり性別間に有意差はなかった。次に遺体解剖の所見から、回外筋を残した状態での回内角度は45.57±8.84°であり、切断後は56.42±9.35°となり、回外筋切断後の可動域に有意な差を認めた(P<0.01)。また、靭帯・関節包の制動要因については、外側側副靭帯・輪状靭帯の緊張が高くなることが観察された。骨は14肢とも橈骨粗面は尺骨と衝突しなかった。これは解剖用のメスを橈骨粗面と尺骨の間に挟み、最大回内させても容易にメスを抜き出すことができた事から骨の衝突はないといえる。その後、健常人の真の回内を測定した。可動域は86.09±16.52°であり、回内との可動域に有意な差が認められた(P<0.01)。また、性別比較では男性87.33±15.52°、女性84.60±17.69°であり、回内と比較し有意な差が認められた(P<0.01)。性別間に有意な差はなかった。【考察】回内角度は健常人108°、遺体45°であること、遺体による回外筋の切断前後の可動域の差を約11°認めたことから制動の大きさを示している。しかし、健常可動域にはまだ不十分である。そこで、他の要因として、近位橈尺関節周囲の軟部組織と橈骨と尺骨の衝突、手関節の可動性が考えられる。靭帯・関節包の観察により外側側副靭帯、並びに輪状靭帯の緊張により回内制動されることが確認された。また、橈骨と尺骨の衝突は、回内位で生じないことが確認できた。これは橈骨の生理的湾曲と橈骨頭が楕円形であることで衝突を回避し、より大きな可動域を確保しているものと考えられる。しかし、そのまま回内への可動を許すと近位橈尺関節は脱臼するため、これらを制動する要因として橈骨頭の軸回旋を安定化させる、外側側副靭帯と輪状靭帯が緊張することが、回内制動に最も適していると考えることができる。また外側側副靭帯は橈骨頭の上端より上の部分から、内下方に走行していることも制動に適しているのではないかと考えられる。また、健常人の真の回内は約86°であり、回内と比較すると22°の角度を手関節が担っている。遺体で回外筋切断後も約56°であったこと、健常人での回内と真の回内の角度に約22°の差を認めることから手関節部も大きな制動要因になる可能性が高いと考えられる。これらのことから回外筋・外側側副靭帯と輪状靭帯の変性、手関節の柔軟性が真の回内の可動性を制限する要因になると考えられる。【理学療法学研究としての意義】回内の可動性の測定において、真の回内と回内に分類して考えることで、可動性の異常に対する原因を切り分け、治療対象を明確化でき、回内の測定はこれら2種類の可動域に着目する必要があると言える。また、回外筋・側副靭帯・輪状靭帯・手関節の変性は回内制動の原因となることが示唆された。
1 0 0 0 OA 東海道五十三次之内 石部 おはん
- 著者
- 豊国
- 出版者
- 伊勢屋
- 雑誌
- [役者見立東海道五十三駅]
- 著者
- 菅原 光
- 出版者
- 専修大学法学研究所
- 雑誌
- 専修大学法学研究所所報 (ISSN:09137165)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.113-127, 2016-03-10
- 著者
- 中村 剛也 本間 隆満 宮原 裕一 花里 孝幸 朴 虎東
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.5, pp.851-862, 2013 (Released:2013-09-17)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 1
諏訪湖の Microcystis の見かけの比増殖速度や最大現存量に対して湖水回転率が与える影響を 1992 年から 2003 年で調査した。20% day−1 以上に達するようなフラッシング時に加えて対数増殖期の回転率の上昇が 2% day−1 以上に達すると,Microcystis の見かけの比増殖速度は抑制され始めた。6 月から 7 月の回転率が Microcystis の最大現存量に強い影響を与えていることが示唆された。本研究は短期・長期的な湖水回転率が Microcystis に影響を与えていることを示すものである。
1 0 0 0 OA ホタルの光と人の感性について
- 著者
- 阿部 宣男 稲垣 照美 木村 尚美 松井 隆文 安久 正紘
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 感性工学研究論文集 (ISSN:13461958)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.41-50, 2003 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 5
The fantastic light of firefly, which keeps fascinating the heart of Japanese from ancient time, and the ecosystem, are taken up as one of cure fields being benefit from the nature. In this study, from the viewpoints of semantic differentials and engineering, we focused on the light of firefly, and we examined whether they cause the human spirit any effects or not. It was possible to find for welfare utilizations that there is the high possibility that a sufficient cure effect exists in the light emission pattern of firefly and the ecosystem. This research is the first basic trial turned to the creation of cure space for hospices and welfare facilities, which utilize the firefly and the mini ecosystem artificially modeled in an enclosure.
1 0 0 0 OA 神田川におけるアユ溯上の水質要因に関する研究
- 著者
- 風間 真理 小倉 紀雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.11, pp.745-749, 2001-11-10 (Released:2007-02-22)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3
The aim of the investigation is to show how the Ayu (Plecoglossus altivelis), a fish living in clean streams, can return to an urban river that believed to be polluted in the past. It was found that the ammonia nitrogen concentration had decreased remarkably, by monitoring of the water quality at the river. Due to the qualitative improvement of the sewage treatment water that is the river's main discharge source, the ammonia nitrogen concentration was decreased. Ammonia is an important substance for the survival of the creature; and a safe level, which makes the Ayu's survival possible, was estimated.
1 0 0 0 OA 書評 小塩隆士著 『再分配の厚生分析 : 公平と効率を問う』
- 著者
- 玉手 慎太郎
- 出版者
- 南山大学社会倫理研究所
- 雑誌
- 社会と倫理 (ISSN:13440616)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.178-182, 2013-11-20 (Released:2016-04-15)