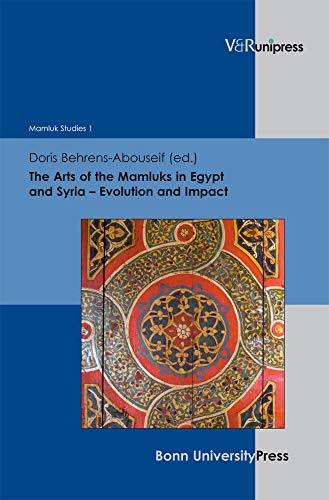1 0 0 0 OA 花粉による訪花性アザミウマ類の簡易飼育法
- 著者
- 村井 保 石井 卓爾
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.149-154, 1982-08-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 31 49 8
ヒラズハナアザミウマの飼育法を検討した結果,以下のことが明らかとなった。1) ヒラズハナアザミウマは薄膜(シーロンフィルム)を通して液体飼料を吸汁でき,この薄膜を通して液中によく産卵することがわかった。2) ヒラズハナアザミウマは,蜂蜜液だけでは発育,産卵できなかったが,チャ,ナシ,イチゴ,チューリップ,マツなどの花粉と蜂蜜液の組み合わせでは,餌を交換しなくても幼虫が発育し,85∼90%の高率で羽化成虫を得ることができた。さらに,この方法により産卵も促進した。3) ハナアザミウマも花粉と蜂蜜液で飼育できることがわかり,訪花性アザミウマ類の簡易大量飼育の可能性が示唆された。4) 本法による発育調査の結果,ヒラズハナアザミウマ,ハナアザミウマとも,羽化までの発育は揃い,成虫の生存期間は長く,産卵数は極めて多いことがわかり,訪花性アザミウマ類にとって,本飼育法は,葉や果実を用いる飼育よりも本来の餌条件に適合していることがわかった。
1 0 0 0 IR GCOE全体研究会 民法教科書総選挙
- 著者
- 森田 果
- 出版者
- 北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局, 北海道大学情報法政策学研究センター
- 雑誌
- 新世代法政策学研究 (ISSN:1883342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.109-148, 2013-01
1 0 0 0 OA 教育講演5 中枢神経系におけるアクアポリン-4 (AQP4) の役割
- 著者
- 安井 正人
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.11, pp.786-788, 2009 (Released:2009-12-28)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3 3
体内水分バランスは,生体の恒常性維持機能のもっとも重要な調節機構である.水分バランスの不均衡は,様々な病態にともなってみとめられ,その補正が治療上有効となることが多い.水チャネル,アクアポリンの発見は,体内水分バランスや分泌・吸収に対するわれわれの理解を分子レベルまで深めることとなった.腎臓における尿の濃縮・希釈はもちろんのこと,涙液・唾液の分泌にも重要な働きをしている.アクアポリンの結晶構造が解明されたことで,水分子がいかにしてアクアポリンのポアを選択的に通過するか,分子動力学シミュレーションを駆使して再現することも可能となった.アクアポリンの調節機構に対する理解も進みつつあり,アクアポリンを標的とする創薬への期待が高まっている.脳においても水バランスの重要性は例外ではない.アクアポリンの分布から考えて,神経細胞ではなくグリア細胞がその役割を担っていると考えられている.グリア細胞に発現しているアクアポリン-4(AQP4)は,脳浮腫の病態生理に関与している事が明らかになったのみならず,最近ではNMOの患者に特異的にみとめられるNMO-IgGの抗原としてAQP4が同定されるなど,AQP4は臨床的にも大変注目を集めている.AQP4の立体構造も解明され,分子標的創薬の面からも期待が高まっている.
1 0 0 0 IR 超低周波~中波帯変動磁場のマウス生殖器官への影響
- 著者
- 畑中 恒夫 渡部 逸平 渡邊 亮太 渡部 逸平 ワタナベ イッペイ Watanabe Ippei 渡邊 亮太 ワタナベ リョウタ Watanabe Ryota
- 出版者
- 千葉大学教育学部
- 雑誌
- 千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:13482084)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.371-376, 2014-03
人々の電化生活が発達するにつれて,人を含め動物たちは様々人工的な電磁波にさらされるようになり,それらの電磁波の生体に及ぼす影響についての研究が盛んに行われている。我々は以前,ネズミ駆除器からの超低周波電磁場曝露により,雄マウスの精子数が減少することを報告している。これらの効果が現れるには,毎日8時間,1月の曝露時間が必要であり,おそらく長期にわたる感覚ストレスが影響するものと思われる。一方,ラット精巣への短時間の超音波照射により加熱作用が生じ,精子数が減少することが報告されている。そこで今回,感覚ストレス説の確認のため,コイルを用いてマウス精巣に直接変動磁場を与え,周波数及び曝露時間を変え,影響を調べた。コイルでの磁場曝露の際,不動化のために麻酔を用いた。50Hzの超低周波正弦波磁場の長時間曝露で,麻酔の副作用による影響に加えて,精子数の減少が見られた。麻酔下でも変動磁場の影響が見られたことから,感覚ストレス以外の作用機序の関与も考えられた。ラジオ波領域の変動磁場への短時間の曝露では500KHz,1MHzでは影響がなかったが,誘導電流が大きい3MHzの磁場で精子の減少が見られ,誘導電流による加熱効果の影響が示唆された。電磁場,変動磁場による精子減少の作用機序解明には,精子形成過程のどの段階で影響を及ぼすのか,時間経過を考慮したさらなる研究が必要である。The effects on an extremely low frequency(ELF)and radio frequency magnetic field on the genital organs ofadult male mice were investigated. The scrota of male were placed on a coil with the diameter of 2 cm and exposed to alternating magnetic fields under a general anesthesia. Long term exposure to an ELF magnetic field(50 Hz sinusoidal field)at 1.5 mT for 5 consecutive weeks reduced sperm count significantly. Sperm reduction from magnetic exposure was not inhibited by general anesthesia. This suggests that magnetic exposure directory exert an effect on genital organs, not via a psychological pathway from magnetoreception. In order to evaluate acute effects of radio frequency magnetic fields, the specimen was exposed to 500 KHz, 1 MHz or 3 MHz magnetic fields at 1.7 mT for 15min in consecutive two days. Only 3 MHz magnetic field effectively reduced sperm count. A high-frequency magnetic field induces large electrical current and generates large heat, so the reduction of sperm count could be responsible to heat effect of induced current. Further studies of heat shock effects on spermatogenesis are required.
1 0 0 0 OA 植民地官僚の政治史 : 朝鮮・台湾総督府と帝国日本
1 0 0 0 OA 朴庚守「鄭芝溶の日本語詩研究」
- 著者
- 李 修京 李 修京
- 出版者
- 山口県立大学
- 雑誌
- 山口県立大学國際文化學部紀要 (ISSN:13427148)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.A71-A78, 2005-03-25
- 著者
- Doris Behrens-Abouseif (ed.)
- 出版者
- Bonn University Press
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 OA NIRS研究と臨床への応用
- 著者
- 住谷 さつき
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 脳と精神の医学 (ISSN:09157328)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.163-169, 2009-09-25 (Released:2010-10-05)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 光伝播シミュレーションによるNIRS信号の解釈に関する検討
- 著者
- 岡田 英史
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.44-51, 2010 (Released:2011-07-14)
- 参考文献数
- 8
生体組織内のヘモグロビンによる吸収と赤血球による散乱が、近赤外分光法(NIRS)の検出信号に及ぼす影響をシミュレーションによって解析した。細い単一血管を模擬したモデルでは、flow effectと呼ばれるNIRS信号に対する赤血球の散乱変化の影響が大きくなった。これに対して、血液と周囲の組織からなる生体組織モデルでは、散乱変化のNIRS信号への寄与は小さく、NIRS信号が主としてヘモグロビンなどの吸収変化に依存することが明らかになった。NIRSによる脳機能計測は生体組織モデルを対象としたものに近いため、NIRS信号を脳機能賦活によるヘモグロビン濃度変化に起因するものと近似して解析を行う方法は妥当であると考えられる。
1 0 0 0 OA 客観的観念論と私法学(一)ーラーレンツ法学の体系的再構成の試みー
- 著者
- 藤田 貴宏
- 出版者
- 早稲田法学会
- 雑誌
- 早稲田法学 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.143-247, 1999-02-20
1 0 0 0 IR テレビCMは逆行条件づけか?
- 著者
- 中島 定彦 Sadahiko Nakajima
- 出版者
- 関西学院大学人文学会
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.39-53, 2010-09
1 0 0 0 OA カンボジアの塩辛
- 著者
- 小崎 道雄
- 出版者
- 日本食品保蔵科学会
- 雑誌
- 日本食品保蔵科学会誌 (ISSN:13441213)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.139-146, 2002-05-31 (Released:2011-05-20)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA 岡山大学における医学教育の現況
- 著者
- 高原 滋夫
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.35-39, 1970-04-25 (Released:2011-08-11)
1 0 0 0 レシピテキストからのフローグラフコーパス作成 (データ工学)
- 著者
- 前田 浩邦 山肩 洋子 森 信介
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.214, pp.37-42, 2013-09-12
料理は複数の材料に対しそれぞれ加工を加えたり,混ぜ合わせたりしながら,一つの料理を作り出していく流れ作業である.よってこれまでも,レシピの表現形式のひとつとして,作業フローグラフが用いられてきた.従来も,レシピテキストを半自動でフローグラフに変換する研究が行われていたが,これらの研究で対象としていたレシピは,プロの料理人や編集者により製作されたものであり,すでに規格がある程度統一されているため,ルールを適応することが比較的容易であったと考えられる.一方,Web上で最も多いのはCOOKPADや楽天レシピに掲載されているようなユーザ投稿型のレシピであるが,これらのレシピは表現の自由度が高く,従来型のルールにあてはめることが困難である.そこで本研究では,投稿型のレシピテキストをフローグラフに変換する際のデータフォーマットを提案する.さらに,特徴的であった事例を複数紹介する.
- 著者
- 中川 浩子 菅佐原 洋 山本 淳一
- 出版者
- 日本行動分析学会
- 雑誌
- 日本行動分析学会年次大会プログラム・発表論文集
- 巻号頁・発行日
- no.29, 2011-09-10
1 0 0 0 OA ^[○!R]二〇〇五年衆議院選挙における三大紙の社説比較 : 概念ネットワーク分析の適用
- 著者
- 鈴木 努
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- no.69, pp.2-21, 2006-07-31
- 被引用文献数
- 3
It is said that the result of the general election 2005 was greatly affected by mass media's news coverage. In this paper I compare the editorials of the three major newspapers in Japan: Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun and Mainichi Shimbun. Co-occurrence networks and centering resonance analysis are used to examine the features of the texts. Relevance, consistency and uniqueness are the most important elements that the media texts should have in order to be convincing with the readers. The elements are shown clearly and visually with some network analysis methods.
- 著者
- 澤井 真
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.4, pp.1132-1133, 2012-03-30
1 0 0 0 IR 重症片麻痺患者に対する逆方向連鎖化を用いた起き上がり,寝返り練習の効果
- 著者
- 中田 衛樹 岡田 一馬 山崎 裕司 山崎 生希 山崎 倫 大森 貴允 冨岡 真光
- 出版者
- 高知リハビリテーション学院
- 雑誌
- 高知リハビリテーション学院紀要 (ISSN:13455648)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.13-16, 2015-03-31
認知症を合併した重症片麻痺患者に対し,逆方向連鎖化の技法を用いた寝返り・起き上がり動作練習を実施した.寝返り動作は介入セッション,起き上がり動作は8セッション目に動作が自立した.介入中,身体機能および認知機能の改善は認められなかった.介入後,速やかに起居動作が自立したことから,認知症を合併した重症片麻痺患者に対する今回の動作練習は,有効に機能したものと考えられた
1 0 0 0 OA 他者評価を利用した食習慣改善ソーシャルメディア
- 著者
- 竹内 俊貴 藤井 達也 小川 恭平 鳴海 拓志 谷川 智洋 廣瀬 通孝
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- pp.D-MDF04, (Released:2015-07-23)
- 参考文献数
- 21
Modern people are concerned with healthy eating habits; however, sustaining these habits often requires a vigilant self-monitoring and a strong will. The satisfaction found in a meal is influenced not only by the food itself, but also by external stimuli and information. This effect is called expectation assimilation in behavioral science. We propose a social media system that enables people to begin eating meals that are more healthful naturally and without conscious effort. This system uses others' positive evaluations as a trigger of expectation assimilation. Using the proposed system, users share information on their meals and evaluate the yumminess and healthfulness of each other's meals. Novelty of the system is that the system modifies others' evaluations, displaying evaluations of healthfulness as those of yumminess to the user consuming the meal. Therefore, users tend to eat more foods that are evaluated as healthful foods by others and thereby, improve their eating habits without noticing it. In this paper, we report about the mechanism of the proposed system and results of a user study under controlled circumstances. Moreover, we integrated our method with a published mobile application that already had a lot of users. We examined our proposal in the real-world context with the application and, consequently, proved practical effectiveness of the method.