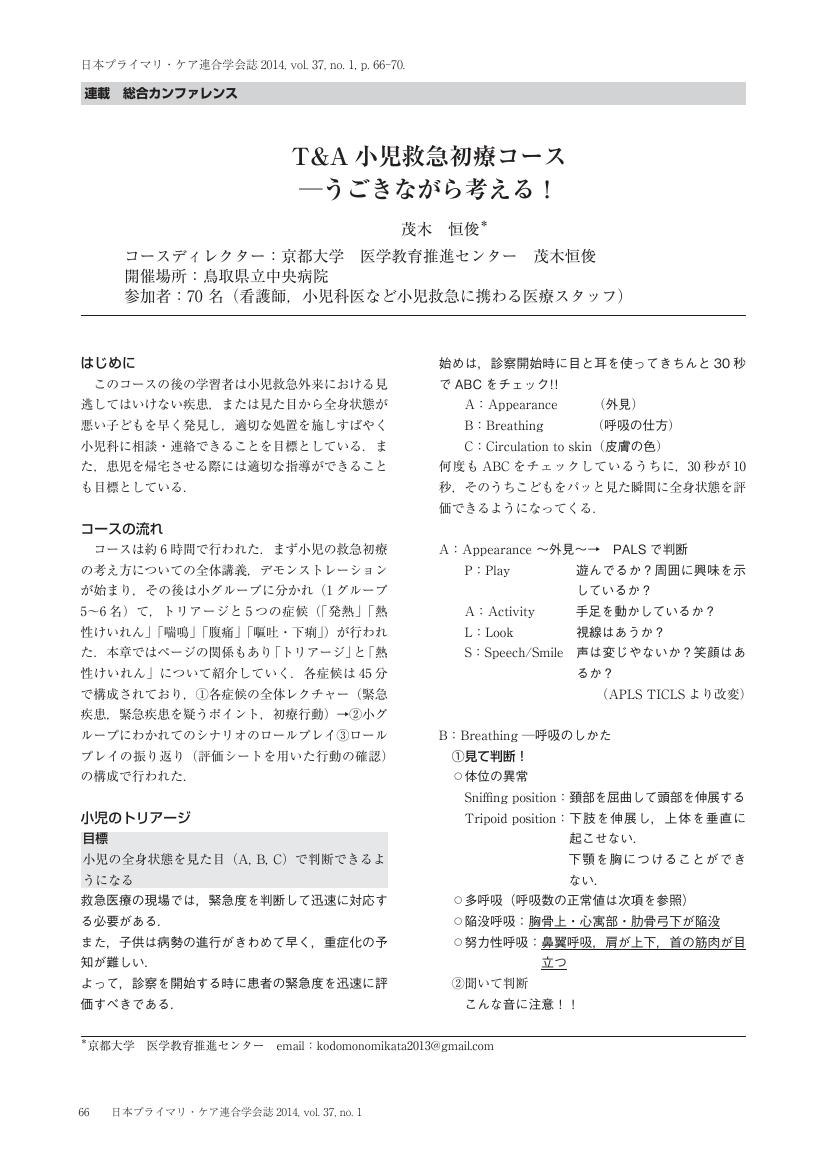- 著者
- Ogihara Yuji Uchida Yukiko
- 出版者
- Frontiers
- 雑誌
- Frontiers in psychology (ISSN:16641078)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, 2014-03-05
- 被引用文献数
- 70
個人主義的な人は、親しい友人の数が少なく幸福感が低い -日本社会の個人主義化がもたらす負の側面を示唆-. 京都大学プレスリリース. 2014-03-19.
1 0 0 0 OA T&A小児救急初療コース─うごきながら考える!
- 著者
- 茂木 恒俊
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.66-67, 2014 (Released:2014-03-28)
1 0 0 0 ジュール・ヴェルヌの小説『海底二万里』における科学的資料の位置
- 著者
- 石橋 正孝
- 出版者
- 明治学院大学文学会
- 雑誌
- 明學佛文論叢 (ISSN:13499173)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.29-55, 2010-03
1 0 0 0 OA 定型発達児ならびに発達障害児の不眠に対する認知行動療法的アプローチ法の開発
定型発達児および発達障害児の不眠症の有病率に大きさ差はなかったが,発達障害児の方が,睡眠についての不安が強い可能性が示唆された.入眠までの環境調整を確実にすることが重要であり,その上で認知行動療法的アプローチを加えることが有用であると考えられた.行動療法的アプローチとしては,消去法,入眠儀式,時間制限法などがあり,これらを組み合わせて行うことが有用であるが,症例毎にその特性が異なることから画一的な治療では十分な効果を得ることは困難であり,個々の症例にあわせた治療をの選択が必要である.今後は,大規模調査により本人・家族から得た情報より判定したタイプ別類型と,それに基づく治療法を確立していく必要がある.
- 著者
- 村上 暁信
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.124-127, 2003-11-29
1 0 0 0 OA ビザンツ皇帝権と霊性
1 0 0 0 OA イタリアの現代美術
- 著者
- ペルショウ アンリ 目形 照
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.47-56, 1964-01-20
1 0 0 0 関東南部産スギタニルリシジミの食餌植物と寄主転換
- 著者
- 岩野 秀俊 山本 嘉彰 梅村 三千夫 畠山 吉則
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.327-334, 2006
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2
関東南部においてトチノキが分布しない地域でスギタニルリシジミの分布範囲が拡大しているが,それらの地域での本種の食樹を明らかにするため現地調査を実施した.神奈川県津久井町および箱根町から数種植物の花や花蕾,幼蕾を持ち帰り、幼虫の発見に努めた.津久井町ではスギタニルリシジミの食樹として,ミズキならびにヤマフジを利用しさらに相模湖町ではハリエンジュも食樹の一つである可能性が高いことが判明した.また箱根町では新たにキハダの幼蕾から多数の幼虫が見つかったため,食樹と認定した.県内のトチノキ非分布域では新食樹に寄主転換することで,分布勢力の拡大を計っていることを示唆した.
1 0 0 0 OA 歯石形成機序に関する分子疫学的解析:患者唾液中の細菌とナノバクテリアの役割
Corynebacterium matruchotiiはバイオフィルムの石灰化に重要な役割を果たしている。しかし、C. matruchotiiと歯石沈着の関連における疫学調査や臨床データが少ない。その理由は、C. matruchotiiの簡便な検出方法が存在しないためである。本研究では、C. matruchotiiの簡便な検出方法の確立を目指した。C. matruchotiiの分子疫学調査に利用できる比較的安価で特異的な抗原を抽出した。C. matruchotiiのカルシウム結合タンパク質は20種類存在し、そのタンパク質の多くは酸性タンパクであることが明らかとなった。
- 著者
- 前田 芳男 城山 侑介 両角 光男 本間 里見 大西 康伸 村上 祐治
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会研究報告. 九州支部. 3, 計画系
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.181-184, 2007-03-01
1 0 0 0 IR 中学校理科における熱分解や電気分解の実験・観察の現状と工夫
- 著者
- 三木 崇史 梶原 篤
- 出版者
- 奈良教育大学教育実践開発研究センター
- 雑誌
- 教育実践開発研究センター研究紀要 = Bulletin of Center for Educational Research and Development (ISSN:21865841)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.199-202, 2012-03
- 著者
- 植田 和光
- 出版者
- 公益社団法人日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 : seibutsu-kogaku kaishi (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.10, pp.473-475, 2008-10-25
動物はさまざまな食べ物を口から摂取し,消化後,必要な栄養素を小腸から吸収して生きている.単糖やアミノ酸など水溶性化合物は脂質二重層を通過できないため,それらを特異的に通過させる膜タンパク質であるトランスポーターを小腸上皮に発現させ体内に吸収している.一方,食物中に含まれるさまざまな脂溶性低分子化合物は自由に脂質二重層を通過し,体内に吸収される.問題は,それらの脂溶性低分子化合物の中に多くの有害物質が含まれていることである.それゆえ,我々の体は有害なものを何らかの方法で見分けて排出する必要が生じる.たとえば,コレステロールと植物ステロールであるシトステロールとの構造の違いはエチル基ひとつだが,シトステロールは我々の体にとって有害である.我々の体はコレステロールとシトステロールを識別しており,食物中のコレステロールは50-60%が小腸上皮から吸収されるのに対して,シトステロールは排出系が働いた結果5%以下しか吸収されない.最近,ABCタンパク質の多くのメンバーが体内での脂質,脂溶性物質の移動を担っていることが明らかになってきた.上記のシトステロール排出はABCG5/ABCG8が担っている.また本稿で述べるように,ABCA1とABCG1はコレステロールを移動させることによって体内のコレステロール恒常性に重要な役割を果たしている.ABCタンパク質の異常は高脂血症,動脈硬化,糖尿病,老人性の失明,新生児呼吸不全,皮膚疾患など多くの疾病と結びついており,ABCタンパク質の発現や機能を調節することができれば,多くの疾病の予防や治療に役立つことが期待される.
1 0 0 0 OA 健康生成モデルにもとづいた食嗜好と偏食の機序に関する研究
健康生成論にもとづき食嗜好と偏食の機序について検討した。その結果,1)偏食の構成概念が明らかにされ,食嗜好,偏食行動を測定する尺度を開発した。2)首尾一貫感覚は食感覚に対する受容性と正の相関があり,ソーシャルサーポートは,偏食行動と負の相関があった。3)好きな味と嫌いな味に対する前頭前野の反応の相違が示された。4)偏食の改善は,健康状態に影響することを確認した。味覚感受性は,偏食や食嗜好に影響を与える傾向があるが,内的資源や外的資源を媒介とした時,味刺激に対する感情の調節が図られ偏食行動は緩衝される可能性がある。内的資源や外的資源の充実による食行動の改善について今後も検討する必要がある。
- 著者
- 阿知波 信夫
- 出版者
- 日本食品保蔵科学会
- 雑誌
- 日本食品保蔵科学会誌 = Food preservation science (ISSN:13441213)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.91-99, 2006-05-31
- 被引用文献数
- 7 8
日本は今、"豊食"の時代と呼ばれ、多種多様な食べ物を、しかも手軽に入手し摂食することができる。しかしながら、遺伝子組換え野菜、残留農薬問題、調理時の微生物汚染由来の食中毒など、食の安全の確保は最も重要なテーマのひとつである。そこで、これら様々な問題を解決する手段として電解水に着目し、各ステージに合った具体的利用とそのときの効果をまとめた。第1章で農産物の生産現場での病害の防除を目的とした利用法について、第2章では培養液ならびに葉面散布液として利用したときの農産物の生育ならびに内容成分への影響について、第3章では収穫後の農産物の微生物汚染の機序とその対策について、そして第4章では最も一般的な殺菌剤である次亜塩素酸ナトリウムと比較したカット野菜への殺菌効果ならびに品質への影響について調査した結果を報告する。
1 0 0 0 OA つくば市周辺地域における三次元水文地質モデルの構築と帯水層の透水性の推定への適用
- 著者
- 越谷 賢 丸井 敦尚
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.3, pp.421-440, 2012-06-25 (Released:2012-07-09)
- 参考文献数
- 38
Three-dimensional earth sciences information is being made available in digital formats because such information is useful and understandable to various users. In this study, we develop a three-dimensional hydrogeological model of Tsukuba City and the surrounding region, and develop a method for estimating the hydraulic conductivity of aquifers in combination with the three-dimensional hydrogeological model and other related hydrogeological information with the primary objective of proposing a method for evaluating groundwater resources. The three-dimensional hydrogeological model was developed using a geological map and drilling data with data interpolated using a geostatistical method. The model developed reproduced the data used well, and it was found to be accurate for practical use. Moreover, this model could be used for various types of visualization, from which information could be extracted and applied immediately to numerical simulations; this provided information that was useful and understandable for evaluating groundwater resources. The proposed method for estimating the hydraulic conductivity of aquifers was developed from hydraulic conductivities obtained from various drilling surveys, which were grouped together taking geology and stratigraphy into consideration based on a three-dimensional hydrogeological model, and using a statistical analysis. This method can be used to rapidly evaluate trends in hydraulic conductivity by integrating data distributed over a broad area. In addition, if a columnar section of an evaluated point is obtained, this method can be used to determine the actual hydraulic conductivity of aquifers. Therefore, these methods were found to be effective for evaluating groundwater resources.
1 0 0 0 OA 非平衡プラズマによる含水物超燃焼熱システムの着火・燃焼過程の解明
マイクロ波プラズマの性質を診断して、予混合バーナーおよび火花点火機関の着火に適用した。マグネトロンを電源に用いた場合から研究を始め、このプラズマ発信源を半導体に置き換えることによって安定したプラズマを生成することができた。エタノールのように含水性のある燃料に、マイクロ波プラズマを利用した着火システムは、含水の効果により有用であることが分かった。さらに、含水エタノール燃料の場合、レーザーブレークダウンによるプラズマ生成によっても着火を促進するなど有益な知見を得た。
1 0 0 0 The distribution of cellular retinoic acid-binding protein I during odontogenesis in the rat incisor
- 著者
- BERKOVITZ BKB
- 雑誌
- Arch Oral Biol
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.837-843, 1993
- 被引用文献数
- 1 9
1 0 0 0 OA 脊髄性筋萎縮症原因蛋白質SMNの神経細胞における機能の解析
我々は脊髄性筋萎縮症患者由来の繊維芽細胞を使ってこの疾患の原因タンパク質であるSMNタンパク質の発現調節について研究を続けてきた。その結果、RNA結合タンパク質のhnRNP A2がSMNタンパク質の翻訳のレベルでの調節に密接に関与しており、SMNタンパク質の安定的継続的発現にはA2が不可欠であることが解った。このA2タンパク質は最近、同じ運動神経を侵す筋萎縮性側索硬化症に於いてその変異が見つかっており、我々の発見は脊髄性筋萎縮症に於けるSMNの発現の調節を介した神経細胞での役割を理解するうえで重要な意味を持つ。更に、筋萎縮性側索硬化症の発症のメカニズムに於いてのSMNの重要な役割が示唆される。
1 0 0 0 高純度オゾンによるシリコン酸化膜の作製と評価
- 著者
- 一村 信吾 中村 健 黒河 明 野中 秀彦 村上 寛
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. CPM, 電子部品・材料
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.220, pp.13-18, 1997-08-04
高純度のオゾンを供給できるオゾンビーム発生装置を用いて、極薄シリコン酸化膜の形成におけるオゾンの効果を検討した。加熱清浄化によって得たSi(111)及びSi(100)面をスタート表面として、高純度オゾンによるシリコンの酸化を酸素分子による酸化と比較した。酸化に伴うシリコン表面の変化は、X線光電子分光法(XPS)によるOls強度変化、Si2pの形状変化、ならびに2倍高調波発声法(SHG)の強度変化で調べた。これから、オゾンがシリコン表面で解離して生成する原子状酸素が、高い反応確率でシリコンのバックボンドに挿入し完全性の高いSi-O-Siネットワークを形成するというオゾン酸化の特長を明らかにした。