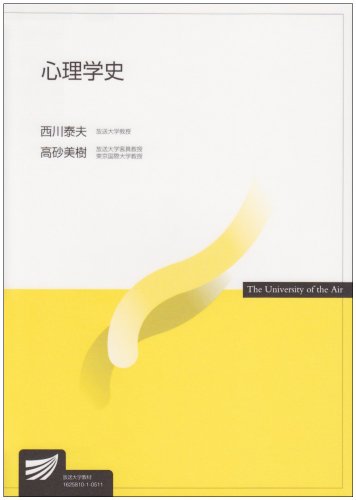1 0 0 0 OA ヴァルター・ベンヤミンの「視覚的無意識」について
1 0 0 0 IR 天平雲 : 奈良教育大学学生広報. Vol. 185
- 出版者
- 奈良教育大学
- 雑誌
- 天平雲 : 奈良教育大学学生広報
- 巻号頁・発行日
- vol.185, 2007-04-20
平成18年度卒業式・終了式/平成19年度入学式/平成18年度学生表彰式/学生団体・委員会の紹介/研究式紹介「岡澤研究室」/クラブ紹介「茶道部」/みんなが落ち着ける場所<すぎのこ>/日本留学事情/学生が企画するイベント情報/オリジナル商品「瓦煎餅」を発売!/大学からのお知らせ
- 著者
- 加藤 久典 奈良坂 祥子 東江 咲乃
- 出版者
- 必須アミノ酸研究委員会
- 雑誌
- 必須アミノ酸研究 (ISSN:03874141)
- 巻号頁・発行日
- no.173, pp.15-21, 2005-08
1 0 0 0 OA サザンカにおける土用芽の発生と花芽の形成および開花の関係
- 著者
- 中島 敦司 養父 志乃夫 櫛田 達矢 永田 洋
- 出版者
- 一般社団法人日本森林学会
- 雑誌
- 日本林學會誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.69-75, 1997-05-16
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 6
サザンカを3月18日にビニールハウスへ搬入し4月18日に再び自然の野外に移した。フラッシュの終了した5月8日に, 半数の個体に対して緩効性肥料(10-10-10)を1個体当り20g 施し, 5月12日, 6月11日, 7月11日, 8月10日, 9月9日の各日に, 18時間日長に調節した18℃恒温または25℃恒温のグロースチャンバー内か蛍光灯下の圃場に移したところ, 花芽の形成は5月12日に25℃および野外-長日に移した区で早くなった。また, 花芽の形成割合と土用芽の発生割合は負の関係にあった(γ=0.78)。さらに, 発育を続けている花芽を着生したままの葉芽は頂芽, 側芽ともに二次成長することはなかった。土用芽は同一節位上に形成された花芽が発育しなかったか, 形成された花芽のすべてが落下したか, 花芽を形成しなかった頂芽においてのみ認められた。そして, 開花率と土用芽の発生割合の間には有意な負の相関が示された(γ=-0.53)。この結果, サザンカの花芽と葉芽の発育および展開は相互に抑制する関係にあると考えられた。
1 0 0 0 OA 老人性大動脈弁狭窄症における僧帽弁輪・弁尖への石灰化進展による僧帽弁狭窄の合併
老人性大動脈弁狭窄(AS)では僧帽弁狭窄(MS)がしばしば観察される。本研究では、3次元経食道心エコー法により僧帽弁複合体を評価し、弁輪弁尖の石灰化と僧帽弁口面積(MVA)の関連を検討し、大動脈弁置換術後このMSが心血行動態に及ぼす影響を負荷心エコー法により検討した。MVAはAS群で小さく、約1/4の症例は中等度以上のMSを呈し、MVAは、内側弁輪面積、僧帽後尖と弁輪のなす角度に規定されていた。負荷時さらにMSが増悪することはなく、負荷前に比べ負荷後MVAは増大した。負荷時のMVAの増大は血流量増加と比例した。ASに合併するMSは偽性のことが多く、高度でない限りは治療の対象とはならない。
1 0 0 0 GUIを用いたヘアスタイルデザインシステムの開発
- 著者
- 三枝 太 安藤 真 森島 繁生
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, 1996-03-11
- 被引用文献数
- 2
ヒューマン・インタフェース、知的画像符号化などの分野での表情合成技術においては、人物頭部画像のリアルな合成が必要不可欠なものとなっている。筆者らは、頭髪を「空間曲線」によって近似し、近似的なアンチエイリアシングや予測を用いた効率的なレンダリングを取り入れることで、より高速で質の高い画像の生成に成功した。頭髪の生成には、予め与えられた人物頭部の3次元モデル表面に自動的に生成する方法を提案した。しかし、この手法では髪型をインタラクティブにデザインできないという問題点が残されていた。そこで髪型をインタラクティブに編集するインタフェースの実現により、より自然な頭髪画像の生成に成功したので報告する。
1 0 0 0 パラメータ制御による頭髪像の生成
最近、頭髪や毛皮にみられるような複雑かつ非常に細かなテクスチャをコンピュータ・グラフィックスにより生成する方法の研究がさかんになってきた。このような状況において、第38回全国大会における筆者らの「三角柱と房のモデルによる頭髪の生成」は、頭髪特有の複雑で細かななテクスチャを生成できるのみならずその全体構造である髪型を制御することをも可能とする方法を述べた最初の報告であった。本報告は、前記報告での頭髪生成方法に基づき、頭髪像を生成するために必要な10個のパラメータについて述べ、パラメータの変化が生成頭髪像に与える影響を実際の生成画像で示す。Hair and fur image generation is an important problem in CG. The appearance of hair and fun is not characterized by their complex textures alone. Our trigonal prism based wisp model seems to be the first which clearly handles hair style (shape) generation. This paper introduces the ten parameters needed for efficient hair image generation using the trigonal prism based wisp model.
1 0 0 0 心理学史
- 著者
- 西川泰夫 高砂美樹編著
- 出版者
- 放送大学教育振興会
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 赤外線画像を用いた男女識別の試行(一般セッション)
- 著者
- 西野 聰 松田 淳 五十嵐 幸代
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. PRMU, パターン認識・メディア理解 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.302, pp.101-106, 2005-09-15
男女識別は大型商業施設やアミューズメント施設等の来客統計をとるためなどに必要である.従来の男女識別方は, 服装や歩き方, 足圧, 髪型および声など人物の外見を利用した方法である.しかしこれらの特徴は人間の意思により恣意的に変えることのできる特徴である.本手法は男女の特徴の相違を赤外線画像の顔または手の熱分布により行う生体的特徴を用いた新しい概念に基づく男女識別方である.したがって, 本手法は従来手法にない強固な男女識別を実現可能な法である.
1 0 0 0 OA モダニズムと中東欧の藝術 ・文化
- 著者
- 圀府寺 司 コウデラ ツカサ
- 出版者
- 大阪大学21世紀COEプログラム「インターフェイスの人文学」
- 巻号頁・発行日
- 2007-01
大阪大学21世紀COEプログラム「インターフェイスの人文学」 / Osaka University the 21st Century COE Program Interface Humanities
1 0 0 0 蒸気機関の数理構造と効率論からみる非線形非平衡物理学
本年度は主に二つの研究課題に取り組み、成果を得た。(i)有限時間で動作する熱機関、具体的には有限時間カルノーサイクルに局所平衡を仮定してその最大仕事率時の効率論を構築した。有限時間過程においても作業物質に熱力学諸変数が定義可能(局所平衡仮定)とすることで、熱力学的力と流れやこれらを結ぶ関係式について作業物質や熱源の熱力学変数を用いた新しい表現を導いた。これらの表現を用いて、有限時間カルノーサイクルが線形非平衡状態での最大仕事率時の効率の上限値を達成するモデルであることを示すことにも成功した。こうした局所平衡仮定に基づく熱機関の定式化は従来の非平衡熱力学と親和性が高く、非平衡蒸気機関の理論を構築する際の第ゼロ近似としての役割を果たすことも期待できる。以上の成果をまとめた論文を現在投稿中である。続いて(ii)結合振動子系における「同期のエネルギー論」の構築に取り組んだ。結合振動子がリズムを揃える同期現象は位相方程式によって簡潔に記述される非線形力学系の一例である。一方、リズム現象自体はエネルギーの流出入がバランスすることで維持される非平衡散逸系の典型例であり、非平衡熱力学の研究対象として考えることもできる。本研究では微小生物の鞭毛の流体力学的相互作用による同期現象を念頭に、結合振動子系にエネルギー論を導入した。まずそれぞれ円周上に束縛された二つの結合振動子に独立な白色ガウスノイズが加わった系のフォッカー・プランク方程式を考え、その解析解を導いた。続いて得られた確率分布関数を利用し、非平衡熱力学や揺らぎの熱力学を適用することで、結合振動子の振動に伴うエネルギー散逸率の公式を導出した。これを流体力学的相互作用するストークス球などへ適用し、同期・非同期によるエネルギー散逸率への影響を定量的に評価することにも着手した。これらの成果は日本物理学会において発表され、現在論文を準備中である。
1 0 0 0 こう筋に対する外科的アプローチ 文献的考察:―文献的考察―
- 著者
- 市村 恵一 田中 利善 北原 伸郎
- 出版者
- The Society of Practical Otolaryngology
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.9, pp.1209-1219, 1989
- 被引用文献数
- 7 3
The masseter muscle, which contributes to mastication, originates on the zygomatic arch and inserts into the lateral surface of the mandible. Although relatively rare, benign masseteric hypertrophy and intramasseteric hemangioma are two important conditions affecting this muscle. Patients with these lesions complain of the cosmetic deformity rather than the functional disorder. Unless desired for cosmetic reasons there is little justification for any operative treatment. However, as no report could be found of the esthetic problem being solved by conservative treatment, surgical correction is advised when the chief complaint is esthetic.<br>Surgical treatment involves resection of the hypertrophied musculature or excision of the tumor with a surrounding margin of normal muscle. We list here the important aspects of surgery of the masseter.<br>1) Careful preoperative planning, including CT and MRI, is indispensable.<br>2) An extraoral approach is preferred in most cases. The masseter muscle is exposed through a curvilinear incision around the angle of the mandible for cosmetic reasons. A postauricular incision extending to the submandibular area is used instead of a routine preauricular parotid skin incision.<br>3) Care should be exercised to identify and preserve the lower branches of the facial nerve. They should either be dissected free and retracted (in case of tumor) or remain on the surface of the muscle (in cases of muscle hypertrophy) to protect them from damage.<br>4) Ligation of the feeding vessels helps to minimize blood loss.<br>5) Oozing from the muscle can be controlled by an infrared contact coagulator.<br>6) Postoperatively continuous suction with a fenestrated polyethylene drain for 2 days and a pressure dressing for 5- to 7-days is recommended to prevent hematoma and resultant scar formation, which causes swelling or trismus.<br>7) Patients should begin chewing early to prevent trismus.
1 0 0 0 OA Retrospective Study of Haemoparasites in Cattle in Southern Italy by Reverse Line Blot Hybridization
- 著者
- Luigi CECI Fabrizio IARUSSI Beatrice GRECO Rosanna LACINIO Stefania FORNELLI Grazia CARELLI
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.13-0365, (Released:2014-03-07)
- 被引用文献数
- 9 27
Tick-borne diseases are widespread in tropical and temperate regions and are responsible for important economic losses in those areas. In order to assess the presence and prevalence of various pathogens in southern Italy, we retrospectively analyzed cattle blood samples collected for a previous study in 2000 using reverse line blot (RLB) hybridization. The study had been carried out in three regions of southern Italy on 1,500 randomly selected and apparently healthy adult cattle. RLB showed that 43.7% of the cattle were positive for nine different species of haemoparasites, with either a single infection or a mixed infection. Theileria buffeli was the most common species found, being present in 27.3% of the animals, followed by Anaplasma marginale in 18.1%, Anaplasma centrale in 13.8%, Babesia bigemina and Anaplasma bovis in 4.2%, Anaplasma phagocytophilum in 1.7%, Babesia bovis in 1.6%, Babesia major in 0.2%, and Babesia divergens in 0.1%. Complete blood counts showed different degrees of anaemia in 363 animals (24.2%) and of these, 169 were RLB-positive for at least one pathogen. Among the ticks that were collected from the cattle, the following species were identified: Rhipicephalus bursa, Ixodes ricinus, Hyalomma marginatum, Boophilus annulatus, Dermacentor marginatus and Haemaphysalis (sulcata, parva, inermis and punctata). The results obtained confirmed the spread of endemic tick-borne pathogens in the regions studied.
1 0 0 0 OA イネにおける細胞質雄性不稔と稔性回復の遺伝学的研究(農学部)
- 著者
- 新城 長有
- 出版者
- 琉球大学
- 雑誌
- 琉球大学農学部学術報告 (ISSN:03704246)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.1-57, 1975-12-01
- 被引用文献数
- 6
筆者はインド型イネChinsurah Boro II品種が雄性不稔細胞質と稔性回復遺伝子をもつことを発見し, 連続戻交雑法を用いて両因子を日本型イネの台中65号へ導入した。育成された上記isogenic系統を主材料にして, 雄性不稔の遺伝, 他形質に対する細胞質と稔性回復遺伝子の効果, 稔性回復遺伝子の座位, 雄性不稔イネにおける花粉退化の時期, 雄性不稔細胞質と稔性回復遺伝子の地理的分布, および雑種イネ育種に必要な三系統の育成法を研究した。結論の要約は下記のとおりである。A雄性不稔の遺伝インド型イネChinsurah BoroIIに由来する雄性不稔細胞質を(ms-boro), その稔性回復遺伝子をRfと命名した。(ms-boro)Rf Rfの遺伝子型をもつ系統は完全雄性稔, (ms-boro)Rf rfは部分雄性稔(花粉稔性約50%)で, (ms-boro)rf rfは完全雄性不稔であった。一方上記3系統の雌性配偶子は健全であった。正常細胞質(n-boro)をもつ個体は核内遺伝子型に関係なく, すべて完全雄性稔になった。(ms-boro)rf rf×(n-boro)Rf rfのF_1世代においては, 部分雄性稔と完全雄性不稔個体が1 : 1の比に分離したが, (ms-boro)rf rf×(ms-boro)Rf rfのF_1では稔性の分離は観察されず, すべての個体が部分雄性稔(花粉稔性約50%)になった。(ms-boro)Rf rf系統の自殖次代には完全雄性稔および部分雄性稔個体が1 : 1の比に分離した。したがって(ms-boro)Rf rf個体においては, 花粉形成期のある時期にrf遺伝子をもつ花粉は雄性不稔細胞質との相互作用で死滅し, Rf花粉のみが正常に発育するといういわゆる雄性配偶体不稔性と結論した。(ms-boro)rf rf×Rf RfのF_1個体の花分稔性は50%を示すが, 種子稔性は90%以上になる。したがって本雄性不稔細胞質と稔性回復遺伝子は雑種イネの育成に利用できるものと考えられる。なお, 雑種イネ育成に必要な3系統, すなわち雄性不稔系統, 雄性不稔維持系統および稔性回復系統の育成方法についても理論的に示した。B量的形質に対する細胞質と核内遺伝子の効果作出可能な6 isogenic系統を育成し, 5反覆の乱魂法を用いて, 1970年の第1期作と第2期作で栽培し, 出穂日, 穂数, 主稈葉数, 稈長, 第1節間長, 第2節間長および第3節間長(節間は最上位から数えた。)を測定し, 系統間の比較を行った。雄性不稔系統の稈長は他の5系統に比較して約7cm短く, 1%水準で有意であった。雄性不稔系統の短稈性は, おもに第1∿第3節間長の短縮に起因する。他の5系統の稈長間には有意差はなかった。雄性不稔系統の示す出穂日, 穂数, 主稈葉数は他の系統と同程度であった。雄性不稔系統のこのような特性は交雑圃における受粉体制に好影響をもたらすものと考えられる。C Rf遺伝子の座位まず三染色体系統を用いて, Rf遺伝子の座乗染色体を確定し, つぎに既2標識遺伝子系統との交雑を行ない座位を明らかにした。三染色体分析では3系交雑法を適用した。まずTrisomics×(ms-boro)Rf Rfの交雑F_1から三染体個体を染色体数の観察によって迸抜し, つぎにF_1の三染色体植物を父本にして雄性不稔系統へ交雑し, 次代植物の種子稔性を調査した。その結果Rf遺伝子はTrisomic C系統の過剰染色体, つまり岩田らの第7染色体に座上することが判明した。Rf fl間の組換価は約0.4%で, pglとRf間のそれは約12%, pglとfl間は約20%であった。したがって第7染色体上における遺伝子の配列順序はpgl-Rf-flである。D花粉退化の細胞組識学的研究本雄性不稔系統における花粉の発育過程を観察した。滅数分列は正常に進行し, 花分四分子も正常に形成される。しかし花粉1核期でその発育を停止し, 2核期以後は観察されない。タペート細胞は正常である。出穂期の不稔花粉はヨード・ヨードカリ液で染色されない。不稔花粉は球形で発芽孔を有するが, 形は正常花粉よりも小さい。E雄性不稔細胞質と稔性回復遺伝子の分布(1)日本の水稲奨励品種について細胞質と核内遺伝子型の検定法を考案し, その検定法に基づいて1962年度の日本水稲奨励品種150品種を検定した。19品種(12.7%)の品種は弱稔性回復遺伝子をもち, 他の131品種は非回復遺伝子をもっていた。弱回復遺伝子をもつ品種のほとんどは京都以南に集中的に分布した。これらの品種のほとんどは在来品種から分離育種法によって育成された品種であった。供試日本稲品種には雄性不稔細胞質は発見されなかった。(2)外国品種について本研究に用いたイネ品種は15国から蒐集した153品種でった。細胞質検定親に遺伝子型(n-boro)rf rfの6系統を, 核内遺伝子検定親には遺伝子型(ms-boro)rf rfの6系統を用いた。これらの検定親と153品種との交雑を行なった。主としてF_1の花粉および種子稔性から, それぞれの品種の細胞質型と核内遺伝子型を推定した。雑種不稔性の併発によって, これらの推定が困難であった組合せについては, B_1F_1か自家受粉による後代系統の稔性から推定した。細胞質の検定を行なった146品種のうち, 4品種がChinsur
- 著者
- 原田 桂太
- 出版者
- 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所
- 雑誌
- 瀬戸臨海実験所年報 = Annual report of the Seto Marine Biological Laboratory (ISSN:09136002)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.49-64, 2010-12-25
京都大学白浜水族館にて、2007年4月から2008年9月までに一般の来館者に対して、来館者の年齢層、来館者がどこから来ているか、当水族館の展示がどう評価されているか、などを調査するためにアンケート調査を行った。年齢別で面白かったかどうかを見ると、70歳以上と回答した人を除いて、「おもしろかった」「どちらかといえばおもしろかった」と回答した人の合計が、それぞれの年齢層で9割前後を占めた。10代と20代、および70歳以上では、「つまらなかった」と回答した人の割合がやや高かった。当水族館を知った手段としては、「家族、友だち、知人の話や紹介」と回答した人の割合が白浜周辺からの来館者では高く、遠隔地からの来館者ほど低い傾向が見られた。白浜周辺以外からの来館者では、「たまたま見つけた」と回答した人の割合が高い傾向があった。和歌山県以外の近畿圏からの1回目の来館者数が、全体の半分以上を占めた。また、来館数を「2-4回目」「5 回目以上」と回答した人の割合は、白浜周辺からの来館者ほど高く、遠隔地からの来館者ほど低い傾向が見られた。
1 0 0 0 OA 口唇と頬の構造と機能訓練
- 著者
- 竹原 祥子 下山 和弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.403-406, 2007-03-31 (Released:2014-02-26)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 顎関節外側靭帯についての組織学的観察
- 著者
- 黒川 悦郎
- 出版者
- 口腔病学会
- 雑誌
- 口腔病学会雑誌 (ISSN:03009149)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.508-535, 1986-06-30 (Released:2010-10-08)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
Seven temporomandibular joints from the cadavers were investigated to elucidate the histological structure of the temporomandibular ligament. Serial sections were made and stained for observation by light microscope.The temporomandibular ligament was separated into the medial horizontal portion (the third layer of the lateral wall of the human temporomandibular joint) and the outer oblique one (the fourth layer) .Both portions were attached to the outer surface of the articular tubercles and the lateral margin of the mandibular fossa as they entwined with each other.The third layer was attached to the mandibular condyle somewhat posteroinferiorly of the lateral pole and the fourth was attached over broader area. The temporomandibular ligament was fundamentally composed of thin collagenous fibers called primary fibers (5-12μm in width) . These fibers were formed large bundles secondarily and were called secondary fibers.In the third layer, the secondary fibers (50-15μm in width) were arranged densely and almost parallely. These secondary fibers were sometimes united with the primary fibers branching from the other secondary fibers. At the attached areas, the secondary fibers branched into primary fibers and these fibers penetrated into the bone in an entangled state.In the upper region of the fourth layer, wavy primary fibers were arranged relatively densely. In the lower region, the thickness of the secondary fibers increased gradually. These secondary fibers (20-80μm in width) invaded the periosteum of the condyle.
1 0 0 0 口唇と頬の構造と機能訓練 : I. 口唇と頬に関する基礎知識
- 著者
- 竹原 祥子 下山 和弘
- 雑誌
- 老年歯科医学 = Japanese journal of gerodontology (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.403-406, 2007-03-31
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 多様な暖冷房方式と通風利用による快適性と省エネ性の統合的評価手法に関する研究
「建物」と暖冷房「機器」の両者を踏まえ、快適性と省エネ性を統合的に評価する手法(以下、統合的評価手法と記す)を検討し、提案するに至った。検討にあたって、各種暖冷房方式による温熱環境の差異や実働効率などの機器の稼働状況などの実態を実験・実測により把握し、そのデータを整備した。また、通風による冷房負荷削減効果を予測する上で不可欠となる、建物に作用する風圧力に関するデータベースを風洞実験により整備した。なお、統合的評価手法については、今後も検討・改良を加えていく所存である。An integrated assessment method of comfort and energy saving were investigated, and proposed in this study. This method is based on both sides of "Building specifications" and "HVAC systems". In this investigation of the method, thermal environment by various HVAC systems and actual efficiency of equipments were arranged by experiments and actual survey. Moreover, the data base of wind pressure coefficients of buildings was maintained by the wind tunnel experiment.
1 0 0 0 OA アフガニスタン教員養成短大の特別支援教育教員養成課程カリキュラム開発
アフガニスタンの教員養成短期大学における特別支援教育教員養成課程開設のためのカリキュラム開発の基礎研究に取り組んだ。教育関連法規、現地ニーズやリソース、イスラム教、特別支援教育の現状、国家教育戦略計画等を踏まえて、教員養成短期大学の特別支援教育教員養成課程のカリキュラム原案を作成した。アフガニスタンの特別支援教育教員養成カリキュラム開発においては、イスラム教、国家教育戦略計画やインクルーシブ&チャイルドフレンドリー教育方針、関係者の合意形成、カリキュラム承認プロセス、カリキュラム開発と人材育成が必要であることなどに配慮したカリキュラム開発を考慮することが大切であると考えられた。