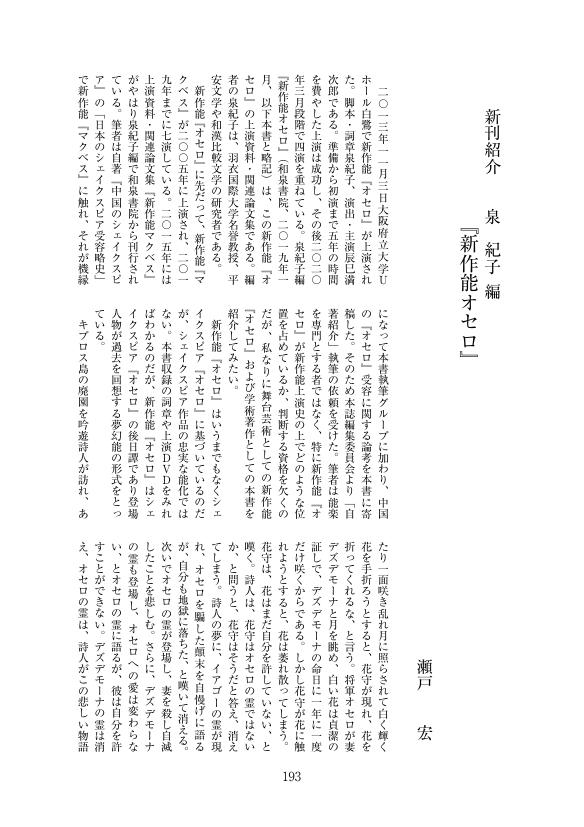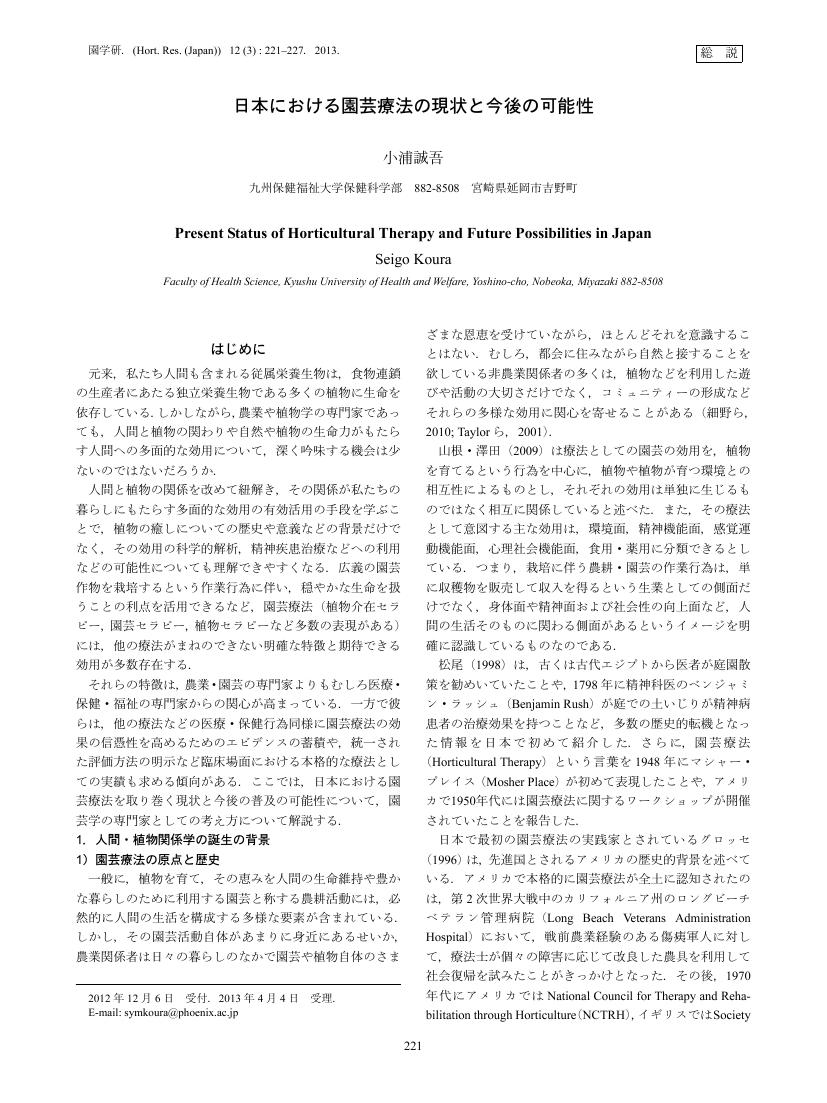2 0 0 0 OA 小学校通学区域の形成過程
- 著者
- 酒川 茂
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.116-138, 1983-04-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 84
- 被引用文献数
- 3
School districts are one form of social region. The purpose of this study is to consider how primary school districts have been formed in relation to certain factors. It is assumed that the influence of those factors varies with the geographical characters of each region. Therefore, the author divided the case study area (Hiroshima City) into three regions: the region of the old castle town (inner city), the region surrounding the inner city, and the region which has been consolidated since 1971. As a result of this analysis, the formation processes of primary school districts are classified into four types. These types are summarized as follows:In the region of the old castle town (the inner city), it was decided at first that school districts would be the same as each Shoku established by the Daiku-Shoku-Sei. This area consisted of Buke-Yashiki (samurai districts), Machi-Yashiki (Chonin districts), and Shingai (newly opened districts). Though these blocks characterized each Shoku, they were not equivalent to social regions. Afterwards, a lot of primary schools were established. Those school districts were based on population distribution, and their boundaries were natural boundaries in many cases. However, the blocks of this area were changed by war damage and land readjustment after the war. Since then, school districts have been reformed according to the actual circumstances, especially in regard to traffic safety problems of school attendance.There are sprawl areas in both the regions surrounding the inner city and the region which has been consolidated since 1971. In these areas, there had been one school in most of the villages for a long time. Therefore, each school district had been strongly united as the social region. After the war, the population increased and now these areas are contiguous with the inner city. The areas of original villages have lost their meaning as school districts. It is considered that the present school districts are the new social regions replacing the original villages. The traffic safety of school attendance has become the most important factor in the formation of school districts. On the other hand, there are few sites for new schools in these areas. It is difficult to establish new schools as previously planned. This is apt to cause social problems about school districts.In the rural areas within the region, which have been consolidated since 1971, one to three schools were established in each village. However, the population decreased rapidly after the war and a lot of schools were combined. The aim of these school combinations was to maintain a reasonable scale for the schools and to reduce the costs of education. In these areas, school districts have been formed according to the convenience of school attendance. As a factor in the formation of school districts, the existence of transport facilities for school attendance is more important than the distance of school attendance. The Oaza, which is recognized as important territorial relational grouping, has been adopted as the unit of school districts in those cases where the Oaza is contained in one traffic region.There are new towns in both the region surrounding the inner city and the region which has been consolidated since 1971. When these new towns are constructed, primary schools are established intentionally. The factors in the formation of school districts, for example, the population distribution, the distance of school attendance, the traffic safety of school attendance, etc., are considered in the new town planning. Therefore, school districts are expected to become the new social regions from their inception.These results show us that the basic factor in the formation of school districts is the population distribution, and that the traffic safety of school attendance is the single most important and common factor at present.
2 0 0 0 OA 男性の喫煙率と年齢および職種との関連性について
- 著者
- 星野 立夫 田辺 光子 大塚 裕子 清水 文子 山下 幸枝 坂下 清一 大濱 正 宮崎 博子 三浦 賢佑
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 健康医学 (ISSN:09140328)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.152-155, 2002-09-30 (Released:2012-08-27)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
禁煙指導の一助とするため,男性の喫煙率と年齢および職種との関連性を人間ドック受診者で調べた。受診者数の多い5職種を選び,その職種の2000年度の男性受診者全員を対象とした。男性の喫煙率は,若い年代で高く,年代が進むにつれて低下する傾向を示したが,年代だけでなく職場環境も喫煙率に影響している事が示唆された。生活習慣病予防のためには若い年代に対する禁煙指導の強化が望まれるが,職場環境を考慮したたばこ対策が必要と考えられた。
2 0 0 0 OA 泉 紀子 編『新作能オセロ』
- 著者
- 瀬戸 宏
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.193-194, 2020-06-15 (Released:2020-07-07)
- 著者
- 森田 真吾
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.50-58, 2020-03-30 (Released:2020-04-09)
- 参考文献数
- 19
本研究では、文部省『中等文法』の指導内容について、橋本進吉の文法学説との連続性にではなく、むしろ両者の差異に注目することによって『中等文法』の独自性を見出そうと試みた。その結果、『中等文法』における橋本学説に対するアレンジは、文法の指導内容を学習者にとってより身近なものとするための配慮に基づいて行われていたことが確認できた。また『中等文法』に援用されている橋本学説以外の内容については、いわゆる「五種選定本」の影響を指摘することができ、それにより『中等文法』は当時一般に流布していた文法教科書の内容を視野に入れつつ、それらを一つに収斂させて指導内容を整えようとしていた可能性があることが明らかになった。
2 0 0 0 OA 漢語文法は古今同じ (上)
- 著者
- 高橋 君平
- 出版者
- 日本中国語学会
- 雑誌
- 中国語学 (ISSN:05780969)
- 巻号頁・発行日
- vol.1972, no.216, pp.14-22,13, 1972-10-15 (Released:2010-03-19)
2 0 0 0 OA ミズナギドリ目の骨学に関する二•三の知見
- 著者
- 黒田 長久
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 鳥 (ISSN:00409480)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2-3, pp.41-61, 1983-10-25 (Released:2007-09-28)
- 参考文献数
- 17
筆者のミズナギドリ目の骨学の研究(1953-59)で欠除していた数属の骨格標本が,W.R.P.BOURNE 博士博士のご好意でBritish Museumから提供されたので,比較検討した.この論文では,その主な点について述べた. Procellaria と Adamastor は縁が近く,後者はより潜水適応を示すが,ともに Calonectris に連る. Bulweria は, Pterodroma その他の属と上膊骨が細く長い点で異なり,特異であるが (飛翔法を反映),腰骨,頭骨などの類似度から小型の Pterodroma(Cookialia) に近い. Pterodroma は涙骨の癒合,上膊骨その他の点でフルマカモメ群に連る. Halobaena と Pachyptila はすべての点で同一型を示し, Pagodroma (これは Fulmarus により近い)と共にフルマカモメ群に属する. Oceanodroma も腰骨,上膊骨,(頭骨)などからフルマカモメ群に連る. Hydrobates はその小型に関連して Oceanodroma と多少頭骨に違いを認めた.
2 0 0 0 OA オランダ東インド会社によるバタヴィアの水路網と空間形成
- 著者
- 松田 浩子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.685, pp.705-714, 2013-03-30 (Released:2013-06-03)
Batavia was the port city founded by the Dutch United East India Company in the Ciliwung River Delta of Java located in the Asian monsoon tectonic zone. Construction of the urban area and land reclamation of the environs were conducted under the water management based on waterways having multi functions such as self-defense, transportation, drainage, water storage and irrigation. This paper explains changes of the water management and the space structure in the 17th and 18th centuries according to maps, official ordinances and travel records. Structure and features of the channel network are discussed in relation to geomorphology and hydrological conditions of Java.
2 0 0 0 OA 日本における園芸療法の現状と今後の可能性
- 著者
- 小浦 誠吾
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.221-227, 2013 (Released:2013-09-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4
2 0 0 0 OA 五十君麻理子著「ローマ大衆の法知識—プラウトゥス喜劇における「笑源」としての法」
- 著者
- 葛西 康徳
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.307-310, 2014-03-30 (Released:2019-10-11)
2 0 0 0 OA 真空調理における加熱温度と殺菌効果について
- 著者
- 金井 美惠子 安谷屋 倭子 深作 貴子 大迫 早苗
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 2019年度大会(一社)日本調理科学
- 巻号頁・発行日
- pp.160, 2019 (Released:2019-08-26)
【目的】乳製品,食肉加工食品,魚肉練り製品の安全を踏まえた品質管理法は既に確立されているが,真空調理の安全性についての科学的な報告は少ない。多分,真空調理を開発した当初のシェフの興味は,食品の味覚等にあったと推察される。真空調理食品は食中毒細菌であるボツリヌス菌やウエルシュ菌の増殖があると厳しい結果をもたらす可能性があるので,ウエルシュ菌等を用いて微生物学的な検討を行った。【方法】真空調理の適切な加熱温度を明らかにするために,次の検討を行った。第1:ウエルシュ菌を魚すり身に接種・混和し,種々の温度で湯煎加熱した。第2:生の鶏肉および加熱調理後の微生物汚染について検討した。第3:ホテルレストランで提供されている牛肉ステーキ,カキの真空調理食品,ついて実験し,残存菌をどのようにコントロールするかを考察した。【結果および考察】1)生活型ウエルシュ菌は一般的な真空調理温度である60℃の加熱で検出されなくなった。2)ウエルシュ菌芽胞は80℃,60分の加熱後も残存した。3)0℃のチルド冷蔵庫に7日間保存後の残存芽胞数の変化はなく,二次加熱による菌数変化もみられなかった。4)真空調理した鶏肉からは,大腸菌,大腸菌群,低温細菌は検出されなかった。5)食肉の焼き色と風味づけのための事前加熱は汚染菌を減らすのに効果的であった。6)ホテルレストランにおけるビーフステーキ,カキの調理食品および調理過程での実験成績も同様の傾向であった。7)低温真空調理食品はチルド保存をすることが望ましい。8)真空調理過程における香辛料の利用はウエルシュ菌など,芽胞形成菌の汚染をもたらすと考えられた。
2 0 0 0 OA 超音波画像を用いた膝関節伸展等尺性筋力の予測
- 著者
- 北川 孝 寺田 茂 三秋 泰一 中川 敬夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0508, 2015 (Released:2015-04-30)
【はじめに,目的】近年,超音波診断装置を用いた筋内脂肪増加の評価方法として筋エコー輝度(以下,筋輝度)の有用性が注目されている(Euardo 2012, Fukumoto 2012)。また機器による筋輝度測定の違いをキャリブレーションした指標として輝度比(Luminosity ratio,LR)が報告されている(Wu 2010)。大腿四頭筋の筋力発揮には筋厚や羽状角などの筋の形態的要因が影響するとされているが,筋力と筋輝度およびLRとの関連についての報告は十分にはない。また筋輝度と筋力の関係を検討したものは対象者が限られた年代を対象としているものが多い。本研究の目的は幅広い年代の健常者における大腿四頭筋の筋厚,筋輝度およびLRが膝伸展筋力に及ぼす影響を調べ,その値から膝関節伸展の最大等尺性筋力の予測式を立てることである。【方法】対象は成人男女各20名(平均年齢38.7±11.5歳,身長165.9±7.5cm,体重58.8±10.0kg,大腿周径50.2±4.4cm)とした。選択基準は20-59歳の健常者で日常生活が自立している者とし,除外基準は体幹または下肢の手術歴のある者,神経学的疾患および筋骨格系疾患を有する者とした。測定項目は皮下脂肪厚・輝度および大腿直筋(RF)・中間広筋(VI)の筋厚・筋輝度,膝関節伸展等尺性筋力とした。超音波診断装置(GEヘルスケア社製LOGIQ P5)を使用し,安静端座位での利き足の大腿四頭筋の横断画像を記録した。10MHzのリニアプローブを使用し,ゲインなどの画質条件は同一の設定で測定した。記録部位は上前腸骨棘と膝蓋骨上縁の中点とし,プローブは皮膚面に対して垂直に保持し,筋肉を圧迫しないよう皮膚に軽く接触させた。画像解析ソフト(Image J)を使用して3回の画像の皮下脂肪厚(fat-T)および皮下脂肪輝度(fat-EI),RFの筋厚(RFMT)および筋輝度(RFEI),VIの筋厚(VIMT)および筋輝度(VIEI)を測定し,平均値を算出した。またRFEI,VIEIをfat-EIで除したものをそれぞれRFLR,VILRとした。膝関節伸展等尺性筋力の測定には筋力測定装置(ミナト医科学株式会社製コンビット)を使用し,膝関節屈曲60°位の端座位にて利き足の膝関節伸展等尺性筋力(Nm)を測定した。筋力値は3回測定したうちの最大値を使用した。統計学的解析としてPearsonの相関係数およびSpearmanの順位相関係数を用い対象者の筋力値とその特性および画像所見との関連性を検討した。また筋力値を従属変数,対象者の特性および画像所見の中から筋力値と有意な相関がみられた項目を独立変数とし,ステップワイズ法を用いて重回帰分析を行った。すべての統計の有意水準は5%未満とした。また本研究での皮下脂肪輝度および筋輝度の信頼性を調べるためにfat-EI,RFEI,VIEIそれぞれの同一検者による2回の測定値について級内相関係数を求めた。【結果】輝度測定の級内相関係数は0.99であった。筋力値は151.3±52.3Nm,fat-Tは0.54±0.25cm,fat-EIは94.1±11.3pixel,RFMTは1.87±0.42cm,RFEIは71.9±13.8pixel,RFLRは0.77±0.17,VIMTは2.02±0.50cm,VIEIは54.7±11.8pixel,VILRは0.59±0.14であった。相関分析の結果,筋力値と身長,体重,大腿周径,fat-T,fat-EI,RFMT,RFEI,RFLR,VIMT,VIEI,VILRに有意な相関がみられた。重回帰分析の結果,筋力値に影響を与える有意な因子として身長,VIMTが抽出された。標準回帰係数は身長が0.57(p<0.001),VIMTが0.49(p<0.001)であった。筋力値の予測式は,[筋力値(Nm)=-585.1+3.95×身長(cm)+40.5×VIMT(cm),p<0.001]であり,その決定係数は0.67であった。【考察】級内相関係数で求めた輝度の信頼性は0.99であり,高い信頼性が認められた。本研究の結果より,膝関節伸展の最大筋力には身長および中間広筋の筋厚が影響することが示唆された。【理学療法学研究としての意義】臨床では膝関節周囲の疼痛や臥床状態などにより膝関節伸展筋力を測定することが困難な患者が多く見受けられる。そのような症例においても本研究における結果が応用できれば,非侵襲的に筋の量および質の評価が可能となると期待される。
2 0 0 0 OA 震災のこころのケアからみた心理療法・箱庭療法
- 著者
- 河合 俊雄
- 出版者
- 日本箱庭療法学会
- 雑誌
- 箱庭療法学研究 (ISSN:09163662)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.1-2, 2012 (Released:2012-12-25)
- 著者
- 谷口 高士
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.9, pp.682-687, 2006-09-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 生活保護の受給期間 : 廃止世帯からみた考察
- 著者
- 藤原 千沙 湯澤 直美 石田 浩
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.4, pp.87-99, 2010-02-25 (Released:2018-02-01)
生活保護の受給期間に関する議論では,毎年7月1日現在の被保護世帯を対象に,保護の開始から調査時点までを受給期間とする「被保護者全国一斉調査」(厚生労働省)が用いられるのが一般的である。これに対し,本研究は,A自治体における保護廃止世帯を対象に,保護の開始から廃止までを受給期間として分析し,保護継続世帯と合わせて生存分析を行った。その結果,以下の諸点が明らかとなった。第一に,一時点の受給継続世帯を対象とした調査では調査対象にあがらない1年未満廃止世帯が相当数存在する。第二に,世帯主の学歴・性別・世帯類型により受給期間に違いがみられた。第三に,自立助長という生活保護制度の目的に沿った保護廃止であるか否かにより受給期間の傾向は異なる。第四に,廃止世帯と保護継続世帯の双方を考慮した分析では,世帯主の性別と世帯類型により保護の継続確率(生存率)に違いのあることが推察された。
2 0 0 0 OA 6.抗菌薬
- 著者
- 千田 金吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.6, pp.1143-1148, 2007 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 7
抗菌薬は日常診療で多用されるため,常に副作用を念頭に置く.ミノサイクリンやST合剤や抗結核薬の使用では,比較的頻度が高い.ペニシリン系薬剤のようにペニシリウムなどの環境真菌に曝露されていたり動物の飼料に配合されている薬剤に感作されていると,速やかに反応が起きる.初めての使用では2週間程度で感作が成立する.薬剤がハプテンとしてペプチドと共有結合し,主要組織適合複合体分子を介してT細胞に抗原提示されることが多い.主要組織適合複合体分子は各個人で異なるため,発症にも個人差がみられる.
2 0 0 0 OA 日本手話におけるポライトネス
- 著者
- 吉岡 佳子
- 出版者
- 日本手話学会
- 雑誌
- 手話学研究 (ISSN:18843204)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.3-36, 2013 (Released:2014-12-21)
- 参考文献数
- 26
Although sign linguistics and pragmatics started almost at the same time in the early 1960's, few studies have been reported so far on pragmatics in sign languages. The present study aims at examining how politeness is realized in Japanese Sign Language (JSL). For this purpose, a videotaped discourse completion test (6 requests and 6 rejections) was conducted with the help of 8 native JSL signers. As a result, the JSL signers used a variety of politeness strategies, including both positive and negative ones, proposed by Brown & Levinson (1978/1987). It is particularly noteworthy that off-record strategies, i.e., indirect language uses with implicature, were observed in 12 cases among 90. In addition, a nonmanual marker (NMM) "polite grimace" was observed 19 times both in requests and in rejections. It co-occurred with /ask/, /reject/, /it's OK/, /sorry/ and /borrow/. Using this NMM, the signers seemingly showed their feelings such as "I really hate to tell you this, but", "against my will, I have to say", etc. Hoza (2007) reports that "polite grimace" is also observed in ASL. However, the NMM "polite grimace" in JSL is unique in that it is often combined with two-handed signs, which are derived from unmarked one-handed signs and show deference, and/or bowing, i.e., a traditional etiquette in Japan. Thus, the present study clarifies that the politeness theory is applicable to JSL too. From another viewpoint, it indicates the richness of JSL as a language.
2 0 0 0 OA 人間の疲れとは何か:その心理学的考察
- 著者
- 斉藤 良夫
- 出版者
- 公益財団法人大原記念労働科学研究所
- 雑誌
- 労働科学 (ISSN:0022443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.1, pp.13-24, 2012-02-10 (Released:2013-09-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
従来の労働者の疲労研究では,彼らの疲れの体験に関して科学的議論が行われてこなかった。そこで,労働者の長期的な疲労の研究方法を構築する目的で,人間の疲れとは何かに関する心理学的考察を行った。まず,ロシアの心理学者A. N. レオンチェフの活動理論を参考にして,人間の生活活動における心理的構造について論じた。次に,人間の疲れの現象には動機,欲求,感情,記憶などのさまざまな心理現象と関連する特徴があることを述べ,“人間の疲れは生活活動へのモティベーションの減退を基本的内容とする認知現象である”と規定した。最後に,労働者の長期的疲労の研究のために彼らの疲れを長期間にわたって調査研究する意義について述べた。
2 0 0 0 OA 砕氷艦「しらせ」主発電機用原動機 - 三井16V42M-B型ディーゼル機関
- 著者
- 原田 和弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.197-201, 2010 (Released:2012-12-06)
- 著者
- Yuji ICHIYAMA Takahito KOSHIBA Hisatoshi ITO Akihiro TAMURA
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- pp.191205, (Released:2020-06-26)
- 被引用文献数
- 6
Early Paleozoic serpentinite melanges in Japan preserve the oldest high–P metamorphic rocks in the circum–Pacific orogenic belt. To understand the tectonic regime at the subduction initiation of the proto–Japan convergent plate boundary, whole–rock geochemistry, and zircon U–Pb geochronology were investigated for amphibolite blocks in the Omi serpentinite mélange, central Japan. The studied amphibolites from two different localities have the mineral assemblage of albite + clinozoisite + amphibole ± rutile ± titanite, which characterize epidote–amphibolite facies metamorphism. Whole–rock trace element concentrations of the amphibolites suggest that gabbroic protoliths formed possibly in an oceanic setting. The zircon U–Pb weighted mean ages obtained from two amphibolite samples indicate that the protolith was formed in the Cambrian. The protolith ages of the studied amphibolites are comparable with those of reported Early Paleozoic ophiolite and high–pressure rocks in Paleozoic serpentinite mélanges in Japan. This fact implies that the young hot oceanic crust was subducting into the East Asian convergent plate margin during the Cambrian.
2 0 0 0 OA 結晶学における可視化ソフトウェアの開発と応用例
- 著者
- 門馬 綱一
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.173-178, 2014-06-30 (Released:2014-07-09)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
Features of the three-dimensional (3D) visualization software VESTA and a program for maximum entropy method (MEM) analysis Dysnomia are reviewed. VESTA has a unique feature to simultaneously visualize crystal, volumetric and morphology data. Multiple numbers of crystal structure data can be overlaid and compared in the same 3D space. Two examples of how these features are utilized in the X-ray crystallographic study are presented. In Dysnomia, several new features are implemented for improvement of the results of MEM analysis and better performance of calculation. New features in the latest version of VESTA are also explained, and some thoughts on the future of crystallographic visualization software are discussed.