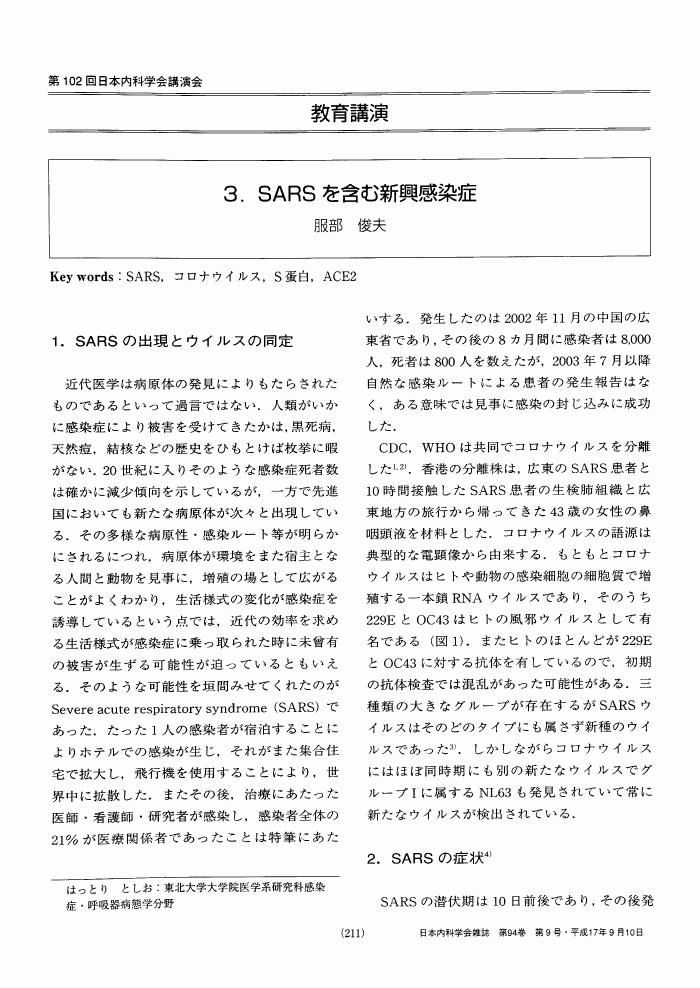2 0 0 0 OA ウォームアップ, クールダウンの意義
- 著者
- 青木 純一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第44回(1993) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.79, 1993-10-05 (Released:2017-08-25)
2 0 0 0 OA 運動システムを介した他者動作の予測
- 著者
- 池上 剛
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.573-579, 2017-08-10 (Released:2017-08-19)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 1993 (平成5) 年の日本の天候の特徴
- 著者
- 北村 修
- 出版者
- The Society of Agricultural Meteorology of Japan
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.33-41, 1994-06-10 (Released:2010-02-25)
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA 管楽器の発音原理(<小特集>音楽音響における最近の話題)
- 著者
- 足立 整治
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.11, pp.657-662, 2004-11-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 41
2 0 0 0 OA 中西印刷株式会社の事例報告
- 著者
- 守屋 貴司
- 出版者
- 労務理論学会
- 雑誌
- 労務理論学会誌 (ISSN:24331880)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.11, 2010 (Released:2018-05-04)
2 0 0 0 OA 中高年女性の配偶者に対する感情と性に関する評価
- 著者
- 安田 かづ子 細江 容子
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.52-60, 2004-07-31 (Released:2010-02-04)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
中高年女性の性の問題は, 更年期に特有のものと理解されることが多い。しかし, 性のあり方は結婚生活とも密接に関連しており, 性の問題は, パートナーとの関係性の中でも捉えられる必要がある。本研究では, (1) 配偶者に対する感情と性の満足の評価との関係, (2) 更年期と性の満足の評価との関係を明らかにすることを目的とした。性の満足には, これまでの性の快感の程度が大きく影響をしていることが明らかとなったことから, これまでの性の関係の累積性が性の評価に関わると言える。また, 更年期の影響は, 情緒的要因の嫌でも応じた性の有無にみられたことから, 中高年期は夫と妻の性の欲求の差が更年期に大きく感じられると推測される。
- 著者
- 林 拓児 石川 定 河村 隆史 中川 大樹 川平 和美
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.129-132, 2017 (Released:2017-02-28)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕通所リハビリテーション利用中の慢性期脳卒中片麻痺者に対して促通反復療法(治療的電気刺激・振動刺激併用)を低頻度で施行し,片麻痺上肢の麻痺改善効果を検討した.〔対象と方法〕通所リハビリテーション利用中の慢性期片麻痺者43名を対象に,麻痺側の上肢と手指に30分間,週2回の低頻度で12週間,治療を実施した.実施した治療法により伝統的な片麻痺治療法群と促通反復療法群に分け,上田式12段階片麻痺機能テスト法による評価をもとに,治療前後の麻痺の程度,改善度,有効率(改善人数/対象者数)を2群間で比較した.〔結果〕促通反復療法が伝統的な片麻痺治療法よりすべての指標において有意に高い麻痺改善の効果を示した.〔結語〕促通反復療法は低頻度でも有効な慢性期脳卒中片麻痺の治療法として今後の発展が期待できる.
2 0 0 0 OA 3. SARSを含む新興感染症
- 著者
- 服部 俊夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.9, pp.1915-1920, 2005-09-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA フランスの公立小学校における学校週4日制実施の背景と課題
- 著者
- 小野田 正利
- 出版者
- 日本比較教育学会
- 雑誌
- 比較教育学研究 (ISSN:09166785)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.23, pp.15-24, 1997-05-30 (Released:2011-01-27)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 睡眠と健康
- 著者
- 高田 真澄
- 出版者
- 一般社団法人日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.22-26, 2018 (Released:2018-01-31)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 6
Since World War II, Japan has achieved remarkable economic development and has become an advanced country. Particularly in the industrial field, a production system has been developed to reduce the loss of machining time by adopting a shiftwork in factories operating 24 hours a day, which contributes to the improvement of productivity. Nowadays, this shiftwork practice has spread from the industrial field to other businesses such as 24-hour entertainment facilities and convenience stores, which lead to sleep deprivation in Japanese society. Even at home, certain conditions adversely affect sleeping habits. We are concerned about the risks of physical and mental health, impairments posed by the use of tablets, PCs, smartphones, and other devices so popular in today’s Japan, as they delay sleep. It is urgent to improve poor sleeping habits because their outcomes such as sleep disorders and deprivation may also lead to traffic and industrial accidents.
2 0 0 0 OA 異なる気候条件下で暮らす女子高校生の「冷え性」と生活状況の検討
- 著者
- 土屋 基 鈴木 勝彦 井上 忠夫 樋口 和洋
- 出版者
- The Japanese Society of Health and Human Ecology
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.207-218, 2005-09-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 2
- 著者
- 西内 舞 川崎 弘作 後藤 顕一
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.113-123, 2018-07-31 (Released:2018-08-22)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
本研究では, 自己決定理論から動機づけを捉え「理科学習の意義の認識」が「相互評価表を活用する学習活動(以下, 相互評価活動と略す)への動機づけ」にどのような影響を与えているかについて明らかにすることを目的とした。本目的を達成するために, まず, 学習者が認識している「理科学習の意義の認識」と「相互評価活動への動機づけ」を測定するための質問紙を検討, 作成した。次に, 高校生を対象にこれらの質問紙による調査を実施し, 調査結果を基に「理科学習の意義の認識」が「相互評価活動への動機づけ」にどのような影響を与えているかについて共分散構造分析により明らかにした。その結果, 理科学習を通して, 学習者自身が, 「理科学習の意義の認識」を「科学的能力」が身に付くと捉えると, 「相互評価活動への動機づけ」のうち, 自律性の高い「同一化・成長」の動機づけに正の影響を与え, 自律性の低い「外的調整」には負の影響を与えていることが明かになった。また, 「理科学習の意義の認識」を「科学と身近な自然や日常生活の理解」と捉えると, 「相互評価活動への動機づけ」のうち, 自律性の高い「内発的調整」, 「同一化・成長」, 「同一化・将来」の動機づけに加え, 自律性の低い動機づけである「取り入れ・他者」にも正の影響を与えていることが明らかになった。つまり, 「理科学習の意義の認識」を「科学と身近な自然や日常生活の理解」と捉えると, 自律性の低い動機づけまで高めてしまう危険性が示唆されたと考えられる。
2 0 0 0 OA Extraction and Amplification of the Human Mitochondrial DNA from the Jomon Skeletal Remains
- 著者
- Takahiro KUNISADA Ken-ichi SHINODA
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Journal of the Anthropological Society of Nippon (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.4, pp.471-482, 1990 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
縄文時代人骨3体から DNA を抽出し, PCR 法を用いてミトコンドリア DNAを増幅して解析を行い,その方法論的な問題点を考察した。今回用いた方法では,試料の保存状態•部位にかかわらず,ほぼ安定して DNA の分離と増幅が可能であり,その有効性が確かめられた。分離された DNA は,そのほとんどがヒト由来のものではなかったが, PCR 法によりヒトミトコンドリア由来の DNA の増幅を確認することができた。ミトコンドリア DNAのV 領域および D ループ領域に対する制限酵素を用いた解析では多型は検出できなかった。しかし増幅した V 領域の塩基配列を決定したところ,1個体では1箇所の変異が見出された。
2 0 0 0 OA 東京都内のペットショップで飼育されている犬猫における動物由来感染症病原体保有状況調査
- 著者
- 山崎 翔子 岩本 百合子 金谷 和明 畠山 薫 上原 さとみ 鈴木 淳
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.8, pp.495-499, 2019-08-20 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 30
都内ペットショップで飼養されている犬及び猫の病原体保有状況を調査した.54施設において,犬364頭から糞便355検体及び被毛361検体,猫113頭から糞便111検体及び被毛112検体を採取した.動物由来感染症の病原体として,Campylobacter jejuni(犬糞便5検体),Giardia intestinalis(Assemblage A)(猫糞便2検体),病原大腸菌(EPEC O119:NM)(猫糞便1検体),皮膚糸状菌(犬被毛4検体,猫被毛4検体)が検出された.施設内に病原体が持ち込まれることを前提とした検疫体制の整備と,施設内での交差汚染を防ぐための衛生管理が重要であると考えられた.
2 0 0 0 OA 科学コミュニケーションを巡る歴史と教訓
- 著者
- 標葉 隆馬 田中 幹人
- 出版者
- National Institute of Public Health
- 雑誌
- 保健医療科学 (ISSN:13476459)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.103-114, 2018-02-01 (Released:2018-04-14)
- 参考文献数
- 77
東日本大震災は直接的な人的被害のみならず,大きな社会的被害と混乱をもたらした.この東日本大震災を巡る社会的課題の一端について考察するために,本稿では日本の科学コミュニケーションが持つ構造的問題とその歴史的経緯について検討を行う.(特に再生医療分野のリスクコミュニケーションに関する)最近の研究において,科学的コンテンツは重要であるものの,それ以上に潜在的なリスク,事故の際の対応スキーム,責任の所在などへの関心事がより一般の人々の中で優先的であることが見出されている.このことは「信頼」の醸成において,責任体制も含めた事故後の対応スキームの共有が重要であることを含意している.また,コミュニケーションの実践においても利害関係や責任の所在の明示が重要であることを指摘する.同時に,東日本大震災を巡るメディア動向とその含意についても,最近までの研究成果を踏まえながら考察を加える.東日本大震災において,とりわけ全国メディアとソーシャルメディアにおいて福島第一原子力発電所事故がメディア上の関心の中心事となり,東北地方の被災地における地震・津波に関する話題が相対的に背景化したこと,一方で被災現地のメディアでは異なるメディア関心が見出されてきたことを指摘する.
2 0 0 0 OA タイトジャンクションシール制御技術を利用した中枢神経疾患治療薬のためのDDS開発
- 著者
- 橋本 洋佑 近藤 昌夫 竹田 浩之
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.374-384, 2019-11-25 (Released:2020-02-25)
- 参考文献数
- 42
血液脳関門が有する強固な密着結合は、中枢神経系疾患の薬物療法の発達を妨げている要因の1つである。血液脳関門で形成されるバリアのうち、特に1kDa以下の分子の脳内への流入を制限する密着結合の形成にはclaudin-5(CLDN-5)が必須であり、CLDN-5のバリア機能の阻害による血液脳関門突破法の開発が期待されている。当研究グループは近年このCLDN-5の機能を阻害することが可能な抗体の開発に成功し、この抗体によるバリア制御技術について報告してきた。本稿では、筆者らが抗CLDN-5抗体を取得するためにとったアプローチと取得した抗体のCLDN-5阻害活性、また密着結合制御技術の中枢神経系疾患治療への応用の可能性について紹介する。
2 0 0 0 OA コミュニケーション原理
- 著者
- 定延 利之
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.276-291, 2005-04-01 (Released:2015-04-01)
- 参考文献数
- 44
本稿は,日常会話に代表される人間同士のコミュニケーションの原理を明らかにしようとするものである.伝統的なコミュニケーション観に多かれ少なかれ共通する原理として,次の四つを挙げることができる.(i)情報伝達を前提とする;(ii)意図を前提とする;(iii)共在を前提とする;(iv)行動を前提とする.だが,これらの原理が諸現象を見る研究者の目を曇らせ,不当な記述や説明を生み出してしまっていることも実は少なくない.本稿は日本語の話し言葉の観察を通して,このことを具体的に示す.最終的に,より有用なコミュニケーション観として導き出されるのは,「当事者たちの共在が当事者間で了解されている」と当事者たちが確信している状況と,そこでの行動,というものである.
2 0 0 0 OA 日本人女子(4~17才)の身体比例について
- 著者
- 柳沢 澄子 須貝 容子 芦沢 玖美
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.163-173, 1965-03-30 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
Of the Japanese girls of ages ranging from 4 to 17, stature, span, upperlimb length, lowerlimb length, acromion height, waist height, foot length, and total head height, and their proportions with stature were measured and calculated, and statistics were taken of each age group. The results obtained by examining the growth sequnece are summalized below.1) Stature, span, upperlimb lenhth and lowerlimb length, and waist height increase till 14 years old showing significant difference between each age, and acromion height till 11 years samely, but after these years the growth rate becomes little. The time when the stature increases most speedily is 10-11 years of age. The total head height increases slowly through the years of age from 4 to 17. (Tables 3. 1, 3. 2, Fig. 1)2) Foot length, lowerlimb length, stature, total head height and upperlimb length reach their adult values at 12, and 17 years of age respectively. (Fig.2)3) Values of indices of span, upperlimb length lowerlimb length, waist height, to stature gradually increase with ages, and reach their greatest values at 11 years of ages, and after that diminish a little till adult. Indices of foot length and total head height, to stature diminish with age. (Tables 4.1, 4.2)4) The characteristics of body proportions of the materials of 4, 7, 10, 13, and 16 years compared with those of adult are shown in Fig. 3.
2 0 0 0 OA 驚異の生体物質アパタイトと表面技術
- 著者
- 青木 秀希 矢嶋 龍彦 小山 利幸
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.744-744, 2007 (Released:2008-08-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 3
2 0 0 0 OA 小学生における味覚閾値と疲労やストレスとの関連
- 著者
- 永井 亜矢子 久保田 優 東山 幸恵
- 出版者
- Japan Society of Nutrition and Food Science
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.5, pp.249-254, 2013 (Released:2013-10-21)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1
正常な味覚閾値は健康な食生活に大切である。味覚閾値に影響を及ぼす因子の一つとして疲労やストレスが挙げられるが, それらが味覚閾値にどのような影響を与えるかを検討した研究は特に小児において殆どみられない。そこで, 健常な小学生男女58名を対象に, 疲労やストレスが味覚閾値とどのように関連するのかを検討した。味覚閾値は濾紙ディスク法を用いて4基本味を測定した。ストレスは唾液α-アミラーゼ活性を, 疲労はチャルダー疲労スケールを指標として評価した。唾液α-アミラーゼ活性によるストレス度別に4群で比較したところ, 味覚低下者数に違いはなかった。チャルダー疲労スケールでは, 非疲労群に比べ疲労群で有意に味覚低下者数が多かった (身体的疲労:酸味p=0.02, 精神的疲労:塩味p=0.03, 総合的疲労:酸味p<0.01, 苦味p=0.02) 。以上より, 小児において疲労は特定の味覚閾値を上昇させる可能性が示唆された。